新しい知見
従来Epstein-Barr virus(EBV)の診断法は臨床および血液学的診断法に頼るしかなかった.近年開発されたreal-time PCR法は蛍光色素とArレーザーとを用いウイルスDNAを迅速簡便に定量解析できるシステムである.同法は,造血幹細胞・生体肝移植後の致命的な合併症であるEBV関連リンパ増殖性疾患の診断およびその治療効果の判定に応用されている.real-time PCR法によりEBV関連リンパ増殖性疾患を早期診断できるようになり免疫抑制剤を減量するなどして,進行を抑制・自然退縮させることが可能である.
雑誌目次
検査と技術33巻8号
2005年08月発行
雑誌目次
病気のはなし
伝染性単核球症
著者: 原紳也 , 木村宏
ページ範囲:P.704 - P.707
技術講座 免疫
抗核抗体―間接蛍光抗体法
著者: 陣内記代 , 大竹皓子
ページ範囲:P.709 - P.714
新しい知見
抗核抗体(anti nuclear antibody,ANA)は膠原病患者血清中に広く認められる細胞核成分に反応する自己抗体の総称で,特定の疾患または臨床症状と関連するため膠原病の早期診断,予後の推定および治療方針の決定などにおいて重要とされている.
ANA検査はヒト喉頭癌由来細胞であるHEp-2細胞を核材とした間接蛍光抗体法が広く用いられているが,近年,間接蛍光抗体法と同様にスクリーニング検査を目的とした,複数の特異核抗原を固相化したELISA(enzyme-linked immunosorbent assay)法や固相化抗原にHEp-2細胞抽出成分と複数のリコンビナント抗原を用いた全自動EIA(enzyme immunoassay)法なども報告されている.これらの方法は操作が簡便で,迅速に多数検体処理が可能であり,客観的な結果が得られることから,検査効率の向上が図れると期待されている.
病理
染色骨髄液塗抹標本を用いたDNA抽出と微小残存病変検索への臨床応用
著者: 宮西節子
ページ範囲:P.715 - P.718
新しい知見
染色後数年間保存された骨髄液塗抹標本からDNAを抽出した報告は極めて少ないので,基礎的検討を行いさらに微小残存病変の検出に臨床応用した.
塗抹標本は細胞溶解液で塗抹部分を剥離し,プロテイナーゼK消化後,フェノール/クロロホルム法で精製した.標本1枚からの抽出量は5.4±3.26μg(平均±SD)で,PCR法によるβ-グロビン遺伝子の増幅可能なサイズは,3年間保存した塗抹標本では4/5例で536bp,4~5年間保存では1/5例で268bpを増幅することができた.目的とする遺伝子の増幅サイズを考えたプライマーを設計することにより,微小残存病変(minimal residual disease,MRD)検出をはじめとする多様な遺伝子検査に応用することができる.
血液
骨髄穿刺標本作製法
著者: 野上小民 , 高木康
ページ範囲:P.719 - P.723
新しい知見
成人の急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia,ALL)は,予後不良とされている.そのうち30%の症例は,染色体検査:フィラデルフィア染色体(Ph染色体)陽性,遺伝子検査:BCR/ABL mRNA陽性であり,形態学的にはリンパ球系芽球細胞優位(POD染色:陰性),細胞表面マーカー:CD10,CD19,CD33,CD34,KORSA陽性である.すなわち二系統の細胞系列の性質を併せ持つ,いわゆるbiphenotypeといわれている.このような症例は,通常の化学療法では治療不可能である.近年開発されたBCR/ABLチロシンキナーゼの阻害剤であるメシル酸イマチニブが,Ph染色体陽性の慢性骨髄性白血病(chronic myeloid leukemia,CML)のほかにPh陽性のALLにも効果があると報告された.国内でも初期の寛解導入療法後に化学療法とイマチニブとを併用する多施設共同試験が進み,効果が期待されている.このような症例では,標本の形態学観察と併せて染色体検査,遺伝子検査,細胞表面マーカーが必要である.
疾患と検査値の推移
心房細動とPT,INR
著者: 岩出和徳 , 青崎正彦 , 巽藤緒
ページ範囲:P.731 - P.737
はじめに
近年,心房細動による血栓塞栓症,特に脳塞栓症が注目されている.脳塞栓症は,前兆なく突然発症し,他のタイプの脳梗塞と比べ死亡率が高く,後遺症も重篤であり,QOL(quality of life,生活の質)の観点からもその予防は重要である.海外を中心にその血栓塞栓症予防の大規模臨床試験が数々発表され,わが国でも治療指針であるガイドラインが作成されている.
本稿では,心房細動における血栓塞栓症およびその予防(ワルファリン療法)について概説し,ワルファリン療法の際に用いられる凝血学的検査であるプロトロンビン時間(prothrombin time,PT)および国際標準比(International Normalized Ratio,INR)について解説する.
オピニオン
臨床検査の価値をアピールしよう
著者: 坂野弘太郎
ページ範囲:P.708 - P.708
今日,患者さん,医療従事者,病院経営陣にとって臨床検査はブラックボックスになっており,必ずしも正当な理解や評価をされていません.これまで「臨床検査の顔が見えない」は,臨床検査のプロが信頼を勝ち得ていることの賞賛の言葉でしたが,今や「コストを削減しても臨床検査のアウトプットは変わらない」と誤解されてしまう一因となっています.
「給食コストを削減すると患者さんから不満の声があがるが,検査コストを削減しても当事者以外には強い不満の声があがらない」ため,検査はコスト削減の格好のターゲットとなっています.確かに検査コストを削減しても,すぐには大問題は発生しないかもしれません.検査医,検査技師が最大限の努力を払い,当面は乗り切ることができる運用を工夫するからです.これまでに育ってきた人材がいるため,少々の無理をすることもできます.しかし,昨今はぎりぎりの一線を越えるコスト削減も多く,正確性,迅速性,測定値以外の付加価値情報,リスクマネジメント,院内感染対策,人材の教育や育成など,すぐには大問題として顕在化しないものの,医療の質の維持や向上に不可欠なインフラが確実に犠牲になっています.
絵で見る免疫学 基礎編68
自然免疫の細胞と役割(2) 自然免疫におけるパターン認識レセプターその2 TLR(Toll-like receptor)
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.726 - P.727
筆者が免疫の研究を始めたころ,ヒトIgG抗体作製の際に,抗原とするヒトIgGに結核菌抽出物を加えエマルジョンを作りこれを動物に投与するように指導された.ヒトIgG抗体を作るのになぜ結核菌抽出物を加えるのかとの問いに「とにかく抗体がよくできるから」との答えしか得られなかった.あれから40年,TLR(Toll-like receptor)の発見でようやくその答えが得られた.TLRに関しては先に述べているが(第31巻第9号,804-805,2003),最近TLRの研究成果が著しいので新しい知見を加えて再度取り上げる.
獲得免疫系における非自己はマクロファージや樹状細胞などの抗原提示細胞が取り込んだ病原体を消化してできたペプチドである.TLRが発見される以前は自然免疫系における非自己はその実態が明らかではなかったが,自然免疫系における非自己とは病原体の細胞壁の構成成分である脂質と蛋白質そして核酸などの分子であり,TLRがこれらを認識することが明らかになった.したがって,TLRは侵入した病原体を迅速に認識し排除する免疫応答システムの引き金であるといえよう.TLRが病原体特有の分子を認識すると,細胞内のシグナル伝達回路を活性化してIL(interleukin)-12,IL-6やTNF(tumor necrosis factor,腫瘍壊死因子)-α,IFN(interferon)-α,IFN-βなどのサイトカインの産生を促すので,TLRは自然免疫のみならず獲得免疫系をも活性化し,感染防御機構において重要な役割を果たすのである(図1).結核菌抽出物をアジュバント(免疫応答を増強する意味)として用いる理由はここにあったのである.現在9種類のTLRの機能が明確にされている.
ワンポイントアドバイス
測定値への干渉要因を考える
著者: 早川美恵子
ページ範囲:P.775 - P.775
私たちは,新しい試薬や機器の検討に当たって,干渉物質の影響確認を行っている.通常検討されている干渉物質は,ビリルビン,ヘモグロビン,乳び,の三物質である.しかし,検討で影響がなかったからといって安心してはいけない.例えば,「乳び」の代用として頻用されているホルマジンは,脂質とは粒子の大きさや質量などが異なっているので,検出原理によっては,実際の乳びとは影響の度合いが違ってくることになる.また,「ヘモグロビンの影響」といっても,“溶血によるさまざまな物質が遊出した場合の影響をヘモグロビン指数として表現した”ということであるので,同じ溶血指数であっても,赤血球から逸脱してくる物質の量には個人差があり,影響の度合いも異なってくることになる.
この三物質の他にも,体内には肉眼では判断できない多種多様の物質が存在し,何が測定系に影響を与えるのかは予測がつかない.
けんさアラカルト
―異常値となるメカニズム 3.脂質検査異常値データ・1―家族性高コレステロール血症と検査データ
著者: 塚本秀子
ページ範囲:P.776 - P.777
種々のリポ蛋白質のうちでコレステロールの含量の多いLDL(low density lipoprotein,低比重リポ蛋白質)は冠動脈疾患(coronary heart disease,CHD)などの動脈硬化性疾患と最も関連が強い.多くの疫学研究により血清総コレステロール(total cholesterol,TC)の上昇に比例し,CHDの発症危険率が増すことは周知の事実である.例えばTCが200mg/dlのときの危険率を基準とするとTC250mg/dlでは2倍,TC300mg/dlでは4倍にも上昇するという.また近年ではCHDの診療,管理にはTCよりもLDL-コレステロール(LDL-C)の測定に重点が移ってきている.そして日常検査のなかでLDL-Cの高値に度々遭遇するが,これが原発性(一次性)高コレステロールなのか続発性(二次性)なのか見極めなければならない.ここではCHD発症の危険率の高い原発性高脂血症の一つである家族性高コレステロール血症(familial hypercholesterolemia,FH)についてわれわれの検査データを中心に述べる.
■家族性高コレステロール血症,FHの成因
FHはLDLレセプターの遺伝的欠損(異常症)によることが明らかとなっている.両親から受け継いだ1対のレセプター遺伝子のうち片方のみに欠損を示すヘテロ接合体と両方の完全欠損を示すホモ接合体とがある.これらは常染色体優性遺伝疾患であり,発症頻度はヘテロ接合体で約500人に1例と比較的多く,ホモ接合体は約100万人に1例とされている.すべての細胞は細胞膜にLDLレセプターを有している.これを介してLDLを細胞内に取り込み分解・合成を行い,細胞内への過剰なコレステロールの蓄積を防ぐことで血中のコレステロール値を調節している.FHではこのレセプターの遺伝子に異常があるためLDLレセプターそのものが欠損したり,機能が障害されたりするので,細胞内にLDLを取り込めず,血中にLDL-Cが多量に停滞してしまう.その結果,著明な高コレステロール血症を呈することになる.図にはその成因となるLDL遺伝子変異を示した.現時点で国内では80種以上の多様性が認められている.
輸血副作用の現状
著者: 田山達也
ページ範囲:P.778 - P.779
2003年,医療機関から血液センターに報告された輸血副作用(疑いを含む)の症例数は,非溶血性副作用1,307件(81.4%),輸血感染症256件(15.9%),溶血性副作用25件(1.6%),輸血関連移植片対宿主病(transfusion associated-graft versus host disease,TA-GVHD)およびその他3件の計1,606件であった(図,仮集計).報告数は年々増加しており,特に2003年は輸血感染症報告が対前年比1.8倍に増加したことが特記される.
非溶血性副作用では,例年,蕁麻疹や発熱などの軽微な副作用が70%程度を占める一方で,アナフィラキシー(様)反応および血圧低下を伴ったアナフィラキシー(様)ショック,血圧低下や呼吸困難などの重篤な副作用が20%程度報告されている.血液センターは,これらの症例について抗HLA抗体,抗血小板抗体,抗顆粒球抗体,抗IgA抗体など約15種類の血漿蛋白質抗体および血漿蛋白質欠損を調査している.血漿蛋白質欠損症例は,重篤な副作用として報告されることが多く,1997年から2003年までにIgA欠損4例,ハプトグロビン欠損13例,C9欠損3例が確認されている.IgA欠損者が数百人に1人とされる欧米に比べて,日本人のIgA欠損者は数万人に1人と少ない.一方,日本ではハプトグロビン欠損者は4,000~9,000人に1人と欧米より多く,輸血副作用の原因となっている.これらの症例の再発防止には,次回以降の輸血で洗浄した血液製剤を用いるか,ステロイド剤の前投与などの処置を行うことが有効である.
今月の表紙
百聞は一見に如かず・20 心機能障害を形態から見ると?
著者: 松谷章司
ページ範囲:P.730 - P.730
昔,組織培養の基礎を学ぶ目的で,ラット胎児の種々の臓器を培養したことがある.組織を無菌的に摘出し,さらに注意深く細片にして,調製した培地を入れたシャーレに散布するのである.変性したり,死滅し浮かんだ細胞は何度か培養液を交換すると除去され,いわゆる生きのいい細胞だけがシャーレの底にシート状に張り付くのである.ほとんど無色透明な細胞なので,倒立位相差顕微鏡でコントラストを付けて観察すると,in vitroでも生き続ける個々の細胞の生命力に驚かされる.今でも印象に残っているのは心筋細胞である.散在性にシャーレの底に定着した心筋細胞は各々特有のリズムで収縮し始め,しばらくして,小集団を作るとそれぞれ連動して収縮し,やがてシャーレの底一面にシート状になったとき,全部の細胞が同じリズムで収縮するのは実に感動的であった.心筋の収縮というものを細胞形態で観察できたのだった.種々の病態において心筋組織はどのような病理形態学的違いを示すのだろうか.心筋症を高血圧症あるいは悪液質の場合と病理形態学的に比較してみる.
心筋症の定義は心機能障害を伴う心筋疾患であり,①拡張型心筋症,②肥大型心筋症,③拘束型心筋症,④不整脈原性右室心筋症などが挙げられる.
Laboratory Practice 生理 超音波像の読みかた
小児科疾患
著者: 久守孝司
ページ範囲:P.738 - P.746
はじめに
超音波検査は,小児に最適の画像検査であり,今や臨床に不可欠である.検査の対象領域は成人以上に広く,新生児・乳児期の頭蓋内・脊髄(髄膜瘤など)・股関節(股関節脱臼など)などの領域はその代表である.
装置の選択は重要で,特に探触子にこだわるべきである.体が小さく目的臓器までの距離が短いことを最大限に生かすため,高周波(すなわち高解像度)の探触子,できれば小型のコンベックス型のものを使用する.また,検査場所は,保温や児の不安軽減のため,児がいるベッドサイドに装置を移動して行うことも検討していただきたい.
ここでは,小児腹部領域に限って,代表的な疾患の超音波画像を紹介する.
生化学 自動分析装置の検査データの質を上げるためのポイント
クロスコンタミネーションやキャリーオーバーの軽減化・回避
著者: 松尾宏 , 稲次稔
ページ範囲:P.747 - P.749
はじめに
現在医療関係者に最も普及しているオープンディスクリートタイプの自動分析装置において,反応セルまたは試薬ピペットのクロスコンタミネーションによる測定値への影響は無視できないものであり,装置または試薬キット導入時に必須の基礎検討対象課題となっています.対策を講じた一例として,弊社の自動分析装置,JCA-BMシリーズに搭載されているコンタミネーションマップ作成プログラムについて説明します.
検査室の安全管理・6
わが国の臨床検査室の安全管理の実態およびマニュアル・その1 臨床検査室の安全管理の実態
著者: 石橋みどり
ページ範囲:P.763 - P.768
はじめに
患者の取り違え,投薬ミス,手術後管理の不適切などの医療事故が社会的問題としてクローズアップされて久しい.これは臨床検査の分野においても同様であり,多くの患者が臨床検査データにより病態の診断,治療経過の観察がなされている状況を考慮すれば投薬ミスなどと同様,重要な課題と考えられる.殊に遺伝子検査,染色体検査,感染症検査など,診断特異性が高く,結果が診断に直結する検査が普及した昨今では検査過誤が重大な医療事故につながる可能性を秘めている.また,採血,生理機能検査など,臨床検査技師が患者に直接,医療行為を行う機会が増加し,患者との接触から派生するインシデントも増加傾向にあり,臨床検査の安全対策確立が急務となっている.
今回,「臨床検査室の安全管理」シリーズでは,「わが国の臨床検査室の安全管理の実態およびマニュアル」というテーマで2回にわたり,その1「臨床検査室の安全管理の実態」と,その2「臨床検査室の安全管理指針」について,厚生労働省科学研究班での研究結果の概要を紹介しながら臨床検査室の安全管理について述べてみたい.
トピックス
血栓症急性期の病態把握に有用な凝血分子マーカー,フィブリンモノマー複合体
著者: 山口桂司 , 北島勲
ページ範囲:P.785 - P.788
はじめに
近年,高齢化や生活習慣の欧米化に伴って,わが国でも血栓・塞栓症は増加傾向にある.新潟県中越地震後の車中生活によって下肢深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症が多発したことは記憶に新しい.心筋梗塞,脳梗塞,肺血栓塞栓症は生命にかかわる血栓性疾患であり,早期診断と早期治療が重要である.今まで,凝固線溶の分子マーカーとして,トロンビン-アンチトロンビン複合体(thrombin-antithrombin complex,TAT),プロトロンビンフラグメント1+2(prothrombin fragment,PF1+2),フィブリノペプタイドA(fibrinopeptide A,FPA),Dダイマーなどが利用されてきた.しかし,これらは凝固系活性化の最終段階産物であり,血栓症の結果の評価として利用され,その有用性に関しては議論がある.近年,フィブリンモノマー複合体(fibrin monomer complex,FMC)の新しい抗体が作製され,その定量化により血栓症急性期の病態の予知・早期診断としての有用性が期待されている.
本稿ではなぜFMCが急性期の病態を捉えることができるのか,抗体の原理と臨床データを示すとともに,今後の臨床検査への応用について述べる.
間質性膀胱炎
著者: 間宮良美
ページ範囲:P.788 - P.790
はじめに
泌尿器科領域で最近関心が高まっている疾患の一つに間質性膀胱炎(interstitial cystitis)がある.欧米ではごく一般的な疾患で,米国では70万人以上の患者がいるといわれている.一方,わが国では漠然と難治性の慢性膀胱炎とされ研究対象にされていなかった経緯があるが,近年,それらの症例のうちに間質性膀胱炎がかなりの割合で含まれている可能性が指摘され,2002年に日本間質性膀胱炎研究会(ホームページhttp://sicj.umin.jp/)が設立されるなど注目を浴びるようになった.
本疾患は年齢,性別を問わず発病するが特に女性に多くみられる.発病の原因については未だ不明な点が多いが,膀胱の非特異的防御機構であるグリコサミノグリカン(glycosaminoglycan,GAG)層の欠損,変性説が有力視されている.なんらかの要因でGAG層がダメージを受け,それが修復せずに続いている状態が間質性膀胱炎といえる.したがって,間質性膀胱炎とは一つの疾患ではなく,頻尿,尿意切迫感,膀胱部の疼痛などを主訴とし,感染や特異的な病理所見を伴わない症候群として捉えるのが一般的である.通常の膀胱炎は細菌による尿路感染で抗生物質がよく効くが,本疾患に対しては無効である.ただし,尿路感染があるから本疾患を否定できるものではなく,感染が消失してからも症状が持続する場合は本疾患を疑うべきである.また,頻尿や尿意切迫感などの症状が強い場合には,いわゆる過活動膀胱(over active bladder,OAB)として診断・治療されることがあり,この場合抗コリン剤を投与しても症状が改善しないときにも本疾患を疑うべきである.そのほか,間質性膀胱炎と鑑別すべき疾患として膀胱癌,膣感染症,子宮内膜症,放射線性膀胱炎,前立腺炎,神経症などがある.
本疾患の診断にたどりつくまでには容易でないことが多く,慢性膀胱炎として長期間抗生剤を投与されたり,心身症として治療されたりする場合も多い.
どうする?パニック値 血液
4.血中PaCO2異常値
著者: 田窪敏夫
ページ範囲:P.728 - P.729
当院の基準
PaCO2は比較的一定に保たれている(正常域 35~45Torr).年齢による変動はほとんどないが,男女差については,一般に女性のほうがわずかに低いとの報告がある.
対応法
異常値をみたら,まず,呼吸状態を把握する.PaCO2は換気の指標であると考えられており,低PaCO2では過換気が,高PaCO2では低換気が予想される.さらにPaCO2単独でなく,PaO2,HCO3-の値と組み合わせて解釈することが大切である.PaCO2の異常がみられる原因疾患を表に示す.
検査じょうほう室 生理:超音波検査のステップアップ
甲状腺
著者: 三村喜美 , 太田寿 , 森田新二
ページ範囲:P.750 - P.756
はじめに
甲状腺の画像診断としては超音波,軟X線,各種シンチグラフィ,CT,さらにMRIなどが行われる.これらの検査はそれぞれに特徴を有し,目的に応じて実施されている.超音波検査は操作も簡便で非侵襲的でかつ安価であり,また多くの情報がリアルタイムに得られることより甲状腺腫瘍の鑑別診断の第一段階の検査として,CTやMRIよりも広く臨床の場に応用されている.画像処理技術の向上により5mm以下の小さな病変も描出可能である.またドプラ効果(Doppler effect)を応用し,甲状腺あるいは腫瘍内部の血流の状態も観察することができる.甲状腺の超音波検査はスクリーニング検査から診療前検査あるいは手術前の精密検査としておおいに活用されている.甲状腺超音波検査を実施するための操作方法,画像撮影のコツ,良性・悪性診断について簡単に述べる.
血液:自動血球分析装置のフラッグ処理で困ったこと
血清鉄が正常なのに[Iron Deficiency?]
著者: 横尾ハル江
ページ範囲:P.757 - P.759
はじめに
近年,自動血球計数装置は,血球計数だけではなく白血球5分類も同時測定できる装置が主流となっています.当検査室も2000年3月よりXE-2100とSP-100とを接続したXE-AlphaNを使用しています.XE-2100では血球計数には主に直流電流を用いて細胞の大きさを捉えるDC検出方式が,白血球5分類には高周波電流を用いて細胞内部の情報を主に捉えるRF検出方式とDC検出方式との両方を使用したRF/DC検出方式と半導体レーザーを使用したフローサイトメトリーとの二法が用いられています.半導体レーザーは一つの細胞から得られる前方散乱光,側方散乱光,側方蛍光の三つの信号を解析して細胞を弁別します.前方散乱光からは細胞の大きさの情報を,側方散乱光からは細胞の内部情報(核の形,顆粒の有無など)を引き出し,側方蛍光からは主に核酸量(DNA,RNA)の情報を得ています.赤芽球の検出,網赤血球,血小板測定の一部にも半導体レーザーを使用したフローサイトメトリーが用いられています.HGB測定にはSLS-Hb法が使用されています1,2).
XE-2100でのPOSITIVE検体にはデータになんらかの異常が認められ39種類のIPメッセージ(インタープリティブメッセージ)のどれかが出力されます.これがフラッグのことです.[Iron Deficiency?]はMCHC,MCV,RDW-CVより判定します.
生化学:臓器マーカー
前立腺マーカー
著者: 伊藤一人
ページ範囲:P.760 - P.762
はじめに
前立腺マーカー=前立腺特異抗原(prostate specific antigen,PSA)といっても差し支えないほど,PSAおよびPSA関連マーカーの前立腺マーカーとしての現時点での役割は大きい.
PSA検査の出現によって世界中の前立腺癌のランドスケープは一変したといわれている.PSA検査出現以前には前立腺癌の約半数は既に骨に転移した状態で発見されており,治療法は限られ,骨転移症例の約半数の症例は5年以内に死亡していた.欧米諸国において前立腺癌はその罹患率・死亡率の高さから社会問題となっていたが,1980年代後半からPSAスクリーニングが普及し,その後1992年前後よりカナダ・米国の前立腺癌の死亡率は低下傾向にある.
わが国において,前立腺癌は現在男性癌の6番目の罹患率,8番目の死亡率であるが,今後急激な増加が予測され,1995年の死亡率の実測値と,2015年の死亡予測値の比は,約3倍と男性癌中で最も高い1)ことからも,前立腺マーカーとしてのPSAを用いた最適なスクリーニングシステムの確立は急務である.
臨床検査技師のための実践医療データベース論
第8章 検査データベースの構築
著者: 片岡浩巳
ページ範囲:P.769 - P.774
はじめに
本章から,実践医療データベース論の最大の目的であった検査データベースについて解説を進めていく.
検査データベースの利用目的は,円滑な検査業務の遂行にあるが,もう一つの重要な目的に,エビデンス創出のための多角的な情報検索の実現がある.これには,その情報検索に適したデータベースの設計を行うことが必要である.しかし,一般的な検査室に導入されている臨床検査情報システムは,多角的な情報検索に耐えうる設計は行われていない.各種の情報検索を高速に行えるようにするには,データベースの利用目的を明確にし,その目的に合った最適な設計を行うことと,データベースの運用方法に対しても,厳しい制約を設ける必要がある.例えば,数値型の連続値の検査結果項目の場合,テーブルの中に報告用の文字型フィールドと検索用の数値型フィールドとを同時に持たせることである.この設定により検査値の数値比較が高速に実行できる.また,定性値と定量値といった複数の表現形で検査結果を入力したいのであれば,新しい検査項目を増設する必要があり,マスターの保守を徹底して行うことが重要である.
本章では,どのような検索要求にも耐え,日常検査業務にも利用可能な検査データベース構築のための基本的なスキーマの設計事例について紹介する.さらに,このデータベースを利用して,第9章で解説する予定の各種集計業務やTAT分析,そして,第10,11章で解説する予定の感度特異度やROC分析について,SQLを用いて短時間で解くことができるデータベースの設計を行うことを目標とした.
ラボクイズ
一般検査 1
著者: 吉野一敬
ページ範囲:P.724 - P.724
一般検査のうち嚢胞液の検査は,検体や検査の取り扱いが難しいもののひとつです.
問題1 症例:発症時年齢52歳,女性.
縦隔洞に嚢胞があることが判明して他院より紹介された患者です.縦隔洞に楕円形の嚢胞があり嚢胞液を穿刺吸引,嚢胞液は肉眼的に少し粘液性のコーヒー牛乳様検体でした.図1,2は縦隔洞嚢胞内よりの膿汁液より検出したもので大きさは直径が0.2~0.4mmで円形もしくは多型性です.
7月号の解答と解説
著者: 東克巳
ページ範囲:P.725 - P.725
【問題1】 解答:③好塩基球
解説:造血器腫瘍の補助的診断の一つ,免疫学的方法のうち,フローサイトメトリー(flow cytometry,FCM)が造血器腫瘍の病型分類に,化学療法など治療後のフォローアップに威力を発揮している.
急性白血病では,治療効果の評価指標として,骨髄中の芽球が5%未満を完全寛解としている.しかし,これは白血病が治癒したことにはならない.腫瘍細胞が再増殖すると再発ということになる.ほんのわずかに白血病細胞が残っていることを微小残存病変(minimal residual disease,MRD)という.このMRD検出にもFCMが威力を発揮する.これはCD45ゲーティング(ブラストゲーティング)といわれるSSC/CD45の解析である.
けんさ質問箱Q&A
乳糜体腔液の確認の仕かたは
著者: 𠮷村英雄
ページ範囲:P.781 - P.782
乳糜体腔液の確認の仕かたは,細胞診検査室でズダン染色をすべきなのでしょうか.そうであるならば,そのとき,沈渣でズダン染色をして確認すべきでしょうか,教えてください.(岐阜市 A.O.生)
体腔液は,胸腔や腹腔および心膜腔に病的に貯留した液で,血管内圧の亢進・循環障害や門脈圧の亢進および膠質浸透圧の低下などによって起こると考えられている濾出液と毛細血管浸透圧の亢進やリンパ灌流の低下などに起因するとされている滲出液とに大別されます.また,その外観から漿液性,血性,膿様,粘液様,乳糜などに分けられます.
NMP22検査の有用性は
著者: 武島仁
ページ範囲:P.783 - P.784
尿路上皮癌において尿中NMP22検査は尿細胞診より感受性が高いといわれています.その測定上のコツと有用性,そして最近開発された簡易検査法についても教えてください.(東京都板橋区 M.A.生)
■膀胱癌とは
膀胱癌の腫瘍マーカーであるNMP22について説明する前に,膀胱癌について若干の解説をします.
基本情報
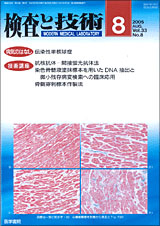
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
