「一般検査を担当することになったけど,どの本を見て勉強すればよいのかわからない」 「一般検査は対象となる検査材料が多いため本も多岐にわたる.すべてが一冊にまとまった本はないのか」などの悩みを抱えている方は,ぜひ本書を読んでみてください.
本書は,多くの病院で日常的に検査されている一般検査領域におけるほぼすべての検査を1冊にまとめた内容となっております.
雑誌目次
検査と技術45巻3号
2017年03月発行
雑誌目次
増刊号 一般検査ベーシックマスター
序文 フリーアクセス
著者: 脇田満
ページ範囲:P.180 - P.180
第1部 基礎から学ぼう一般検査
尿定性検査
著者: 脇田満
ページ範囲:P.182 - P.189
はじめに
尿定性検査は,尿中に排泄された蛋白やブドウ糖をはじめ,さまざまな成分を定性または半定量的に測定できるため,腎・泌尿器疾患のスクリーニング検査として用いられている.多くの検査室では試験紙法による検査が実施されている.
従来の試験紙は,製造メーカーごとに検出感度が異なっていたため測定結果に差異が生じていた.2004年4月に日本臨床検査標準協議会(Japanese Committee For Clinical Laboratory Standards:JCCLS)は,「尿試験紙検査法JCCLS提案指針—尿蛋白,尿ブドウ糖,尿潜血試験紙部分表示の統一化」を発表し,国内で販売される試験紙の蛋白,ブドウ糖,潜血の3項目について1+の濃度が統一化された(蛋白1+:30mg/dL,ブドウ糖1+:100mg/dL,潜血1+:0.06mg/dL).本稿では,試験紙法を中心に解説する.
尿定量検査
著者: 堀尾勝
ページ範囲:P.190 - P.195
はじめに
尿蛋白は慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の重症度と関連しており,尿蛋白定量はCKD診療の基本である.24時間蓄尿によって1日排泄量を算出することが重要であるが,一般臨床では蓄尿が煩雑であり,随時尿の尿クレアチニン(Cr)補正値を用いる場合が多い1).
糸球体障害と尿細管障害では排泄される尿蛋白の種類が異なるため,アルブミン,β2ミクログロブリン(β2-microglobulin:β2-MG),α1ミクログロブリン(α1-microglobulin:α1-MG),NAG(N-acetyl-β-D-glucosaminidase)など,個別の蛋白の測定も有用である.ほかに,ブドウ糖,電解質,尿酸,クレアチニン,アミラーゼなど多くの物質の定量検査が行われるが,測定項目によっては尿のpH(hydrogen ion exponent)などが測定に影響する場合もある.測定に影響する要因や尿排泄の機序,日内変動の影響を理解しておくことが重要である.
本稿では,尿定量検査のうち,主な項目について述べる.
尿沈渣検査—血球
著者: 佐伯仁志
ページ範囲:P.196 - P.202
はじめに
尿中に血球成分を認めるということは,腎泌尿器系に出血や炎症などの何らかの異常が存在することを示唆し,これらを検出することの臨床的意義は大きい.例えば,尿中の赤血球は出血所見を示すのみならず,詳細に赤血球形態を観察することで出血部位を推定することが可能である.白血球も,好中球や好酸球などを詳細に観察することで有用な情報を提供することが可能である.
本稿では,日常の鏡検法,各所見出現の意義および紛らわしい成分との鑑別法などについて述べる.
尿沈渣検査—上皮細胞
著者: 田中雅美
ページ範囲:P.204 - P.213
はじめに
尿沈渣検査において,形態的に類似する良性細胞の分類や,異型細胞に類似する良性細胞の判定に苦慮することがある.このような状況を回避するためには,どうしたらよいのだろうか.それは,①上皮細胞の機能と形態,②上皮細胞の出現する臨床的意義,③異型細胞と異型細胞類似細胞の鑑別,の3項目について理解を深めることである.つまり,上皮細胞の機能・基本形態,そして,その細胞が出現する臨床的意義を学ぶことで類似細胞の比較・鑑別が容易になり,細胞分類や良悪の判定,組織型の推定が可能になるのである.
尿沈渣検査—円柱
著者: 久代真也
ページ範囲:P.214 - P.222
はじめに
円柱の分類法は,Lippmanの分類から「尿沈渣検査法」(1991年)1)で現在の骨格となる分類法に変わり,「尿沈渣検査法2000」(JCCLS GP1-P3:2000年)2)で臨床的意義を加えられ,「尿沈渣検査法2010」(JCCLS GP1-P4:2010年)3)へと変化し,次第に臨床的関連性が明らかにされてきた.
本稿では,日常検査で分類可能な円柱について,出現機序・形態特徴と鑑別ポイント,臨床的意義および関連性,ピットフォールを解説する.
尿沈渣検査—塩類・結晶類
著者: 堀田真希
ページ範囲:P.224 - P.235
塩類・結晶類
尿中に出現する塩類・結晶類は,大部分が摂取した飲食物や体内の塩類代謝によるものである1).代謝された成分が腎臓から排泄され,尿路系や排尿後の採尿容器内で,種々の物理化学的作用(含有濃度,pH,温度,共存物質など)によって溶解度が低下し,析出する.よって,尿沈渣にみられる塩類・結晶類の多くは通常尿成分であるが,病的状態によって出現する結晶はもとより,通常結晶においても病態によって重要な成分になることもしばしばあり,臨床的意義のある成分を鑑別し,報告することは非常に重要である.
便潜血検査
著者: 岡田茂治
ページ範囲:P.236 - P.242
はじめに
便潜血検査とは,化学法,免疫法を含めて使用されている便中ヘモグロビン(hemoglobin:Hb)検査の呼称である.しかし,現在,化学法は実施されておらず,抗ヒトヘモグロビンA0(hemoglobin A0:HbA0)抗体を用いた免疫学的便Hb検査法(以下,便Hb検査)が実施されている.
便Hb検査は臨床診療,人間ドック(個人健診),がん検診(対策型検診)と広く利用されている検査法であるが,対象や目的によって使用するカットオフ値が違うことや,他の臨床検査項目のような標準化が進んでいないことなどを認識していただきたい.今回,日常検査やコントロールサーベイで注意するべき点と今後の課題を中心にまとめた1).
寄生虫検査—虫卵・虫体
著者: 野崎司 , 浅井さとみ , 宮地勇人
ページ範囲:P.243 - P.250
はじめに
わが国の社会生活環境の変化によって,寄生虫症の動向は目覚ましい変貌を遂げた.昭和30年代まで,多くの感染者がみられた消化管寄生虫症は,公衆衛生環境の改善とともに影を潜めた.一方,熱帯・亜熱帯の開発途上国では依然として多様な寄生虫症が流行し,住民のみならず,その地を訪れる旅行者にも感染の危険がある.
また,日本人のグルメ嗜好やペット嗜好の変化に伴い,まれな寄生虫に感染するケースも増えている.このように,寄生虫症は海外からの輸入寄生虫症,ペットからの人獣共通寄生虫症などの多様化がみられ,診断・治療を左右する検査の重要性が増している.寄生虫は原虫類と蠕虫類に大別され,特に後者において,顕微鏡観察による鑑別と同定は難渋する.本稿では,蠕虫類を中心に,寄生虫の虫卵・虫体の顕微鏡検査について概説する.
寄生虫検査—原虫,マラリア
著者: 石井明
ページ範囲:P.251 - P.257
はじめに
日本国内の寄生虫感染者数は,大戦後の衛生状態の改善や集団駆虫によって激減した.しかし,海外旅行ブームや食品流通機構の発達によって,世界中から多種多様な寄生虫症が国内にもち込まれる危険性が増大している.人体内部に寄生する寄生虫は,単細胞真核生物である原虫類と多細胞からなる蠕虫類とに大別される.国内で注目されている原虫症は,1999年4月に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づく感染症発生動向調査の対象として挙げられている1).再興寄生虫症のマラリア,赤痢アメーバ症(アメーバ赤痢),ランブル鞭毛虫症(ジアルジア症),そして新興寄生虫症のクリプトスポリジウム症である.また,調査対象とはなっていないが,腟トリコモナス症は性感染症として問題となっている.
このような原虫症に対して診断を施すには,まず検体を適切に処理し,検出すべき原虫の種類や発育段階などに応じた最適検査法を選択することが重要である.さらに,一般検査室での原虫検査は光学顕微鏡によるものが主であるので,検査対象にあった顕微鏡の倍率,明るさやコントラストの調整方法,原虫を正確に鑑別するための形態的特徴を理解し,観察眼を養うことが必要である.
髄液検査
著者: 林晃司 , 境佑香梨 , 林聡
ページ範囲:P.258 - P.266
はじめに
中枢神経疾患が疑われるときに実施する髄液検査は緊急性が高い.特に細菌性髄膜炎は,症状が急速に進行し生命にかかわることがあるため,迅速かつ正確な結果報告が求められる.また,化学療法中に髄液腔内に腫瘍細胞が転移し増加する例がみられ,欠かせない検査となっている.
髄液検査は他の穿刺液検査に先んじ,『髄液検査法2002』1)によって標準化され,さらに『髄液検査技術教本』2)も発刊された.本稿では検査の進め方,臨床的意義,ピットフォールを述べる.
穿刺液検査—胸水・腹水,関節液
著者: 保科ひづる
ページ範囲:P.268 - P.276
はじめに
胸腔・腹腔および関節腔から得られた穿刺液検体については,検査は行われているが検査マニュアルとしては示されていない.今回,見直したい検査項目などを含め,細胞数算定や分画などの検査結果を診療へ導けるように解説したい.胸腔や腹腔,関節腔は,中皮細胞または滑膜細胞で覆われ,通常でも少量の液が潤滑剤として存在し,胸水・腹水は腔内の臓器の摩擦や癒着を防いで保護し,関節液は関節の潤滑作用と軟骨の栄養補給をしている.胸水や腹水は,胸腔や腹腔内の血管内静水圧と血漿膠質浸透圧とのバランスで均衡を保って一定量に保たれているが,そのバランスが崩れると貯留してくる.関節液は,滑膜が何らかの原因で炎症を起こした場合に,増量して貯留する.穿刺液検査は,その貯留原因を突き止め,治療へと結びつけるために施行される.
精液検査
著者: 佐藤和文
ページ範囲:P.277 - P.282
はじめに
精液検査は尿検査と同様に体外へ排出(射精)された液を検査し,上流の状態(造精機能)を推定するものである.留意点は他の検査と異なり,生きた細胞を検査することである.精子は精巣の精細管で形成され,精巣上体に真っ白な精子懸濁液として貯留される.射精時には精巣上体から出る精子の散逸防止と保護をするために,総量約90倍量の精囊腺液・前立腺液・カウパー(Cowper)腺液が加わって精液として射精される.精液は被検者の体調を含め造精部位の変動,各腺分泌液との比率,禁欲期間などによって大幅な濃度差を生じる.
精液検査では細胞数,形態と同様に運動性をみることも大切である.通常の血球計算盤は計測室底面に格子を刻んであるため,格子線によって自由な運動が阻害される.そのため,精液検査用に開発されたマクラー(Makler)計算盤の格子線は,精子運動を阻害しないよう,計測室の天井にあたるカバーガラスに刻まれている.マクラー計算盤は精子濃度,運動率,直進率などを計測できるが,運動精子・不動精子・奇形精子などを瞬時に判断して計測しなければならないので,使用にあたっては十分な訓練を必要とする.
運動精子を含め,計測するコツは“気象情報の読み方”であり,地図に合わせた雲の動きをみる気象レーダーを想像し,計測区画に想像した縦または横の直線を移動させ,その線にかかった精子を計測する.ヒトの目は動くものにとらわれる傾向があるので,とらわれずに計測できる訓練が必要である.
無精子の確認については液化した全精液をスピッツに入れ,3,000Gで15分間遠心後,上清を除去し全沈渣をピペットでシャーレに入れて鏡検する.精子が皆無なら無精子(azoospermia),数個なら隠れ無精子(cryptozoospermia),全量○mL中△個,1mL中×個などを報告する.造精機能は予想以上にデリケートで,数カ月前からの疲労やストレスの蓄積,喫煙,高熱,薬物,放射線などにも影響される.
第2部 一般検査の「質」を保つTips&Techniques Situation 1—検体採取から検査まで 尿検査
尿を適切に採取する
著者: 佐々木彩
ページ範囲:P.284 - P.286
Quality Controlのために
尿は患者にとって苦痛を伴わず簡便に採取できる検体である.しかし,尿は同じ人においても,温度や食物,水分摂取などによって成分が著しく変動するため,検査目的や患者の病態に応じて適切な採尿時間,採尿方法を選択しなければ正しい結果は得られない.また,細菌増殖により含有成分が変質しやすいため,適切な保存法を選択する必要がある.本稿では尿検体の種類および採尿時の注意点について解説する.
尿中アスコルビン酸が検査値に与える影響を考える
著者: 山本裕之
ページ範囲:P.287 - P.289
Quality Controlのために
・アスコルビン酸は非常に強力な還元作用を示し,試験紙の反応を阻害・抑制する働きをもつ.
・尿の出ない患者にペットボトルのお茶や清涼飲用水の飲用を勧めていないだろうか? 正しい検査結果を臨床にフィードバックするためには,患者の協力が必要であり,必要に応じて説明を行えるよう試験紙の特性を理解しておく.
・アスコルビン酸の影響を防ぐために,各社が発売中の試験紙には様々な改良がなされているが,想定以上のアスコルビン酸濃度では偽陰性化が起こる.
糞便検査
便を適切に採取する—便潜血検査
著者: 福田嘉明
ページ範囲:P.290 - P.292
Quality Controlのために
便潜血検査は,男女合計のがん死亡数予測1位の大腸がん1)を早期に発見できる重要なスクリーニング検査である.本法は,採便容器に設定されている既定量を採便し実施する.この採便操作は,被験者(患者や検診受診者)によって実施されていることが多い.したがって,被検者が正確に既定の採便量を採取できるかどうかが分析精度に大きく影響する.本稿では,便潜血検査において最も重要な採便操作について解説する.
寄生虫検査
便を適切に採取する—寄生虫検査
著者: 福富裕之
ページ範囲:P.293 - P.295
Quality Controlのために
・寄生虫検査では細菌検査よりも使用する便量が多く,検査の目的により量も異なるので,量不足にならないように適正量を採取する.
・原虫の栄養型を検出するためには,できる限り新鮮な便を用いる.
・便のなかからは蠕虫類の虫体が検出されることもあるので,必ず肉眼による外観の観察を行う.
髄液検査
髄液を適切に採取する
著者: 石山雅大
ページ範囲:P.296 - P.298
Quality Controlのために
脳脊髄液(以下,髄液)は,脳室ならびにくも膜下腔に無色透明の水様で存在する体腔液の一つで,中枢神経系の保護や恒常性の維持,そして組織液としての機能をもつとされている1).髄液の採取は検査や治療目的により採取部位が異なり,またその採取量にも制限があるため,検査を進める場合には,まず検査目的と採取部位,そして患者属性を確認することが重要となる.本稿では髄液の採取方法の違いと,その取扱いについて解説する.
検体採取から検査までの所要時間が検査値に与える影響を考える
著者: 石山雅大
ページ範囲:P.300 - P.301
Quality Controlのために
髄液は蛋白,脂質成分が少なく浸透圧も低いため,採取後放置していると様々な検査値に影響を及ぼす.この項では影響がある検査値を呈示し,それを防ぐにはどのように対応すべきか考えてみたい.
穿刺液検査
体腔液を適切に採取する
著者: 山里勝信
ページ範囲:P.302 - P.305
Quality Controlのために
体腔液(胸水,腹水,心囊液)は健常人でも少量存在するが,貯留する場合は炎症や腫瘍など何らかの原因疾患の随伴症状としてみられる.そのため,原因疾患の確定診断や体腔液貯留による呼吸困難などの症状を軽減することを目的として,体腔穿刺が行われる.したがって,体腔液の採取方法および適切な検体処理について十分に理解しておくことが重要である.
精液検査
精液を適切に採取する
著者: 青井陽子
ページ範囲:P.306 - P.307
Quality Controlのために
精液検査の所見は,射精間隔,採取後の時間経過,温度や湿度の変化,紫外線などの影響を受ける.また,検査実施前の約3カ月間に患った発熱疾患などが影響する可能性がある.採取にあたっては遺物混入や細菌汚染を避けるため,採取前には排尿し,手洗い後,マスターベーションにて滅菌された容器に精液全量を採取する.これらを検査者は患者にきちんと説明しておく必要がある.また,受け渡しはプライバシーに注意して確実に行う必要がある.
Situation 2—検査の実施 尿検査
尿の一般的性状から病態を読み解く
著者: 服部亮輔
ページ範囲:P.308 - P.310
Quality Controlのために
・尿の一般的性状(色調と混濁)は,尿定性,尿沈渣,尿定量検査などを実施する前に第一に観察するべき項目であり,さまざまな情報を得ることができる.
・一般的性状は種々の生理・病理学的条件,服用している薬剤などの影響によって変化するため,詳細に観察する必要がある.
—ココがポイント!—尿定性検査
著者: 服部亮輔 , 原美津夫
ページ範囲:P.311 - P.313
Quality Controlのために
・尿中には老廃物,薬剤または薬剤代謝産物など,さまざまな成分が含まれている.そのため,単純な構造で反応原理も化学的なものが多い尿定性試験紙法では,偽反応(偽陰性・偽陽性・異常発色)を起こすことがある.
・偽反応を発見し,正しい結果を報告するためには,尿定性試験紙の原理,含まれている試薬,偽反応の原因について正しく理解することが重要である.
・必要に応じて,確認検査を行うことが望ましい.
—検査の質を保つためのテクニック—尿沈渣標本作製
著者: 溝口義浩
ページ範囲:P.314 - P.317
Quality Controlのために
尿沈渣検査の正確さおよび精密さを保証するためには標準化が必要である.例えば遠心器やスピッツの選択など,使用する機材,遠心条件をはじめ,尿の攪拌,分注,上清の除去,沈渣積載量,カバーガラスの積載時の手技など技術面も含め,一連の尿沈渣標本作製手技をその検査に携わる検査技師が同一の方法で実施しなければ,検査結果を保証することはできない.つまり,この一連の流れが正しく行われていなければ,検査の質を低下させてしまう要因となる.
—検査の質を保つためのテクニック—尿沈渣鏡検
著者: 友田美穂子
ページ範囲:P.319 - P.323
Quality Controlのために
尿沈渣中の細胞は,比重や尿の性状,疾患,治療などさまざまな要因により変性・崩壊や多彩な形態変化を呈する.そのような条件に惑わされず正しく判定を行うためには,①細胞を判定するための基準(判定基準)を用いて鑑別を行うこと,②細胞の説明が判定基準に沿ってできるようになるまでトレーニングを行うこと,③さまざまな要因による細胞変化のバリエーションを知ること,が重要である.
糞便検査
便の一般的性状から病態を読み解く
著者: 石澤毅士
ページ範囲:P.324 - P.326
Quality Controlのために
・糞便の性状は腸管の状態を反映しており,形状・色調・臭気を観察することで病態を推測することができる.
・糞便の性状から病態を的確に把握することで,適切な検査法の選択に関与できる可能性もあるため,臨床側とのコミュニケーションも重要である.
—ココがポイント!—便潜血検査
著者: 石澤毅士
ページ範囲:P.327 - P.329
Quality Controlのために
・便潜血検査には,化学法と免疫法があり,現在では免疫法がほとんどである.
・免疫法はヒトヘモグロビン抗体を用いた抗原抗体反応を原理としており,ヒトヘモグロビンに特異的であり,下部消化管出血のスクリーニング検査として有用である.
・上部消化管出血では検出率が低いため注意が必要である.
・採便後,室温に保存すると偽低値となるので,速やかに検査をするか,検査まで冷蔵保存する.
寄生虫検査
—適切な検査プランを立てるために—とても重要,患者情報
著者: 加島準子
ページ範囲:P.330 - P.332
Quality Controlのために
国内で検査技師が寄生虫を見る機会が減り,形態学的鑑別の技術向上が難しくなってきている.このため,寄生虫検査を行う際には,入手可能な患者情報はなるべく多いほうがよい.患者情報によって感染の可能性のある寄生虫が予測できれば,適切な検査法の選択につながり,検出した寄生虫の鑑別に関しても,これらの情報を組み合わせて考えることで,より的確なものに近づけることができる.患者情報を有効に生かせるように,寄生虫に関して事前にある程度の知識をもっておくことが求められる.
—適切な検査プランを立てるために—知っておきたい感染経路と発育史
著者: 加島準子
ページ範囲:P.334 - P.337
Quality Controlのために
適切な検査を行ううえで,寄生虫の感染経路と発育史を知っておくことは患者情報と合わせて重要である.寄生虫感染が疑われるとき,成熟した成虫が産卵する前や潜伏期に検査をして陰性となっても,感染を否定することはできない.駆虫後の検査も,残った幼虫や片節が成熟して産卵するまでの時期を考慮に入れる必要がある.このように寄生虫感染の有無を確定するために,発育史を知ったうえで検査の適切な時期,適切な検体の選定が求められる.また,感染経路を知っておくことで,感染原因を推測することもできる.
—検査の質を保つためのテクニック—集卵法
著者: 福富裕之
ページ範囲:P.338 - P.339
Quality Controlのために
・集卵法を実施する場合には,目的とする寄生虫卵が検出できる方法を選択する.
・全ての集卵法はアメーバなど原虫の栄養型の検出には不向きなので,これらの疾患が疑われる場合には,直接薄層塗抹法も平行して行うのが望ましい.
・寄生虫疾患が疑われる場合には,繰り返しの検査を実施する.
—検査の質を保つためのテクニック—アメーバ類の鑑別編
著者: 福富裕之
ページ範囲:P.340 - P.343
Quality Controlのために
・アメーバ類で重要なのは,赤痢アメーバと病原性自由生活アメーバである.
・アメーバ類には,栄養型とシスト(囊子)があるので,それぞれの形態をしっかりと把握する.
・便の検査でシャルコー・ライデン結晶を検出したら,赤痢アメーバ症を強く疑う.
・赤痢アメーバ症は,無症候性のシスト保有者が最も多いので,正常便であっても,赤痢アメーバ症を否定しない.
髄液検査
なぜ,結果を迅速に報告することが重要なのか
著者: 菊地雅寛 , 田中敏典 , 山本修
ページ範囲:P.344 - P.346
Quality Controlのために
髄液化学検査は脳脊髄液(以下,髄液)中の化学物質を測定する検査で,各種中枢神経系疾患の診断に有用である.日常検査において一般的に測定されている項目として,蛋白,糖,LD,CK,Clなどが挙げられる.診断には,髄液細胞数や髄液化学検査などの検査結果を総合的に判断することが必要になる.
—検査の質を保つためのテクニック—細胞鑑別:髄液検査編
著者: 金沢聖美
ページ範囲:P.347 - P.352
Quality Controlのために
・検査室では臨床の現場は見えないが,髄液検査を必要とする患者は一般的に緊急性が高く,安定した精度の高いデータを検査室到着後30分以内に報告することが重要である.
・一般検査部門は,検体採取後一番早く検体を受け取り結果報告することになる.まずはスクリーニング検査部門として,炎症の有無や病態の振り分けが必要となる.
・計算盤上での細胞分類は,核形の鑑別だけでは限界がある.細胞質の染色性や細胞の大きさを確認することで細胞分類がしやすくなる.
—検査の質を保つためのテクニック—内部精度管理と教育
著者: 田中雅美 , 宿谷賢一
ページ範囲:P.353 - P.355
Quality Controlのために
ISO 15189の認定取得にあたり,標準作業手順書(standard operation procedure:SOP)の作成やスキルマップ(スタッフの技能・知識の状況を把握)の作成を行い,力量基準の設定をした1).以前は,実務経験が長ければ力量があるとされていたが,形態検査の習得には個人差があり,経験だけでは評価ができない.力量は,細胞判定能力,技術や検査の知識のレベルをあわせて評価されなければならない.検査の質を保ち,臨床から信頼される検査室であるためには,教育と技術習得の努力をする必要がある.
穿刺液検査
—検査の質を保つためのテクニック—メイ・ギムザ標本の作製
著者: 山里勝信
ページ範囲:P.356 - P.359
Quality Controlのために
形態検査を行ううえで,標本作製の手技や染色性は細胞判定にまで影響を及ぼす可能性がある.そのため標本作製者は,検体の性状を把握し,良好な標本を作製する必要がある.
—検査の質を保つためのテクニック—細胞鑑別:穿刺液検査編
著者: 竹村浩之
ページ範囲:P.360 - P.366
Quality Controlのために
穿刺液検査において,生体の一部に液体の貯留が認められる場合,特に胸水や腹水では,まず滲出液か濾出液かを鑑別することが,診断上,大いに参考になる.また,体腔液中に増加する細胞成分は疾患・病態によって異なるため,細胞成分の分類は,重要な検査情報である.特に腫瘍性疾患において体腔液中に腫瘍細胞を認めるか否かは,病期診断や治療法の決定の根拠となる.臨床側が患者の病態を把握し早急に正しい治療を進めていくためには,われわれ検査技師が迅速かつ正確な検査結果を提供しなければならない.そのためには,細胞を観察するための標本を正確に作製することはいうまでもないが,細胞を観察する際の鑑別ポイントや間違いやすい細胞についてしっかりと把握し,「細胞を見る目」を養うことが重要となってくる.
検査値から漏出液と滲出液を推定する
著者: 田中あゆみ
ページ範囲:P.368 - P.371
Quality Controlのために
漏出液とは,うっ血,変性,水血症,浮腫など,炎症以外の基礎疾患が原因で漏れ出た液体である.滲出液とは,炎症や悪性腫瘍から滲み出して貯留した液体であり,その原因検索と,病態の確定診断のために精査が必要となる.穿刺液検査についても,今後の精査および治療要否の判定を方向づけることを目的として,両者の鑑別を行う必要がある.
精液検査
精液の一般的性状から病態を読み解く
著者: 久野豊
ページ範囲:P.372 - P.374
Quality Controlのために
精液検査は採取時期や採取方法,検査までの時間により結果が大きく変動する.そのため3カ月以内に2回以上の検査を行い,平均値で報告する.また,最後の射精後,2日間から7日間の禁欲期間をおいて採取しなければ,精子数や精液量に影響が出る.さらに,射出直後は精囊腺由来蛋白のゲル状部分が存在するため,前立腺由来の蛋白分解酵素によりゲル状部分が液化され均一になるまで,室温または37℃のインキュベーターに5分間から15分間程度静置し,採取から1時間以内に検査する.
一般的性状には病態につながる情報が含まれていることもあるため,必ず実施する.
—検査の質を保つためのテクニック—運動率・正常形態率
著者: 久野豊
ページ範囲:P.376 - P.379
Quality Controlのために
精子の運動率や正常形態率は,総精子数と同様に,妊孕能を評価するうえで重要な検査である.一方,検査前の工程(精液の混和,標本作製など)に結果が大きく左右されるため,標準作業手順を守り,少なくとも2回以上の検査を実施して平均値で報告する.2回の差が許容誤差範囲を超える場合は,再度,標本を作製し直して再測定することが望ましい.
Situation 3—結果と報告 尿検査
異型細胞を認めたときは,こうやって進めよう
著者: 横山貴
ページ範囲:P.380 - P.383
Quality Controlのために
尿沈渣検査において異型細胞として取り扱う細胞は,基本的には「悪性細胞」または「悪性を疑う細胞」である1).正常な細胞と鑑別するためには,正常細胞の特徴を十分に把握することが重要である.ビギナーが陥りがちなミスとしては,カテーテル挿入後,尿路感染症,尿路結石症や治療にともなう核クロマチンの変性をクロマチンの増量として認識し,「悪性細胞」または「悪性を疑う細胞」と誤判定してしまうことである.このようなことがないように,なかなか容易ではないが,日頃から異型細胞と報告した場合は,その後,本当に異型細胞であったのか,それとも良性細胞であったのかを,カルテなどを閲覧し患者背景や他の検査結果などを確認することが重要である.これにより,異型細胞の鑑別スキルが向上する.
迅速報告!! 尿検査のパニック値
著者: 原美津夫
ページ範囲:P.384 - P.386
Quality Controlのために
・現在では,生化学検査結果などが1時間弱で報告可能となり,病院における尿定性検査の重要性は薄れてきている.しかし,クリニックなどの即座に生化学検査が実施できない施設では,病態を把握するための重要なスクリーニング検査の一つであることに変わりはなく,以下のケースでは尿定性検査結果の迅速な報告が非常に有用となる.
・尿沈渣検査では緊急報告値の認識が乏しいのが現状である.しかし,患者の診療科・年齢・性別などによっては,迅速な報告が,その後の診断や治療に有用な成分が存在する.
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—十分な量が採れていない尿が提出された場合
著者: 西山大揮
ページ範囲:P.387 - P.389
Quality Controlのために
・尿一般検査では,尿定性検査に約1〜2mL,尿沈渣検査に10mL,尿生化学検査に約1〜2mLほどの尿が必要になる.
・『尿沈渣検査法2010』1)では,「尿量を原則10mLとする.尿量が少ない場合でもできる限り検査を実施し,その旨を記載する」と定められている.
・一日尿量は成人で通常800〜1,500mLほどである.
・尿量の減少する病態は,乏尿,無尿,尿閉に分類される.
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—尿中に食物残渣を認める尿が提出された場合
著者: 梶明香
ページ範囲:P.390 - P.391
Quality Controlのために
尿中に食物残渣を認める尿が提出された場合,多くは肛門からの混入(採尿時のコンタミネーション)が考えられる1).女性や乳児・高齢者では,しばしば採尿の際に糞便が混入し,尿沈渣像に食物残渣がみられる1).
肛門からの混入であれば臨床的意義は乏しい2).しかし,大腸癌が膀胱に浸潤した膀胱腸瘻の場合にも尿沈渣像に食物残渣が認められる.膀胱腸瘻の症例では,膀胱と腸管が交通して糞尿を呈し,それを契機に大腸癌が発見されることがあるため,注意深く観察する必要がある1).
糞便検査
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—室温で数日保存されていた検体が提出された場合
著者: 山浦久
ページ範囲:P.392 - P.393
Quality Controlのために
糞便検査は検体採取を患者にお願いする必要があるため,その採取方法,保存方法などが測定結果を変動させる要因となる.すなわち,採便後の時間経過,保存温度によってヘモグロビンの安定性は大きく左右される.測定機器の精度管理は当然大事だが,測定前の検体がどう採取されて,どんな状態で提出されたのかを把握することも重要である.
寄生虫検査
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—鏡検時にアメーバのように動くものを認めた場合
著者: 福富裕之
ページ範囲:P.394 - P.396
Quality Controlのために
・検出されるアメーバ類で重要なものは,赤痢アメーバと髄液中の病原性自由生活アメーバなので,これらが検出された場合には迅速に報告を行う.
・鞭毛虫類,繊毛虫類,白血球などもアメーバ類と誤認する可能性があることを,理解しておく.
・アメーバ類の多くは短時間で運動性を失うので,できる限り画像に残しておく.
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—虫卵のような成分が何か判断がつかない場合
著者: 福富裕之
ページ範囲:P.398 - P.400
Quality Controlのために
・普段から,寄生虫のアトラスに記載されている寄生虫の名称と虫卵の特徴を把握しておく.
・便からは,植物や魚類の寄生虫卵も検出されることがあるので注意する.
・虫卵のような成分を認めたら,漠然と観察するのではなく,構造の一つひとつを観察する.
迅速報告!! 寄生虫検査のパニック値
著者: 福富裕之
ページ範囲:P.401 - P.403
Quality Controlのために
・日本人の旅行者がマラリアに感染すると重症化することが多いので注意する.
・髄液や体腔液から検出される寄生虫には臨床上重要なものが多いので,基本的にはすべてパニック値として報告する.
・糞線虫には類似する線虫類も多いので,パニック値として報告する場合には誤認がないように注意する.
髄液検査
迅速報告!! 髄液検査のパニック値
著者: 奈良豊
ページ範囲:P.404 - P.407
Quality Controlのために
・髄液検査は一般検査での検査報告が中枢神経系疾患の治療診断に結びつく重要な検査であり,特に細菌性髄膜炎は早急な治療が必要となるため,正確性と迅速性が必要である.
・病初期に細菌性髄膜炎でも単核球優位やウイルス性髄膜炎でも多形核球優位の場合がある.
・疾患によっては細胞数,細胞分類,臨床化学検査が乖離する場合があるので注意する.
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—計算盤内で細菌を認めた場合
著者: 金城和美
ページ範囲:P.408 - P.411
Quality Controlのために
計算盤内に細菌を認めた場合(図1),もっとも考えられる病態は細菌性髄膜炎である.細菌性髄膜炎は緊急対応を要する疾患として位置づけられており,早期の診断と適切な抗菌薬治療は患者の転帰に大きく影響する.また,髄液細胞は採取後の変性が著しいため,採取後1時間以内には細胞検査を実施しなければならない1).担当技師は細菌性髄膜炎の可能性が認められた時点で,迷わず,臨床への第一報の報告を行い,次の検査へと速やかに進めることが重要である.
穿刺液検査
自動血球分析装置を用いた細胞数算定の進め方
著者: 小林紘士
ページ範囲:P.412 - P.414
Quality Controlのために
一般検査領域において,穿刺液検査を実施するにあたり最も重要なことは,滲出液と濾出液を鑑別し疾病の診断や病態の判定に必要な情報を提供することであり,このことは以前より知られている.その中でも細胞数の算定は近年,自動血球分析装置でも測定でき,簡便かつ迅速な結果報告が可能となった.
本稿では,自動血球分析装置の使用上の注意点とスキャッタグラムの見方などを,当施設での症例を交えて紹介する.
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—鏡検時に細胞集塊を認めた場合
著者: 三橋太
ページ範囲:P.416 - P.418
Quality Controlのために
一般検査領域における穿刺液細胞の検査は,細胞数の算定が基本であり,近年では自動血球分析装置によって算定を実施している施設もある.しかし,穿刺液における細胞分画はさまざまな病態を推測できることから重要であり,塗抹標本による分画を実施していない場合,従来からのフックス・ローゼンタール(Fuchs-Rosenthal)計算盤を使用した鏡検による算定において,計算盤上で可能な限り分画することが推奨されている1).鏡検時にしばしば認められる細胞集塊については,病態を推測するうえで多くの情報を有しているため注意深く観察し,塗抹標本の作製や,細胞診検査の必要性を臨床に伝えることなどが重要である.
精液検査
—こんな症例と遭遇したとき,あなたならどうする?—精液中に精子がまったく認められない場合
著者: 三橋太
ページ範囲:P.420 - P.421
Quality Controlのために
精液検査は,体外に排出(射精)された精液により主に造精機能を推定するものであり,精液量,精子濃度,運動率,精子正常形態率,白血球数などを測定する.その基準値は表1に示すとおりであり,精子濃度の基準値は15×106/mL以上とされている1).しかし,無精子症や乏精子症では鏡検時に精子がまったく認められない場合があり,適切な再検査が必要となってくる.精子濃度に影響を与える要因は,禁欲期間など採取時に関連するものと混和などの検査時に関連するものがあり,双方を考慮することが重要である.
基本情報
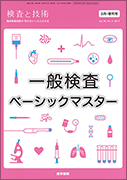
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
