学会発表や論文執筆って,どうやって進めればよいだろう?
本増刊号は,その悩みや疑問に応えることをコンセプトに企画しました.
雑誌目次
検査と技術48巻9号
2020年09月発行
雑誌目次
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
はじめに フリーアクセス
著者: 菊地良介
ページ範囲:P.851 - P.851
1章 研究をはじめよう!
臨床検査技師が研究を行うメリット—臨床検査医の視点から
著者: 矢冨裕
ページ範囲:P.856 - P.858
はじめに
私は,現在,大学病院の検査部門に勤務しており,多くの臨床検査技師とともに働いています.特定機能病院における高度な医療を臨床検査の面から支えるべく,各診療科から依頼される検査を,質高く,できるだけ迅速に結果返却できるように務めています.大学病院における臨床検査技師にとって,研究は本務ではありません.しかし,日々,多くの症例の検査を実施するなかで,解決すべき問題点が多々発生します.それを解決するためにも,研究マインドをもつことは極めて大切であり,さらには,自己研鑽という形になりますが,実際に基礎・臨床研究を行うメリットがあることを実感しています.
この貴重な誌面をいただき,私自身,また,私たちの検査部で行われている研究の一例を紹介し,それを踏まえ,大学病院検査部門内というかなり限定された条件下ではありますが,臨床検査技師が研究を行うメリットに関して,私見を述べさせていただきます.
臨床検査技師が研究を行うメリット—臨床検査技師の視点から
著者: 菊地良介
ページ範囲:P.859 - P.860
臨床検査技師の英語表記は?
皆さんは,臨床検査技師の英語表記をご存じですか?
国際臨床検査技師連盟(International Federation of Biomedical Laboratory Science:IFBLS)は,2002年の総会で,教育レベルから鑑み,われわれはMedical TechnologistではなくLaboratory Scientistであると提言し,臨床検査技師の名称を“Biomedical Laboratory Scientist”としました.
2章 研究の進めかた
研究と論文の種類—研究デザインを決めよう
著者: 松田和之
ページ範囲:P.862 - P.868
はじめに
毎日のルーチン検査を通して抱く疑問,自身の学問的興味から抱く疑問,これらの疑問は,クリニカルクエスチョンやリサーチクエスチョンといえる.このようなさまざまな疑問を解決する,疑問に取り組むことがまさに“研究”である.しかし,“研究”は,高価な試薬,高価な装置を用いて,論文作成(英語・日本語)を行うことのみではない.
毎日行っている検査業務中に何げなく感じる「ここをこうしたら,もっと検査しやすいのに……」というような運用・環境上の疑問であっても,「その疑問を上司に相談してみて,それを実行して(変化させて)みて,そして運用・環境が変わったか,その変更によってどんな影響が出たか,部内のミーティングで報告した」というように,疑問・問題点を洗い出す(はじめに)→方策を考える(方法・材料)→実行する(結果)→影響を考える(考察)という形で捉えてみると,これはまさに“研究的思考”そのものである.この研究的思考をすでに多くの人が経験しているはずである.さらに,部内ミーティングで報告までしていたとすれば,それは,いわば論文や学会発表と同様に自身の考えを他者に論理的に伝えることまで行っているのである.
“研究”を始めるに際しては,「何か課題を見つけなければ」と焦るのではなく,普段感じる疑問を大切にすることがとても重要であると考える.しかし,疑問の解決に至った過程(成果)を公開する方法,つまり部内報告→学会発表→論文発表には公開の範囲(影響)と公開の時間に違いがある.公開の範囲は,部内報告では特定の施設内の人,学会発表は学会会場に来た人であるが,論文発表は多くはインターネットで不特定多数の人(もちろん興味のある人しか読まないが)に届けられる.さらに,公開の時間については,部内報告や学会発表は限られた時間内であるが,論文,特に英語論文などはPubMed上に半永久的に公開されてしまう.
以上から,論文発表までを視野に入れた場合,論理性がとても重要になる.論理性を担保するためには,疑問を解決する手段,研究のデザイン,研究の成果をどのような形式の論文で発表するかについて,知識を得ておく必要がある.本稿では,研究デザインと論文形式の種類について主なものを概説する.
研究テーマの見つけかた
著者: 鈴木敦夫
ページ範囲:P.869 - P.874
はじめに
「検査部は宝の山だ」—こんな言葉を聞いたことがあるだろうか.臨床の現場には研究の対象となるものがたくさん落ちている.患者データ,得られた検体,業務における疑問や問題など,どれも貴重なものである.われわれ臨床検査技師にとっても,日常業務を行う現場そのものが研究の場所であり,研究を遂行するうえで最も重要な“宝”であることに疑いの余地はない.
文献の集めかた・読みかた
著者: 武村和哉
ページ範囲:P.875 - P.879
はじめに
研究を始める際には,その分野についてどこまで解明されているのか,何が問題となっているのかを調査する必要がある.また,自分の研究結果を考察するうえでも,過去の研究成果を参照しなければならない.このように,研究を行うにあたって,文献を読むことは不可欠なものとなっている.
本稿では,代表的な論文情報データベースの紹介や効率的な文献検索のテクニック,文献の収集方法と読むべき文献について,最後に論文の構造とその読みかたを解説する.
対象者とアウトカムの設定方法—バイアスの少ない研究を目指そう
著者: 中杤昌弘
ページ範囲:P.880 - P.885
はじめに
これまでの稿で紹介されてきたように,PECO/PICOによって研究のリサーチクエスチョンを明確化し,研究デザインを決めてきた.しかし,PECO/PICOで定めた対象者(PECO/PICOのPEC/PIC部分)とアウトカム(PECO/PICOのO)の設定は本当にこれで大丈夫だろうか? 研究デザインに穴がありはしないだろうか?
医学研究(特に人を対象とした研究)では,データの収集過程でしばしば意図しない偏り(バイアス)がデータに入り込み,誤った研究結果,誤った解釈をもたらすことがある.そのため,バイアスの影響を受けない,あるいは受ける影響を可能な限り少なくするように,研究の対象者とアウトカムを設定する必要がある.本稿では,さまざまなバイアスとその対処方法について紹介する.
データの分析—医学統計の基本を学ぼう
著者: 中杤昌弘
ページ範囲:P.886 - P.896
はじめに
医学研究の論文を読むと,患者群と健常者群のデータを比較して,各群の平均値を棒グラフで示しP値を添えた結果をよくみかける.これらは医学統計によって導き出されたものである.医学統計は適切に扱えば大変便利な学問であるが,誤って使っている事例も多い.本稿では,“手持ちのデータを用いてどのような流れでデータ解析を行えばよいか?”“論文で結果を読み取る際にはどのような点に注意して読み取るべきか?”に焦点を当て,医学統計の基本を説明する.
3章 倫理は研究の大前提!
倫理ってなんだろう?
著者: 大沼健一郎
ページ範囲:P.898 - P.900
はじめに
広辞苑では,“倫理”とは「人として守り行うべき道.善悪・正邪の判断において普遍的な規準となるもの」とされている.そもそも科学研究は,科学者同士がお互いの研究に対して信頼できるということが前提にあり,研究成果は正確に実施された研究に基づく“事実”として社会に受け入れられることが多い.そのため,研究における不正行為は科学と社会の信頼関係を揺るがし,大きな損失となる.よって,科学者は研究における各プロセスで規範にのっとった適正な研究の立案・実施・報告を行うという義務があり,その規範である研究倫理,生命倫理あるいは出版倫理を遵守しなければならない.本稿では,主に研究倫理の倫理指針を示した文書について概説する.
個人情報保護—症例の扱いかた
著者: 大沼健一郎
ページ範囲:P.901 - P.904
はじめに
学術研究,特に医学分野において,診療や臨床研究を行う者がその過程で病状をはじめとする他者の個人情報を入手する機会は多い.本稿では,医学研究実施時の個人情報の取り扱いに関する研究者の責務について,特に2015年に改正された個人情報保護法の改正点に基づき,個人情報と個人識別符号,要配慮個人情報,匿名加工情報,ゲノム情報の取り扱いかた,および症例報告時の個人情報の取り扱いについて概説する.
著者資格・ミスコンダクト(研究不正)・COI
著者: 武村和哉
ページ範囲:P.905 - P.907
はじめに
不適切な研究行為は,労力・資源の無駄遣いとなるうえ,社会的な信頼を失墜させることにつながる.実際,STAP(stimulus-triggered acquisition of pluripotency)細胞やディオバン(一般名バルサルタン)に関する研究不正は社会現象にもなったため,記憶にある読者も多いであろう.本稿では,著者資格(authorship),ミスコンダクト(研究不正),利益相反(conflict of interest:COI)の概要とその注意点について解説する.
残余検体の取り扱いかた
著者: 横崎典哉
ページ範囲:P.908 - P.909
残余検体
残余検体とは,臨床検査を終了後の検体の残余部分のことをいう1).診療上,再検査および追検査の可能性があるため,臨床検査検体(血液,体腔液などの体液,尿,糞便,その他の分泌物,臓器・組織,細胞などの生体試料をいい,検体から作製された標本を含む)は指示された検査に必要な量より通常若干多く採取され,多くの場合一定の期間保存される.保存期間は各施設の設備や方針によって異なるが,尿・糞便であれば当日中,生化学検査に用いられた血清であれば1〜2週間,感染症検査関係であれば1カ月,病理組織標本であれば年単位などである.
倫理審査委員会と研究計画書の書きかた
著者: 桝谷亮太
ページ範囲:P.910 - P.916
はじめに
人を対象とした医学系研究を行うにあたって,必須となるのが倫理審査である.しかしながら,普段研究活動を行っていない臨床検査技師にとって倫理申請書類(研究計画書など)の書きかたや注意すべき点を学ぶ機会は少ないと思われる.
本稿では,倫理審査の流れ,申請書類(研究計画書など)の内容,そしてどのようなときに倫理審査が必要になるかについて解説していきたい.なお,本稿は文部科学省および厚生労働省による「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」1)(以下,倫理指針)の内容に沿って記述するが,倫理指針を含む各種のガイドラインは随時更新されるため,常に最新版を参考にされたい.
倫理申請の必要がない研究
著者: 岡田光貴
ページ範囲:P.917 - P.919
はじめに
基本的に,人を対象とした研究はほとんどの場合,倫理申請が必要である.一方で,人を対象とした研究でも例外的に申請が不要なものがあり,また,実験動物や培養細胞を用いた研究に関しては倫理申請が不要である.これら倫理申請を不要とする研究について本稿で解説する.
4章 知っておくべき研究TIPS
研究費申請をしよう!
著者: 齋藤良一
ページ範囲:P.922 - P.927
はじめに
臨床検査技師の多くの方は,日常の検査業務を通して疑問などが生じた際,その理由を明らかにしたいと感じたことがあるのではなかろうか.また一部の方は,その理由を解き明かす実験を進めた際,必要な試薬や機器の購入ができなくて困った経験をされたのではなかろうか.一方,自身ですでに研究費を獲得した方でも,よりたくさんの研究資金を得ようと行動しているのではなかろうか.ここでは,研究資金を獲得する際に必要となる研究費の申請について,研究助成の制度や種類,申請方法,注意点など筆者の私見も交えながら概説する.
“ロジック”でまとめる研究計画書
著者: 大川龍之介
ページ範囲:P.928 - P.934
はじめに
研究はある程度定められた期間,予算内で遂行されるべきである.途中で予算を使い切る,予測通りに結果が出ず行き詰まる,研究者自身の不意な異動などにより研究を断念すると,せっかくの貴重な研究成果が公になる前に終わってしまう.したがって,これらの問題なく研究を遂行するためには,予算配分,想定外の結果が得られた際の次のアクション,研究期間の設定など,丹念に練られた研究計画書が必須である.
また研究には終わりはなく,計画なき研究の遂行はにじんだ絵の具のように,不明瞭な広がりをみせてしまう.一定の区切りをつけて,そのユニットごとに研究成果をまとめ,報告していくことが肝要である.
さらに研究には研究費が必要であり,部内における補助金の申請,各種財団や日本学術振興会の科学研究費(科研費)などの競争的研究資金を獲得するためには,多くの場合,研究計画書の申請が必須である.競争率の高い助成金を獲得するためには,優れた研究計画書を書かなければならない.
本稿では,主に助成金申請のための研究計画書の書きかたについて述べる.それはそのまま円滑な研究の遂行につながるものと考えられる.なお,研究デザイン,研究テーマの見つけかたに関しては他の項(2章「研究の進めかた」)を参考いただきたい.
—知らないと怖い! 知的財産①—研究の新規性と特許申請フロー
著者: 春名真徳
ページ範囲:P.936 - P.942
医療分野での特許出願の有用性
近年,大学や病院の研究者と,企業とが共同研究を行い,その成果を特許出願する事例が増加している.研究者としては,研究成果を試薬や治療薬として実用化したいとの思いがあり,企業としては,そのような製品を他社に先駆けて販売し,市場独占したいとの狙いがある.研究成果を臨床に還元するという最終的な共通の目標のため,特許出願は研究者と企業とを結びつける手段となり得る.
もちろん,特許出願を行わずとも共同研究は可能である.しかしながら,特許出願を行っていること(あるいは,特許出願を前提としていること)は,企業として開発の方針を立てやすく,共同研究を先へ先へと進める原動力になり得る.
—知らないと怖い! 知的財産②—著作物の引用と転載
著者: 春名真徳
ページ範囲:P.943 - P.945
著作権法が関与し得る撤回論文の状況
撤回論文データベース(The Retraction Watch Database)では,撤回理由により,撤回論文を検索することができる1).
2010年1月1日〜2020年4月30日までの撤回論文数を検索すると17,026本あり,そのうち,1,660本が「文章,データ,画像の盗用」を理由とするものであり,301本が「著作権法上の申立」を理由とするものである.
医学研究者(Biomedical Laboratory Scientist)を目指すには—学士・修士・博士号
著者: 松田和之
ページ範囲:P.946 - P.950
はじめに
医学研究というフィールドにおいて,多くの研究者の研究成果を知ること,逆に多くの研究者へ自身の研究成果を公開・伝えること,これが研究者間のコミュニケーションである.このときに,“信頼性”ある成果を受容し,また発信することが研究の根幹であることは言うまでもない.しかし,見ず知らずの研究者同士が相手(相手のデータ・成果)を信頼する1つの基準〔世界的に共通する基準(資格)〕が研究発表者の博士号(Doctor of Philosophy:Ph.D.)であるといえる.Ph.D.を取得している人物は,信頼性をもった研究者であるとみなされるはずである.要するに,Ph.D.を取得する過程で,研究に必要な基礎力を得ているという共通認識が根底にある.しかし,よくいわれるようにPh.D.取得は最終地点ではなく,研究者としての通過地点である.“終了”ではなく“修了”であり,通過許可証を得た研究者なのである.
本稿では,修士課程・博士課程に関連する事項について概説する.
5章 学会発表のアドバイス
Acceptされる抄録の書きかた
著者: 小林剛
ページ範囲:P.952 - P.955
はじめに
学会発表をすることが決まると,初めにやらないといけないことは“抄録(abstract)作成”である.抄録は学会発表の土台であり,抄録の出来が学会発表の出来を左右するといっても過言ではない.さらに,学会発表後の論文投稿においてもabstractが重要な役割を担ってくる.査読者がその論文を評価する際,初めにabstractから目を通して,論文の大体の流れを把握する.論文の“第一印象”はabstractによって決まるといっても過言ではないだろう.したがって,本文がいくら上手に書けていたとしても,abstractがイマイチだと,すぐにリジェクトされることもある.
学会発表において,自分が登録した演題が採用(accept)してもらえるかどうかは,発表タイトルとその抄録の内容によって全てが決まる.国内学会では,比較的採用率が高いものが多いのに対し,国際学会では採用率が低いものも存在する.基本的に,学会の査読者は短時間で抄録を採点し,複数の査読者の採点結果によって,その演題の採否が決定される.査読者にとっては,短時間で採点をしないといけないため,わかりやすくて読みやすい抄録ほど,高い点数をつけることが多い.したがって,文字数が限られているなかで,いかに“わかりやすく,魅力的な抄録”を書けるかが重要になってくる.
本稿では,採用してもらえる魅力的な抄録を書くためのノウハウを紹介したいと思う.これから学会発表デビューを考えている方や,よく学会発表をされている方にも,ぜひ目を通していただきたい.
見やすいポスターの作成と発表の進めかた
著者: 田崎雅義
ページ範囲:P.956 - P.960
はじめに
ポスター発表は,自身の研究成果を世に発信できる貴重な機会である.それと同時に,参加者と研究についてディスカッションできる絶好のチャンスでもある.いくら研究内容が優れていようと,参加者に足を止めて見てもらえなければ意味がない.学術集会によっては1,000を超えるポスターが貼られている.そのなかで,文字がびっしりと書かれたポスターをじっくり見る人がどれだけいるだろうか.数あるポスターのなかから自身のポスターの閲覧に時間を割いてもらうためには,“見やすさ”を重視したポスターを作ることが極めて大切である.
ポスター発表と口頭発表の違いは大きく2つある.1つ目は,発表時間が短いことである.そのため,ポスター発表では研究の細部まで説明しているとそれだけで発表時間がなくなってしまう.要点を絞って簡潔に説明することが望ましい.2つ目は,ポスター発表は発表者が研究内容を説明しない時間帯もあるということである.口頭発表は,研究データをスクリーンに投射し,説明を加えながら発表するが,ポスター発表の場合,発表者が不在でも参加者が閲覧できる時間がある.そのため,発表者の説明がなくとも理解してもらえるように,工夫したポスター作りを心掛ける必要がある.
本稿では,“見やすさ”を重視したポスターの作成方法について解説する.しかし,ここで説明するのはあくまでもその1例である.なぜなら,研究発表には,症例報告もあれば,病理画像を中心とした発表,グラフを多数提示する発表,アンケートを中心とした発表などさまざまなものがあり,研究内容に合わせポスターを作成することが重要なためである.ぜひとも,本稿を参考に,自身の研究内容に合った方法でポスターを作成していただきたい.そして,作成したポスターを携え,ポスター発表でしか味わえない研究発表の臨場感を楽しんでいただきたい.
見やすい口頭発表用スライド作成とプレゼンの進めかた
著者: 原祐樹
ページ範囲:P.961 - P.965
見やすいスライドの重要性
読者の皆さまも学会や勉強会に参加して,さまざまな発表を聞かれたことがあると思うが,どういった発表に対してよい発表だったと感じるだろうか.難しい内容であるにもかかわらず,とてもわかりやすく引き込まれたといった経験をおもちの読者の方もいるかと思う.
ほとんどの学会では口頭発表あるいはポスター発表に振り分けられるが,両者の1番の相違は,聴衆がスライドをじっくり見ることができるかどうかである.ポスターの場合は,発表前後にポスターをじっくり見ることができるため,聞き手も内容に関して理解を深めやすい.一方で,口頭発表は限られた時間内で展開していくため,1枚のスライドをじっくり見ることができない.つまり,口頭発表ではよりわかりやすいスライドが求められることになる.本稿では,見やすい口頭発表用スライドの作成方法と発表当日のプレゼンテーション(以下,プレゼン)の進めかたについて概説する.
質疑応答を乗り切る
著者: 岩田英紘
ページ範囲:P.966 - P.968
はじめに—質疑応答は誰しも不安
皆さんは,質疑応答が得意だろうか?
“私は得意ではない”と思った方も,安心してほしい.大勢の聴講者の前で議論するのは,誰しも緊張し,うまくできるか不安になるだろう.発表経験が少ない方であればなおさらで,むしろ当然のことだと思う.また,発表は事前に練習ができるが,質問は当日のその場面になってみないとどんな質問が来るかわからないため,より不安が募るのも無理もないだろう.
しかし,経験が少ないからといって,学会の場での質疑に対し,どんな応答をしても許されるわけではない.学会の発表時間は自分だけのものではなく,聴講者の大切な時間も共有していることを意識しなければいけないからである.質疑応答では,質問者や聴講者に対するマナーも非常に大切である.
本稿では,学会発表に慣れていない方でも押さえてほしい,質疑応答を乗り切るためのポイントを6つにまとめた(表1).どれも決して難しいことではなく,心得ていれば実践できることである.以下に,順に紹介していきたい.
6章 論文執筆のアドバイス
試薬検討の評価と基本的な書きかた
著者: 村越大輝
ページ範囲:P.970 - P.974
はじめに
研究と聞くと,大学や大学病院で盛んに行われており,新しくて画期的なことをやるものといったイメージをもたれる方も多いかもしれないが,必ずしもそうではなく,市中病院でも研究が行える可能性は十分にある.研究は基礎研究,応用研究,開発研究に大別され,臨床検査における基礎研究は新規医療技術の開発が中心となり,応用研究は開発された医療技術の評価や比較であり,開発研究はどちらの要素も兼ね備えた発展的な研究である.どれも必要不可欠な研究で,大学,大学病院,市中病院とそれぞれの機能や役割に合わせた研究が求められる.
市中病院の主な役割は,応用研究として測定系で起こるピットフォールの精査や新規試薬の性能評価,既存試薬との比較検討を実施することである.また,機器・試薬の導入や変更は検査室の重要な役割であり,性能を把握したうえで導入するためにも検討方法や評価方法を熟知し,適切な評価を自施設で実施することが望ましい.
本稿では,試薬の性能評価と比較検討を行う際の妥当性の確認方法(validation:バリデーション)と評価について解説する.また,その際の研究論文の構成についても触れるので執筆の際の参考にしていただきたい.
症例報告の基本的な書きかた
著者: 大﨑博之
ページ範囲:P.976 - P.979
はじめに
症例報告(case report)は,原著論文などに比べ過小評価される傾向にある.これは,実験や数十例以上の症例が必要な原著論文と異なり,1〜数例の症例があれば執筆できること,海外学術誌の多くが症例報告を掲載しなくなったこと注などが原因と考える.しかし,希少症例や例外的な所見を呈した症例などから得られた教訓・知見を論文にして,情報を発信することは臨床的に重要な意味をもつ.そもそも,原著論文と症例報告は役割が違うものであり,比較する対象ではない.
症例報告は,医療現場で働く臨床検査技師が初めて書く論文のスタイルとして最適と考える.その理由として,日々の業務のなかでまれな症例や例外的な所見を呈した症例などに遭遇することは少なくないこと,特別な機材や試薬がなくとも執筆できることなどがある.ただし,希少症例といってもある程度はすでに症例報告として論文にされている場合が多い.自身が経験した症例が既報の症例報告の内容と同じであれば,論文にすることは困難である.いずれにしろ症例報告においても論文とするからには,なんらかの教訓や新たな知見が必要となる1).
原著論文の基本的な書きかた
著者: 松尾英将
ページ範囲:P.980 - P.984
はじめに
研究の結果,もし新規性のある十分な量の実験データが得られたら,原著論文(英語では,Original Article, Research Article, Regular Article, Full Paperなど)としてまとめることになる.本稿では,主に原著論文の基本的な書きかたや,その後の英文校正について概説する.内容は英語論文の執筆を想定したものであるが,その多くは日本語論文にも応用可能である.
科学論文で使える日本語表現
著者: 桝谷亮太
ページ範囲:P.985 - P.988
はじめに
研究は,計画を立案して倫理申請し,その成果を学会発表や論文執筆により社会に還元するまでが1つの流れである.しかし,いざ国内雑誌に投稿しようと思って書き進めたものの,初めて論文を執筆する場合は文章がうまくまとまらず,苦労することが多いのではないかと思う.実際,ルーチン業務の傍らで研究を行う臨床検査技師にとって,研究の手法のみならず文書における日本語表現の方法まで学ぶ機会は少ないのが現状である.科学論文を書くにあたっては,守るべきルールやポイントがあり,それを知っているだけで論文の書きかたはすぐ上達する.
本稿では,一般的な文書と違い科学論文で求められる表現について紹介するとともに,表記法のルールについて解説する.これから国内雑誌への投稿を目指す方にとって,少しでもお役に立てば幸いである.
TableおよびFigure作成のポイント
著者: 鈴木敦夫
ページ範囲:P.989 - P.995
はじめに
研究成果の発表にあたり,表(Table)や図(Figure)は欠かせないものである.質の高い“伝わる”図表は読者の理解を容易にする他,査読の段階でEditorやReviewerによい印象を与え,論文の採択に近づくことができる.しかし,やみくもに作成しても“伝わる”図表は完成しない.
本稿では,論文執筆に必要な図表の作成について,一般的なルールや基本的事項に触れながら良い例・悪い例を提示しつつ私見を交えて概説する.
Referenceの重要性
著者: 大沼健一郎
ページ範囲:P.996 - P.1000
はじめに
研究により得られた新知見を論文にまとめる際,背景(Introduction),材料と方法(Materials and Methods)および考察(Discussion)の各項において,自身が得た研究成果に加え,他者が先行して発表したデータや研究成果に言及することが必要不可欠である.“自分の説のよりどころとして他の文章や事例または古人の語を引くこと”を“引用(Citation)”と言い,論文作成時には引用したデータの一覧を“参考文献(Reference)”として文末にリストとして明示する.すなわち,Referenceとは自身が発表する研究論文の新規性・独創性・信頼性を明確にするだけでなく,読者に対する正確な書誌情報の提供を担う役割をもち,論文を執筆するうえで重要な項目である.
文献管理ソフトの使いかた
著者: 大沼健一郎
ページ範囲:P.1001 - P.1005
はじめに
論文を執筆するうえで,文献は研究背景や研究の必要性の考案,研究方法の立案,さらには,自身の新知見の主張などにおいて重要である.研究を実施するにあたって,研究前・研究中・論文作成時とさまざまな段階で文献を検索・収集し,管理する必要がある.しかし,膨大な文献を管理することとなり,容易ではない.特に,論文執筆時の参考文献リストの作成は,投稿誌を変更すれば修正が必要になるなど,大変煩雑な作業である.
本稿では,文献管理にかかわる煩雑な作業を効率化することができる5種類の代表的な文献管理ソフトについて概説する.
論文の投稿先を探す
著者: 岡田光貴
ページ範囲:P.1006 - P.1013
はじめに
研究成果は最終的には論文として広く社会に公表するのが最良である.しかし,どれほど学問的に優れた論文であっても,投稿先の学術雑誌とのミスマッチがあれば採択には至らない.実際,筆者も学術雑誌が求める研究領域と異なっていたために論文が不採択となった経験が複数回ある.論文が不採択となった場合,新たな投稿先の選定や,それに伴う書式の変更などがあるため,さらに時間と労力を要することになる.本稿では,日本と海外それぞれの学術雑誌を対象として,論文の投稿先を選定するコツを解説する.
論文を投稿しよう!
著者: 松尾英将
ページ範囲:P.1014 - P.1016
はじめに
論文を書き上げれば,いよいよ投稿である.しかし論文を投稿しても,すぐに採択(Accept)されることはほとんどなく,修正要求(Revision)への対応など,越えるべきハードルは多い.
本稿では,論文投稿から雑誌への掲載までの流れや対応について,特に投稿作業が煩雑な国際学術誌に焦点を当てて解説する.なお,論文投稿は近年ほとんどの場合電子化されており,本稿でも電子投稿を前提として記載する.
7章 成功と失敗から学ぼう!
—私の成功・失敗談①—駆け出し研究者の苦悩
著者: 岡田光貴
ページ範囲:P.1018 - P.1019
はじめに
私は博士号を取得してまだ3年ほどの“駆け出し研究者”である.博士号の取得後は医療施設で臨床検査技師として勤め,現在は私立大学の教員である.私は博士課程の修了と同時に研究者として独立し,自身の力で研究を遂行しなければならなくなった.指導者や同じ研究室のメンバーがいないという私の境遇が,同じ状況にある多くの研究者の参考になれば幸いと考えている.
本稿では,私が研究者として独立してから実感した“苦悩”を挙げるとともに,それらにどう対応してきたかを紹介する.
—私の成功・失敗談②—困ったときは誰かが助けてくれる! 研究仲間を大切にしよう!
著者: 桝谷亮太
ページ範囲:P.1020 - P.1021
はじめに
私の研究領域は検査血液学,血栓止血学,膠原病アレルギー学と,どちらかといえば特定の疾患や領域を深くというより,ルーチン業務で疑問に感じた症例や現象を対象としている.そのため,日頃から疑問に感じたことは自分が納得できるまで検証しようと心掛けている.
そんな私の研究生活のなかで転機となったのが,APTT試薬の違いが接触因子欠乏症の診断に与える影響に関する研究で2018(平成30)年度の日本検査血液学会学術賞を受賞できたことであった.それまでは認知度の低かった分野が,私の研究によって少しずつ認知されるようになったと教えていただいた際は,社会に貢献することができたとうれしく感じたのを覚えている.また,私のなかでこの研究成果が自信につながった理由は,その研究で仮説を証明するために行った実験が,血栓止血学やルーチン業務には全く関係のない,細胞培養実験で培ったアイデアから着想できたことであった.一見,無関係に思えることが,新しいアイデアを生み出すために必要な布石になっているのだと思うと,普段のルーチン業務や研究活動にも励みが出る.日頃からアイデアを頭のなかで練りながら,何か新しいことができないかと考えながら物事を見ることが,私にとっての研究のモチベーションを保つ秘訣である.
—私の成功・失敗談③—オリジナルのアイデアや研究成果は英語論文にしておこう!
著者: 大﨑博之
ページ範囲:P.1022 - P.1023
尿中A細胞の検出法の開発
筆者は現在,尿中のある細胞(仮にA細胞とする)について研究を行っている.このA細胞は,特定の泌尿器疾患の患者尿中に出現することが知られており,両者の関連については以前より研究が行われている.しかし,それらの研究で実施されている尿中A細胞の検出方法には,特別な機材や試薬が必要となるため,一般病院の日常検査として実施することは困難であった.
そこで筆者は,一般病院の日常検査として実施できる尿中A細胞の検出方法の開発を目的として検討を行った.そして,B法で尿細胞診標本を作製し,それにA細胞マーカー抗体の免疫染色(酵素抗体法)を追加してA細胞を検出する方法を考案した.liquid-based cytologyであるB法で尿細胞診標本を作製することで国際的な標準化が可能となり,さらに,免疫染色に酵素抗体法を採用することで自動化も可能となった.
—私の成功・失敗談④—弱気は最大の敵
著者: 小林剛
ページ範囲:P.1024 - P.1025
はじめに
私は2012年に広島県にある呉共済病院病理診断科で臨床検査技師として働き始めた.病理細胞診業務に携わっているうちに,もっと癌に関する知識を深めたいと思うようになり,2016年に社会人大学院生として,広島大学大学院医系科学研究科分子病理学研究室に入学した.癌幹細胞に関連した分子に着目し,2本の筆頭論文を執筆することができ,2019年に医学博士を取得した.現在も病理細胞診業務の傍ら,分子病理学的な研究を継続している.
今回私は大学院での研究生活を振り返り,研究成果,成功体験,失敗談などについて,簡単に示したいと思う.
—私の成功・失敗談⑤—見極める力・取りこぼさない力の重要性
著者: 田崎雅義
ページ範囲:P.1026 - P.1027
新規アミロイド共存蛋白質の同定と機能解明
2017年,筆者らは,脳アミロイドアンギオパチーにおける新規アミロイド共存蛋白質としてSRPX1(sushi repeat-containing protein 1)を同定し,本病態におけるその役割を明らかにした1).脳アミロイドアンギオパチーは,アミロイドベータ(amyloid β:Aβ)蛋白質により形成されたアミロイド線維が脳血管に沈着し,その結果として脆弱化した血管が破綻して脳出血を呈する加齢性の疾患である.超高齢社会の到来とともに,患者数は増加の一途をたどっているが,いまだ本疾患の早期診断法・予防法・治療法の開発には至っていない.そのため,本疾患の病態を明らかとし,これらの開発につなげることが求められている.
そこで筆者らは,本疾患に関与する新規分子を探索し,その機能を明らかとすることを目的として研究に取り組んだ.解析手法を簡単に説明すると,ホルマリン固定脳組織切片からlaser microdissection(顕微鏡型の装置で目的領域を分取する装置)を用いてアミロイド陽性部位を採取し,組織を可溶化後,LC-MS/MS(liquid chromatography-tandem mass spectrometry,質量分析装置)で組織に含まれる蛋白質を網羅的に解析する.そして,コントロール群と比較することで病態への関与が疑われる分子をピックアップした.無数の蛋白質が同定されたが,筆者らはそのなかからSRPX1に絞り研究を行い,本蛋白質がAβ誘導性の血管変性に関与していることを見いだした.
8章 臨床検査技師の研究留学
Whitaker Cardiovascular Institute, Boston University School of Medicineへのポスドク留学
著者: 菊地良介
ページ範囲:P.1030 - P.1034
本稿では,臨床検査技師である私が2011年6月〜2013年3月までポスドクとして研究留学した体験を紹介する.
Baker Heart and Diabetes Institute(Melbourne, Australia)への国際共同研究としての留学
著者: 大川龍之介
ページ範囲:P.1035 - P.1037
当時の状況・留学を志すきっかけ
はじめに私の職歴を紹介させていただきたい.大学を卒業後,東京大学医学部附属病院検査部臨床化学検査室において,臨床検査技師として8年,主任臨床検査技師として2年半勤めた.その後,私が病院在職中に2年間臨床検査技師長を務められ,東京医科歯科大学に教授として異動された戸塚実先生のもとへ,教員として異動した.
もともと医学研究がしたくて就職先に東京大学を選んだこともあり,附属病院に入職後すぐに研究をスタートし,昼は日常業務,夜は実験という1日をすごしていた.博士号を取得した頃,周りから“すごく研究している技師がいる”と言われ,執筆や講演依頼などが増えたが,自分としては“人前で話すほど研究能力も業績も全く足りていない! 一度,朝から晩まで研究活動にどっぷり浸かり実力をつけたい”と思い,留学に対する強い希望が芽生えていた.
Department of Molecular Medicine, University of Pavia(Italy)へのVisiting Researcherとしての留学
著者: 田崎雅義
ページ範囲:P.1038 - P.1040
留学を志すきっかけ・当時の状況
著者は,熊本大学大学院臨床検査医学分野の安東由喜雄前教授のもとで学部4年生の卒業研究の折より,研究のいろはを学んだ.修士課程を卒業後,母校の熊本大学医学部保健学科臨床検査技術科学専攻の教員となり,臨床検査技師の教育にも携わるようになった.安東教授には,学部4年時にロンドンでの国際学会に参加させていただき,そこで見た,世界を舞台に活躍されている先生の姿に強い憧れを抱いたことを鮮明に覚えている.いま思えば,この経験が著者のターニングポイントであり,自然と留学を志すきっかけとなったに違いない.
諸先生方の多大なるサポートがあり,2017年,悲願であったイタリアの地でVisiting Researcher兼,熊本大学の職員として1年半の研究留学をスタートすることができた.Visiting Researcherとは,客員研究員のことで,大学の施設を自由に利用することが許可された海外研究者に与えられた職名である.先方からの給与はなく,熊本大学からの一部の給与と民間助成金を留学の資金とした.
University of Southern California(USC)&Children's Hospital Los Angels(CHLA)へのポスドク留学
著者: 大楠清文
ページ範囲:P.1042 - P.1044
当時の状況と留学を志すきっかけ
私は東京医科歯科大学医学部附属臨床検査技師学校を卒業後,虎の門病院臨床化学検査部(7年間),千葉県こども病院(7年間)にて臨床検査技師として勤務した後,専門分野のさらなる研鑽を目的に2001年7月から約2年半の間,ポスドク研究者としてロサンゼルスにある南カリフォルニア大学(University of Southern California:USC)とロサンゼルス小児病院(Children's Hospital Los Angeles:CHLA)での留学を経験した.
2001年当時は,感染症の迅速診断として核酸増幅法が臨床検査室の現場で一般的に使用されていなかったため,遺伝子学的診断法の修得と米国の臨床微生物検査体制を学びたかったことが留学を志すきっかけとなった.そして振り返れば,私に臨床微生物検査の魅力を伝授してくれた千葉県こども病院検査科長・川上浩氏(当時)との出会いが留学への一歩を後押しした.川上師匠は,私の仕事のモットーである“菌は生き物だ”“菌は噓をつかない”“患者情報から起炎菌を想定せよ”を伝授してくれた恩師である.留学の本当の目的は,日本でこのまま仕事をしても川上師匠を超えることはできない,師匠を超えたいというのが一番の理由だったかもしれない.
9章 研究のすゝめ
日常業務の問題点から研究への足がかり—市中病院での学術活動
著者: 岩田英紘 , 原祐樹
ページ範囲:P.1046 - P.1052
病理検査編 岩田英紘
入職からの経歴(表1)
私は,大学4年生の卒業研究で病理研究室に所属し,主にFISH(fluorescence in situ hybridization)検査や免疫組織化学染色を経験しました.卒業後は大学院の修士課程へ進学し研究に励む一方で,細胞検査士の資格を取得しました.その後現在の職場に就職し,今年で11年目を迎えました.入職直後に病理検査室へ配属され,現在に至ります.入職後,2年目に国際細胞検査士,4年目に二級臨床検査士(病理),7年目には認定病理検査技師の資格を取得しました.
日常業務の問題点から研究への足がかり—探究心から始まる研究
著者: 大杉千尋
ページ範囲:P.1053 - P.1057
これまでの経歴
福島県立総合衛生学院臨床検査学科を卒業後,宮城県白石市の蔵王連峰のふもとにある公立刈田綜合病院に入職した.当院は宮城県南部に位置する地域医療の基幹病院として一般病床254床を有し,救急指定病院,第2種感染症指定医療機関,災害拠点病院などの役割を担っている.また,回復期病棟や地域包括ケア病棟を開設し,急性期後の治療・支援にも力を入れている.
そのなかで,検査部には15名の臨床検査技師が在籍している.大きく検体検査(一般検査,血液・輸血検査,生化学・免疫検査),生理検査,細菌検査,病理検査の4部門に分かれ,採血業務も行っており,おのおの担当部署を兼務しながら業務にあたっている.私は入職後,日直・待機に備えて約4カ月間各部署の仕事を経験し,その後は生化学検査を担当した.そして入職から約1年後に血液・輸血検査も兼務するようになり,現在は血液・輸血検査と採血業務を担当している.
専門性を活かした現場研究への展開—Be a specialist, not a generalist.
著者: 鈴木敦夫
ページ範囲:P.1058 - P.1062
はじめに
“研究”と一言で表現してもその内容はさまざまですが,1つの疑問や問題に対して,論理的に考え,時に実験的な検証をして解決することが全ての“研究”活動に共通するものであると私は考えています.
臨床検査技師の現場はすなわち各検査室であり,そこで発生する日常業務上の問題や課題,あるいは大小さまざまな疑問は,その場で業務に従事するわれわれ臨床検査技師が解決しなければなりません.時に,日常業務の延長線上にある小さな実験や検討は研究として認識されていないこともあるかもしれませんが,冒頭で申し上げたフローで構成される問題提起から論理的解決までのプロセスを満たしているものは,大小にかかわらず十分に研究活動に値すると思います.すなわち研究というものは,われわれにとって非常に身近なものです.
しかし,その1つのテーマを広げ,深く掘り下げるためには,ある種のトレーニングが必要です.また,レベルの高い研究を遂行することや,その研究活動の継続にあたっては,十分な“専門性”が必要です.この専門性は,主に“学術的な知識”だけではなく“専門分野における経験”によって構成されると考えます.一方で,経験だけがあってもそれだけでは研究活動を遂行することは困難で,教科書レベルの知識から専門書レベルの知識,さらには専門学会へ参加して最新の知見を得るなどして豊富なデータをもっておく必要があります.そして,どのように研究を行うかについては,他者からのアドバイスや指導も必要になります.
さて本稿では,“専門性を活かした現場研究への展開”というテーマに沿って,いかに専門性をもち研究を遂行するか,自身のこれまでの経験を交えてご紹介します.甚だ恐縮ではありますが,いま研究を行っている方々や,これから研究にチャレンジしようと考えている方々にとって,少しでも参考になればと思います.
臨床現場から教育現場へ—教育機関でなすべき臨床検査技師の育成
著者: 大川龍之介
ページ範囲:P.1063 - P.1068
入職後からの経歴,研究に対する壁について
初めにせんえつながら私の経歴を紹介させていただきたい(図1).私は,2002年3月に東邦大学理学部生物分子科学科を卒業後,同年4月,東京大学医学部附属病院(以下,東大病院)検査部に入職した.同じ東邦大学を卒業され,東大病院検査部に入職した諸先輩方が,病院で働きながら研究し,学位を取得していることを知っていたため,私も入職直後から日常業務に加えて研究をするという意識を常にもって働いていた.ところが当時,東大病院検査部は予想に反して,それほど研究が活発に行われておらず,学位取得のための研究テーマを見つけることがなかなか困難であった.テーマ探しに悪戦苦闘していた頃,山梨大学より矢冨裕先生(現・東大病院検査部長)が検査部副部長として東大病院に移られた.矢冨先生は,研究する技師を探しておられたため,研究テーマを必死に探していた私にとってはまさに渡りに船であった.おかげで,矢冨先生から研究テーマ,さらには研究指導もいただき,入職2年目(2003年10月)より,東邦大学大学院理学研究科の博士前期(修士)課程に社会人大学院生として入学,2008年3月に博士号(理学)を取得することができた.
他の多くの病院検査部でもそうであるように,東大病院検査部でも日常業務終了後,自己研さんのために研究を行う臨床検査技師は少数派であった.したがって,周りの先輩技師からの逆風がなかったわけではない.しかしながら,当時,矢冨先生や戸塚実技師長(現・長野県立こども病院),直属の上司であった大久保滋夫副技師長(現・文京学院大学教授)の理解が得られていたこと,また,夜22時頃まで研究した後は,決まっていつもの定食屋に一緒に行く研究仲間もいたことから,幸いにも研究を苦痛に感じたことは全くなかった.また,当たり前のことだが,臨床検査技師は日常業務がメインである.したがって,研究も人一倍行ったが,日常業務に関連する仕事(業務改善,ISO,システム更新,実習生の教育など)も人一倍行った.次第に,日常検査に関して先輩方に頼まれることも増え,日常検査において貢献できるようになってくると,より多くの方から研究に対する理解が得られるように変わっていったと記憶している.
臨床現場から教育現場へ—地方の中小規模病院でも研究はできる!
著者: 大﨑博之
ページ範囲:P.1069 - P.1073
入職から現在まで(表1)
私は,高知県の3年制短期大学を卒業後,愛媛県の国立病院(現・国立病院機構)に就職しました.当時,世間はまだバブルに浮かれていましたが,臨床検査技師の求人は極めて少なく,私はパート職員での社会人スタートとなりました.運よく翌年から正職員として雇用され,就職4年目に香川県の国立病院に転勤となりました.ちょうどその頃に3年制の専門学校・短期大学の卒業者が,放送大学で単位を取得して,研究論文を学位授与機構(現・大学改革支援・学位授与機構)に提出することで学士を取得できる制度が開始されました.私もその制度を利用して28歳で学士(保健衛生学)を取得できました.香川県の国立病院に12年間勤務した後に,教員として香川県立保健医療大学に赴任しました.そこで4年間お世話になっている間に香川大学大学院の博士課程を修了し,39歳にしてようやく博士(医学)の学位を取得することができました.次に愛媛県の大学に6年間勤務し,2016年度より神戸大学大学院の准教授として教育と研究に従事しています.したがって2020年度時点の私のキャリアは,病院勤務15年,教員15年目となります.
研究的好奇心から臨床現場への還元と成果—症例の出会いと謎解きの面白さ
著者: 藤田清貴
ページ範囲:P.1074 - P.1080
はじめに
臨床検査は病気の診断や治療効果を判定するうえで必要不可欠なものであり,診療支援ができる実践的な知識と技術を身につけ,検査値から病態を推測できる質の高い臨床検査技師の育成を望む声が大きくなっている.一方,臨床検査技師は,医療機関で活躍する以外に,生殖医療分野における臨床エンブリオロジスト,科学捜査研究や製薬・試薬関連企業での研究開発など,これまで以上に幅広い分野での活躍が期待されている.そのためには,高度な専門知識と応用能力をもち,科学的視野および技術で問題解決のできるbiomedical laboratory scientistとしての臨床検査技師の育成が急務である.そこで本学では,国家資格を取得するためだけの教育ではなく,実践的な知識と技術能力を身につけ,検査値から病態を推測し診療支援ができる臨床検査技師,および検査技術学を応用しscientistとして他分野で活躍できる臨床検査技師の育成を目的とした“検査技術学科”を2013年にスタートさせた.現在,教育現場にかかわって約20年であるが,表1に示したように,約25年間は一般病院の臨床現場で臨床検査技師として働いていた.
今回,長年の臨床・教育現場での経験を踏まえ,いかに研究的好奇心が大切か,さまざまな症例との出会いと“謎解き”がいかに面白いかを紹介しながら,臨床現場への還元とその成果について述べてみたい.
研究のすゝめ—Bedside to Bench, Bench to Bedside
著者: 菊地良介
ページ範囲:P.1081 - P.1087
はじめに
筆者の勤める名古屋大学医学部附属病院は,明治4(1871)年名古屋藩評定所跡に公立の仮病院が設置されたことに始まる.以来140年の歳月を越えて,教育や研究を行う大学附属病院であるとともに,患者に質の高い医療や有益な情報を提供するために,ほぼ全ての医学領域の専門医がそろい,多くの医療者が力を合わせて良質なチーム医療の実現を目指している.
筆者は,2007年に名古屋大学大学院医学系研究科博士課程前期課程(修士)を修了後,同大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門に入職した.臨床検査部門での日常業務と並行して,2008年4月からは,同大学大学院医学系研究科循環器内科学講座に社会人大学院生として籍を置き,研究活動を始めた.2011年3月に同大学大学院医学系研究科を修了(短縮修了)し,2011年6月〜2013年3月まで,ボストン大学医学部ワイタッカー心臓血管研究所にpost-doctoral fellow(博士研究員)として留学した(同病院研究休職).帰国後,2013年4月に名古屋大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門に復職した.
当院の臨床検査部門には70名弱の臨床検査技師が在籍している.臨床検査部門所属の職員は,検査部,輸血部および病理部に分かれ日夜業務を行っている.入職当初筆者は,新人ローテーションとして3週間ずつ8部署を経験して回り,その後は輸血検査を担当した.現在は臨床化学・免疫学的検査を担当している.2015年からは,名古屋大学医学部保健学科と中部大学生命健康科学部の臨床講師(生命医科学科)を兼任し,2016年からは,愛知県臨床検査技師会理事(精度管理事業担当),日本臨床衛生検査技師会国際交流ワーキンググループ委員などを拝命し,臨床検査技師の国際化についても活動をしている(表1).
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.852 - P.854
基本情報
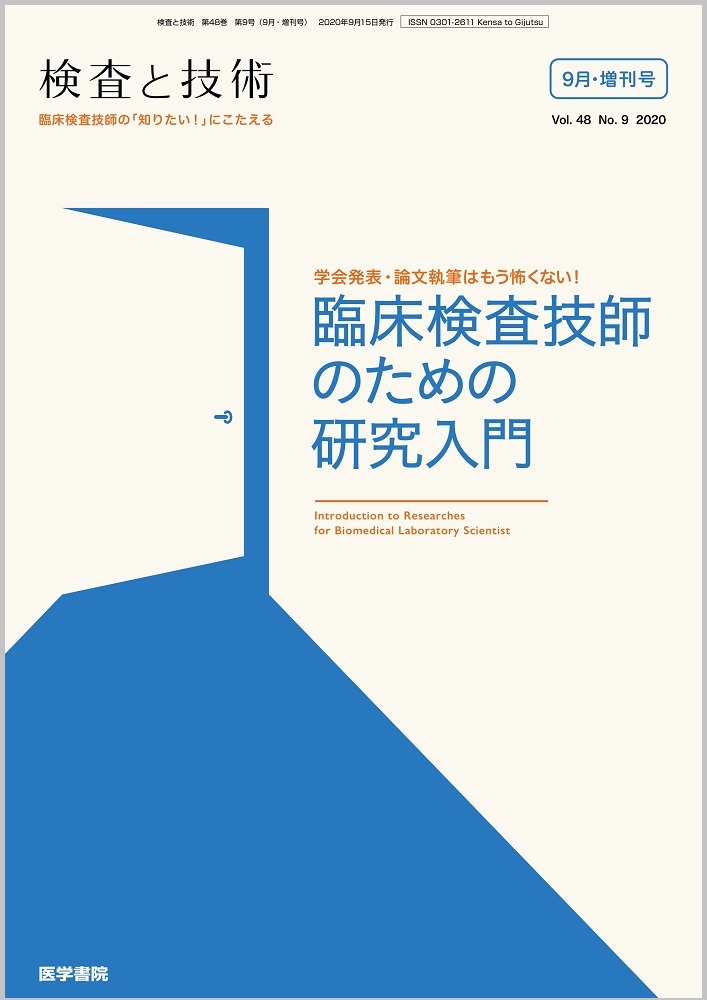
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
