培地を観察している3人の微生物検査技師に出会ったとします.そして,それぞれに「いま,何をしていますか?」と質問してみると,次のような返答がありました.1人目のA技師は「見てのとおり,菌を釣っているのだ」,2人目のB技師は「見てのとおり,菌を同定・感受性機器にかけようとしているのだ」,3人目のC技師は「見てのとおり,グラム染色像と患者背景とを加味して起炎菌を捉えようとしているのだ」.どの技師も,やっている行為は“培地を観察する”ことで共通しています.しかし,それぞれの返答は違います.それは見ているところが違うからです.
よりよい技師になるためには,「自分がやっている目の前の取り組みが何につながっているのか」を見いだすことが重要です.コロニーを拾うだけの技師になるのか? なんでもすぐ機器にかける技師になるのか? 起炎菌を捉えられる技師になるのか? 私は,ただ業務として仕事をするのではなく,志を持って“志事”をすることこそが大切だと思うのです.そして,この志を導く上司(師匠)の存在もまた欠かすことができません.
雑誌目次
検査と技術49巻3号
2021年03月発行
雑誌目次
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
序文 フリーアクセス
著者: 大楠清文
ページ範囲:P.170 - P.171
総論 基本的な技術と操作法
微生物検査の基本的な考え方
著者: 大楠清文
ページ範囲:P.178 - P.182
Summary
微生物検査は,①塗抹検査(顕微鏡による直接的な観察),②迅速抗原検査(免疫学的な方法による抗原の検出),③細菌の分離培養と菌種の同定,④薬剤感受性試験,⑤病原体の遺伝子検査,の5つに大別される.これらの検査を適宜活用することによって感染症の診断と治療を行う.おのおのの検査は独立した“点”としてのツールではなく,全ては“感染症診療の最適化”のために双方向の“線”で結ばれて存在する.本稿では,おのおのの検査の特徴を紹介しながら,臨床微生物検査の基本的な考え方を概説したい.
なお,より大きな枠組みとして,私が大切だと考えている微生物検査の“志事”については,序文に誌幅を取って述べさせていただいた.ぜひそちらも併せてご一読いただきたい.
基礎技術(無菌操作,消毒と滅菌)
著者: 小松方
ページ範囲:P.183 - P.189
はじめに
微生物検査に携わる臨床検査技師は常にバイオハザード(生物災害)と背中合わせにある.そのため,経験年数を問わずバイオセーフティー(生物災害対策,バイオハザード対策)のレベルを理解し,必要な設備環境整備と操作技術を身につけたうえで検査に携わることが最低条件である.設備環境は一度構築してしまうと,後々の改修などが大掛かりとなるため,初期設計が重要である.現在はISO 15189を取得する施設が急増しており,設備環境も一定の基準を満たす必要がある.
一方,個人の技術面については常日頃から検査室内において個人の意識のみならず,検査室スタッフお互いの注意喚起が重要である.経験が豊富になればなるほど,バイオセーフティーについて軽視しがちになる.検査中は微生物を含むエアロゾルが発生しやすいシチュエーションが多くある.微生物を含むエアロゾルの発生はバイオハザードの主たる原因であり,どのような操作時にエアロゾルが発生しやすいのかなど,常に意識が必要である.
本稿では,バイオセーフティーを念頭に置いた,検査室環境整備や操作技術などに関する基礎技術について解説する.
検体採取・保存と検体の品質評価
著者: 安藤隆
ページ範囲:P.190 - P.196
はじめに
微生物検査では,検体の良否が検査成績に多大な影響を及ぼす.不適切な検体では検査精度に乏しく,得られた結果が臨床側に誤った解釈を与える恐れもある.微生物検査に従事する臨床検査技師は,検体採取,搬送,保存および検体の品質評価について正しい知識を備えていなければならない.
塗抹検査
著者: 永田邦昭
ページ範囲:P.197 - P.205
Summary
塗抹検査の基本的な技術と操作法,染色結果の解釈法などについて,実症例を提示しながらクイズを交えて紹介する(クイズは図中に掲載).解説文も参考にしながら考えていただきたい.
定量培養(喀痰,尿)
著者: 木村圭吾
ページ範囲:P.206 - P.210
喀痰の定量培養
“喀痰の定量培養”と聞いて,どれほどの先生がイメージできるだろうか.現在,実際に微生物検査に従事している現役の臨床検査技師の先生方にはなじみが薄いかもしれないが,その歴史は古く,1962年のLouriaらの報告までさかのぼる.
元来,喀痰は口腔内常在菌による汚染が避けきれない材料であり,また喀痰内における菌の分布が不均一であることより,通常の方法での分離培養では真の原因菌を判断しかねる場合が少なくない,という側面をもつ.仮に肺内における感染症原因菌であれば,その菌は喀出の途中で口腔内で汚染された菌よりも数量的に多く存在するであろう,との考え方から試みられたのが定量培養である.
集落の観察
著者: 藏前仁
ページ範囲:P.211 - P.217
はじめに
近年,質量分析装置などの技術革新により細菌同定検査は迅速性と簡易性の恩恵を得ている.しかし,それらをより効率よく,確実なものにするために寒天培地上の集落観察は細菌検査において,いまなお重要な位置付けにある.
集落の形態的特徴に加えて,性状,培地の種類,培養温度,培養時間,ガス環境を紐付けて菌種を想定し,検査フローを組み立てることで正確・迅速な菌種同定につながる.本稿では日常検査における集落の観察について,その特徴および観察のポイントを述べる.
スライド凝集試験(赤痢菌,サルモネラ菌)
著者: 森朋子 , 小野惠美
ページ範囲:P.218 - P.220
はじめに
スライド凝集試験は,生化学的性状により菌の属や種が決定した後,血清型を決定するために実施する検査で,特別な器具を必要としないため検査室で容易に実施することができる.検査室では主に赤痢菌(Shigella属),サルモネラ菌(Salmonella属),下痢原性大腸菌,コレラ菌(Vibrio cholerae)に対して実施するが,ここではShigella属とSalmonella属のスライド凝集試験について述べる.
試験管培地を用いた腸内細菌目細菌の簡易同定
著者: 杵渕貴洋
ページ範囲:P.222 - P.229
はじめに
細菌の菌種同定法としては,一般的に簡易同定キットや自動機器を用いた方法が用いられるが,近年においては質量分析法〔マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計(matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometer:MALDI-TOF MS)〕が同定法のツールとして加わった.しかしながら,これらの方法は菌種によっては誤同定が起こりうることがあり,場合によっては確認試験を実施する必要がある.特に腸内細菌目細菌(Enterobacterales)では試験管培地を確認試験の1つとして使用することが可能であり,数種類の試験管培地を使用することで正しい菌種同定へとつながる.また,上記のような検査機器を用いなくても,平板培地上に発育したコロニーから菌種を想定し,5種類程度の試験管培地を用いることで腸内細菌目細菌の簡易同定が可能である.
本稿では,主に北海道社会事業協会富良野病院(以下,当院)で常備している試験管培地に焦点を当てて,各種機器や特殊な試薬を使用しなくても,その反応性から簡易同定が可能な腸内細菌目細菌の同定について解説する.
薬剤感受性試験:耐性菌の判定
著者: 中村竜也
ページ範囲:P.230 - P.239
薬剤感受性試験の役割
感染症治療において抗菌薬を使用する場合,適切な薬剤の選択が不可欠であり,その指標となるのが薬剤感受性試験である.薬剤感受性試験の結果から抗菌力のある(=感性:suspectible)薬剤を見いだし,同時に薬剤の体内動態,宿主の病態や免疫能,副作用などを総合的に勘案して計画的な投与法を検討し,抗菌薬を選択するのが常道である.
一方,薬剤耐性菌が世界的に問題となっており,薬剤感受性試験の役割は治療薬の選定だけでなく,薬剤耐性菌の検出能力も問われるようになってきている.故に,薬剤感受性試験法やブレイクポイントの理解,問題となる薬剤耐性の検出法などの知識を深めることが重要である.中でも薬剤耐性菌の検出は,抗菌薬の選択に大きな影響を及ぼすだけでなく,重大な薬剤耐性菌の場合には感染対策上も問題となる.そのため,薬剤感受性試験結果を読み解き,薬剤耐性を見逃さずに検出するように注意しなくてはならない.
感染症法・ワクチン
著者: 幸福知己
ページ範囲:P.240 - P.244
はじめに
微生物検査を担当する臨床検査技師には,培養検査や遺伝子検査などの基本的な手技や知識の習得に加え,感染症全般の幅広い知識を身につけることが求められる.本稿では,感染症法ならびにワクチンに関する基本的事項について解説する.
各論 菌種別の培養・同定方法 グラム陽性球菌
黄色ブドウ球菌—Staphylococcus aureus
著者: 仁木誠
ページ範囲:P.246 - P.249
Summary
黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)はブドウ球菌(Staphylococcus)属において,臨床上最も重要な菌種であり,組織への直接的な侵入により皮膚軟部組織感染症や感染性心内膜炎など,また,産生する毒素により食中毒や毒素性ショック症候群などさまざまな感染症を引き起こす.
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は院内で分離される薬剤耐性菌として最も分離頻度が高く,β-ラクタム系抗菌薬をはじめ多くの抗菌薬に耐性を示すことや,免疫能の低下した患者に感染しやすいことから院内感染対策上重要な菌として認識されている.
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌—Coagulase negative staphylococci(CNS)
著者: 仁木誠
ページ範囲:P.250 - P.252
Summary
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌(CNS)は皮膚の常在菌叢として存在し,免疫能の低下した患者や人工物が挿入されている患者に日和見感染症や医原性感染症を引き起こす.菌種によりその病原性や性状は異なり,CNSのなかでも病原性の高いStaphylococcus lugdunensisは敗血症や感染性心内膜炎などの原因となる.また,メチシリン耐性の判定には黄色ブドウ球菌(S. aureus)と同様にオキサシリン(MPIPC)とセフォキシチン(CFX)を用いるが,菌種により判定基準や判定可能な薬剤が異なるため注意を要する.
A,C,G群溶血性レンサ球菌(GAS,GCS,GGS)—Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (SDSE)
著者: 山本剛
ページ範囲:P.253 - P.257
Summary
Lancefield分類で同定される溶血性レンサ球菌のうち,A群,C群およびG群として同定される菌種は複数の病原因子をもつため病原性が高く,急性咽頭炎をはじめとした上気道感染症から,重篤になれば発熱性疾患をはじめショックや筋膜壊死などの全身性疾患を起こすことが知られている.そのため,一早い同定結果が求められ,患者の予後は微生物検査技師の力量に左右されると言っても過言ではない.今回はA,CおよびG群溶血性レンサ球菌について解説する.
B群溶血性レンサ球菌(GBS)—Streptococcus agalactiae
著者: 山本剛
ページ範囲:P.258 - P.261
Summary
LancefieldでB群に分類される溶血性レンサ球菌で,主にStreptococcus agalactiaeのことを指す.新生児侵襲性感染症では主に母子感染が関係した伝播様式により髄膜炎や敗血症を引き起こすことが知られており,肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)やインフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)type bのワクチンの接種が小児で定期化してからは,小児の髄膜炎例の原因菌としては本菌が最多となった.そのため,妊婦検診でStreptococcus agalactiaeの検出を行う臨床的意義が高くなってきている.成人では糖尿病患者を中心に敗血症や皮膚軟部組織感染症の患者が発生しているが,A群溶血性レンサ球菌(GAS)やSDSEと異なり劇症化する症例は少ない.血清型を調べることにより病原性の高い菌かどうかも判明するため,疫学調査の目的もあるが病原性の確認に微生物検査は必要である.
肺炎球菌—Streptococcus pneumoniae
著者: 山本剛
ページ範囲:P.262 - P.264
Summary
肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)はヒトから分離されるポピュラーな菌である.病原性が高く,敗血症や髄膜炎などの重篤な感染症を引き起こし,最悪の場合は死亡する.莢膜を有するため免疫回避を起こし,小児や高齢者,脾臓機能が落ちた患者や多発性骨髄腫など液性免疫が低下している患者で頻回に感染を起こすためワクチン接種を行っている.第一選択となるペニシリンG(PCG)の耐性菌は治療に難渋し,特に組織移行の悪い髄膜炎を起こしている場合は大きな問題になる.そのため,PCGの感受性は投与経路や髄膜炎,非髄膜炎それぞれに判定基準が設けられており,微生物検査技師としては必ず知っておきたい内容である.
腸球菌—Enterococcus spp.
著者: 松本竹久
ページ範囲:P.265 - P.267
Summary
腸球菌(Enterococcus属菌)はヒトを含め動物の腸管内常在菌であり,病原性が低いため健常者での感染症はまれである.病院では尿路感染症や菌血症,感染性心内膜炎の原因菌として検出され,E. faecalisやE. faeciumはよく検出されるが,他のE. avium,E. casseliflavus,E. gallinarumが感染症の原因菌となることはまれである.バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)は国内外での院内感染の原因菌として重要な菌である.また,輸入鶏肉からのVREの検出が報告されており,院内外の広範な環境汚染を引き起こす危険性が高いため,注意が必要である.
栄養要求性レンサ球菌—Nutritionally variant streptococci(NVS)
著者: 松本竹久
ページ範囲:P.268 - P.269
Summary
NVSは栄養要求性レンサ球菌のことを指し,栄養要求性が通常のViridans streptococciとは異なる菌群である.現在,ヒトから分離されるNVSには,Abiotrophia defectivaとGranulicatella adiacens,G. elegansがあり,ヒトの口腔内や腸管内の常在細菌であるが,感染性心内膜炎の起炎菌として重要な細菌である.
グラム陰性球菌
カタル球菌—Moraxella catarrhalis
著者: 中山麻美
ページ範囲:P.270 - P.271
Summary
カタル球菌(Moraxella catarrhalis)はヒトの鼻咽頭粘膜に常在するグラム陰性双球菌である.慢性気道感染症患者では保有率が高く,中耳炎や副鼻腔炎の起炎菌となる.呼吸器感染症では,肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)やインフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)と同時に検出されることが多い.
患者背景とグラム(Gram)染色からM. catarrhalisが疑われた場合,翌日の培地上で“hockey puck test”陽性の集落であるかを確認する.また,ほとんどの株がβ-ラクタマーゼを産生することから,β-ラクタマーゼ試験が陽性であることがポイントである.さらには,ブチレート試験陽性を確認することで同定できる.ナイセリア(Neisseria)属菌との鑑別にはDNase産生が陽性であることが有用である.
淋菌—Neisseria gonorrhoeae
著者: 中山麻美
ページ範囲:P.272 - P.274
Summary
淋菌(Neisseria gonorrhoeae)はグラム陰性の腎臓型またはそら豆型の双球菌である.
ヒトにのみ感染し,淋菌感染症は性感染症(STD)の1つである.尿道炎,前立腺炎,精巣上体炎,腟炎,子宮頸管炎,骨盤内炎症性疾患(PID)を起こす.また,菌血症,心内膜炎,関節炎などの播種性淋菌感染症(DGI)を引き起こすことがある.
ペニシリン系薬,テトラサイクリン系薬,ニューキノロン系薬の耐性菌が増加している.
髄膜炎菌—Neisseria meningitidis
著者: 中山麻美
ページ範囲:P.276 - P.277
Summary
髄膜炎菌(Neisseria meningitidis)による感染症は,年間20〜40例程度とわが国ではまれである.しかしながら,感染症法では侵襲性髄膜炎菌感染症が5類感染症(全数把握)に分類されているため,髄液や血液などの無菌部位から検出された場合は,直ちに報告することが義務付けられている.また,飛沫や直接的な接触においてヒトからヒトへ伝播するため,本菌が分離された際は患者やその家族のみならず,治療にあたる医療従事者への感染を防ぐために予防投与が必要なケースもある.したがって,治療のみならず感染管理の面においても,迅速かつ正確な菌種同定が求められる.
グラム陽性桿菌
リステリア菌—Listeria monocytogenes
著者: 大瀧博文
ページ範囲:P.278 - P.279
Summary
リステリア菌(Listeria monocytogenes)は自然環境に広く存在し,食物媒介感染症を引き起こすことで広く知られている.海外では大規模なアウトブレイクの報告もしばしば認める.健常成人における本菌の感染は限定的であるが,ハイリスクグループとされる高齢者や妊婦(胎児含む),新生児,易感染宿主に対しては強い病原性を示し,血流感染および中枢神経感染を引き起こす.日常検査で頻繁に遭遇する菌では決してないが,抗菌薬適正使用を含む臨床的意義の観点から,誤ることなく微生物学的検査を遂行する必要がある.
バチルス属菌(炭疽菌,セレウス菌)—Bacillus anthracis,Bacillus cereus
著者: 大瀧博文
ページ範囲:P.280 - P.282
Summary
炭疽は炭疽菌(Bacillus anthracis)により引き起こされる感染症である.炭疽は家畜や野生動物,ヒトに発症する人獣共通感染症であり,主に南ヨーロッパ,東ヨーロッパ,中央アジア,中央アフリカなどで発生を認める.特に,途上国および家畜衛生環境の整っていない国に多い.日本における炭疽の発生は1994年を最後に認めていないが,2001年に米国で発生したバイオテロ事件のような不測の事態にも備えて,臨床検査技師として診断および臨床微生物検査に関する最低限の知識をもち合わせておくことは重要と考える.
一方,食中毒の原因菌として知られるセレウス菌(B. cereus)は,環境中に広く存在し,食中毒を除き本来は低病原性の日和見病原菌として認識されているが,近年,高病原性株の存在も報告されている.B. cereusは日常検査にてしばしば認めるため,臨床的意義および微生物学的所見はしっかりと把握しておきたい.
ジフテリア菌—Corynebacterium diphtheriae
著者: 西村恵子
ページ範囲:P.283 - P.285
Summary
ジフテリアはジフテリア菌(Corynebacterium diphtheriae)の感染によって引き起こされる上気道粘膜疾患であり,菌の産生する毒素により全身的な中毒症状を呈し,重篤化し死に至ることもある.毒素産生株と非産生株があり,毒素非産生株ではその病原性は低い.国内のジフテリア患者の届け出数は,1945年には約8万6千人であったが,トキソイドワクチンの接種により,1990年代では21人と著しく減少し,2000年以降発生例はない.しかし,2001年,国内でジフテリア症状を呈した患者からジフテリア毒素産生能をもったC. ulceransが分離され,2017年までに25例が確認されており注意が必要である1).
ノカルジア属菌—Nocardia spp.
著者: 西村恵子
ページ範囲:P.286 - P.289
Summary
ノカルジア(Nocardia)属は,好気性の放線菌であり,土壌・水など自然界に広く存在する.本属菌に起因するノカルジア症は,創傷部からの菌侵入などにより,皮膚および皮下組織に病巣を形成する皮膚ノカルジア症と,経気道的に肺に感染し,血行性に全身臓器に播種する内臓ノカルジア症に分類される.中でも脳に播種する脳膿瘍は重篤な感染症であり,注意が必要である.また,健常者でも感染を起こすことはあるが,多くは日和見感染であり,ステロイドなどの免疫抑制剤の使用や基礎疾患をもつ免疫不全宿主における感染症として重要である.
本属菌は発育に時間を要するため,上記のような患者情報を念頭にグラム(Gram)染色を注意深く観察し,培養期間を延長することで分離可能となる.
グラム陰性桿菌
腸内細菌科グラム陰性桿菌—Escherichia coli,Klebsiella spp.,Enterobacter spp.,Citrobacter spp.
著者: 中村彰宏
ページ範囲:P.290 - P.296
Summary
2016年に“腸内細菌目(Enterobacterales)”と“腸内細菌科(Enterobacteriaceae)”が再分類された.大腸菌(Escherichia coli),クレブシエラ(Klebsiella)属,エンテロバクター(Enterobacter)属およびシトロバクター(Citrobacter)属は後者の代表格で,ヒトの腸管内に常在し,さまざまな感染症を引き起こすコモンな感染症原因細菌である.また,それらは菌種によってさまざまな薬剤感受性パターンを示し,獲得型耐性因子も多様であるため,菌種を正確に同定することは大変重要である.近年,質量分析や遺伝子解析などによる同定が注目されているが,これらの検査にもピットフォールが存在するため,それぞれの同定手法の特徴をよく理解し,使い分ける必要がある.
セラチア・マルセッセンス—Serratia marcescens
著者: 中村彰宏
ページ範囲:P.298 - P.299
Summary
2016年に“腸内細菌目(Enterobacterales)”と“腸内細菌科(Enterobacteriaceae)”が再分類され,セラチア・マルセッセンス(Serratia marcescens)は“腸内細菌目>エルシニア科(Yersiniaceae)”に分類され,“腸内細菌科”とは区別された.本菌はヒト腸管内に常在することはまれであり,自然界や環境中に多く存在する.特に湿潤環境を好み,点滴ラインからの医療関連感染や院内アウトブレイクの事例も報告されているため,正確な菌種同定は重要である.また,本菌は薬剤耐性傾向の強い菌種であるため,治療薬選択にも注意を要する.
腸管出血性大腸菌—Enterohemorrhagic Escherichia coli(EHEC)
著者: 磯崎将博
ページ範囲:P.300 - P.302
Summary
腸管出血性大腸菌(EHEC)感染症に関する世界で最初の報告は,1982年の米国ミシガン州とオレゴン州で発生したハンバーガーを原因とするO157:H7集団感染である1).日本においては1990年に埼玉県の幼稚園で井戸水汚染による集団感染が発生し2),1996年には全国的な発生が確認され社会問題となった.以降,EHECのなかでも,とりわけO157については多くの医療機関でも積極的に検査が実施されるようになった.一方で,O157以外の血清型については見落とされることも多い.そこで本稿では,従来のEHEC検査の問題点に触れ,EHECを見落とさないためのポイントを解説する.
赤痢菌—Shigella spp.
著者: 磯崎将博
ページ範囲:P.303 - P.305
Summary
赤痢菌(Shigella属)は細菌性赤痢の原因菌であり,1898年に志賀潔によって発見され,その名にちなんでShigellaという属名が付けられた.日本国内における細菌性赤痢患者数は,戦後しばらくは10万人を超え,毎年2万人近くが死亡していたが,1974年に2,000人を割り,現在まで徐々に減少傾向にある.近年の患者数は100〜200人程度で,日常検査でもあまり遭遇することのない比較的まれな細菌になりつつある.最近の報告例の約半数は,インド,インドネシア,タイなど,主にアジア地域からの輸入感染例が占めている.しかし,まれに国内で大規模集団感染を起こすこともあるため,決して見落としてはならない重要な細菌の1つである.そこで本稿では,Shigella属の基本的な特徴や培養・同定方法について解説する.
チフス菌,パラチフスA菌—Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A
著者: 富樫真弓
ページ範囲:P.306 - P.309
Summary
チフス菌,パラチフスA菌はグラム陰性桿菌で,腸内細菌目サルモネラ(Salmonella)属に含まれる.チフス菌の正式名称はSalmonella enterica subsp. enterica serovar Typhiで,略して表記する場合はS. Typhiとする.パラチフスA菌の正式名称はSalmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi Aで,略して表記する場合はS. Paratyphi Aとする.ヒトに病原性を示す一般的なSalmonella属とは生化学的性状および病原性の強さが異なる.それぞれチフス症,パラチフス症の原因菌として臨床上重要な菌である.ともにヒトのみに感染し,リンパ行性に全身感染症を起こす.
非チフス性サルモネラ菌—Salmonella spp.
著者: 富樫真弓
ページ範囲:P.310 - P.312
Summary
サルモネラ(Salmonella)属は通性嫌気性グラム陰性桿菌で,腸内細菌目に含まれる.自然界に広く分布しており,ペット(ミドリガメや鳥類,爬虫類など)が感染源になることがある.ヒトに病原性を示すのはS. enterica subsp. entericaとS. enterica subsp. arizonaeである.臨床材料から多く検出されるのは主にS. enterica subsp. entericaで,原因食品として豚肉や鶏卵が挙げられるが,近年,ワクチンの普及によって鶏卵由来の感染は減少している.S. enterica subsp. arizonaeはヘビやトカゲなど,爬虫類の腸管常在菌であり,これらを介してヒトに胃腸炎を起こす.
エルシニア属菌—Yersinia spp.
著者: 富樫真弓
ページ範囲:P.313 - P.315
Summary
エルシニア(Yersinia)属は腸内細菌目に含まれる通性嫌気性グラム陰性桿菌で,1菌種を除き,周毛性鞭毛を有する.現在21菌種に分類され1),ヒトに病原性を示すのはペスト菌(Y. pestis),Y. enterocolitica,Y. pseudotuberculosisの3菌種である.Y. pestisはノミを介して感染し,腺ペストや肺ペストを引き起こす.肺ペストは飛沫によってヒトからヒトへ伝播し,致死率は非常に高い.21世紀以降,アフリカ,南北アメリカ,アジアで患者が報告されているが,日本では1927年以降,国内発生の報告はない.Y. enterocoliticaおよびY. pseudotuberculosisは食品や水を介した経口感染から主に感染性異腸炎を起こす.本稿では培養,同定,病態についてはY. enterocoliticaおよびY. pseudotuberculosisを対象に述べる.
ビブリオ属菌(コレラ菌,腸炎ビブリオ,他)—Vibrio spp.
著者: 早川貴範
ページ範囲:P.316 - P.319
Summary
ビブリオ(Vibrio)属菌は淡水や海水に広く分布し,魚介類や飲料水の摂取,海水への曝露によりヒトに感染するオキシダーゼ陽性ブドウ糖発酵グラム陰性桿菌である.コレラ菌(V. cholerae)や腸炎ビブリオ(V. parahaemolyticus)のように胃腸炎・下痢症などの腸管感染症を起こす群と,V. alginolyticusやV. vulnificusのように敗血症・創傷感染などの腸管外感染症を起こす群に大別される.Vibrio属食中毒のほとんどは海外旅行者からの輸入散発例である.腸管外感染症では肝障害や糖尿病などの基礎疾患を有する患者でしばしば重篤例を引き起こす.
エロモナス属菌—Aeromonas spp.
著者: 早川貴範
ページ範囲:P.320 - P.322
Summary
エロモナス(Aeromonas)属菌は淡水域の常在菌で,河川,湖沼,その周辺の土壌および魚介類などに広く分布し,衛生状態の悪い汽水域や湾内,沿岸海水からもよく分離されるオキシダーゼ陽性のブドウ糖発酵グラム陰性桿菌である.本菌感染症の発生は菌の増殖が活発な夏季に多い.現在20菌種以上が報告されており,A. hydrophila complex,A. caviae complex,A. veronii complexに大別される1).魚類,爬虫類および両生類に対しても病原性を示す.ヒト感染症には一般に中温性Aeromonas属菌が起因し,胃腸炎や下痢症などの腸管感染症,創傷感染症などの腸管外感染症を引き起こす.
緑膿菌—Pseudomonas aeruginosa
著者: 上地幸平
ページ範囲:P.323 - P.325
Summary
緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)は主に湿潤環境に分布し,医療関連感染や日和見感染における重要な菌種の1つである.本菌は特徴的な集落性状(金属様光沢)を示すことから比較的容易に同定可能である.P. aeruginosaはさまざまな抗菌薬に耐性を示し,その耐性機序として,β-ラクタマーゼなどの酵素産生や外膜蛋白の変異・欠損,薬剤排出ポンプの機能亢進などが知られている.本菌のなかでも,多剤耐性株やβ-ラクタム系抗菌薬耐性を示すIMP型などのメタロ-β-ラクタマーゼ(MBL)産生株は院内感染対策上,特に重要である.本稿ではP. aeruginosaの細菌学的特徴や培養・同定のポイントなどを概説する.
アシネトバクター属菌—Acinetobacter spp.
著者: 上地幸平
ページ範囲:P.326 - P.328
Summary
アシネトバクター(Acinetobacter)属菌のなかでもA. baumanniiは医療関連感染の主な起炎菌として知られ,院内感染対策上重要な菌種の1つである.世界的には本菌の多剤耐性化が問題となり,OXA-23-likeカルバペネマーゼ産生株のまん延や多剤耐性アシネトバクター(MDRA)の院内感染事例が多数報告されているものの,日本における分離株の薬剤感受性は比較的良好であり,院内感染事例も散発例である.本稿ではAcinetobacter属菌の細菌学的特徴や培養・同定のポイントなどを概説する.
ステノトロフォモナス・マルトフィリア—Stenotrophomonas maltophilia
著者: 佐々木雅一
ページ範囲:P.329 - P.331
Summary
ステノトロフォモナス・マルトフィリア(Stenotrophomonas maltophilia)はブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌で,環境中に存在する弱毒の日和見病原菌である.人工呼吸器関連肺炎(VAP)としても頻度が高く,国内においても起因菌の上位菌種である.培養1日ではコロニーサイズは小さいものの,日常検査で利用する培地・培養条件で検出が可能である.染色体性のメタロ-β-ラクタマーゼを産生し,β-ラクタム系薬剤には耐性傾向を示すことから,しばしば菌交代現象としての検出も認められる.したがって,起因菌としての判断は慎重に行う必要がある菌である.
レジオネラ属菌—Legionella spp.
著者: 佐々木雅一
ページ範囲:P.332 - P.334
Summary
レジオネラ(Legionella)属菌は広く環境中に存在し,水のある環境(河川,沼,人工的な貯水池など)や土壌に存在する.環境からのエアロゾル感染や汚染水の誤嚥により感染し,ヒト−ヒト感染はない.重症型は急激な経過をたどる.グラム染色は難染性であり,ヒメネス染色が利用される.培養にはB-CYEやWYOα寒天培地などの特殊培地を必要とする.近年,尿中抗原検査は尿中のL. pneumophila血清型1LPS抗原に加えて,L. pneumophila L7/L12抗原を標的とする検査試薬が登場している.
インフルエンザ菌—Haemophilus influenzae
著者: 静野健一
ページ範囲:P.335 - P.337
Summary
インフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)は,主に気管支炎や肺炎などの下気道感染症や,中耳炎,副鼻腔炎などの局所感染症から分離され,まれに菌血症や髄膜炎の起炎菌となる.露滴状のmucoid型コロニーを形成する株は莢膜株と呼ばれ,a〜fの血清型に分類される.このうち,b型(Hib)は敗血症,髄膜炎などの侵襲性疾患を引き起こす強毒株であるが,2013年にワクチンが定期接種化されてから,国内ではほとんど認められなくなっている(表1).
なお,国内の保菌調査において,3歳までに50%以上がH. influenzaeを上気道に保菌していたとの報告もあり1),小児の気道由来検体で分離された場合には,起炎菌であるかどうかの確認が必要である.
百日咳菌—Bordetella pertussis
著者: 静野健一
ページ範囲:P.338 - P.340
Summary
百日咳菌(Bordetella pertussis)が引き起こす百日咳は,強い痙攣性の咳発作を引き起こし,乳児では重篤化するため特に注意が必要である.麻疹ウイルスと同程度の強い伝播力をもち,ワクチンの効果は永続的ではないため,成人も発症する.培養検査には専用培地を必要とし,感染初期の風邪症状を呈するカタル期に最も分離率が高く,特徴的な咳症状が続く痙咳期になると検出率は低下するが,近年,遺伝子検査の普及により報告数が増加している.類似の症状を引き起こすパラ百日咳菌(B. parapertussis)は,百日咳毒素(PT)を産生しないため,症状は百日咳よりも軽い.その他,まれであるがB. holmesiiやB. bronchisepticaなどが報告されている.なお,2018年1月より5類感染症・全数把握疾患となったため,菌の分離や遺伝子検出など要件を満たした際は7日以内の届け出が必要となる.
パスツレラ属菌—Pasteurella spp.
著者: 静野健一
ページ範囲:P.341 - P.343
Summary
パスツレラ(Pasteurella)属には十数菌種が含まれ,P. multocidaがヒトを含め人畜共通感染症として最も多く分離される.P.multocidaはヒトを除くほとんどの動物の口腔内に常在し,イヌの75%,ネコのほぼ100%が保菌しているとされ1),イヌ・ネコ咬傷時,受傷から短時間に腫脹,疼痛を認めた場合には本菌の感染を疑う.創傷感染症の他,気管支炎や肺炎などの下気道感染症からも分離され,重症例では敗血症を伴う死亡例も報告されている2).P.multocidaの他,P.canis,P.dagmatis,P.stomatisなどがイヌ・ネコに関連する感染症起炎菌として報告されている.
カンピロバクター属菌—Campylobacter spp.
著者: 大城健哉
ページ範囲:P.344 - P.346
Summary
カンピロバクター(Campylobacter)属はらせん状のグラム陰性桿菌で,一端または両端に1本の鞭毛を有する.C. jejuniやC. coliは細菌性食中毒の原因菌1位で,腸管感染症,菌血症,敗血症の原因菌となる.C. jejuniやC. coliを目的とした便培養はスキロー(Skirrow)培地などの選択培地を用い,42℃,微好気環境で培養を行う.C. jejuniの腸管感染症の続発症として,まれに反応性関節炎〔ライター(Reiter)症候群〕やギラン・バレー(Guillain-Barré)症候群を引き起こす場合がある.C. fetusは髄膜炎や敗血症などの原因菌となる.
ヘリコバクター・ピロリ—Helicobacter pylori
著者: 大城健哉
ページ範囲:P.348 - P.349
Summary
ヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)はらせん状のグラム陰性桿菌で,一端に4〜8本の鞭毛を有し,2〜3回ねじれたS字状を示す.強力なウレアーゼを産生し,胃酸を中和して胃粘膜に定着する.微好気性菌で,H. pylori専用の選択培地や血液寒天培地を用いて35℃,微好気培養を行う.慢性萎縮性胃炎や胃・十二指腸潰瘍,胃粘膜関連リンパ組織(MALT)リンパ腫,胃癌,特発性血小板減少性紫斑病,鉄欠乏性貧血などの疾患との関連性がある.一次除菌で使用するクラリスロマイシン(CAM)の耐性菌が年々増加傾向にある.
ヘリコバクター・シネディ—Helicobacter cinaedi
著者: 大城健哉
ページ範囲:P.350 - P.351
Summary
ヘリコバクター・シネディまたはシナジー(Helicobacter cinaedi)はらせん状のグラム陰性桿菌で,3回以上ねじれた長めの菌体で観察される.微好気性で,水素濃度5〜10%で発育が促進される.CCDA培地に発育しない.菌血症や蜂窩織炎などの原因菌となり,動脈硬化症との関連性も報告されている.マクロライド系抗菌薬とフルオロキノロン系抗菌薬に耐性で,カルバペネム系抗菌薬やアミノグリコシド系抗菌薬,テトラサイクリン系抗菌薬に感性を示す.
クラミジア/マイコプラズマ/スピロヘータ/リケッチア
肺炎マイコプラズマ—Mycoplasma pneumoniae
著者: 舟橋恵二
ページ範囲:P.352 - P.354
Summary
マイコプラズマ科(Mycoplasmataceae)マイコプラズマ(Mycoplasma)属菌は,主に脊椎動物の細胞に付着して寄生する.肺炎マイコプラズマ(M. pneumoniae)は非定型肺炎の病原因子として,1944年にEatonら1)が発表した研究成果に基づき初めて認識された.今日では,市中肺炎や急性気管支炎の診療上最もよく遭遇する病原体の1つとなっている.M. pneumoniaeの培養を行っている施設は少なく,臨床では主に血清抗体価測定や遺伝子検出が検査診断法として用いられている.
2000年以降,M. pneumoniaeの第一選択薬とされてきたマクロライド(ML)系抗菌薬に耐性を示す株が分離されるようになった.さらに遷延例や重症化例の報告も散見されており,急性期の検査診断を迅速に行うことが必要とされている.本稿ではM. pneumoniaeについて,一般的な知識として必要な内容を解説する.
クラミジア(クラミドフィラ)—Chlamydia trachomatis,Chlamydia pneumoniae,Chlamydia psittaci
著者: 舟橋恵二
ページ範囲:P.355 - P.357
Summary
ヒトに病原性を示すクラミジア科(Chlamydiaceae)クラミジア(Chlamydia)属菌として,トラコーマ・クラミジア(C. trachomatis),肺炎クラミジア(C. pneumoniae),オウム病クラミジア(C. psittaci)などが知られている.主にC. trachomatisは新生児肺炎や性器感染症を,C. pneumoniaeは市中肺炎を,C. psittaciは人獣共通感染症であるオウム病を引き起こす.
クラミジア属は,1999年Everettらにより16Sと23SのリボソームRNA遺伝子の分析が行われ1),クラミジア属とクラミドフィラ(Chlamydophila)属に分別することが提唱された.しかしその後の議論により,クラミドフィラ属の菌種は全てクラミジア属へ回帰している2).クラミジア属による感染症の治療では,β-ラクタム系抗菌薬が有効でないため,他の感染症との鑑別を要する場合もある.本稿ではクラミジア属菌のC. trachomatis,C. pneumoniae,C. psittaciについてそれぞれ解説する.
梅毒トレポネーマ—Treponema pallidum
著者: 大楠清文
ページ範囲:P.358 - P.360
Summary
・梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)は直径0.1〜0.2μm,長さ6〜20μmの屈曲した6〜14施転のらせん状菌である.
・通常の明視野光学顕微鏡では視認できず,暗視野顕微鏡で観察される.
・試験管内での培養は不可能で,ウサギの睾丸内で培養する以外に現実的方法はなく,血清学的な診断が主流である.
・血清抗体は感染後,初めにカルジオリピンに対する抗体価(非トレポネーマ抗原による検査:VDRL,RPR,自動化法)が上昇し,次いでトレポネーマに対する特異的抗体価(トレポネーマ抗原による検査:FTA-ABS法,TPHA法)が上昇する.
・海外ではペニシリンGの筋注単回投与が一般的であるが,国内ではペニシリンGの筋注は使用できないため,経口合成ペニシリン剤(アモキシシリンなど)を長期間投与することが推奨されている.
・全数報告対象の5類感染症である.
レプトスピラ属菌—Leptospira spp.
著者: 八幡照幸
ページ範囲:P.361 - P.363
Summary
レプトスピラ(Leptospira)属菌は,スピロヘータ目レプトスピラ科の好気性グラム陰性細菌である.病原性レプトスピラはヒトを含めた120種以上の動物(哺乳類,爬虫類,両生類)などから分離されており1),感染回復後の保菌動物の腎臓に定着,保菌され,これらの種,群間で循環伝播している1〜4).ヒトへの感染は,皮膚の擦過傷や切り傷,また結膜や粘膜と,保菌動物の尿,または尿によって汚染された水や土壌との接触,汚染された水や食物の飲食で起こり,まれではあるが性交や母乳を介してのヒト−ヒト感染の報告もある.動物咬傷感染はないとされる4,5).
リケッチア—Rickettsiaceae
著者: 八幡照幸
ページ範囲:P.364 - P.367
Summary
リケッチア(Rickettsiaceae)は,小型の非運動性グラム陰性球・桿菌で,動物細胞のなかでしか増殖できない偏性細胞内寄生細菌である.ダニやシラミなどの節足動物を介してヒトへ感染するが,生体外では速やかに死滅する.リケッチア感染症は,リケッチア目に属する6属菌(Rickettsia属菌,Orientia属菌,Anaplasma属菌,Ehrlichia属菌,Neorickettsia属菌,Neoehrlichia属菌)によって引き起こされ,米国疾病管理予防センター(CDC)は,紅斑熱群,発疹熱群,発疹チフス群,その他のリケッチア症群に分類している1).
わが国では,①日本紅斑熱,②ロッキー山紅斑熱(RMSF),③つつが虫病,④発しんチフスの4疾患が4類感染症全数把握疾患に指定されている.RMSFは2020年11月現在まで国内での報告はない2).
嫌気性菌
バクテロイデス属菌—Bacteroides spp.
著者: 中村明子 , 太田浩敏 , 山岸由佳 , 三鴨廣繁
ページ範囲:P.368 - P.370
Summary
バクテロイデス(Bacteroides)属菌は,グラム陰性の偏性嫌気性桿菌であるが,酸素耐性が強く比較的培養しやすい.non-fragilis BacteroidesグループはB. fragilisと比較して薬剤耐性度が高いため,これらを鑑別することが臨床上重要である.GAM寒天培地,ブルセラHK寒天培地などに嫌気条件で容易に発育し,生化学的性状,質量分析法により菌名の同定は比較的容易である.Bacteroides属は,横隔膜より下部の感染症を中心に最も多く検出され,腹腔内感染症,消化器および生殖器に対する術後感染症において,臨床上重要である.近年,クリンダマイシンだけではなく,セフメタゾール,アンピシリン・スルバクタムの耐性率が上昇しており,B. fragilisではカルバペネム薬耐性も低頻度ながら検出されている.
フソバクテリウム属菌—Fusobacterium spp.
著者: 宮﨑成美 , 太田浩敏 , 山岸由佳 , 三鴨廣繁
ページ範囲:P.371 - P.373
Summary
フソバクテリウム(Fusobacterium)属菌は無芽胞の偏性嫌気性グラム陰性桿菌であり,臨床上重要な菌種として,F. necrophorum,F. nucleatum,F. varium,F. mortiferumなどが知られている.口腔咽頭部,消化管,生殖器などに常在しており,全身のさまざまな臓器の化膿性感染症から分離され,特に,F. necrophorumはレミエール(Lemierre)症候群との関連性が高い.また,炎症性腸疾患や大腸癌との関連も報告されている.
Fusobacterium属菌は酸素感受性であるため,培養時は酸素への曝露がないよう取り扱う必要がある.菌種はグラム(Gram)染色形態,コロニー性状,生化学的性状などにより同定可能である.多くの株がペニシリン系薬,セファロスポリン系薬,カルバペネム系薬,クリンダマイシン,メトロニダゾールなどの抗菌薬に感性を示す.
アクチノマイセス属菌—Actinomyces spp.
著者: 品川雅明
ページ範囲:P.374 - P.376
Summary
アクチノマイセス(Actinomyces)属は,放線菌目(Actinomycetales)に属し,非抗酸性である点がノカルジア(Nocardia)属との鑑別点である.ヒトでは,口腔,消化管,腟に生息しており,内因性により放線菌症を発症することがある.Actinomyces属による感染症を疑うポイントは,膿汁中の硫黄顆粒,フィラメント状のグラム陽性桿菌,嫌気培養によるクモの足様spider formの集落(A. israelii),嫌気培養によるピンク色から赤色の集落(A. odontolyticus)などである.
ディフィシル菌—Clostridioides difficile
著者: 品川雅明
ページ範囲:P.377 - P.379
Summary
ディフィシル菌(Clostridioides difficile)は以前,Clostridium difficileと命名されていた.トキシン産生株では,高齢,抗菌薬使用などのリスク因子により,下痢症や偽膜性大腸炎を引き起こす.C. difficile感染症(CDI)の診断検査は,便性状検査,迅速簡易キットによるグルタミン酸脱水素酵素(GDH)およびトキシン検査,培養検査(toxigenic culture),核酸増幅検査(NAAT)を組み合わせたアルゴリズムが推奨されている.
ウエルシュ菌—Clostridium perfringens
著者: 村上忍
ページ範囲:P.380 - P.381
Summary
ウエルシュ菌(Clostridium perfringens)は嫌気性グラム陽性有芽胞桿菌である.嫌気性菌用血液寒天培地でR型の集落としてみられ,強い溶血性(二重溶血帯)を示す.コロニーからのグラム(Gram)染色では極めて大型の車輌状桿菌として観察される.生体内では芽胞を形成するが,日常細菌検査で通常使用する培地では芽胞は形成されない.C. perfringensは胆汁から高率に分離されることを念頭に置いて検査を行う必要がある.ガス壊疽の起炎菌として重要であり,またエンテロトキシンを産生し食中毒の原因となる.
ボツリヌス菌—Clostridium botulinum
著者: 村上忍
ページ範囲:P.382 - P.383
Summary
ボツリヌス菌(Clostridium botulinum)はボツリヌス症の原因菌で,嫌気性グラム陽性有芽胞桿菌である.菌体の一端近くに菌体の幅よりやや大きい楕円形の芽胞を形成する.メズサの頭状集落を作り,リパーゼ反応陽性である.芽胞の形で土壌中に広く分布し,野菜,肉類を汚染し,ボツリヌス毒素による食餌性ボツリヌス症,乳児ボツリヌス症,創傷性ボツリヌス症の3つの疾患が知られている.ボツリヌス症の確定には毒素の検出が必要で,マウスを用いた毒素試験と毒素・抗毒素中和反応試験が行われる.
破傷風菌—Clostridium tetani
著者: 村上忍
ページ範囲:P.384 - P.385
Summary
破傷風菌(Clostridium tetani)は破傷風の原因菌で,嫌気性グラム陽性有芽胞桿菌である.グラム(Gram)染色により端在性の大きな円形の芽胞を有し,いわゆる“太鼓バチ状”と呼ばれる特徴ある形態を呈する.湿潤な培地では繊細なスウォーミングをする特徴がある.C. tetaniは芽胞の形で土壌中に広く分布し,創傷部位から体内に侵入する.三叉神経の硬直,嚥下困難,開口困難,全身性痙攣が起こる.感染部位で発芽・増殖し,破傷風毒素と溶血毒を産生する.発症には破傷風毒素が関与する.
抗酸菌
結核菌—Mycobacterium tuberculosis
著者: 伏脇猛司
ページ範囲:P.386 - P.390
Summary
近年の飛躍的な技術の進歩により感染症検査は大きく変化しているが,結核菌(Mycobacterium tuberculosis)検査はまだまだ手作業が多く,実務,結果の解釈,ともに熟慮を要する部分が多い.本稿では検査を進めるうえでの注意事項を中心に記す.
非結核性抗酸菌(遅発育菌・迅速発育菌)—Nontuberculous mycobacteria(NTM)
著者: 伏脇猛司
ページ範囲:P.391 - P.394
Summary
非結核性抗酸菌(NTM)は環境やさまざまな動物に存在するため,同じ抗酸菌でも結核菌(Mycobacterium tuberculosis)とは分けて考えないといけない.NTMは感染経路,病原性,治療の是非や治療法など,まだまだわかっていないことが多く,それらの指標となる臨床微生物検査の分野においても発展途上である.これらを踏まえたうえで,どのように検査に対峙すべきか,考えるきっかけを目指して記述する.
真菌
カンジダ属菌—Candida spp.
著者: 田澤庸子
ページ範囲:P.395 - P.397
Summary
Candida albicansをはじめとするカンジダ(Candida)属菌は皮膚表面や上気道,腸管内,腟などの粘膜の常在菌であり,易感染性宿主においては日和見感染を起こすことが知られている.特にカテーテル関連血流感染やカンジダ血症の場合は,早期に菌種の推定あるいは同定結果を報告することで,薬剤感受性の推測につながる.日常検査における同定はCandida属用酵素基質培地,簡易同定キット,自動機器を用いた酵母同定用パネル,質量分析装置(MALDI-TOF MS)などが用いられる.
アスペルギルス属菌—Aspergillus spp.
著者: 田澤庸子
ページ範囲:P.398 - P.400
Summary
アスペルギルス(Aspergillus)属は自然環境に広く存在し,発酵食品や医薬品,酵素,有機酸などの製造過程で使用される菌種がある一方で,ヒトや動物の日和見感染の原因となる菌種,マイコトキシンの産生や食品汚染菌として食品衛生上問題となる菌種がある.Aspergillus属のうち,ヒトにアスペルギルス症を引き起こす菌種として最も多く分離されるのはA. fumigatusである.Aspergillus属を目的とした分離培養は,真菌用培地で35℃一夜培養後,1〜2週間室温培養する.同定は,巨大集落の観察(色調,発育速度,表面の性状)および顕微鏡学的形態観察の所見から既知菌種の形態と照合して同定する.
クリプトコックス属菌—Cryptococcus spp.
著者: 田澤庸子
ページ範囲:P.401 - P.403
Summary
クリプトコックス症はクリプトコックス(Cryptococcus)属菌による感染症で,その主要な原因菌種はC. neoformansおよびC. gattiiである.環境中のCryptococcus属菌は,経気道的に吸入してヒトに感染し,肺,脳・髄膜,皮膚,さらに播種性に感染症を起こす.C. neoformans/C. gattiiの同定は,墨汁法による厚い莢膜の観察,37℃の発育能およびフェノールオキシダーゼ産生で可能である.両菌種の鑑別は,カナバニン・グリシン・ブロモチモールブルー(CGB)寒天培地上の発育,またはマトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計(MALDI-TOF MS)による同定でできる.
ムーコル目菌(接合菌)—Mucor spp., Rhizopus spp.など
著者: 奈須聖子
ページ範囲:P.404 - P.407
Summary
近年,免疫不全患者の増加に伴い,深在性真菌症が増加している.まれに外傷などに続発する限局性の皮膚ムーコル症を除けば,最も急性に進行し予後不良な真菌症と知られていることからも,検出された場合は迅速に報告することが望ましい.
また,分子生物学的手法を用いた系統分類により2007年に接合菌門がなくなり,新分類におけるケカビ亜門のムーコル目(Mucorales)に属するため,感染症はムーコル症(mucormycosis)と呼ばれている.
ヒトにおけるムーコル症の原因菌は,ムーコル(Mucor)属,リゾプス(Rhizopus)属,リゾムーコル(Rhizomucor)属,リクテイミア(Lichtheimia)属〔アブシジア(Absidia)属〕,クスダマカビ(Cunninghamella)属,ハリサシカビモドキ(Syncephalastrum)属などがある1).これらの構造体は他の真菌に比べ特徴的であるため,属レベルの同定が容易にできるよう本稿で述べていく.
ニューモシスチス・イロベチイ—Pneumocystis jirovecii
著者: 奈須聖子
ページ範囲:P.408 - P.409
Summary
ニューモシスチス・イロベチイ(Pneumocystis jirovecii)は,白血病などの悪性腫瘍,骨髄移植,後天性免疫不全症候群(AIDS)患者など細胞性免疫不全宿主に日和見感染症の代表疾患であるニューモシスチス感染症を引き起こす病原微生物である.感染病変の主座は肺で,ほとんどの場合はニューモシスチス肺炎(PCP)を呈し,肺炎以外の感染症はまれである1,2).以前はP. cariniiと呼ばれていたが,ヒトに感染するものとは種類が異なり,現在ではP. jiroveciiがヒトに感染する菌であることが判明している.
真菌クイズ「菌トレ」
著者: 奈須聖子
ページ範囲:P.410 - P.416
問題1 赤い色素に注意!!
症例
ミャンマー国籍の20歳代,女性.出産のために来日.頭痛,発熱,意識障害で救急搬送.
頭部CT検査により,右前頭葉,右視床,左後頭葉にLDA(low density area)を認め,脳膿瘍,水頭症が疑われた.胸部単純X線検査で右中肺野に結節影が認められた.
原虫
赤痢アメーバ—Entamoeba histolytica
著者: 松村隆弘
ページ範囲:P.417 - P.419
Summary
腸管寄生原虫である赤痢アメーバ(Entamoeba histolytica)を病原体とするアメーバ赤痢は,発生動向調査が始まった1999年以降,右肩上がりに増加し,2016年の1,152件/年をピークに近年では850件前後と高い水準で推移しており,わが国の代表すべき寄生虫感染症となっている.しかし,細菌と異なり一般施設での培養検査は実施できず,当日提出された検体中の囊子(cyst)や栄養型(trophozoite)を顕微鏡下で検出することが多く,初見で赤痢アメーバを判定することは困難である.故に,病態や形態学的特徴,検査法などの知識を整理して覚えておく必要がある.
マラリア—Plasmodium spp.
著者: 松村隆弘
ページ範囲:P.420 - P.423
Summary
マラリアはアフリカを中心とした熱帯・亜熱帯地域で流行しており,2018年には推定2億2,800万人が罹患し,推定40.5万人が死亡した重要な寄生虫感染症である1).2000年と比較すると検査キットや治療薬などの普及により死者数は半数以下となったが,感染者数は4,000万人程度の減少であり,2014年以降大きな減少はみられていない.わが国では輸入感染症として認知され,過去5年間では40〜60件/年程度の報告数で推移している.
ヒトに感染するマラリア原虫は,ヒトに宿主特異性を示す熱帯熱マラリア原虫(Plasmodium falciparum:Pf),三日熱マラリア原虫(P. vivax:Pv),四日熱マラリア原虫(P. malariae:Pm),卵形マラリア原虫(P. ovale:Po)の4種であったが,2000年以降,マレーシアを中心に感染者が増加傾向にあるサルを自然宿主とした二日熱マラリア原虫(P. knowlesi:Pk)の1種が加わり,現在は5種となっている.
原虫クイズ「虫トレ」
著者: 松村隆弘
ページ範囲:P.425 - P.430
以下に示す写真を見て,原虫名を答えられるようにしましょう.裏面に答えと押さえておきたい事項を記載してあります(切り取ればカルタとしても使えます).
付録
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.172 - P.175
基本情報
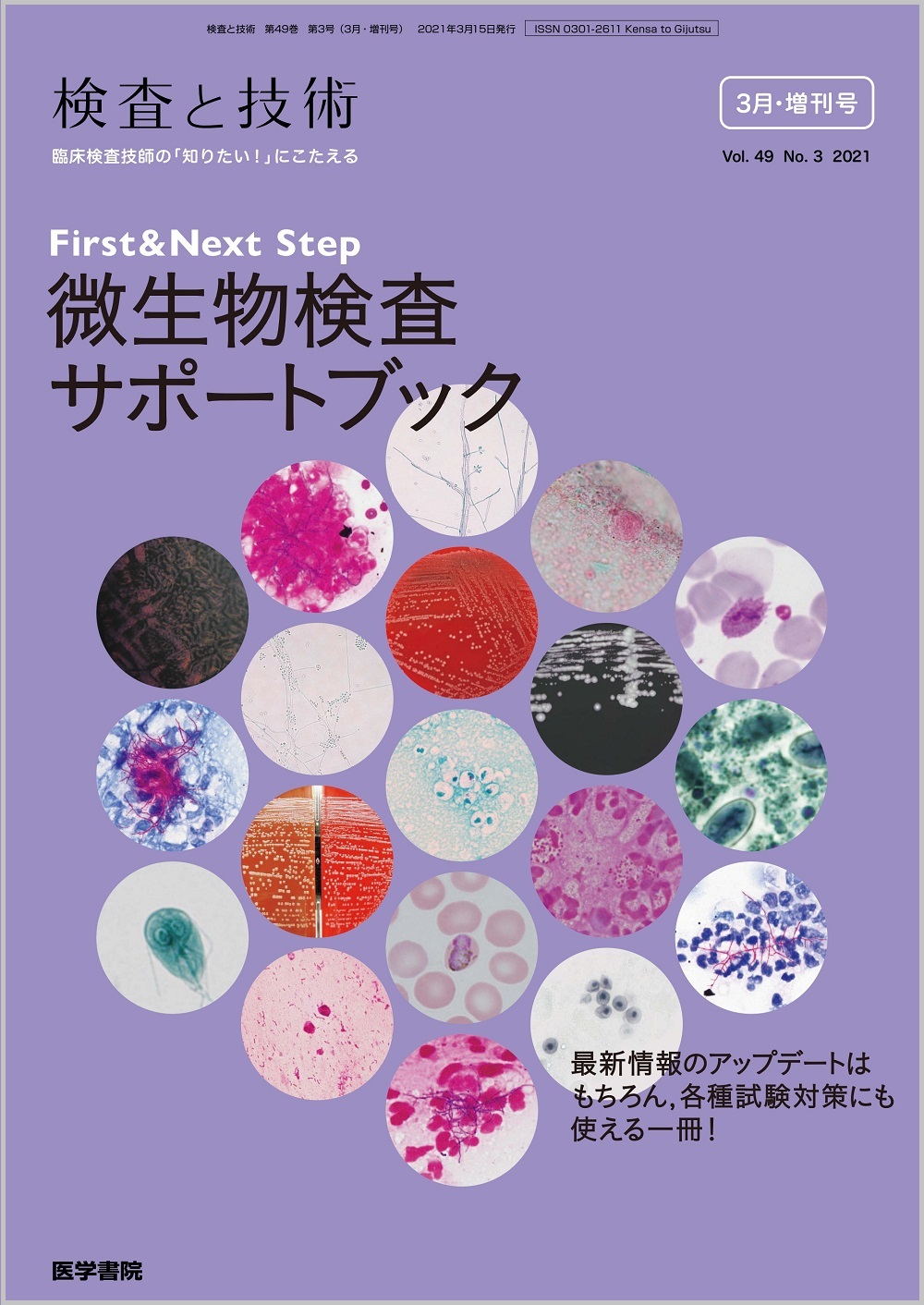
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
