Point
●機能性消化管疾患(FGIDs)は,主に機能性ディスペプシア(FD)と過敏性腸症候群(IBS)に分類される.
●FDとIBSは互いに合併しやすく,症状の背景には種々のストレスなどの心理社会的要因や内臓知覚過敏,消化管運動異常などが関係していることや感染性腸炎後に発症リスクが高まることなど類似点も多い.
●FDとIBSは,器質的疾患を認めないが腹部症状を生じる疾患で,症状や経過から診断される.診断の際には各種検査を用い器質的疾患の除外が重要である.
●治療経過中も治療抵抗例などでは,器質的疾患が背景に存在しないか検索が必要である.
雑誌目次
検査と技術49巻8号
2021年08月発行
雑誌目次
病気のはなし
機能性消化管疾患—機能性ディスペプシア(FD),過敏性腸症候群(IBS)
著者: 岡本陽祐 , 五十嵐良典
ページ範囲:P.848 - P.855
技術講座 生化学
シリーズ 臨床化学検査の基礎をなす方法と原理・3
臨床化学分析における呈色反応
著者: 亀田貴寛
ページ範囲:P.874 - P.879
Point
●臨床化学分析の呈色反応は,化学的呈色反応と酵素的呈色反応に大きく分けることができる.
●化学的呈色反応にはキレート呈色反応や色素結合反応などがあり,エチレンジアミン四酢酸(EDTA)血漿検体ではキレート呈色反応で低値を示す項目もあるので注意が必要である.
●酵素的呈色反応には過酸化水素(H2O2)・ペルオキシダーゼ(POD)共役系酵素法やNAD(P)H系酵素法などがあり,酸化酵素反応においては還元物質が負の誤差を与える.
●測定原理を理解し,日々の検査で生じる問題点や疑問点の検討から研究につなぐことも患者へのよりよい医療の提供の1つの形である.
輸血
—step up編—溶血性貧血の診断と検査
著者: 亀﨑豊実
ページ範囲:P.880 - P.887
Point
●溶血性貧血は,赤血球がさまざまな原因により早期に壊れることで生じる貧血の総称であり,全ての病型に共通の診断基準がある.
●診断基準の項目がより多く認められると診断は確からしくなるが,例外もあることに留意する.
●溶血の存在が診断された後は,特徴的な症状や検査所見によりグループ分けして,溶血性貧血の病型診断を進める.溶血性貧血の病型により治療法や予後が異なるため,各病型に特異的な検査で診断の確定を行うことが重要である.
●免疫性か否か,赤血球形態異常,平均赤血球容積(MCV)の値,家族歴の有無,血小板減少の有無などが主なチェックポイントとなる.
微生物
微生物学領域の抗原検査
著者: 宮本仁志
ページ範囲:P.888 - P.893
Point
●キットを使用する前に添付文書を熟読し,操作方法だけではなく使用目的・交差反応・妨害物質など,キットの特徴を確認する.
●イムノクロマトグラフィー(ICA)法は検査への熟練が不要であるが,多量の血液成分の混入や高粘稠度の検体においては正確な結果が得られない場合がある.
●キットは抗原定量検査や遺伝子検査と比較すると感度は劣るため,検査キットが陰性でも目的とする微生物を否定するものではない.
生理
腹部エコー領域におけるカラードプラの活用
著者: 刑部恵介 , 杉山博子 , 西川徹
ページ範囲:P.894 - P.899
Point
●ドプラ法の原理,装置の取り扱いを理解し,必ず練習を行ってから使用する必要がある.
●ドプラ法で検査を行う場合には,呼吸,体位変換および走査部位を工夫し,対象病変を浅部に描出してから検査を行うことが大切である.
●腫瘍性病変の評価の場合には低速血流の検出を目的に調整するが,血管病変の場合はやや高めの設定で行う.
●胆囊の評価を行う場合には,病変がプローブから深部となる頸部や消化管運動の影響を受けやすい腹腔側に位置する場合は血流が得られにくいことがある.
●膵腫瘍性病変の血流評価を行う場合には,消化管の影響を受けやすいため圧迫しすぎないように注意する.また心窩部横走査にこだわらず,縦走査でも観察するとよい.
トピックス
超音波医学における人工知能活用の現状と展望
著者: 中田典生
ページ範囲:P.856 - P.858
現在の超音波診断装置はPOCUSを中心に進んでいる
超音波診断装置は大きくカート型とモバイル型に分けられる.東京慈恵会医科大学附属病院でも毎年超音波(ultrasonography:US)診断装置の購入要望が各診療部門から上がってくるが,近年ノートPCタイプに代表されるモバイル型のUS装置は,その機動性や低価格などの理由から,病棟やスペースの限られている特定の外来診察スペースでの需要が増えている.いわゆるPOCUS(point of care US)を目的とする装置のマーケットが世界的に増大している.ノート型US装置は,さらにスマートフォン(以下,スマホ)型ならびに通常のスマホに接続可能なUS装置として進歩してきた.一方で,POCUS分野では,穿刺や生検手技に両手を使うことから,US装置の画面が好みの位置に固定できるカート型の需要はまだ高いのが現状である.また,近年のUS装置の高性能化に伴い,ハイエンド装置の価格はますます上昇傾向にあり,医療経営が苦しい病院にとっては頭の痛い問題となっている.
もともとUS装置はその利便性と低価格であることや最小限のメンテナンスを背景とする経済性により,日本では販売が伸びてきた.しかしハイエンド装置のマーケットは現状の日本では限界があると考えられる.人工知能(artificial intelligence:AI)の観点からすると,US装置に搭載されるグラフィックボードの利活用が考えられるが,US装置の電源確保と省スペースのため,ハイエンドUS装置のこれ以上の大型化には疑問が残るし,ハイエンド装置のみでのAI活用では,後述する専門家並みの病変指摘などのAIの利点を多くのユーザーが享受できなくなってしまう.したがって近い将来,US装置のAI診断支援はAIサーバーを設置して,クライアントであるモバイル型US装置と無線ネットワークを使ってAI診断支援を行う手法のほうが実用的であると考えられる.
スポーツドクターが用いる運動器エコーの実際
著者: 岩本航 , 加藤拓也
ページ範囲:P.860 - P.863
はじめに
スポーツドクターが選手にかかわる場所は,医療機関以外にも試合会場や練習場,合宿地や宿泊先など多岐にわたる.近年,携帯性に優れた超音波診断装置(エコー)が開発され,場所を問わず使用が可能になったことで,スポーツ現場にエコーを持ち込むドクターが増えている.現場ですぐに画像評価が行えることは,大きなメリットである.医療機関でも,スポーツドクターがエコーを使う意義は大きい.本稿ではスポーツドクターがどのように運動器エコーを用いているのか,自験例を中心に紹介させていただく.
FOCUS
臨床検査技師に求められるノンテクニカルスキル
著者: 辰巳陽一
ページ範囲:P.864 - P.869
臨床検査技師と医療チーム
医療は1人の医療者で成り立つものでなくチームとして協働しなければならないということは,もはやあらためて取り上げるほどのことではなく,“チーム医療”という言葉は,われわれ医療者には,外出の際にはマスクをしなければならないのと同様の“強制的”な常識といえるかもしれない.
ただ,チーム医療という言葉の響きからは多職種が協働して患者を救命する場面や救急医療現場や手術室のような切迫した場面が連想され,臨床検査技師の一部からは,直接患者と接触する機会が少ないため,チーム医療に参加しているという感覚は乏しいという意見を耳にする.しかし,いま,医療チームに臨床検査技師は欠くことはできず,簡単に思いつくだけで,栄養サポートチーム(nutrition support team:NST)での患者の検査値をもとにした病態評価やその説明をはじめとし,感染制御チーム(infection control team:ICT)での微生物検査結果についての資料作成や院内への情報発信,それ以外にも,呼吸器ケアチーム,糖尿病診療,血管診療チームなど,その活躍の場は多彩である.ただ,“多職種医療チーム”の概念は,必ずしも確立されているわけではなく,その認識も職種によって異なる.したがって,臨床検査技師として参加する医療チームのあるべきかたちを認識するとともに,チームにおいての行動規範を認識するのは意味があることではないだろうか.
がん患者との面接(検査内容説明)のときに知っておいてもらいたいがん患者のこと
著者: 三浦里織
ページ範囲:P.870 - P.873
はじめに
「もうだめなのかしら……」,外来で医師から現在の治療継続が困難となったことを説明され,患者がぽつりとつぶやかれた.医師は,「がんの遺伝子を調べて,今後の治療を探しましょう」と説明し,患者は少しほっとしたものの困った表情で,ゲノム検査の説明を受けるため,専門外来を受診することとなった.
十数年前であれば抗がん剤の種類も少なく,一度治療が継続困難となると,患者の人生は永らえることが難しい状況であった.しかし現在は,がんの遺伝子解析が進み,治療継続が困難となった上記のような患者でも,治療の選択肢が増える可能性が生じてきた.2018年には「第3期がん対策推進基本計画」の分野別施策の1つとして,“がんゲノム医療”の整備や推進に取り組むことが閣議決定され,現在のがんゲノム医療が発展している.
がんゲノム医療においては,専門資格としての臨床細胞遺伝学認定士が患者の診断に関連して中心的な役割を担っている.そのなかで,患者の今後の治療に対して医師や看護師を含むさまざまな医療スタッフとコミュニケーションをとる場面がでてきたのではないかと考える.
また,医療者だけでなく,「検査を受けたい」と遺伝外来に訪れた患者にも接する機会が増えているのではないだろうか.そこで,本稿ではがん患者の置かれている立場や,その心理状況について紹介する.患者とコミュニケーションをとる際の手助けとしていただきたい.
過去問deセルフチェック!
生化学・臨床化学(糖質)
ページ範囲:P.887 - P.887
過去の臨床検査技師国家試験にチャレンジして,知識をブラッシュアップしましょう.以下の問題にチャレンジしていただいたあと,別ページの解答と解説をお読みください.
解答と解説
ページ範囲:P.907 - P.907
糖質とはアルデヒド基またはケトン基をもつ多価アルコール分子とその誘導体・重合体の総称をいいます.アルデヒド基をもつ糖はアルドース,ケトン基をもつ糖はケトースに分類され,単糖類はそれ以上加水分解することのできない糖質の基本単位となります.単糖類を構成する炭素数は,生体内では通常3〜6個であり,その炭素数により三炭糖(トリオース),四炭糖(テトロオース),五炭糖(ペントース:リボース,キシロース,アラビノースなど),六炭糖(ヘキソース:グルコース,ガラクトース,マンノース,フルクトース)と呼ばれています.さらに,2分子の単糖類は,それぞれのヒドロキシ基から1分子の水分子がとれて結合します(グリコシド結合).単糖類が数個(明確な定義はない)結合したものは少糖類(二糖類,三糖類,四糖類),多数結合したものは多糖類(グリコーゲン,デンプン,セルロースなど)と呼ばれています.アカルボース(問題1,選択肢4)は,放線菌の培養由来の四糖類であり,2型糖尿病を治療するための経口血糖降下薬に用いられています.その作用は,小腸から分泌されるα-グルコシダーゼや膵臓から分泌されるα-アミラーゼを阻害します.
糖新生(問題3,選択肢4)とは,グルコースが解糖系により分解されてピルビン酸になる経路を,ほぼ逆行してグルコースを合成する経路です.さらにグルコースの分解産物を材料とするだけでなく,アミノ酸や脂質を材料とすることも可能な経路です.この解糖系の始めのステップで働いている酵素がヘキソキナーゼ(hexokinase:HK)です.
疾患と検査値の推移
慢性リンパ性白血病
著者: 三ツ橋雄之
ページ範囲:P.900 - P.906
Point
●慢性リンパ性白血病(CLL)は末梢血に成熟リンパ球の増生を認めるB細胞腫瘍である.
●CLLのリンパ球は細胞形態や表面形質に特徴があり,いずれも診断に有用な所見である.
●CLLは欧米に多く,日本を含むアジアではまれな疾患である.高齢者に多く,進行は緩徐であることが多い.
●CLLは近年の分子遺伝学的研究の進展により病態の解明が進み,分子標的薬など新たな治療法の選択が可能となってきている.
臨床検査のピットフォール
—知らなかったは通用しない!—凝固線溶検査におけるヘマトクリット補正
著者: 桝谷亮太
ページ範囲:P.908 - P.911
はじめに
凝固線溶検査は,測定に至るまでの検体の取り扱いによって結果が変動することが知られている.現在わが国においては,日本検査血液学会標準化委員会凝固検査用サンプル取扱い標準化ワーキンググループが提唱する“凝固検査検体取扱いに関するコンセンサス”に準じて検査を行うことが推奨されている1).また,凝固線溶検査に用いる採血管に添加されている抗凝固剤のクエン酸ナトリウムは,エチレンジアミン四酢酸(ethylenediaminetetraacetic acid:EDTA)などのように顆粒や粉末状ではなく水溶液であるため,適切な検体量を遵守しなければ検査結果に影響が出る2,3).加えて,CLSI(Clinical and Laboratory Standards Institute)ガイドライン(H21-A5)4)では検体のヘマトクリット(hematocrit:Ht)が55%を超える場合,クエン酸ナトリウムの濃度を調整することが推奨されている.しかしながら,Htが55%を超える場合にクエン酸ナトリウムの濃度の調整が推奨されていることは意外と知られていない,もしくは知っていても対応していないのが現状であると思われる.
本稿では,Ht値と凝固線溶検査の関係について述べるとともに,多血症患者や新生児などで遭遇する高Htの検体における補正方法について解説する.
Q&A 読者質問箱
感染症の迅速検査を行う際の検査前確率・検査後確率について教えてください.
著者: 大瀧博文
ページ範囲:P.912 - P.914
Q 感染症の迅速検査を行う際の検査前確率・検査後確率について教えてください.
A 新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)のパンデミックにより,感染症検査分野はこれまでにない多くの注目を集めています.これらの検査になじみが薄かった検査室においても,毎日のようにPCR(polymerase chain reaction)検査や抗原検査などの迅速検査に関するワードが飛び交っていたことと推察します.PCR検査が多くの施設で実施されるようになってからは,遺伝子関連試薬や消耗品が軒並み品切れ状態となり,チップ類やチューブ類ですら取り合いの状況になりました.マスメディアでは連日のように検査数の増加を求める声が取り上げられ,何が最善策なのかが明確でないまま進んできた感もありますが,無症状感染者の存在がこれらのコントロールを非常に難しくしたことは皆さんもご存じの通りかと思います.
臨床医からの質問に答える
梅毒に関する検査結果についてどのように評価したらよいか教えてください.
著者: 村松崇 , 木内英
ページ範囲:P.916 - P.919
はじめに
梅毒は近年報告数が増加しており,治療後も防御免疫が成立せず何回も感染しうる病原体です.治療は確立しているものの,未治療の場合は深刻な合併症をもたらすため,適切に検査・治療を行う必要がある重要な感染症といえます.
梅毒に関する検査としては血清反応を用いたものが主体です.病原体の検出が難しいため,抗体を検出する検査が主体となります.そのため,感染の時期や患者の免疫の状態により,いくつかのパターンを呈することがあります.治療終了後も陽性反応がみられることがあり,病歴などの情報をしっかり確認して解釈する必要があります.日本および米国でガイドライン1,2),総説3)が発表されており,本稿ではその情報を基に述べます.
ワンポイントアドバイス
剝離しやすい硬組織検体の抗原賦活化法
著者: 廣瀬さやか
ページ範囲:P.920 - P.922
はじめに
免疫組織化学染色(以下,免疫染色)において,最適な標本を作製するためには,①固定液の浸透,②脱灰液の選択,③包埋過程における脱水・置換・パラフィン浸透,④パラフィン切片の厚さ,⑤切片の十分な伸展・乾燥など,プレアナリシス工程が重要である.しかし,適切なパラフィン切片が得られても,染色工程での抗原賦活化処理,特に加熱処理において,切片への負荷が大きいために切片の剝離が問題となることがある.本稿では,特に切片の剝離しやすい軟骨,骨,歯などの硬組織切片における加熱処理の工夫を解説する.
連載 帰ってきた やなさん。・22
自作スタンプ!
著者: 柳田絵美衣
ページ範囲:P.923 - P.923
「某検査の学校で病理学の講義を担当し,早くも数回の講義を終えた(本誌49巻7号838頁参照).われわれの講義スタイルは,「授業中に暇はない!」スタンスで,学生に授業内容をレポートに書き込んでもらい,授業の終了時に提出してもらう→評価をつけて,次回の講義時に返却する……という,結構なスパルタ方式にした.つまり,「授業を聴いていないと,後で勉強するにもなんの資料も手元に残らないぞ♥」スタイルだ.無論,「パワポくださ〜い」という抵抗勢力は少なからずあったそうだが,同僚が「絶対に渡しません!」と最後まで折れなかったことで,この方式をいまも続行している(頑張ってくれ,学生たち!).
提出してもらったレポートを見ると,実に素晴らしい.講義を聴きながら,よくぞここまで書けたなぁと感心するほど,びっちり書き込まれている.中には「どうしたのかな?」というレポートもあるが,とりあえず白紙は1枚もない.ある日,同僚が「レポートの評価のために買った♪」と,スタンプを持ってきた.ハムスターやらネコちゃんが「Good!」とか「みました!」という文字とともに笑っているスタンプだ.ご,50代のおっさんがこれを使うのか(←同僚は昔からカワイイ物好き).「これを押してあげようと思うんだよ」と,ご本人も笑っている.「お,おう.学生も喜ぶさ」そう私は呟いた.
書評
国循・天理よろづ印 心エコー読影ドリル【Web動画付】 フリーアクセス
著者: 伊藤浩
ページ範囲:P.924 - P.924
クイズ形式で楽しく心エコーの実力がアップ
私の専門分野は心エコー図法である,以前,病院で心エコー図検査をしていた時,謎解きのような快感を覚えたことが何回もあった,漫然とルーチンの断面を記録しているだけではどんな疾患かわからない,疾患に特徴的な心エコー所見を覚えていた,あるいは画面上のわずかなヒントに気付くことで正解にたどり着くことができた,このような経験である,そのような心エコー図検査ならではの快感を再現しているのが本書である,まさしく“ドリル”である,
単なる正解を求めるクイズ本ではない,本書の特徴は心エコー画像から所見を読ませること,それ自体がクイズである,付録の動画をしっかりと見ないとなかなか正解できない,所見を読み,数値データも参考にしながら,どのような心疾患,どのような病態であるか考えていく,まさに心エコー図検査のプロセスそのものである,「1章 小手調べの20症例!」は誰でも知っているはずの典型的な症例であり,自分のレベルを知ることができる,次の「2章 いよいよ本番の30症例!」は実力試験である,心エコー診断にたどり着くことも大事だが,ぜひ解説を読み込んでいただきたい,各症例の最後にあるLearning Pointを覚えるだけでも十分に勉強になる(本書の末尾には各症例のLearning Pointをまとめたものも掲載されている),
INFORMATION
千里ライフサイエンスセミナーS3—「ライフステージとがん,細胞老化の関与とその治療標的としての可能性」 フリーアクセス
ページ範囲:P.906 - P.906
2021年(第66回)一級臨床検査士資格認定試験受験申請の手引き フリーアクセス
ページ範囲:P.911 - P.911
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.846 - P.847
『臨床検査』8月号のお知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.845 - P.845
医学書院ウェブサイトをご利用ください フリーアクセス
ページ範囲:P.919 - P.919
「ラボクイズ」解答/読者アンケートFAX
ページ範囲:P.925 - P.925
あとがき・次号予告 フリーアクセス
著者: 八鍬恒芳
ページ範囲:P.930 - P.930
週末はすっかり巣ごもり生活になっておりますが,私は最近料理をするようになりました.購入したレシピ本やインターネットの情報から,見よう見まねで作っているのですが,ピザ生地作りなど素材から作っていく料理が特に好きです.コロナ禍なので買い物をする場所も限定されますが,材料を調べて,現地(スーパーなど)に赴き,数ある食材から最適なものを選び,朝からじっくり作り上げていくのはなかなか楽しく気分転換に最適です.料理の全工程は,論文や原稿を作成する作業にも似ており,調理中にいいアイデアが浮かぶこともあります.さて,COVID-19関連での検査技師の仕事は拡大していく一方ですが,なにをやるにしてもしっかりと下調べをし,慎重かつ柔軟に対応していきたいものです.
基本情報
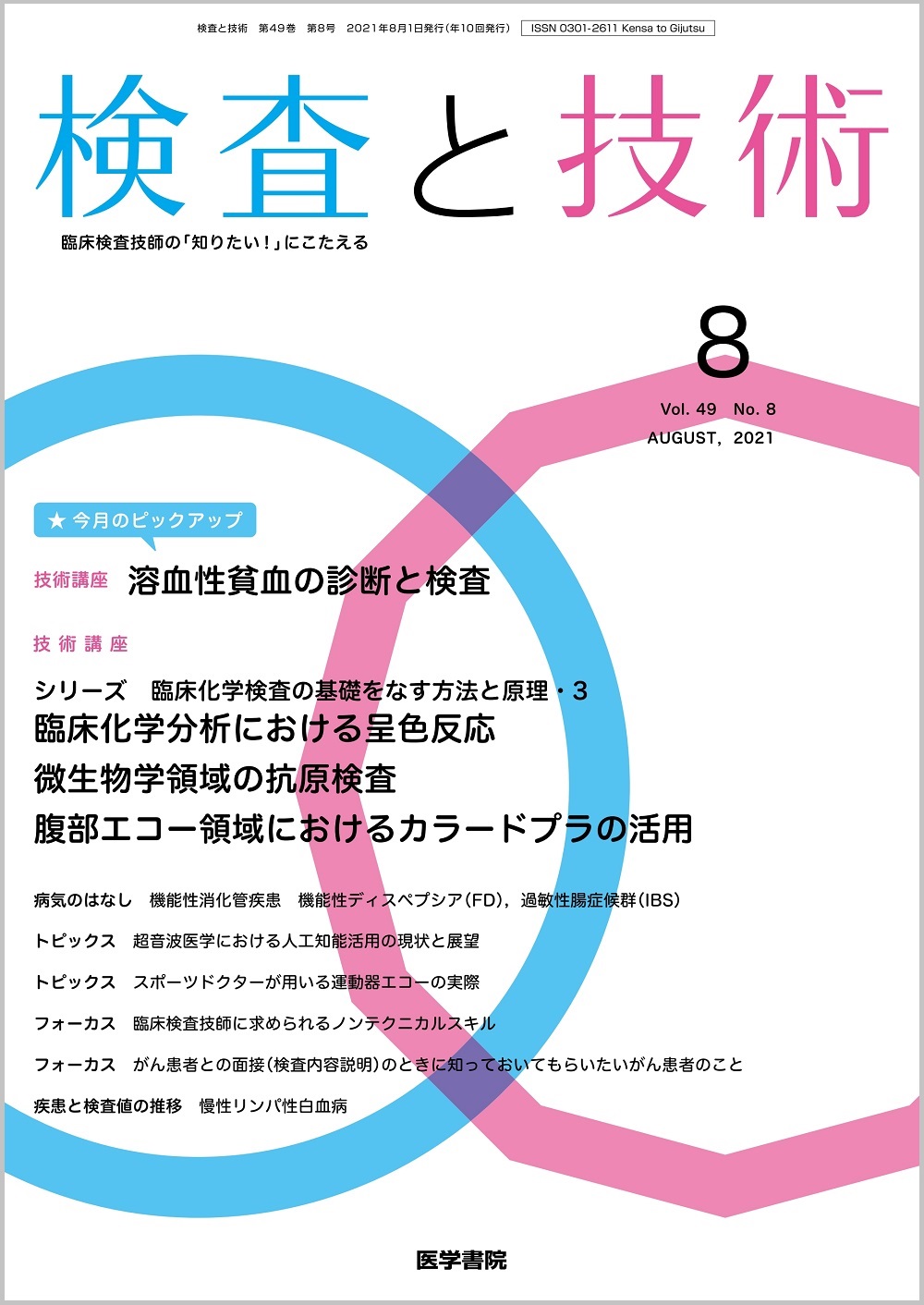
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
