Point
●鉄欠乏性貧血では,ヘモグロビン値の低下,平均赤血球容積(MCV)と平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)の低下(小球性低色素性貧血)に加え,血清鉄の低下,総鉄結合能(TIBC)の上昇,血清フェリチン値の低下を認める.
●妊娠可能年齢にある女性で非常に頻度が高い.悪性腫瘍などを伴うことがあるため,鉄欠乏性貧血と診断した場合は,鉄の補充だけではなく,鉄欠乏をきたした原因の検索を行うことが重要である.
●鉄剤は経口投与が原則である.鉄剤の投与は貧血が改善し,血清フェリチン値が正常化するまで続行する.
●静注鉄剤を使用する場合は,治療開始前に総鉄投与量を計算して鉄過剰症をきたさないようにする.
雑誌目次
検査と技術50巻11号
2022年11月発行
雑誌目次
病気のはなし
鉄欠乏性貧血
著者: 北中明
ページ範囲:P.1212 - P.1217
技術講座 生化学
電気泳動法による異常蛋白の分析および判読の仕方
著者: 藤田清貴
ページ範囲:P.1233 - P.1239
Point
●血清蛋白分画検査(SPE)では,アルブミン分画より幅の狭い蛋白帯が正常の分画と異なる位置にみられた場合,M蛋白を疑う必要があります.
●免疫固定電気泳動法(IFE)では,抗体と抗原の量的比率で濃さが変わることから,形成されるバンドの濃さで目的蛋白の増減を判定することはできません.
●M蛋白は,免疫電気泳動法(IEP)で正常の免疫グロブリンの沈降線とは異なる形態(M-bow)を呈するか,全く新しい沈降線として観察されます.
微生物
微生物検査において病原体の取り扱いに必要なバイオセーフティ
著者: 三澤成毅
ページ範囲:P.1240 - P.1249
Point
●微生物を安全に取り扱うには,微生物の感染性レベルに合わせた感染防御対策であるバイオセーフティが必須となる.
●感染性によるリスク群(1〜4群)と,感染症法に基づく特定病原体等(一〜四種病原体等)の分類を勉強し,ヒトに感染症を起こす微生物について知ることが重要である.
●国内の微生物検査室は,四種病原体等を取り扱うことを前提に,検査室の設備基準に合わせてレイアウトする.
●検査室内感染を防ぐには,設備とともに感染防御に対する知識と技術を,教育と訓練によって習得する.
病理
術中迅速細胞診
著者: 生澤竜
ページ範囲:P.1250 - P.1255
Point
●術中迅速細胞診は術中病理組織診より簡易的で検査時間が短く,補助的な役割を担うことがある.
●適切な標本作製方法や標本の評価には十分なトレーニングが必要である.
●領域によっては事前検査ができないため唯一の細胞診標本となる.
生理
シリーズ エコー検査における緊急報告・2
血管エコー
著者: 湯浅麻美 , 平田有紀奈
ページ範囲:P.1256 - P.1260
Point
●画像所見だけでなく,症状や病歴に応じて緊急度を判断する.
●緊急所見,準緊急所見では“プラスα”で得られる所見についても,評価することを考慮する.
●緊急所見は診断の遅れが生命の危機に直結する病態であり,迅速性を最優先し,不必要な時間をかけないことが重要である.
●エコー検査を始めて間がないうちは,医師に報告する前に上級技師に相談する.
トピックス
超音波検査における肝脂肪化診断
著者: 橋本眞里子 , 飯島尋子
ページ範囲:P.1218 - P.1221
はじめに
近年,メタボリック症候群を背景に,脂肪肝の患者が増加し,特定健診受診者における脂肪肝の割合は25%を超えると報告されている.脂肪肝はアルコール性脂肪肝および非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)に大きく分類され,特にNAFLDの増加が注目されている.NAFLDは病態がほとんど進行しない非アルコール性脂肪肝(nonalcoholic fatty liver:NAFL,以前の単純性脂肪肝)と進行性の非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis:NASH)に分類され,NASHの5〜20%は肝硬変や肝癌の発症母地となることより1)、肝線維化の評価とともに脂肪肝(肝脂肪化)の診断は重要である.
病理学的には従来,30%以上の脂肪変性を認めるものを脂肪肝とし,その拾い上げは,超音波Bモードにおける肝実質輝度上昇,肝腎コントラスト,深部減衰,脈管の不明瞭化による診断(図1,表1)が中心的役割を担い,感度,特異度ともに良好であるが,近年,脂肪肝の定義とされた5%以上の脂肪滴1,2)を診断することは極めて困難である.この問題を解決すべく,超音波の減衰を数値化する方法の開発により肝脂肪化の定量評価が可能となり,2022年4月より保険適用となった.
現時点で超音波減衰法による肝脂肪化診断が可能な定量法には,CAP(controlled attenuation parameter)(Echosens社,フランス),ATI(attenuation imaging)(キヤノンメディカル社),UGAP(ultrasound-guided attenuation parameter)(GEヘルスケア・ジャパン社),ATT(attenuation coefficient)(富士フイルムヘルスケア社)がある.本稿では超音波減衰法による肝脂肪化診断について概説する.
最新のガイドラインに基づく心不全評価—心エコー法による心機能評価の注意点
著者: 駒村和雄
ページ範囲:P.1222 - P.1224
はじめに
“心不全”の定義はガイドライン上,「なんらかの心臓機能障害,すなわち,心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果,呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し,それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」1)とされている.
ここで,“心ポンプ機能”は,心収縮機能および心拡張機能の両方を指すが,心不全の生命予後や治療内容の選択に深くかかわるのは心収縮機能である.本稿では誌面の都合もあり,心収縮機能にかかわる心エコー検査について概説する.
FOCUS
臨床検査部門における医療安全の取り組み
著者: 岩尾舞
ページ範囲:P.1226 - P.1228
慶應義塾大学病院の医療安全管理部
慶應義塾大学病院(以下,当院)の医療安全管理部(以下,院安)では,院内で発生したさまざまな事例についての検証,医療事故調査制度に基づく調査や報告書の作成,提出されたインシデントレポートの分析,構築された再発予防策が適切かどうかのモニタリング,院内マニュアルの新規作成や改定,マニュアル整備などを行っている.
院安は,専属医師2名,専属看護師2名,専属薬剤師1名,事務員5名で構成されている.さらに兼任の医師2名,薬剤師1名,診療放射線技師2名,臨床工学技士1名もメンバーとなっており,毎週提出されるインシデントレポートを多職種で検討するカンファレンスを開催している.この“医療安全管理部医療者間ミーティング”では,インシデントレポート内容の共有に加え,(事例発生部署だけではなく)部門横断的な対応の必要性や,インシデントレポートの背景に潜んでいる体制の問題点がないかどうか,などを多職種の視点から議論している.
臨床検査技師による皮膚,爪の検体採取
著者: 大竹京子
ページ範囲:P.1229 - P.1232
はじめに
平成26(2014)年6月に成立した「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,平成27(2015)年4月1日から臨床検査技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受け,診療の補助として採血に加え,検体採取に関する5つの業務を担うことが認められた.
本稿では,臨床検査技師が検体採取をする有用性,富家病院(以下,当院)での採取するときの工夫,取り組みについて紹介する.
過去問deセルフチェック!
糖尿病の検査
ページ範囲:P.1225 - P.1225
過去の臨床検査技師国家試験にチャレンジして,知識をブラッシュアップしましょう.以下の問題にチャレンジしていただいたあと,別ページの解答と解説をお読みください.
解答と解説
ページ範囲:P.1267 - P.1267
糖尿病への対策がわが国の医療における重要な課題の1つになっていることは言うまでもありません.糖尿病の診療において検査が果たす役割は大きいですが,特に重要なのは,血糖(ブドウ糖)とヘモグロビンA1c(hemoglobin A1c:HbA1c)です.血糖は文字通り,検査した時点での血中ブドウ糖濃度です.一方,HbA1cは全ヘモグロビンに占める糖化ヘモグロビンの割合(%)です.糖化ヘモグロビンは,ヘモグロビンとブドウ糖が非酵素的に結合したもので,血糖値の程度と期間に依存して増加します.HbA1cはこの糖化ヘモグロビンが全ヘモグロビンに占める割合をパーセント(%)で表したものです.いったん糖化したヘモグロビンは,赤血球の寿命(120日)が尽きるまで元には戻りませんので,HbA1cは過去1〜2カ月の血糖値の平均を反映します.
糖尿病の検査を行い,①早朝空腹時血糖値126mg/dL以上,②75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値200mg/dL以上,③随時血糖値200mg/dL以上,④HbA1c 6.5%以上のうち,①〜③のいずれかと④が確認できれば,糖尿病と診断されます.①〜④のいずれか1つだけを認めた場合は“糖尿病型”と診断されます.別の日に再検査を行い,再び“糖尿病型”となれば糖尿病と診断されます.ただし,HbA1cのみのデータで糖尿病の診断を下すことはできません.詳細は,日本糖尿病学会の糖尿病診断基準をご参照ください.なお,糖化アルブミンであるグリコアルブミンは糖尿病の診断には使われません.問題1,2では,この糖尿病診断における検査の基本が問われています.
疾患と検査値の推移
原発性アルドステロン症
著者: 下澤達雄
ページ範囲:P.1262 - P.1266
Point
●原発性アルドステロン症は高血圧のなかでも頻繁に認められる二次性高血圧で,早期発見・早期治療により脳心腎障害を予防できる.
●スクリーニングにはアルドステロン/レニン比が用いられ,その後負荷試験,画像診断,副腎静脈サンプリングにて確定診断と病型分類を行う.
●副腎腫瘤は摘出により速やかにアルドステロン値が低下するのに対し,副腎過形成では内服治療を行うためアルドステロン値は高値を維持する.
臨床検査のピットフォール
強乳びの検体を用いた電解質測定は要注意
著者: 河野正臣
ページ範囲:P.1268 - P.1271
はじめに
食後一過性に血中に増加する脂肪成分〔主にカイロミクロン(chylomicron:CM)により運搬されるトリグリセリド(triglyceride:TG)〕は,リポ蛋白リパーゼ(lipoprotein lipase:LPL)により加水分解されて脂肪酸などに代謝される1).食後,時間を置かずに採血した場合,血液中に残った脂肪成分により血清(血漿)は乳白色を呈する.これを“乳び”という.健常人では経過時間とともに脂肪成分は分解されるため,食後,時間を置いて採血することで乳びを避けることができる.しかし,脂質異常症など血中脂肪成分の高濃度状態が持続している病態では,食後,時間を置いての採血にもかかわらず乳びを呈し,血中脂肪成分の濃度が極めて高い検体においてはミルク状の強乳びとなる.一般的な軽度の乳びは検査に影響を与えることは少ないが,強乳び検体になると検査にさまざまな影響を与える.本稿では,強乳び検体が電解質〔主にナトリウム(natrium:Na)〕測定に与える影響について述べる.
Q&A 読者質問箱
右室自由壁という言葉を参考書でよくみかけるのですが,具体的には心臓のどこの部分なのか,心臓の図を用いて示していただきたいです.
著者: 久武真二
ページ範囲:P.1272 - P.1274
Q 右室自由壁という言葉を参考書でよくみかけるのですが,具体的には心臓のどこの部分なのか,心臓の図を用いて示していただきたいです.
A ヒトの心臓は,2心房2心室の合計4つの心腔で構成されています.そのうちの右側に存在する心室が右室です.
臨床医からの質問に答える
PCRやLAMP法では,核酸抽出は不要ですか?
著者: 南木融
ページ範囲:P.1276 - P.1280
はじめに
現在,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染を調べる遺伝子検査としてはPCR法とLAMP(loop-mediated isothermal amplification)法を用いた検査などがあります.遺伝子検査のなかで最も汎用されているPCR検査は,ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction:PCR)を利用することで,ウイルス由来の特異的な遺伝子配列領域を100〜1,000万倍以上に増幅することができる極めて高感度な分析手法です.
PCR法を用いたSARS-CoV-2の検出には大きく分けると2種類の手法があります.1つは国立感染症研究所が作成した『病原体検出マニュアル2019-nCoV Ver.2.9.1』1)に基づく核酸精製とリアルタイムPCR法(以下,感染研法という)であり,もう1つはRNAの抽出精製が不要で,変性した検体から直接ウイルスRNAの逆転写とリアルタイムPCRを同時に行うことができる方法(直接PCR法)です.本稿では感染研法と直接PCR法についてのメリットとデメリットや検査を正しく行うためのポイントについて解説していきます.
ワンポイントアドバイス
アルギン酸ナトリウムを用いたセルブロック作製法
著者: 加戸伸明
ページ範囲:P.1282 - P.1284
はじめに
Papanicolaou染色標本観察後,同様の標本を作製することが不可能な細胞診検体において,セルブロック法は極めて重要な技術であるといえる.セルブロック法は,平成28(2016)年度に初めて診療報酬点数が認定された後,現在では呼吸器領域や消化器領域,婦人科領域そして悪性リンパ腫と適応対象が拡大され注目を集めている.本稿で紹介するアルギン酸ナトリウム法では,培養細胞を用いた核酸品質の検討も行われている.10%中性緩衝ホルマリンの固定条件に留意する必要があるものの,組織標本と同等の核酸品質や安定した蛋白発現を得ることが可能と報告されており1),がんゲノム医療時代を迎えたわが国において今後セルブロック法の役割がますます大きくなっていくことが予想される.
連載 帰ってきた やなさん。・34
VRを初体験!
著者: 柳田絵美衣
ページ範囲:P.1285 - P.1285
「面白いものを見つけたで」と,帰省するたびに兄が何かを勧めてくる(←そして必ず私も買ってしまう).「一緒に遊ぼう.面白いから!」と,今回,うれしそうに見せてきたのは“VRゲーム”(VRはvirtual realityの略.ゴーグルを装着すると,仮想空間が目の前に広がる)! 数日前に購入したらしく,目をキラキラさせながら誘ってきた.「え〜.VRって乗り物酔いみたいになりそうでイヤ」と渋っていると,私の頭にVRゴーグルをグイグイ装着しはじめ,「これがコントローラーな」と,手に握らせてきた.「ふぁ〜ん」と装置の起動音が聞こえると,視界が…….足元に広がる畳は,左奥10mほど先まで続き,その向こうには庭.庭には“ししおどし”の音の中を優雅に舞う2匹の蛍…….右奥には窓.窓の向こうに,雪化粧をした富士山が見える…….すごい! スタート画面に衝撃を受けていると,「このゲーム,やってみて.まずはEasyモード」と,ゲームをスタートさせる兄.
音楽のリズムに合わせて,次々に現れる敵から放たれる銃弾を避け,コントローラーを敵に向けてボタンを押し,シューティングする……という“リズム”ゲームだ.
書評
—ジェネラリストのための—がん診療ポケットブック フリーアクセス
著者: 渡辺亨
ページ範囲:P.1275 - P.1275
がん診療「ジェネラリスト活躍の時」
二人に一人が罹患するほど,がんは「当たり前の」疾患であり,肺がん,胃がん,大腸がん,乳がん,肝臓がんは,罹患率,死亡率も高く「五大がん」と呼ばれています.他にも前立腺がん,子宮頸がん検診が公費負担されており,卵巣がん,膵臓がん,膀胱がん,食道がんなども,医療者から見て何ら特別な病気ではありません.
がん治療として,最初に発展したのは外科手術,次に放射線治療で,これらは局所治療と分類されます.一方,現在は全身治療として,抗がん剤などの薬物療法が治療の主体を担っており,がん診療を専門としている病院,診療所も全国に多数整備されています.昭和の時代,がん薬物療法を受ける患者は,副作用に苦しみながら数週間入院するのが当たり前でした.しかし,好中球増加因子(G-CSF),制吐剤,抗生剤など,各種の有効な副作用対策薬の開発とともに,モノクローナル抗体薬,ホルモン療法薬,免疫チェックポイント阻害薬など,新しい作用機序を持ち,優れた効果が得られる治療薬が導入され,「外来化学療法室」が専門病院に整備され,今やがんの薬物療法は通院で受ける時代,がんと共に生活を送り,仕事を続ける人が増えています.通院でがん薬物療法を受けている患者は,治療の間に生じる副作用の苦痛,病院を離れている不安などから,頻繁に病院受診を希望しますが,予約が取りにくい,受診しても待ち時間がすごく長い,担当医は手術中で対応できない,偉い先生は学会出張で不在,など必ずしも満足できるとは言えません.一方で,広範囲の診療能力を有する「ジェネラリスト」がかかりつけ医として21世紀の医療を支えています.
医学英語論文 手トリ足トリ いまさら聞けない論文の書きかた フリーアクセス
著者: 戸口田淳也
ページ範囲:P.1281 - P.1281
初めて論文を書く学生のみならず,指導者もお薦め
著者の堀内圭輔先生とは整形外科の臨床における専門領域を共有していることから,以前より親交を深めていただいている.同時に基礎生物学の研究にも従事されていることから,私が編集委員を務めている学術誌に投稿された論文の査読をしばしばご依頼申し上げている.大きな声では言えないが,査読者のreviewの質は,いわゆるピンキリである.その中で著者のreviewは,内容を十分理解した上で,研究の目的は論理的なものであるのか,実験計画に見落としがないのか,結果の解釈は妥当であるのか,そして結論は結果から推定されるものなのかという点について,毎回極めて適切なコメントを頂いている.たとえ最終的な意見がrejectであっても,投稿者にとって有用なアドバイスとなるコメントをcomfortable Englishで提示され,いつも敬服していた.本書を一読して,なるほど論文を書くということに対して,このような確固たる姿勢を持っておられるから,あのようなreview commentが書けるのだと納得した次第である.
著者が述べているように,学術論文とは情報を他者と共有するためのツールである.SNSを介しての情報共有と異なる点は,情報の質,信頼性に関して,複数の専門家が内容を吟味した上で公開されることである.そして公開された情報に基づいてさらに深く,あるいは広く研究が行われ,その成果が再び学術論文として公開されていく.つまり学術論文を書くということは,小さな歩みであるかもしれないが,科学の進歩に貢献するということであり,自分の発見したことを,わくわくする気持ちで文章にするということである(私の大学院生時代のボスは,Nature誌に単独著者でI foundで始まる論文を書かれていた!).
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1210 - P.1211
『臨床検査』11月号のお知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.1209 - P.1209
「ラボクイズ」解答/読者アンケートFAX
ページ範囲:P.1289 - P.1289
あとがき・次号予告 フリーアクセス
著者: 大楠清文
ページ範囲:P.1292 - P.1292
この「あとがき」を9月下旬に書いておりますが,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の第7波が収束しつつあります.本号がお手元に届く頃にはさらに感染者数が減少していることを心から願っております.
さて,「今月のピックアップ」は,技術講座「微生物検査において病原体の取り扱いに必要なバイオセーフティ」としました.コロナ禍において,SARS-CoV-2の抗原検査や遺伝子検査では,微生物検査に携わる検査技師だけでなく,さまざまな検査分野の検査技師が日勤や夜勤等で従事していることと思います.バイオセーフティでは,病原体の安全取扱い技術や管理規則の設定といったソフト面と,施設や設備基準のようなハード面の,両面からの対策が重要です.本記事では,国立感染症研究所によるBSLや感染症法による設備基準との互いの関連性を含めて,核酸増幅検査や抗酸菌検査も行うことを想定した微生物検査室の一例も提示していただいています.さらには,検査室内のゾーニング,個人防護具(PPE)の使用,基本操作など押さえておくべき知識や技術のポイントが端的にわかりやすく解説されています.ぜひ,本稿をお読みいただき,バイオセーフティの原理・原則を十分に理解した上で,自施設の検査室に即応したバイオハザード対策の構築と教育や訓練に役立てていただければと思います.
基本情報
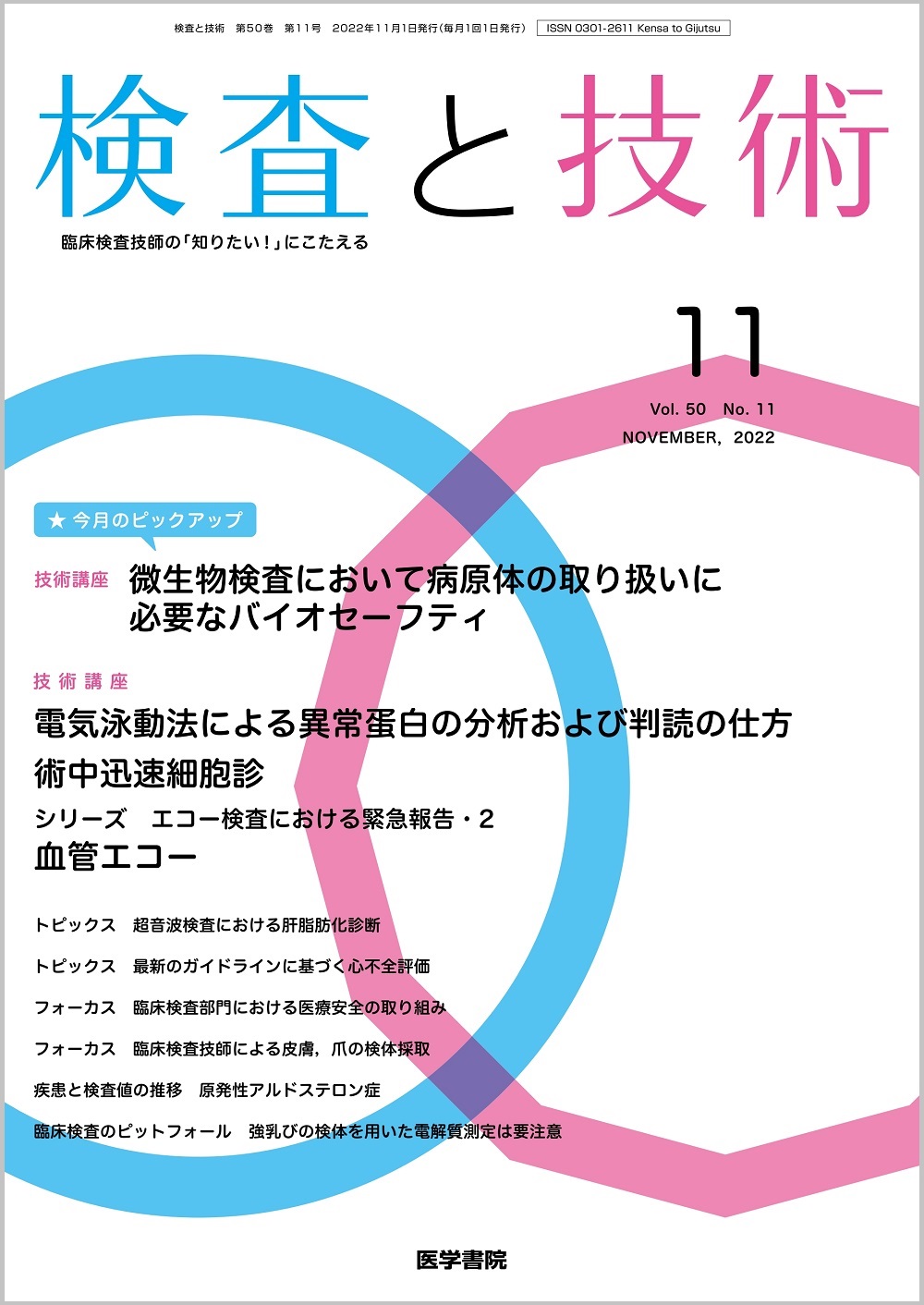
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
