Point
●近年,自己免疫性肝炎(AIH)の患者数は増加しており,ステロイドが奏効する一方で適切な治療がなされないと肝硬変や肝不全に至る.そのため適切な診断と治療が必要である.
●確実な診断を行うために診断基準および典型的な検査所見を把握すること,および治療についての基本的な知識を身につけることは重要である.
●本稿では,AIHの診断・治療についての基本的な事項を中心に述べる.
雑誌目次
検査と技術50巻6号
2022年06月発行
雑誌目次
病気のはなし
自己免疫性肝炎
著者: 松井哲平 , 和久井紀貴 , 永井英成
ページ範囲:P.574 - P.579
技術講座 生化学
持続血糖モニタリング
著者: 佐藤亜位
ページ範囲:P.598 - P.605
Point
●持続血糖モニタリング(CGM)とは,糖尿病治療において近年用いられるようになった検査手法であり,それに基づいた新しい血糖コントロール指標が示されています.
●いままでの検査手法ではわからなかった低血糖を含めた血糖値の変動を目で見て確認することができます.
●主にインスリン療法を行っている1型糖尿病患者に使用されていますが,2型糖尿病にも適応は広がっています.
●値の誤差やタイムラグはありますが,その特性を理解して使用することで患者のQOL,血糖コントロールの改善に有用とされています.
血液
造血器腫瘍細胞の検出—自動血球分析装置のスキャッターとの関連
著者: 井上まどか
ページ範囲:P.606 - P.610
Point
●現在の自動血球分析装置は,正常の白血球分画だけでなく,幼若細胞,異常細胞(白血病細胞,リンパ腫細胞など),異型リンパ球,有核赤血球などの検出が可能なまでに進化している.
●白血球分画を得るためのスキャッターを確認することで異常細胞の存在に気付く場合もあるため,スキャッターを確認することは重要である.
●その一方で,スキャッターや自動血球分析装置からのフラグだけでは気付けない場合もあることを知っておく必要がある.
●自分が使用する自動血球分析装置の測定原理やスキャッター,強み・弱みも理解したうえで日常検査を行う必要があると考えられる.
生理
心臓超音波検査—伝わるレポートの作成と伝達方法
著者: 大沼秀知
ページ範囲:P.612 - P.619
Point
●計測値の羅列では診断につながりません.依頼内容から臨床医の“ここを見てほしい”を考え,どの評価法,どの画像が診断に有用か整理して心臓超音波検査(心エコー図検査)を進めましょう.
●“心エコー診断が身体所見と合わない”,“診断を裏付ける客観的数値などが記載されていない”,“特徴的な所見を満たしていない”,このようなレポートは信用されません.
●心エコー図検査で使用する計算式はさまざまな仮定や法則のうえに成り立っています.測定原理,測定限界を理解して正しいデータを報告しましょう.
●心機能の指標に絶対のものはありません.検査中/検査後に算出した値が修飾されていないか考える“クセ”をつけましょう.
●心エコー図とレポートは検査室の“モノ”ではありません.相手に伝わって初めて生かされる情報です.
トピックス
新型コロナウイルス変異株解析のルーチン化,その現況
著者: 溝口美祐紀
ページ範囲:P.580 - P.584
はじめに
新型コロナウイルス(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2:SARS-CoV-2)が2019年12月に中華人民共和国湖北省武漢市で検出されて以来,世界的感染拡大を続けている.2020年11月に英国で変異株(アルファ株:B.1.1.7)が報告され,2021年11月にオミクロン株(B.1.1.529)が国立感染症研究所(National Institute of Infectious Diseases:NIID)によって懸念される変異株(variant of concern:VOC)と位置付けられ,監視体制の強化が開始されている.
血液検査領域における人工知能(AI)の導入
著者: 松井啓隆
ページ範囲:P.586 - P.589
はじめに
ある日の外来に,倦怠感を訴える患者が来院したとする.この患者に対して血液検査を行ったところ,自動血球計数装置からは,白血球数の増加と未熟白血球の存在,貧血,血小板減少を示す数値が得られた.また,同時に行った生化学検査からは,乳酸脱水素酵素(lactate dehydrogenase:LD)と尿酸値の増加,C反応性蛋白(C-reactive protein:CRP)の高値が報告された.これを見た臨床検査技師は造血器腫瘍を疑い,末梢血塗抹標本を作製してギムザ(Giemsa)染色標本の顕微鏡観察を行ったところ,やはり骨髄芽球と顆粒球の形態異常が認められたため,血液内科医に報告した.報告を受けた血液内科医は骨髄穿刺を行い,ギムザ染色に加え,ペルオキシダーゼ染色やエステラーゼ染色などの特殊染色も実施するよう指示した.さらに,血液細胞の表面抗原解析と染色体分析も提出した.これら一連の検査データから急性骨髄性白血病であると診断し,今後の造血幹細胞移植の必要性も視野に入れつつ,寛解導入療法を開始した.
こうした一連の検査・診断は,今もって医師や臨床検査技師の経験と勘に依存するところが大きい.なぜなら,いずれのプロセスも,まず疑わないことには次の段階に進まないからである.倦怠感を単なる疲労と捉え,患者を帰してしまえば白血球数の異常増加も知りようがないし,仮に血液検査を行ったとしても,LDや尿酸値が上昇していることの意義を解釈できなければ,細菌感染症と診断して抗菌薬投与のみで終えてしまうかもしれない.
こうしたなか,現在,血液疾患を含むあらゆる分野において,機械学習(machine learning)を取り入れた疾患の診断や予後予測システムの開発が行われ,見逃しを防ぎ適切な医療介入を行うための取り組みが続けられている.本稿では,人工知能(artificial intelligence:AI)や機械学習の概念を解説し,最近の血液検査領域からの論文を引用しながら,血液検査領域における機械学習装置の活用について紹介する.
FOCUS
急性膵炎の診断—尿中トリプシノーゲン2
著者: 北川元二
ページ範囲:P.590 - P.593
はじめに
急性膵炎の致命率は近年著明に改善しているが,2016年の全国疫学調査では急性膵炎全体で1.8%,重症急性膵炎で6.1%といまだ死亡例が存在していることが大きな課題である.急性膵炎の重症化率・死亡率の改善には,発症早期に診断し治療を開始することが最も重要である.急性膵炎の診療において有効性が明らかになっている早期に実施すべき診療行為を列挙した“Pancreatitis Bundle 2021”では,発症後48時間以内に診断し,重症度に応じたモニタリングを行うことが挙げられている1).腹痛を主訴とする原因疾患は多岐にわたるが,そのなかに急性膵炎が含まれる.血中・尿中膵酵素の値が上昇していれば,急性膵炎を強く疑うことになるが,鑑別診断に苦慮する場合も少なくない.
急性膵炎を迅速・簡便に診断することが可能であり,他の血中膵酵素測定と比較して同等の精度を有する“尿中トリプシノーゲン2”の測定検査が開発され2),わが国でも2020年11月1日より保険適用となった.本稿では,「急性膵炎診療ガイドライン2021」1)を踏まえて,尿中トリプシノーゲン2の測定意義について述べる.
心臓移植におけるエベロリムスの役割
著者: 木村祐樹 , 奥村貴裕 , 室原豊明
ページ範囲:P.594 - P.597
はじめに
平成21(2009)年に「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」が改正されて以降,わが国における心臓移植の件数は年々増加し,2019年度には年間79例に到達した.コロナ禍においてもドナー患者・家族のご協力や日本臓器移植ネットワークをはじめとした関連団体・施設の努力により,2020年度も約50例の心臓移植を行うことができており,心臓移植は重症心不全患者に対する確立した治療となっている.
日本での心臓移植の成績は10年生存率89.3%と世界と比較しても極めて良好である1).心臓移植後の死因として,移植後早期は拒絶反応と感染症が重要であるが,遠隔期には悪性腫瘍,移植心冠動脈病変,腎不全の割合が増加してくる(図1)2).長期の生存率を維持するためには,急性期だけではなく遠隔期の合併症を意識した免疫抑制療法が必要である.
この課題を解決するうえで,エベロリムスは非常に重要な存在となっている.2007年1月に承認されたエベロリムスは,細胞質内のFK506結合蛋白と複合体を形成し,哺乳類ラパマイシン標的蛋白質(mammalian target of rapamycin:mTOR)に結合することにより,造血細胞(T細胞,B細胞),血管平滑筋細胞,酵母などで細胞周期をG1期で停止させることで効果を発揮する1).エベロリムスにはカルシニューリン阻害薬による腎機能障害の抑制に加え,移植心冠動脈病変の抑制や抗腫瘍効果など特有な効果が報告されている3).そのため,国立循環器病研究センターの報告では心臓移植後1年において65%の患者でエベロリムスが併用されており4),当院においても67%(6/9例)の患者でエベロリムスの併用を行っている.
本稿では,心臓移植におけるエベロリムスの使用方法や役割,問題点に関して概説する.
過去問deセルフチェック!
甲状腺超音波検査の基本
ページ範囲:P.585 - P.585
過去の臨床検査技師国家試験にチャレンジして,知識をブラッシュアップしましょう.以下の問題にチャレンジしていただいたあと,別ページの解答と解説をお読みください.
解答と解説
ページ範囲:P.611 - P.611
超音波像における甲状腺と周囲臓器および主な甲状腺病変の特徴を覚えておくとよい.甲状腺の横断像では,甲状腺に囲まれるように気管(問題1③)が位置し,甲状腺の外側には甲状腺近傍から順に総頸動脈(問題1②),内頸静脈(問題1①),頸部リンパ節などが描出される.気管の後方やや左側には食道(問題1④)の一部が描出されることが多い.副甲状腺は腫大すれば甲状腺に接して描出される.超音波像における甲状腺病態の特徴を記す.
疾患と検査値の推移
慢性膵炎
著者: 佐久間文 , 入澤篤志
ページ範囲:P.620 - P.627
Point
●慢性膵炎は上腹部痛や背部痛を主訴とし,長い年月をかけて膵臓の線維化が進行する疾患である.非代償期では内分泌機能低下による糖尿病や,外分泌機能低下による消化吸収障害や下痢が生じる.
●慢性膵炎の診断は,特徴的な画像所見や膵酵素異常などの検査所見,腹痛などの臨床症候の組み合わせから行う.
●BT-PABA試験はわが国で施行可能な膵外分泌機能の評価法であるが,薬剤や合併疾患により異常値を呈することがあり,膵疾患に特異的ではないことに留意する.
●慢性膵炎は膵発癌のリスク因子であり,血液検査や画像検査などで注意深く経過観察する必要がある.
臨床医からの質問に答える
アメーバ性虫垂炎の診断のポイントを教えてください.
著者: 渡辺恒二
ページ範囲:P.628 - P.631
赤痢アメーバ症とアメーバ性虫垂炎
赤痢アメーバ症は,赤痢アメーバ(Entamoeba histolytica)による感染症(腸管寄生虫症)である.赤痢アメーバは,体外環境中でも長期間安定しているシスト(囊子)型と,ヒトの体内で大腸組織を破壊する栄養型の2つの形態を有する.外部環境もしくは他の感染者から直接的に,シスト型赤痢アメーバを経口的に摂取することにより感染伝播が起こる.経口摂取されたシスト型赤痢アメーバは,胃や小腸などの強酸または強アルカリの環境を通過し,大腸に達すると栄養型赤痢アメーバに脱嚢する.栄養型赤痢アメーバの表面にある接着因子(レクチン)を介して,ヒトの大腸粘膜表面のムチンに接着することで感染が成立する.
大腸に感染を起こした栄養型赤痢アメーバは粘膜下組織に侵入し,下痢や血便などの腸炎(アメーバ性腸炎),血管への浸潤が起こると血流を介して肝膿瘍(アメーバ性肝膿瘍)などの病気を引き起こす.アメーバ性腸炎やアメーバ性肝膿瘍など,赤痢アメーバによる侵襲性感染症をアメーバ赤痢と呼ぶ(図1).
臨床検査のピットフォール
血中タクロリムス濃度測定の検査前プロセスを意識していますか?
著者: 度會理佳 , 菊地良介
ページ範囲:P.632 - P.634
はじめに
世界保健機関(World Health Organization:WHO)では,1987年の総会において臓器移植のガイドライン制定を実施することが決議され,1991年に「移植ガイドライン」が制定された.この決議を受けて,1990年代後半には多くの国々で臓器移植のための法律が制定され,実際に臓器移植が実施されてきた.
わが国における2019年の全臓器移植件数は2,680件,そのうち腎臓移植が2,057件,肝臓移植が395件である1).腎移植の2,057件のうち,生体腎移植が1,827件(88.8%)と大部分を占めている.最近では親子間より夫婦間での腎移植が多くなってきており,また生体腎移植全体としては血液型不適合移植が増加している.肝移植に関しては,2019年末までに実施された件数は成人・小児を合わせて10,038例あり,年間で約400例程度の肝移植が実施されている.移植には拒絶反応のコントロールが必須であり,そのためにさまざまな種類の免疫抑制剤を組み合わせて免疫抑制療法が実施されている.
臨床検査の過程には,検査前プロセス・検査プロセス・検査後プロセスの3過程があり,これらを遵守することで臨床検査の品質を保証している.検査前プロセスとは,検査に提供される前の検体の採取や搬送などの過程のことである.検体検査では,例えば採血管の不一致,検体凝固,輸液混入,検体放置などがこの過程のトラブルに該当し,検査結果の誤った解釈につながる.信頼できる検査結果を得るために,検査室は検査前プロセスを厳重に管理し,適切な状態で検査を行うことが非常に重要である.
本稿では免疫抑制剤,主にタクロリムスについてと血中薬物濃度測定における検査前プロセスの重要性について紹介する.
Q&A 読者質問箱
乳び検体を測定する際の注意点や,濁度との関係について教えてください.
著者: 清宮正徳
ページ範囲:P.635 - P.637
Q 乳び検体を測定する際の注意点や,濁度との関係について教えてください.
A 自動分析装置から検体ごとの溶血・黄疸・乳び指数が出力されますが,これらの指数には明確な基準がなく,装置メーカーや機種によって出力値が異なります.特に乳びについては標準物質がありません.乳びが認められる場合は中性脂肪(triglyceride:TG)濃度が高値ですが,TGが高くても乳びを認めない症例も多く存在します.また,極端に強い乳び検体(ミルク状)では後述する容積置換現象に対応する必要があります.
ワンポイントアドバイス
リアルタイムPCRに用いられるクエンチャーの種類と使い分け
著者: 松田和之
ページ範囲:P.638 - P.640
はじめに
新型コロナウイルス遺伝子検査にも応用されている反応がリアルタイムPCR(polymerase chain reaction)である.リアルタイムPCRの手法の1つがポリメラーゼの5’-3’エキソヌクレアーゼ活性(5’末端から3’末端の方向にホスホジエステル結合を加水分解)を利用した加水分解プローブ法である1).これは,蛍光物質とクエンチャーで標識したdual-labeledプローブを用いた方法であり,いわゆるTaqManプローブ法とも呼ばれる.プローブの両末端に標識された蛍光物質とクエンチャーの間での蛍光共鳴エネルギー移動(fluorescence resonance energy transfer:FRET)により,加水分解されていないプローブでは蛍光物質からの蛍光が抑制(クエンチング)され,プローブが加水分解されるとFRETが起こらず,蛍光物質からの蛍光が検出される2,3).
連載 帰ってきた やなさん。・30
始まる前から……
著者: 柳田絵美衣
ページ範囲:P.641 - P.641
春! それは,“始まり”の季節.今年の春は,柳田も始まるのです.大学院(博士課程)が.人見知りをする柳田は友だちを作るスキルが絶望的に低いため,博士課程でも学友を作れないだろうと思っていた.しかし! なんとっ! 仲良しの病理技師も一緒に入学となったのだ.地元(兵庫)にいた頃からずっと応援してくださっていて,しかも母校である神戸常盤短期大学(現・神戸常盤大学)の先輩! 心強すぎる.しかし,入学前から2人で不安いっぱいなのである.
柳田は勤務先の大学に社会人大学院制度がないため,博士課程も学外の大学に入学を決めた.修士課程も違う学校だったのだが,出席日数が足りず,学生課に呼び出されて「ヤル気あるんですかねぇ!? えぇ〜!?」と叱られ,通常よりも1年長く遠回りをして修士課程を修了した〔大人になっても,あんな叱られ方するんだね(本誌49巻6号711頁)〕.そんなこともあり,博士課程は“落ちこぼれない”,“叱られない”を目標に掲げ,ヤル気にみなぎっていた(←落ちこぼれない,叱られないは最低レベルだろ……).
書評
誰も教えてくれなかった皮疹の診かた・考えかた[Web動画付] フリーアクセス
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.683 - P.683
良い本.買ったほうがいい.
さて書評である.
この本の書評は難しい.なぜならとても良い本だからだ.
トップジャーナルに学ぶ センスのいい科学英語論文の書き方 フリーアクセス
著者: 倉本秋
ページ範囲:P.684 - P.684
language barrierに苦しんだ,若き日の自分に贈りたい一冊
本書の著者であるジャンさんとの出会いは,1980年代後半までさかのぼる.当時私が勤務していた東大病院分院の助教授から,ジャンさんを紹介された.知り合って10年間は,2週間に1回程度おしゃべりの機会を持ち,論文ができたら校閲してもらっていた.その後,私の職場は高知大,そして高知医療再生機構へと変わったが,投稿論文は全てジャンさんの手を経ており,今では機構が販売する学内委員会Web審査システムの英文マニュアルまで校正をお願いしている.
今回,『トップジャーナルに学ぶ センスのいい科学英語論文の書き方』を読み進めながら,30年以上前にレトロな東大分院の建物で教えてもらっていたことは,ステップⅠの「英語のマインドをつくる」に述べられている内容であったと気付いた.確かに,科学論文を書こうとする日本人は皆,英作文はできる.しかし残念なことに,「(日本の)学校英文法」とは似て非なる,「英文」を構成する法則,コンセプトの理解は欠落している.native speaker(以下,native)が学ぶようなparagraph writingの概念を教える授業は,日本にはないからである.そこをすっ飛ばして中学から大学まで英語を学んだ若い研究者たちは,卒前,あるいは卒後しばらくして初めての論文を完成させる.「事実は現在形で」とか,「受動態は少なめがよい」とかいう先輩の指示だけを道標に.“paragraph”を日本語の「段落」に置き換えただけの頭では,「ミニエッセイ風」などの構成は思いも至らない.このような前提を知らないと,nativeのproofreadを受け取ったとき,その朱字を許容し難い場合がある.nativeも,日本人の文の順序や改行を怪訝に思いながら,校正と格闘する羽目になる.
INFORMATION
一級臨床検査士資格認定試験 フリーアクセス
ページ範囲:P.584 - P.584
2022年(第38回)「緒方富雄賞」候補者推薦のお願い フリーアクセス
ページ範囲:P.597 - P.597
POCT測定認定士資格認定試験 フリーアクセス
ページ範囲:P.640 - P.640
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.572 - P.573
『臨床検査』6月号のお知らせ フリーアクセス
ページ範囲:P.571 - P.571
医学書院ウェブサイトをご利用ください フリーアクセス
ページ範囲:P.593 - P.593
「ラボクイズ」解答/読者アンケートFAX
ページ範囲:P.685 - P.685
あとがき・次号予告 フリーアクセス
著者: 大楠清文
ページ範囲:P.690 - P.690
本号には「第68回臨床検査技師国家試験」の解答と解説が掲載されています.3月23日の合格発表によれば,新卒は4,092名受験して3,537名の合格で,合格率は昨年よりも5.2%ダウンして86.4%,既卒を含めると3,729名の合格,合格率75.4%でした.2年以上にわたる新型コロナウイルス感染症の影響を受けて,入構制限や対面授業の中止などで受験勉強は困難と苦労の連続であったことと思います.合格された皆さま,本当におめでとうございます.
2015年にオックスフォード大学と野村総合研究所によって「20年後までに日本の仕事の約50%が人工知能やロボット等で代替可能になる」との見通しが公表され,AI(人工知能)の技術の発展によって“なくなる仕事(代替可能性が高い)”と“残る仕事(代替可能性が低い)”が話題となり,おのおの100種類の仕事が列記されましたが,“臨床検査技師”はどちらにも含まれていませんでした.その本質として,まさしく言い得て妙な提言が2019年に日本臨床衛生検査技師会「臨床検査技師あり方推進ワーキンググループ」から公表されています.『AIはあくまで「道具」であり「道具」には必ず「使う人」が必要となる.つまりAIは我々にとって仕事を奪う「脅威」ではなく,人間と「共存」していく存在となっていくと予想する.実際の医療現場では患者を中心としての業務であり,複雑な表現を交えたコミュニケーションが必要であるが,臨床検査技師がこれからのAI時代を生き残るためにはAIを活用できる人材の育成を急ぎ,AIと共に「コミュニケーション力」を磨き患者の近い場所で業務を実践し,他医療職に信頼される職種になっていくことが必要と考える』.
基本情報
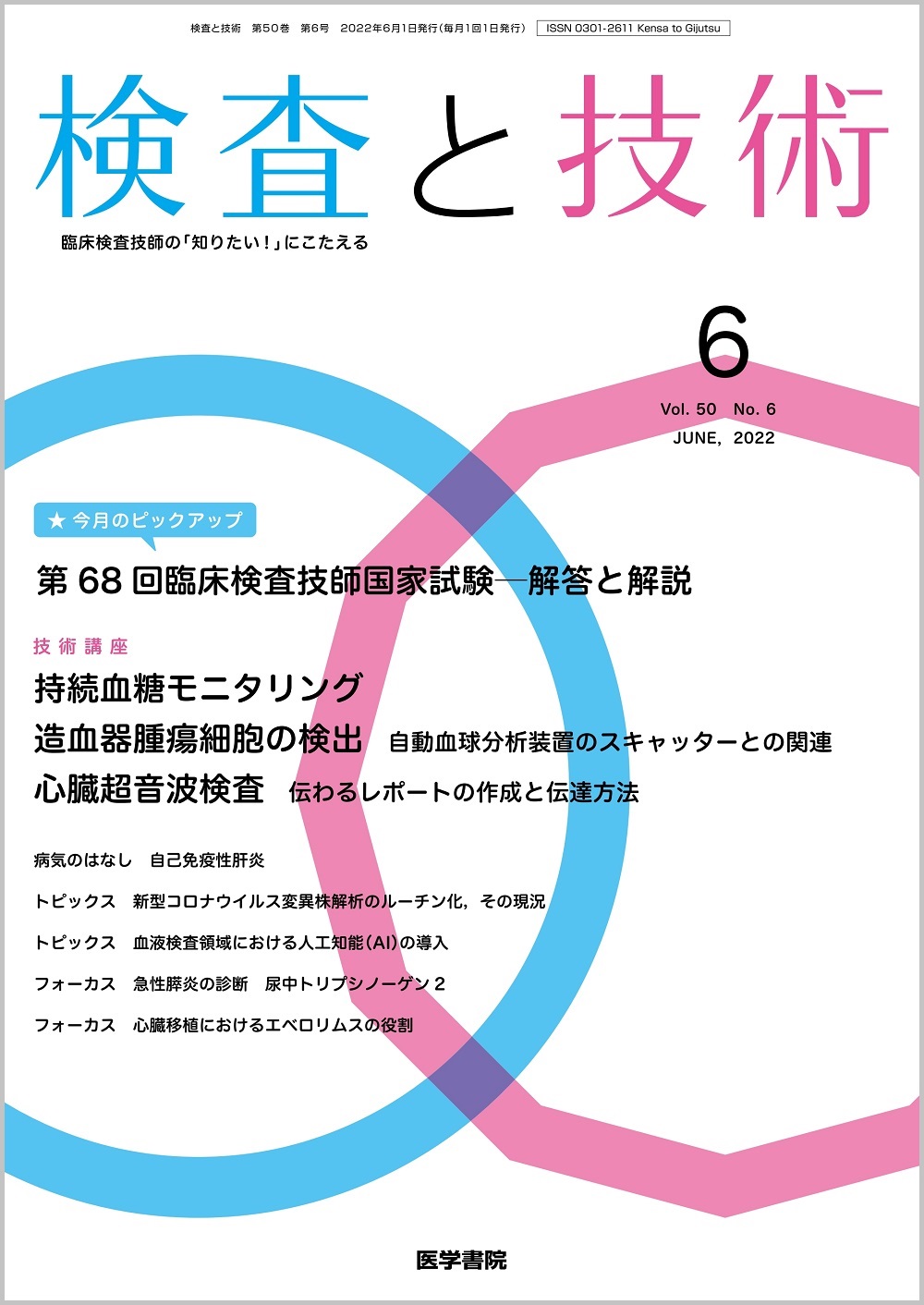
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
