『検査と技術』増大号『症例から学ぶ—疾患と検査値の推移』をお届けします.本企画は,『検査と技術』誌において長年掲載され,好評をいただいております「疾患と検査値の推移」欄を基に,増大号として再編集したものです.
臨床検査が医療の根幹を成すことは誰もが認めるところです.そして,チーム医療が何より重要である現在,検査室からの検査データを通した診療側への情報発信が大変大きな意味を持ちます.検査室では,検査データを通して患者さんの医学的状況を診ることになりますが,治療を含め,実臨床でどのようなことがなされ,それが検査値にどのような影響を与えるかを検査に携わる者も認識することで,検査側からより適切な情報発信が可能になります.本増大号『症例から学ぶ—疾患と検査値の推移』においては,代表的な疾患を選び,疾患の説明をするだけでなく,実際の治療等の経過を追う過程での検査値の推移がまとめられています.診療場面における,この検査データのダイナミックな推移を知ることにより,検査に携わる者も,より深い検査データの読みが可能となり,さらに有益な診療現場へのフィードバックが可能になります.
雑誌目次
検査と技術51巻3号
2023年03月発行
雑誌目次
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
はじめに フリーアクセス
著者: 矢冨裕
ページ範囲:P.177 - P.177
1章 消化器疾患
急性肝炎
著者: 篠原美絵 , 石井耕司
ページ範囲:P.180 - P.187
Point
●急性肝炎とは主に肝炎ウイルスが原因で起きる急性のびまん性疾患で,肝炎ウイルスにはA型,B型,C型,D型,E型の5種類がある.
●通常では急性感染の場合,A型,E型は一過性感染であるが,C型(約70%)やB型,D型の一部では慢性化することがある.
●初発症状は倦怠感,食欲低下,微熱などの非特異的症状が多い.著明な黄疸や意識障害がみられる場合には重症化に注意する.
●急性肝炎の約90%は自然治癒し予後はよいが,1〜2%は劇症化するため注意が必要である.
肝硬変
著者: 影山憲貴
ページ範囲:P.188 - P.195
Point
●肝硬変とは慢性肝障害が進行して肝細胞が壊死と再生を繰り返す過程で,肝線維化や類洞の毛細血管化が生じて肝臓が硬く変化した状態であり,肝機能が低下している.また,病理組織学的に明確な概念規定がある.
●肝硬変の原因は,C型肝炎ウイルス(HCV)・B型肝炎ウイルス(HBV)が全体の約60%を占め,次いでアルコール性が約20%を占める.ウイルス性は減少傾向を示し,アルコール性は増加傾向を示している.
●機能的な分類として,代償性(自覚症状に乏しい)と非代償性(さまざまな自覚症状を認める)に区別する.
●確定診断は肝生検による組織診断であるが,一般的には血液検査所見,画像所見,臨床症状などから総合的に判断し診断される.
●肝硬変が進行した際の主な合併症は肝不全,門脈圧亢進症,消化管出血,肝細胞癌の発生である.また,肝不全の主な徴候は肝性脳症,腹水,浮腫,黄疸である.
肝癌
著者: 今村潤
ページ範囲:P.196 - P.201
Point
●肝癌は主に肝細胞癌を指し,慢性肝炎・肝硬変などなんらかの肝疾患を背景に発生するという特徴をもつ.
●治療法は種々あり,腫瘍の状態および肝機能を考慮して決められるため,検査値が重要となる.
●肝機能を評価するために,血清アルブミン,血清ビリルビン,プロトロンビン活性の測定は必須である.
●病勢および治療効果の評価のために,腫瘍マーカーであるα-フェトプロテイン(AFP)とPIVKA-Ⅱが用いられており,大変役立つ.
自己免疫性肝炎
著者: 小池和彦
ページ範囲:P.202 - P.209
Point
●自己免疫性肝炎(AIH)の病因は不明であるが,肝障害の発症と病態の進展にはなんらかの自己免疫機序の関与が想定されている.
●肝炎ウイルス検査が陰性であり,さらに免疫グロブリンの上昇や抗核抗体(ANA),抗平滑筋抗体(ASMA),抗LKM-1抗体などの自己抗体が陽性となることが特徴の肝障害である.
●出現する自己抗体の種類によって病型が分類され,病型により副腎皮質ステロイド治療の反応性,臨床像や予後が異なる.
●適切な診断のもと副腎皮質ステロイド治療を行えば,わが国の多くの症例の予後は良好である.
急性膵炎
著者: 辻喜久
ページ範囲:P.210 - P.215
Point
●急性膵炎は重症化した場合,死亡率は現在でも決して低くない.
●予後を改善するためには,正確な診断と重症度評価に基づき,適切な初期治療をできるだけ早く開始することが重要と考えられている.
●発症早期の正確な重症化予測は容易ではない場合も多い.
●急性膵炎患者の多くは若い働き盛りの男女であり,悲惨な予後を回避するために,医療関係者の不断の努力が必要である.
2章 血液・造血器疾患
鉄欠乏性貧血
著者: 鈴木隆浩
ページ範囲:P.216 - P.220
Point
●鉄欠乏性貧血(IDA)は体内鉄絶対量の減少によって発症する貧血であり,貧血の原因として最も頻度が高い.
●血清鉄の低下,不飽和鉄結合能(UIBC)の増加,血清フェリチンの低下を伴う小球性低色素性貧血が認められるが,血清フェリチンの低下が最も重要な所見である.
●注意すべき鑑別疾患に慢性疾患に伴う貧血(ACD)があり,IDAとは血清フェリチンで鑑別される.
●IDAでは軽度の血小板増加がしばしば認められる.
二次性貧血
著者: 和田秀穂 , 竹内麻子
ページ範囲:P.221 - P.226
Point
●二次性貧血は,血液・造血器疾患以外の基礎疾患により二次性に生じた貧血の総称である.
●慢性疾患ではしばしば出血などの明らかな原因を認められない小球性〜正球性の貧血がみられ,慢性疾患に伴う貧血(ACD)と呼ばれる.
●慢性腎臓病(CKD)では,腎臓におけるエリスロポエチン(EPO)産生能の低下が主な原因となり,腎性貧血を呈する.
●基礎疾患のコントロールが最善の治療である.
成人T細胞白血病・リンパ腫
著者: 長谷川寛雄
ページ範囲:P.227 - P.232
Point
●成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)は難治性の白血病・リンパ腫である.その病態は多彩であり,病態によって注目すべき検査値も変わりうる.
●診断,病型,予後の判断のために(異常)リンパ球数,LD,UN,Alb,補正カルシウム(Ca)値が必要である.
●非ホジキンリンパ腫全般にマーカーとして使用されている可溶性インターロイキン-2受容体(sIL-2R)は本疾患の病態の変化の把握に大変役立つ.
播種性血管内凝固
著者: 窓岩清治
ページ範囲:P.233 - P.239
Point
●播種性血管内凝固(DIC)は,固形がんや造血器腫瘍,感染症などが主な原因となり,血液凝固系が過度に活性化された病態である.
●DICをきたす基礎疾患が線維素溶解系(線溶系)にも影響を及ぼすために,DICの病態が修飾される.
●DICの診断には,血小板数や凝固線溶一般検査に加えて,トロンビン−アンチトロンビン複合体(TAT)や可溶性フィブリン(SF)などの凝固系分子マーカーが用いられる.
●プラスミン-α2-プラスミンインヒビター複合体(PIC)や,プラスミノゲンアクチベータインヒビター-1(PAI-1),白血球エラスターゼによる架橋化フィブリン分解産物(e-XDP)などの分子マーカーは,DICの病型や生命予後を予測するうえで有用である.
多発性骨髄腫
著者: 笠松哲光 , 齋藤貴之 , 村上博和
ページ範囲:P.240 - P.245
Point
●多発性骨髄腫の診断には,血液・尿検査以外に画像診断が必須である.
●予後予測には主に国際病期分類(ISS)が用いられ,血清アルブミンおよびβ2-ミクログロブリン測定が必要である.
●改訂版ISSでは,高リスク染色体異常と血清LDHの測定が加わっている.
●治療効果判定には,M蛋白量のみならず,骨髄検査および画像診断が必須である.
再生不良性貧血
著者: 臼杵憲祐
ページ範囲:P.246 - P.252
Point
●再生不良性貧血は,造血幹細胞が減少して,骨髄の低形成と汎血球減少を呈する症候群である.
●特発性と二次性の薬剤性や肝炎関連などがある.多くは造血幹細胞に対する免疫学的な傷害である.
●日本における罹患率は年間100万人に8.3人であり,まれではあるが,欧米諸国に比べて数倍高い.
●診断には採血検査,骨髄検査,胸腰椎体のMRIなどが必要である.
免疫性血小板減少症
著者: 高蓋寿朗
ページ範囲:P.253 - P.258
Point
●免疫性血小板減少症(ITP)が疑われた症例では,血小板減少をきたす原因となる他の疾患,病態を除外することによって診断を進めていく.
●ITPの病態を反映し,特異性の比較的高い検査項目を組み合わせ,積極的にITPを診断する「ITP診断基準案」が作成されているが,実用化に至っていない.
●ITPは症例ごとの経過,治療に対する反応が多様であり,症例に応じた的確な治療法の選択と慎重な経過観察が重要である.
血栓性血小板減少性紫斑病
著者: 森下英理子 , 林朋恵
ページ範囲:P.259 - P.265
Point
●原因不明の血小板減少と微小血管性溶血性貧血(MAHA)を認めた場合,血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)を疑うことが重要である.ADAMTS13活性を測定し,10%未満に著減していればTTPと診断し,抗ADAMTS13自己抗体が陽性であれば後天性TTP,陰性であればUSSを疑う.
●従来はMAHA,血小板減少,腎機能障害,発熱,動揺性精神神経症状の5徴候を示すものをTTPと診断していたが,現在は5徴候全てそろわなくてもTTPを疑う.5徴候のなかでも,血小板減少と溶血性貧血の2徴候が診断に重要である.
●MAHAの検査所見としては,ヘモグロビン(Hb)12g/dL未満の貧血,破砕赤血球の出現,間接ビリルビン,LD,網状赤血球の上昇,ハプトグロビン(Hp)の著減,直接クームス(Coombs)試験陰性を認める.
重症熱性血小板減少症候群
著者: 安川正貴
ページ範囲:P.266 - P.271
Point
●重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は,マダニが媒介する新興ウイルス感染症である.日本国内では西日本を中心に,主として春〜秋に患者が発生している.
●臨床症状は,高熱,消化器症状,出血傾向,中枢神経症状などであり,多臓器不全をきたしやすく致死率は25〜30%である.
●検査成績として,白血球減少,血小板減少,肝機能異常,CK値,LD値,フェリチン値の上昇,凝固異常などの頻度が高く,骨髄穿刺検査では血球貪食像を示す.高度の炎症所見があるにもかかわらず,CRPの上昇が認められないことが多い.
3章 腎・泌尿器・生殖器疾患
急性糸球体腎炎
著者: 小池健太郎 , 川村哲也
ページ範囲:P.272 - P.276
Point
●急性糸球体腎炎は感染を契機に発症する.先行感染から1〜2週間(平均10日)程度経過したのちに,突然の血圧上昇,肉眼的血尿,浮腫などで発症する.小児に多い疾患である.
●急性糸球体腎炎の診断には蛋白尿,血尿といった尿異常に加え,補体(C3,CH50)の低下やASO,ASKの上昇が根拠になる.
●腎生検を施行した場合には,管内増殖性変化や免疫複合体の沈着(hump)が特徴的である.
●予後は比較的良好な疾患である.
慢性腎不全
著者: 木村秀樹
ページ範囲:P.277 - P.283
Point
●現行の慢性腎不全は,推算糸球体濾過量(eGFR)が60mL/分/1.73m2未満の状態を示し,糖尿病性腎臓病,慢性腎炎,腎硬化症が主因である.
●eGFR<60の病態は,国民の約14.5%に認められ,高齢者になると増加し70歳台で約30%,80歳以上では約40%と著明に増加する.
●eGFRが30〜59の病態では,高血圧の合併,血清クレアチニン(Cr),UN値が上昇し,eGFRが15〜29の病態では,易疲労感,腎性貧血,夜間尿と多尿,血清P値上昇,Ca値低下を認める.eGFR<15の病態では,吐気,食欲低下,息切れ,K値の上昇,代謝性アシドーシスが合併する.
●慢性腎不全の進行とともに,超音波所見では腎皮質の菲薄化とエコー輝度の増強,腎表面の凹凸不整の増強,腎サイズの縮小を呈する.
●慢性腎不全の進行過程では,1/Cr,eGFRが直線的に低下していく.UN/Cr>10〜20の病態では脱水,蛋白摂取量の増加を,UN/Cr<10の病態では蛋白摂取量の低下を示す.
膀胱癌
著者: 尾張拓也 , 三宅牧人 , 藤本清秀
ページ範囲:P.284 - P.290
Point
●膀胱癌は膀胱粘膜上皮(尿路上皮)より発生した悪性腫瘍である.
●適切な治療選択を行うためにCT,MRIなどの画像検査および経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)による正確な病理組織学的診断が重要である.
●狭帯域光観察(NBI)や5-アミノレブリン酸(5-ALA)を用いた光力学診断(PDD)などの可視化技術により,腫瘍の高感度検出が可能となった.
前立腺癌
著者: 深貝隆志
ページ範囲:P.291 - P.297
Point
●前立腺癌は男性が罹患する癌のなかで最も年間の罹患数が多い癌である.
●前立腺癌の診断には前立腺特異抗原(PSA)が有効である.一般的な基準値は4ng/mLであり,経超音波下の針生検により診断が確定する.
●PSAは早期診断に有用であり,近年PSAを用いた前立腺癌検診は死亡率を低下させることが証明されてきている.
●PSAは治療後の再発(再燃)のモニタリングにも有効であり,臨床の場で広く使われている.
4章 内分泌・代謝・栄養
副甲状腺機能亢進症・低下症
著者: 宮﨑直子
ページ範囲:P.298 - P.305
Point
●副甲状腺機能亢進症とは副甲状腺ホルモン(PTH)の慢性的な分泌過剰状態により生じる代謝異常である.
●副甲状腺機能亢進症のうち,高カルシウム(Ca)血症・低リン血症も認める場合を原発性副甲状腺機能亢進症(pHPT),慢性腎不全などから起こる低Ca血症などによりPTHが過剰に分泌される状態を続発性副甲状腺機能亢進症(sHPT)と呼ぶ.
●副甲状腺機能低下症はPTH作用障害により低Ca血症・高リン血症を呈する疾患であり,PTH分泌不全と標的組織のPTH不応性に大別される.
●PTHの標的組織は腎臓と骨であり,その役割はCa代謝調節の中枢として極めて重要である.
糖尿病
著者: 竹本稔
ページ範囲:P.306 - P.313
Point
●糖尿病とはインスリン作用の不足に基づく慢性の高血糖を主徴とする代謝疾患群であり,管理不良な糖尿病ではさまざまな合併症を生ずる.
●よりよい血糖管理のために,慢性的な高血糖の指標のみならず持続血糖モニターが使用可能であり,血糖値の日内変動を観察できる.
●糖尿病は血糖値のみならず脂質代謝にも影響し,血糖管理に伴い脂質代謝も改善する.
脂質異常症
著者: 蔵野信
ページ範囲:P.314 - P.320
Point
●脂質異常症関連の検査値は,総コレステロール(TC),中性脂肪(TG),LDL-コレステロール(LDL-C),HDL-コレステロール(HDL-C)がルーチン検査では汎用される.
●LDL-C,HDL-Cは,著しい高TG血症では測定系の問題により正確に測定できない場合がある.
●脂質異常症関連の検査値は,生活習慣により異常をきたす他,遺伝的な要因による原発性脂質異常症や他の疾患による二次性脂質異常症により異常をきたしている場合も多く,他の検査値も参考に病態を判断しなければならない.
痛風
著者: 谷口敦夫
ページ範囲:P.321 - P.325
Point
●痛風とは,尿酸塩結晶が慢性的に関節内に沈着する疾患である.この尿酸塩結晶を原因として痛風発作が生じる.痛風発作は急性単関節炎であり,母趾中足趾節(MTP)関節に好発する.痛風はメタボリックシンドロームの合併が多い.
●高尿酸血症は,血清尿酸値7.0mg/dLを超える場合をいう.高尿酸血症は痛風の生化学的基盤である.
●痛風発作のときには血清尿酸値が低下することがあり,診断で注意を要する.この機序には,インターロイキン(IL)-6やコルチゾールが関与していると考えられている.
原発性アルドステロン症
著者: 若山綾子 , 臼倉幹哉
ページ範囲:P.326 - P.332
Point
●低K血症を伴わない原発性アルドステロン症(PA)症例も存在するため,血清K値が正常でもPAは除外できない.
●スクリーニングには,血漿アルドステロン濃度/血漿レニン活性比(ARR)が有用である.
●手術適応を判断する場合は,病型・局在診断のため副腎静脈サンプリング(AVS)の施行が推奨される.
●PA術後に高血圧が治癒しない症例や,腎機能が悪化する症例があるため,術前の臓器障害の評価と,術後の慎重な経過観察が必要である.
5章 膠原病・免疫疾患
全身性エリテマトーデス
著者: 岩崎由希子
ページ範囲:P.333 - P.340
Point
●全身性エリテマトーデス(SLE)は全身性の慢性炎症性疾患で,ステロイドを中心とした治療の進歩により予後は改善したものの,寛解・増悪を繰り返すことが多い.
●抗核抗体(ANA)は対応する核内抗原により染色パターンはさまざまあるものの,少なくとも活動期には通常陽性となり,ANA陰性のSLEは珍しい.
●抗ds-DNA抗体,補体価などは一般的には疾患の活動性を反映して変動する.
●SLEに特異性の高い自己抗体として抗ds-DNA抗体の他,抗Sm抗体が知られる.
血管炎
著者: 村岡成
ページ範囲:P.341 - P.348
Point
●血管炎は,血管壁の炎症による非特異的な全身症状と,血管狭窄あるいは拡張・出血による臓器症状を呈する.
●不可逆的な臓器障害,QOLの低下を防ぐためには,迅速な診断と治療が必要である.
●大型,中型血管炎は簡便で特異性の高い検査がないため,全身症状を呈する発熱患者では血管炎を鑑別に挙げることが重要である.
●小型血管炎の診断において抗好中球細胞質抗体(ANCA)は有用なマーカーである.特徴的な症状から血管炎を疑い,診断の補助として用いるべきである.
6章 呼吸器疾患
慢性閉塞性肺疾患
著者: 上ノ宮彰
ページ範囲:P.349 - P.355
Point
●慢性閉塞性肺疾患(COPD)は,進行性の疾患である.その進行はとても緩徐であり,自覚症状が乏しいまま経過する.
●呼吸機能検査を行うことでCOPDの病期の分類が可能である.指標となるのは1秒量/予測1秒量(%FEV1)である.また,フローボリューム曲線は特徴的な形状を示す.
●近年,気管支喘息や間質性肺炎との合併症が報告され,気腫型COPDとの鑑別が必要となっている.気管支喘息との鑑別には呼吸機能検査が必須であり,特に重要なのは気道閉塞の可逆性,呼気一酸化炭素濃度の検査である.間質性肺炎との鑑別にはCT検査が有用である.
間質性肺炎
著者: 皿谷健
ページ範囲:P.356 - P.360
Point
●間質性肺炎は特発性と二次性に分けて考える.
●さらに,特発性間質性肺炎(IIPs)は抗線維化薬の適応となる特発性肺線維症(IPF)とそれ以外で分けて考える.
●間質性肺炎の急性増悪では末梢血KL-6の上昇が診断に役立つことがあり,特にIPFでは高値になりやすいが,急性増悪から上昇するまで1〜2週を要することがあるため,他の疾患群を鑑別に挙げることが重要である.
サルコイドーシス
著者: 四十坊典晴
ページ範囲:P.361 - P.366
Point
●サルコイドーシスは原因不明の全身性肉芽腫性疾患である.自覚症状がなく胸部単純X線写真で異常を指摘される場合と,眼症状,呼吸器症状,不整脈などの循環器症状からサルコイドーシスが疑われる場合がある.
●胸部単純X線写真上両側肺門縦隔リンパ節腫脹(BHL)が特徴的で,サルコイドーシスでは血清アンジオテンシンⅠ変換酵素(ACE),血清可溶性インターロイキン2受容体(sIL-2R),血清リゾチーム上昇があり,診断基準に採用されている.
●自然軽快する症例から多臓器病変を認め,進行する症例まである.軽快した場合ACEなどの血清マーカーは低下する.進行し,治療が必要な場合はステロイドが第一選択となる.治療効果がある場合もACEなどの血清マーカーは低下する.
肺MAC症
著者: 北田清悟
ページ範囲:P.367 - P.372
Point
●肺MAC症は近年増加傾向にあり,その診断管理の重要性が増している.
●確定診断は診断基準を用いて行うが,抗GPLcore抗体測定が補助診断として有用である.
●治療の目標は自覚症状の改善と重症化防止のための病勢コントロールである.
●抗GPLcore抗体は病勢モニタリングにも有用である.
7章 心血管疾患
心筋梗塞
著者: 小西正紹 , 坂賢一郎 , 木村一雄
ページ範囲:P.374 - P.378
Point
●心筋梗塞は,心電図でST上昇を認めるST上昇型心筋梗塞と,認めない非ST上昇型心筋梗塞に大別される.
●ST上昇型急性心筋梗塞に対し有効性の確立された治療である緊急再灌流療法を行うためには,12誘導心電図による速やかな診断が必要とされる.
●非ST上昇型心筋梗塞の診断には,心筋トロポニンを中心とした心筋バイオマーカーが重要な役割を果たす.
心不全
著者: 板橋奈津 , 加藤祐子
ページ範囲:P.379 - P.386
Point
●心不全は病態を示す概念であり,個別の病因を示すものではない.
●脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)は診断や治療経過を診るのに有用であるが,腎機能や年齢などの影響を受けやすく,個人差があるため判断に注意を要する.
●血液などの検査所見は診断や治療効果評価などをあくまでサポートするものであり,患者を診て状態を評価することが重要である.
深部静脈血栓症
著者: 岡島年也
ページ範囲:P.387 - P.393
Point
●主訴が下肢症状である疾患としてまず思い浮かぶのは,閉塞性動脈硬化症などの動脈疾患であるが,静脈疾患である深部静脈血栓症(DVT)も忘れてはならない.
●DVTを単に四肢の静脈疾患と捉えるのではなく,静脈血栓塞栓症(VTE)として肺血栓塞栓症(PTE)や奇異性脳塞栓症も念頭に全身を診なければならない.
●血液検査は,DVTの初期鑑別をはじめ治療効果判定やDVTの再発の予測指標として有用である.
●DVTの確定診断には画像検査が必須である.
8章 感染症
感染性心内膜炎
著者: 前田正
ページ範囲:P.394 - P.398
Point
●感染性心内膜炎は,多彩な主訴や持続する原因不明の発熱で受診することが多く,診断が遅れることがある.
●特異的な検査値はないため,問診や診察所見,検査所見を総合的に判断する必要がある.
●経胸壁心エコー検査では明らかな疣贅を指摘できないこともあるため,Duke診断基準と照らし合わせて診断する.血液培養検査は最も重要な検査といえる.
梅毒
著者: 関川喜之 , 本郷偉元
ページ範囲:P.399 - P.405
Point
●多彩な症状を呈し,「梅毒は自由だ」といわれる.無症状で経過する症例もある.
●梅毒検査を入院時や術前のルーチン検査,あるいは検診で行う必要はない.
●梅毒トレポネーマ抗体検査(TPLAなど)が陽性ならば,現在もしくは過去の感染を反映する.
●非トレポネーマ脂質抗体検査(RPRなど)が疾患活動性を反映する.
●梅毒を診たらHIVも疑う.
ヒト免疫不全ウイルス感染症,後天性免疫不全症候群
著者: 戸田祐太
ページ範囲:P.406 - P.414
Point
●HIV感染はヒト免疫不全ウイルス(HIV)というウイルスへの持続感染を表す用語で,HIV感染者のうち免疫低下のために,後天性免疫不全症候群(AIDS)指標疾患(23種類の日和見感染症)を合併した患者をAIDS発症患者と呼ぶ.
●日本では,HIV感染者およびAIDS患者の新規報告数は,2007年頃をピークに横ばい〜やや減少傾向となっている.感染経路は,当初は血液製剤による感染が主体であったが,1990年以降は性感染症,特に同性間の性的接触による感染が拡大し,いまでは半数以上を占めている.
●HIV感染症の臨床病期は,急性感染期・無症候期・AIDS発症期に大別される.急性感染期または無症候期に診断され,早期に治療が開始されれば,高い免疫力を維持できるため,無症状のままの生活を継続し,非感染者と同等の余命が期待できる.
●HIV診療に重要な検査数値として,CD4陽性リンパ球(CD4)数とHIV RNA量(ウイルス量)があり,CD4数が免疫機能の指標として重要である一方,ウイルス量は治療薬の効果判定に重要である.
9章 その他
ギラン・バレー症候群
著者: 川邉清一
ページ範囲:P.416 - P.422
Point
●ギラン・バレー症候群(GBS)は自己免疫性に末梢神経が障害される疾患である.
●さまざまな感染症後に発症することが多い.
●髄鞘が障害される脱髄型と軸索が障害される軸索型がある.
●診断には脳脊髄液検査,末梢神経伝導検査,血液中の抗ガングリオシド抗体の検出などが必要である.
●重症例では呼吸機能検査,血液ガス検査,血液生化学検査,血清IgG検査などが行われる.
妊娠高血圧症候群
著者: 永松健
ページ範囲:P.423 - P.428
Point
●妊娠高血圧症候群の病態機序は,胎盤由来の血管機能障害因子によって起こる母体の血管機能障害による高血圧と臓器障害である.
●血管新生関連因子の胎盤産生量の変化に基づく血中sFlt-1/PlGF比が発症予知マーカーとして臨床導入されることが期待される.
●妊婦に高血圧を確認した場合は,腎機能,肝機能,血液凝固にかかわる血液検査値の変動にも留意する.
●子癇やHELLP症候群などが疑われる場合は,鑑別のための検査を実施して迅速な診断に努める.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.178 - P.179
基本情報
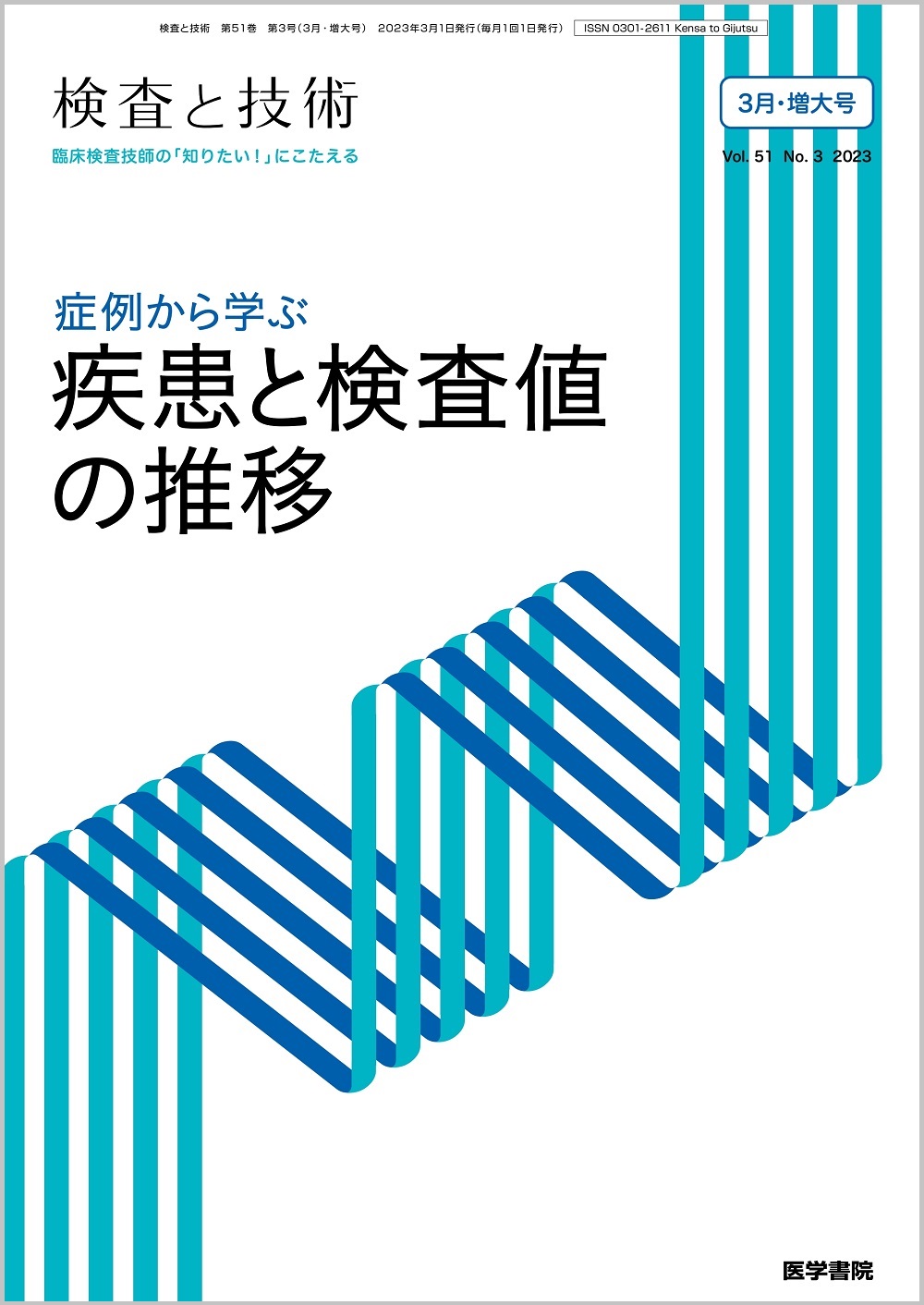
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
