血栓止血検査は,ある程度の医療機関であれば日中・夜間を問わず24時間365日検査が実施されているのではないでしょうか.ただ,自分も含め血栓止血学を得意とする医療従事者が少ないように思います.血液検査というと主に血球計算や血液像をはじめとした形態学の書籍を多く目にしますが,血栓止血検査となると血液学の本の一部に掲載されていることが多く,これまで血栓止血検査に特化した書籍をあまり見かけることはありませんでした.そこで「なければ作ってしまおう」と思い,この企画に至りました.
雑誌目次
検査と技術51巻9号
2023年09月発行
雑誌目次
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
1章 概論
一次止血による止血機構
著者: 矢冨裕
ページ範囲:P.892 - P.897
はじめに
人類の歴史は,感染症との闘いの歴史であったとよく言われる.人類は,その闘いの過程で,精緻な免疫能を獲得し,感染症に立ち向かってきた.同じように,人類の歴史は怪我との闘いの歴史であったとも言える.
人体においては,やはり精緻な仕組みで血栓が形成されるが,これは,長い歴史において,人類が生存のために獲得したものと考えられる.つまり,平時には血管内では血栓が生じないで体内循環が維持される一方,怪我をして出血した場合には局所で止血栓が形成され,われわれの体からの失血が防がれるわけである.本来の生理的過程では,血管内では血栓ができず,血管外の出血巣で止血栓が形成されるべきところが,病的な場合にはこの逆,つまり血管内で血栓ができ,血管外に出血しても止血栓ができない.このように,血管内で血栓ができるのが血栓性疾患(血栓症)であり,血管外に出血しても止血栓ができないのが出血性疾患である.本稿では,生理的止血機構とその破綻による出血に関して記述するが,そのなかでも初期の止血栓形成,つまり,一次止血を中心に概説する.
二次止血による止血機構
著者: 岡本好司 , 田村利尚
ページ範囲:P.898 - P.903
はじめに
医療従事者にとって,止血不能の状態は最悪の状態であり,その機序や異常な病態を理解することは大事なことである.血液は液状の形態であり,全身の組織・細胞にくまなく到達し,酸素や栄養を供給し,老廃物を肝臓や肺などの重要臓器に持ち帰り,代謝・解毒・再生などを行うメッセンジャーである.したがって,血液が血管外へ喪失することを防ぐために強力な止血機構がヒトに備わっていることは至極当然である.本稿では,止血機構のうち二次止血によるものを概説する.
2章 検査前プロセス
採血が血栓止血検査に及ぼす影響
著者: 小宮山豊 , 松田将門
ページ範囲:P.906 - P.913
はじめに
血栓止血検査には,血小板血栓にかかわる一次止血,フィブリン析出にかかわる二次止血,そしてフィブリン溶解にかかわる線溶それぞれに関する検査があり,血液が凝固する能力や血栓を溶解する能力を測定する.具体的な検査項目として,一次止血関連では血小板数や血小板凝集能など,二次止血関連ではプロトロンビン時間(prothrombin time:PT)や活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT),クロスミキシング試験,各種凝固因子活性,希釈ラッセル蛇毒時間(dilute Russell's viper venom time:dRVVT)など,線溶関連ではフィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP)やDダイマー(D-dimer:DD)などがある.このような血栓止血検査のうち,血小板数以外のほとんどの検査では,クエン酸Naを抗凝固剤に用いて採血することで,採血から検査実施までの間も患者体内と同等の凝固・線溶能を保持し,採血後に採血管内で凝固や線溶を進行させないことが,正しい検査の前提である.言い換えれば,不適切な採血管の選択や採血手技は原因不明の検査値変動の原因となり,臨床医の検査値判断に重大な影響を及ぼす可能性がある.これを防止するため,本稿では,適切な採血管の選択と採血手技について解説する.
血栓止血検査用検体の採血法やその後の取扱いに関する注意事項は,表1に示すように,①採血管,②採血手技,③操作(搬送),そして④保存と融解,に大別される1).採血手技は日本臨床検査標準協議会(Japanese Committee for Clinical Laboratory Standards:JCCLS)の「標準採血法ガイドラインGP4-A3」2)に則っているが,基本的には米国の臨床・検査標準協会(Clinical and Laboratory Standards Institute:CLSI)のガイドラインH21-A53)に準拠した採血法である.本稿では表1のうち,採血管と採血手技に関する注意点を解説する.
採血後の検体の保存や搬送条件が血栓止血検査に及ぼす影響
著者: 松田将門 , 小宮山豊
ページ範囲:P.914 - P.920
はじめに
血栓止血検査には,前項「採血が血栓止血検査に及ぼす影響」で解説したようにさまざまな検査項目があり,それぞれに適切な採血後の検体取扱い手順がある.本稿ではそのうち,フィブリン析出時間を検出する検査(凝固時間検査)における採血後の検体取扱いについて解説する.具体的には,採血後から検査室に運ばれて到着するまでの間の検体取扱いである.ここでは,検体の“保存”と“搬送”という2つのキーワードが存在する.なお,ここでいう検体保存とは,採血後の検体が検査室に到着するまでの間の“全血”の保存を指す点に注意されたい.検査室に到着した後の保存,すなわち遠心などの前処理をしてから測定するまでの間や測定後の“血漿”の保存については,次項「血漿分離処理」や「凝固検体の保管」を参照されたい.
本稿で解説する検体取扱いに関し,その適切な手順は,日本検査血液学会標準化委員会の凝固検査用サンプル取扱い標準化ワーキンググループが作成した「凝固検査検体取扱いに関するコンセンサス」(以下,コンセンサス)に明記されており1,2),これを遵守していただきたい.コンセンサスは,先行して発表されている米国の臨床・検査標準協会(Clinical and Laboratory Standards Institute:CLSI)のガイドライン3)や英国の標準化委員会(British Committee for Standards in Haematology)のガイドライン4)を参考に作成された.つまり,コンセンサスの規定は世界水準といえる.
以下,検体の保存と搬送に大別し,それぞれの注意点を概説する.
血漿分離処理
著者: 家子正裕
ページ範囲:P.921 - P.924
はじめに
出血や血栓症をきたす止血機能異常症は時に致死的であり,その診断や治療効果の判定に用いる止血機能検査は重要な検査である.例えば,プロトロンビン時間(prothrombin time:PT)は外因系および共通系凝固因子量を反映し,これらの凝固因子欠乏症のスクリーニング検査として用いられるばかりでなく,PT国際標準比(PT-international normalized ratio:PT-INR)はワルファリンによる抗凝固療法のモニタリング検査として頻用される.PT-INRは,どの試薬で測定してもほぼ同様な値となるように標準化された指標である.しかし,標準化されているPT-INRも,血漿サンプルの作製処理が異なれば値も異なる.その最も大きな要因の1つは,全血サンプルから血漿サンプルを作製するために行う遠心分離処理方法の違いである.特に,血漿サンプル中の残存血小板数が大きな影響をもたらすことは以前から指摘されていた.
本稿では,血漿サンプル作製時における適切な遠心分離処理方法を解説するとともにその重要性を再確認したい.
凝固検体の保管
著者: 家子正裕
ページ範囲:P.925 - P.928
はじめに
凝固時間検査は止血機能異常症における診断や治療効果の判定などに必須であり,正確な検査結果が求められる.しかし,凝固時間検査は再現性に乏しく,またさまざまなピットフォールが存在する.その1つがサンプルの劣化である.いかに測定試薬の標準化が行われていても,劣化したサンプルを用いた測定では結果が真の値とは異なり,偽陽性や偽陰性が生じることも少なくない.
採血後の全血サンプルおよび遠心分離処理後の血漿サンプルにおいて,それぞれの保存温度や保管時間などの保管条件によってサンプルの劣化を招くことがあり,それが誤診や治療結果の誤判断を招くことも少なくない.本稿では,全血サンプルおよび血漿サンプルの保管に伴うピットフォールとその対策について解説したい.
高ヘマトクリット(Ht)患者への対応
著者: 家子正裕
ページ範囲:P.929 - P.931
はじめに
出血症や血栓性疾患は時に致死的である.止血機能検査は,これら疾患の診断および治療効果判定に用いられる.そのため,正確な検査結果が求められるが,止血機能検査,特に凝固時間検査にはさまざまなピットフォールが存在する.採血方法,サンプルの保存条件,遠心分離処理方法などさまざまあるが,患者自身の状態も1つのピットフォールになる場合がある.凝固時間検査に影響する薬剤が投与されている場合や多血症患者のようにヘマトクリット(Ht)値が高い場合である.特に,高Ht患者の凝固時間検査には注意を要する.日本検査血液学会標準化委員会の「凝固検査検体取扱い関するコンセンサス」1)には,「患者のヘマトクリット値(Ht)が55%以上の場合はクエン酸ナトリウム溶液量を調整する」とある.
本稿では,高Ht患者における見かけ上の凝固時間検査異常の原因とその対策法について解説する.
3章 検査プロセス
血小板数/MPV
著者: 冨山佳昭
ページ範囲:P.934 - P.937
はじめに
血小板数は,血小板の産生,破壊,分布のバランスにより一定数に保たれている.
血小板産生に関して,血小板は骨髄において巨核球より産生される.巨核球はトロンボポエチンなどのさまざまなサイトカインにより造血幹細胞から分化・成熟する.巨核球の分化・成熟過程は極めてユニークであり,成熟とともに核のDNA量は増加するが,細胞質の分裂は起こらず多倍体となり大型化し,最終的に巨核球は血管類洞の近傍に局在し,血管内腔にproplateletと呼ばれる突起様構造物を伸展させ,血小板を血管内に放出する.
血小板破壊に関しては,放出された血小板は循環血液中で約7〜10日間の寿命を有し,老化とともに主として脾臓,肝臓の網内系にて破壊され処理される.
生体内での分布に関しては,血小板全体の約3分の1は脾臓内に分布している.そのため,脾腫や脾機能亢進があると,分布異常のため血小板数が減少する.循環血液中の血小板数は,これら産生,破壊,分布のバランスが崩れることにより血小板減少や血小板増多をきたす.
網血小板/幼若血小板分画
著者: 金子誠
ページ範囲:P.938 - P.941
網血小板と幼若血小板分画
網血小板(reticulated platelets:RP)1-3)は,骨髄から末梢循環に新たに放出されたばかりの血小板分画である.このRPの数は血小板造血(thrombopoiesis)が亢進することに伴って増加して,また産生低下に伴い減少することから,血小板造血の指標として用いられる.骨髄中では,RP数は末梢血の平均2〜3倍程度存在して巨核球の数と相関しており,巨核球形成(megakaryopoiesis)の状況を反映したマーカーでもある.このように骨髄における巨核球形成・血小板造血を反映していることが,赤血球造血を反映する網(状)赤血球(reticulocytes)の境遇に類似していることから,網(状)血小板と呼ばれる.
これらRPを含む未熟・幼若な血小板は,成熟した血小板に比べて細胞容積が大きく,RNA量や血小板内顆粒を多く含んでいる.RPのRNAは,巨核球RNAの名残とも考えられていたが,血小板内でもこのRNAによりタンパク合成されていることが示されており,成熟した血小板と比較して反応性が高い血小板である.RPは定常状態で全血小板数の約5%で,24〜36時間程度でRNA分解が進行し,体積が減少するとされる.この“若い”血小板と“成熟した”血小板については,全く異質なものを明確に区別しているわけではなく,血小板の大きさや,含有するRNA量など連続性のある対象物についてカットオフ値(RNA量や血小板の大きさ)を用いて恣意的に区別しているのである.
出血時間
著者: 野村昌作
ページ範囲:P.942 - P.945
はじめに
出血時間とは,止血機能に関与する血小板の異常や血管壁の状態を調べるために,皮膚にメスで創傷を作り,そこから湧出する血液が自然に止血するまでの時間を測定する検査のことである1,2).この検査は一次止血を反映し,多くの検査室で用いられている.メカニズムとしては,血漿中のフォン・ヴィレブランド因子(von Willebrand factor:VWF)を介する血小板の内皮下組織への粘着による凝集塊形成および血管壁の反射的収縮の関与が考えられている.病的には血管異常および血小板凝集能異常で延長するとされ,手術前のスクリーニング検査や出血傾向の患者に対する検査として利用されている.
古くから用いられている検査法であり,手技も簡易で有用であると評価されている一方,手技が正確性に乏しく臨床的有用性が低いと否定的な意見もまれではない.
本稿では,出血時間の測定方法と臨床における意義や問題点などについて解説したい.
血小板凝集能
著者: 冨山佳昭
ページ範囲:P.946 - P.950
はじめに
血小板は生理的な止血機構に必須の細胞であるとともに,一方では病的な動脈血栓形成においても中心的な役割を担っている.止血や血栓形成の過程において,血小板の機能はダイナミックに変化している.本稿では,血小板の機能を把握する代表的な検査法として“血小板凝集能”の原理および測定方法につき解説する.
PT
著者: 涌井昌俊
ページ範囲:P.951 - P.955
はじめに
凝固・線溶検査は,未消費の凝固・線溶関連因子を総体または個別に評価するものと,凝固・線溶関連因子が体内で消費された痕跡を評価するものに大別される(図1).前者はプロトロンビン時間(prothrombin time:PT),活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT),フィブリノゲン,第XIII因子(FXIII)活性,アンチトロンビン活性,その他の各種凝固・線溶因子活性,抗凝固・線溶因子活性が挙げられる.後者はトロンビン-アンチトロンビン複合体(thrombin-antithrombin complex:TAT),可溶性フィブリンモノマー複合体,プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体(plasmin-α2 antiplasmin inhibitor complex:PIC),フィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP),Dダイマーが挙げられる.
凝固・線溶関連因子が体内で消費された痕跡の評価はマーカー分子の抗原量の測定に基づくのに対して,未消費の凝固・線溶関連因子を総体または個別に評価する検査は主に活性を対象とし,凝固時間法または合成基質法で実施される.凝固と線溶はそれぞれ活性化凝固因子,活性化線溶因子による酵素反応のカスケードで成立し,トランスグルタミナーゼである活性化FXIII(FXIIIa)を除けばいずれもセリンプロテアーゼ反応である.PT,APTT,フィブリノゲンその他の凝固因子(FXIIIを除く)の測定に用いられる凝固時間法およびFXIII活性,アンチトロンビン活性などの測定に用いられる合成基質法はいずれも試験管内で惹起される因子の酵素反応を利用する.前者はカスケードの最終生成物であるフィブリンの析出が検出されるまでの時間を,後者はカスケードの下流で生じる活性化凝固因子による合成基質からの生成物を,それぞれ測定する.
PTとAPTTは代表的な凝固スクリーニング検査であり,生体内でまだ消費されていない凝固因子(FXIIIを除く)の活性を総体として評価する検査である.PTは外因系凝固能を総合的に評価する.因子活性欠乏または因子インヒビターによる外因系凝固異常の検索,ワルファリン療法のモニタリングに用いられる.
APTT
著者: 涌井昌俊
ページ範囲:P.956 - P.960
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)はプロトロンビン時間(prothrombin time:PT)とともに代表的な凝固スクリーニング検査であり,内因系凝固能を総合的に評価する.因子活性欠乏または因子インヒビターによる内因系凝固異常やループスアンチコアグラント(lupus anticoagulants:LA)の検索,ヘパリン療法のモニタリングに用いられる.
クロスミキシング試験
著者: 天野景裕
ページ範囲:P.961 - P.964
クロスミキシング試験
クロスミキシング試験とは,被検血漿に正常血漿を各種比率で混合し,活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)やプロトロンビン時間(prothrombin time:PT)を測定する検査である.正常血漿との混合比率は特に決められたものはないが,東京医科大学病院(以下,当院)では正常血漿の割合が0%,10%,20%,50%,80%,90%,100%の7点での測定を施行している.最近の血液凝固検査機器には自動多点希釈機能が備わっている機種があるので,混合直後に測定するものは上記のように設定し自動化が可能である.この混合直後の反応を“即時反応”と呼ぶ.それ以外に,混合後37℃で2時間インキュベーションし,十分に時間をかけて反応させたものも測定する必要がある.これを“遅延反応”と呼ぶ.当院では正常血漿が0%,50%,100%の3点のみ検体を作製して,37℃2時間インキュベーション後にAPTTやPTを測定している.
各種凝固因子定量
著者: 高木明
ページ範囲:P.965 - P.968
測定原理
凝固因子定量法は,凝固因子の活性を測定する方法と凝固因子タンパクを抗原抗体反応の特異性を用いて免疫学的に測定する方法とに大別される.
フィブリノゲン(Fbg)
著者: 鈴木敦夫
ページ範囲:P.969 - P.973
はじめに
フィブリノゲン(fibrinogen:Fbg)は,3つのポリペプチド(Aα鎖,Bβ鎖,γ鎖)から成るヘテロ3量体が重合してダイマーを形成した6量体〔(AαBβγ)2〕で,分子量約340 kDaの糖タンパク質である.肝実質細胞で合成され,循環血漿中あるいは血小板α顆粒中に含まれる.血中半減期はおよそ3〜4日である.Fbgは極めて多様な機能をもつが,凝血学的には一次止血および二次止血の両者において極めて重要な働きを有する.特に,Fbgからフィブリンへの転化は二次止血(血液凝固反応)において最終段階を担う反応であり,生体の止血能を評価するうえでは重要なスクリーニング検査項目のうちの1つである.
SF/SFMC・FMC
著者: 古賀震
ページ範囲:P.974 - P.977
測定原理・基準値
SF(soluble fibrin:可溶性フィブリン)
ラテックス免疫比濁法(LTIA),商品名:イアトロSFⅡ(LSIメディエンス社),基準値:7μg/mL未満,また健常人95パーセンタイルは5μg/mL.
SF(soluble fibrin:可溶性フィブリン)
ラテックス免疫比濁法(LTIA),商品名:ナノピアSF(積水メディカル社),基準値:7μg/mL未満.
FMC(fibrin monomer complex:フィブリンモノマー複合体)
ラテックス免疫比濁法(LTIA),商品名:オートLIA FM(ロシュ・ダイアグノスティックス社),基準値:6.1μg/mL以下.
キットや検査法で異なるので注意を要する.
AT/PS/PC
著者: 寺上貴子 , 森下英理子
ページ範囲:P.978 - P.983
アンチトロンビン
アンチトロンビン(antithrombin:AT)は,肝臓で合成される分子量約58,000の血液凝固阻害作用を有するセリンプロテアーゼインヒビターである.トロンビン,活性化血液凝固第Ⅹ因子(actibated factor Ⅹa:FⅩa),活性化血液凝固第Ⅺ因子(FⅪa),カリクレインなどの凝固系因子,ならびに線溶系のプラスミンと1対1で複合体を形成することで酵素活性を阻害し,抗凝固作用を発揮する.ATは単独ではその阻害反応はゆっくり進むが,ヘパリン存在下では構造変化が生じて約1,000倍に加速する.ヘパリンが結合することにより抗トロンビン活性が促進するため,ヘパリンの抗凝固効果は血漿AT活性に依存する.大部分は遊離型として存在し,一部は血管内皮細胞上のヘパリン様物質と結合して存在する.ATの血中半減期は健常者で約65時間であるが,播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation:DIC)では短縮する.
Dダイマー/FDP
著者: 窓岩清治
ページ範囲:P.984 - P.988
Dダイマー
■測定原理
Dダイマー(D-dimer:DD)は,D分画やDD分画を認識するモノクローナル抗体(必ずしもDD/Eの分子構造を立体的に認識するものではない)などを用いたラテックス凝集法や,酵素抗体法(enzyme immunoassay:EIA法)などにより,免疫化学的に測定される(表1)1).またテストストリップ上に微量の全血検体を添加し,抗原抗体反応と免疫クロマトグラフィー法を組み合わせたポイントオブケア測定系(point of care testing:POCT)は,救急医療の現場や大規模災害で,静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism:VTE)などの血栓性疾患のスクリーニング検査として活用されている.
TAT
著者: 朝倉英策
ページ範囲:P.989 - P.992
測定原理
トロンビンとその代表的な阻害因子であるアンチトロンビン(antithrombin:AT)が1:1で結合した複合体が,トロンビン-アンチトロンビン複合体(thrombin-antithrombin complex:TAT)である(図1,2).TATは酵素免疫測定法,化学発光酵素免疫測定法,ラテックス免疫比濁法などによる測定が可能であり,数種類の試薬が存在する.例えば,トロンビンおよびアンチトロンビンに対する2種類の抗体を使用したサンドイッチELISA(enzyme-linked immunosorbent assay)法や,TATが形成されることで新しく出現する抗原を認識する抗体を用いたラテックス免疫比濁法などがある.
TATを測定することで,凝固活性化の程度を間接的に評価することができる.トロンビンは血中半減期が極めて短いため,直接測定することはできないが,TATの血中半減期は3〜15分程度あるため,測定が可能となる.
PIC/プラスミノゲン/t-PA・PAI-1複合体/α2PI/PAI-1
著者: 長屋聡美 , 森下英理子
ページ範囲:P.993 - P.996
はじめに
線維素溶解(線溶)とは,凝固カスケードの進行に伴って生じた不溶性のフィブリン(線維素)を可溶性のフィブリン分解産物に分解し,組織傷害などで生じた止血血栓を溶解・除去する機構である.線溶反応は,プラスミノゲンアクチベータ(plasminogen activator:PA)が,酵素前駆体であるプラスミノゲンのArg561-Val562ペプチド結合を加水分解し,プラスミンに転換することで始まる1).生理的なPAとしては,組織型PA(tissue-type PA:t-PA)とウロキナーゼ型PA(urokinase-type PA:u-PA)の2種類が存在しているが,血管内皮細胞で産生されて血管内線溶にかかわるのは,主にt-PAである2).生成されたプラスミンはフィブリンを分解し,フィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP)やDダイマーを生じる(図1).t-PAおよびプラスミノゲンはフィブリン親和性が高いため,フィブリン上におけるプラスミン生成とフィブリン溶解が効率よく進行する2,3).
各因子インヒビター(Ⅷ,Ⅸ,XIII,Ⅴ)
著者: 野上恵嗣
ページ範囲:P.997 - P.1000
第Ⅷ因子インヒビター,第Ⅸ因子インヒビター
■基準値
0.6BU/mL(BU:Bethesda単位)以上を陽性と判定する(Bethesda法での測定限界とされる).
VWF抗原/VWF活性/VWFマルチマー解析
著者: 岡本修一
ページ範囲:P.1001 - P.1004
はじめに
フォン・ヴィレブランド因子(von Willebrand factor:VWF)は,血管損傷部位における血小板の粘着・凝集,流血中の凝固第Ⅷ因子(factor Ⅷ:FⅧ)の安定化作用を有する糖タンパク質である.VWFの約80%は血管内皮細胞,残りが巨核球から産生・分泌され,血中では分子量500〜20,000kDaからなるマルチマーを形成する.VWFサブユニットのドメイン構造は,FⅧ,血小板表面膜糖タンパク質(glycoprotein:GP),コラーゲンなどとの結合部位となって止血機能を発揮する.出血症状を有し,プロトロンビン時間(prothrombin time:PT)とフィブリノゲンが正常,かつ活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)の延長をきたした場合には,フォン・ヴィレブランド病(von Willebrand disease:VWD)や後天性フォン・ヴィレブランド症候群(acquired von Willebrand syndrome:AVWS)に代表される,VWFの量的・質的異常を鑑別する必要がある.そのための検査として,本稿ではVWF抗原量,VWF活性値,VWFマルチマー解析を取り上げる1,2).
ADAMTS13活性/ADAMTS13インヒビター
著者: 山田真也 , 松本雅則
ページ範囲:P.1005 - P.1008
はじめに
ADAMTS13とは,a disintegrin-like and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motifs 13の略であり,フォン・ヴィレブランド因子(von Willebrand factor:VWF)の特異的切断酵素である.通常,VWFは血管内皮細胞や骨髄巨核球に貯蔵され,血管内皮の障害・出血などの際に血中に放出される.VWFは分子量約50万〜2,000万に及ぶマルチマー構造を呈するが,高分子量のマルチマーほど止血能が高い.血管内皮や骨髄巨核球から放出されるVWFには,超巨大VWF(unusually-large VWF:UL-VWF)マルチマーが含まれているが,ADAMTS13により部分的に切断されることで,適切なサイズのVWFマルチマーとなり,止血が行われる.VWFの構造を図1に示した.
ADAMTS13が著減すると,血中にUL-VWFマルチマーが残存し,過剰な血栓形成により致死的な血栓症を呈する.先天的にADAMTS13が低下しているものを,先天性血栓性血小板減少性紫斑病(congenital thrombotic thrombocytopenic purpura:cTTP),別名Upshaw-Schulman syndrome(USS)と呼ぶ.一方,ADAMTS13に対する自己抗体が産生されることで後天的にADAMTS13活性が低下したものを,後天性TTPと呼ぶ.ADAMTS13活性,ADAMTS13インヒビター力価は,これらの疾患の診断,治療方針決定のために重要な検査項目である.
HIT抗体
著者: 安本篤史
ページ範囲:P.1009 - P.1012
はじめに
HIT抗体とは,ヘパリン起因性血小板減少症(heparin-induced thrombocytopenia:HIT)の診断のために用いられる検査で,抗血小板第4因子(platelet factor 4:PF4)/ヘパリン複合体抗体の通称である.HIT抗体の検出には,一般的に免疫学的測定法が用いられ,ラテックス凝集免疫比濁法と化学発光免疫測定法(chemiluminescent immunoassay:CLIA),酵素免疫測定法(enzyme-linked immunosorbent assay:ELISA),イムノクロマト法がある.これらの免疫学的測定法は簡便で迅速に行うことができ,感度が高いため,陰性の場合は99%の確率でHITを否定できるが,特異度が低いため,陽性であってもHITと確定することはできない.そのためHIT抗体が陽性の場合,確定診断のためには機能的測定法を行う必要がある(表1).
抗カルジオリピン抗体/抗カルジオリピン-β2GPⅠ複合体抗体/抗β2GPⅠ抗体
著者: 野島順三
ページ範囲:P.1013 - P.1016
基本的な測定原理
抗カルジオリピン抗体(anticardiolipin antibodies:aCL),抗カルジオリピン/β2グリコプロテインⅠ複合体抗体(anticardiolipin/β2-glycoprotein Ⅰ antibodies:aCL/β2GPⅠ),抗β2グリコプロテインⅠ抗体(antiβ2-glycoprotein Ⅰ antibodies:aβ2GPⅠ)は,いずれも免疫測定法により定量される代表的な抗リン脂質抗体であり1),抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid syndrome:APS)国際分類基準(“Sapporo Criteria” Sydney改訂版)に採択されている重要な検査項目である2).
aCLの基本的な測定原理(aCL測定系,図1a)は,固相化したカルジオリピンにリン脂質結合タンパク質であるβ2GPⅠを結合させた複合体を抗原とする.血清中では環状構造で存在するβ2GPⅠは,カルジオリピンなど酸性リン脂質(陰性荷電)に結合することにより伸長構造を呈する.aCLは,構造変化を起こしたβ2GPⅠ分子上のネオエピトープを認識して結合する抗体であり,正確にはβ2GPⅠ依存性aCLと呼ばれる3).APSの臨床病態に特異性の高い臨床的意義をもつ抗リン脂質抗体は,β2GPⅠ依存性aCLであることが確認されている.しかし,aCL測定系は原理上,β2GPⅠ依存性aCL以外にも固相化カルジオリピンに直接結合するβ2GPⅠ非依存性aCL(他の膠原病や感染症患者にしばしば出現する抗体)も混在して検出され,測定された抗体価がどちらに依存するaCLなのか,鑑別するのが難しい.
4章 検査後プロセス
血小板凝集能による抗血小板療法のモニタリングとしての役割
著者: 羽藤高明
ページ範囲:P.1018 - P.1022
はじめに
抗血小板療法は冠動脈疾患や脳梗塞のようなアテローム血栓症の治療に広く用いられており,アスピリンとP2Y12阻害薬(クロピドグレル,プラスグレル,チカグレロル)はその代表的な薬剤である.これらの薬剤は血小板凝集を抑制する作用を有しているが,その作用が不十分で残存血小板凝集能の高い状態はHPR〔high(on-treatment)platelet reactivity〕と呼ばれている.HPRを示す患者は血栓性イベントの再発率が高い一方,血小板凝集が強く抑制される薬剤を服用している患者は出血性イベントの発生率が高いことが報告1)されている.そこで,血小板凝集能測定機器を用いて抗血小板薬の効果をモニタリングし,その結果に応じて抗血小板療法を調整することによって予後を改善しようとする試みがなされてきた.本稿では,抗血小板療法のモニタリングを取り巻く現状とその課題について述べる.
ワルファリンのコントロールにおけるPTの意義
著者: 益永信豊 , 赤尾昌治
ページ範囲:P.1023 - P.1027
はじめに
ワルファリンは,当初はネズミを駆除するための殺鼠剤として使用されていた薬剤だが,1950年代より抗凝固薬として使用されるようになった.わが国では1962年に導入され,60年以上の歴史がある古い薬剤である.心房細動による心原性脳塞栓症の予防をはじめ多くの疾患で有効性が示される一方で,出血合併症の懸念や至適用量調節の難しさなど,実臨床では使用しづらいと感じる場面に遭遇することが多い.本稿ではワルファリンのコントロールにおけるPTの役割とコントロールの実際について述べる.
DOACが凝固検査値に与える影響
著者: 奥山裕司
ページ範囲:P.1028 - P.1033
4つのDOACの作用機序と大規模試験の評価ポイント
わが国では2011年から,相次いで新規機序の抗凝固薬が使用できるようになり,現在4種類が使用できる(表1)1).名称としては,非ビタミンK依存性抗凝固薬(non-vitamin K dependent anticoagulant:NOAC),あるいは経口抗凝固薬(direct oral anticoagulant:DOAC)という名称が一般的となっている.ダビガトランはトロンビンの活性部位に直接かつ可逆的に結合することで,フィブリノゲンからフィブリンへの変換作用を阻害することで血栓形成を抑制する.活性化第Ⅹ因子(FⅩa)阻害薬(リバーロキサバン,アピキサバン,エドキサバン)はトロンビンの生成を誘導するFⅩaの活性を阻害することでトロンビンの生成を阻害し,ひいては血栓形成を抑制する.いずれの薬剤も,服用後の効果発現は速やかで,血中半減期はおおむね12時間程度である.
DOACの臨床的有用性を検討した大規模試験を評価する際には,いずれの試験も非弁膜症性心房細動患者を対象としていることの他にいくつかのポイントがある.①まず対象となった患者群のCHADS2スコアである.抗凝固薬の利益・不利益のバランスは,CHADS2スコアが高いほうが一般に利益が大きいほうに傾く.そのため,CHADS2スコア2点以上で有用であったとしても1点で有用であるとは限らない.②次に,対照となったワルファリン群のTTRである(TTRについては後述).過去の多数の報告があるようにTTRと心原性塞栓,大出血,生命予後は相関がある.不十分な質のワルファリン治療を対照とした試験では,薬剤の評価は的確に行うことができない.③また減量基準を決め,2つの用量を使用した試験(3つのFⅩa阻害薬)では,そのような基準に従って使用した場合の成績であると認識すべきである.
APTTによるヘパリンモニタリングとしての役割
著者: 藤森祐多
ページ範囲:P.1034 - P.1037
はじめに
ヘパリンは1916年に医学生だったJay Mcleanによりイヌの肝臓および心臓から発見された抗凝固物質である1).その発見から100年以上が経った現在も抗凝固療法を目的に日常臨床で広く使用されている抗凝固薬である.現在臨床で用いられるヘパリンはイヌ由来ではなく,ブタの小腸粘膜由来のヘパリンである.ヘパリンは単一の分子ではなく,分子量3,000〜35,000の酸性ムコ多糖であり,未分画ヘパリンと呼ばれる2).
1990年代に未分画ヘパリンから化学的あるいは酵素によって解重合することで得られる低分子量ヘパリンが開発された1).低分子量ヘパリンは未分画ヘパリンと同様に抗凝固薬として日常臨床で使用されているが,出血リスクがより低いとされている2).さらに,ヘパリンの最小単位のペンタサッカライドであるフォンダパリヌクスが開発され,抗凝固薬としての有効性が確認されている.各薬剤の特徴を表1にまとめた.
なお,本稿における“ヘパリン”とは,未分画ヘパリンのことを示す.
—症例提示①—後天性血栓性血小板減少性紫斑病(後天性TTP)
著者: 上田恭典
ページ範囲:P.1038 - P.1042
はじめに
血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP)は,微小血管における血小板を中心とする血栓形成によって,血小板減少,機械的な溶血性貧血,阻血による臓器障害を呈する血栓性微小血管症(thrombotic microangiopathy:TMA)の代表的な疾患の1つである.病態と病因の詳細は他稿で述べられるが,フォン・ヴィレブランド因子(von Willebrand factor:VWF)の切断酵素であるADAMTS13(a disintegrin-like and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motifs 13)が先天的に欠乏,もしくは中和抗体や結合抗体によって活性が著減するために,血管内皮から分泌されたVWFの非常に大きな重合体が,切断されないまま血小板と結合し,微小血管でVWF血小板血栓を生じることによって惹起される病態であることが判明している.TTPは現在では,ADAMTS13活性が10%未満の場合を指し,基礎疾患のない場合も,他疾患に続発した場合もTTPであるとの診断となる1).
ADAMTS13についての知見が得られるまでは,TTPは“血小板減少,微小血管性溶血性貧血,腎機能障害,発熱,動揺する神経障害”の5徴を呈する疾患とされてきた.本稿では,後天性免疫性のTTPについて,病態の異なった3症例の初診時検査結果を提示し,診断に至るまでの特徴的で重要な項目や問題点について述べ,全体的な特徴について触れたい.
—症例提示②—後天性血友病A
著者: 日笠聡
ページ範囲:P.1043 - P.1046
はじめに
出血傾向の既往がないにもかかわらず,後天的に凝固因子に対する抗体(インヒビター)が出現し,さまざまな出血症状をきたすことがある.これらのほとんどは凝固第Ⅷ因子(factor FⅧ:FⅧ)に対する自己抗体による後天性血友病Aであり,他の凝固因子に対する自己抗体は極めてまれである.
一部の先天性血友病患者にも,凝固因子の補充療法によって,補充した凝固因子に対するインヒビターが出現するが,この場合は同種抗体(alloantibody)であり,後天性凝固因子インヒビターにみられる自己抗体(autoantibody)とは区別される.
後天性血友病Aは特に基礎疾患を有しない場合もあるが,自己免疫疾患や悪性腫瘍,分娩,薬剤投与などの基礎疾患から発病する場合が多い1,2).発症年齢は50歳以上が90%近くを占め,60〜70歳台での発症が最も多いことから,加齢も発症要因の1つと考えられている1,2).女性の場合はしばしば分娩後に発症するため,20〜30歳台にもピークがあるが,全体の男女比には差はない1,2).
—症例提示③—抗リン脂質抗体症候群
著者: 山﨑哲 , 鈴木典子
ページ範囲:P.1047 - P.1050
はじめに
抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid syndrome:APS)は,抗リン脂質抗体(antiphospholipid antibodies:aPL)の存在下に認められる,動静脈血栓症および妊娠合併症をきたす疾患である.若年者や動脈硬化病変の非存在下での血栓症,また再発性血栓症では,積極的にAPSを疑う必要がある1).
aPLの検出には,凝固時間法によるループスアンチコアグラント(lupus anticoagulant:LA)と固相化抗原測定による抗カルジオリピン抗体(anticardiolipin antibodies:aCL)や,β2グリコプロテインI依存性抗カルジオリピン抗体(anticardiolipin/β2 glicoprotein I antibodies:aCL/β2GPI),抗リン脂質抗体パネル(aCL IgG,IgMおよび抗β2GPI IgG,IgM)が,保険診療において測定できる.LAの検出には希釈ラッセル蛇毒時間(diluted Russell's viper venom time:dRVVT)や活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)をベースとした方法が用いられる.基本的にはAPTTの延長所見がなければLA陽性の可能性は低いと考えられるが,APTT試薬の特性にも影響されるので,注意が必要である.臨床的背景からAPSが疑われる,または,積極的に疑うべき病態が存在する場合にはLAやaCLおよびaCL/β2GPIが追加依頼される.しかし,出血症状を伴わないAPTT延長,特に軽度の延長についてはあまり注目されずに見逃されることも懸念されるため,検査室としては注意を払いたいポイントである.特に,APTT試薬のLAに対する感受性の違いから,その延長度は大きく異なるため2),APTTの軽度延長であってもLAや凝固因子の低下,特に軽症血友病などが潜んでいる可能性もあるため,臨床像とあわせて注意深く評価する必要がある.
本稿では,非典型例ではあるが,模擬症例を提示して,診断に至る過程で検査室が注意すべきポイントについて考えてみたい.
—症例提示④—FDP・Dダイマーの逆転
著者: 徳永尚樹
ページ範囲:P.1051 - P.1054
はじめに
フィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP)はフィブリノゲンまたはフィブリン分解産物の総称であり,その増加は一次線溶および二次線溶の亢進を示す.一方,Dダイマー(D-dimer:DD)は,活性化凝固第XIII因子によりフィブリノゲンのD分画が架橋結合した安定化フィブリンが分解されることで生成されるFDP分画の1つであり,その存在は二次線溶の亢進を意味し,血栓形成の証拠となる1).これらは出血傾向の評価に加え,播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)の診断や,肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症などの静脈血栓症,がん関連血栓症などさまざまな病態の把握において,欠かせない検査である.
FDPとDDの値は理論的に逆転しないが,しばしば値が逆転する場合がある.本稿では,FDP,DDの異常値のなかでも,特にFDP,DDが逆転した場合の対応方法について,症例を提示しながら解説する.
—症例提示⑤—FDP・Dダイマーの異常高値—胸水・腹水由来や非特異的反応など
著者: 徳竹孝好
ページ範囲:P.1055 - P.1058
はじめに
フィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP)は,播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)や,ウロキナーゼあるいは組織プラスミノゲン活性化因子(tissue plasminogen activator:t-PA)による血栓溶解療法だけでなく,各種原因に基づく生体内の線溶亢進の結果として増加する.FDPのなかでもDダイマーは,凝固第XIII因子で重合したフィブリン(cross-linked fibrin degradation products:XDP)の分解により生じ,生体内の血栓形成の証拠となる1).
FDP・Dダイマーの検査は抗原抗体反応を原理としているため,他の検査項目同様に,免疫測定系にみられる非特異反応が起こりうる.さらに採血手技や検体処理過程,疾患や患者の状態によっても,病態と合わない検査結果が得られることもあることから,得られた値が真の値か非特異反応による影響なのかを鑑別する必要がある.
今回,病態と合わないFDP・Dダイマーの異常高値の要因を,症例提示して解説する.
5章 疾患まとめ
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
著者: 柏木浩和
ページ範囲:P.1060 - P.1063
疾患概念
特発性血小板減少性紫斑病(idiopathic thrombocytopenic purpura:ITP)は,抗血小板自己抗体を中心とする免疫的機序により血小板減少が生じる自己免疫疾患である.近年では,(一次性)免疫性血小板減少症(primary immune thrombocytopenia)と呼ばれることが多くなっている.発症時期により,新規診断ITP(診断後3カ月以内),持続性ITP(診断後3〜12カ月間,血小板減少が継続もしくは無治療で寛解を維持できない),慢性ITP(診断後12カ月以上,血小板減少が継続もしくは無治療で寛解を維持できない)に分類される1).
先天性血液凝固異常/異常症
著者: 川杉和夫
ページ範囲:P.1064 - P.1067
疾患概念
先天性の血液凝固異常症(血栓性素因)とは,生理的な凝固制御因子であるアンチトロンビン(antithrombin:AT),プロテインC(protein C:PC),プロテインS(protein S:PS)の遺伝子に異常が生じ,凝固を抑制するこれらの因子活性などが低下して,血栓症〔特に静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism:VTE)〕を発症しやすい状態に陥っていることを意味する.また,先天性血液凝固異常症の原因には上記の他にヘパリンコファクターⅡ(heparin cofactor Ⅱ:HCⅡ)欠乏症,プラスミノゲン異常症などの疾患も存在する.しかし,それら疾患は頻度的には非常にまれであり,また,病態として必ずしも確立されていない疾患も含まれており,先天性血液凝固異常症といえば,AT欠乏症,PC欠乏症,PS欠乏症を指すのが一般的である.一方,欧米では凝固第Ⅴ因子ライデン変異1)(factor Ⅴ Leiden,第Ⅴ因子のArg506がGlnに置換した異常分子となっている)が主要な先天性血液凝固異常症であり,白人の血栓症患者の10〜20%を占めている.しかし,日本人ではいまだにfactor Ⅴ Leidenが検出されておらず,わが国の患者であればほぼこの疾患を考慮しないでもよいと現時点では考えられている.
血友病
著者: 天野景裕
ページ範囲:P.1068 - P.1072
疾患概念・疫学
血友病とは,血液凝固第Ⅷ因子(factor Ⅷ:FⅧ)あるいは第Ⅸ因子(FⅨ)の量的,質的異常によるX染色体連鎖性潜性遺伝形式の先天性出血性疾患であり,FⅧ欠乏症が血友病A,FⅨ欠乏症が血友病Bである.血友病Aの発生頻度は男子出生約5,000人に1人で,血友病Bは血友病Aの約5分の1である.令和4年度の「血液凝固異常症全国調査報告書」(令和4年5月31日時点)では,血友病Aの生存患者数は5,776人(うち女性が94人)で,血友病Bは1,294人(うち女性が38人)であった1).
血友病の出血症状は急性出血として以下のような出血が挙げられる(血友病Aと血友病Bでその出血症状に差はない).内出血は皮下出血,関節内出血,筋肉内出血,頭蓋内出血で,外出血は口腔内・歯肉出血,鼻出血,腎出血(血尿),消化管出血,外傷後出血,血精液など.乳児期後半頃より軽微な打撲による皮下出血が反復して出現し,幼児期以降は関節内出血や筋肉内出血などの深部出血が多くみられるようになるのが特徴的である2).慢性的に関節内出血を繰り返すと,関節変形と拘縮を生じて血友病性関節症となり,患者の生活の質(QOL)を大きく低下させる.
後天性血友病A
著者: 酒井道生
ページ範囲:P.1073 - P.1077
はじめに
生体内には複数種の血液凝固因子が存在するが,“自己免疫性後天性凝固因子欠乏症”とは,通常は,単独の凝固因子に対する自己抗体の出現によりその機能が低下し,主として出血傾向を呈する疾患群の総称である.理論的には全ての血液凝固因子に対して自己抗体が生じうるが,後天性血友病Aの発症頻度が最も高い.
なお,厚生労働省の指定難病の1つとして,“自己免疫性後天性凝固因子欠乏症”(指定難病288)があり,現在,①“自己免疫性後天性凝固第XIII因子(factor XIII:FXIII)欠乏症”,②“自己免疫性後天性凝固第Ⅷ因子(FⅧ)欠乏症(後天性血友病A)”,③“自己免疫性後天性フォン・ヴィレブランド因子(von Willebrand factor:VWF)欠乏症”,④“自己免疫性後天性凝固第Ⅴ因子(FⅤ)欠乏症”,⑤“自己免疫性後天性凝固第Ⅹ因子(FⅩ)欠乏症”の5疾病がその対象となっている(5章「自己免疫性後天性凝固因子欠乏症」を参照).
von Willebrand病(VWD)
著者: 岡本修一
ページ範囲:P.1078 - P.1081
疾患概念
フォン・ヴィレブランド病(von Willebrand disease:VWD)は,1926年にErik Adolf von Willebrand医師が報告した,北欧Åland諸島の血族結婚を繰り返す家系の先天性出血性素因にさかのぼる.
本疾患は,フォン・ヴィレブランド因子(von Willebrand factor:VWF)の量的・質的異常によって止血障害をきたす先天性疾患である.その大部分は常染色体顕性遺伝,一部が常染色体潜性遺伝形式をとる.
播種性血管内凝固(DIC)
著者: 朝倉英策
ページ範囲:P.1082 - P.1087
疾患概念
播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)は,基礎疾患(表1)の存在下に全身性持続性の著しい凝固活性化をきたし,細小血管内に微小血栓が多発する重篤な病態である1-4).凝固活性化とともに線溶活性化がみられるが,基礎疾患により,その程度には相当な差異がみられる(図1).進行すると血小板や凝固因子といった止血因子が低下し,消費性凝固障害の病態となる.DICの2大症状は,出血症状と臓器症状であるが,臨床症状が出現すると予後は極めて不良となるため,臨床症状の出現がない時点で治療開始できるのが理想である.
がん(固形がん)とDIC
著者: 関義信
ページ範囲:P.1088 - P.1092
疾患概念および疫学
播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)は,がんの腫瘍随伴症候群の1つである.1998年の旧厚生省による調査(これ以降,厚生労働省による調査は行われていない)では,DIC症例数(絶対数)の多い基礎疾患は,肝細胞癌(5位),肺癌(8位),胃癌(9位),結腸癌(13位)と,固形がんがベスト15位内に4つ順位を占めている(表1)1).各固形がんのDIC発症頻度は決して高くはないが,固形がん症例の6.8%がDICと診断されたという報告がある.DICを早期にかつ適切に診断・治療しなければ,担がん患者の生命予後や生活の質(QOL)を著しく悪化させる可能性があり,常にDICを念頭に置いて診療することが望ましい.
急性前骨髄球性白血病(APL)とDIC
著者: 池添隆之
ページ範囲:P.1093 - P.1096
APLの疾患概念
急性前骨髄球性白血病(acute promyelocytic leukemia:APL)は,急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia:AML)の約10%を占める,まれな造血器悪性腫瘍である.転座型染色体異常t(15;17)の結果形成されるPML::RARαキメラ遺伝子が,APLの病態形成に中心的な役割を果たす.初発APL153例に対して行ったシーケンス解析によると,約70%の症例でFLT3,WT1,KRASやNRASのいずれかに遺伝子変異を認めた一方,AMLで高頻度にみられるDNMT3A,NPM1,TET2やRUNX1にはほとんど異常を認めず,APLは細胞遺伝学的にAMLとは明らかに異なる造血器腫瘍である1).
敗血症とDIC
著者: 和田英夫 , 市川由布子
ページ範囲:P.1097 - P.1100
疾患概念
国際血栓止血学会(International Society on Thrombosis and Haemostasis:ISTH)は,播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)を“さまざまな原因によって引き起こされる広範な血管内の凝固活性化を特徴とする後天的な症候群であり,微小血栓は最小血管で生じるとともに,これに障害を与え,極めて重症になると機能障害をきたすこともある”と定義し,“DICはフィブリン関連産物(fibrin related products:FRMs)〔可溶性フィブリン(soluble fibrin:SF),フィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP),Dダイマーなど〕の生成と,これを反映した細小血管の後天的(炎症性)あるいは非炎症性障害を特徴とする疾患である”との概念を示した.また,以前の敗血症の定義は“全身性炎症反応症候群(systemic inflammatory response syndrome:SIRS)を呈する感染症”であったが,現在では“臓器障害を呈する感染症”に変わった.したがって,現在の敗血症の概念は,“フィブリン分解産物が増加する,細小血管の炎症性障害を特徴とする臓器障害を伴う感染症”である1).
小児領域のDIC
著者: 江上直樹 , 落合正行 , 石村匡崇 , 大賀正一
ページ範囲:P.1101 - P.1105
疾患概念・病態生理・発生機序
早産児,新生児から成人に至るまで,播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)の疾患概念に相違はない.しかしながら,新生児,小児では特にDICの発症リスクが高く重症化しやすいため,速やかな診断,治療が必要となる.
新生児期は,血液凝固因子の大半を産生する肝機能が未熟である.とりわけビタミンK依存性因子である第Ⅱ,Ⅶ,Ⅸ,Ⅹ因子は低値であり,その傾向は早産児ほど顕著となる.一方,凝固抑制因子であるプロテインC(protein C:PC),プロテインS(protein S:PS),アンチトロンビンなども肝臓で産生されるビタミンK依存性因子であり,低値である.生理的な状態では凝固因子と凝固抑制因子がともに低値でバランスが保たれるが,一度なんらかの要因でこのバランスが崩れると,容易にDICを発症する.
産科領域のDIC
著者: 小林隆夫
ページ範囲:P.1106 - P.1110
はじめに
産科における播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)の病態は,消費性凝固障害とそれに続く線溶亢進現象に起因する出血傾向,および臓器の循環障害に起因する全身の臓器障害である.危機的産科出血は,わが国では現在でもなお妊産婦死亡原因の第1位を占める.したがって,妊娠中および分娩時の疾患が原因で起こる産科DICに際しては,不可逆的になる前に早期に診断し,早期に適切な治療をしなければならない1,2).
深部静脈血栓症(DVT)/肺血栓塞栓症(PE)
著者: 荻原義人 , 土肥薫 , 伊藤正明
ページ範囲:P.1111 - P.1115
疾患概念
肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism:PTEまたはPE,本稿ではPEを用いる.なお,本稿でのPEは急性PEを指す)と深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)は一連の病態と考えられており,まとめて静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism:VTE)と呼ばれる.
四肢の筋膜より深層を走行する深部静脈に発生した血栓症をDVTと呼び,それより中枢側に位置する腸骨静脈,下大静脈,鎖骨下静脈,腕頭静脈,上大静脈,さらに内頸静脈に発生した血栓症もDVTに含まれる.静脈血栓が遊離し,塞栓子として肺動脈を閉塞した結果,PEを発症する.PEの塞栓源の約90%は下肢あるいは骨盤内の静脈由来とされる1).
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)
著者: 宮川義隆
ページ範囲:P.1116 - P.1120
疾患概念
血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP)は,急性かつ致死的な血液疾患であり,国の指定難病である1).全身の微小血管内に血小板血栓が形成され,多臓器が障害される.原因不明の溶血性貧血と血小板減少がみられる患者は,血栓性微小血管症(thrombotic microangiopathy:TMA)を疑う(図1).このうち,志賀毒素(ベロ毒素)を産生する病原性大腸菌感染による溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome:HUS)は,発熱,血性下痢を伴う急性大腸炎と急性腎障害を特徴とする.発熱,動揺性精神神経症状を示し,腎障害が軽いTMAはTTPを疑う1).なお,TMAには補体経路の異常活性化で発症する非典型溶血性尿毒症症候群(補体介在性TMA)も含まれる(図1).
溶血性尿毒症症候群(HUS)
著者: 山田真也 , 松本雅則
ページ範囲:P.1121 - P.1124
はじめに
溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome:HUS)は,先進諸国における小児の急性腎障害(acute kidney injury:AKI)の原因として最も頻度が高い.また,一般にHUSの原因として,腸管出血性大腸菌(enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC),その他の感染症(肺炎球菌,インフルエンザウイルスなど)や一部の薬剤が挙げられるが,HUSのほとんどはEHECによるものである.なおEHECは志賀毒素産生大腸菌(Shiga toxin-producing Escherichia coli:STEC)とも呼ばれる.本稿では,STECにより生じるHUS(STEC-HUS)の診断,治療について,「溶血性尿毒症症候群の診断・治療ガイドライン」1)を参考に解説する.
非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)
著者: 山田真也 , 松本雅則
ページ範囲:P.1125 - P.1129
疾患概念
非典型溶血性尿毒症症候群(atypical hemolytic uremic syndrome:aHUS)の理解のためには,まず血栓性微小血管症(thrombotic microangiopathy:TMA)を理解する必要がある.TMAは,微小血管障害性溶血性貧血,血小板減少,急性腎障害(acute kidney injury:AKI)を3徴候とする疾患概念である.TMAの中には,原因が比較的はっきりとしている志賀毒素産生性腸管出血性大腸菌関連溶血性尿毒症症候群(Shiga-toxin producing Escherichia coli hemolytic uremic syndrome:STEC-HUS)や血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP)が存在する一方,その他のTMAに該当する疾患をどのように分類するかは,年代やガイドラインごとに異なってきた.その変遷を図1に示す.「非典型溶血性尿毒症症候群診療ガイド2023(案)」によると,TMAのうち,STEC-HUS,TTP,二次性TMA以外をaHUSとしているが問題が発生している.また,病態を反映した用語として,“補体介在性TMA”の名称が用いられることがあるが,国際的なコンセンサスは得られていない.aHUSは他の原因がなく,補体の異常により生じるTMAと捉えることができる.
ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)
著者: 髙田眞紀子
ページ範囲:P.1130 - P.1134
はじめに
ヘパリン起因性血小板減少症(heparin-induced thrombocytopenia:HIT)は,ヘパリン使用中に血小板減少症を生じた際に必ず鑑別に挙げなければならない疾患である.本稿ではHITの臨床像や病態生理について概説し,「ヘパリン起因性血小板減少症の診断・治療ガイドライン」1)に則してHITの診断と治療の進め方について理解が深められるように解説する.
抗リン脂質抗体症候群(APS)
著者: 野島順三
ページ範囲:P.1135 - P.1138
疾患概念
抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid syndrome:APS)は,種々のリン脂質およびリン脂質とリン脂質結合タンパク質との複合体を標的抗原とする自己抗体群〔抗リン脂質抗体(群)〕の出現に伴い,動・静脈血栓症や妊娠合併症などを発症する自己免疫疾患である1,2).APSの診断上重要な抗リン脂質抗体は,リン脂質依存性凝固検査により検出されるループスアンチコアグラント(lupus anticoagulant:LA)活性3)と,免疫測定法で定量される抗カルジオリピン抗体(anticardiolipin antibodies:aCL)および抗β2グリコプロテインⅠ抗体(antiβ2-glycoprotein Ⅰ antibodies:aβ2GPⅠ)である4).これまでの研究から,臨床的意義をもつ抗リン脂質抗体は,リン脂質そのものを認識する抗体ではなく,リン脂質あるいは陰性荷電物質に結合することにより構造変化を起こしたβ2GPⅠ分子上のエピトープを認識して結合する抗体(β2GPⅠ依存性aCLあるいはaβ2GPⅠ)であることが確認されている5).さらに近年,LA活性のもう1つの原因抗体として,細胞膜の主要な酸性リン脂質であるホスファチジルセリンとプロトロンビンとの複合体に対する抗リン脂質抗体〔抗ホスファチジルセリン/プロトロンビン抗体(antiphosphatidylserine/prothrombin antibodies:aPS/PT)6)〕が確認され,APSは極めて多様性に富む疾患であると推測される.
APSは,臨床的に原発性APSと続発性APSに分類される1).原発性APSは,既知の膠原病や明らかな基礎疾患・誘因をもたないタイプで,抗リン脂質抗体の出現に伴い,脳梗塞・心筋梗塞・深部静脈血栓症や原因不明の習慣流死産などが認められる.一方,続発性APSは膠原病に合併するタイプで,基礎疾患としては全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus:SLE)が最も代表的である.さらに,まれではあるがAPSの特殊型として,全身広範な血栓で発症し,急激な多臓器不全・重症呼吸不全・重篤な血小板減少症などを合併し,極めて予後不良な劇症型APSがある.
自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(厚生労働省指定難病288)—診断ガイドと凝固検査
著者: 一瀬白帝
ページ範囲:P.1139 - P.1144
はじめに
自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(autoimmune coagulation factor deficiency:AiCFD)は,主に高齢者が原因不明の出血症状として発症するまれな疾患である.筆者らは2009年から本疾患を対象とした厚生労働省(厚労省)科学研究事業(班研究)を実施しており,後述する5疾患を指定難病288として制定してきた.本稿では,これまでにまとめて発表したわが国におけるAiCFDのエビデンスに基づいて1-6),各疾患の概要と凝固検査を中心に解説する.
なお,紙幅の都合で各疾患の詳細については記述できないので,引用文献を参照していただききたい1-6).
発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)と血栓症
著者: 高森弘之 , 西村純一
ページ範囲:P.1145 - P.1150
はじめに
発作性夜間ヘモグロビン尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria:PNH)は,PIGA(phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A)遺伝子変異による造血器クローン疾患であり,血管内溶血,血栓症,骨髄不全症が特徴的な臨床症状である1).PIGA遺伝子は,GPIアンカー型タンパク質(glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins:GPI-APs)の生合成に関与し,機能喪失型の遺伝子変異が生じると,GPI-APsの生合成が阻害される.CD55/59は,赤血球で補体制御の中心的役割を果たすGPI-APsである.PIGA遺伝子変異が生じた造血幹細胞レベルの細胞から分化したPNH赤血球はCD55/59を欠損するため,補体経路の活性化により溶血し,PNHのさまざまな臨床症状を引き起こす.PIGA遺伝子変異により生じたPNHクローンが拡大しなければ臨床症状は顕在化しないが,拡大機序はいまだ十分に解明されていない.
血栓症はPNHにおいて最も重篤な臨床症状の1つである.抗補体薬であるエクリズマブ(eculizumab:ECU)の登場により血栓症のリスクが改善されたことから,補体経路と血栓症の関連が示唆されている2).抗補体薬によりPNHの臨床成績は著しく改善してきているが,それでもなおPNH診療において血栓症は最も注意が必要な合併症の1つである.
COVID-19と凝固異常
著者: 内場光浩
ページ範囲:P.1151 - P.1155
はじめに
SARS-CoV-2ウイルスによる感染症(COVID-19)の世界的感染拡大は医療の領域を含め,世界全体の社会のあり方を大きく変えた.COVID-19にはいくつかの臨床的な特徴があるが,その1つに血小板系を含む広義の凝固線溶異常があり,COVID-19の病態形成や患者予後に影響を与えている.本稿ではCOVID-19における現在考えられている広義の凝固線溶異常の病態について概説し,病態形成や予後に対する影響について述べる.また,SARS-CoV-2に対するワクチン投与でも凝固異常などが合併する場合があるため,この点についても記載する.なおSARS-CoV-2はウイルス名で,SARS-CoV-2によって引き起こされる疾患名がCOVID-19である.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.888 - P.890
基本情報
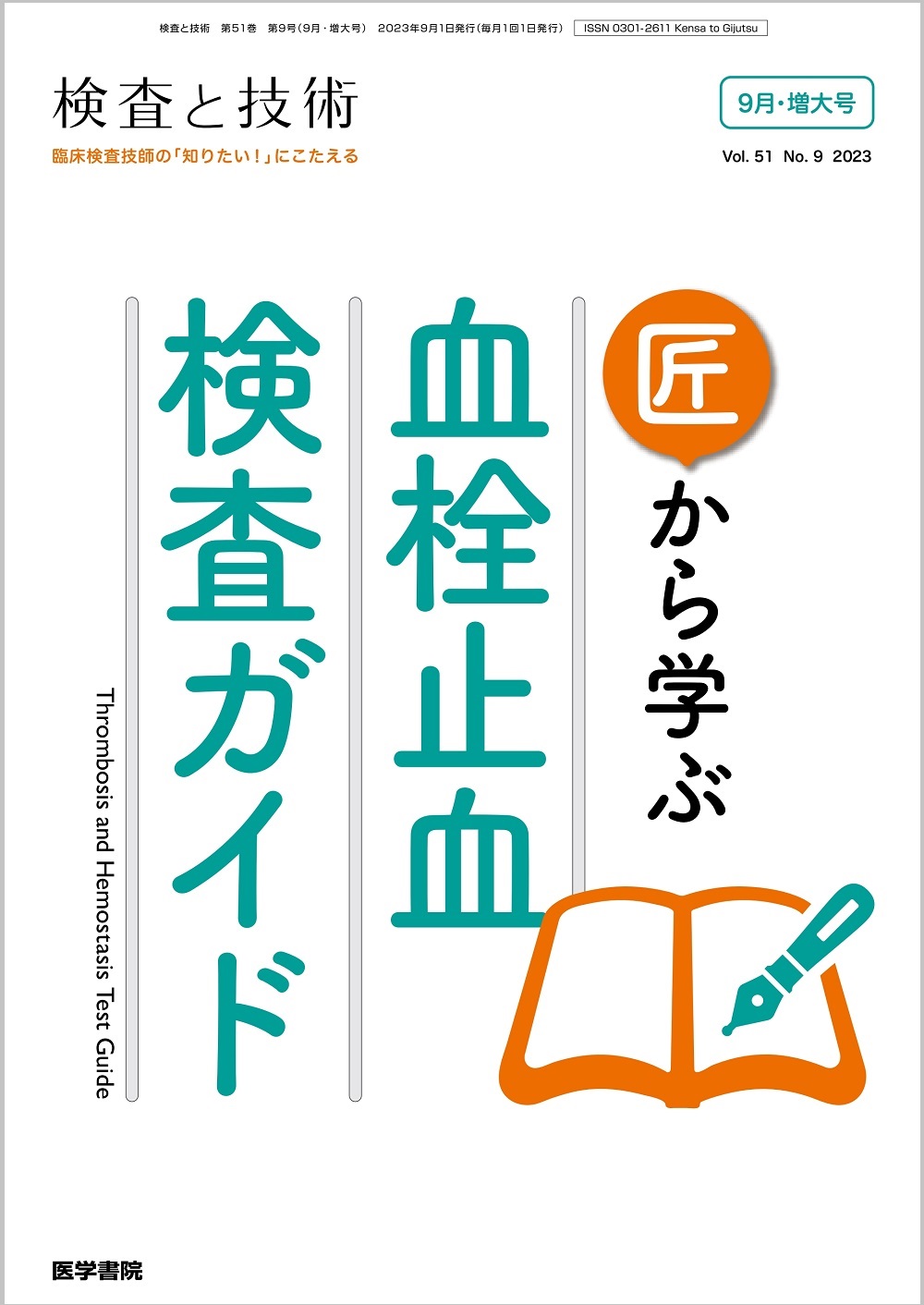
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
