POCUS(point of care ultrasound)は“病変の的を絞って短時間で行う超音波検査”のことであり,救急の現場や外来診察時に医師が活用している手法である.近年,超音波機器が高精度でありながら小型化されてきたことや,POCUS関連の学会・研究会における検査法の確立化なども相まって,POCUSはより広い分野で用いられるようになってきている.
雑誌目次
検査と技術52巻3号
2024年03月発行
雑誌目次
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
1章 POCUSを知る・使う
POCUSのコンセプト
著者: 谷口信行
ページ範囲:P.164 - P.167
POCTとPOCUS
検査に関わる皆さんは,POCT(point-of-care testing)という言葉をよくご存じだと思います.POCTは,被検者の傍らで医療従事者が行う検査であり,具体例としては,尿検査,血糖,妊娠反応,最近ではCOVID-19の抗原検査などがよく知られています.その場で行う心電図検査も,これに該当します.
日本でも,「POCTガイドライン第5版」が発刊されています1).その中でPOCTの定義として,「POCTとは,被検者の傍らで医療従事者(医師や看護師等)自らが行う簡便な検査である.医療従事者が検査の必要性を決定してから,その結果によって行動するまでの時間の短縮および被検者が検査を身近に感ずるという利点を活かして,迅速かつ適切な診療・看護,疾病の予防,健康増進等に寄与し,ひいては医療の質,被検者のQOLおよび満足度の向上に資する検査である.」としています.また,補足に,「POCTとは,小型で容易に持ち運べる簡便な機器・試薬を言うのではなく,あくまでも検査の仕組み(システム)を示す」と記載されています.
救急の現場での活用法
著者: 瀬良誠
ページ範囲:P.168 - P.173
はじめに
日本救急医学会から2022年に発刊された「救急point-of-care超音波診療指針」には,「医療者がベッドサイドでポイントを絞って自ら実施し,臨床決断と手技の向上に役立てる超音波検査はpoint-of-care ultrasonography(POCUS)と呼ばれるようになり」,「救急現場では領域を問わず積極的に活用されるようになってきた」と記載されている1).この,領域を問わず活用して臨床決断に役立てるということが,救急での大きな特徴の1つである.ACEP(American College of Emergency Physicians)のガイドラインでは,POCUSを機能面から以下の5つに分類している2).蘇生(resuscitative),診断(diagnostic),症状あるいは兆候に基づく(symptom or sign-based),手技のガイド(procedure guidance),治療とモニタリング(therapeutic and monitoring)である.領域を問わずという観点から,本稿では誌面の都合上,“診断”と“症状あるいは兆候に基づく”という2つについて解説する.
在宅医療での活用法
著者: 千葉裕
ページ範囲:P.174 - P.180
はじめに
それまで主に検査室で行われていた系統的エコー検査に対して,臨床医がベッドサイドでポイントを絞って行い迅速な診断につなげるエコー検査を,包括的にPOCUSと呼ぶ.さまざまな医療現場で,このPOCUSが急速に普及している1).泌尿器科専門医から在宅医療の分野に飛び込んだ筆者にとっても,このPOCUSは大変有用なツールとして,日常の診療に役立っている2)(図1).在宅医療現場でのPOCUSの活用法について解説する.
POCUSにAIを活用する
著者: 楠瀬賢也
ページ範囲:P.181 - P.185
はじめに
近年の医療分野においては,超音波診断装置の技術進化を見過ごすことができない.これらの装置は昔に比べて大幅に性能が向上し,さらにはバッテリー駆動のコンパクトなポータブルタイプも開発・市販されている.これにより,かつては循環器専門医に限られていた心エコー図検査が,現在では救急・麻酔科・一般内科・総合診療科などの広範な医学領域における医師たちによっても利用されている.
この超音波診断装置の使用方法の中に,“point-of-care ultrasound(POCUS)”と呼ばれる方法がある.これはハイエンドマシーンを使った検査室での精査としての心エコー図検査とは異なり,臨床医が患者を診療(care)する現場(point)で直接行う超音波検査を指す.従来は超音波技師が検査室で記録し,後から医師が解釈するのに対し,POCUSでは,医師自身が超音波所見を得てそれを患者の病状に対応させる,という即時性が求められる.
2章 超音波機器の基本と適切な使用法
超音波機器の基本・各種プローブの使い方
著者: 八鍬恒芳
ページ範囲:P.186 - P.190
超音波機器の種類
POCUSでは基本的に汎用性が高く,可搬性に優れた機器が望まれる.近年では,機器のダウンサイズ化と相まって,高解像度の画像を提供しつつ筐体が小さい機器が増えてきている.ここでは超音波機器の種類と主な特徴を述べる(図1).
超音波画像の調整法
著者: 八鍬恒芳
ページ範囲:P.191 - P.198
超音波機器は電源を入れればすぐに使用できるが,ある程度の画像調整を行わないと最適な画像を得られない.また,操作パネルの使用法も会得しておく必要がある.ここでは,最低限必要な画像調整法や主な機能の使い方を解説する.
アーチファクトの種類
著者: 八鍬恒芳
ページ範囲:P.199 - P.202
超音波が体内の組織で反射することで得られる超音波の画像だが,超音波は真っすぐに反射しないことや何度も反射を繰り返したり,音が屈折したりとさまざまな特性を持っている.そのため,実際には存在しないものを画像化してしまう“アーチファクト”による像が発生することがある.代表的なアーチファクトとその対処法について解説する.
3章 領域ごとの基本走査法
腹部領域
著者: 谷口真由美 , 竹之内陽子 , 岩﨑隆一 , 妹尾顕祐 , 小倉麻衣子 , 火口郁美 , 木村正樹 , 中藤流以 , 今村祐志 , 畠二郎
ページ範囲:P.203 - P.210
はじめに
POCUSの目的は既存疾患の経過観察から緊急性の高い疾患の病態評価まで多様である.本稿では急性腹症として遭遇頻度の高い疾患をある程度網羅し,超音波検査の経験が少ない検者でもベッドサイドで迅速かつ簡便に走査できるように考案された“6アプローチ”について述べる.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
心臓領域
著者: 山田博胤
ページ範囲:P.211 - P.219
心臓領域のPOCUS
循環器診療で一般的に用いられている包括的心エコー図検査は,多くの断面描出を必要とし,断層法,ドプラ法,3D法などさまざまなテクニックを駆使して行う検査である.そのため,30分以上の検査時間を要し,画像を正しく描出してその解釈ができるようになるには,少なくても数カ月のトレーニングを要する.一方で,目的を限定したPOCUSは,限られた断面のみを描出して迅速に施行でき,かつ,短期間でのトレーニングで習得できることが求められている.ここでは,心臓領域のPOCUSとして最もよく用いられている手法であるFoCUS(focused cardiac ultrasound)について解説する.ただし,一般的なFoCUSでは,急性心筋梗塞や大動脈解離などの重要な救急疾患の検出が困難な場合も少なくない.そこで本稿では,一般的なFoCUSをbasic FoCUSとして解説し,観察断面と観察項目を追加したadvanced FoCUSについても解説を加えた.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
血管領域
著者: 太田智行
ページ範囲:P.220 - P.225
はじめに
POCUSの目的の1つは,臨床情報を加味した上で,ベッドサイドの超音波検査を用い,早く正確な診断を行い,迅速に正しく介入し,予後を最良化することである.誤解があるかもしれないが,POCUSはCT検査を排除するものではない.CT検査装置がない環境ではもちろん,患者のバイタルサインが不安定でCT検査が難しい場合などでは,超音波検査しか頼れないが,現代の救急医療でCT検査を完全に省略することは困難である.従って,実際はCT検査前に可能な診断はつけて,迅速介入の準備を始めたり,CT検査後の経過観察で,超音波検査を積極的に利用しながら,刻々と変化する患者の容態を追跡したりすることがPOCUSの役割になることが多い.ただし,CTやMRI検査による画像診断だけでは正確な病態が見落とされるようなピットフォールもあるため,POCUSの視点は救急医療では必須である.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
表在領域
著者: 尾本きよか
ページ範囲:P.226 - P.233
はじめに
●表示方法に関する共通事項
日本超音波医学会による基本肢位を図11)に示す.
この基本肢位は,腹部だけでなく表在領域(甲状腺,運動器,皮膚・皮下組織ほか)にも適用され,これを基準に超音波像をモニター画面に表示する.横断像・水平断像(左右方向)ではCT画像と同じように足側から見たように表示する.モニター画面の左側は患者(被検者)の右側になるように表示し,縦断像・矢状断像(上下方向,頭尾方向)では,画面の左が患者(被検者)の頭側になるように表示することを原則とする.
●使用する探触子
表在領域の超音波診断では,通常,リニア走査方式による中心周波数が7MHz以上の探触子を使用して観察する.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
肺・気道領域
著者: 関谷充晃
ページ範囲:P.234 - P.241
胸部の基本走査法
●呼吸器領域における超音波の特徴
肺は豊富な空気を含み,肋骨や椎体などからなる骨性胸郭に囲まれている.超音波の特性として,プローブ(探触子)と標的病変との間に空気や骨が存在すると病変自体の実像を描出できないことから,肺エコーが全ての呼吸器疾患に応用できるわけではない.また,肺エコーでは,さまざまなアーチファクト(虚像)が生じる.通常,超音波診断においては弱点となり得るアーチファクトを診断のために利用するのが肺エコーの特徴である.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
4章 症状別検査の進め方
上腹部痛
著者: 今村祐志
ページ範囲:P.242 - P.246
はじめに
POCUSとは,point-of-care ultrasonographyの略語であり,ポイントオブケアにおける超音波検査である.日本ポイントオブケア超音波学会の説明によると“ポイントオブケア(Point of care/POC)とは,診療にあたり,被検者(患者)の傍らで医療従事者が行うもので,検査ではPOC testing(POCT)のごとく表現される.検査時間の短縮および,迅速かつ適切な検査,診療・疾患の予防,健康増進等に寄与し,ひいては医療の質と患者のQOL(Quality of life)向上に資するものである.具体例とし,外来での血糖や心電図検査,救急の場面での超音波検査などがある.”である.すなわち,病棟,救急外来や往診先などにおいて,診療をしながら行われる超音波検査である.通常の超音波検査と異なり,診療に必要な情報のみ得ることを目的としており,評価する部位や項目を絞って行われる.ポケットに入る小型超音波機器も開発され,聴診器のように用いられている.
下腹部痛
著者: 多田明良
ページ範囲:P.247 - P.254
はじめに
POCUSとは医師や看護師が臨床所見に基づいて焦点を絞りベッドサイドでリアルタイムに行う超音波検査を指す.さらにPOCUSで用いられるプロトコルは外傷性腹腔内出血検索のためのFAST(focused assessment with sonography in trauma)に代表されるように初学者にとっても簡便であり短時間で習得できるものであることが多い.
腹痛に関するPOCUSとして頻用されている領域は先に挙げたFASTの他,胆道,腎尿路,大動脈などであり,特に救急現場で広く応用されている.
一方で,これらは単一の病態や臓器に対するプロトコルであって,複数の臓器,多様な疾患を原因とする腹痛の一般外来診療では必ずしも有用とはいえない.
例えば外来診療において腹痛症例にエコーを行う場合,圧痛部位のみの走査では原因疾患を見逃すこともあり,そもそも圧痛部位が移動したり圧痛の局在がはっきりしないケースもある.また,胆道,腎尿路,大動脈,消化管やその他の原因が同時に鑑別に挙がることもある.
一方で見逃しを恐れるあまり,外来診療で検査室のクオリティーを求め超音波で観察し得る全ての腹腔内臓器をくまなく走査(系統走査)することもあるかもしれない.しかし,外来診療では時間の制限という問題もある.
悪心・嘔吐
著者: 中藤流以 , 畠二郎 , 今村祐志
ページ範囲:P.255 - P.262
概要
●悪心・嘔吐の病態,原因疾患
悪心は“何かを吐きそうな感じ”,嘔吐は“口から唾液や消化液,吐物を吐き出してしまう状態”で,何らかの原因により嘔吐中枢が刺激されることで起こる.その原因は消化管閉塞や腹腔内の占拠性病変のみならず,自律神経障害,中枢神経疾患や電解質・ホルモンの異常など,多岐にわたる.領域別の疾患・病態としては,消化器領域以外に,腎・泌尿器領域,産科・婦人科領域,頭蓋内病変や薬物・中毒などが含まれる1).
POCUSでこれら全ての疾患・病態を網羅することは容易ではないため,比較的頻回に遭遇し,臨床的に重要かつ典型例で,検出が可能な疾患あるいは病態についての評価を目指すことになる.具体的には,急性胆囊炎および胆石発作,尿管結石,消化管穿孔,腸閉塞,急性虫垂炎,大動脈瘤および大動脈解離,腹水貯留などが挙げられている2).
下痢・血便
著者: 高田珠子
ページ範囲:P.263 - P.269
はじめに
下痢は,持続期間により大きく,急性下痢(2週間未満),持続性下痢(2週間以上4週間未満),慢性下痢(4週間以上)に分けられる.本稿では急性下痢について,自験例を交えて解説する.
腹部膨満
著者: 植村和平 , 白崎優太
ページ範囲:P.270 - P.277
腹部膨満とは
●さまざまな腹部膨満の類義語
“腹部膨満感”には,“腹部膨満(abdominal distension)”,“腹部膨隆(abdominal swelling)”など,さまざまな類似の用語がみられる.日本の成書では,主に“膨隆”は他覚的所見であり,“膨満”は自覚症状とされることが多いようだが,混同して用いられることもある.さらにややこしいことに,腹部膨満に関してはなぜ自覚症状として出現するのか,正確な機序は知られていないが,さまざまな疾患でみられる症状である.
まず,用語の整理を行っておくが,2018年に世界保健機関から,約30年ぶりとなる「国際疾病分類(International Classification of Diseases:ICD)の第11回改訂版(以下,ICD-11)」が発表された.そこでは,腹部膨満を“abdominal distension”,腹水やabdominal distension以外での腹部腫瘤による膨隆を“swelling”と表現している.また近年の論文の表現としては,主訴としての表現に“abdominal bloating”と記載されている.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
血尿
著者: 紺野啓
ページ範囲:P.278 - P.287
血尿患者に対するPOCUS
血尿を来す疾患は多岐にわたるが,本稿では成人の肉眼的血尿について取り上げる.血尿患者の臨床的取り扱いについては,「血尿診断ガイドライン2023」1)が提唱されている.本ガイドラインの主な対象は顕微鏡的血尿で,肉眼的血尿についてはほとんど記載がない.しかし,そのわずかな記載の中でも,診断の初期段階における,超音波を用いた腎後性因子スクリーニングの有用性については明確に言及がなされている1).
これら腎後性因子の多くは,画像診断上,腎または尿路におけるなんらかの形態異常として捉え得る.従って,肉眼的血尿を対象に行うPOCUSの意義は,診療の最初期段階で,これらをいち早く拾い上げることにある.この意味で,腎・尿路系の結石ないしは腫瘍は,最もよい適応である.
胸痛
著者: 泉学
ページ範囲:P.288 - P.296
はじめに
胸痛は,救急外来で遭遇する最も一般的な症状のうちの1つである.しかし,多くの胸痛症例において,“胸が痛い”という単一の症状で来院されることは,決して多くはない.むしろ,“不快感”“苦しい”“圧迫される”など一定しないことの方が多い印象である.また,胸部臓器における症状においても,心窩部の症状を表現型として訴えることもあり,最初から疾患を限定せずに対応する必要がある.例えば,胸痛という触れ込みで,救急外来を受診した症例が,実は腹部消化器疾患の放散痛であることも少なくない.胸痛(および胸部の症状)の診療に際しては,特に生命に直結するいわゆる“killer chest pain”に対して,正確かつ迅速さが求められる.
胸痛の鑑別疾患としては,急性冠症候群を始めとした虚血性心疾患,胸部大動脈解離,肺血栓塞栓症が鑑別診断の上位に挙げられるが,その他にも,心タンポナーデ,気胸(特に緊張性気胸),特発性食道破裂(Boerhaave症候群)を,特に生命予後に直結する重篤疾患として挙げる必要がある.さらには,急性心膜炎,急性心筋炎,不整脈(徐脈,頻拍),たこつぼ型心筋症(心筋症),心臓弁膜症,肥大型心筋症,胸膜炎,縦隔気腫,逆流性食道炎,消化器疾患(消化性潰瘍,胆石症,急性膵炎など),帯状疱疹,肋間神経痛,心臓神経症などの疾患群も鑑別に挙げておきたい.
呼吸困難
著者: 栁沼和史 , 鈴木昭広
ページ範囲:P.298 - P.304
はじめに
POCUS領域で注目を浴びる肺エコーは呼吸困難の鑑別ツールとして有用で,COVID-19パンデミックを経て爆発的な普及をみせている.本稿では,まず肺エコーの総論について簡単に述べ,次に各論として,代表的な病態である気胸,胸水貯留,sonographic interstitial syndrome(SIS)について,病態生理を簡潔に説明する.その後,実際の画像を提示しながら,診断に至る過程,肺エコーに関する代表的なエビデンス,最後に肺エコーの注意点・限界点について解説する.超音波の設定や肺エコーに関する基本操作,基本画像については,3章「肺・気道」を参照されたい.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
下肢の浮腫・腫脹
著者: 濱口浩敏
ページ範囲:P.305 - P.311
はじめに
救急医療の現場では,下肢の浮腫(むくみ)・腫脹症状を主訴として来院される患者は多い.そのような患者でも,血管エコー検査を用いることで病態が判明する場合がある.本稿では,救急外来で下肢の浮腫・腫脹を呈した患者に対して,POCUSで行う血管エコー検査について解説する.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
意識障害・めまい
著者: 濱口浩敏
ページ範囲:P.312 - P.320
はじめに
救急医療の現場では,意識障害やめまい症状を主訴として来院される患者は多い.そのような患者も,血管エコー検査を用いることで病態が判明する場合がある.本稿では,意識障害やめまい症状を呈して救急外来を受診した患者に対し,POCUSで行う血管エコー検査について解説する.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
外傷の全身評価
著者: 伊禮裕人 , 瀬良誠
ページ範囲:P.321 - P.327
はじめに—症例提示
24歳,男性.バイク走行中に大型トラックと接触し受傷,バイクから数m離れた場所まで飛ばされていたとのこと.救急隊接触時のバイタルサインは意識JCS1-1,脈拍100回/分,血圧110/73mmHg,呼吸数30回/分,SpO2 95%(室内気)であった.E-FAST(extended focused assessment with sonography in trauma)は陰性,血液検査を行った後に全身のCT検査を実施した.CT検査で右多発肋骨骨折,右肺尖部に軽度の気胸,右肺挫傷,右橈骨遠位端骨折の診断となった.いずれも保存加療の方針で胸部外科,整形外科へ入院を相談し,準備を進めている.
上記は,外傷診療ではよくみる光景であろう.上述したE-FASTとは,外傷診療で用いる超音波検査技法のことである.ここではその内容について解説し,実臨床でどのように活用するかを例示していく.
骨折・関節の痛みや腫れ
著者: 北村亮 , 白石吉彦
ページ範囲:P.328 - P.333
はじめに
超音波診断装置の小型化によりベッドサイドへの普及が進み,超音波検査は救急現場や往診などで積極的に利用されるようになった.医療従事者がベッドサイドで観察範囲を絞り,臨床決断と侵襲的手技の質向上のために実施する超音波検査はpoint-of-care ultrasound(POCUS)と呼ばれ,その概念は国際的にも広く共有されるようになってきた.
運動器では骨折,関節液貯留,腱・靭帯損傷,皮下膿瘍や異物など軟部組織の病変などが適応となるが,その中でも骨折は比較的正確に診断可能であり,系統的レビューでは感度65〜100%,特異度79〜100%であった1).下肢については,病歴・身体所見をもとに開発されたオタワ足関節ルール,膝関節ルールがあり,見逃し回避を目指しているため,それぞれ感度は98%,99%と高いが,特異度は26〜48%,49%と低い2).一方で上肢については,各部位の身体所見の診断精度はばらつきが非常に大きい3).骨折部位別では鎖骨,眼窩,足,足関節,肋骨,大腿骨,上腕骨などは超音波検査のよい適応とされ,一方で橈骨,尺骨,脛骨,腓骨遠位端はその解剖学的形態から偽陽性となることも多く注意が必要である4).
肋骨骨折は気胸や肺挫傷などの合併症も多く,経過を通じて無気肺や肺炎を生じるリスクもあるため,その診断は非常に重要である.第一選択として胸部X線検査が施行されることが多いが,その診断精度はメタ解析では感度66%,特異度100%(救急医が読影)であった一方,POCUSの診断精度は感度97%,特異度89%であった5).
頸部・乳腺などの皮下領域の腫れ(膨隆)
著者: 鯉渕晴美
ページ範囲:P.334 - P.341
はじめに
皮膚の皮下結節・腫瘤・硬結(いわゆる“しこり”“腫れ”)では,腫瘍だけではなく,皮下膿瘍などの皮膚あるいは軟部組織感染症,リンパ節腫大,腹壁ヘルニアなど,幅広い疾患でPOCUSが行われる1).しかし,体表POCUSのエビデンスを示した論文は少ない.
皮膚疾患は皮膚科医のみならず総合診療医や家庭医が診察する機会が多く,プローブを病変に当てれば病変の超音波像が得られることから,皮膚皮下組織エコーをマスターしておくことは有用である.その前にまずは皮膚構造が超音波でどのようにみえるか理解することが必要である.皮膚皮下組織エコーは10MHz以上の高周波プローブを使用するが,特に浅い部分の表皮を評価する場合,15MHz以上の高周波プローブが必要となることもある.
プローブと皮膚の間にゼリーを介して皮膚表面を観察すると,皮膚表面の境界部エコー(高エコー)に続いて薄い低エコー層がみられ,これが表皮に相当する.真皮はやや高エコー層として描出され,その深部の皮下組織は真皮よりもやや低エコーに描出される2)(図1).
小児の腹痛
著者: 市村将 , 竹井寛和
ページ範囲:P.342 - P.350
小児の腹痛診療の特徴
●小児×超音波検査
小児は,成人と比較して筋肉や脂肪が少ない,体格が小さい,放射線感受性が高いなどの解剖学的特徴がある.超音波検査は放射線被曝がなく,侵襲が少なく,リアルタイムに繰り返し行うことができるなどメリットが多く,小児の画像検査としては非常に有用である.一方で,大泣き,大暴れする乳幼児では,正確で精度の高い検査を行うのが難しいことがある.“子どもを少しも泣かせず楽しんでもらいながら行う超音波検査”は,小児領域における立派な“技術”の1つである.慣れてくれば検査中に問診と診察を行い,検査をしながら有用な情報を得ることも可能である.小児だけではなく保護者にも気を配りながら検査を進めていくとよい.
小児の精巣腫大・痛み
著者: 市橋光
ページ範囲:P.351 - P.356
はじめに
男子の陰囊が急に腫れて痛くなる症状を“急性陰囊症”と称するが,その中で最も重要な疾患は精巣(精索)捻転である.本稿では精巣(精索)捻転を中心に述べ,他の鑑別疾患についても触れる.
尿が出ない
著者: 亀田徹
ページ範囲:P.357 - P.364
はじめに
救急や入院診療に関わる医療従事者が“尿が出ない”患者に接する機会は少なくない.その際に超音波検査を使いこなせれば,診療やケアの質が向上する.近年はPOCUSが普及し,ベッドサイドでカート式やポケットサイズの超音波診断装置が手軽に利用できるようになった.“尿が出ない”という症状に対し,これらポータブル超音波診断装置で評価は十分に可能である.まず,ベッドサイドで迅速に評価して患者の苦痛を軽減し,必要に応じて超音波検査室で原因精査を行えばよい.
POCUSではまず,膀胱に尿がたまっているか,どの程度たまっているかの評価から始める.時には尿道カテーテルが入っていても尿が出ないこともあるし,カテーテルを挿入しても尿が出ないこともある.本稿では“尿が出ない”場合を想定し,フローチャート(図1)でアウトラインを示し,各論を展開していく.さらに尿道カテーテル挿入手技に関するPOCUSの役割についても言及する.
—検査値から検査を考える—甲状腺機能が高い—甲状腺中毒症の鑑別
著者: 國井葉
ページ範囲:P.365 - P.372
甲状腺中毒症の鑑別
甲状腺中毒症とは,甲状腺ホルモンである遊離トリヨードサイロキシン(free triiodothyronine:FT3)と遊離サイロキシン(free thyroxine:FT4)が高値となり,その結果,甲状腺ホルモンが過剰に作用する状態である.
甲状腺中毒症を認めたら,どのように鑑別を行っていくか超音波検査の特徴を含めフローチャートを図1に示す.まず甲状腺刺激ホルモン(thyroid stimulating hormone:TSH)を確認し,TSHが抑制されているようであれば,甲状腺原発の甲状腺中毒症を鑑別していく.もし,TSHが抑制されていない,すなわち正常または高値であるならば中枢性の甲状腺中毒症,TSH受容体異常症などを考えなくてはいけない.
—検査値から検査を考える—肝酵素値異常—ビリルビンが高い,ALT/ASTが高い
著者: 小川眞広
ページ範囲:P.374 - P.383
はじめに
肝臓は“沈黙の臓器”ともいわれるように,重症化するまでは患者本人からの主訴として来院することは少なく,医療従事者が肝疾患を疑い問診しなければ採血結果をみるまで指摘されないケースも多い.従って内科への受診動機も,健診(検診)や他疾患加療中の採血検査における肝酵素値異常や軽度の黄疸となることが多い.この際,超音波検査を依頼するか,POCUSとして自らが検査を施行する2通りに分かれる.
本来,超音波検査は時間・空間分解能が高いため細かな情報を得ることが可能であり,近年の装置の発展に伴い,数mmの腫瘤性病変の指摘や,種々のソフトや血流評価を加味することで慢性肝疾患の進行度の過程や早期癌と前癌病変の鑑別診断などが可能となる精密診断的な一面も持つ検査法である.精査としての超音波検査とは別に,POCUSとして初診時に問診と同時に触診感覚で超音波検査を行うことも推奨されている.これにより原因疾患へのショートカットが可能となり,不必要な検査を省略することができ医療経済的にも有用性が高い.ここでは,POCUSと検査室で行う検査の違いも考えながら,肝酵素値異常(ビリルビンが高い,ALT/ASTが高い)に遭遇した際の超音波検査の活用法について解説する.
超音波検査室で行うスクリーニング検査では,系統的走査法として肝臓,胆囊・肝外胆管,膵臓,脾臓,腎臓,腹部大動脈を主な対象臓器とする.「腹部超音波検診判定マニュアル改訂版(2021年)」1)に記載されている推奨記録断面の25断面を,推奨記録25断面としている(表1).さらに適時異常所見がある部位でオプションとして拡大撮影,高周波プローブによる観察,カラードプラ,エラストグラフィ,さらには造影超音波検査などを付加して診断を深めている1,2).異常所見がない場合には目安として約10〜15分程度で終了することを目標としている.肝臓に関係する断面は全部で13断面であり,門脈圧亢進状態の把握という意味からの脾腫の有無を間接所見として入れると14断面,閉塞性黄疸も考慮し胆道・膵臓の評価の8断面も加えると22断面となる.
これに対し,POCUSの概念は,短時間(約5分)で見逃してはいけない重篤な疾患を見極めること,非専門医であっても診断可能となる疾患を対象とすること,装置の依存性の少ない重要な所見を対象とすること,としており,救急外来などで有症状症例に対しいち早くPOCUSを活用することが重要となる.POCUSでは9カ所の部位で操作を行うことを推奨し〔①心窩部走査:大動脈・下大静脈・膵臓・肝左葉・心囊液,②右肋間走査:胸水・腹水(肝表面)(右肺・肝臓・胆囊・右腎臓),③右側腹部走査:腹水(モリソン窩)(右腎臓〜結腸),④右下腹部走査:腹水(右傍結腸溝)(上行結腸・虫垂・回腸),⑤下腹部走査:腹水(ダグラス窩)(膀胱・前立腺・子宮・卵巣・直腸),⑥左下腹部走査:腹水(左傍結腸溝)(下行結腸・空腸),⑦左側腹部走査(左腎・結腸),⑧左肋間走査:胸水・腹水(脾臓・左肺),⑨腹部正中走査(①以外の部位の観察.小腸や皮膚・皮下組織・筋肉などの観察)〕(図1),10番目は視点を変えて周囲臓器の観察を行うこととしている.肝臓に関係する走査部位は他臓器と合わせて3カ所となっており,脾腫の有無を間接所見として入れても4カ所となっている(図1).POCUSではある走査断面を規定するのではなく,その部位で観察可能な臓器の状態を把握する.従って,同じ②右肋間走査であっても図1の3枚のように肝臓のほか胸水・腹水・胆囊炎の有無を評価する部位としている.
検査室で行う系統的走査とPOCUSで行う走査は同じ超音波B-mode像であり,装置の差以外にはみえる部位は同じである.さらに,実際の検査では1断面での静止画のみで評価するのではなく,その部位での扇動操作や呼吸性の移動による動画像で判断を下すため,実際には数十枚の静止画像が含まれている.両者の差は時間的制約であり,POCUSはある程度重篤な疾患に的を絞って割り切った検査法となっており,ある程度時間に余裕があり細かな情報を拾い上げることを求められる検査室での検査との相違点といえる.もちろん同じ検査法であり,熟練者においてはPOCUSで施行する3カ所の走査で系統的走査とほぼ同等の評価が可能な場合もある.POCUSは,非専門医であっても判断可能な疾患を対象としており,観察のポイントを逃さないことが重要となる.今回ここでは肝酵素値異常(ビリルビンが高い,ALT/ASTが高い)を呈する肝・胆道系疾患の,POCUSからみる超音波画像の特徴を解説する.
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2027年3月31日まで)。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.162 - P.163
基本情報
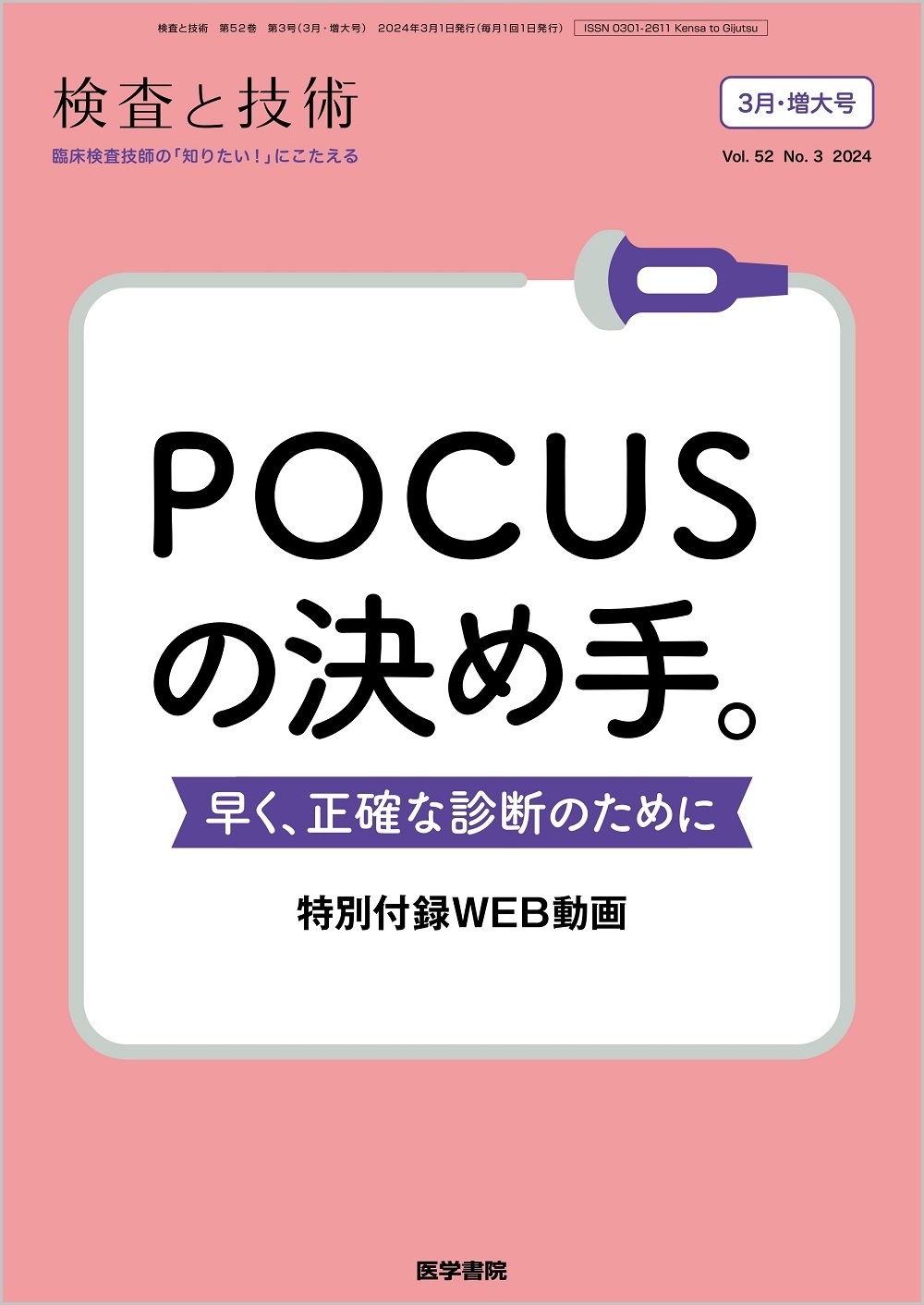
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
