伝染性単核症は発熱,全身のリンパ節腫脹および多数の異型リンパ球の出現とを3主徴とする疾患群で,病原としてウイルス説が有力視されている.また,患者血清中にしばしば異好抗体の増加が証明され,最近ではEBウイルス抗体価の上昇が注目されている.今回は本疾患患者末梢血中に出現するいわゆる異型リンパ球の代表的形態について解説してみた.
雑誌目次
臨床検査16巻5号
1972年05月発行
雑誌目次
カラーグラフ
技術解説
マイクロタイターによるウイルスの微量中和反応
著者: 赤尾頼幸 , 志賀定祠
ページ範囲:P.459 - P.470
マイクロタイター法は1954年にTakatsy1)らによって考案されたが,その後1962年にSever2)がこれを改良し紹介して以来,広くウイルスの血清学的検査に応用され,急速に普及した.
本法の利点は,(1)微量試料を用いて測定が可能であること,(2)従来の方法と比べて感度と精度に不都合がないこと,(3)操作が簡単で,特にダイリューターを用いて多数試料の希釈が同時にできること,(4)抗原や試薬が少量ですむので経済的であることなどがあげられる.
免疫グロブリンの定量法
著者: 臼井美津子
ページ範囲:P.471 - P.478
電気泳動法によって血漿タンパクが5つの分画に分けられ,抗体活性は最も易動度の遅いγ-グロブリンと名づけられた分画にあることが明らかにされたのは1939年である.その後,物理化学的および免疫学的なタンパク分析法が次々と考案開発されてくると,抗体活性をもつタンパクは,その物理学的な性質についても抗原構造の点からみても,非常に不均一なものの集りであることが明らかにされてきた.
抗体活性をもつタンパクおよびそれと抗原性の類似するタンパクをも含めた一群のタンパクを,今日では免疫グロブリンと呼んでいる.そして免疫グロブリンはその分子の抗原構造によって少なくとも5つのクラスに分けられ,それぞれにIgG(γG),IgA(γA),IgM(γM),IgD(γD),およびIgE(γE)と名づけられた.免疫反応に関与するグロブリンとして統一されてとらえられてはいるものの,その生物学的活性はクラスによっても異なり,さらにサブクラスによっても異なっている.
ランゲルハンス島のA,B,D細胞の染色法
著者: 藤田恒夫 , 渡辺雪子
ページ範囲:P.479 - P.482
ランゲルハンス島の細胞型
ランゲルハンス島の染色標本で染まり方の異なる2種類が存在することは,ウサギやモルモットのように島細胞が大型で染色性も明瞭な動物で,すでに今世紀初頭から気づかれていた(Ssobolew;1902,Tschassownikow;1906).その後,複雑な複合固定液とゲンチアナ紫-オレンジ,あるいはゲンチアナ紫-酸フクシンというような,今日ではあまり用いられることのない染色法によって,2種の細胞の顆粒を積極的に染め分ける方法が開発され(Lane;1907,Bensley;1911),Bensleyは今日も用いられるA細胞,B細胞の名を提唱した.
Bensley(1911)はモルモットの膵島に色素に染まらぬ明るい細胞を見いだしてC細胞(clearcell)と名づけた.その後Bloom(1931)はツェンケル-ホルマリン固定,アザン染色のヒトの膵島に,淡青色に染まる微細な顆粒をもつ細胞を見いだし,D細胞と名づけた.
総説
臨床化学検査における測定誤差の許容限界
著者: 仁科甫啓
ページ範囲:P.483 - P.489
精密度の設計
臨床検査,特に臨床化学検査における測定誤差はどの程度まで許容されるであろうか.臨床化学領域ばかりでなく,他の分野でも同じであるが,すべての分析結果は精度の高いほど望ましいことは論を待たない.一方,同時にそのためのむだな精力の消費もいましめるべきであろう.理想的な精密度設定のためのシェーマを図1に示すが,消費エネルギーと精密度の関係は等比級数的で,誤差をゼロにするためには無限大のエネルギーが必要となる.一方,臨床的有用性は実験誤差が大きいとほとんどゼロとなるが,精密度の上昇に伴って直線的に増加する.しかし,精密度がある程度以上よくなっても有用性はそれに伴って増加せず,頭うちとなるだろう.現実に設計されるべき精密度は臨床的有用性が十分高く,しかも労力の最小の点が望ましくなる(図1の↓の印で示す).
さて,検査的有用性はどのように決められるであろうか.
私のくふう
マイクロタイター用連続・定速滴下器
著者: 吉田治雄
ページ範囲:P.489 - P.489
マイクロタイターは時間,試薬,労力の軽減の利点のある反面,操作が細かいだけに心労はかえって大きいという問題がある.特に滴下操作は微妙な調節を指先の感覚だけで行なうために,絶えず緊張していなければならず,精神面の負担はかなり大きい.これを改善するため,連続して使え,定速で滴下でき,自由に止め出しができる滴下器を作った.現在4本をルーチンに使用し,満足のいく結果をえているので紹介する.
フラッシュミキサーのすべり止め
著者: 萩原啓司
ページ範囲:P.523 - P.523
フラッシュミキサーは用途が広く,日常検査においても頻繁に使われている.卓上用小型のものの中には,吸盤がついていても撹拌時の振動に伴って多少なりとも移動するようである.
近ごろの実験台やサイドテーブルなどの天板には,メラミン樹脂を主体にした合成樹脂板が多く使われているが,この台上でミキサーを撹拌するとすべりはいっそうひどくなり,片手で押えていなければならないほどである.スイッチを入れたままうっかり放置したら,動き回って机上から転落することも起こりうる.そのうえかなり強い騒音を発する.
臨床検査の問題点・40
リポタンパクの測定—支持体電気泳動法を中心に
著者: 菅野剛史 , 林幸子 , 長裕子 , 河合忠
ページ範囲:P.490 - P.496
リポタンパクの測定には,超遠心分析法,電気泳動法,沈殿法,免疫化学的分析法......があるが,臨床検査室で広く用いられているものはβ—Lテスト,硫酸デキストランを使った沈殿法,それと支持体電気泳動法である.このうち特に注目されている支持体電気泳動法を取り上げ,その種類と性質,方法を検討する(カットは各種染色法による泳動像).
ME機器の安全対策・5
臨床検査技師の取り扱うME機器の安全対策
著者: 本田正節
ページ範囲:P.497 - P.501
最近のME機器の進歩はまことにめざましいものがある.医学者はより新しい,より進歩したME機器の出現を渇望し,また工学者はこれらの機械が医学で,測定にあるいは治療に役だつことに注目し,国内的にも国際的にもM側とE側との歩みよりが行なわれ,約10年前よりME学会が設立されて,お互いに研鑽を重ねた結果,現在の盛況をみるに至ったわけである.
しかし,このような絢爛たる成果のかげに,電撃傷とか電撃死といういたましい事故が起こっていることは見のがせない事実である,ことに医学に携わっている者は,電気あるいは電子工学の知識の不足から,検査中の患者が心室細動を起こして急死しても,それは患者の心臓自体が弱って停止したいわゆる心臓死であると信じてしまっていて,実は電子機器の使用法を誤ったための,弱い電流による電撃死であることに気づかないこともありうるのではないかと思われる.現にアメリカでは年間の入院患者のうち,1200人が電撃によっで命を落としているという1,8).この死亡数はあまりにも多いので,どこまで信用してよいかわからないが,おそらく厳密な調査の結果発表されたものであろうと考えられるので,決して対岸の火災視することは許されない.
論壇
血清検査の問題点
著者: 堀越晃
ページ範囲:P.502 - P.503
私たちが日常行なっている臨床検査,特に血清学的検査について常日ごろ感じていることを述べて,皆さんといっしょに考えてみたいと思う.
座談会
臨床検査室の救急処置
著者: 上野幸久 , 安西喬 , 高橋昭三
ページ範囲:P.504 - P.510
検査室というところは,可燃性のもの,酸・アルカリ,また感染の危険のある材料をいつも扱っている.今月はその中で働いている技師が小さなきずをうけたり直接試薬を手にかけたり,検体にふれた場合どんな危険があるか,またそういう危険にさらされた場合にまず何をしたらよいか,検査室に関係深いドクターに話し合っていただいた.
第1回国際細胞検査士試験から—日本から一人ぼっちの受験
著者: 斎藤多紀子
ページ範囲:P.511 - P.512
第1回の国際細胞検査士の試験(CT;IAC-RegistryExamination)は,第4回国際臨床細胞学会(1971年5月27日)の第3日めの26日に,ロンドンのパークレーンにあるクロスバーナーハウスで行なわれました.日本からは関西医大の水野潤二先生が国際試験の委員をなさっています.受験者は17人で私を除いてほかの方は皆さんヨーロッパの方々でした.お互いと自分の国の名を言ってあいさつをかわましたが,私の記憶しているかぎりでは,
イギリス(1人)フランス(2人)
研究
ブドウ球菌分離同定の再検討—特にDNase活性,卵黄反応について
著者: 竹森紘一 , 横田英子 , 高安敦子 , 森哲夫 , 沢江義郎
ページ範囲:P.513 - P.515
まえがき
ブドウ球菌はBergey's Manual1)によると,コアグラーゼ産生能およびマンニット分解能とにより,黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)と表皮ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis)の2種類に分類され,病原菌は主としてコアグラーゼ産生,マンニット分解の黄色ブドウ球菌であるとされている.そこで,日常検査における病原ブドウ球菌の確認方法として,コァグラーゼ試験が用いられている.
しかし,多数の検体を処理しなければならない場合には,このテストもかなり煩雑なものとなる可能性があり,直接コアグラーゼの有無をはかり知るとか,画線塗抹のように同時に多数のコロニーを検査できることが必要となる.また,1検体から分離されてくるコロニーが均一な生物学的性状をもち,1コロニーの検索ですべてのコロニーをおし測るに十分であるかを確かめる必要がある.そこで,われわれは,コアグラーゼ試験,核酸分解酵素活性試験2)(以下DNA試験と略)とGillespieand Alder3)によって報告された卵黄反応とを比較しながら,黄色ブドウ球菌同定のための迅速で,より正確な方法について,再検討をしたので報告する.
市販ウシおよびヒトフィブリノゲンに混在する線溶系因子の検討
著者: 宮谷勝明 , 高畑譲二
ページ範囲:P.516 - P.518
著者らは先にフィブリン平板法を用いてヒトフィブリノゲンの中に混在する線溶系因子,特にプラスミノゲン・プロアクチベーターは,ウシフィブリノゲンのそれよりもきわめて大量に含まれていたことを報告1)してきたが,今回は,SK活性化溶解測定法2)に若干改変を加えた3種の方法を用い,ウシフィブリノゲン5種とヒトフィブリノゲン3種を基質の対象としてフィブリンの溶解時間に及ぼす諸因子の影響について吟味を行なったので,その成績を報告する.
全自動血球計器数の検討
著者: 泉口康幸 , 奈須守正 , 高島琴江 , 原宏
ページ範囲:P.519 - P.523
はじめに
血球計数面においても精度管理の必要性が叫ばれるようになるとともに,血球計数器および希釈装置の自動化の必要性が痛感されるようになった1-3).測定者による個人誤差をなくし,精度管理を容易にする点のみならず,増加する検体を処理するにも血球計数の全自動化が有利なのは当然といえよう.現在,全自動血球計数器としてSMA-4A(Technicon社,図1)およびコールター・カウンターモデルS(Coulter Electronics社,Model Sと略す,図2)がわが国では使用されている.SMA-4Aについてはすでに報告したが,今回は新たに導入したModel Sの機能を検討するとともにSMA-4Aと比較検討した.
Model Sは抗凝固剤を加えた血液1.2mlを検体とし,白血球数(WBCと略す),赤血球数(RBCと略す),血色素量(Hgbと略す),平均赤血球容積(MCVと略す)を測定し,これらの成績から赤血球容積(Hctと略す),平均赤血球血色素量(MCHと略す),平均赤血球血色素濃度(MCHCと略す)を求め,これらがプリントされる.WBCとHgbは等張の希釈液Isoton(Model S用希釈液)にて1:224倍に希釈され,Iysing S(Model S用の溶血剤Hgb測定用試薬)を加えて251倍に希釈され測定される.RBCとMCVは1:50000に希釈され,従来のコールター・カウンターと同様5-7)に測定される(図3).Model Sは44.7μlの血液をlsotonにて1:225に希釈したのちに測定できる2次吸引器がある.SMA-4Aの測定原理,測定方法については従来の報告を参照されたい.なお以下の実験において‘抗凝固剤の検討’以外はEDTA-2Kを抗凝固剤として用いた.
水を含まない新オルトトルイジン—ホウ酸試薬の開発と自動化学分析機への導入
著者: 高原喜八郎 , 中西茂子 , 鳥田美恵子 , 山田博
ページ範囲:P.524 - P.528
はじめに
1964年に佐々木匡秀1)らによって報告されたオルトトルイジン—ホウ酸試薬(O-TB試薬)は,今日なお血漿グルコース(血グ)の直接定量用試薬として,臨床化学の分野に広く貢献している7-9).さてこの試薬は氷酢酸(氷酢)より成っているために,氷酢によるタンパクの凝固を防ぐという目的から,水が飽和ホウ酸水として4%の割合に加えられていたが,この永は血グの直接定量を行なうのに対しては,実はタンパク凝固防止の意味はなかったようである.
すなわち第1の理由として,オルトトルイジン(O-T)が氷酢中に2%(v/v)以上に溶存してさえいれば,通常の実施条件下では血清を加えても何らの混濁もきたさないからである.これは塩基としてのO-Tが,氷酢と結合して塩のようなものを作るためからであろう.ただし2%未満では混濁をきたしやすかった.第2の理由は,水入りのO-TB試薬では血清タンパクに異常をきたすような例(ネフローゼ血清など)では,ときとして混濁を生ずる場合があるといわれているからである.
マカロニを用いたシロネズミ大動脈の顕微鏡標本の作り方
著者: 中館興一 , 高橋ミツ子 , 矢川寛一
ページ範囲:P.529 - P.531
マカロニで組織片を支持することにより,確実かつ容易に大動脈壁の縦断面標本を作る方法を述べた.すなわち,縦に切り開いた大動脈を任意の長さに切断し,内膜面を内側にしてうず巻き状に巻いてからマカロニの円筒につめ,凍結して薄切する.切片は水に浮かべるとマカロニから自然に離れ,伸展して細長い縦断面となる.
残った組織片はマカロニごとアルコール脱水をすすめ,純アルコール脱水時に組織片からマカロニを除きパラフィン包埋を行なって薄切する.この標本は最初の整形どおり,うず巻き状のものが得られる.
ひろば
心理的技術の効用
著者: 村田徳治郎
ページ範囲:P.528 - P.528
技師法の改正によって,われわれの職場は広がったことになる.つまり臨床の場で入院・外来の患者さんや被検者と直接検査を介して接する機会ができるようになったからだ.今まで私どもは,すでに採取されたところの体液なり排泄物の分析や測定にのみ能力を傾倒できたのであるが,新しい分野においては検者と被検者のヒューマンリレーションが測定に大きな影響となることが考えられる.特殊な測定はともかく,普通の臨床検査としての脳波,心電図,肺機能などにしろ,また採血にしても対象となる被検者の側を考慮してみる必要がなかろうか.同じ目的の検査でも,被検者の年齢,性別,性格,職業また教養の多寡によって臨機応変に接してゆかねばならないであろう.
従来の教科書によると,検査に対する恐怖や心配によるマイナス点を除くために,被検者に検査の内容や目的を十分理解するよう話してやることもあるが,経験的にこの答は基本的なもので,多忙な臨床検査の場では多くは応用されがたい.被検者の条件や要因にもより一概に断定的なものではないが,高・幼年者には物柔らかく笑顔にて,肉体的労働者にはいささか高姿勢かつ無愛想に,知的職業者には検査機器のメカニズムやその臨床的応用,他の分野への応用などを雑談的に話している.これはできるかぎり短時間に被検者の不安や恐怖また心配を除き,リラックスした状態にするためと,検者の指示がスムーズに被検者に伝達され受けとめられるための操作である.ときにはジョークや相手の趣味に合わせてもよく,いわゆる世にいう相手を見て法をとけ方式である.そのために新たにこの分野で働くわれわれは,その職域において検者と被検者という立場に,自分を含めての心理的技術をなおざりにはできない.つまり技と心を一致せしめてこそ成り立つ技術,それが臨床検査技師の課題であるまいか.ご批評を乞う.
新しいキットの紹介
O-Phthal-Aldehyde反応による血清遊離コレステロールの直接測定法
著者: 平塚孝一 , 石黒紀子
ページ範囲:P.532 - P.536
はじめに
遊離コレステロールの測定は,その技術的煩雑さと,他により容易に行なえる同じ目的の検査法が普遍化してきたことにより,臨床的価値は最近薄らいできたといわれているが,今日なお肝機能検査法として,その病態把握に意義がある1)とされる.
従来,有機溶媒でまず総コレステロールを抽出し,この抽出液にジギトニンを作用させると,特異的に遊離コレステロールがジギトニドを形成し沈殿するので,これをアセトンで洗浄後,発色させ比色した.しかしながら,この沈殿物を定量的に集める操作に注意しないと,その操作だけで容易に5%ぐらいの誤差を生ずるという2).このような理由から,遊離型コレステロール測定法の簡易化が進められLieberman-Burchard反応によるHoeflmyer-Fried法3)やKiliani反応を利用したRosenthal変法による遊離型コレステロールの直接測定法4)が出現した.
新しい機器の紹介
臨床用クロライドカウンターによる体液クロール定量法
著者: 片柳典子 , 水野映二 , 中島徹
ページ範囲:P.537 - P.540
調節ツマミと電解フローセル・システムをクロライドカウンターに導入し,実用的な装置に改良した.本法が,特に従来のSchales-Schales法に比較してすぐれている点は,次のとおりである.
(1)試料の色調に関係なく測定可能である.
(2)用手法でよく起こる終末点の個人差が解決され,測定値が客観的である.
(3)アルカリ性尿,着色,混濁試料においても,本法では前処理なく正確な定量が可能である.
(4)精密度,正確度が向上し,試料の微量化とともに,フローセルの導入により能率化することができた.
霞が関だより・2
衛生検査所の登録制度
著者: A.H.
ページ範囲:P.541 - P.541
衛生検査所とは,臨床検査センター,衛生検査センターなどとそれぞれ名称は異なるが,いわゆる臨床検査施設であって,開業医,学校,事業所などから委託を受けて検査を行なう施設である.
衛生検査所は昭和30年代の後半からしだいに全国的に増加してきたようである.これらの年次別の正確な数は必ずしも明らかでないが,医療需要の増加と医療従事者の不足に加えて,臨床検査技術の高度化,多様化が多くの開業医に臨床検査の相当部分を他に委託する傾向を生じさせ,これが衛生検査所数の増加となって表われてきたものと考えられる.これらの衛生検査所の設立の目的,態様はさまざまであり,検査技術や精度管理の面からみてもかなりの格差が見受けられ,現にその検査結果が十分でなかったため,医療事故を生じたケースもあったほどである.
質疑応答
血球計算|R/X|管理方法について
著者: H.N生 , 新谷和夫
ページ範囲:P.542 - P.542
問 |R/X|の正常限界(血色素4%,赤血球8%,ヘマトクリット3%,白血球20%)として記された数値は,新谷らは経験的なものと「臨床病理」臨時増刊(特集第18号)‘精度管理の実際と評価’に発表してますが,正常限界の算定方法と目視算法での利用価値および目視算法での正常限界の算定方法も,同じ要領で実施すればいいでしょうか.
検査技師のための解剖図譜・5
膵臓・十二指腸
著者: 三島好雄
ページ範囲:P.544 - P.545
膵は上腹部にあって後腹膜におおわれ,長さ14-16cmの横に細長い臓器で,頭部,頸部,体部,尾部に区分されでいる.十二指腸は膵頭部をかかえこむようにC型に彎曲し,長さ約30cmで大部分が後腹膜腔に固定されている.十二指腸は上水平部,下行部,下水平部,上行部の4部に分けられる.十二指腸の上水平部は消化性潰瘍の好発部位であり,またX線的に球部(Bulbusduodeni)と呼ばれている.十二指腸下行部には総胆管と膵管が開口する.膵管には主膵管(ductof Wirsung)と副膵管(duct of Santori)の2本があり,主膵管は総胆管とともに大十二指腸乳頭(ファーター乳頭)部に開口し,副膵管はその上方2-3cmのところで,小十二指腸乳頭部に開口する.膵管が総胆管と合流する部分はファーター膨大部といわれているが,膵管と総胆管との関係は非常に個体差があり,膵管と総胆管が別々に十二指腸に開口するものもある.
膵の前方には胃および横行結腸,背面には門脈,上腸間膜動静脈,左腎動静脈,腹部大動脈および下大静脈がある.また膵と平行しで,その背面を脾動静脈が走る.
検査機器のメカニズム・5
血圧計(観血式)
著者: 瓜谷富三
ページ範囲:P.546 - P.547
1.血圧計と圧力トランスジューサー
血圧を測るには,一般に腕帯と圧力計を使うRiva Rocciの聴診法が用いられているが,ここで述べるのは,直接血管にカテーテルや注射針を挿入して測定する観血式電気血圧計である.一般的な構成は図1のとおりで,この中で圧力トランスジューサーは圧力を電気信号に変える重要な機能をもっている.圧力トランスジューサーは今まで多くの種類が発表されたが,現在は抵抗線歪ゲージを使うものが代表的である.また最近では,半導体歪ゲージのトランスジューサーもいくつか見られるようになった.
抵抗線歪ゲージの原理は簡単で,抵抗線に弾性限界内で力を加え伸長させると抵抗値が増すことを利用するもので,圧力計の場合は受圧膜に作用するわずかな力を抵抗線に伝えている(図2).
検査室の用語事典
一般検査,血液学的検査
著者: 寺田秀夫
ページ範囲:P.548 - P.549
26) Nephron;ネフロン
腎の機能的単位で,糸球体とこれを入れているボーマン嚢からなるマルピギー小体と,これに連なる尿細管よりなる.尿細管は主管→近位尿細管→ヘンレ環→遠位尿細管→集合管に分けられ,その長さは50mmに及び,両側腎の尿細管の全長は約70マイルに達する.
Senior Course 生化学
尿および尿中ポルフィリンの定量
著者: 坂岸良克
ページ範囲:P.551 - P.551
先天性ポルフィリアをはじめとしてポルフィリンの定量を必要とする疾患は少なくない.日本では20数例の先天性ポルフィリアが発見されているが,これは北欧に比べると1/10である.人種上の差がその理由であるかもしれないが,定量の不十分なためということも考慮しなければならない.そこで,尿および尿中ポルフィリンとその誘導体であるALA(δ-アミノレブリン酸),PBG(ポルホビリノーゲン)の定量についてまとめてみる.
ポルフィリンはコハク酸とグリシンからALAを経てPBGとなり,重合してウロポルフィリノーゲン(UPG)コプロポルフィリノーゲン(CPG)からプロトポルフィリン(PP)になる.UPGは図のUPと同じくピロールの8個の角に-COOHをもつが,7,6,5,4(CPG),3,2(PP)と1個の-COOHをもつ8種のポルフィリンは薄層クロマトグラフィーで簡単に検出分別される.この場合使われる展開剤は次のようなものである.
血液
血小板第3因子能(1)カオリン活性化法
著者: 安永幸二郎
ページ範囲:P.552 - P.552
血小板には止血凝固に関与する多くの因子が含まれているが,トロンボプラスチン形成に関与する因子は血小板第3因子と呼ばれる.血小板第3因子は血小板の脂質タンパク分画に含まれ,phosphatidyl ethanolamine(セファリン),phosphatidyl choline(レシチン),phosphatidyl serineなどのリン脂質成分からなる.大豆のリン脂質や脳のリン脂質でも同様の作用を示し,このような血小板第3因子を代用するリン脂質は,組織トロンボプラスチンに対して部分トロンボプラスチンと呼ばれる.近時血小板第3因子の作用はその粒子が血漿凝固因子の反応に触媒作用面を提供するものと考えられている.
血小板第3因子の検査で心得ておくべきことの第1点は血小板第3因子の検査には血小板から放出された活性をみる血小板第3因子能と,血小板を破壊することによって血小板内の第3因子量のトータルを測定する2つがあるということで,第2点は血小板第3因子能検査にはカオリンを加えて血小板に接触—活性化を行ない,第3因子の放出を起こさせる方法(カオリン活性化法)と,トロンボプラスチン形成試験法(トロンビンが血小板に作用すると考えられる)があるが,この両者は多少意義が異なるということである.カオリン活性化法にはカルシウム再加時間法(Hardisty&Hutton)とStypven時間法(Spaet&Cintron)がある.
血清
α-フェトプロテイン
著者: 稲井真弥
ページ範囲:P.553 - P.553
現在までに癌の免疫学的な診断法として考案され発表されたものは多数あるが,そのほとんどのものは理論的な根拠があいまいで,癌の診断法としての特異性も低く,実用化されるに至らなかった.最近原発性肝癌の診断法として注目されてきたα-フェトプロテイン(αf)の証明は,免疫学的な手法を応用した癌の検査法として実用化された最初のものである.
細菌
Proteus属の鑑別と分類—フェニールァラニン脱アミノ反応を中心として
著者: 橋本雅一
ページ範囲:P.554 - P.554
Proteus属は,腸内細菌の中でもいくつか独特な性状を示す1群の菌で,BergeyのManual(第7版,1957)では,1属5種(Prot. vulgaris,Prot. mirabilis,Prot. morganii,Prot. rettgeriとProt. inconstans)に分類されている.この菌属がほかの腸内細菌と鑑別される主要な性状は,フェニールアラニンの酸化的脱アミノ反応によるフェニールピルビン酸(PPA)の産生と,リジンの脱炭酸反応である.
したがって,この菌属の鑑別には,まずこの2つの性状の検査が行なわれなければならないはずであるが,ルーチンの検査にはまだほとんど採用されていないようである.その理由としては,ふつう用いられる非選択培地(たとえばBTB乳糖加寒天)では,この菌属の多くが特有な遊走を示すし,また胆汁酸塩加培地(たとえばSS寒天)でも集落の性状からこの菌属の鑑別が容易に行なわれることが多く,確認培養でもその尿素分解性などの性状から,その確認が容易であるということがあげられよう.しかし,遊走現象はH型菌では著明であっても,発育してきた菌株がO型菌であれば,遊走の有無はこの菌属の推定には役だたない.また,SS寒天でのH2S産生による特有な集落性状も,Prot. mirabilisではこの性状を欠くものがしばしば出現するので,この菌属の推定には絶対的な基準とはならないであろう.
病理
硬組織と器械(1)
著者: 桔梗辰三
ページ範囲:P.555 - P.555
系統的にせよ局所的にせよ,骨そのものの検索が主目的の場合は,自ら臨機応変の処置をとらなければならないが,一般的剖検に伴う手技としての硬組織の取り扱いを述べる.
硬組織処理に用いられる機器にはノコギリ,ハサミ,タガネ,ナイフ類と脱灰装置がある.ノコギリには主として剖検時骨組織切除に用いられる手動または電動(リプショーなど),大きな骨を処理する電動帯鋸(マキタバンドソー)などがある.剖検用電動鋸は小型の丸ノコギリの形をしているが,1分間約3万回の小さな振動により硬いものを細かく砕きながら切断する.用途に応じて各種の形がある.付属品としてスタンド,足踏スイッチ,鋸削吸引器などがある.骨専用の帯ノコは見あたらないが,プラスチック加工用の帯ノコに目の細かい,薄い刃を作ってとりつけるとよい.
生理
計測用体表電極(2)—電極材料の電気化学的性質
著者: 深井俊博
ページ範囲:P.556 - P.556
われわれが電極を用いる場合,電極に起因するいろいろな問題に出合う.たとえば電極のサビ,記録基線の動揺,ペンの振り切れ,ハムの混入,脳波の左右差などである.これらは電極電位の安定性,分極電圧や電極インピーダンスの大小と密接な関係がある.実際にはこれにペーストの種類,温度などの因子も加わり原因は複雑となる.前に電極の電気化学について若干説明したが今回は特に実際的な問題をとり上げながら電極材料の電気化学的性質を考えてみる.
業務指導のポイント
検査機器購入時のポイント
著者: 井上正三
ページ範囲:P.557 - P.557
神戸市医師会臨床検査センターでは発足以来約10年を迎え,取扱件数も1か月約7万件を数えるようになり,検査センターの従事者は約80名を数えている,最近になって考えることは,いかにして省力化するかということで,これは機械化によるのが現在の方法であることはもちろんであり,1966年ごろより機械化に取り組んできた.検査機器購入時に最も関心をはらわねばならないのは,故障による検査の遅れであり,また精度はどうか,試薬使用量の増加,検体の増加をも考えねばならない.この中で最大の関心事は故障の有無である.ここにわれわれ検査センターにおける過去の故障の,また補修の回数を調査してみると次のとおりである.
1)オートアナライザー(4-5年使用)
基本情報
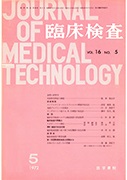
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
