従来,消化管,ことに回腸末端部における非特異性限局性腸炎,回腸終末炎(Ileitis ter-minalis)またはクローン病(Crohn's disease)と呼称される腸壁の好酸球蜂窩織炎に関して,他方胃における同様の病理所見の本態についても多くの議論がなされてきたが,近年これに関して新しい話題として提供されたのがこのアニサキス症(anisakiasis)である.アニサキス(Anisakis)というのは海獣(クジラ,イルカ,アザラシなど)の胃に寄生する回虫の名称であり,その幼虫がヒトの消化管に穿入し,上記の病理組織学的所見を特徴とする寄生虫性肉芽腫症を呈するものである.その成因に関しては別に解説するが,ヒトがアニサキス幼虫を包蔵する種々の海魚(サバ,スケソワダラ,スルメイカ,アジなど)の生食に際して,幼虫がヒトの胃または腸壁につきささり,胃潰瘍,胃腫瘍,急性腹症などの臨床症状を発現するもので,その病理診断は好酸球肉芽組織内に断端としてみられる特有な幼虫形態の寄生虫学的診断に待たねばならない.
雑誌目次
臨床検査16巻7号
1972年07月発行
雑誌目次
カラーグラフ
技術解説
フィラリア症の検査
著者: 田中寛
ページ範囲:P.683 - P.692
わが国のフィラリア症はおもに奄美大島,沖縄に分布し,そのほか九州,四国の一部に浸淫地が知られていた.1962年から始まった厚生省のフィラリア駆除対策により,各地のフィラリア保虫者は激減し,奄美大島ではかつて陽性率が10%を越えていたのに,今日では保虫者をみつけるのが困難なほどに減少した.沖縄でも陽性率30%もの部落があったが,今日では著しく低率になっている.
一方,慢性のフィラリア症はまだ見られ,象皮腫,陰嚢水腫,乳糜尿の患者は旧浸淫地域ばかりでなく,都市の病院でもしばしば遭遇する.フィラリア症の確定診断は末梢血液からミクロフィラリアを検出することによるが,この検査はひんぱんに行なわれるものではないので,適切な方法で検査が行なわれていないのが現状である.
リゾチーム(ムラミダーゼ)の簡易測定法—白血病の鑑別診断のために
著者: 桑島実 , 河合忠
ページ範囲:P.693 - P.701
最近,白血病の分類,ことに単球性白血病の補助診断の1つにリゾチームの測定が注目され,白血病の治療効果および予後の判定や腎疾患,消化管の潰瘍性疾患などの診断にも意義があると言われている1-3).
1907年Nicolleがニワトリ卵白中に溶菌作用のある酵素の存在を予想したが,リゾチームに関する最初の記載は1922年Fleming4)による.当時ロンドンに流行していた感冒にかかった彼は,自分の鼻汁を細菌培地に落としてみたところ,ある種の細菌では溶菌現象の起こることを見いだした.鼻汁以外に涙,血漿,喀痰,膿その他の体液成分,パパイヤや卵白にもこの現象がみられたことから,溶菌作用のある酵素様物質という意味でリゾチーム(Lysozyme)と名付けた.同時にリゾチームに対して最も感受性の高い細菌としてMicrococcus lysodeikticusを分離した.
アニサキス症—その病理診断を中心に
著者: 吉村裕之
ページ範囲:P.702 - P.707
消化管にみられる好酸球肉芽腫形成炎は,回腸末端炎,またはクローン病とも呼称されるものもあり,また胃における好酸球蜂窩織炎についても先人により多数の報告がなされている.その本態については議論が多く,この中には病巣内に病理組織学的に寄生虫体の断端が見いだされたとの記載がなされているものがある.わが国においてもすでに塩田(1940),工藤(1951),砂原(1954)らの報告で,腸壁の好酸球蜂窩織炎の所見の中に幼若回虫(?)の断面を認めており,胃においても越家(1954),村上(1960),内山ら(1961)らは幼線虫の断面が認められたとしている.
近年これらの病因論に新しい問題の提起がなされた,アニサキス症である.この直接の動機となったのはオランダのVan Thiel (1960-62)であって,氏らはロッテルダム近郊で11名の急性腹症を訴えて外科的に手術された患者の小腸病巣部から,ある種の幼線虫を見いだし,この寄生虫はこの地方で多量にとれるニシンに寄生するEUS-toma rotundatumであろうとした.同時に患部はいずれも好酸球肉芽組織であることを明らかにした.後日,彼はこの幼線虫は実はアニサキス(Anisakis)であると訂正し,本症をアニサキス症(anisakiasis)と呼称すべきであると述べている.オランダにおける患者の多くは漁夫で,ニシンの生食または不完全料理によってこの幼線虫が消化管壁に穿入して起こったものと推察した.
私のくふう
TPHAトレイのマークと混和
著者: 渡辺茂夫
ページ範囲:P.701 - P.701
梅毒血清反応のスクリーニングにTP感作血球凝集反応が使用されるようになってきた.また甲状腺抗体検出法にも赤血球凝集反応がある.今後これらの検査が多く使用されるようになってくるものと思われる.
私は,この反応検査を行なううえで常に次のような点について,どのような方法を取り入れると,より確実な検査ができるだろうかと考えていた.その1つに,トレイに検体を分注する際,検査台の色や台紙などでホールが光って,時々検体のはいったホールにまた検体を入れるなどして困ったので,トレイに移動するマークを思いついた.未感作血球のふたは色も目立ちやすい.ホールとホールの間に置いて右または左の方向に移動しつつ分注すると,まちがえることがなくなった(図1).
病理組織標本固定容器
著者: 鈴木盛雄
ページ範囲:P.742 - P.742
組織および臓器の固定は,組織標本作製のたいせつな第1歩であるから,組織を取り出したら,迅速かつ簡易に十分なる固定が必要である.
従来,組織および臓器を写真撮影,くぎによる張り付け,固定液に浸漬していたが,金属が腐蝕し,さびが組織中に溶出,浮き上がり,固定液が均等に浸透せず,変質しやすく,変形,部分的組織の収縮,細部構造の破壊,自家融解が起こり,標本所見に悪い影響を与えるなど,種々欠陥があった.
総説
分子状酸素の動態
著者: 井川幸雄
ページ範囲:P.708 - P.713
われわれは約80%の窒素と約20%の酸素と0.03%の炭酸ガス,その他からできている‘大気’という海の底に生きていて,絶えず酸素を取り入れ,炭酸ガスを放出するという物々交換をしながら生きている,そして動物が地球上に発生して以来,この物々交換を休むことなくくり返して(栄養素のように体のいくばくかの貯えをもつことなしに)生きてきたのである.
呼吸というのは,この大気から肺胞を介して酸素を受け取り,これを血流によって体の細胞まで届け,その帰りに細胞から放出された炭酸ガスを肺に運び,これを大気中に放出する過程である.
臨床検査の問題点・42
糞便の寄生虫卵
著者: 鈴木了司 , 森雄一
ページ範囲:P.714 - P.720
近年,わが国の寄生率は著しく低下しているが,その反面珍しい虫卵の検出もかなりある.ここでは,セロファン厚層塗抹法やTween 80クエン酸緩衝液法を取り上げ,また類似している虫卵の鑑別,紛らわしい物との見わけ方など,検査室での問題点を具体的に検討する.(カットは肝吸虫卵)
ME機器の安全対策・7
生理検査室における安全対策
著者: 本間伊佐子 , 石山陽事 , 江部充
ページ範囲:P.721 - P.725
生理学的機能検査が広く行なわれるようになり,各種のME機器が使用されてきた.心電図,心音図,脳波,筋電図,脈波,超音波,基礎代謝,各種の呼吸機能などの検査に,それぞれ独立した単能機器が用いられるばかりでなく,さらに高度の複雑な機能検査も要求され,そのためには種々の機器を組み合わせて使用することも多い.したがって機器が複雑化してゆく傾向にあるが,必要性に応じて最小限の組み合わせで使用することが望ましい.むやみに装置を複雑化したり大型化したりすることは機能面と,人体安全性の立場から避けたいものである.機械が複雑になればなるほど,安全性について考慮をはらわなければならないことは当然である.一方,日常頻繁に用いられている機器では,これらの操作に慣れてしまって,とかく無意識的に操作してしまうために,かえって安全性がなおざりにされることもある.
生理学的検査の場合には,まず第1に患者ならびに検査に対する安全性が考慮されねばならない.次に機器に対する障害の除去に主眼がおかれる.
論壇
—病態生理に力点を—日本臨床病理学会総会を担当して
著者: 山崎晴一朗
ページ範囲:P.726 - P.727
第19回日本臨床病理学会総会を担当してその責任の重責を痛感しているところである.学会をいかに運営するかが問題であるが,最も臨床病理学会にふさわしい学会にしたいと思っている.
座談会
検査技師の見た欧米の臨床検査
著者: 藤沢武吉 , 稲生富三 , 斎藤多紀子 , 樫田良精
ページ範囲:P.728 - P.736
最近,海外旅行に出かけるチャンスがふえてきた.今月は海外の視察見学旅行をした方と留学した方に,技師の目から見たヨーロッパ,アメリカの臨床検査について話をうかがってみた.日本の検査室のあり方を考えるうえにも,また今後出かけていく人々のためにも一助となれば幸いである.
検査室の常用機器・1
高圧滅菌器—特に小型オートクレーブについて
著者: 古橋正吉
ページ範囲:P.738 - P.742
筆者に与えられたテーマは,検査室の常用機器としての‘高圧滅菌器’ということで,今後検査室などで購入する際の1つの目安になることを書くようにとのことである.
ひと口にオートクレーブといってもいろいろな種類のものがある.食品や医療品の大量滅菌工場で使う大型装置,病院の中材や手術室で使う大型,中型の装置のほかに,検査室や研究室で細菌培地の滅菌の目的に使う小型のもの(図1,2)などがある.
海外だより
—欧米(北欧,東欧,西欧,米国およびカナダ)の病院検査室(8)—アムステルダムのヴリエ大学付属病院中央検査部門
著者: 佐々木禎一
ページ範囲:P.743 - P.747
筆者はすでに7回にわたって,北欧と東欧諸国の病院検査室の訪問見学記を報告してきたが,今回から西欧の病院を対象として報告しようと思う.しかし,西欧の病院については従来も比較的見聞の機会もあったようにも感ぜられるので,そのうち珍しい3か国すなわち,オランダ,ポルトガルとイタリアの病院を紹介してみよう.この第8報ではオランダの首都,アムステルダムで見学した新装間もないCentral Clinical Chemistry Laboratory,Vrije University Hospital(ヴリエ大学付属病院中央臨床化学部門)についての概説をしてみたい.
オランダはデンマークに近いところに位置し,むしろ北欧諸国の1つとしてもみられる.したがって医療を含む社会保障機構などは,北欧の例に類似していると考えるのはきわめて当然のことであろう.またこの国を想起するとき,木の靴,チューリップ,チーズ,風車,そして運河という観光的イメージが先んじてはくるが,海抜0メートル以下にある自分たちの土地を,必死になって守っているという現実も見のがすことができない点である.
虎の門病院臨床生化学検査部での研修を終えて—息づく検査室
著者: 杉田収
ページ範囲:P.748 - P.749
筆者は,昨年3月新潟大理学部の大学院(修士課程)を卒業し,新潟の病院検査室に勤務したが,実務に先だち東京の虎の門病院臨床生化学検査部(北村元仕部長)に研修する機会を得て,6か月間実際の生化学検査に従事した.見たもの,聞いたもの,感じたもの……をなまのまま語ってもらう‘虎の門体験記’である.
第19回衛生検査技師国家試験第2回臨床検査技師国家試験—問題と解答
ページ範囲:P.762 - P.775
第2回臨床検査技師国家試験,第19回衛生検査技師国家試験は,3月19日(日)全国8か所(東京は立教大)にて実施された.前者の受験者は,3年制の検査技師学校と大学の薬学部・獣医学部卒業生(指定科目修了)らで,第1回の約1/3であった.
受験者数は‘衛検’が2765人,‘臨検’が3688人,合格者数はそれぞれ2183人,(79.0%),2795人(75.8%)であった.ここに例年どおり全問題(‘衛検’は1-11,‘臨検’は1-15)と解答を掲載する.次回は10月実施予定.
研究
色素結合基質(Blue starch polymer)によるアミラーゼの微量測定について
著者: 松尾武文 , 石浜義民 , 瀬合秀昭 , 池田寿江
ページ範囲:P.750 - P.752
血清および尿のα—アミラーゼ活性の測定に,不溶性デンプンに色素を結合したchromogenic法(色素原法)が最近注目されてきた1).今回,私たちはBlue starchpolymerを基質としたchromogenic法について検討を加えた.まず測定操作の微量化を試み,それに伴う反応条件についての改良を行なった結果,微量法でも著しく精密度を向上することができたので以下に述べる.
新しいキットの紹介
RPRの梅毒検査における実用性の検討
著者: 金丸佳郎 , 有泉昇 , 保坂みさ
ページ範囲:P.753 - P.755
梅毒の血清学的反応(補助診断法)としては,脂質抗原(Cardiolipin-Lecithin抗原)を用いた方法と,トレポネーマ抗原を用いた方法とがある.わが国で広く行なわれている方法には,前者として緒方法,凝集法,ガラス板法(Serologic Tests for Syphilis;STS),後者としてFTA-ABS法(Fluorescent Treponemal Antib-ody-Absorption Test),TPHA法(Treponema Pa-llidum Hemagglutination),RPCF法(Reiter ProteinComplement Fixation)がある1).多くの検査機関では脂質抗原を用いたSTS3法を行ない,その陽性血清について,TPHA法を実施しているようである.また,保存血液の厚生省生物学的製剤基準2)によれば,STSのうち沈降反応,補体結合反応,各1法を実施すればよいことになっている.
これら広く用いられている脂質抗原による方法は,抗原の調整,検査器具の整備など,種々の問題があり,スクリーニングに使用されるガラス板法といえども例外ではない.各法の梅毒に対する特異性は,STS3法を併用して85%,TPHA法,FTA-ABS法は98%以上である3).
体液アミラーゼ新測定法の検討—特に正常値について
著者: 玄番昭夫 , 下山智恵子 , 尾内紀子
ページ範囲:P.756 - P.761
はじめに
アミラーゼ(α-amylase,α−1,4-glucan 4-glucano-hydrolase,3.2.1.1)の活性測定法は,その原理から大別すると次の3種に分類できる.
(1) Amyloclastic法
ひろば
医療器具の創意・くふうに思う
著者: 大竹敬二
ページ範囲:P.775 - P.775
近年各種医療器具の出現が多く,目を見張るばかりである.去年医療器メーカーが医学会総合医器展でアイディア募集を行なったところ,400件以上も全国から集まったというから驚きである.まさに医療器アイディア時代の感がする.当然医療器に関する創意・くふうであり,日ごろからの医療器に対する関心の表われであると理解する.
この中には組織中の専門家が入れ替わり立ち替わり試みて完成したものは少なく,地道な検査生活を送りながら,長い期間に少しずつ前進し,作りくふうされたものが多いことを思うと,感謝しなくてはいけないと思う.
霞が関だより・4
春の国家試験から
著者: A.H.
ページ範囲:P.777 - P.777
1.春の国家試験
第2回臨床検査技師国家試験と第19回衛生検査技師国家試験は,去る3月19日全国8地区においていっせいに施行されたが,その合格者が4月27日に発表された.
両試験の受験者数,合格数および合格率はそれぞれ次のとおりであった.
質疑応答
グラフ
米・英の医療機器展から—自動化・高度化の進む臨床検査機器
著者: 高原喜八郎
ページ範囲:P.779 - P.782
アメリカの‘最新メディカルエレクトロニクス展…’が2月22-27日に,イギリスの‘英国の医学と医療機器展’が2月28日-3月6日まで,相次いで東京で開催され,臨床検査に関連深い機器も数多く展示された.
質,量ともに見過ごせない機種の多い中で,出品物の特徴を要約すると,アメリカ展では奇抜なアイディアに基づく新方式のものや,高度に洗練されたコンパクトデザインの製品が多かった一方,イギリス展では,自動分析技術の中で最後まで自動化が取り残ざれている血清の遠心分離操作を,常識的な手段で自動分析システムに導入した成果が示されていたことからも,奇に走らず地道な努力をつづけるお国柄が製品群にも表われていた.
検査技師のための解剖図譜・7
小腸・大腸
著者: 三島好雄
ページ範囲:P.784 - P.785
小腸の長さは平均5-7mで十二指腸,空腸,回腸に区別される.しかし,ふつう小腸という場合には空腸と回腸を意味する.これに続く大腸は平均1-1.5mの長さで盲腸,上行結腸,横行結腸,下行結腸,S状結腸よりなる.十二指腸は幽門輪により胃と境され,十二指腸曲によって空腸と境されている.空腸は漸次回腸に移行するが,空腸は全小腸の2/5を,回腸は3/5を占めている.回腸と大腸の境にはBauhin弁がある.盲腸は小腸移行部より下方にある盲嚢で,最も太く,その下端に虫垂を有し,上方は上行結腸に移行する.
上行結腸,横行結腸,下行結腸は小腸を取り囲むように腹腔内を右から左に走り,左下腹部で屈曲してS状結腸となり,直腸に移行する.腸管の太さは十二指腸が最も細く,大腸が最も太いが,小腸の粘膜面にはひだが多数にあり,さらに無数の絨毛があるので,その表面積は著しく広い.腸管は内面から,粘膜,筋層,漿膜の3層よりなるが,多くのLieberkühn腺とリンパ小節を有する.
検査機器のメカニズム・7
眼振計とエレクトロレチノグラフ
著者: 瓜谷富三
ページ範囲:P.786 - P.787
1.眼振
眼振計は眼球運動記録装置の1つで,前庭器官を刺激したときに生じる眼振の記録に耳鼻科領域で使われるほか,眼球運動系・脳神経系の検査にも活用されている.
眼振計による眼球運動検出の方法は図1のとおりである.眼球には角膜網膜電位があって,目が動くと周囲の組織に電界変化を及ぼす.これを電極で検出するが,暗室内や閉眼中の眼振を取り出し,被検者に苦痛がないのが,この方法の特徴とされている.
検査室の用語事典
一般検査,血液学的検査
著者: 寺田秀夫
ページ範囲:P.788 - P.789
38) Schistosoma mansoni;マンソン住血吸虫
カリブ海沿岸地方や南アフリカに多くみられ,長さは雄1cm,雌1.6cmで,虫卵は糞便に,まれに尿,肝生検,直腸生検材料から発見される.大腸下部の腸間膜静脈に好んで寄生し,出血性腸炎を起こし,また肝膿瘍なども形成する.
Senior Course 生化学
ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ系を利用する尿酸の定量法とその自動化
著者: 坂岸良克
ページ範囲:P.791 - P.791
血清および尿中の尿酸の定量法はほとんどFolin法によっている.すなわち,Brownの試薬に含まれるリンタングステン酸をアルカリ性下で尿酸により還元し,生じたタングステンブルーを660nmで比色する.しかし,この方法は少なからぬ問題点をもっており,白濁が加わったり,服用している薬物の干渉を受けたりする.このために特異性の高いウリカーゼを利用する方法が導入され,292nmで比色するUV法はオートアナライザー法にも取り入れられている.
ウリカーゼは図の(1)のように尿酸を酸化してアラントインにする酵素であるが,その際同時にH2O2が生じる.Lorentzら1)やDomagkら2)は血糖の酵素法を応用して,この反応にペルオキシダーゼ・o—ジアニシジン系を組み合わせ尿酸定量法とした.Kageyama3)は井川らのカタラーゼ・メタノール系を利用したHantz反応によって尿酸を定量する方法を報告している.このようなくふうは日常検査に携わっていると時々頭にひらめくものであるが,十分な検討をするひまもなく見のがしてしまうこともあろう.最近,GochmanとSchmitz4)は還元物質の影響を受けない酸化反応を組み合わせて尿酸定量法とし,その自動化法を報告したので紹介する.
血液
巨核球
著者: 安永幸二郎
ページ範囲:P.792 - P.792
巨核球が血小板の母細胞であることに異論はないが,巨核球から血小板が産生される様式に関してはなお十分には明らかではない.一般には巨核球細胞質で顆粒の集塊形成に続いて分界が行なわれ,血小板として分離するものと信じており,近時これを裏書きするような電顕像も報告されている.骨髄中の巨核球の状況を知ることは,血小板病態の診断や治療において重要な意味をもっている.
血清
多発性骨髄腫(1)
著者: 稲井真弥
ページ範囲:P.793 - P.793
多発性骨髄腫(Multiple Myeloma;MM)は免疫グロブリンを産生する形質細胞系の腫瘍性増殖をきたす疾患で,その病態生理が明らかでなかった1930年ごろまでは,診断は剖検あるいは腫瘤の生検によってなさていた.すなわち肉眼的な骨の変化や生検材料による形質細胞の異常増殖など,形態的な変化を見いだすことに検査の重点がおかれていた.1937年,Tiseliusによって電気泳動法による血清タンパクの研究が開発されて以来,MMにおけるγ—グロブリンの異常が注目され,その後免疫化学の進歩によって免疫グロブリンの構造が解明されるにつれて,MMは免疫グロブリンの異常をきたす疾患であることが明らかとなった.そして免疫グロブリンの検査法が進歩した今日では,MMはそれほど珍しい疾患ではなくなった.
細菌
Alkalescens-Dispar菌群
著者: 橋本雅一
ページ範囲:P.794 - P.794
1918年F.W.Andrewesは,赤痢患者の大便から分離され,少なくとも赤痢の原因と関連づけて考えられていた菌群のなかに,インドール反応陽性,MR試験陽性,V-P反応陰性で,グルコースのはいったシモンズの培地では発育するが,クエン酸のはいったシモンズの培地では発育しないという性状のほかに,尿素非分解,ゼラチンを液化しない点で大腸菌にかなり似てはいるが,運動性がなく,またガス発生がないという点で赤痢菌とも似ている性状をもつ腸内細菌が混入していることを見いだした.いわば,生化学的にはこれらの菌群は,大腸菌と赤痢菌の中間の性状をもっていた菌群ということになる.当時,真の赤痢菌としては,ShigelladysenteriaeとSh.Plexneriの2菌種が知られていたにすぎなかったが,このような菌群をも赤痢菌あるいは赤痢菌群とみなすかどうかは病因学的に重要な問題であった.Andrewesは,これらの菌群が赤痢菌そのものに対する抗血清によって凝集されないこと,酸凝集反応でも真の赤痢菌とは異なってほとんどが凝集すること,またペプトン水でのアルカリ産生の速さやあるいはウサギに対する発病性の違いなどの点から,これらの菌群を赤痢菌とはっきり区別し,このうち乳糖非分解の菌株をBacterium alkalescens,乳糖遅分解の菌株をB.disparと呼ぶことを提案していた.
その後,赤痢菌の性状についての研究がすすみ,血清学的分類が行なわれるようになっても,その生化学的性状の類似性から,前者はSh,alkalescens,後者はSh.disparと呼ばれていた時代もあった.しかし,腸内細菌の生化学的性状がさらに詳しく検討されるようになって,これらの菌群は,(1)サリシン発酵性,(2)muca-te発酵性,(3)リシン脱炭酸反応陽性などの性状を示すことから,生化学的にもこれらの菌群を赤痢菌属として分類することに疑問が生じていた.
病理
録音・再生機の活用
著者: 桔梗辰三
ページ範囲:P.795 - P.795
剖検,切り出しおよび病理組織学的検査では書類の作製がぼう大な時間と労力を要する.その能率向上をはかるうえで種々のくふうがなされているが,その1つとして所見を記載する際,見たものをその時その場で文章にするのが望ましい.口述文章を録音し,あとで書類に直すと検索中は目を離さずにすみ,長いまたは詳細な文章を作ることに苦痛を覚えないので,より正確にして緻密な所見が残せる.
このような理由で種々の録音兼再生機を使用してみた.現在使用中の機械は多少の不満は残るが,それを紹介したい.ソニー製のSective BM−30を本体とするカセット式テープレコーダーで,種々の付属品がある.本機の使用法はデクタフォン,ビクタフォンテや他のテープレコーダーと根本的な差はない.
生理
インピーダンスプレチスモグラフと電極
著者: 栗沢貫治
ページ範囲:P.796 - P.796
心電図や脳波は生体内に発生した電圧を導出して増幅記録するものであるが,生体を電気的導体とみなし,そのインピーダンスを測定して血流や呼吸の状態を知ろうとする装置がインピーダンスプレチスモグラフである.インピーダンスプレチスモグラフ(以下,IPGと略)はまだあまり臨床的に利用されてはいないが,血流の定量的計測,肺疾患の診断など諸方面から研究が進められており,将来は一般的な検査手段となる可能性がある.今回はこのIPGの原理とその電極について概説したい.
業務指導のポイント
新しいキットの検査手順—正しい評価のために
著者: 佐々木禎一
ページ範囲:P.797 - P.797
新しく開発された,あるいは市販される試薬キットの評価を目的とした検討は,依頼されたか否かにかかわらずユーザーにとっては不可欠なことである.
検討の結果得られた成績は,そのキットの評価に直結するので,必要な検討項目をあらかじめ明確にしておくべきである.検討の程度も多種多様にわたるが,筆者らの実際例を中心に実施すべき事項と成績の解釈のしかたについて,以下記述してみよう.
基本情報
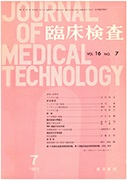
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
