赤血球系と識別できる細胞のうち,最も幼弱なものは前赤芽球と呼ばれる.この細胞が骨髄の中で次第に成熟するにつれ,漸次,青染性赤芽球,多染性赤芽球の過程を経過し,ついに正染性赤芽球となり,次いで核を失い,網赤血球に変わり,ある期間を骨髄中で過ごしたのち,末梢血液にはいり,1-2日経つと成熟赤血球ができ上がり,以後平均120日間血管内を流れて,酸素運搬という赤血球系細胞本来の役割を果たす.
ここでは,血液学的に正常な患者から採取した骨髄穿刺液および末梢血液の塗抹標本に,ライト染色を施した場合の赤血球系細胞を,最も幼若な前赤芽球から終末細胞の赤血球まで,成熟の順に従って並べてみた.
雑誌目次
臨床検査16巻8号
1972年08月発行
雑誌目次
カラーグラフ
赤血球系細胞の形態—I.正常像
著者: 野村武夫
ページ範囲:P.804 - P.805
技術解説
エリスロン(赤血球系)細胞の形態学
著者: 野村武夫
ページ範囲:P.807 - P.814
エリスロン(erythron)とは,‘血管内を流れる赤血球およびこれのもとになる骨髄中の細胞によって構成される組織’と定義される概念である1).すなわち,赤血球および赤芽球を一括して組織とみなすわけであり,赤血球と赤芽球の機能的なつながりを強調するのに便利な用語である(図1).
エリスロンは被検材料を容易に入手できるという特徴があり,したがって,血液疾患に限らず種々の病態において,形態学的にどのような変化を生じるかがよく知られている.ここでは,エリスロンに属する細胞の形態学についての解説が主旨であるが,まず,エリスロンの最終産物となっている赤血球が製造されるまでの過程に言及しておくことにする.このような知識は,形態学に対する理解を深め,また,興味をいっそう増すのに役だつと考えるからである.
骨髄穿刺液からの切片標本作製法とその見方
著者: 神山隆一 , 斎藤菊蔵 , 牧野三四子 , 伊東佐知子 , 折笠美枝
ページ範囲:P.815 - P.820
1929年Arinkin1)により始められた骨髄穿刺法は,血液疾患をはじめ種々の疾病の際に欠くべからざる検査法の1つとなっている.
この骨髄穿刺において,有核細胞数および塗抹標本からのみでは,末梢血が混入したために,一見細胞数が少なく見えるのか否か判断困難な場合が少なくない.この際,同時に骨髄組織標本を作製することにより,骨髄が真に低形成であるのか否か,またその程度,逆には過形成の状態なども正確に知りうるのである.
酵素を扱うための基礎知識
著者: 山下辰久
ページ範囲:P.821 - P.825
生命現象は,網目状に組み合わさった多種多様の化学反応が,酵素の触媒反応により円滑に行なわれているといっても過言ではない.すなわち酵素は生命活動の直接のにない手であり,したがって酵素の研究は生命現象の解明に重大な役割を果たしている.
一方,酵素化学の進歩に伴い,身体の病的現象が酵素系の変化と密接な関係があることが明らかとなり,酵素の活性およびその他の諸性質の検索が疾患の診断,予後あるいは治療効果の判定に有力であることが判明するにつれ,体液(血液を含めた)中の各種酵素の活性測定が,疾病の診断の目的のために生化学検査のうえで重要な位置を占めるようになった.
総説
嫌気性菌感染症
著者: 鈴木祥一郎 , 二宮敬宇
ページ範囲:P.826 - P.831
無芽胞嫌気性菌が人体の常在菌としても,また病原菌としても,重要であることがしだいに認められてきた.しかし,現在の嫌気性菌の研究は,好気性菌に比べいろいろの点で遅れている.すなわち,分類,同定法,病原性,薬剤感受性テストなどにつき,統一された見解が必要で,その完成が待たれる.
私のくふう
スピッツの整理箱
著者: 宮脇良樹
ページ範囲:P.831 - P.831
従来,大小のスピッツ,ウィダール試験管の整理・格納には実験台の引き出し,木箱などを使用している検査室が多い.これは,スペースを広くとり整理に不便であり,古いものはほこりがたまりやすく,いざ大量に使用するときには不便である.
そこでパチンコ台にヒントを得,このようなスピッツ格納箱を考え,現在使用している.
培地保存の湿潤箱
著者: 萩原武夫
ページ範囲:P.890 - P.890
細菌の分離,同定または感受性試験を実施するときに,培地を従来のように冷蔵庫に長期間保存すると,冷蔵庫の脱湿作用のため凝固水がかれて細菌の発育が不十分であったり,新鮮な培地に比べ硫化水素産生能や糖分解能など,生化学的性状が変化し,正しい結果が得られなくなる.しかも,冷蔵庫には収容能力に限度がある.
そこで,私は凝固水を保ち,作製時の状態をできるだけ長く保持するための湿潤室を作り,これを室温に置いて保管する方法を考案した.
臨床検査の問題点・43
リウマチの血清反応
著者: 水谷昭夫 , 笠原和恵
ページ範囲:P.832 - P.838
血清学的検査のうちでむずかしいものの1つにリウマチの血清反応がある.検査室では,慢性関節リウマチをどう考えたらよいか,その主役であるリウマチ因子にはどんな性質があるのか,またその検出法の検討,さらには簡易検査の試薬の取り扱いにも言及する.(カットはRA試薬の電顕像:蛙の卵様の薄い被膜のcoating)
ME機器の安全対策・8
ICU・CCUの安全対策
著者: 近藤正幸
ページ範囲:P.839 - P.844
各種のME機器,医療器械が開発,実用化されて検査,診断,治療の分野で効果的な役割を果たしているが,それに加えて,PPC(Progressive Patient Care)の概念に基づく患者管理システムとしてのICU・CCUが導入され,運用されるようになって,特に治療・看護を重点的に行なう必要のある患者に対する医療効果は,一段と向上している.
また,ICU・CCUは,最新の病院設備と並んで病院近代化の重要な要素と考えられている.大学病院,官公立病院などの大病院では,その大半がすでに何らかの形態でこのシステムを運用しており,中小病院においても年々増加する傾向にある.
公害物質の検査法・1【新連載】
カドミウム
著者: 山県登
ページ範囲:P.845 - P.850
水銀,鉛,カドミウムは元素であるから消滅することがなく,廃棄物から微生物へ取り入れられ,植物,魚,ウシ,ブタなど食用となるものに移動し蓄積され,さらにヒトの体に沈着することになり,限度を越えると重篤な疾患を起こすもので,にわかに注目を浴びてきた.
PCB (パークロルビフェニル),アフラトキシン(カビ毒のうち最強力のもの)は有機物であるが,分解を受けにくく,これまた人体に侵入すると重大な病変をひき越こすもので,環境汚染の立役者となっている.
論壇
臨床検査技師の卒後教育
著者: 小林種一
ページ範囲:P.852 - P.853
臨床検査技師学校における3年間は,検査技術の理論と実際についての概要の教育を受けたにすぎない.ことに臨床病理といえば,微生物学,血清学,血液学,病理学,寄生虫学,生化学,生理学とその範囲が広く,そのうちの一部門の検査技術をマスターするとしても,かなりの期間実地修練を必要とするものばかりである.また今日の技術者に求められているのは,単に日常検査を行なうだけでなく,理論をしっかり身につけたTechnologistとなることである.
このような社会の要望にこたえるためには,少なくとも卒業直後の5年間を,自らも実技のトレーニング期間であると自覚して,きびしい試練にも堪え,積極的に幅広く勉学する気持をもってほしいのである.この5年間を充実した勉学の日々を続けることのできた人は,将来もすぐれた中堅技師として斯道を進みつづけることを信ずるのである.また新卒技師の受け入れ施設においては,十分に技術習得のできる場を提供すべきである.もし技術指導を行なうことの無理な施設であれば,一定期間,リーダーのいる施設に委託して技術研修を受けさせる必要がある.
座談会
採血業務の問題点—MTとナースの間
著者: 茂手木皓喜 , 佐々木良子 , 水戸部光衛 , 宇佐美千恵子 , 守屋博
ページ範囲:P.854 - P.861
昨年1月の法律改正により技師も採血できるようになった.採血から検査へと一本化されたことはよいが,反面,人手不足による労働強化や時間不足によるデータのバラツキなど,問題点が浮かび上がってきた.またどちらが採るかで看護婦との間にもトラブルが生じてきている.そこで今月は,採血業務はどうあるべきかを,看護婦,技師の双方から話し合っていただいた.
検査室の常用機器・2
恒温器
著者: 白戸四郎
ページ範囲:P.862 - P.865
はじめに恒温器という名前であるが,この名前の定義はそれほど一定してはいない.人によって恒温水槽を考える人もあれば,孵卵器を考える人もある.商品名としてどちらにも使われているし包括して使う場合もある.さらに,われわれが検査室で使うものばかりでなく環境試験器などまで含まれるという人もある.しかし本稿では検査室の常用機器としての恒温器ということであるから,その範囲内で包括的に考えることにしたい.
さて科学機器協会で毎年出版する科学機器総覧では媒体を液体とするものを恒温槽,空気を媒体とするもののうち乾燥を目的とするものを乾燥器,灰化・加熱を目的とするものを電気炉・加熱器,細菌培養などを目的とするものを定温器と分類している.したがってウォーターバスは恒温槽に,孵卵器,低温恒温槽,ディープフリーザーなどは定温器の中にはいる.
海外だより
—欧米(北欧,東欧,西欧,米国およびカナダ)の病院検査室(9)—リスボン(ポルトガル)のエスコラール病院中央検査部
著者: 佐々木禎一
ページ範囲:P.866 - P.869
欧州の中にあって,南西部のスペイン,さらに離れたポルトガルは,いろいろな意味で異質な国といえよう.したがってそこの病院とその中の中央検査部門の実情については,きわめてわれわれの興味をひくところである,
スペインの病院中央検査部については,すでに1969年バルセロナを訪れたおりに,サンタクルース・サンパブロ病院(Hospital de la SantaCruz y San Pablo)を見学して,その紹介を行なった1)が,今回の旅行で欧州から米大陸に飛ぶ前に寄ったポルトガルのリスボンで,強引に見学したエスコラール病院(Hospital Escolar)の様子を紹介してみたい.
欧米旅行見聞記
検査業務のシステム化
著者: 中甫
ページ範囲:P.870 - P.871
最初の訪問地ロンドンのヒスロー空港に降り立った時は,おりしも小雨で何か東京の天候を思わせるようだったが,街の古い赤レンガ建ての街並みは日本とはまったく異なり,印象的であった.私の今回の欧米旅行の目的の第1は,われわれが使用している英国製自動分析機Vickers M300のために,私が開発した血清総コレステロール測定法についてディスカッションしたい,とのビカース社の化学者グループよりの要請があったので,数日間ロンドン郊外の研究所で過ごすことであった.第2はこの機会に欧米の検査室を実際に自分の目で見て諸外国の現状を把握することで,英国,スイス,米国の検査室を訪問した.第3はコレステロール測定法で広く知られているDr.ZakおよびDr,Zlatkisの研究室を訪ねて,コレステロール測定法について語る機会をもつことだった.
はじめての海外旅行でもあったので何でも見よう,聞こう,語ろうとかなりのハードスケジュールを承知で欧米5か国をかけ足で回って来た.以下その時の印象を2,3かいつまんで述べてみたいと思う.
学会印象記
第21回日本衛生検査学会
著者: 森安惟一郎 , 桂栄孝
ページ範囲:P.872 - P.873
第21回衛生検査学会は,4月22,23日の両日快晴にめぐまれた大分市(5会場)にて開催された.演題,シンポジウムは年々その数を増し,また‘夜の自由集会’も‘夕べのシンポジウム’として内容的に高められた.科別演題数は微生物40,血清40,血液33,臨床化学75,病理8,細胞診11,生理10,尿・管理ほか16で,シンポジウムは別表のとおりである.参加者約2500人.学会長・寺田勝美(大分県衛生検査技師会長).
研究
VMA定性検査法の改良
著者: 宮川富三雄 , 丹羽正治
ページ範囲:P.874 - P.877
はじめに
尿中3-methoxy-4-hydroxymandelic acid(以下VanMy1 mandelic acid;VMA)は1957年Armstrongら1)によって検出されて以来,その定量検査法はSand1er2),Sunderman3),Gitlow4),Pisano5),三宅6)らによって改良されてきた.
一方,定性検査法は佐藤ら7)によって考案され,従来ジアゾ化パラニトロアニリン発色反応が用いられてきたが,自然排泄尿をそのまま検体として用いるかぎり,その結果は検体のpHおよび濃縮程度,反応の特異性など種々の影響によって相違する.そのため同一検体についてクレアチニン補正を加えた定量検査成績を基準として比較した場合,両者の不一致が目だち,ことに低域値においてその差が著しい.
o-トルイジンーホウ酸(o-TB)試薬の保存条件と品質変化
著者: 佐々木禎一 , 松井早苗 , 池辺正 , 越瀬博子
ページ範囲:P.878 - P.880
はじめに
われわれは増加の一途をたどる日々の血糖検査を消化する手段として,従来から使用してきたo-トルイジンーホウ酸(o-TB)試薬を用いてのオートアナライザーによる迅速測定を試み,その設定条件や実際の測定成績の評価などについてすでに報じてきた1-3).
これらの成績から日常検査法として適切な測定法であるとの結論を下すことができた.しかし同時に,解決すべき点として日差変動が若干大きいことを指摘し,その原因についても論及してみた2).
パラフィン包埋装置についての検討TISSUE-TEK—包埋センター,TISSUE-TEK IIシステムについて
著者: 平山章
ページ範囲:P.881 - P.886
はじめに
今日の臨床検査部門は昔日のそれに比べて器械化,自動化は著しく進み,目をみはるものがあり,果てはコンピュータ導入も現実の課題として取り上げられるに至っているが,その中で事病理検査部門になると,これまた対称的に遅れており,わずかに自動染色装置,自動脱水脱脂装置程度のものしか見いだせない.
普通病理組織標本を作製するにあたって,最も手数のかかる仕事となっているものは,組織片の包埋とブロック付けおよび薄切であるが,これらは現在の段階では自動化は当分望めず,もっぱら人手をわずらわすことになっているのが実情である.
尿培養法に関する2,3の検討
著者: 小林章男 , 石川明 , 田中仲
ページ範囲:P.887 - P.890
尿中菌数が105/ml以上あれば尿路感染症が疑われるという診断基準が確立されて以来,尿培養は非常に普及し,どこの検査室でも最も多い細菌検査と思われる.尿培養法は米国においてほとんど完全に確立された7)ように考えられるが,設備,人員の十分でない施設で実際に尿検体を扱う際,なお注意すべき点,許容しうる限界点など検討される必要があると考えられる.これらの問題点の理解によって尿検体の合理的検査法も進められると思われる.以下諸家の追試にもなるが,われわれの成績を報告する.
新しいキットの紹介
新しい尿酸測定用キット‘ウリカラー・400’の検討
著者: 影山信雄
ページ範囲:P.891 - P.895
はじめに
わが国で広く用いられている尿酸測定法は,リンタングステン酸比色法である1)が,試料中に含まれる尿酸以外の還元物質の影響を受け特異性に乏しく,特に尿ではこの傾向が著しい欠点がある2).したがって,特異性という点からみればウリカーゼを用いた方法が理想的と思われるが,従来から行なわれているウリカーゼ紫外部吸収法は,紫外部分析法であるための機器の問題や,リンタングステン酸比色法より必ずしも再現性がよくなく3)ウリカーゼ比色法4-6)は操作が煩雑である.
これらの欠点を補う目的で,筆者はウリカーゼとカタラーゼを用いた尿酸の比色定量法(以下U-C・H法と略す)を報告し,特異性ならびに再現性がすぐれていることを指摘し,かつ,血清と尿とが同じ方法で測定できる利点も述べた7).
‘DyAmyl’によるアミラーゼ測定法
著者: 小田原美津 , 中根清司
ページ範囲:P.896 - P.899
アミラーゼ活性測定法として,徒来から検討されてきたamyloclastic法1-3),saccharogenic法4)は,いずれも基質としてデンプンが用いられるが,誤差を伴う種種の欠点がある.特に,基質となるデンプンはアミロースとアミロペクチンの混合物であり,その混合比は原料により異なり,また収穫の時期,温度などにより異なり,測定値の大きいバラツキの原因となるものである.
最近,Ceska5,6),Babson7,8),Klein9,10)らによりchromogenicな基質を用いる方法が開発された.そのなかの小野薬品から‘DyAmyl’の名で発売されたReacton Red−2Bと結合したアミロペクチンを基質としたアミラーゼ測定キットを検討する機会を得たので,その結果を報告する.
霞が関だより・5
臨床検査技師国家試験を受験するには
著者: K.I.
ページ範囲:P.901 - P.901
前回には,衛生検査技師から,臨床検査技師になるための,いくつかの間題を取りあげたが,その後も似て非なる照会が多いので,その中から最も身近の,また今後とも数多くの照会があると思われる例を,2つばかり挙げてみることとした.( )内は筆者注.
例1.薬科大学(獣医大学)を卒業したが,臨床検査技師国家試験を受験するのに必要な,厚生大臣指定の5科目を履修していない.単位の取得にはどのような方法があるか教示して貰いたい.
質疑応答
珍しい血液型・ボンベイブラッドについて
著者: T生 , 安田純一
ページ範囲:P.902 - P.902
問 血液の中に‘ボンベイ・ブラッド’という特殊な血液型のあることを知りましたが,O型の一種で普通のO型はH物質が多いが,ボンベイ・ブラッドにはまったくなく,普通のO型にない抗Hをもっているとのことで,同じO型どうしを混ぜると凝固するとのことですが,
(1)凝固するのはすでに抗Hをもっているからということですか.
グラフ
組織と病変の見方 肉眼像と組織像の対比—生殖器とその病変(1)
著者: 金子仁
ページ範囲:P.903 - P.906
生殖器の疾患を男性と女性に分けて見ると,女性器が大部分である.膣は別としても,子宮と卵巣にかなり重要な疾患が集中している.
子宮に最も多く見られる病変に子宮筋腫がある.これは良性非上皮腫瘍の代表である.組織学的に成熟した平滑筋線維が束状に交錯して走り,肉眼的に‘カラクサ模様’を示す.生前に発見されないだけで,剖検するとかなりな率に子宮筋腫がある.
検査技師のための解剖図譜・8
腎臓
著者: 三島好雄
ページ範囲:P.908 - P.909
腎臓はおよそ第11胸椎から第3腰椎の高さで,後腹膜腔内,脊柱の両側に位置する実質性臓器である.ほぼ左右対称の位置にあるが,右腎は肝右葉の下にあるので,左腎より1-2cm下方にあるのがふつうである.えんどう形で、成人では長さ約10cm,幅約6cm,厚さ約4cmで重量は約110gである.前面は後腹膜をへだてて腹腔臓器に,側面は側腹筋に接し,背面は腰筋・腰方形筋など厚い筋群におおわれている.
肉眼的に腎臓は外層をなす皮質と内層をなす髄質とに区分しうるが,顕微鏡的にはネフロン(nephron)の集まりよりなっている.ネフロンは糸球体と尿細管よりなる.糸球体(glomerulus)は皮質の全体にわたって散在し,尿細管(tubulus)を経て髄質にはいる.髄質中で尿細管は集合管一乳頭管となって腎孟に注ぐ.
検査機器のメカニズム・8
オージオメーター
著者: 瓜谷富三
ページ範囲:P.910 - P.911
1.オージオメーター
オージオメーターは聴力検査に広く用いられている機器で,その構成を図2に示す.被検者に受話器で音を与え,その周波数と強度を調節して最少可聴値を求め,オージオグラムを作成する.オージオグラムの縦軸は,JISで定められた正常者の最少可聴値を基準(0db)とした聴力損失で表わす.オージオメーターには音源の種類から,純音オージオメーターと語音オージオメーターに分かれ,また用途からは診断用と選別用(スクリーニング,に分かれる.
他に周波数や強度が自動的に切り替わり,被検者)スイッチによる応答で,オージオグラムが画がかれる自動記録オージオメーターがある.受話器は一般のヘッドホーンと同じ気導用と,頭骨に振動を伝える骨導用の2種がある.気導測定で聴力障害が発見された時は続いて骨導測定を行ない,外耳道,鼓膜,耳小骨などの伝音系の障害か,内耳感覚器,聴神経,中枢路などの感音系の障害かを調べる.
検査室の用語事典・8
一般検査,血液学的検査
著者: 寺田秀夫
ページ範囲:P.912 - P.913
45) Uremia;尿毒症
腎機能障害が起こると,種々の物質が血中に停滞するが,尿素,残余窒素(NPN)または尿素窒素(BUN),クレアチニンなどは糸球体の障害によって、糸球体からの濾過が困難になる.慢性腎炎や原発性萎縮腎が進行して,これらの物質が血中に高濃度に停滞して,食欲不振,悪心,嘔吐,頭重感,不眠,けいれん,譫妄,昏睡などの症状を呈した場合をいう.予後不良である.
Senior Course 生化学
Michael Somogyiとその業績
著者: 坂岸良克
ページ範囲:P.915 - P.915
昨年10月,電気泳動法の創始者Tiselius教授がなくなって,次第に化学の世界も変わりつつあることを痛感していたとき,実はもう1人の偉大なる化学者が世を去ったことに気づかなかったことは漸塊にたえない,すなわち,血糖,尿糖,アミラーゼなどの測定にその名を残しているSomogyi博士である.
Michael Somogyiは1833年3月7日にオーストラリア・ハンガリーのライナースドルフで生まれた.ブダペスト大学にはいったのは彼が16歳の時で,学制の違いからこれを日本の例にあてはめることはできないが,とにかくその後工業化学で学土号をとるまで同大学で化学を学んだ.卒業後は生化学教室の助手になったが,アメリカ合衆国の自由と実力の世界にあこがれて渡米した.ところが,就職はそれほど思うようにならず,ニューヨークでドイツ人の物理学者に駅者として雇われ,のちにシンシナチーの織物会社に移ったが,その俸給は週7ドルであったといわれている.
血液
血小板抗体(1)—血小板凝集試験
著者: 安永幸二郎
ページ範囲:P.916 - P.916
血小板抗体の証明法には種々の方法がある.そのうち比較的有用と考えられるのは,1)血小板凝集試験,2)血小板補体結合試験,3)血小板抗グロブリン消費試験,4)血小板第3因子放出試験,5)血小板14C—セロトニン放出試験,6)ウサギ血小板減少効果などである.
以下なるべくルーチン検査としての立場からそれらの方法を述べていくことにする.
血清
多発性骨髄腫(2)
著者: 稲井真弥
ページ範囲:P.917 - P.917
3.多発性骨髄腫の免疫学的検査法
先に述べたように多発性骨髄腫(MMと略す)は形質細胞の腫瘍性増殖により,免疫グロブリンの産生異常をきたす疾患であり,MMの診断確定には免疫学的な検査法は重要な役割をもっている.すなわちM成分を証明し,このM成分を形成する免疫グロブリンの種類,つまりIgG型のMMかあるいはIgA型かなどを決定し,またそのL鎖の型を決め,さらに各免疫グロブリンの定量を行なうなどすべて免疫学的な方法,主としてゲル内沈降反応によって行なわれる.
細菌
Edwardsiella属について
著者: 橋本雅一
ページ範囲:P.918 - P.918
坂崎と村田(1962)は,SalmonellaとArizona菌群の生態を調査するために,冷血動物腸内細菌を検討していたところ,これまで記載のない1群の腸内細菌を見いだし,彼らがこれまで取り扱っていた腸内細菌中にはわずか2株しか含まれていない種類の菌であることを知った.しかし,ヘビからはこのような菌が100株以上も検出され,しかもその生化学的性状は全く同一で,血清学的にも相互に密接な関係があることを認めた.これらの菌群はSalmonellaの性状にかなり似ていたが,ほとんどの菌株がインドールを産生し,また糖分解のパターンが非常に狭いという特徴をもっていた.
一方,アメリカでEwingら(1964)は,このような性状をもつ菌を3株見いだしていたが,その後生物型1483-59と記載された菌株の研究を通じて,これらの菌群が腸内細菌の新しい1群であることを認め,坂崎らがAsakusa群,King and Adler(1964)がBartholomew群と呼んでいた菌群を含めて,Edwardsiella属と命名した.現在この菌属には1菌種(Edwardsiella tarda)だげが含まれ,血清学的には17のO抗原と11のH抗原の存在が知られている(Sakazaki;1967).
病理
報告書の印字—IBM磁気カード・タイプライター(MC)
著者: 桔梗辰三
ページ範囲:P.919 - P.919
剖検にしても外科的摘出物の検索にしても,書類作製には多大の時間と労力が必要である.まず剖検では数ページに及ぶ肉眼所見の記載があり,外科病理でも数行から1-2ページの記載事項がある.1〜数日して顕微鏡的所見が追加され,かつ最終診断ならびに意見が合わさって報告書が完成する.しかもこの際しばしば先の肉眼所見に追加訂正すべきことが出てくる.普通報告書は数枚の複写をとるものであり,また後々の検索に供するため報告書の一部分を何枚か複写して整理することにすると,形態病理診断部門では書類作製に費やされる労力と時間は膨大なものになる.
肉眼的観察と最終報告書作製との間に1〜数日の余裕があるにもかかわらず,検鏡用標本ができてから報告書を作製して,主治医に渡す時間を最小限にしようとすれば種々の制約が生ずる.余裕のある時期に肉眼所見を清書すればよさそうであるが,前記のごとく加筆訂正のことを考えるとそうもいかない.タイプミスをペンで修正した報告書を提出することまで考えると,タイピストはかなりの熟練者でないといけないことになる.
生理
計測用体表電極(5)—筋電図測定用電極について
著者: 渡辺清
ページ範囲:P.920 - P.920
筋の組織は骨格筋,平滑筋,心筋に大別され,興奮により活動電位を発生するが,このうち骨格筋より発生する活動電位を記録したものが筋電図であり,平滑筋,心筋の活動電位の記録は平滑筋筋電図,および心電図として別に扱われる.
筋電図は心電図のように一定の誘導方法はなく,いくつかの筋肉を選んで,いかなる方法により記録したかによって診断価値が変わってくる.そのため大別して2つの方法が使われる.
業務指導のポイント
永久基本記録—永久保存ノート
著者: 松村義寛
ページ範囲:P.921 - P.921
臨床検査の結果は客観的に記録され毎日の日常検査ノートが残される.このノートの書き方,整理についてはすでに述べられた.
検査件数の増加に伴って,この記録の量は膨大なものとなり,検査室の貴重な資料として活用されなければならない.検査結果の記録は個人についていえば日記のようなものといえるが,これに対して履歴書に相当するものが,ここに述べる永久基本記録である.
基本情報
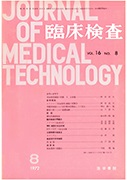
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
