ヘマトキシリン(Hematoxylin;H)は中南米にのみ産する豆科の植物であるカンペシア木より抽出して作る色素であり,その合成には成功していない.最近,このHは品不足となり入手困難な状況である.そこでわが国で,これにかわるべき合成色素があれば便利である.
ガレイン(Gallein)とピロカテコールバイオレット(Pyrocatechol Violet)はこの目的のために,再発見された合成色素である.かつて生物試料染色以外の目的に用いられていたが,現在はほとんど用いられていない色素である,これは,その分子構造の一部にキノイド環があり,アルミニウムと結合して発色し,染色性を発揮する点がHと同じである.したがって染められる細胞核の形態もHと類似であり,代用色素として用いられる.ここでは,その長所と短所を示す.(1177ページ参照)
雑誌目次
臨床検査18巻11号
1974年11月発行
雑誌目次
カラーグラフ
ヘマトキシリン代用色素—ガレインとピロカテコール・バイオレット
著者: 山田喬
ページ範囲:P.1160 - P.1161
技術解説
乳酸菌の細菌学
著者: 光岡知足
ページ範囲:P.1163 - P.1172
乳酸菌とは
いわゆる乳酸菌と称する菌群は,糖類を醗酵して多量の乳酸を生成する細菌の総称で,分類学的には乳酸菌科(Lactobacillaceae)をもって代表される.形態学的には球菌と杆菌とに分かれ,いずれも酸素の少ない環境に好んで発育し,各種の糖から乳酸を生成する.
この乳酸醗酵の形式は,さらにホモ乳酸醗酵(homofermentative)とヘテロ乳酸醗酵(hete-rofermentative)に大別される.ホモ乳酸醗酵は糖類から理論数100%を示す収最で乳酸を生成する醗酵で,これを行う乳酸菌をホモ乳酸菌と呼んでいる.ヘテロ乳酸醗酵はヘキソースから乳酸と乳酸以外の物質(アルコール,炭酸ガス,酢酸など)を生成する醗酵で,これを行う乳酸菌をヘテロ乳酸菌と呼んでいる.
フィブリノゲンの免疫学的定量法
著者: 川越裕也
ページ範囲:P.1173 - P.1176
フィブリノゲンは分子量34.1万のタンパクであり,他の動物に注射することにより比較的容易に抗体を作らせることができる.こうして作られた抗フィブリノゲン血清は商品化され多数市場に出ている.抗フィブリノゲン血漿を使用してフィブリノゲンを定量することは他のタンパク体の検索と同様に行われ,ほとんどすべての血清学的方法によりなされ得るものである,紙面の関係上,ここでは沈降反応を利用した方法と凝集反応を利用した方法の二,三についてのみ紹介するに止める.
グラフ
ヘマトキシリン代用色素—ガレインとピロカテコール・バイオレット
著者: 山田喬
ページ範囲:P.1177 - P.1178
ヘマ卜キシリンは,1972年春より不足しがちとなり,本年になっては全く輸入が止まってしまった状態である,その原因がいまだ不明であるので,明日にも大量に輸入されるかもしれないが,あるいは当分は入手できないかもしれない状態である.多年ヘマトキシリンにより細胞核染色像に親しんできたわれわれにとって,これは重大な事態である.そこで,ヘマトキシリンにかわるべく,しかも合成できる色素があれば急場をしのげるといえよう.
しかし,色素により染め出される核の形態は複雑であり,異なる染色機構を持つ色素によって染め出される核の形態は異なってくる.たとえば,チオニン系の色素であるメチレンブルーとアズールブルーよりなるギムザ染色により染め出される核の形態と,アルミニュウムとラックさせて染色機能が発揮されるヘマトキシリン(図1)により染め出される核の形態は異なる.
総説
血清総タンパク
著者: 石井暢
ページ範囲:P.1179 - P.1184
血清総タンパク測定は臨床検査室における日常検査として,最も数多い検査の一つである.したがってその測定法も種々の方法が開発されている.
血清タンパクは血清成分中,最も多量に含まれる成分で,その量はおおむね6.5〜8.0 g/dl付近であるが,このタンパクの多様性が漸次明らかとなるに従って,これをそれぞれの分画に分けて測定することが臨床病理学的にいっそうの興味を引き起こしている.
臨床化学分析談話会より・15<関東支部>
足元を見なおす機会—血糖,Chol.の定量反応機構
著者: 野間昭夫
ページ範囲:P.1185 - P.1185
第174回分析談話会関東支部会(46.6.18)は東大薬学部記念講堂にて開催された.本年4月より始まっているシリーズ「測定法と臨床的評価」の第3回めとして「血糖およびコレステロール測定法の反応機構」について東北大薬学部の南原利夫先生の講演が行われた.
常日ごろ,増加の一途をたどるルーチン検査に追われて,機械的に検査を行い,特に省力化の一つとしてキット使用による検査が多く行われる昨今において,その測定法の反応機構にまで目を向けることができないでいる人が多いことと思われる。そこでこの日の講演は常に前方のみを見ていなければならない人々にとって,今一度足元を見つめてみる絶好の機会を与えられ,非常に有意義なタべであった.そこで今回はこの日の南原先生の講演の要点に触れてみたい.
座談会
血清総タンパク
著者: 菅野剛史 , 坂岸良克 , 正路喜代美 , 四反田都 , 石井暢
ページ範囲:P.1186 - P.1193
N社のソケットはT社の電球をネジ込んでもうまく納まる.これは工業製品が規格化されていて互換性があるからである.臨床化学の分野ではどうであろうか.病院間のデータの偏差はマイナス面が大きい.データの互換性を高めるにはどうしても分析法の標準化が必要となってくる.
異常値の出た時・23
異常赤血球の出現
著者: 内野治人
ページ範囲:P.1194 - P.1198
末梢血に異常赤血球が出現したことを判定するためには,まず,技術的に標本作製上のいろいろの問題が,判定に耐えるだけのものでなければならないことはいうまでもない.
塗抹標本の引き方として十分赤血球が拡がっていることがまず前提にあり,次に染色の一定性が要求される.pHによる赤血球染色性の色の変化があることはいうまでもない.次にこのようにして,標準的に作製された条件下での標本について,顕微鏡下に,すぐ油浸を用いないで,全視野を見ることや,塗抹の引き始めと終わりとの赤血球分布の濃度差などを念頭において標本を見る必要がある.一般に若い医師にとっては,末梢血塗抹標本を見るということは,すぐ白血球分類を行うという目的が多く,赤血球の正常からの偏位を見ることを失念することが多い傾向があることは,注意しなければならない点であろう.
ひろば
緊急検査と今後
著者: 大竹敬二
ページ範囲:P.1198 - P.1198
昼夜緊急検査の提出件数増加に伴い,検査室側は頭の痛い難題続出で苦慮することが多くなった.平常勤務でかなり疲れている上に,休日夜間と30時間以上の勤務を連続して実施しなければならない一方,男性は年々淋しく,心労のために医療事故に巻き込まれないか心配でならない.
技師が一度医療事故を起こすと生涯を捧に振る厳しい損害賠償が待っているし,最近の医療事故の判例からも求償権の行使は許されないとつれない解決をとりつつあるので,緊急時の医療事故は決して少なくないが,無理して危い夜の勤務をしたがらない技師の出現にも注目したい.
質疑応答
ASO値測定について
著者: T生 , 松橋直
ページ範囲:P.1199 - P.1199
問(1)血球浮遊液を加えてからの試験管内の溶血変化時間を経時的にみたところ下のような結果を得ました.30分時と最終判定時(45分時)とは変化がありませんので最終判定時を血球浮遊液加後30分として判断してよろしいでしょうか.
(2)血球浮遊液作製に際し,ヒト血液の場合はO型血とありますが,他の型(A,AB, B)の使用の可否について.
論壇
病院病理解剖とその振興について
著者: 畠山茂
ページ範囲:P.1200 - P.1201
病理解剖の持つ意義
現代医学における病理解剖の持つ意義とか重みは,ますます増大していると思われる.その原因はいろいろあるが,その一つとして最近の臨床検査の進歩に基づく診断技術の向上があろう.たとえば,現在の肝や腎機能検査はわれわれにそれら臓器の機能異常や病因について以前に比し格段に正確な知識を与えてくれるようになった.ごく軽い肝炎や腎機能異常も診断でき,生検材料との対比から機能異常と形態の相関についても,かなりのレベルまで知ることができるようになりつつあるし,また小さな腫瘍の存在の有無なども将来かなり正確に指摘できるようになるだろう。診断技術の向上には自己検証を伴うフィードバック過程を伴っていなければならないのは当然で,検証の最有力な手段が病理解剖であることはいうまでもないだろう.
病理解剖は,生命の終着点で行うものであるから,生前の検査から推測されたすべての病態をそのままとらえることは不可能である.しかしこれまで蓄積された病理学の知識を総動員して正確な病気の診断を下すことはできよう.この場合の正確さとは疾患の総合的な把握理解であって,細部にわたった,たとえば細胞の分子生物学的な変化の解析などは,病理解剖の持っている方法論上の制約によって大きくはばまれているのが現状であろう.しかし,そのことによって病理解剖の意義はいささかも減ずるものではない.
臨床検査の問題点・68
補体の検査—定量法を中心に
著者: 稲井真弥 , 巴山顕次
ページ範囲:P.1202 - P.1207
梅毒血清反応に適用されている補体結合反応(緒方法,Kolmer法……)には,多くの検査室が100%溶血法を使っているが,精度の高い50%溶血法の合理性はまだまだ理解されていない.補体の成分や性質など初歩的な説明を通して補体価の定量法,検体の取り扱い,さらには多くの可能性をひめた"補体"の活用法を話し合い,補体の検査を身近かなものにしたい,(カットは,正常ヒト血清のβ1c(C3)およびβ1E(C4)沈降線)
私のくふう
中検中央採血台の改良
著者: 福田邦昭
ページ範囲:P.1207 - P.1207
より早く,より正確な検査成績を提出するため,採血業務を中央化し,採取時のまちがいをなくし,能率化および合理化を行う.
当中検で使用している採血台は,不用意なる患者による腕移動などによって起こりうる採血スピッツなどの容器類の落下破損防止を考慮,さらに採血者サイドの仕事がやりよいようにした,二段式採血台です.
研究
ヘモグロビン専用直読光電比色計の検定法
著者: 松原高賢
ページ範囲:P.1208 - P.1214
はじめに
ユーザーの立場からの光電比色計の検定手技を解説した格好の成書が見当たらないので,その要領や注意事項を織りまぜつつ日本商事(株)製ヘモグロビン専用直読光電比色計(NSK Hb計と略)の検定成績を述べる.
新しいキットの紹介
溶連菌由来抗体検出用試薬スライド法および凝集法(Microtiter法)によるASO価測定—特に溶血法(中和反応)との比較および使用経験
著者: 岩田進 , 河合忠
ページ範囲:P.1215 - P.1218
はじめに
溶血性レンサ球菌感染症ならびにそれに関連した疾患の診断には大きく細菌学的検査法と血清学的検査法がある.細菌学的方法は,感染と発症の時期のずれや,感染の軽重,抗生物質の進歩,菌の強弱など種々の因子により検出率は著しく低い.血清学的方法は,患者血清中に認められる溶連菌の菌体外毒素に対する抗体を証明することで,代表的な方法に抗ストレプトリジンO価測定(以下ASO価)があり,このほか表に示すごとく種々の外毒素に対する抗体価測定法が開発されている.このうちで日常検査として最も広く行われているものは,毒素中和反応を利用したASO価測定ならびに受身凝集反応を利用した抗ストレプトキナーゼ価測定(以下ASK価測定)である.特に急性腎炎,リウマチ熱などにおいては,先行感染としての溶連菌感染の証明は必要であり,ASO価測定が診断上重要な根拠となっている.ASO価測定は,現在では小規模の施設にも採用され普及しているが,術式に全く問題がないわけではなく,血清希釈の煩雑さや,それに伴う誤差,血球の問題,リポタンパクの影響や判定上の問題などがある.またA群溶連菌の中には,SLO弱産生株や,非産生株が存在する1,2)ことからASO価以外の方法の併用が望ましいといわれている.したがって,限られた人員で多種目の検査を行うには,ASO価測定の簡易化は望まれるところであった.
血清分離剤Sure-Sepの検討
著者: 八島弘昌 , 井尻潔 , 池田美佐子 , 松島照雄 , 室木邦生 , 河内一仁 , 野中清美 , 野村礼子
ページ範囲:P.1219 - P.1221
はじめに
近来,臨床検査の検体数や項目数の増加により,臨床検査の自動化,能率化,省力化が考えられ,自動分析機器の導入が図られているが,その前処理の段階が案外忘れられているのではなかろうか.臨床検査の検体の多くは血清または血漿に分離されて分析されるが,この検体分離作業が一般ルーチン検査のように多数の検体を分離する場合には意外に時間と労力を要するものである.
血清分離は遠心後血清層の分離は迅速に行うことがたいせつであるが,同時に分離に使用するピペットによる汚染もできるだけ避けることが望ましく,そのためにピペットの再生に時間と労力を要するものである.そのうえ,血清をできるだけ多く採取しようとすれば,ピペットの使用を誤って血球を吸い上げるようになり溶血の原因ともなる.またオーストラリア抗原,梅毒などの血清は特に注意が必要で,なるべく操作を簡略化し,ピペットを用いないで大量検体を処理する必要がある.このためにプラスチック製粒子の血清分離剤がE社,S社より発売されている.今般われわれはWarner-Lambert社より発売の"Sure-Sep"の使用の機会を得て,これら血清(血漿)分離剤の比較検討を試みたのでその結果を報告する.
紫外部吸収法LDH測定用キットの検討—LDH活性値に及ぼす要因について
著者: 菰田二一 , 坂岸良克
ページ範囲:P.1222 - P.1224
従来,臨床検査における酵素化学分析の多くは,可視部比色法によって求められてきた.この理由としては,紫外部吸収法(UV法)が,試薬として純品の助酵素を必要とするばかりでなく,分析技術ならびに分析機器の違い,さらにより厳重な温度規制が要求されることなどがあげられよう.ことにUV法は,1検体当たりの測定時間が3分前後という迅速さにもかかわらず,多数検体を同時に扱う場合に必ずしも処理時間をそれほど短縮することができず,現在,臨床検査分野の趨勢であるキット化,簡易化,スピード化という要求に応じきれなかった点にあるようである.
しかしながら,酵素活性を国際単位で表す慣習が臨床化学に受け入れられてから久しいだけでなく,近年,酵素診断に対する期待がますます高まるにつれて,その成績に対する精度,確度の要求は,日を追って厳しさを増し,UV法が急速に採用される傾向になりつつあることも事実である.
霞が関だより・28
医療従事者の養成・教育について
著者: K.M.
ページ範囲:P.1225 - P.1225
これまでの医療は,医師と看護婦が中必であると老えられていたが,医療技術が高度になり専門分化してくるに従って,臨床検査技師,衛生検査技師,診療放射線技師,診療エックス線技師,理学療法士(P.T.),作業療法士(O.T.),視能訓練士などのいわゆる"パラメディカル"と呼ばれている医療従事者がチームを組むことが必要となってきた.この医療従事者はいずれも高度の専門的な知識や技術を必要とされており,その養成教育はそれぞれの法律に定められているカリキュラムに従って行われている.しかし,医師や看護婦のように歴史も古くその教育方法や指導者の養成など系統的な教育体制が確立されているものから,歴史も浅く指導者の養成が必要な段階のものまであるのが現状である.一般に医学教育ではその教育内容やカリキュラムに関する議論は活発に行われており,それぞれの専門分野で知識や技能を教えることの必要性は一般に認められている.しかし,その授業や学習の方法"HOW TO TEACH"については必ずしも重要視されているとはいえない.いわゆる初等・中等教育で行われている指導者や講師が一方的に学生に教える講義や実習の形式が使われている.また各種の教育機器を使用した視聴覚教育などの技法も必ずしも十分に取り入れられているとはいえない.
日常検査の基礎技術
溶血の検査法
著者: 三輪史郎 , 宮地隆興 , 米原ヤス子
ページ範囲:P.1227 - P.1234
溶血性貧血は一つの症候群であって種々の病態によるものが含まれている.したがって溶血の検査法はきわめて多岐にわたることになる.貧血・網赤血球増加・間接ビリルビン増加はほぼ必発する所見であり,また赤血球形態の観察は,ここでは取りあげないが,諸検査の前提になることをまず強調しておきたい.
先天性溶血性貧血のうち赤血球膜の異常による遺伝性球状赤血球症では浸透圧脆弱性試験,ヘモグロビン異常,特に不安定ヘモグロビンによるものでは不安定ヘモグロビンの検出,また赤血球酵素異常(欠乏)によるものでは赤血球内諸酵素活性や解糖中間体・ATP・GSH測定が病態決定の決め手となる.一方,後天性溶血性貧血のうち免疫学的機序によるもの(自己免疫性溶血性貧血など)ではクームス試験はたいせつな検査法である.また発作性夜間血色素尿症(PNH)ではHam試験やショ糖溶血試験(砂糖水試験;sugar-water test)が診断の決め手となる,赤血球形態異常の有無は上記諸疾患でもたいせつな手がかりとなることは前述したが,ことに赤血球破砕症候群ではむしろ唯一のよりどころといっても過言ではない.
検査と主要疾患・23
髄膜炎
著者: 横田万之助
ページ範囲:P.1236 - P.1237
髄液が主として問題となる
1.採液 これは医師の役目.腰椎穿刺法と槽穿刺法と2法がある.前者には微妙なコツがあり,熟練を要するが,深すぎぬことが第一.後者は以前にいわれたような危険性はなく,むしろ容易に実施できるので試みられたい.
2.検査 ただちに検査室へ持参,正確なオーダーを付して依頼する.細胞数と糖量はただちに実施のこと──時間をおくと狂う.
検査機器のメカニズム・35
温度計
著者: 西山俊広
ページ範囲:P.1238 - P.1239
デジタル温度計について
温度計は原理やその用途などにより,きわめて多種多様なものが,製作されている.温度計を大別するとアナログ式とデジタル式のものがあり,前者の場合はその時の指示を示す携帯用指示温度計や過去の温度経過を記録にとる温度記録計がある.後者は直接温度値が読み取れるので,測定者の個人差による読み取り誤差は起こりえない.このデジタル式温度計も携帯用(主に1点測定)と数十点の温度を自動的に計測する多点式のものとがある.1点測定では1/100℃の測定精度のものもあるが,ここではポーダブル用で最も汎用性があり,かつ,精度もよい温度計として,デジタル式抵抗温度計(横河,形名2804)について説明する.抵抗式温度計は,一般にJIS規格(抵抗値100Ω/50Ω)で定められた白金測温抵抗体をセンサ(検温部または感温部)として,そのセンサを本体に接続するだけで,−100〜500℃間の温度を測定し,最終桁0.1℃の単位で表示するポータブルのデジタル式温度計である.図1にその外観と測定表示例を示す.センサ部の外形は用途により,それぞれ最良な測定を行うため大きさ・形状など千差万別であり,本内容では省略する.
測定精度は本体とセンサの誤差で決まるもので,たとえば−100〜100℃の場合,本体0.2℃,センサ0.3℃合わせて0.5℃である.しかし本体と専用センサ(図2)を組み合わせて試験した場合には測定精度0.3℃である.
検査室の用語事典
常用病名
著者: 伊藤巌
ページ範囲:P.1241 - P.1241
89)肺気腫;Pulmonary emphysema
空気の蓄積により肺が過度に拡張した状態をいう.臨床的に重要なのは慢性肺気腫で,多くは慢性気管支炎,気管支喘息に続発し,緩慢に進行する.診断にはX線所見,肺機能検査成績が重要である.換気機能低下のため低酸素血症を生じ,重症例では高炭酸ガス血症,呼吸性アシドーシス,肺性心をきたす.
血清学的検査
著者: 伊藤忠一
ページ範囲:P.1242 - P.1242
85)Sensitization;感作
次のようないろいろな意味に用いられる.
(1)既往反応のため抗原で処理する操作,しばしば単なる免疫操作をさす場合もある.
組織と病変の見方—肉眼像と組織像の対比
癌腫
著者: 金子仁
ページ範囲:P.1243 - P.1246
今まで,臓器別の疾患を掲載し,その中にいくつか癌腫を入れたが,本篇では,今まで述べなかった癌につき示説する.
口唇癌,舌癌は皮膚癌と同じく,組織学に扁平上皮癌である.
付・組織と病変の見方
病理学総論(その2)
著者: 金子仁
ページ範囲:P.1247 - P.1247
炎症(inflammation, Entzundung)
炎症を一口に定義すれば"刺激に対する組織の反応"である.生体の防御的反応と理解してよい.
炎症の症状は昔から,発赤,熱感,腫脹,疼痛,機能障害といわれている.炎症の原因は,
Senior Course 生化学
自動化学検査・11—測定法上の問題点
著者: 中甫
ページ範囲:P.1248 - P.1249
前号までに広く自動化されているおもな測定項目について項目ごとに解説を行ってきたが,今回はその他の自動化が試みられている数項目について自動化にあたっての測定法上の問題点について述べる.ディスクリート方式で機構上測定法に最も大きな制約を与えるのは,除タンパク操作を行わず直接測定法で行う機種がほとんどを占めることである.フロー方式においてはダイアライザーを用いているのでこれらの問題点がかなり軽減されるのに対して,ディスクリート方式では測定にあたって考慮しなければならない最も大きな因子となる.ここでは主として直接法での問題点を中心に自動化における注意点を解説する.
血液
NBTテスト
著者: 中島弘二
ページ範囲:P.1250 - P.1251
好中球の殺菌消化能
好中球は生体内に侵入した細菌などに対して遊走,貧食後細胞内で殺菌消化することにより細菌の侵入に対して生体を防御している.すなわち好中球は遊走,貧食,殺菌消化の能力を合わせ持つことにより細菌感染に対して生体防御の役割を持つものであり,それらの低下により生体は容易に細菌感染にさらされる.それらの能力の低下した例が疾患または症候群として認められるようになってきた.特に殺菌能力に関しては貧食した細菌を入れたファゴゾーム(phagosome)に対して種々の酵素系を持ったライソゾーム(lysozome)が融合し細菌の殺菌消化を行う.ライソゾーム内にはリゾチームをはじめ種々の殺菌消化作用をいとなむ酵素系が存在するが,なかでもKlebanoffらはrnyeloperoxidase (MPO)系が重要な役割を果たしているという.すなわちMPOはH2O2およびCl—,I—,Ba—のハロゲンイオンの3者の協力により強力な殺菌作用を発揮する.
殺菌消化時における好中球に起こる代謝過程の特徴はhexose monophosphate shunt (HMS)の著明な活性化にある(図).
血清
ウイルスの血清学的検査
著者: 中村正夫
ページ範囲:P.1252 - P.1253
新しいウイルス性疾患とウイルス学的検索
ウイルス感染症の新しい分野を開発するためには,その基礎としてウイルス学的検索が重要な役割を持っている.未知ウイルス感染症のみならず,既知のウイルスについても,次々と新しい事実が見出されつつある.これらの研究には,ウイルス分離,血清学的検索その他,各方面からの検討が必要である.この稿では,ウイルスの血清学的検査を中心に述べることが目的であるが,一つの疾患,患者を対象として考えた場合には,ウイルス分離,血清学的検査,その他の方法を総合して判断することが当然行われるべきであるので,ここでは,ウイルス血清検査を含めた,広い意味のウイルス検査の立場から述べたいと思う.
現在,原因不明の疾患の中には,ウイルスが原因と考えられているものがいくつかあるが,その二,三の例を述べてみよう.
細菌
臨床細菌検査に対する診療報酬のあり方
著者: 三輪谷俊夫 , 前島健治
ページ範囲:P.1254 - P.1255
本稿は1973年6月関西において創立された感染症研究会の世話人16名(臨床医,基礎細菌学者,細菌検査技師の代表によって構成)があらゆる角度から討議して得られた合意点を著者らがまとめたものである.討議のたたき台になったのは1971年7月内科系社会保険連合(内保連と略称)によって提案された「内科関係診療報酬改正案」細菌学的検査の項である.これは現行の診療報酬制度よりは多少報酬点数がよくなってはいるが,理念的には全く現行のものを踏襲したものにすぎない.ことばを換えれば,精度の高い確実な検査をすればするほど損をし,手抜き検査をすればするほど得をするたぐいのものである.そこで急遽,感染症研究会の発起人世話人会をひらき,1年近く討議して下記のような結論を得たので,内保連加盟学会である日本臨床病理学会の代表者に答申したところ,1973年1月31日の内保連提案の再度の改正案にわれわれの主張が全面的に採択されるに至った.この改正案では結果としての項目別報酬点数しか記載されていないので,その理論的背景・理念をまとめ,読者といっしょに考えてみたい.
微生物学的検査料の抜本的な改正試案
著者: 三輪谷俊夫 , 前島健治
ページ範囲:P.1260 - P.1261
"抜本的な改正がなぜ必要か"については本誌1254ページを参照されたい.内保連の改正案においても"各料金はその時の物価や人件費に応じて毎年改定する"必要性が強調されているが,別表の改正試案の点数は1972年に検討した当時の算定に基づくものであることをご考慮いただきたい.われわれは点数そのものにこだわっているのではない.抜本的な改正の理念をご理解いただき,改正の機運が全国的に盛りあがることを念願する.
さて,本誌1255ページの"問題点そのⅡ"についてであるが,結論的には微生物学的検査料は前納式と後納式を併用すべきである.
病理
臨床病理学的立場よりみた電子顕微鏡学・11—電顕写真のとり方および資料の整理法
著者: 相原薫
ページ範囲:P.1256 - P.1257
電顕写真のとり方
電顕像は螢光板の上で直接観察できるが,螢光板による像の観察は①おおまかな所見をつかむこと,②記録する視野を決めること,③焦点を合わせるために行うもので,詳細な電顕像の解析は電子線を感光材料に感光させ現像処理のあと引き伸ばし,焼き付けしたものについて行われる.
生理
腎クリアランス
著者: 小船善弘
ページ範囲:P.1258 - P.1259
腎機能検査の中で,クリアランス試験は,腎循環,糸球体からの濾過量,腎尿細管での再吸収および排泄,水・電解質代謝調節能などを,定量的に把握しうることで,今日,腎生理学的研究面における応用と同時に,腎機能の臨床検査法として,すぐれたものであることはいうまでもない.すなわち腎障害の程度,疾患の病期,重症度,予後の判定,病気診断の補助的資料などにおけるクリアランス法の役割はきわめて重要なものであり,日常臨床医が繁用する理由もここにある.
しかしクリアランスの持つ意義は,決して決定的証明をなされているものでなく,一般的に了解されている事がらとして取り扱われているにすぎないことも事実である.さらに腎疾患に際して,クリアランス法により得られた値からは,腎疾患の病名や病型に関する診断を期待することは適当でなく,腎の持つ現在の機能を示すだげのものであることは,銘記すべきであろう.
基本情報
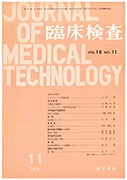
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
