Yersinia enterocoliticaの感染病像は多彩であるが,発生頻度としては,幼児の下痢症,および虫垂炎を疑わせる胃腸炎症状が最も多い.本菌は腸内細菌科としての一般的性状を示し,分離,同定法も赤痢菌やサルモネラに準ずる.ただし,分離培養および確認培養の一部は25℃ 48時間の条件で行う.本菌感染症では血中抗体価の著しい上昇が認められる場合が多いので,抗体価の測定は診断的な意義を持っている.
雑誌目次
臨床検査18巻2号
1974年02月発行
雑誌目次
カラーグラフ
技術解説
高速自動化学分析装置・1 CentrifiChem
著者: 斎藤正行 , 松田基 , 実方悟 , 中村健三
ページ範囲:P.133 - P.136
第3の自動分析機として新しく登場した遠心力を利用したいわゆるFast Analyzer (高速自動化学分析装置)は米国Oak Ridge国立研究所のDr.Norman,G.Andersonらによって1968年に開発されたものである.
この研究はNIHのGeneral Medical SciencesとAtomic Energy Commissionの両機関よりの援助で行われた関係上,これらの頭文字をとって別名GeMSAECとも呼ばれ,アメリカ政府の特許である.
高速自動化学分析装置・2 RotoChem Ⅱ
著者: 奥田清 , 小林紀崇
ページ範囲:P.137 - P.142
本装置の概要
基本的な分析原理は他の遠心方式のfast analyzerと同じである.RotoChem Ⅱでは試薬とサンプルを分注したトランスファーディスク(回転盤)を本体に装填し,反応条件をプログラムしたカートリッジ磁気テープを本装置のテープデッキに装着し,コントロールボタンを押すだけで自動的に測定が開始される.コンピューターは測定中の反応経過を8回とらえ,AD変換,単位(IUほか)への換算,希釈率の補正などを行い,その結果が正常値,異常値,リニアーレンジの表示とともに,ディスプレイタイプライターでタイプアウトされて出てくる.もちろん反応条件の変更なども簡単に行うことができ,他の遠心方式の装置(GeMSAEC,CentrifiChemなど)に比して柔軟性に富むということができよう,さらにコンピューターを利用して,データファイリングや統計処理もある程度可能で,応用範囲が広いのが特徴である.
Yersinia enterocoliticaの検査法
著者: 丸山務
ページ範囲:P.143 - P.148
Yersinia enterocolitica感染症
Y.enterocoliticaがヒトの病原菌として知られるようになってからの歴史は比較的新しい.本菌は虫垂炎との関連から問題が提起されたこともあって,当初は主として,虫垂炎やこれを疑わせる疾患である腸間膜リンパ節炎,あるいは回腸末端炎の一起因菌として,北欧やフランスなど欧州の一部で注目されていた.その後世界各国から報告された本菌感染症例の累積は,本菌が小児下痢症の重要な起因菌となりうること,さらに,敗血症による死の転機をとる急性経過から,関節炎などの慢性疾患にわたる多彩な病像をとることが明らかにされてきた.
年齢別,症候別発生頻度では,2歳以下の胃腸炎が大部分を占め,高年齢になるにしたがって病像の多様化がみられる1)(図1).
総説
血液型判定における過誤
著者: 遠山博
ページ範囲:P.149 - P.154
血液型不適合輸血の原因として,次の2種類の失敗のあることは申すまでもない.
(1)血液型判定の誤り;technical errors(判定用血清の不良,判定方法の誤り,判定技術の未熟,特別な血液で元来誤りやすい血液など)
学会印象記 第24回電気泳動学会総会
—新しい検索の場—ワークショップの登場
著者: 加野象次郎
ページ範囲:P.155 - P.155
第24回電気泳動学会総会は,10月19,20日の両日,秋たけなわの仙台(宮城県医師会館)において開かれた.
本年度の総会は,いくつかの点で特色あるものであった.まず,昨年10月1日逝去された児玉桂三先生の追悼会が合わせ行われたことであり,次にワークショップという新たな企画が試みられたこと,そして,シンポジウムの内容に血漿以外の体液が扱われたこと,などが挙げられよう.
臨床検査の問題点・60
血液培養検査
著者: 藤森一平 , 木村雅英
ページ範囲:P.156 - P.160
菌の検出率を高めるには,カルチャーボトルの性質をよく知って使い分けなければならない.培地の選択,血液の接種量,採血時期などの技術面の検討のほかに,臨床側の要求にこたえる検査データの出しかたを話し合う.(カットはカルチャーボトルに生えた菌)
異常値の出た時・14
カルシウム
著者: 稲垣克彦 , 柳沢勉
ページ範囲:P.161 - P.166
カルシウム(Ca)はリン酸とともに骨骼の形成にあずかるほか,重要な生理機能の発現に不可欠の因子でもある.神経,筋の興奮,血液凝固,またタンパクと結合しやすく酵素タンパク,膜タンパクに結合してそれらの生物学的活性を調節し,ホルモン合成またその作用の発現などと密接な関係を有している.
成人1人における生体内Caは約1kgでその99%は骨にあり,軟組織に4g,細胞外液には1gが含まれているにすぎない.
論壇
これからの臨床検査
著者: 黒川一郎
ページ範囲:P.168 - P.169
臨床検査が医療体系の一環として重要なポイントであることはすでに言いつくされているようにみえる.しかし,このような議論があまりにもくり返されると一種の不毛さも感じられるのである.
海外だより
台湾で訪ねた臨床検査室—台湾医学会総會参加のおりに
著者: 佐々木禎一
ページ範囲:P.170 - P.174
1972年11月,私は台湾医学会第65届総會(The 65 thAnnual Meeting of The Formosan Medical Associa-tion)のシンポジウムに招かれ,牧野秀夫(名古屋保健衛生大,内科),野本昭三(信州大病院,中検)両先生およびTechnicon日本支社の坪武氏とともに台湾を訪れた.
ちょうど日中国交回復の直後であったためいろいろの懸念推測も口にされたが,結果的には全く友好に満ちた旅行であった.私としては3回目の訪台であったが,今回は学会シンポジウムへの出席と,栄総医院核子医学中心でのセミナーとが主目的であったこと,前記諸先生といっしょだったこと,かつての知己に逢い旧交を温めえたこと,さらに初めて台北市以外の南部を訪問するプランがあったことなどで,初めての台湾訪問のような心境であった.
臨床化学分析談話会より・6
臨床家のするどい観察—臨床家からの提言と分析者の責務
著者: 菅野剛史
ページ範囲:P.175 - P.175
167回の関東支部談話会はアイソエンザイムシリーズの第2回でアルカリホスファターゼを特集し,血清アルカリホスファターゼについて東大医・第1内科の鈴木宏先生,尿のアルカリホスファターゼについて東大分院・泌尿器科の阿曽佳郎先生と,王子病院内科の井上昇先生に実例を中心に話題提供をお願いした.以下その概要を紹介する.
1)血清アルカリホスファターゼのアイソザイム
研究
関東逓信病院システムにおける臨床検査データ処理(Ⅱ)—その果たすべき機能と将来構想
著者: 春日誠次 , 鈴木康之
ページ範囲:P.176 - P.179
前号には本病院において現在行われているコンピューターによる8つのシステムの概略とその中のひとつである臨床検査のデータ処理システムについて述べた.この現行システムは,システム化以前に行われていた検査室の機能ないしは作業の流れには基本的にふれず,データのファイルという面でコンピューターを利用する方針をとっている.これは臨床検査の現行作業を行いながら,新しいシステムへ移行する過程からすればその第1歩としてやむを得ないひとつの方向であった.検査室内の作業の流れに直接ふれないでデータファイルにのみコンピューターを利用するということは,検査室の作業の繁雑をコンピューターの利用によってより合理的にするのとは別な方向であって,現行の作業に加えてデータファイルのための新たな作業が加わる結果をまねいている.
一方でこのような繁雑さに加えて,本院における臨床検査データ処理システムの現況としては,
新しい機器の紹介
免疫拡散板による血清IgDおよびIgE測定法の検討
著者: 宮谷勝明 , 高畑譲二 , 福井巌
ページ範囲:P.180 - P.182
免疫グロブリンは,現在IgA,IgM,IgG,IgDおよびIgEの化学的,生物学的性状の異なったタンパクが確認されている1).この中でIgDの免疫グロブリンの占める割合はわずか0.2%である2)とされ,IgEのそれはさらに少なく0.002%に過ぎない3)とされている.このように,きわめて微量成分であるために,正確でしかも容易に測定しうる定量法の開発が望まれていた.最近,Faheyら4)によって完成された一元平板免疫拡散板であるBehringwerkeのIgDおよびIgEを用いて測定を行う場合の測定条件について吟味を加えるとともに,あわせてこれらの測定法を用いて健常成人の血清IgD,IgEをも測定したのでその成績について報告する.
ひろば
小さな誇り
著者: 大竹敬二
ページ範囲:P.182 - P.182
検査室仲間から,‘君は何の必要があって,これほどまでに,医療機器に執念を持ち続けるのか,くだらん’とよく言われる.その忠告のたびに,経済的にも決して恵まれない私にも限度はあると反省している.
しかし限度ある多くの悪条件の中で,多くの方々が努力し,進歩・発展していることだけは確かである.その甲斐あってか,今までの検査部長は,医師または専門職の人に限られていたが,地方の検査技師にも,検査部長になっている方が最近特にふえてきた.また,その方々の理論水準もかなり向上され,技師としての自信と誇りを,若い方々に植えつけるようになった.
物価の高騰に悩む
著者: 村田徳治郎
ページ範囲:P.188 - P.188
ピペット操作している時,試験管に試薬を注入した前後の管に注入したかどうか一瞬まようことがよくある.神経を集中しようと努力しているのだが,頭からどうしても離れてくれぬものがある.
近頃は朝目をさますたびに物が高くなっていることである.しかも生活必需品の上昇には目をまわしてしまうほどである.月給日の翌日でさえ,欲しい技術書なり医書さえ今日このごろは家計を思えば遠慮せねばならなくなった.共稼ぎしてなんとかやりくり算段できたのが,妻君の出産・育児で赤字になった家計のうめあわせをするため,夜おそくまで内職をする友人も珍しくない.医療機関は他の企業と異なり利潤のみを目的としていない以上,そこに働く多くの医療従業員はまさに今日の物価の高騰のため深刻に悩んでいるのである.その不安,心配が仕事の場に持ちこまれそれが仕事に大きな影響を及ぼすのは当然のことである.ましてや労多くして賃金の低い医療機関では,人手不足はますます拍車がかかり看護婦をはじめ患者の給食員らは1人で何倍かの仕事をせざるを得ない状態である.それでも今日では1人の給与で1人が1か月賄なえないのである.
新しいキットの紹介
改良されたアミラーゼ測定キット"DyAmyl-L"の検討
著者: 竹久元彬 , 野中清美 , 富浦茂基 , 八島弘昌
ページ範囲:P.183 - P.188
はじめに
α-アミラーゼ測定法として,初めて色素結合基質を用いる方法がBabsonら1,2)やCeskaら3,4)により開発されて以来,Amyloclastic法5-7)やSaccharogenic法8,9)などの従来法の欠点である基質デンプンの不安定さや不均一性を解消し,正確度,再現性を向上させ,測定精度を許容範囲内に収めうる代表的アミラーゼ測定方法として,一躍注目を浴びるに至った.さらに市販キットとしてReactone Red 2Bと結合したAmylopectinを基質とする"DyAmyl",Cibacron Blue F3GA-Amyloseを基質とする"Phadebas"などが知られている.これらの市販キットについては種々検討が加えられ,多くの報告10-13)により,その優秀性が実証されている.しかしながら測定に際して用時に基質を溶解させねばならないので非常に煩雑であること,また尿アミラーゼ測定に関しても,いま一歩不満足なものであった.
今般,Warner-Lambert KKより"DyAmyl"に続いて新たに発表された"DyAmyl-L"キットは,基質と沈殿試薬を液状とし,操作を簡易化させ,沈殿試薬の溶媒をメチルアルコールからエチレングリコールモノメチルエーテルに変更し,測定精度,正確度,再現性などの点において良好な結果が得られるとしている.
MICROSTIXの使用経験—細菌尿の簡単な検査
著者: 田尾巴子 , 鶴田良子 , 高野洋子 , 山口司 , 柴田進
ページ範囲:P.189 - P.192
尿路感染症の検査室的診断は,患者から可及的無菌状況で採尿し,①それを遠心沈殿して沈渣を検鏡し,膿球および細菌の有無を調べ,②尿の細菌培養を行い,そこに検出される細菌の種類と数を観察する2方面の技術に要約される.
ところが検鏡も培養もめんどうであるから,それらを回避し簡単な操作で尿路感染症の患者をふるい分けようとする技術が考案された.まず水の汚染の検査に使用されていたGriess (1879)の亜硝酸塩試薬1-4)を細菌尿のふるい分けに応用する試みがWeltmannによって(1925)行われ2),次いで呼吸活動をしている生菌が,2,3,5-tri-phenyl tetrazolium chloride(TTC)を不溶性で紫紅色のformazanに還元する事実(Wundt,1950)5)に着目し,TTC試薬に一定量の尿を加えて紫紅色沈殿物(37℃4時間)を生ずることをもって細菌尿を検出しようとする単純なテストが発表された(Simmons andWilliams,1962)6).
昭和48年度第27回,28回二級臨床病理技術士資格認定試験学科筆記試験
著者: 金子仁 , 富田仁 , 吉岡守正 , 小林稔
ページ範囲:P.193 - P.205
問題
臨床化学
1)次のような検査成績報告書が出来上った.この場合あなたはどうしますか?
(ただし,血清は約0.3mlしかのこっていない)
霞が関だより・21
やる気と認識—秋の国家試験から
著者: K.I
ページ範囲:P.206 - P.206
昨年11月14日,第5回臨床検査技師国家試験,第22回衛生検査技師試験の合格発表があった.過去に行われた他の職種の試験もそうであったが,概して秋の試験は結果がよくないというのが数字のうえからみて言える.
秋の試験は,受験者数も,春の試験より少ないので,わずかな数によって結果を示すパーセンテージも上下しやすく,見方もいろいろあるが,一般的には次のようになるのではないかと思われる.
質疑応答
血中δ-ALADの測定法について
著者: T生 , 和田攻
ページ範囲:P.207 - P.207
問 下記の方法にてδ-ALADを測定しているが,正常値(0.74〜1.46)よりもはるかに低値がでるがどこに問題があるのでしょうか.考えられる点は,①吸光度をmg/lになおしHt値を1/100倍したものを活性値としている,②凍結時間の多少,の2点であるが,そのほかにどんな点に問題があるのか.なお私の求めた活性値の範囲は0.16〜1.23です.
測定法
日常検査の基礎技術
試験菌株の保存法
著者: 坂崎利一
ページ範囲:P.209 - P.216
どのような分野の仕事であろうと,微生物を扱う人たちにとって,株の保存は実務に付随する重要な業務である.臨床細菌検査室においても例外ではなく,特に近年,細菌検査の精度管理の必要性が叫ばれているおりから,それに用いる菌株の保存は,これからの臨床検査においては,ないがしろにできない仕事となろう.
この種の菌は従来しばしば標準菌株と呼ばれているが,この名称は当たらない.生物には標準はありえないし,同じ菌種,同じ血清型であっても,すべての点において完全に同じ菌は存在しえない.それぞれどこかで異なっている.したがって,精度管理に用いる菌株はもちろん由緒正しいものでなければならないが,それは"標準菌株"ではなくて"試験菌株"あるいは"パイロット菌株"と呼ばれなくてはならない.
検査と主要疾患・14
慢性関節リウマチ
著者: 塩川優一
ページ範囲:P.218 - P.219
1.慢性関節リウマチ(RA)の概念
RAは年齢よりいえば30〜50歳で発病することが多く,性別では女性に多い疾患(80%)である.そのおもな臨床症状は慢性の多発性の関節炎で,関節の変形をきたし,ついには寝たきりになることがある.また内臓にもしばしば病変を認める.
検査機器のメカニズム・26
マグネチックスターラー
著者: 水野映二
ページ範囲:P.220 - P.221
溶解攪拌,滴定攪拌に使用されるマグネチックスターラーは1個掛の小形から10個掛の大型まで,また加熱攪拌のホットプレート式,および恒温攪拌のウォーターバス式など表2に示すように53種類余り市販されている.今回はその一例の最も簡単な構造の装置について述べる.
検査室の用語事典
常用病名
著者: 伊藤巌
ページ範囲:P.223 - P.223
10)エリテマトーデス;lupus erythematodes
全身性エリテマトーデス(略称SLE)とも呼ばれ,患者の80〜90%が女性で,発病は15〜40歳に多い.膠原病の一種で,原因については自己免疫説が有力である.臨床症状は多彩で,顔面の定型的な蝶形発疹を欠くことも少なくない.血液または骨髄穿刺液からLE細胞を証明することが,診断上重要である.しばしば腎病変を伴い,その程度が予後を左右する.治療には副腎皮質ホルモンが用いられる.
血清学的検査
著者: 伊藤忠一
ページ範囲:P.224 - P.224
8)α-Fetoprotein;αフェトタンパク
成人肝では産生されないが胎児の肝で産生されるα-globulinである.胎生6週ごろより産生されはじめ,12週から14週で最高値血清濃度(300mg/dl前後)に達し以後徐々に減少し,生後はほとんど血清には検出されなくなる.肝癌,奇形腫などの際に成人の血清中にも高濃度に出現するので,その臨床的診断に応用されている.
走査電顕の目・14
尿沈渣—結核菌
著者: 木下英親 , 田崎寛
ページ範囲:P.225 - P.226
腎・膀胱結核も,肺結核と同様,化学療法の出現以来発生頻度は減少してきているが,近年にいたりその減少速度の緩慢化が指摘され,最多発年齢の高年齢化,発生年齢の分散化などが一般的傾向となっている.臨床症状としては,膀胱炎症状が初発症状として最も多いが,腎部腫瘤,側腹痛,腰痛の腎症状や,発熱などの不定症状も多くなり,無症候性血尿を主訴とするものもまた,化学療法時代にはいって増加しているとの報告がある.
このように,腎・膀胱結核の疫学像,臨床像が変化して,診断がむずかしくなってきているが,尿中結核菌の証明と,静脈性腎盂撮影,逆行性腎盂撮影などによる腎盂像,膀胱鏡検査による膀胱粘膜の所見が,腎・膀胱結核の診断法であることにかわりはなく,これらにより,治療方針が決定され,臨床経過の観察が行なわれている.
シリーズ・一般検査 ふん便検査・2
便の定性検査,顕微鏡的検査
著者: 猪狩淳
ページ範囲:P.227 - P.228
消化管,特に腸管の吸収機能を知る臨床検査はいろいろあるが,手軽に,患者に負担をかけずにできるものは便検査であろう.便の外観,性状をよく観察することで腸管の機能の良否,炎症性変化の有無を見当づけることができ,さらに便中物質の定性,定量検査,顕微鏡検査で,その状態を確かめうる.
私たちの検査室
日本の結核病学界の中枢にあって—財団法人結核予防会結核研究所附属療養所 臨床検査科
ページ範囲:P.229 - P.232
往時の結核のメッカ,清瀬市の一角に,この長い名前の私たちの検査室がある.池袋から30分足らずで,近年の街の発展ぶりには目をみはるものがあるが,清瀬村時代の静寂な武蔵野のたたずまいを懐しむ人も多い.この地に13もあった療養所のほとんどが装いも新たに病院と名を変えた今日もなお,古い木造のままで,療養所の名を固執しているのは,いかにも時代遅れのようであるが,古い革袋にも新しい酒は盛られつつある.従来,日本の結核病学界の中枢にあって幾多の業績をあげてきた当研究所の技術を,呼吸器疾患全般に広げ,この専門分野における最高レベルの診療を目ざしてスタッフは日夜努力している.その最も重要な裏付けとなっているのが,私たちの検査室である.
付・私たちの検査室
新しい検査室へ飛躍!
著者: 工藤是祐
ページ範囲:P.233 - P.233
歴史的にみると,当療養所は他の病院とは異なり,研究所の診療部門として発足したために,臨床検査室が独立の機能を持つようになったのは比較的近年のことである.
附属療養所の開設は昭和22年であるが,当初,検査室として結核菌検査を中心とする1室と洗浄滅菌室が用意され,医師1,検査手4がこれにあたった(研究所には以前から病理,細菌,生化学の3部門があった).この状態がしばらく続いたのち,結核の化学療法時代にはいり,また臨床検査の成長期にもあたり昭和35年ごろから急速に規模を拡大して現在に至っている.したがって現在の部屋は需要の増大に応じ,他目的の部屋を次々に譲り受けたため,まにあわせの感が深く,また器材も十分とはいえず,およそ時代の先端をいく検査室といった外観はない.
Senior Course 生化学
自動化学検査・2—自動化の基礎(2)
著者: 中甫
ページ範囲:P.234 - P.235
前号で自動分析におけるサンプリング,試薬分注および混和,恒温装置について述べたが,今回は,吸光分析,データ記録,その他について解説し,注意点を述べる.
血液
網赤血球の増加と減少
著者: 中島弘二
ページ範囲:P.236 - P.237
赤血球は骨髄内で生産され末梢血中に供給される.血管内を循環し120日後網内系に取り込まれ破壊される.破壊された量だけ骨髄より補われ,血管内に一定量の血液を保っている.
赤血球およびその母細胞である赤芽球のすべてを包含する解剖学的系統をerythronと呼び体内のガス運搬を受け持つひとつの臓器として考える.erythronを3つに分けると便利である.すなわち赤芽球,網赤血球,成熟赤血球でありその関係を図1に示した.幹細胞より分化した赤芽球は成熟することにより核が濃縮し細胞質がせまくなり細胞質内にヘモグロビンが生産蓄積されていく.成熟が進むにつれて核はさらに濃縮し無構造となりやがて脱核する.この時点において,完全に成熟した赤血球とは区別される.すなわち脱核したばかりの赤血球はなおミトコンドリア,リボゾーム,セントリオール,ゴルジ小体を含んでいる.ニューメチレン青,ブリリアントクレーシル青による超生体染色によって成熟赤血球と区別されるがこれらの色素によってみられる顆粒状,糸状構造は色素による人工産物であり,リボゾーム,ミトコンドリアなどの細胞内微小構造物の凝集沈殿である.その形態学的特長により網赤血球と呼ばれている.ライトまたはギムザで染色した場合網赤血球は青味を帯びた大型の赤血球として染まる(多染性大赤血球).細胞内に残っているRNAが青く染まる.血管内に入った網赤血球はさらに24時間の間にヘモグロビンののこり20%を作る.
血清
ウイルスの血清学的検査—補体結合(CF)反応
著者: 中村正夫
ページ範囲:P.238 - P.239
ほとんどのウイルスについて行いうること,また,手技も比較的簡単であるので,ウイルスの血清学的検査方法として最も広く応用されている.
CF反応は一般に感度が低く,特異性の点で他の反応に多少劣る。また,抗体価の上昇も遅い.乳幼児では一般に抗体産生能が低いため,CF抗体価が認められない場合もある.このようなことは本反応の短所である.
細菌
検査業務での滅菌と消毒の実際
著者: 三輪谷俊夫 , 神木照雄
ページ範囲:P.240 - P.241
臨床検査は検査材料の採取から始まる.特に微生物学的検査には検査材料の雑菌汚染(contamination)がその検査結果に重大な悪影響を及ぼすことは周知の事実であり,なにぶん相手が肉眼で見えないものであるだけに,ちょっとの不注意で汚染され,貴重な検査をふいにしてしまうことがある.検査過程において雑菌汚染が起こりうる可能性として次の4つの場合が考えられる.
病理
臨床病理学的立場よりみた電子顕微鏡学・2—電子顕微鏡の種類,特徴および操作法
著者: 相原薫
ページ範囲:P.242 - P.243
光顕と電顕の基本的相違は,光顕は可視光線を用い,電顕は電子線により像をとらえようとすることにあり,光顕では結像系にガラスレンズを用い電顕では電子レンズを用いている(図1).
生理
心音図
著者: 田中久米夫
ページ範囲:P.244 - P.245
心音図は1894年W.Einthovenにより始められたが,臨床的使用に耐えうる心音計は,第二次大戦を契機として進歩を遂げた電子工業により完成をみたものである.
心音図は,臨床的には聴診所見の客観化および恒久的保存記録として利用され,正確な時相の決定や分析もでき,心機図法を応用すればいっそう詳しい心機能の状態をつかみうるなど,心機能検査には欠くことのできないもののひとつである.
My Planning
Laboratory Diagnosisとこれからの臨床検査室のEDPS
著者: Y生 , 菅沼源二
ページ範囲:P.246 - P.247
昨年秋に行われた第5回臨床検査自動化研究会(東京)にも見られるように,現在検査室では,自動化機器をどう使うかから,打ち出されたデータをどう処理するか,またコンピューターをどう生かすかが問題とされている.ホスピタルオートメーションの進むなかでこの"自動化検査室"の問題を技師としてどう考えていったらよいか……
基本情報
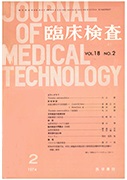
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
