45億年も以前に地球が誕生し,20億年もの長い間を経て,今から27億年前に地殼が安定したと考えられている.さらに10億年も経過して,ようやく生物が誕生したらしい.そして人類が誕生したのは100万年前と推定されている.すなわち,人類の歴史は地球の歴史のうち99.9%以上も過ぎてからのものに過ぎないのである.地球の歴史の中で,大きな造山運動が数回はあったと考えられているし,人類が誕生してからだけでも4回の氷河期を経験している.こうした自然の環境が大きく変動している中で,生物はそれに適応して進化を遂げてきたのである.きっと,生物にとって地球は厳しい生活環境であったに違いない.それになお耐えられるように体内の調節機能が発達して,ホメオスターシスが確立されたのであろう.臨床検査値の生理的変動はそうした調節機能の結果なのである.
人間社会における変革を"波"にたとえて,アメリカの未来学者であるアルビン・トフラー博士は3つの波に分けている."第1の波"は,原始時代からヨーロッパで起きた産業革命までの農業社会であり,人間は自然を畏敬し,自然と調和して生きていた."第2の波"は,産業革命から20世紀を生きつづけた産業社会である.そして,21世紀に向けて,"第3の波"超産業社会へと着実に移行しつつある."第1の波"が自然との調和の上に成り立ったとすれば,"第2の波"はまさに自然を畏れず,人間が自然に挑戦した時代なのである.その結果,農業社会で経験しなかった,新しい人為的な生活環境にさらされることになった.地球上での変化にとどまらず,海底へ,そして宇宙へと人間の生活の場を拡げつつある.そればかりか,原爆・水爆による放射能汚染,産業廃棄物による地球上および地球周辺の空間の汚染,さらに地球自然の貧欲なまでの破壊,など数えきれないほどの生活環境の変化が問題になっている.
雑誌目次
臨床検査34巻1号
1990年01月発行
雑誌目次
今月の主題 異常環境
巻頭言
異常環境と臨床検査
著者: 河合忠
ページ範囲:P.7 - P.7
総説
異常環境への人体の適応
著者: 上田五雨 , 竹岡みち子
ページ範囲:P.8 - P.14
異常環境に生体が曝露されると,代償作用があらわれ,続いて障害,危険,致死状態に入る.外界の刺激には特異的なものと非特異的なものとがあり,生体は体の各系統で,多重反応を示し,障害を修復するようにする.回復が不十分なときには,適応不全とか疾患を呈する.環境の要因が複合的に作用すると,陽性または陰性の交差適応を示す.個体レベルを超えて環境に適応すると,進化が起こる.最近では,異常環境は高度の技術で克服されつつある.
解説
高温
著者: 高谷治
ページ範囲:P.15 - P.19
高温環境は通常でも人類は経験し,生存を保ってきているので,それが湿度とともに過度になり,また運動も加わって長時間に及ぶと異常を発生する.その総称を熱射病というが,この中には日射病(狭義の熱射病),熱疲憊および熱けいれんの3種の病態がある.これらの病的状態に対する診断,治療について,わかりやすく具体的に述べた.特に狭義の熱射病は健康体がおちいる急性の救急疾患であるので,これを救命することは大切なことである.今回はこの予防についてはふれていないが,それぞれの病態については臨床検査が重要であることはもちろんのこと,何かが怠られて大事に至ることは避けたいものである.
低温
著者: 熊切正信
ページ範囲:P.20 - P.23
適応限界を越える寒冷刺激にさらされると,さまざまな病態が惹起される.全身が冷えて低体温になる偶発性低体温症と,裸露部に多い局所障害である凍瘡および凍傷とがある.特に直腸温で35度以下に下がった状態の偶発性低体温症は,外国での独居老人に多いとされていたが,本邦でも注目されるようになった.凍瘡と凍傷については,生活環境の向上と知識の普及とによって減少する傾向にあるが,予防の可能な疾患である.寒冷刺激時の末梢血管の収縮は手,足の温度低下をきたすが,頬,耳にも好発する.これらの部位は,サーモグラフを用いて観察すると,わずかな環境温度の変化にも敏感に反応し低温になる.
高地
著者: 半田健次郎
ページ範囲:P.24 - P.29
高地は低気圧,低酸素分圧,低気温の環境である.生体が高地環境へ曝露された際の生理反応は,その環境の条件,曝露期間の長短によって著しく異なり,個体差も大きい.高地環境曝露に対しては,生体は呼吸・循環機能の亢進を中心とした順応反応により対応する.
急性高山病は,海抜2700m以上の高地へ比較的急速に到達した際に起こる症候群であって,頭痛,不眠,悪心,思考力低下などを訴える.高地肺水腫は最も重症型で,呼吸困難,咳,血痰,チアノーゼ,肺の水泡性ラ音を主症状とする.放置すれば急速に悪化する.迅速な低地移送と酸素吸入が不可欠である.
無重力
著者: 谷島一嘉
ページ範囲:P.30 - P.34
無重量の地上での模擬には,自由落下,弾道飛行,懸垂,長期臥床,水浸,6°ヘッドダウンなどの手段があり,目的に応じて使い分けられる.宇宙の無重量による人体の変化は,循環系のデコンディショニングと起立耐性の低下,骨からの持続的なCaの喪失,抗重力筋を主にした筋肉の萎縮,宇宙酔いなどがあげられる.特に,Caの喪失についてはまだ有効な対策がないのが今後の問題である.宇宙での臨床検査は,無重量という環境条件が地上で考えられないほど特殊なこと,持ち込む検査機器の安全性その他に関する厳しい制限があること,などのために特別な工夫が必要である.
微小重力とライフサイエンス実験
著者: 向井千秋
ページ範囲:P.35 - P.40
微小重力を利用したライフサイエンス研究は,長期宇宙滞在や火星飛行を可能にするだけでなく,重力環境から免れることのできない地球上生命体と重力との関連を知るうえで非常に魅力的な分野と思われる.本稿では,宇宙環境,特に微小重力環境を積極的に利用して行うライフサイエンス実験を紹介するとともに,その有用性や宇宙ステーション時代に向けての発展性について述べたい.
減圧による障害
著者: 池田知純
ページ範囲:P.41 - P.45
減圧によって生じる障害には,体腔内の容積が減圧に伴って増加することによる圧外傷やガス塞栓症,体内の不活性ガスが過飽和になって発生する減圧症,および臨床症状を呈するまでに長期間を要する骨壊死などがある.本稿では,これらのうち,減圧症と骨壊死を中心として,症状,発症機序について概説するとともに,主に障害の予防ないし軽減の見地から,今後さらに発展させるべき検査法について述べた.
放射線
著者: 赤沼篤夫
ページ範囲:P.46 - P.50
自然環境には自然放射線もあり,生物はこれと共存してきた.環境を破壊するのは人工放射線であって,今世紀はじめより,まず医療に,ついで産業に利用されてきた.この人工放射線は,われわれの生活環境および労働環境との調和を図りつつ利用されなければならない.生活環境,労働環境を破壊するのが事故である.この異常環境に対して,まず生命保全の処置を行う必要がある.LD50は約3.5Gyと考えられているが,正しい医療処置により,5Gy程度の被曝までは生存できる.
赤外線・紫外線―眼科の立場から
著者: 堀内知光
ページ範囲:P.51 - P.55
科学の進歩とともに,生活環境は大きく変わり,われわれを取りまく赤外線,可視光線,紫外線などの,強さも量も増加している.眼科の立場から,これら電磁波の眼球に及ぼす作用,特に熱作用と光化学作用を述べ,その結果とされている眼組織のさまざまな障害を紹介する.
振動
著者: 的場恒孝
ページ範囲:P.56 - P.60
この地球に存在する万物は,みな振動体である.人間もまた振動を発生している.このことは心音図,指尖容積脈波図,手掌のマイクロバイブレーションなどでみることができる.振動の人体への障害影響で問題となるのは,手腕系振動障害(または振動病),全身振動障害,公害としての低周波振動・交通振動である.これらの疾病の症状は,症度によって差がみられるが,全身的に影響する.良い影響として振動が使われている例としては,理学療法で用いられるバイブレータがある.
音
著者: 猪忠彦
ページ範囲:P.61 - P.67
音や振動については,これをうまく利用したビジネスが多数成立している一方で,出された音や振動が人体に好ましからざる影響を及ぼしている場合もよくみられる.エネルギー消費量の急激な増大とともに騒音の発生量も増加し,騒音性難聴,ディスコ難聴,超低周波音公害などの社会問題も発生してきている.その一方で,防音,遮音,吸音,消音などの技術も進んできており,これらの好ましからざる影響から逃れるには,人々が自分の耳をどのように適切に管理できるかにかかっているといえよう.
大気汚染
著者: 島正吾 , 落合昭博
ページ範囲:P.68 - P.74
近年,大気汚染にかかわる環境問題は,酸性雨やフロンガスなどによる成層圏オゾン層の破壊の問題,炭酸ガス,メタンガスなどによる地球の温室効果,あるいは浮遊粉塵や排気ガス中に含まれる各種の新しい有害物質による環境汚染の進行とヒトへの健康影響などが注目されており,いずれも新しい次元において今後の取り組みが大きな課題となっている.ここでは,こうした地球規模レベルでの環境汚染の実態を浮きぼりにし,長期,微量かつ慢性曝露下における複雑にして深刻な今日的課題をめぐる今後の対応のありかたに言及せんとした.
時差
著者: 本間研一
ページ範囲:P.75 - P.79
人が急激な時差の変化に暴露されると,不眠,覚醒困難,精神作業能力の低下,胃腸障害などを主症状とする一過性の精神身体的不調が生じる.原因は,再同調速度の異なる2つの生体リズム系に生じる内的脱同調にあると考えられる.その結果,睡眠構造や体温リズム,ホルモン分泌に特徴的な変化があらわれ,生体機能の時間的統一が失われる.時差症状は1週間ほどで自然に消失するので,多くの場合問題ないが,リズムの逆行性再同調による時差症状の遷延化や,くり返し時差に曝露されることによる症状の慢性化は治療の対象となることがある.
話題
宇宙ステーションの健康モニター
著者: 井川幸雄
ページ範囲:P.80 - P.83
宇宙ステーションは,救急医療の面で地球とは独立した医療単位になるので,診断から治療にいたるすべての医療が要求され,さらには疾病の予防も担当する必要がある.しかも,医師が常駐しないことも前提となっている.容量的にコンパクトなドライケミストリーの採用が今のところ予定されているが,機器の開発は民間との協力で進められており,検査項目の選定は宇宙での特殊環境を考慮にいれるが,民間病院での救急医療の経験に基づく優先順位を参考にして決められる.
スポーツ医学に用いられるセンサ・テレメトリ
著者: 芝山秀太郎 , 井元一豊
ページ範囲:P.84 - P.88
スポーツ医学における検査では,運動する生体を取りあげるのが原則であり,スポーツ活動時の自由を拘束せず,無理なくセンサを装着しうることが条件である.生体電気現象や生体内外の物理的活動を採取するために,センサやトランスデューサには,一般の臨床検査とは異なる用法が工夫されており,多チャネルのテレメトリも実用化されている.しかし,法的規制が強化されたので,新たな遠隔距離無線搬送技術の開発が緊要の課題である.
カラーグラフ
腎臓病の病理・1【新連載】
腎生検の実際
著者: 坂口弘 , 緒方謙太郎
ページ範囲:P.90 - P.93
経皮的腎生検法は,1951年,Iverson&Brunによってはじめて紹介された.これは今日,腎疾患,特に糸球体腎炎の組織分類,病像・病態の把握などのためになくてはならない検査法の1つとなっている.この検査は生検針を用いて腎組織を,長さ約1~2cm,幅約1mmの検体として採取し,光学顕微鏡,電子顕微鏡,さらに蛍光抗体法による検索を行うものである.腎臓病の病理について概観する前に,本稿では,腎生検の意義,実際に行われている生検手技,採取された検体のそれぞれの検索のための処理方法とその原理について述べた.
TOPICS
抗イディオタイプ抗体のワクチンとしての応用
著者: 竹田多恵
ページ範囲:P.94 - P.95
抗体が個々の抗原と特異的に結合する可変部領域には,抗原に対応した固有の型,すなわちイディオタイプがある.これは抗体(Ab1)のH鎖とL鎖のN末端約100個のアミノ酸で構成されていて,それ自体もまた抗原決定基となりうる.すなわち,抗イディオタイプ抗体(Ab2)を誘導することができる.このAb2の中には,ほんの一部ではあるが元の抗原と同じか類似の構造(内的イメージ)を持ち,元の抗原と同じ抗原性を示すことができるものがある.これにヒントを得て,Ab2をウイルス感染や癌の予防・治療に応用する試みがなされるようになった.
ワクチンとして使える可能性をはじめて示したのはSacksらである.彼らは,アフリカ睡眠病の病原体Trypanosoma rhodesienseに対するモノクローン抗体(MAb)でマウスを免疫し,得られたAb2をマウスに投与したところ予防効果が得られたと報告してる1).ただこの時の予防効果は,MAbを調整したのと同じ近縁のマウスにしか発現されなかった(allotype-restricted).内的イメージを持つAb2ではなかったようである.抗体可変部のイディオタイプ決定基の中には遺伝的背景が関与する領域や,パラトープ(抗原と直接結合する部分)にあずからない領域もあるので,Ab2がすべて有効なワクチンとはなりえない.
血清コレステロールの正常値
著者: 小泉順二 , 馬渕宏 , 竹田亮祐
ページ範囲:P.95 - P.96
血清コレステロール(TC)が冠動脈硬化の重要な危険因子であることは,広く知られている.血清脂質の正常値は,従来,一般健康人の集団の平均±標準偏差で決められていた.しかし,この方法では環境因子により異なった値となり,また,健康人と思われる人で将来動脈硬化症を生じるおそれのある高脂血症患者を除外することはできず,動脈硬化症の危険因子としての高脂血症を定義する標準値(正常値)を決定することは困難である.したがって,正常値として大規模な疫学調査から得られた正常値が採用されるようになっている.
フラミンガム・スタディによると,TCと冠動脈硬化症(CHD)の関係は,240mg/dlを越えると直線的に高くなると,CHDを生じる閾値が考えられていた1).しかし,1986年に発表されたMultiple Risk Factor Intervention Trial(MRFIT)の成績で,150mg/dlより300mg/dlまで,TCが上昇すればするだけCHDによる死亡が増加することが示され2),現在では,TCは低ければ低いほうが冠動脈硬化に良いと考えられている.
ホスホエタノールアミン
著者: 片岡洋行
ページ範囲:P.96 - P.97
ホスホエタノールアミン(PEA)は,リン脂質代謝の重要な中間体であり,動物の組織や体液中に広く存在することが知られている.
PEAの生理的意義については,リン脂質の構成成分としての役割を除いて十分解明されていないが,ラット乳癌細胞に対して増殖促進作用1)あるいは増殖阻害作用2)を示すことや,造血機能に対する生理的な抑制因子として作用している可能性3)が示唆されている、また,アルカリホスファターゼ活性低下を伴う低リン酸酵素症4)や代謝性骨障害5))の患者の尿中にPEAが多量に排泄されることから,これらの疾患の生化学的指標となっている.また最近,アルツハイマー病(AD)やハンチントン舞踏病(HD)患者の脳内PEA含量が病変の好発する領域で著しく減少していることが認められ,注目されている6).そこで本稿では,PEAとADおよびHDの病因との関連性に関する知見について紹介する.
アルカリホスファターゼの化学発光基質AMPPD
著者: 芦原義弘
ページ範囲:P.97 - P.98
臨床検査に用いられるアルカリホスファターゼの基質としては,従来より比色測定用のp-ニトロフェニルリン酸(PNP)が知られている.また,高感度基質としては4-メチルウンベリフェリルリン酸(4MUP)が一般的である.これらは臨床検査の分野では生化学のみならず,免疫血清でのEIAの標識酵素であるアルカリホスファターゼの基質として利用されている.一方,EIAにおける迅速,高感度化にともない,化学発光あるいは生物発光法が注目されている.本稿では,最近報告されたアルカリホスファターゼの新規な化学発光基質(AMPPD)の反応原理,その特徴,応用について述べる.
1988年,米国のDr.Bronsteinらは,アルカリホスファターゼの安定な化学発光基質3-(2'-spiroadamantane)4-methoxy-4-(3"-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane(AMPPD)を合成した1).その構造は図1の(Ⅰ)に示すように,ジオキセタンに結合するフェニルリン酸とジオキセタン骨格を立体的に安定化させるアダマンチル基よりなる.このAMPPDは酵素により加水分解されて,比較的不安定な中間体(Ⅱ)となる.この化合物はアルカリ溶液中でジオキセタン骨格が開裂して,1重項励起状態のm-ヒドロキシ安息香酸メチルエステル(Ⅲ)とアダマンタノンになる.この励起化合物(Ⅲ)は波長470nmの光を発して基底状態に戻る.この反応は酵素で励起化合物の生成をくり返すため,酵素反応時間20分~30分で発光量がプラトーになる増幅型となっている.アルカリホスファターゼのこの基質に対するKm値は2×10-4mol/lであってPNPや4MUPと類似しており,基質の親和性にアダマンチル基は影響していない.
HCV抗体検査
著者: 宮村達男
ページ範囲:P.98 - P.99
実験的に感染の成立した非A非B型肝炎感染チンパンジーの血漿から抽出されたRNAのcDNAライブラリーから,回復期の患者血清を用いてimmunoscreeningされて得たcDNAクローンが,非A非B型肝炎の原因としてのC型肝炎ウイルス(hepatitis C virus:HCV)由来であろうとする根拠は2つある.1つは,その遺伝子がまったくヒトやチンパンジーの細胞DNAとハイブリダイズせず,gene walkingの結果,全長約10kbのプラス鎖のRNAであったことである1).この塩基配列は,一部のフラビウイルスと相同性があり,クローニングの出発材料であるチンパンジーの血漿の感染実験を長年にわたって地道にやっていたCDCのBradleyらが1982年当時から想定していた感染性因子の諸性状と矛盾しない2).
もうひとつの根拠は,はじめに得られたcDNA断片の近傍のcDNA (非構造蛋白をコードする領域の一部)を組換え酵母の中で発現させ,得られたポリペプチドを用いた抗体のアッセイの結果である3).すなわち,①この抗体が輸血後非A非B型肝炎の大半や散発性の非A非B型肝炎の半数以上に検出されること,②A型やB型肝炎患者にこの抗体は検出されない.これらの結果は,このアッセイ系の抗原が非A非B型肝炎の原因となる感染性因子に由来することを示すと同時に,さらにこのアッセイ系が感染性のウイルスの存在を示唆することがわかり,ウイルスキャリアの検出や,ウイルスの感染経路などについて調べるHCVの血清疫学に強力な武器となりうることがわかった4).日本での献血人口の約1%前後がウイルスキャリアであろうことから,輸血用の供血者のスクリーニングにも有用であることが示された5).また,このアッセイを利用して,肝硬変や肝癌患者(非B型)にも高率に抗HCV抗体が検出されること6)や,母児感染や夫婦間の感染を示唆するような症例も見いだされた7).
Acanthamoebaによるコンタクトレンズ保存液汚染と角膜炎
著者: 坂本雅子
ページ範囲:P.99 - P.100
Acanthamoebaによるコンタクトレンズ(以下CL)保存液汚染とそれによる角膜炎が問題となり,一部マスコミで報導され,特にCL装用者においては混乱をきたしたのは記憶に新しい.
Acanthamoeba角膜炎はAcanthamoebaの寄生によっておこる感染症であり,近年欧米で注目され,本症例の半数以上がCL装用者であることからCLの保存方法などとあわせて問題となっている.以下Acanthamoebaの特徴,検査方法,疫学などについて紹介する.
学会印象記 第36回日本臨床病理学会総会
医療全般から見た臨床検査の再検討―経験主義から統合的選択へ,医学判断学の登場!!/新たな試みに満ちた充実の3日間
著者: 野口英郷
ページ範囲:P.102 - P.103
平成時代最初の第36回日本臨床病理学会総会は,1989年10月5日(木)から7日(土)までの3日間にわたり,京都市宝ヶ池の国立京都国際会館にて,京都大学医学部臨床検査医学教授・村地孝総会会長の下で開催された.一般口演379題,一般掲示343題の計722題のほかに,シンポジウムが16ものテーマで討論された.また,恒例の総会会長講演と特別講演があり,他に技術セミナーが10本,各種専門部会7本があり,最後に公開フォーラムが持たれた.なお,3日間を通して,120社にのぼる医療関連企業の参加の下に,恒例の医療検査機器展示会が今年は同一会場に併設された.
総会会長講演は「calpainとcalpastatin」であった.calpainはCa2+で活性化されるSH基を持ったプロテアーゼの総称で,細胞内ペプチド鎖の限定分解を担う非リソソーム・プロテアーゼであり,calpastatinはcalpainに特異的に作用する細胞内在抑制因子の総称であって,両者とも細胞内に局在して,calpain―calpastatin系という一種の生体制御系を形成している.calpainにはⅠ型とⅡ型,calpastatinには組織型と赤血球型というそれぞれ2種ずつのアイソエンザイムが存在する。両者ともほとんどすべての動物細胞に分布しているが,それらの含有量には組織細胞の種類により大差がある.この事象の意義の解析は今後の課題である.
編集者への手紙
顕微蛍光測光装置による単一細胞内pH測定の検討
著者: 庄野正行 , 石田富士雄 , 池原敏孝 , 宮本博司
ページ範囲:P.104 - P.104
従来細胞内pHの測定は,pH電極,弱酸性,弱塩基色素などを用いていたが,現在は超高感度pH指示薬BCECF-AMが使われるようになった.BCECF―AMは細胞内pH測定のための蛍光試薬としてRinkらによって開発されたfluorescin誘導体である.BCECF-AMは細胞膜を透過した後,細胞内でエステラーゼにより水解され,膜不透過性のBCECFになる.BCECFは励起光450~530nmに対し約504nmにピークをもつ蛍光を発する.現在,細胞内pHは励起光496/450nmの蛍光強度比とpHの関係を示すキャリブレーションカーブ(標準曲線)を用いて算出されている.この方法を基礎にして単一細胞内pHの測定を試みた.図1はThomasらのナジェリシン/K法による標準曲線を示す.
研究
37℃および32℃培養によるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の検出状況に関する検討
著者: 小林宣道 , 鈴木彰 , 大水幸雄 , 上原信之 , 中村徹 , 田代正光 , 黒川一郎 , 熊本悦明
ページ範囲:P.105 - P.108
黄色ブドウ球菌臨床分離株を用いて,32℃および37℃培養におけるメチシリン感受性について調査検討を行った。その結果,被検菌株の約56%は,32℃におけるMICが37℃の2~16倍増加し,それに伴いMRSA検出率の上昇が認められた.また,32℃における感受性試験では,セフェム系多剤耐性傾向を有するMRSAの検出率は37℃に比して有意に高率であった.以上より,MRSAおよびセフェム多剤耐性株の検出において,32℃培養による感受性試験の重要性が示唆された.
資料
解糖阻止剤4種(NaF,モノヨード酢酸,クエン酸,D―マンノース)の比較
著者: 佐藤富美子 , 平野哲夫 , 松崎廣子
ページ範囲:P.109 - P.114
4種の解糖阻止剤について,その阻止効果を比較検討した.NaF,モノヨード酢酸は速効性に欠け,採血1時間以内に血糖値の低下を生ずる.クエン酸は速効性を有するが,溶解性が悪く,検体の溶血が起こりやすい.D―マンノースは速効性を有し,溶解性も良いが,阻止効果は十分でなく,また,血糖および他の検査項目の測定も可能だが,場合によっては影響を及ぼすこともある.以上それぞれ利点,欠点がみられた.
COBAS BACTによる薬剤感受性測定と希釈法,センシディスク法との比較検討
著者: 三澤成毅 , 小栗豊子
ページ範囲:P.115 - P.119
臨床材料分離株を用い,COBAS BACTによる薬剤感受性成績を希釈法ならびにセンシディスク法と比較検討した.COBAS BACTと希釈法およびセンシディスク法との成績の一致率はそれぞれ,90~94%,73~94%であり,センシディスク法より希釈法とよく一致した.薬剤別には,一部の菌種と薬剤の組合せについては一致率が低く,また,偽感性の成績も多く認められた.菌種別には,COBAS BACTと希釈法とでは差が認められなかったのに対し,センシディスク法とではEnterococcusとPseudomonas aeraginosaにおいて一致率が低かった.
質疑応答 臨床化学
リポ蛋白質への超遠心法の影響
著者: Q生 , 寺本民生
ページ範囲:P.121 - P.125
〔問〕HDL,βリポ蛋白を精製するのに超遠心法がよく用いられています.その方法では2~3日超遠心するようですが,その場合,リポ蛋白質として影響はないのでしょうか,ご教示ください.
免疫血清
EIA法によるASO価測定
著者: K生 , 荒川正明
ページ範囲:P.125 - P.127
〔問〕マイクロタイターにSLO (ストレプトリジンO)などの抗原を固定化してEIA法によるASO価測定を実施するのに,よい固定化法,およびその方法(EIA)を確立するまでの注意点および操作法について,具体的にご教示ください.
微生物
Campylobacter pyloriと上部消化管疾患
著者: T生 , 山本一成 , 福田能啓 , 下山孝
ページ範囲:P.127 - P.130
〔問〕最近,上部消化管疾患とCampylobacter pyloriの関係が注目されているようです.その現状とC.pyloriの検出法についてご教示ください.
診断学
健常者にみられる弁口部逆流と病的逆流の鑑別
著者: K生 , 石光敏行
ページ範囲:P.130 - P.133
〔問〕健常者でもみられるという弁口部での逆流について,病的なものとの鑑別はどのように行われるのかご教示ください.
一般検査
フィッシュバーグ濃縮試験直後のPSPテスト
著者: 中西寛治 , 折田義正
ページ範囲:P.133 - P.134
〔問〕フィッシュバーグ濃縮試験直後にPSPテストの依頼がありました.前者で腎臓に負担がかかっていると思われますが,その直後にPSPを実施して正しい成績が出るのでしょうか.よろしくご教示ください.
基本情報
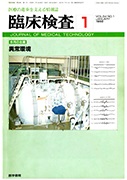
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
