受容体研究,この場合正確にはホルモン受容機構研究はfactとconceptとの間の鎬の削りあいを通して発展してきたとも言えよう.
1942年,F.Albrightは当時使用可能となった副甲状腺ホルモンにより副甲状腺機能低下症患者の補充療法を試み,その一例でこれが失敗に終わったことより,この患者の副甲状腺機能低下症の病態は副甲状腺ホルモンの不足によるのではなく,このホルモンに対する受容機構の障害であるというconceptに達した.ここには,副甲状腺ホルモンが使用可能となったという事実,およびこの症例においてのみそれに対する反応が得られなかったという事実が中心となっている.さらにこのconceptの源流としては,今世紀始め頃から気が付かれていたチャボの一種Seabright-bantamをめぐるconceptがあった.すなわちこのチャボは雄でありながら雌の表現型をとる.したがって男性ホルモンに対し末梢の標的組織が十分に反応しないと考えられた.この考えを敷衍して,ホルモン不全症の中には,ホルモンに対する不応状態があるというconceptがあった.1950年代に入り,ホルモン作用機構の研究が進み,1960年までにホルモン作用機構においてホルモン受容体とそれに引き続き産生される細胞内second-messengerの一つとしてcAMPの意義が確立した.
雑誌目次
臨床検査34巻8号
1990年08月発行
雑誌目次
今月の主題 レセプター
巻頭言
レセプター研究の歴史と展望
著者: 尾形悦郎
ページ範囲:P.887 - P.888
総説
細胞内情報伝達―伝達物質とレセプター
著者: 櫨木修 , 宇井理生
ページ範囲:P.889 - P.893
多くのホルモンは細胞内に取り込まれることなく細胞の機能を変化させる.これは,細胞表面に存在する特異的受容体が細胞外ホルモン濃度変化を認識して細胞内情報伝達系を作働させるためである.受容体のもっ情報変換機構と連動する細胞内伝達系の種類は比較的少なく,いくつかの基本形に分類しうる.
レセプター異常症
著者: 名和田新
ページ範囲:P.895 - P.903
近年の遺伝子工学DNA組み換え技術のめざましい進歩により,ホルモンを含む多くのレセプターの遺伝子構造の解明により,レセプター異常症(レセプター病)の新しい疾患概念が確立された.
レセプター異常症とは,先天性または後天性のレセプター異常により起こる病態で,レセプター病とも呼ぶ.先天性レセプター異常の病因としてレセプターそのものに異常が存在するものと,レセプター以後の細胞内情報伝達機構に異常の存在するものとがあり,広義にはそのどちらも含めたものをレセプター病と呼ぶ.一方,後天性レセプター異常として抗レセプター抗体により惹起される異常も広義にレセプター病に含まれる.本稿では相次いで解明されたレセプター遺伝子DNAを使用してレセプター遺伝子のレベルよりの病因解明がなされつつあるレセプター,およびレセプター以後の情報伝達系の異常症の概念と最近の進歩を紹介する.
技術解説
インスリンレセプター
著者: 本田律子 , 春日雅人
ページ範囲:P.905 - P.909
糖尿病はインスリン分泌の低下,肥満,その他の原因により相対的にインスリンの作用が不足することに起因する疾患群である.インスリンの作用は標的組織の細胞表面に存在するインスリンレセプターを介して発現される.インスリンレセプターに関しては,その構造および機能に関する知見が集積されつつある.本稿では,インスリンレセプターの構造と機能について述べたのち,インスリンレセプターに関する検査法のうちインスリンレセプターへのインスリン結合およびインスリンレセプターのリン酸化について解説を試みる.
TSHレセプター
著者: 内村英正
ページ範囲:P.910 - P.915
TSHレセプターの研究は細胞成分としてきわめて微量であり,その構造解析が著しく遅れていたがphotoaffnity-labellingなどの方法によるcross-linkingによりTSHとレセプターとの強固な複合体をSDS-PAGEなどによる分析でしだいに明らかとなった.ヒトTSHのレセプターはA,B2つのサブユニットからなり,TSHはAサブユニット(50K)に結合するという.情報はBサブユニットに伝えられるが,Bサブユニット(30K)は細胞膜を7回通過して細胞内のアデニール酸シクラーゼcAMP系へと情報を伝達すると考えられている.
ステロイドホルモンレセプター
著者: 中尾誠 , 佐藤文三
ページ範囲:P.916 - P.920
ステロイドホルモンはおのおのの特異的なレセプター(受容体)を介して作用を発現する.臨床医学上非常に重要なことは,乳癌,子宮内膜癌,前立腺癌などのホルモン依存性腫瘍においてレセプターの存在を検索することである.抗ホルモン剤による治療効果を予知し,予後の推定ができるからである.最近エストロゲンレセプターおよびプロゲステロンレセプターの免疫学的測定法が開発され,従来のアイソトープで標識されたホルモンを使用する生化学的測定法とともにますます臨床的に頻用されてくると思われる.
LDLレセプター
著者: 船橋徹 , 松沢佑次
ページ範囲:P.921 - P.927
LDLレセプターはLDLを細胞内に取り込み細胞内コレステロール量の調節に重要な役割を担っている.LDLレセプターの機能異常は血中におけるLDLの貯留を生じさせ,遺伝的なLDLレセプターの欠損または変異によって動脈硬化を高率に合併する家族性高コレステロール血症(FH)を発症させることが知られている.臨床的にはLDLレセプター活性を測定することはFHの診断に必要であるのみならず,その臨床像を理解するうえで重要である.さらにLDLレセプター遺伝子の解析により,その構造と機能の関連が明らかにされつつあり,これらの結果は今後臨床面への応用も期待できるものと思われる.
抗アセチルコリンレセプター抗体
著者: 戸田達史 , 楠進
ページ範囲:P.928 - P.933
重症筋無力症は筋力低下・易疲労性を示す神経筋接合部の疾患であり,本症では特異的に抗アセチルコリンレセプター抗体が検出される.本抗体の検査法には,阻害法(ConA法など),結合法(抗ヒトIgG法など)があり,その原理・測定方法を記した.眼筋型より全身型で本抗体の陽性率が高く,抗ヒトIgG法のほうが陽性率は高い.本抗体の測定は,本症の診断,病態の把握,治療の効果判定にきわめて有用である.
TSHレセプター抗体
著者: 吉田正 , 市川陽一
ページ範囲:P.934 - P.940
TSHレセプター抗体の代表的な測定方法は,TSH結合阻害活性(TRAb,TBll)と甲状腺刺激活性などの生物活性(TSAb,HTACS)に大別される.未治療バセドウ病の80%以上にTRAbやTSAbは認められ,抗甲状腺剤治療の効果判定,寛解や再発の指標として有用である.一方,一部の特発性甲状腺機能低下症では,TRAb陽性の抑制型のレセプター抗体が見いだされ,TRAb強陽性の母親からの新生児は一過性の甲状腺機能低下症を示すことがあり,TRAb測定は臨床上有用である.
インスリンレセプター抗体
著者: 小林正 , 井上勝訓
ページ範囲:P.941 - P.946
インスリンレセプター抗体はインスリン抵抗性の原因となり,インスリンレセプター異常症の中でももっとも頻度が高い.その検出には培養リンパ球が便利であり,標識インスリンとの競合的結合阻害を用いた方法が一般に使われている.レセプター抗体はインスリン作用を阻害する以外にインスリン作用を有し,またその認識部位によってその作用も異なるのでインスリン作用機序の解明にもヒントを与える.
病態解説
ウイルス感染とレセプター
著者: 稲田敏樹 , 山崎修道
ページ範囲:P.947 - P.952
ウイルス感染増殖は,一般にウイルスと細胞表面レセプターとの特異的結合をもってはじまる.しかし,そのレセプターの発現は,細胞,組織,動物種によって一様でなく,さらに,あるウイルスに対するレセプターは一種類とは限らない.また,ウイル特異的レセプター以外に,Fcレセプターを介する感染様式があることも多くのウイルス感染モデルで証明されている.
遺伝子工学的手法を導入した最近の分子生物学的研究は,レセプターの分子構造を明らかにし,ウイルス粒子との結合メカニズムを分子レベルで解明しつつある.HIV感染の研究から,そのレセプター(CD4分子)を感染の予防・治療に応用しようとする実践的研究も進展しつつある.
免疫応答異常とレセプター
著者: 大心池俊哉
ページ範囲:P.953 - P.958
サイトカインは,細胞の増殖や分化を調節する因子として,免疫,造血系に広く作用する.なかでもIL-2は,免疫反応の調節,ことにT細胞の調節や分化をつかさどる因子として1970年代から研究されてきた.分子生物学的手法の導入によってIL-2,IL-2レセプター系と自己免疫疾患,癌などとの関連を示唆する報告も相次いでいる.本稿ではサイトカインレセプターと免疫異常の関連について,IL-2,IL-2レセプター系を中心に概説したい.
成長因子とレセプター―特に腫瘍との関連について
著者: 宮地幸隆 , 庄司享 , 寺園崇 , 入江実
ページ範囲:P.959 - P.964
ヒトEGFレセプターは,全アミノ酸構成が明らかにされた,分子量170Kの糖蛋白である.EGFはEGFレセプターを介して多くの腫瘍の増殖や悪性化との関係が示唆されている,hCG産生腫瘍はEGFレセプターに富み,ヌードマウスに移殖したhCG産生腫瘍は,投与するEGFの濃度により腫瘍の増殖を促進あるいは抑制するbiphasicなeffectを示す.このeffectはEGFレセプターmRNAのexpressionを介してEGFレセプター量を増減することによると思われる.
神経疾患とレセプター
著者: 加藤元博 , 加世田ゆみ子
ページ範囲:P.965 - P.969
脳の変性疾患の代表例について,神経伝達物質レセプターの変化を述べ,病態について考察した.神経伝達物質およびそのレセプター機能による脳病変の検索は,脳障害を神経回路に基づく機能単位毎に選択的に解析できる特長があり,さらに最近はポジトロン・エミッション・トモグラフィー(PET)による患者脳の検索もin-vivoで可能となっているので,今後さらに有用性を増すものと考えられる.
話題
心房性ナトリウム利尿ペプチドレセプター
著者: 森本茂人 , 福尾恵介 , 今中俊爾 , 田淵義勝 , 荻原俊男
ページ範囲:P.970 - P.972
1.はじめに
心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は,松尾教授らにより化学構造が明らかにされた28個のアミノ酸よりなるペプチドで1),心房より分泌され,水・電解質バランスや血圧調節に重要な役割を果たすホルモンである.ANPのレセプターには少なくとも2種類が知られており,これらのレセプターの全アミノ酸配列が知られるようになった.本項においてはANPレセプターの最近の話題を中心に述べる.
血管内皮細胞上のレセプター
著者: 島田和幸
ページ範囲:P.973 - P.974
1.血管内皮細胞の特異的性質
血管内皮細胞は,他の上皮性,間質性細胞などのそれとは異なった特殊な機能を有している.それは,血管内皮細胞が血管内を流れる血液と直に接触する唯一の細胞であることに起因している.そのため,血管内皮細胞上には特異なレセプターが存在し,それらが内皮細胞の特異な機能と結びついている.例えば内皮細胞は,トロンボモジュリン,ヘパリン様グリコサミノグリカンなどを表面に有し,ロンビン,アンチトロンビンⅢなど血中凝固関連因子のレセプターとなり,内皮細胞表面上での凝固反応を阻止している.これは,血管内面において血液の流動性を維持するのに役だっている.一方,流血中のリボ蛋白やインスリンなどのホルモンに関しては,その表面上のレセプターで捕捉した後,内皮細胞内ではそれらを処理し,あるいはシグナル伝達をすることなく単に細胞内を通過させるだけで,これらの物質の真の標的臓器である血管外の実質細胞に輸送する.さらに,内皮細胞自身が,ヒスタミン,アデノシン,プロスタグランジン,カテコラミンなど,種々の生理活性物質の標的細胞となり,内皮細胞由来の血管収縮,弛緩物質の産生,遊出が制御される.
カラーグラフ
学会印象記 第40回電気泳動学会春季大会
二次元電気泳動法の活用と問題点
著者: 中村和行
ページ範囲:P.894 - P.894
電気泳動学会は不惑の年を迎え,一層の発展と充実の道を歩みだしたところである.今回東京都老人総合研究所生化学部の大橋望彦先生を大会会長として,平成2年6月1・2日の両日野口英世記念会館に会員約300名が参加し第40回電気泳動学会が開催された.本会では,教育講演(2題),シンポジウム(6題),一般演題(29題中ポスター発表10題)の発表があった.教育講演1は「細胞バンクとアイソザイム」と題して国立衛生試験所の水沢博博士が国内における細胞バンクの実態と今後の展望を述べられた.細胞バンクでは培養細胞の品質管理が主たる業務であるが,細胞の純度の検定法としては従来細胞内アイソザイムの分析が行われてきたが,それに加えて最近ではDNA-profiling法,すなわちDNAフィンガープリント法を用いて各細胞株の個体識別をきわめて容易に行うことが可能となった経緯と実際を述べられた.
腎臓病の病理・8
尿細管・間質系疾患(I)
著者: 坂口弘 , 緒方謙太郎
ページ範囲:P.976 - P.981
急性腎不全は,急激な腎機能低下によって短期間のうちに尿毒症症候群をきたす病態である.その原因には種々のものがあるが,もっとも頻度の高いものは,急性尿細管壊死である.これは,末梢循環不全による虚血性のものと,重金属や薬物による腎毒性性のものに分けられる.間質性腎炎とは,間質に浮腫ないし線維化,単核細胞の浸潤を示し,尿細管障害を伴う疾患である.それには,原発性のもの,感染症に続発するもの,薬剤性のものなどがあり,さらに免疫学的な発症機序が示唆されているもの,いないものなどさまざまな背景を有するものが含まれている.
TOPICS
αスペクトリンの異常
著者: 林正
ページ範囲:P.983 - P.983
赤血球が個有の形態を保ち,変形したり,復元しうるのは赤血球膜骨格の機能によるものと考えられる.スペクトリンspectrinはその膜骨格を構成する主要なポリペプチドであり,SDS電気泳動法により分子量24000と22000の二つのサブユニットに分かれる.前者をαスペクトリン(Spα),後者をβスペクトリン(Spβ)という.この両者は長い線維状をなし,互いに捻れあってスペクトリンのダイマーdimerを形成し,その端々が自己会合self-associationすることによってテトラマーtetramer,さらにオリゴマーoligomerを形成する.また,これらのスペクトリンは他の骨格タンパク質であるband4.1やactinと結合して網目構造をつくり,さらにglycophorinAやCと結合して膜脂質二重層に固定される.また,Spβはband2.1(ankyrin),band3とも結合して膜脂質に固定される1,2).赤血球膜の電顕観察によると,膜脂質の内側にスペクトリンの線維から構成される六角形の格子構造が認められる3).
こうした膜骨格の異常が赤血球の形態異常と関連することが当然予測されるところである.
E型肝炎
著者: 内田俊和
ページ範囲:P.984 - P.984
E型肝炎は最近新たに発見されたウイルス肝炎で, "E" は経口感染Enterically-transmittedに由来している.これでウイルス肝炎は従来から知られているA型,B型,D (デルタ)型に加え,新たにC型(輸血後型)とE型が発見されたことになる.この他にもF型などのウイルス肝炎があるかどうかは今後の課題である.
以前からヒマラヤ山麓下のネパールやインド亜大陸などの衛生環境が劣悪な国々で,ウイルス肝炎が時々大流行することが知られていた.その規模は大きいもので数万人にも及ぶ.流行は雨期に集中することから,疫学的には感染経路は飲料水や食物を介する経口だろうと考えられていた.経口感染するウイルスには他にA型肝炎があり,その異同が当然問題になっていたわけであるが,1980年になって,A型肝炎の血清アッセイ系が導入されることにより,E型肝炎がA型肝炎と異なることが判明した.
D型肝炎
著者: 岩波栄逸 , 矢野右人
ページ範囲:P.985 - P.986
1977年,イタリアのRizzettoらは,HBVキャリアの肝細胞核内にHBc抗原とは異なった新しい抗原抗体系を発見,δ(デルタ)抗原と命名し報告した1).当初,このδ抗原はHBV関連マーカーの1つでHBc抗原の亜型と考えられていたが,1980年,δ抗原陽性患者の血清によるチンパンジーへの感染実験で,HBVとは別の感染因子(δ因子)として肝炎を発症させることが実証された2).後に,このδ因子は,HBs抗原を外被として,core部分がHBc抗原の代わりにδ抗原とRNAゲノムに置換された構造をもつウイルス粒子で,さらにこのRNAゲノムは不完全なため増殖にはHBVの補助機能を必要とすることもわかった.したがって,δ因子はHBVと常に共存することになる.
1989年,米国カイロン社から発表されたC100抗体は,従来非A非B型と分類されてきた肝炎の大半に検出され,C型肝炎の位置付けが明確となった今日,肝炎はA型,B型,C型,このδ因子によるD型,および東南アジアで流行性に水系感染するとされるE型,に分類されるに至った.
心拍数応答型ペースメーカー
著者: 山分規義 , 桜田春水
ページ範囲:P.986 - P.987
近年ペースメーカーの進歩はめざましく,徐脈性不整脈ばかりでなく,頻脈性不整脈の治療にも使用され,その適応も拡大されてきている.従来はペースメーカーは救命を目的としたが,その後,quality of lifeの向上を目指し,生理的ペーシングとして心房心室同期型ペースメーカーが出現し,最近では心拍数応答型ペースメーカー(rateresponsive pacemaker,以下RR-PM)が話題を集めている.心拍出量を増加させる要因として,心拍数の増加,心房心室同期による前負荷の増大,心収縮力の増大が上げられるが,心拍数増加の影響がもっとも大であるためRR-PMが開発,臨床応用されるにいたった.心拍数を決定する生理的指標として,体動,呼吸数,QT時間,体温,静脈血酸素飽和度,血液pH,右心室圧,右心室収縮性などが上げられるが,本稿ではわが国ですでに臨床応用されている体動,呼吸数,QT時間,体温を感知するRR-PMについて述べる.
粘液線毛輸送系
著者: 梅木茂宣
ページ範囲:P.987 - P.988
粘液線毛輸送系は,分泌腺および粘液細胞による漿液・粘液分泌系と線毛細胞による線毛輸送系の2つの大きな機能系により構成されていて,生体防御機能などの生体の恒常性維持(ホメオスターシス)にそれぞれ重要な働きをしている1・2)。生体の中で粘液線毛輸送系と密接に関係した線毛細胞は,角膜内側,前庭器官,嗅覚細胞,中耳・耳管,鼻涙管,鼻腔,副鼻腔,気道系,卵管,副精巣管などに認められる2).
線毛細胞の線毛は,9対の周辺微小管と2本の中心微小管の9+2構造と呼ばれる微小管構築により構成されている(図1)3).各副線維Aにはそれぞれ隣接する副線維Bに向かってATPaseに富む一対の鍵型構造物の内・外力肢が付着し,これらが伸長および短縮することにより周辺微小管に相互のすべり現象が起こり線毛が屈曲運動する(sliding theory).線毛の正常運動のためにはこのような線毛の正常の超微構造が必要である.
研究
短潜時体性感覚誘発電位(SSEP)の計測に影響を与える因子について
著者: 今本真弓 , 脇英彦 , 吉田裕紀子 , 伊藤嘉子 , 田島諭 , 坂本善弘 , 星田徹
ページ範囲:P.991 - P.994
SSEP検査において,健常人72例を対象とし各頂点潜時ならびに申枢伝導時間(CCT)を指標に用い,SSEP計測時の年齢,性差,身長の影響を検討した.その結果,各頂点潜時は身長の増高および身長を考慮した場合の加齢とともに延長した.また,身長を考慮した場合,性差による差異はなかった.CCTは,加齢とともに延長した.以上の原因として末梢神経の伝導距離および加齢による末梢,中枢神経系の伝導遅延が考えられた.
ニュー・メチレンブルー染色法による白血球細胞の染色における染色色調に対する考察
著者: 相賀静子 , 鈴木優治 , 丹羽和紀
ページ範囲:P.995 - P.998
著者らはニュー・メチレンブルーによる白血球細胞の超生体染色法の色調変化にっいてpHの変化およびヘパリン添加による色素溶液の吸収スペクトルの測定から若干の解析を試みた.
その結果,pH変化とヘパリン添加における色素溶液の吸収スペクトルは各細胞の染色性の色調変化とほぼ一致するシフトを示した.すなわち,白血球系細胞の色調変化は色素と被検物質との物理的な親和性に基づくと考えた.
複雑酩酊患者における血中酒精濃度と脳波像の変化について
著者: 石井みゆき , 田中謙吉 , 斉藤庸男 , 宮内利郎 , 梶原晃
ページ範囲:P.999 - P.1002
酩酊患者にアルコール負荷試験を行い,脳波,血中アルコール濃度および心理検査を実施した.飲酒後1時間で脳波は徐波化し,3時間後に徐波化はもっとも顕著となり,同時に血中濃度も2.5mg/lと最高値を示し,符号検査でも正当数が43%と減少した.精神症状は,易怒的で抑制欠如し,運動失調が目立つ複雑酩酊状態を示した.飲酒終了1時間後,血中濃度の下降とともに徐波化も改善した.
資料
妊婦における抗HTLV-I抗体スクリーニングと確認試験の簡略化について―EIA法,inhibition EIA法,WB法,lF法からの検討
著者: 安藤良弥 , 垣本和宏 , 谷川拓男 , 古木和夫 , 橋本平嗣 , 森山郁子 , 一條元彦
ページ範囲:P.1003 - P.1006
妊婦におけるヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-1)に対する抗体(抗HTLV-1抗体)の測定をEIA法,inhibition EIA法,ウェスタンブロッティング法(WB法),一部についてはIF法により行った.健常妊婦11863例を一次スクリーニングとしてEIA海により検索した結果,うち69例が陽性と判定されたが,これらの検体をinhibition EIA,WB法により再度検討を加えると,カットオフ・インデックス5以上の検体はすべてWB法も陽性であり,カットオフ・インデックス1~5の検体についてはinhibition rateが70%以上の検体ではWB法でも陽性であった.EIA法におけるカットオフ・インデックス1~5の検体についてはinhibition EIAでinhibition rateが70%以上の検体は確認試験をすることなく陽性と断定可能と考えられた.
質疑応答 臨床化学
共存イオンの影響する濃度
著者: K生 , 高橋勝幸 , 関口光夫
ページ範囲:P.1007 - P.1010
〔問〕血清中のNa,K,CIを測定する場合,影響する共存イオンとしてNH4+,各ハロゲンイオン(F―,Br―,I―),HCO3などを調べますが,実際どのくらいの濃度まで影響をみたらよいのでしょうか,また,尿中のNa,K,Clの場合についてもご教示ください.
血液
分葉核球,桿状核球の分類の意義
著者: M生 , 戸川敦
ページ範囲:P.1010 - P.1012
〔問〕最近,末梢血液像検査において,従来からの分葉核球,桿状核球という分類をせずに,好中球(顆粒球)と表記する場合をよくみかけます.これは血球分類装置がそこまで分類しないためなのか,それとも分葉核球,桿状核球という分類自体に意義がなくなったためなのか,現状も含めてご教示ください.
免疫血清
抗核抗体測定に用いる方法
著者: Q生 , 長野百合子
ページ範囲:P.1012 - P.1014
〔問〕抗核抗体測定においては蛍光抗体間接法を用いていますが,酵素抗体法ではなぜいけないのか,その理由をご教示ください.
抗核抗体測定における核材
著者: Q生 , 長野百合子
ページ範囲:P.1014 - P.1016
〔問〕抗核抗体測定において,喉頭癌由来(HEp-2)をなぜ核材として用いるのか,その他の癌細胞ではなぜいけないのか,ご教示ください.また,もし自分自身でこの試薬(キット)を作る場合,どのようにしたらのいのか,方法を具体的にご教示ください.
エッジ効果とは
著者: A生 , 高阪彰
ページ範囲:P.1016 - P.1017
〔問〕「EIAにおけるマイクロプレートへの抗体の吸着」(臨床検査,32(8),936~938,1988)中に"エッジ効果"という言葉があります.詳しくご教示ください.
IgM,lgGの構造とRantz-Randall法によるASO価測定
著者: T生 , 櫻林郁之介 , 和田守史
ページ範囲:P.1018 - P.1019
〔問〕『臨床検査』vol. 32, no. 13, 1672, 1988の「ラテックス凝集法におけるASO価」の記述中,「R-R法においてIgM抗体は,立体構造が柔軟でないため,10個の抗体活性基がすべて抗原との結合に使われるわけではなく,有効抗体活性基の数が少なくなり,2個の抗体活性基(Fab)がともに抗原との結合に関与できるIgG抗体と比較してR-R法での検出はしにくい.」という個所の意味がよくわかりませんでした.詳しくご教示ください.
臨床生理
受動喫煙による肺機能への影響
著者: S生 , 福井順一
ページ範囲:P.1019 - P.1020
〔問〕近年,受動喫煙が生体に悪影響を及ぼすことが注目されるようになりましたが,肺機能に対してはどのような影響があるのかご教示ください.
基本情報
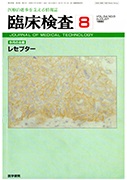
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
