自己免疫疾患,アレルギー性疾患を含めた免疫病を理解するうえで,免疫組織と免疫担当細胞を理解することはたいせっであると考え,筆者らの研究室で行っている接着因子に対する最近の知見を加え,免疫組織と免疫担当細胞を形態学的に観察してみた.
T細胞分化において必須の器官である胸腺は,リンパ球が多い皮質と,Hassall小体などの多い髄質に分けられる.皮質はリンパ球が増殖する場であり,胸腺に入ったいわゆるCD4/CD8 double negativeのプレT細胞は,胸腺上皮細胞から分泌されるIL-7などのサイトカインの影響と,マクロファージから分泌されるIL-1に刺激されたヘルパー/インデューサーのマーカーをもつT細胞がIL-2を分泌しリンパ球増殖を促すと考えられる.皮質に多く存在するT細胞はCD4/CD8 double positiveであり,またCD1陽性であり,髄質に存在するT細胞はCD4あるいはCD8どちらかのsingle positiveであり,またCD3陽性である.胸腺にはいわゆる胸腺上皮細胞,マクロファージとその亜群である樹状細胞(dendritic cell)のほか,筋様細胞や粘液分泌細胞も認められる.胸腺T細胞はこれらに発現されている自己の組織適合性抗原複合体(MHC)を認識することにより,MHC拘束性と自己の細胞に対するトレランスを獲得すると考えられるが,胸腺T細胞がいわゆるdouble negativeからsinglepositiveT細胞にいかにして分化し,MHC拘束性と自己の細胞に対するトレランスを獲得するかの詳細はわかっていない.
雑誌目次
臨床検査35巻12号
1991年11月発行
雑誌目次
特集 アレルギーと自己免疫
カラー図譜
免疫組織と免疫細胞
著者: 島村和男 , 玉置憲一
ページ範囲:P.7 - P.13
I.免疫機能―最近の進歩
1.免疫機能のあらまし
著者: 河合忠
ページ範囲:P.16 - P.21
はじめに
免疫(immunity)という言葉の語源は,"病気から免除されている"ということを意味するラテン語のimmunitasに由来する.この病気にかからないという意味には,生来病気にかからないということ(自然免疫または先天的免疫)と,一度病気にかかった後二度と同じ病気にかからないということ(獲得免疫または後天的免疫)の2つの意味がある.
本来,免疫機能というのは,生体を防御するための働きである.しかし,これが過剰に応答すると過敏症(hypersensitivity)または病的応答(allergy)を示し,生体に障害をもたらす.これは,①異種抗原によって発病する異種免疫病,②同種抗原によって発病する同種免疫病,③自己抗原によって発病する自己免疫病に大別される.また,生来備わっているべき免疫機能が低下または欠損している病的状態を免疫不全症(immunodeficiency)と呼んでいる.
2.免疫担当細胞の遺伝子
1)免疫グロブリン遺伝子と抗体の多様性の生成
著者: 山岸秀夫
ページ範囲:P.23 - P.27
抗体分子
多様な抗原に対応する抗体分子の実体は免疫グロブリン蛋白質であって,図6に示すように重鎖(H鎖)と軽鎖(L鎖)からなっている.C末端側は抗体クラスごとに一定した定常(C)領域である.H鎖とL鎖とは対応するC領域でS-S結合で結ばれ,H鎖同士はさらに,それぞれ対応するヒンジ(H)で3本のS-S結合で結ばれた単位構造(H2L2)を示す.マウスでは,8種の抗体クラスに分類されるが,血清中濃度の高いのはIgM,IgA,IgG (G1,G2A,G2B,G3)の6種で,IgMは5単位構造,IgAは2単位構造として機能する.IgDとIgEは,いずれも1単位構造であるが,細胞(リンパ球)表面に結合して機能する.抗体クラスの違いは,生理活性の違いに対応する.抗体クラスごとに,H鎖はそれぞれ固有のものが使用されるが, L鎖はκとλの2種を共用している.
N末端側は対応する抗原次第で異なる可変(V)領域であり,その中の高頻度変異領域(HVR)が,抗原特異性を決定するうえで重要な相補性決定領域(CDR)に対応することが明らかにされ,N末端側から数えてCDR1,CDR2,CDR3と名付けられている.図7に示すようにH鎖,L鎖ともにV領域を立体構造で示すと,いずれもN端に近い外側に並ぶ.H鎖とL鎖とは,それぞれのCDRが向き合うような型でポケットを形成し抗原を認識する.したがって抗原認識の第1の多様性は,H鎖とL鎖との組み合わせによって形成されることになる.
2) T細胞レセプター遺伝子
著者: 滝本博明 , 吉開泰信
ページ範囲:P.28 - P.29
はじめに
T細胞による抗原認識は,T細胞レセプター(TcR)を介して主要組織適合抗原(MHC)に結合した抗原を認識する.T細胞レセプターは,α鎖とβ鎖からなるヘテロダイマーと,γ鎖とδ鎖からなるヘテロダイマーがある.本稿では,T細胞レセプター遺伝子にっいて概説する.
3.免疫担当細胞の分化
1)B細胞の分化と表面抗原
著者: 王継揚 , 渡邊武
ページ範囲:P.30 - P.34
はじめに
B細胞が骨髄幹細胞から分化する際,決まった順序で免疫グロブリン(Ig)遺伝子の再構成が生じる.すなわち,まずH鎖のDとJの再構成が起こり,続いてH鎖のVからDJへの再構成が生じて,プレB細胞となる.さらに,L鎖のVとJの再構成が生じ,細胞表面にIgMを発現するB細胞となる.この後,抗原刺激などによって,活性化され,最終的に抗体を分泌するプラズマ細胞へ分化する(図14).
したがって,B細胞の分化過程はIg遺伝子の再構成の過程でもある.限りあるV,D,J遺伝子から,再構成を通じて膨大な種類の抗体を産生し,多種多様な抗原に対応することができるようになる.未熟なB細胞の分化は,種々のサイトカインによる刺激や骨髄ストローマ細胞との相互作用によって調節され,機能的な再構成が生じた細胞のみが選択され,成熟する.また,1つのB細胞が一種類の抗体だけを産生するように,Ig遺伝子の2つの対立遺伝子のうち1つだけが発現するように,いわゆるallelic exclusionが起こる.
2)T細胞の分化と自己認識およびトレランスの成立
著者: 中村和史 , 淀井淳司
ページ範囲:P.35 - P.38
はじめに
周知のごとく胸腺(thymus)はT細胞の分化,成熟をつかさどるところである.胸腺におけるT細胞の成熟過程は,T細胞の抗原レセプターであるTcR (Tcel1 receptor)の発現形態により,大きく3つの段階に分けることが可能である.
この間に胸腺では胸腺基質細胞(stromal cell)とT細胞のTcRとの相互作用により,自己認識の可能なT細胞の選択(positive selection)と自己抗原に反応するT細胞の除去(negative selection)が行われ,その結果,自己認識と自己トレランスの成立した成熟T細胞が産生されると考えられている.
4.免疫応答とその調節
1)抗体産生とその調節
著者: 矢田純一
ページ範囲:P.39 - P.40
■B細胞から抗体産生細胞への分化
B細胞の表面には抗原レセプターとしての免疫グロブリンが存在し,抗原分子との結合によってそれらが架橋されることが刺激となってB細胞は抗体産生細胞に分化する過程に入ることになるが,その際T細胞のB細胞への補助作用を必要とする場合とそうでない場合とがある.その違いは抗原の種類によって規制され,T細胞を必要とするものをT細胞(胸腺)依存性抗原,そうでないものをT細胞非依存性抗原という.
後者は抗原分子上に同一の抗原決定基が反復して表出されているという特別の構造をした抗原分子に限られ,IgMクラスの抗体しか産生されない.サルモネラ鞭毛抗原,リポ多糖体,デキストランなどがある.2回目の抗原との反応によっても初回と同様の反応しか起きず,booster効果はみられない.T細胞を必要としない理由は不明であるが,抗原分子自身が抗原非特異的にB細胞の細胞分裂を誘導できる性質(マイトーゲンとしての性質)を持つこと,補体を活性化する能力を持っこと(B細胞は分割された補体第3成分に対するレセプターを持つ)などが関係している可能性がある.
2)細胞性免疫とその調節
著者: 中村玲子
ページ範囲:P.41 - P.43
細胞性免疫
細胞性免疫とはエフェクター機構が細胞によって担われている免疫応答で,IV型アレルギー反応と総称されている.血中抗体は関与しない.反応は抗原特異的なT細胞が抗原を認識することが引き金となって起こるが,最終的なエフェクターがリンホカインによって活性化されたマクロファージである場合と,T細胞自身である場合に大別できる,前者には遅延型アレルギー反応,細胞内寄生菌に対する感染抵抗性などが,後者には移植片拒絶反応,抗腫瘍免疫などの組織・細胞傷害反応が含まれる.それらを表4に示す1).
3)サイトカインと免疫応答の調節
著者: 鈴木博史
ページ範囲:P.44 - P.47
はじめに
免疫反応は大まかに,液性免疫と細胞性免疫に分けられる.液性免疫に中心的役割を果たすのは抗体産生機構である.抗体産生はB細胞の増殖,分化によってもたらされるが,これにはT細胞やマクロファージ,樹状細胞などの助けが必要である.また,細胞性免疫は,T細胞,ナチュラルキラー細胞(NK細胞)やマクロファージが中心になり,腫瘍細胞の破壊や遅延型過敏反応を引き起こす.
これら免疫反応をつかさどる細胞の活性化,分化,増殖に非常に微量で作用し重要な役割を担っているのがサイトカインである.サイトカインの免疫応答における役割は非常に複雑で多岐にわたっているが,本稿ではいくつかの代表的サイトカインについて,抗体産生および細胞性免疫の調節という観点より概説し,そのネットワークについても簡単に触れたい.
5.自己免疫の成立
1)自己抗原と分子相同性
著者: 山本一彦
ページ範囲:P.48 - P.49
はじめに
自己免疫の成立機序は不明であるが,その1つの可能性として自己抗原と外来微生物の分子相同性が考えられている.寄生体とホストの抗原エピトープの相同性1)ということで最初に定義された分子相同性の頻度は意外に高く,たとえば11種類のウイルスに対してマウスで作製した600以上のモノクローナル抗体を,正常のマウスの各臓器との反応性でスクリーニングすると,そのうち3.5%に反応性を認めたとの報告もある2).
分子相同性はmolecular mimicryの訳である.mimicryとは本来,擬態という意味で,動物が別の生物または非生物に似た形態や色彩を持っことによって,他の動物からの攻撃から自己を守ることを指している.したがってmolecular mimicryとは,本来の意味では,寄生体にとって抗原エピトープの相同性から,ホストの中での生存に有利であることを指すべきであろう.このような点では,molecula mimicryは分子擬態と訳されるべきであろうが,表裏一体を成すものとして,抗原性の相同性からホスト側に自己免疫現象を惹起する可能性があるので,これらを含めて広義に分子相同性と訳すことが多い.
2)HLAと自己免疫
著者: 坂根剛 , 岳野光洋
ページ範囲:P.50 - P.52
はじめに
免疫応答は自己と非自己の識別を基本にして成立し,一度,免疫機構の引き金が引かれると,寛容か免疫かというどちらかの様式をとる.正常個体においては自己反応性T細胞の消失もしくは,自己抗原特異的T細胞の末梢レベルでの抑制に基づいて免疫寛容が成立していると考えられており,これがなんらかの機序で破綻すると自己免疫現象の出現につながる.
正常個体の免疫応答性をその多形性に基づいて規定している最も重要な遺伝子は,主要組織適合性抗原(MHC)に連鎖する免疫応答遺伝子である.ヒトMHCであるHLAと自己免疫疾患との関連については,これまでにHLAハプロタイプと疾患感受性という点から議論されてきた.本稿では,これに加えて最近の分子レベルでの解析による知見を含めて,自己免疫発症におけるMHCの役割について概説してみたい.
3)自己抗体産生
著者: 谷本潔昭
ページ範囲:P.53 - P.55
自己抗体は,以前考えられていたような稀な疾患にみられる特異な現象ではなく,正常人でもごく普通にみられる生理的な現象の一部と考えられるようになってきている.この考えを裏付けるものとしては,自己抗体を検出する場合に感度を上げると正常人でも陽性になることが多いこと,老化に伴い自己抗体の検出率が高くなること,赤血球やその他の血球成分の老廃物の処理に自己抗体が深く関係していることなどか考えられよう.したがって,病的ないわゆる自己免疫疾患にみられる自己抗体は,正常に働くべき免疫監視機構がなんらかの機序により破綻し,過剰に抗体が産生されるために起こってくるものと考えられている.
しかしながら,歴史的な背景を知ることも重要であり,これまでに提唱されてきた主要な学説を紹介する.一部は現在でも十分に通用するものである.その後に自己抗体産生の問題点について述べてみたい.
6.アレルギーの成立
1)アレルギーの化学伝達物質
著者: 木原英利 , 森田寛
ページ範囲:P.56 - P.58
はじめに
アレルギーとは,過度で不適当な免疫反応が引き起こす組織障害の総称である.CoombsとGellはアレルギーをその機序によってI~IV型に分類した.現在,アレルギーにこれらの機序が独立して関与していることはむしろ少ないと考えられているが,本稿では特にI型アレルギー反応においてトリガーとして働くマスト細胞から遊離される化学伝達物質に焦点を絞って概説する.
2)IgE抗体産生の調節
著者: 奥平博一
ページ範囲:P.59 - P.61
はじめに
アトピー性疾患患者におけるIgE抗体産生の特徴は,高力価のIgE抗体が持続的に産生されているという点にある.1969年,Claman, H.らにより,抗体産生にはT細胞とB細胞の協力が必要であるという,いわゆるtwo cell theoryが発表されて以来,アトピー患者における持続的なIgE抗体産生は,体内に存在する微量のアレルゲンがT細胞,B細胞を不断に刺激し,継続的にIgE抗体産生細胞を産生し続けることによるというものであった.
しかし,1980年代前半,筆者らはアトピー患者における持続的なIgE抗体産生は,当時知られていなかった長寿命の抗体産生細胞(long-lived antibody forming cell;LL-AFC)の働きによるものであるとする考え方を提唱した.
3)好塩基球,マスト細胞
著者: 山口正雄 , 平井浩一
ページ範囲:P.62 - P.63
はじめに
CoombsとGellによるアレルギー分類のうち,I型は抗原とIgE抗体との反応により惹起されるエネルギー反応の総称であり,この機構の関与する疾患例としてはアトピー型気管支喘息,アレルギー性鼻炎などがあげられる.本稿で扱う好塩基球とマスト細胞は,その活性化の過程でIgE抗体が中心的な役割を持っことから,このI型反応と深い関連があると考えられている.
4)好酸球
著者: 福田健 , 阿久津郁夫 , 真島恵子
ページ範囲:P.63 - P.65
はじめに
好酸球は正常な状態では末梢血白血球の5%以下を占めるにすぎないが,寄生虫症,アレルギー性疾患,ある種の皮膚疾患,悪性腫瘍,血液疾患では増加する.これらの疾患では組織中の好酸球数も増加し,例えば寄生虫症では侵入した虫体の周囲に,代表的なアレルギー疾患の気管支喘息では気管支壁に著しい好酸球の集積を認める.好酸球には特異顆粒と呼ばれる大きな顆粒が多数存在し,ここに寄生虫傷害作用のある蛋白・酵素が存在する.ゆえに,好酸球の本来の機能は寄生虫感染に対する防御と考えられている.
一方,これらの蛋白・酵素は自己の組織や細胞に対しても傷害性を示す.また,好酸球は刺激によりロイコトリエン(LTC4)や血小板凝集因子(PAF)などの炎症性メディエーターも産生・遊離する,このようなことから,アレルギー性疾患での好酸球の役割は,以前考えられていた"炎症の火消し役"とは反対に,"炎症の惹起,増悪"との見方が一般的になってきている.
7.免疫病変の発生機序
1)免疫病の分類と概念
著者: 廣瀬俊一
ページ範囲:P.66 - P.68
はじめに
免疫病とは,免疫異常を起こす疾患を総称する場合がある.この場合,免疫異常が病変の発現に直接つながる疾患と,病変の発現には直接関与しないが免疫学的異常を表現している,すなわち結果として免疫異常が示される疾患とがあり,この両者を区別している場合もあると考えられる.本号は「アレルギーと自己免疫」となっているが,ここでの課題は"免疫病"となっているので,むしろ幅広く免疫異常がみられる疾患をも含めて免疫病の分類と概念について述べ,さらに自己免疫をアレルギーの立場からいかにみるかについて述べることにする.
2)補体と免疫複合体
著者: 吉田浩
ページ範囲:P.69 - P.70
■Arthus現象と血清病
異種蛋白で免疫され,十分な抗体産生がみられているウサギの皮膚に同一抗原を注射すると,局所に炎症が発現し,1~2日後に壊死~潰瘍形成がみられる.このArthus現象は,皮膚~皮下組織での免疫複合体による局所性病変のモデルと考えられている.
抗毒素血清などによる血清療法を受けると,注射後10日前後に発熱し,発疹,リンパ節腫脹,関節炎がみられ,腎病変により尿蛋白陽性となる.この病態は血清病と呼ばれ,免疫複合体(immune complex;IC)による機序がGermuthやDixonらにより立証された.以後,免疫複合体病の名称が定着した.ウサギに131I標識BSAを注入すると,10日前後に関節炎や尿蛋白の出現をみる.この時期には血清補体活性の低下とともに免疫複合体が検出される.病変臓器を蛍光抗体法で検索すると顆粒状沈着が認められ,これを構成するものは注入されたBSAと産生されたウサギのIgG抗体であった.さらに,免疫複合体消失後には抗BSA抗体のみが見いだされ,病変は治癒に至る.本病変は免疫複合体病の代表的実験モデルで,本症発現には免疫複合体と補体の関与が重要であると考えられた.
3)炎症のメディエーター
著者: 平島光臣
ページ範囲:P.71 - P.74
はじめに
炎症は生体防御機構の中で最も重要な機構の1つであり,炎症反応はまず血管透過性の充進による血清蛋白質の血管外浸出,ついで白血球に代表される炎症細胞の血管外への遊出(すなわち病変局所への動員)がみられる.その後,肉芽形成を経て治癒に至る一連の生体反応としてとらえられる.通常好中球の浸潤に始まり,次いでマクロファージやリンパ球,炎症によっては好酸球や好塩基球の浸潤がみられるという反応の経過によって異なる炎症細胞の浸潤をみる.それぞれの白血球は炎症局所へ動員されたあと,局所で炎症反応の進展にきわめて重要な機能を発揮すると予想される.
この白血球の動員機構を惹起する因子である遊走因子は,炎症局所における選択的な炎症細胞浸潤に直接に関与するメディエーターとして炎症反応の進展に重要であると考えられる.補体由来の因子や免疫グロブリン由来因子などの体液性因子のほかに,細胞由来の因子としては,組織肥満細胞が産生する因子群とリンパ球やマクロファージなどが産生するサイトカインが炎症のメディエーターとして近年詳細に検討されるようになった.体液性因子や組織肥満細胞由来因子については多くの総説を参照されることを希望し,今回はとくにサイトカインについて簡単に述べていきたい.
II.アレルギー疾患
1.アレルギー疾患の成立機序
著者: 伊藤幸治
ページ範囲:P.76 - P.79
■アレルギーとは
アレルギーは,フランスのPirqueによって1906年に提唱された概念である.これはギリシャ語のαλλoσ(allos;Other,変化した)とεργo (ergo;action,作用,能力)とを組み合わせて作った言葉で,変化した反応能力を意味する.現在では,アレルギーとは抗原抗体反応のうち病的なものを指している.アレルギー疾患は以下の4型に分けられる(Coombs&Gellの分類,表1),
2.アレルギー疾患に共通の検査
1)皮膚テスト
著者: 早川哲夫
ページ範囲:P.80 - P.81
はじめに
気管支喘息,アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患では,IgE抗体を介した即時型アレルギーが関与しており,IgE抗体の検出はアレルギー性疾患の診断・治療に不可欠である.IgE抗体は組織の肥満細胞に付着するという特徴があり,この特徴を利用して,皮膚組織に少量の抗原を投与し,即時型アレルギー反応の出現の有無によってIgE抗体を検出するのが皮膚テストの原理である.最近ではRAST法,ELISA法などによる血清診断が容易になり,普及しているが,皮膚テストはこれら血清診断法より感度がよく,簡便であり,安価であるなどの理由より,今でも広くアレルゲン(IgE抗体)の検出法として用いられている.
2)P-Kテスト
著者: 十字文子
ページ範囲:P.82 - P.84
P-KテストはPrausnitz-Kustner reaction,pas-sive transfer test, übertragungsmethode,他働転嫁試験などと称される.
3)パッチテスト
著者: 田所憲治
ページ範囲:P.84 - P.85
■抗触性皮膚炎
ある物質が皮膚に接触した後,接触した皮膚に比較的限局して発生した皮膚反応(紅斑,浮腫,丘疹,小水痕などが単独にあるいは混在する湿疹反応であることが多い)を接触性皮膚炎(contact dermatitis)という.
接触性皮膚炎はその機序によりアレルギー性皮膚炎(allergic contact dermatitis)と,物質の刺激による一次性刺激性皮膚炎(primary irritant dermatitis)に分けられる.前者は,細胞性免疫を介する遅延型アレルギーをその主な機序としている.これに対し,接触後5~30分で膨疹発赤反応を生ずるものを接触性蕁麻疹(contact urticaria)といい,これには抗原に対するIgE抗体による即時型アレルギーによるものと,抗体を介さずヒスタミンなどの化学伝達物質(chemicalmediator)が遊離されることによる反応がある.
4)誘発試験
著者: 滝沢始
ページ範囲:P.86 - P.89
アレルギー疾患の診断法として,誘発試験は信頼性の高い検査であるが,同時にアレルギー反応を誘発するのであるから危険性を熟知して行う必要がある.眼アレルギーにおける眼,鼻アレルギーにおける鼻,食物アレルギーにおける摂食試験,および薬物アレルギーにおける試験は各々別項に譲り,ここでは気管支喘息と過敏性肺炎における誘発試験について述べる.
5)総IgE,IgE抗体の測定
著者: 中川武正
ページ範囲:P.89 - P.92
はじめに
気管支喘息やアレルギー性鼻炎などのアレルギー性疾患は,好塩基球・肥満細胞の表面上に結合したIgE抗体とアレルゲンとの反応を介して,細胞内から遊離される化学伝達物質の作用により惹起される.ゆえにその病態生理上,IgE抗体が重要な役割を果たすことは明らかであり,臨床検査でIgE抗体を測定することはアレルギー診断に直結するといっても過言ではない1).また,総IgEはおそらくはIgE抗体の集合体として把握すべきものと考えられ,その測定もまたアレルギー診断の助けとなる.本稿ではこれらの測定法とその意義に関して述べる.
6)IgG(IgGサブクラス),IgM,IgA抗体の測定
著者: 灰田美知子
ページ範囲:P.93 - P.94
近年,各種アレルゲンに対する各クラスの特異的抗体がenzyme linked immunosorbent assay(ELISA)を用いることによって測定可能となり,各種アトピー性疾患でその測定の報告が見られるようになった.しかし,現在IgE抗体以外のIgG,IgA,IgM抗体についての臨床的役割については不明な点が多い.
例えばlgG抗体は,IgE抗体と同様に化学伝達物質を遊離するとの報告もあれば,また,逆に遮断抗体として作用するとの報告もみられる.確かにアトピー性疾患ではIgE抗体のみならず,IgG,IgG4,IgA抗体なども高値を示す傾向があり,今後,これらすべてを配慮することにより,臨床的に有用な情報が得られる可能性がある.
7)ヒスタミン遊離試験
著者: 高石敏昭
ページ範囲:P.95 - P.96
はじめに
好塩基球,マスト細胞は,どちらも細胞膜表面上に高親和性のIgEレセプターを有している.そのレセプターにIgEが結合し,さらに当該抗原がIgEに結合することによってIgEレセプターの架橋が起こり,その後の一連の細胞内情報伝達機構の活性化を介して,最終的には化学伝達物質が放出されて1型アレルギーが発現する.
細胞1個当たりのIgEレセプター数は,ヒト好塩基球で約30万個,ヒトマスト細胞(肺)で約80万個と計算されているが,ヒスタミン遊離反応が引き起こされるためには一部のレセプターに架橋が起これば十分である.
8)好酸球数および好酸球成分の測定
著者: 須甲松伸
ページ範囲:P.97 - P.99
はじめに
酸性色素に染まる白血球すなわち好酸球は,1879年Ehrlichによって見いだされた.その後,好酸球は,寄生虫感染症,アレルギー性疾患などの患者の末梢血中に増加することが知られるようになった.しかし,なぜそれらの疾患で増加するのか,好酸球の役割が何かについては最近まで不明であったが,免疫機構により増殖・分化が制御されていること,好酸球の顕粒中に組織傷害性蛋白(MBP,ECPなど)が含まれていることがわかってきた.
これらの蛋白は,アレルギー病変部の組織に沈着して炎症を起こし,病状を悪化させることが推測されている.こうしたことから,各アレルギー性疾患では,好酸球の数の測定に加えてこれらの蛋白量を測定し,疾患と好酸球の関連が調べられている.
3.アレルギー疾患と検査
6)食物アレルギー
著者: 向山徳子
ページ範囲:P.127 - P.133
はじめに
食物あるいは食品添加物の摂取により生ずる異常反応は広くadverse reaction to foodsと称される.American Academy of Allergy and ImmunologyCommittee1)は食物に対するadverse reactionを表25のように分類し,そのうち食物あるいは食物に含まれている成分を摂取することによって起こる免疫反応を食物アレルギーとした.
その発症機序はI型アレルギーのみならずIII型,IV型が関与していることもあり,また免疫学的機序だけでなく,生体側の消化管の透過性の状態や,感染,遺伝,酵素欠損などにより修飾されることも多く,検査方法の選択や検査データの解釈には十分考慮をはらう必要がある.
7)職業アレルギー
著者: 中村晋
ページ範囲:P.133 - P.141
はじめに
職業に関連したある特定の物質が抗原となって惹起されるアレルギー疾患を職業アレルギーoccupational allergyと呼ぶ.一概に職業といっても歴史的に何百年来連綿と続いている伝統的なものもあれば,最近新しく興った産業もあり,また全国どこにもある普遍的なものから,ある地域にのみ限局する独特で地方色豊かなものまで多彩を極める.したがってこれらの職業に関連する物質には,ごくありふれたものから,一般には考え及ぼないものまで非常に広範囲にわたる.一方このような職業環境において感作性物質(抗原)の作用を受ける生体側の臓器をみるとcase bycaseに異なり,発現するアレルギー症状(疾患)にも差を生ずるのは当然で,同一抗原によっても臨床上ある場合は喘息発作が起ったり鼻症状,結膜症状をみるが,またある場合には皮膚炎が前面に押し出されることがあり,これらが相互に合併することも少くない(表28).
本稿では誌面の都合もあり,職業性接触性皮膚炎については貼布試験など皮膚科的手技が検査の中心となり該当項で詳述されるのでその方に譲ることとし,職業性喘息と職業性過敏性肺臓炎に的を絞って診断に必要な臨床検査について述べる.
8)小児科領域のアレルギー疾患
著者: 早川浩
ページ範囲:P.142 - P.146
はじめに
アレルギー疾患と検査について,小児科領域の成人と異なる点を中心に述べよう.まず小児のアレルギー疾患の特徴を述べ,次に主な疾患の検査に当たって小児において注意すべき事項をあげる.各々の検査そのものについては他の項に譲り,詳細は割愛する.
3)皮膚アレルギー
(1)蕁麻疹
著者: 高路修 , 山本昇壯
ページ範囲:P.104 - P.105
■病態
蕁麻疹は,一般的には掻痒とともに限局性発赤を伴う膨疹として現われ,数時間後には跡形もなく消退する一過性の限局性浮腫である.その膨疹は真皮上層の血管透過性の亢進によって生ずる.血管透過性亢進は種々の化学伝達物質によって惹起されることが知られているが,通常の蕁麻疹ではヒスタミンが最も重要な役割をもっていることは疑いのないところである.
皮膚におけるヒスタミンの大部分は,真皮上層部の血管周囲に多く存在している肥満細胞中のt顆粒に貯蔵されている.肥満細胞は種々の刺激により,ヒスタミンその他の化学伝達物質を遊離するが1),その刺激はアレルギー性のものと非アレルギー性のものに大別される,アレルギー性の場合は,多くはレアギン(主としてIgE)の関与するI型アレルギー反応であるが,III型アレルギー反応に伴う補体の活性化によって産生されるアナフィラトキシンが関与している場合があることも知られている.非アレルギー性の場合には,物質あるいは刺激が直接肥満細胞に対して化学伝達物質遊離因子として作用する.
(2)アトピー性皮膚炎
著者: 前田啓介 , 吉田彦太郎
ページ範囲:P.106 - P.108
はじめに
アトピー性皮膚炎(AD)は,外来性の抗原に対する免疫応答と生体側の異常な反応性によって発症するアレルギー性皮膚疾患である.このatopic dermatitisという名称は,1932年Sulzbergerら1)によって提唱されたが,彼らはCoca,Cookeら2)の提唱したレアギン(IgE)抗体が主役となって発症する即時型アレルギー反応の"アトピー,atopy"を本症の本態と考えた.しかしながら,現在,アトピー性皮膚炎の病態には即時型反応だけでなく種々の免疫反応や生理・生化学的,薬理学的異常などが関与していると思われる.
このようにアレルギーがアトピー性皮膚炎の重要な発症機序であるため,原因アレルゲンの検索が診断と治療に重要な意味を持つ.筆者らは,表13に示すような検査を施行し,診断と治療に役立てている.今回は,アトピー性皮膚炎の免疫学的特徴を中心に,診断に必要な検査について,筆者らの若干の知見を含めて概略を記した.
(3)接触皮膚炎
著者: 中山秀夫
ページ範囲:P.108 - P.110
■病態,病像
接触皮膚炎には,大きく分けて刺激性接触皮膚炎とアレルギー性接触皮膚炎の2種がある.前者は表皮細胞に毒性のある化学物質が付着したために起こる組織障害で,毒性が強ければ水疱,壊死や強度の発赤,腫脹,びらんなどを生ずる.灯油や強酸,強アルカリ,化学兵器などの接触でこれが起こり,ふつうchemicalburnと呼ばれる.
一方,毒性の弱い化学物質が数日くらい皮膚についても,ふつうなんの障害も起こらないが,これが何週間も続くと,皮膚は発赤し,落屑,表皮肥厚が起こって,荒れた皮膚になる.これは台所洗剤や工業用洗剤のような界面活性剤を連用したときとか,化粧品中のプロピレン・グリコール,1,3-ブチレン・グリコールなどが高濃度で含まれているときに起こりやすい.このタイプは慢性刺激性接触皮膚炎と呼ばれる.
(4)光過敏症
著者: 市橋正光
ページ範囲:P.111 - P.115
はじめに
長年にわたり,皮膚は単なる内界と外界のバリヤーであり,その役割は角化細胞と色素細胞が主役と考えられてきた.
しかしながら,1970年代に入ると紫外線(ultraviolet light;UV)に曝露された動物皮膚は紫外線誘発皮膚癌を拒絶できなくなること1,2),腫瘍特異的サプレッサーT細胞が誘導されていること3)が見いだされ,生体免疫系への太陽光の影響が注目されるところとなった.一方では中波長紫外線(UVB)は表皮Langerhans細胞の機能を障害し4),紫外線曝露皮膚に感作物質(ハプテン)を外用すると,ハプテン特異的アレルギー反応を抑制することが見いだされている5).このように皮膚は単なる物理的バリヤーではなく,免疫システムをも備えた臓器であることが理解できる.
5)呼吸器アレルギー
(1)気管支喘息
著者: 放生雅章 , 工藤宏一郎
ページ範囲:P.118 - P.121
概念
気管支喘息はアレルギーを含めた気道狭窄を引き起こすさまざまな機序が,多数の細胞および化学伝達物質を介して,複雑なしくみで起こってくる疾患である.昔から喘息は基本的な概念として「可逆性を有する閉塞性肺疾患」と考えられ,気道平滑筋の収縮がその本態であると思われていた.しかし最近の知見では,この病変は即時型喘息反応の主病変で,あくまで喘息の一部にすぎず,中心はむしろ好酸球浸潤を伴う気道炎症,すなわち慢性剥離性好酸球性気管支炎だとする見解が主流となってきた.
気管支喘息の定義に関しては,過去さまざまな提案がなされているが,未だ病態生理が完全には解明されてはいないことや,その臨床症状が多岐にわたっていることなどから現在なお統一的なものはない.しかし,その試みのいずれにも共通する重要な事項を集めると,次の4項目に要約される.
(2)過敏性肺(臓)炎
著者: 鈴木直仁 , 大田健
ページ範囲:P.121 - P.124
はじめに
過敏性肺(臓)炎(hypersensitivity pneumonitis)は,有機粉塵の反復吸入によって感作され,免疫学的機序によって発症する間質性肺炎1)で,外因性アレルギー性胞隔炎(extrinsic allergic alveolitis)と呼ばれることもある.古くは農夫肺(farmer's lung),サトウキビ肺(bagasscosis)など職業病として報告され,その後鳥飼病(bird fancier's lung),空調病(air conditionerdisease)など職業に関係ない病態も知られるようになって,本症は稀な疾患ではないことが明らかになってきた2).また,原因物質も種々のものが知られるようになり,有機粉塵のみでなく,一部の無機低分子化合物(イソシアネートなど)も本症を惹起しうることが知られてきた.
表21に,現在知られている主な過敏性肺臓炎の種類と推定原因物質3)を示す.わが国では,夏に好発し,しばしば家族内発生を示す夏型過敏性肺臓炎が最も多く,全症例の約3/4を占めていることが特徴である.
(3)PIE症候群
著者: 金子富志人 , 秋山一男
ページ範囲:P.125 - P.127
はじめに
PIE症候群とはpulmonary infiltration with eosinophiliaの略称であり,好酸球増多を伴う肺疾患の総称である.
本症候群に関する最初の報告はLoeffler1,2)によるもので,のちにLoeffler症候群と呼ばれるようになった.その後,Weingartenはtropical eosinophiliaと題する論文を報告した3).Reeder,Goodrichは少しずつ病像や予後の異なる症例をまとめてPIE症候群と呼ぶことを提唱し4),Croftonらは同様の考えからpulmonary eosinophiliaとして,各群間には互いに移行があるとしながらも5群に分類した5).その後,Liebow,Carringtonらは末梢血好酸球増多は示さないが,肺組織に好酸球浸潤を認める症例を報告し,末梢血ばかりでなく組織の好酸球増多を含めた広い概念としてeosinophilic pneumoniaを提唱した6).また,胸部X線上,異常陰影を認めず組織学的に好酸球浸潤を認めた症例も報告されている7).
III.自己免疫疾患
1.自己免疫疾患と成立機序
著者: 狩野庄吾
ページ範囲:P.148 - P.150
はじめに
自己免疫疾患は,自己の生体構成成分に対して免疫学的寛容の制御に破綻をきたした結果として免疫応答が高まり,産生された自己抗体や自己反応性T細胞が関与して発症する疾患である.
2.自己免疫疾患の検査
1)免疫グロブリンとクリオグロブリン
著者: 大谷英樹
ページ範囲:P.151 - P.153
免疫グロブリン
血中濃度の高いmalor immunoglobulin,すなわちIgG,IgAおよびIgMは容易に測定され,臨床的に広く利用されている.これらの免疫グロブリンの増加は,次の2つの様式で起こる1).すなわち,多クローン性(polyclonal)の免疫グロブリン増加と単クローン性(monoclonal)の増加である.両者を鑑別するためには,電気泳動による蛋白分画で,γ分画の形状をよく観察することがたいせつである.
2)リンパ球
(1)リンパ球サブセットの検査
著者: 佐川公矯
ページ範囲:P.154 - P.157
■膜抗原を利用したサブセットの検査
1)膜抗原とモノクローナル抗体のCD分類
ヒトのリンパ球は非常に多様である.ヒトのリンパ球はいくつもの細胞群(subset,サブセット)によって構成されている.サブセットとは,特定の共通の性格を持った細胞の集団である.したがって,1つのサブセットに属している細胞は,他のサブセットに属している細胞とは性格も機能も異なる.当然,細胞表面に表現されている膜抗原のパターンも異なるはずである.この原則を逆に利用して,膜抗原の違いを測定することによって,リンパ球のサブセットが決められてきた.
これらの膜抗原を識別するための試薬として,細胞融合法を応用して,数多くのモノクローナル抗体が作られてきている.これらのモノクローナル抗体と,抗体が認識するヒト白血球の膜抗原は,国際CD分類によって表示されるようになった.CD分類の中でヒトのリンパ球に関係したものを表61,2に示した.この表6に示したモノクローナル抗体を使って,リンパ球のサブセットが解析される.
(2)リンパ球幼若化試験
著者: 西成田進
ページ範囲:P.158 - P.159
はじめに
リンパ球は抗原やマイトーゲン(mitogen:リンパ球分裂促進物質)の刺激によりDNA合成を高めて分裂,増殖し,形態的にも幼若リンパ球に変化する.抗原やマイトーゲンの刺激はモノカイン産生,T細胞からのリンホカイン産生を高め,自身の芽球化を促進するとともにB細胞による抗体産生を増強する.リンパ球幼若化試験は,リンパ球を介した生体内の免疫状態を推測する検査法である.手技の詳細は成書に譲るが1),一般的には被検リンパ球を抗原やマイトーゲンとともに培養した後,リンパ球の反応を3H―サイミジンの取り込みによるDNA合成能で測定する.
主なマイトーゲンとそれに反応するサブポピュレーション,サブセットを示す(表10).
(3)NK細胞活性の検査
著者: 内田温士
ページ範囲:P.160 - P.161
■NK細胞の役割
NK (ナチュラルキラー,natural killer)細胞は,1970年代半ばに腫瘍細胞に対する細胞傷害反応を研究している過程で発見された.当時研究者は,自己あるいは同一組織型の腫瘍に対する特異的細胞傷害反応の発見を期待していた.実際,ある種の癌患者および発癌性ウイルスで誘導した担癌動物でそのような特異反応が観察された.しかしながら,特異抗原で免疫されていない正常の動物やヒトのリンパ系細胞もまた,ある細胞や株化腫瘍細胞を傷害することが判明した.この細胞傷害活性は自然に備わっているものと考えられ,この現象に関与するエフェクター細胞はNK細胞と命名された.
このようにNK細胞は細胞傷害反応によって検出されており,この細胞の定義は主として機能的なものであった.しかし最近の細胞生物学,分子生物学を含む広範な研究により,1988年に開かれた第5回国際NKワークショップで,NK細胞はT細胞レセプターのα,β,γ,δ鎖の再構成がなく,表面形質がCD3-CD16+またはCD3-CD16-のLGL (大顆粒リンパ球)と定義された.LGLとは形態学的には大型で,細胞質が広く,アズール顆粒を含むリンパ球である.
(4)in vitro抗体産生の検査
著者: 村上雅朗 , 杉田昌彦 , 熊谷俊一 , 井村裕夫
ページ範囲:P.161 - P.164
はじめに
正常な免疫応答において,抗原刺激を受けたB細胞は,T細胞や単球およびそれらから産生される種々のサイトカインによる調節を受け活性化,増殖,分化という3つのステップを経て,抗体産生を行うようになる.このB細胞固有の機能としての抗体産生をinvitroで検出する代表的な方法を表13に示した.B細胞の異常な活性化とそれに伴う自己抗体の産生は,全身性エリテマトーデス(SLE)をはじめとする全身性自己免疫性疾患の病態の中心をなすものである.
本稿ではSLEを例にとり,PFC (plaque formingcell)法およびELISA法を用いたin vitro抗体産生機能検査によってB細胞の機能異常や自己抗体の産生機構がどのようにして明らかにされるかを述べる.
(5)サプレッサーT・ヘルパーT細胞機能の検査
著者: 原まさ子
ページ範囲:P.165 - P.166
はじめに
抗原特異的免疫応答の中心的役割を担うT細胞は,T細胞レセプターを介して多様な抗原を認識し,活性化される.その役割として,
(1) B細胞が抗体産生細胞に分化し成熟するのを補助する(ヘルパーT細胞)
3)HLA抗原
(1) HLAクラスI抗原
著者: 安部かすみ , 内藤説也
ページ範囲:P.167 - P.168
はじめに
ヒトの主要組織適合性遺伝子複合体(major histo-compatibility complex)であるHLAは,当初主として同種移植の際の拒絶反応に関与する抗原を支配する遺伝子座領域として発見されたが,現在では生体の防御機構の1つとして重要な役割を担っている遺伝子群と認識されている.生体の防御機構,いわゆる免疫機構は,まず生体が自己,非自己を認識することからその免疫応答は作動するが,その認識過程において,HLAは深いかかわりをもつため自己免疫疾患を中心として,多くの疾患とHLAとの関連性の研究がなされてきたのである.
HLA抗原を規定するヒト第6染色体短腕部にあるHLA遺伝子座は,セントロメアから遠い部よりHLA-A,B,C抗原を規定するクラスI,C2,C4などを規定するクラスIII,HLA-DR,DQ,DPのいわゆるHLA-Dを規定するクラスIIに区分され,それぞれの遺伝子産物をクラスI,II,III抗原と分類して呼んでいる.本稿ではHLAクラスIについての総論,疾患との関連性について述べる.
(2)HLAクラスII抗原
著者: 猪子英俊
ページ範囲:P.169 - P.171
はじめに
ヒト主要組織適合複合体であるHLA抗原(humanleukocyte-associated antigen)は,細菌やウイルスなどの外来抗原をT細胞に抗原提示して活性化し,これらの外来抗原を駆逐するための一連の免疫応答を誘導する重要な抗原系である.すなわち,HLA抗原は自己と非自己を識別する遺伝的標識であり,外来抗原が侵入した際に自己であることを主張しているHLA抗原と照合することにより非自己を認識し,T細胞にその情報を伝達する役割を担っている.したがって,免疫系はHLA抗原の遺伝的標識を手がかりとして自身のHLA抗原を発現している身体を自己と認識し,自らの細胞や臓器に対しては決して免疫的攻撃を加えない,いわゆる免疫学的寛容(トレランス)が成立している.これに対して自己免疫疾患は,自己の抗原や細胞を非自己と誤認し,これに攻撃を加えるために生ずる免疫寛容維持の破綻による疾病であり,HLA抗原がその発症に寄与していることは想像に難くない.
主としてクラスI抗原(HLA-A,-B,-C抗原)は,キラーT細胞の活性化に関与し,クラスII抗原(HLA-DR,-DQ,-DP抗原)はヘルパーT細胞の活性化に関与しているが,本稿では,特に自己免疫疾患の発症に深くかかわっているHLAクラスII抗原を取り上げ,その発症の分子機構と診断のためのDNAタイピングについて概説する.
(3)MHCクラスIII
著者: 徳永勝士
ページ範囲:P.172 - P.174
■MHCクラスIII遺伝子群
MHCクラスIIIという呼び名はもともと便宜的なものである.すなわち,6番染色体短腕上で狭義のHLA(クラスIおよびクラスII)遺伝子群の間に位置する遺伝子を総称したものである.その当時は,クラスIIIとしてB因子,C2,C4A,C4Bの補体遺伝子と21ヒドロキシラーゼ(21OHAおよびB)のみが知られていた.
ところが現在,これらの近傍に新しい遺伝子の存在が続々と報告されており,クラスIIIの定義に関して研究者の間に異論がある.つまり,補体(ここでは以後簡便のために,クラスIIIに属する補体成分を,単に"補体"と呼ぶ)と21OHだけをクラスIIIと考える研究者もあれば,クラスIとクラスIIの間に位置する遺伝子をすべて含めて考える研究者もある.統一見解に至るにはしばらく時間がかかると思われる.
4)補体系
(1)補体分解産物
著者: 清水章 , 宮野章
ページ範囲:P.174 - P.178
はじめに
免疫反応,炎症反応に伴い,補体系が活性化され,補体成分が消費され,生じた分解産物の一部が血中に流れる.従来CH50や補体成分の減少を補体活性化の指標としているが,分解産物の増加のほうがより鋭敏に活性化の程度を反映する.補体分解産物は,それぞれの疾患の重症度,活動性,予後,治療方針を判断する指標として優れている.自己免疫,アレルギー,感染症,炎症,出血,外傷,火傷,手術,透析など広範囲な病態に対し測定されている.
分解物のうち,C4a,C3a,C3dについてのデータが多く報告されている.C4d,C3b,C3c,iC3b,FactorBの分解物,C5a,終末補体コンプレックス(terminalcomplement complex,SC5b-9)なども重要な指標であり,これらのすべてが並行して増減するのではなく,種々の病態によって,血漿中に上昇する成分が異なっている.
(2)免疫複合体
著者: 𠮷野谷定美
ページ範囲:P.178 - P.180
■免疫複合体を検査すべき病態
アレルギー,自己免疫疾患を疑った場合,客観的データとして免疫異常を表わす検査,炎症の程度を表わす検査,組織障害を表わす検査の3つの観点から初期の診断的アプローチが始まると予想される.免疫複合体の検査は,このうち免疫異常を表わす検査として位置づけられ,免疫複合体陽性であればその患者に免疫異常が存在することの証拠となる.
ここで強調したいのは,流血中の免疫複合体が必ずしも患者の主たる病変を生じる原因物質であるとは限らないという点である.ちょうど,自己抗体の検査と似ていると思うが,自己抗体は患者に自己免疫機序があることを表わしており,免疫複合体は自己免疫機序に限らず免疫機構全体の異常を表わしていると考えられる.例えば,肝臓や網内系による異物処理能に問題が生じた場合でも免疫複合体は高値となるし,まだよくわかっていない免疫機構の異常で免疫複合体が高値であると考えられるケースも存在する.
5)自己抗体
(1)リウマトイド因子
著者: 江崎一子 , 延永正
ページ範囲:P.181 - P.184
はじめに
リウマトイド因子(RF)はIgGのFc部位を認識する抗体で,慢性関節リウマチ(RA)やその他の膠原病に高頻度に出現する代表的な自己抗体の1つと考えられている.
RFの存在が最初に確認されたのは1940年で,WaalerによりRA患者血清が家兎γ-グロブリン感作ヒツジ赤血球を凝集することが報告された1).その後,1948年にRoseらはこの凝集反応がRAの診断に応用できることを見いだし,RF測定法としてのWaaler-Rose反応が確立されるに至った2).当初,RA患者血清で高い陽性率を示すことからリウマチ様因子と命名されたが,その後の研究でRFは必ずしもRAに特異的なものではなく,RA以外の膠原病,慢性感染症,肝炎などや,時に正常人にも検出されることがわかってきた.
(2)LE細胞
著者: 横張龍一
ページ範囲:P.185 - P.186
はじめに
急性・活動期の全身性エリテマトーデス(SLE)の患者から採血して試験管内に2時間前後放置,凝血させた後,血塊を壊して白血球を集め,塗抹標本を作製してGiemsa染色を行い,特に辺縁部を注意して検鏡すると,紫紅色の封入体を持った細胞を多数認める.これがLE細胞現象である.LE細胞現象がSLEの診断に主要な意義を持っていたときには,この凝固法のほかに,ヘパリンで凝固を止めた血液を試験管内でガラス玉とともに1~2時間回転させた後,白血球を集めて同様の染色を行う方法もあった.ヘパリン法のほうがきれいなLE細胞を見いだせるとされているが,方法の繁雑さのゆえに現在ではあまり行われていない.ちなみに,EDTA (エチレンジアミン四酢酸)で凝固を止めた場合には,補体がまったく関与できなくなるので,LE細胞の形成はない1).
(3)抗核抗体(蛍光抗体法による)
著者: 東條毅
ページ範囲:P.187 - P.190
■検査の目的
臨床検査における抗核抗体とは,真核細胞の核内に含まれる多種類の抗原性物質に対する自己抗体群の総称である.抗核抗体は抗原特異性にしたがって多種類に分類され,それぞれの抗体名で呼ばれる.抗体陽性疾患の中心となるものは全身性エリテマトーデス(SLE)であるが,この他の膠原病各疾患でもその陽性率の高いことが知られてきた.
核内にある抗原性物質には,生理的な溶液に不溶性のものもある,このため溶液内反応のみでは,患者血清中の抗核抗体群はその一部しか検出することができない.抗核抗体の第一次スクリーニング法としては,抗原性核物質に対する抗体のすべてを一括する検出法が適切である.この目的に合う検出法が,蛍光抗体間接法による抗核抗体検査法である.
(4)抗DNA抗体
著者: 金井芳之
ページ範囲:P.190 - P.192
■LE細胞の発見
いわゆる抗核抗体発見の発端は1948年,Hargravesらが全身性エリテマトーデス(SLE)患者の骨髄塗抹標本中にLE細胞を発見したことにある.LE細胞とは,血液採取後,壊れた細胞核にLE因子が反応し,細胞核が膨化しヘマトキシリン体となり,これを白血球が貧食した結果形成される細胞のことである.正常人の骨髄細胞とSLE患者の血漿を試験管内で保温してもLE細胞は形成されることから,LE細胞を形成する因子はSLE患者血漿中に存在すると考えられた.後の研究で本因子はIgG抗体で,これに対応する抗原はDNA-ヒストン複合体(ヌクレオソーム)であることが明らかにされた.
これを契機に,1960年に一本鎖(ss) DNAに対する抗体がSLE患者血清中に存在することが証明され,抗DNA抗体の種類が注目されるようになった.
(5)抗ENA抗体
著者: 宮地清光 , 鷹野佐恵子 , 田川まり子
ページ範囲:P.193 - P.195
はじめに
ENAは,extractable nuclear antigenの略で,生理食塩水や生食加リン酸緩衝液(PBS)に可溶な核蛋白物質である.
1972年Sharpらは,SLE,進行性全身性硬化症(PSS),多発筋炎/皮膚筋炎の3つの疾患の臨床症状を持ち,抗ENA抗体が陽性の例を混合性結合組織病(MCTD)と名付け報告した1,2).抗ENA抗体は,ENAで感作したヒツジ赤血球を用いた受身感作血球凝集反応(PHA)で検索された.さらにRNase処理ENAを用いたPHA法で抗体価が有意に低下,または陰性化するRNase感受性ENA抗体と,低下しないRNase抵抗性ENA抗体を見いだしていた.後に二重免疫拡散(DID)法にてRNase感受性ENA抗体は抗nRNP抗体,さらに最近ではU1RNP抗体とも呼ばれ,RNase抵抗性ENA抗体は,抗Sm抗体とほぼ例外なく一致した.ほかにspeckled型抗核抗体(ANA)を示し,ENAに対し沈降抗体を示す抗SS-B,抗Ki抗体なども広義に抗ENA抗体と呼ぶ.
(6)抗RNP/Sm抗体
著者: 三浦比斗志 , 大久保光夫
ページ範囲:P.195 - P.197
抗U1-snRNP (snRNP)抗体と抗Sm抗体は抽出可能核抗原(extractable nuclear antigen:ENA)に対する抗体のひとつであり,各種の膠原病患者血清から検出されるが,それぞれの抗体は混合性結合組織病(mixed connective tissue disease;MCTD)と全身性エリテマトーデス(SLE)に対して特異度が高いことが特徴となっている1,2).この抗U1-snRNP (snRNP)抗体とSm抗体に関する最新の知見とその臨床的意義について紹介する.
(7)抗SSA/Ro抗体,抗SSB/La抗体
著者: 秋月正史
ページ範囲:P.197 - P.198
はじめに
抗SSA/Ro抗体と抗SSB/La抗体は,ともに有核細胞の可溶性抽出物を用いた二重免疫拡散法で見いだされた自己抗体である.名称は,高頻度に検出される疾患名(Sjögren syndromeのAおよびB抗体)および発見のきっかけとなった患者名(Ro,La)によるものである.抗SSA抗体と抗Ro抗体,および抗SSB抗体と抗La抗体はそれぞれ独立して記載されたが,後に同一物であることが判明し現在の名称が一般化した.
(8)抗DNAトポイソメラーゼI抗体
著者: 三森経世 , 桑名正隆
ページ範囲:P.198 - P.200
はじめに
膠原病患者血清中には,自己細胞成分に対する多彩な自己抗体が検出される.このような自己抗体は特定の疾患または臨床症状と密接な関連があることが示され,膠原病の診断,病型分類,予後推定,治療方針の決定など,臨床的に有用であることが確認されている.
抗DNAトポイソメラーゼI (Topo I)抗体は,こうした自己抗体の1つで,強皮症のマーカー抗体とされる.本稿では,抗Topo I抗体の対応抗原,測定法,臨床的意義および現在考えられている病因との関連について概説する.
(9)抗セントロメア抗体
著者: 諸井泰興
ページ範囲:P.201 - P.203
はじめに
細胞核成分に対する自己抗体として,きわめて多数の抗核抗体の存在が明らかにされ,しかもそのおのおのが種々のリウマチ性疾患や肝疾患などと関連して出現することが判明している.抗セントロメア抗体(anticentromere antibody;ACA)についても1979年の筆者らによる報告以来,多くの検討が加えられてきた1,2).本抗体は強皮症の病型との関連から臨床家の注目を浴びると同時に,染色体セントロメアという細胞分裂に必須の微小構造に特異的な抗体という点が多くの細胞生物学者の関心を呼び,この方面からの研究も多数に上っている.本稿では,主として臨床的な立場から,ACAに関するこれまでの知見を交えて概説する.
(10)抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体
著者: 斉藤栄造 , 吉本有希子 , 岡田聰
ページ範囲:P.203 - P.206
はじめに
多くの自己免疫疾患で疾患特異的な自己抗体が見いだされる.多発性筋炎(PM)でも,複数の疾患特異的自己抗体が知られている1).このなかで,抗Jo-1抗体を代表とする抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体は,出現頻度が最も高く,臨床的意義,病因的意義がよく検討された代表的な自己抗体である.
アミノアシルtRNA合成酵素は転移RNA (tRNA)にアミノ酸を付加する酵素で,蛋白合成の第一段階で重要な役割を担っている.アミノアシルtRNA合成酵素は複数存在し,個々の酵素は特定のアミノ酸を付加する.この過程で,アミノアシルtRNA合成酵素は活性化アミノ酸と複合体を形成し,次いで,tRNAと結合する.
(11)抗ヒストン抗体
著者: 簑田清次
ページ範囲:P.206 - P.208
はじめに
金身性エリテマトーデス(SLE)をはじめとする自己免疫疾患においては,さまざまな核成分に対する自己抗体が血清中に存在することがその最大の特徴である.抗ピストン抗体は抗DNA抗体と並ぶ代表的自己抗体であり,自己免疫疾患での出現頻度は非常に高率ではあるが,SLEにおける抗二本鎖DNA抗体,抗Sm抗体,抗RNP抗体,混合性結合組織病(MCTD)における抗nRNP抗体,進行性全身性硬化症(PSS)における抗トポイソメラーゼI抗体のように疾患特異性はあまり認められない.したがって,さまざまな自己免疫疾患に出現してくるが,従来有名なことは,薬剤誘発性ループスに非常に高頻度に出現することである.
自己抗体に関する研究は,最近,長足の進歩を遂げているが,その成果の主体は,疾患の再分類化と,自己抗体をプローブとして使用することによる細胞内での自己抗原の機能の解明,すなわち細胞生物学への寄与である.残念ながら,疾患特異性が非常に高い自己抗体ですら,その疾患の発症メカニズムや病態生理に自己抗体が直接的に関与しているという確かな証拠はない.このことは,自己抗体の研究を主体に行っている研究者にとって,大きなジレンマである.
(12)抗PCNA抗体
著者: 高崎芳成
ページ範囲:P.209 - P.211
はじめに
抗PCNA抗体は1978年,宮地らによって全身性エリテマトーデス(SLE)の患者血清中に特異的に検出される抗核抗体(ANA)の1つとして報告された1).宮地らはこの抗体が肝,腎などの実質細胞とは反応せず,増殖を続ける培養細胞やマイトーゲン刺激を受けたリンパ球などの核抗原と特異的に反応することを明らかにし,その対応抗原を増殖性細胞核抗原(proliferatingcell nuclear antigen;PCNA)と名付けた.
その後,この抗原の生物学的および生化学的特性が検討され,細胞周期の1ate G1 phaseに特異的に核内に出現し,分子量34kD,等電点4.8のポリペプチドよりなる酸性核蛋白であることが示された2,3).その結果,Bravoらによって増殖性細胞に特異的に出現する物質として報告されたサイクリンと同一の分子であることが確認され,さらにPCNAはDNAポリメラーゼ―δの補助蛋白としてDNA複製の際,3'末端より5'末端に向かうleading strandの合成に不可欠な物質であることが示された4).
(13)抗カルジオリピン抗体
著者: 市川健司 , 小池隆夫
ページ範囲:P.212 - P.214
はじめに
抗カルジオリピン抗体(aCL),ループスアンチコアグラント(LA),梅毒血清反応の生物学的偽陽性を起こす抗体などの,いわゆる抗リン脂質抗体は,全身性エリテマトーデス(SLE)をはじめとする自己免疫疾患にしばしば認められる.最近,これらの抗リン脂質抗体が,子宮内胎児死亡,各種血栓症,中枢神経症状,血小板減少などの臨床症状と関連することが明らかにされ,1986年,Hughes,Harrisら1)により,上記徴候を呈する患者群に対し"抗リン脂質抗体症候群"という疾患概念が提唱された.
自己免疫疾患患者や,明らかな基礎疾患を持たずに上記の抗リン脂質抗体症候群の臨床症状を呈する患者において,抗リン脂質抗体を正確に測定することは,本症の予後を知り,また治療計画を立てるうえで重要である.本稿では,抗リン脂質抗体のなかでも特に注目されているaCLの固相酵素抗体法を用いた測定法および測定上の問題点を述べ,その臨床的意義を概説する.
(14)ループスアンチコアグラント(ループス抗凝固因子)
著者: 谷口修 , 埜野千穂 , 橋本博史 , 廣瀬俊一
ページ範囲:P.214 - P.217
■ループスアンチコアグラントとは
1952年にConleyとHartmannは,SLE患者で全血凝固時間とプロトロンビン時間の延長を示すが特定の凝固因子欠乏のない,特殊なアンチコアグラント(anticoagulant)を持つ2症例を報告した1).このアンチコアグラントは,特定の凝固因子に対するインヒビター(inhibitor,抑制因子)とは異なる後天性の凝固抑制因子で,1972年にFeinsteinとRapaportにより"1upus anticoagulant"と名づけられた2).
ループスアンチコアグラント(LAC)はγグロブリン分画に存在し,IgGまたはIgMクラスに属する自己抗体で3~5),陰性荷電リン脂質と反応する抗リン脂質抗体であると考えられている6,7).1980年にThiagarajanらは,LACの活性を有するマクログロブリン血症患者のモノクローナル蛋白(IgM,λ)が,陰性荷電リン脂質であるホスファチジルセリン,ホスファチジルイノシトール,ホスファチジン酸とは反応するが,陰性荷電を持たないホスファチジルコリン,ホスファチジルエタノールアミンとは反応しないことを示した6).さらに1982年にShapiroらは,LAC陽性の患者17人のγグロブリン分画が,カルジオリピン(cardiolipin:CL)をはじめとする陰性荷電リン脂質と反応することを二重免疫拡散法で確認した7).
(15)抗ミトコンドリア抗体
著者: 上村朝輝 , 早川晃史 , 打越康郎 , 吉田俊明
ページ範囲:P.217 - P.219
■抗ミトコンドリア抗体とその分類
原発性胆汁性肝硬変(primary biliary cirrhosis;PBC)患者血清中に,ヒトおよびラットの腎尿細管細胞,胃壁細胞あるいは甲状腺上皮細胞内のミトコンドリアと反応する抗体が存在することが蛍光抗体法で明らかにされ,抗ミトコンドリア抗体(antimitochondrial antibody;AMA)と命名された1).このようにAMAはPBCに特異的かつ高頻度に認められる自己抗体の一種で,ミトコンドリアの内膜あるいは外膜に存在する抗原に対する抗体である.
AMAにはM1~M9までの9種類の亜型があることが報告されており,これは主に抗原の存在部位がミトコンドリアの内膜か外膜かという点,およびトリプシン処理に対する抗原の感受性の有無,さらに疾患との関連などの点から表34のように分類されている2).抗原の局在部位とトリプシン処理に対する感受性が同じでも,蛍光抗体法による腎尿細管での主たる反応部位が異なる.
(16)抗LKM抗体
著者: 宮地清光 , 樋渡恒憲
ページ範囲:P.220 - P.222
はじめに
1974年Rizzettoらは慢性活動性肝炎(chronicactive hepatitis)の患者血清中に,抗ミトコンドリア抗体(antimitochondrial antibody;AMA)と異なる自己抗体を発見し,その対応抗原の存在様式より抗肝腎ミクロソーム(liver kidney microsome;LKM)抗体という名称をつけ報告した1).日本ではなぜかその報告はなかったが,当研究所では抗LKM抗体とは別のミクロソーム系の2つの抗体に注目していた2).そこで鑑別のためHomberg教授より同抗体を入手し,1989年から1990年9月まで6例の抗LKM抗体を同定した.これらの症例は,AMA陽性と判定され原発性胆汁性肝硬変(primary biliary cirrhosis)が疑われたものもあった.
本抗体の頻度は,AMAの3%以下と思われるが,抗核抗体(antinuclear antibody;ANA),抗平滑筋抗体(antismooth muscle antibody;ASMA)とは共存しないことから,自己免疫性慢性活動性肝炎のtype2を形成していると思われ重要である.
(17)抗平滑筋抗体
著者: 光井洋 , 池田有成
ページ範囲:P.222 - P.224
抗平滑筋抗体(anti-smooth muscle antibody;SMA)は,1960年代にルポイド肝炎に特徴的な自己抗体として初めて報告された1).現在では肝疾患において,自己免疫機序の関与を示すものと考えられている.
(18)抗TSHレセプター抗体
著者: 玉置治夫 , 網野信行
ページ範囲:P.224 - P.226
はじめに
自己免疫性甲状腺疾患の患者血中には,種々の抗甲状腺自己抗体が存在する1).そのうちでも抗TSHレセプター抗体(TSH receptor antibody;TRAb)は,Basedow病における甲状腺機能亢進症および一部の原発性甲状腺機能低下症の発症原因と考えられ,したがってその測定は疾患の診断および経過観察には必要不可欠と考えられている1,2).
(19)抗サイログロブリン抗体
著者: 網野信行 , 日高洋
ページ範囲:P.226 - P.228
はじめに
サイログロブリンは甲状腺濾胞コロイドの主成分で,分子量約65万の可溶性糖蛋白であり,正常人血清中にも10~40ng/mlの濃度で存在する.このサイログロブリンに対する自己抗体は,自己免疫性甲状腺疾患すなわちBasedow病,橋本病において高率に検出され,その診断にきわめて有用と考えられている1).
(20)抗ミクロソーム抗体
著者: 網野信行 , 日高洋
ページ範囲:P.228 - P.229
はじめに
自己免疫性甲状腺疾患において,抗ミクロソーム抗体(antithyroid microsomal antibody)は高頻度に検出され,自己免疫性甲状腺炎の存在と密接な関係があると考えられている1).最近抗ミクロソーム抗体は,甲状腺ペルオキシダーゼに対する抗体であることが明らかにされており2),甲状腺細胞に対して細胞障害作用を有することが推測されている.
(21)抗赤血球抗体
著者: 遠山博
ページ範囲:P.230 - P.233
赤血型抗体の分類と性状
抗赤血球抗体の存在は,その血清に赤血球を少量加え,なんらかの処置をすることによりそれら赤血球の凝集・溶血などを起こす場合に証明される.
(22)抗リンパ球抗体
著者: 山田明
ページ範囲:P.234 - P.235
はじめに
抗リンパ球抗体は抗白血球抗体の一種である.頻回に輸血を受けた後,あるいは妊娠の後に,輸血のドナーや児の父親の白血球に対し抗体を生じるが,これは特定のHLA抗原に対するものである.全身性エリテマトーデス(SLE)の患者では,約半数に抗リンパ球抗体の出現をみるが,これはしばしばnaturally occurringという言葉を冠して呼ばれるように,輸血などによる人為的な免疫によるものではない.また特定のHLA抗原を持ったリンパ球だけでなく,誰のリンパ球に対しても反応する.自己のリンパ球に対しても反応するので,SLE患者の持つ多彩な自己抗体の一種と考えられている1).
(23)抗血小板抗体
著者: 池田康夫
ページ範囲:P.235 - P.237
はじめに
抗血小板抗体は,大きく自己血小板抗体と同種血小板抗体に分類される.臨床上,その測定意義は異なっているが,測定の原理は同じで,血小板膜に結合する免疫グロブリンを定量する.以下に,抗血小板抗体の測定について,原理や方法,臨床的意義について述べてみたい.
(24)抗好中球細胞質抗体
著者: 吉田雅治
ページ範囲:P.238 - P.240
はじめに
抗好中球細胞質抗体(anti-neutrophil cytoplasmicantibody;ANCA)の報告は,1982年Daviesら1)が半月体形成を伴った巣状,壊死性糸球体腎炎の患者血清中に認めたのが最初である.近年,ANCAがWegener肉芽腫症(Wegener's granulomatosis)の疾患標識抗体であり,疾患活動性の指標になると報告され2,3柱目されている.Wegener肉芽腫症のANCAは,蛍光抗体間接法(indirect immunofluorescence assay;IIF)上,ヒト好中球細胞質がびまん性に染色される(cytoplasmic ANCA;C-ANCA)点が特徴である.一方,最近,顕微鏡的結節性動脈周囲炎(microscopicpolyarteritis nodosa),特発性半月体形成性腎炎(idiopathic crescentic glomerulonephritis)においてもANCAが検出されている4,5).これらはIIF上好中球の核周辺が強く染色され(perinuclear ANCA;P-ANCA),Wegener肉芽腫症のC-ANCAと区別される.すなわち,血管炎症候群6,7)および腎炎を呈する諸疾患のなかで,ANCAが病態に関与するANCA associated vasculitis and glomerulonephritisがあり注目されている.
(25)抗白血球抗体(抗顆粒球抗体)
著者: 高本滋
ページ範囲:P.241 - P.243
はじめに
白血球はリンパ球,顆粒球,単球からなる不均一な集団の総称である.したがって抗白血球抗体という場合,共通抗原に対する抗体と各細胞に対する抗体の総称との2つの意味を持つ.しかし前者の例として確立されているのは抗HLA抗体だけであり,本稿では後者の意味に限定して話を進める.もっとも本号において,抗リンパ球抗体,抗好中球細胞質抗体については別項で解説されるため,これらについては割愛させていただく。また抗単球抗体は頻度も低く,臨床的な意義も十分解明されていないこともあり,詳細は他書1)に譲り,本稿では抗顆粒球抗体(anti-granulocyteantibody;AGA)について概説する.
(26)抗GBM抗体
著者: 大井洋之
ページ範囲:P.243 - P.245
はじめに
抗糸球体基底膜抗体(anti-glomerular basementmembrane antibody;抗GBM抗体)と疾患との関係で種々の検討が行われているものとして腎炎,類天疱瘡,移植腎があげられる.ここでは主に病態,診断,治療において検出が試みられている腎炎について記述する.検出法のほとんどは,皮膚の基底膜を抗原とする類天疱瘡においても同様である.
(27)抗アセチルコリンレセプター抗体
著者: 太田光煕 , 太田潔江
ページ範囲:P.245 - P.247
はじめに
重症筋無力症(myasthenia gravis;MG)は,神経筋接合部の異常に基づく疾患で,臨床的に外眼筋,構音筋,四肢筋などの易疲労性,筋力低下を特徴とし,これらの症状は抗コリンエステラーゼ剤による一過性の症状改善をみるという臨床所見を示す.その病型は,外眼筋のみに障害のみられる最も軽症な眼筋型から,きわめて強い四肢脱力や球症状を呈する全身型重症例まで多様である.
本症は高率に胸腺異常が認められることから,自己免疫疾患として把えられてきた.また,本症に抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)が特異的に検出されることが明らかにされて以来1,2),抗AChR抗体の測定は本症の診断や,治療成績の評価に有用な指標となっている3).
(28)抗インスリン抗体
著者: 山田浩幸 , 老籾宗忠
ページ範囲:P.248 - P.249
最近,精製インスリン,あるいはヒトインスリンが使用されるようになり,インスリン抗体の出現は少なくなってきたと考えられる.しかし,なお,ヒトインスリン使用例においても高いインスリン抗体価を有する症例がみられることも報告されており,インスリン抗体測定法の特徴とその臨床的意義を検討することは重要である.
(29)抗T3,T4抗体
著者: 高田薫 , 網野信行
ページ範囲:P.249 - P.251
はじめに
甲状腺ホルモン,トリヨードサイロニン(triiodothyronine;T3)およびサイロキシン(thyroxine;T4)は大部分がサイロキシン結合グロブリン(thyroxinebinding globulin;TBG),プレアルブミンおよびアルブミンと結合して存在し,ごく一部の遊離型T3,T4(fT3,fT4)が生理的作用を発揮している.しかし,1956年に甲状腺疾患のある患者のなかで,これらの蛋白のほかにT3,T4が免疫グロブリン,すなわち特異自己抗体と結合している症例が見いだされ1),以後,多数例が報告されている.以下に抗T3,T4抗体の特徴,測定法および臨床像について述べる.
(30)抗インスリンレセプター抗体
著者: 荷見澄子
ページ範囲:P.251 - P.253
■検査意義と目的
一般にインスリン抵抗性は,肥満やインスリン非依存型糖尿病において認められる病態である.これらの場合と,非常に著明な高インスリン血症を示し,かつ耐糖能異常を伴うような症例に出会った場合に鑑別すべき疾患の1つとして,B型インスリン抵抗症があげられる.これは,1975年Flier1)によって報告された特異な糖尿病である.その特徴は,インスリン受容体自体に異常は認めないが,血中にインスリン受容体に対する自己抗体が存在することである.すなわち,インスリン受容体のインスリン結合部位がインスリン受容体自己抗体によって阻害され,インスリンがその生物活性を発揮できないために結果として著しいインスリン抵抗性を示す疾患である.この疾患の臨床的特徴は,特異的な皮膚症状acanthosis nigricansのほか,自己免疫疾患としての病像を備えたものである.
このB型インスリン抵抗症と鑑別すべき疾患としては,A型またはC型インスリン抵抗症,多彩な先天異常を伴うレプリコニズムやRabson-Mendenhall症候群,脂肪萎縮性糖尿病などがあげられる.これらとB型インスリン抵抗症の鑑別点として最も重要なポイントは,抗インスリン受容体抗体の存在の有無である.以下に,その測定法について簡単にまとめてみた.
(31)抗胃壁細胞抗体
著者: 米村雄士 , 河北誠
ページ範囲:P.253 - P.254
はじめに
抗胃壁細胞抗体(parietal cell antibody;PCA)は,1962年Irvineら1)により胃粘膜に対する自己抗体として悪性貧血患者血清中から発見された.胃壁細胞の原形質に対する自己抗体で,抗内因子抗体(intrinsicfactor antibody;IFA,次項参照)とともに悪性貧血患者血清中に高率に出現する.しかしPCAはIFAほど悪性貧血に特異的ではなく,悪性貧血以外にも甲状腺疾患,糖尿病,膠原病,胃炎,肝疾患,副腎不全などでも高頻度に出現する.このことからPCAの出現は,少なくともなんらかの胃粘膜病変を示唆するものとも考えられる.
(32)抗内因子抗体
著者: 増田哲哉 , 河北誠
ページ範囲:P.254 - P.256
はじめに
ビタミンB12(B12)欠乏によって発生する悪性貧血は,巨赤芽球性貧血のなかで最も代表的貧血である.萎縮性胃炎,胃粘膜萎縮を基本的病変とし,胃粘膜の壁細胞の減少により内因子(intrinsic factor;IF)分泌障害を起こし,その結果,回腸からのB12吸収障害を招き体内B12貯蔵が枯渇して発生する.
抗内因子抗体(intrinsic factor antibody;IFA)は内因子に対する抗体であり,Schwartz1)により1958年に報告され,その後これが自己抗体であることが明らかにされた,IFAは悪性貧血にほぼ特異的に認められる自己免疫現象とされるが,上述のように悪性貧血の胃粘膜が高度の萎縮性病変を示すことから,本抗体は萎縮性病変の過程で終末期に出現するものと考えられる.
(33)抗横紋筋抗体
著者: 太田光煕 , 太田潔江
ページ範囲:P.256 - P.259
はじめに
自己抗体としての抗筋抗体には,抗横紋筋(骨格筋)抗体,抗平滑筋抗体,抗心筋抗体があり,いずれの抗体も筋組織への反応性を有する.これらの自己抗体の診断学的,病因論的意義は未だ十分には明らかでないが,本抗体の検出は,疾患の診断やその病型の分類,治療,予後などを知るうえで有用な検査である.ここでは抗横紋筋抗体を中心に述べる.
(34)抗心筋抗体
著者: 松森昭 , 的場芳樹 , 河合忠一
ページ範囲:P.259 - P.260
はじめに
なんらかの心筋障害や免疫系の異常により,通常では循環血液と接することのない心筋構成成分が流血中に露出すると,その成分に対しての抗体,すなわち抗心筋抗体が産生される.本稿ではこの抗心筋抗体の測定方法,臨床的意義,最近のトピックス,抗ミオシン抗体を用いた心疾患のイメージングについて概説する.
(35)抗膵島細胞抗体
著者: 小林哲郎
ページ範囲:P.261 - P.265
はじめに
多くのI型糖尿病(インスリン依存型糖尿病,insulin-dependent diabetes mellitus;IDDM)は自己免疫的機序によりβ細胞が障害され発症することが明らかになっており,この際患者血中に検出される膵島細胞抗体(islet cell antibody;ICA)はβ細胞が破壊されている1つの指標として考えられている.また,I型かII型糖尿病(インスリン非依存型糖尿病;noninsulin-dependent diabetes mellitus;NIDDM)かの鑑別にも有用であることが明らかとなっている.本稿ではICAの測定法,臨床意義につき述べてみたい.
(36)抗精子抗体
著者: 神崎秀陽
ページ範囲:P.265 - P.267
はじめに
抗精子抗体の存在が生殖機能を障害する場合があることが知られている.精巣にはいわゆるblood-testisbarrier (血液―精巣関門)があるため,精子は自己の免疫細胞にさらされることなく発育・成熟してゆく.なんらかの原因でこの関門が破綻すると,精子抗原に対しての免疫応答が起こり,自己抗体としての抗精子抗体が誘導されると推測されている.他方,女性性管内での精子や精漿抗原によるisoirnmunizationが,女性側にこれらの抗原に対してのアロ抗体を誘導されることも明らかとなってきた.従来原因不明とされてきた不妊症のなかにこのような精子免疫に起因する症例があることが明らかとなり,それらは"免疫性不妊"として取り扱われている1).
3.自己免疫疾患と検査
1)慢性関節リウマチ
著者: 井上哲文
ページ範囲:P.268 - P.270
はじめに
リウマトイド因子は,慢性関節リウマチ(rheumatoid arthritis;RA)に比較的特異的な自己抗体であり,その診断に大きな手がかりを与えるが,大部分の臨床検査所見は単に慢性炎症を反映するものであり,あまり特徴的なものとは言い難い.しかし,炎症活動性の判定や,合併症の有無および薬物療法による副作用の有無を知るうえでは不可欠である.
本稿においては,本疾患の病態,臨床像,診断を概説するとともに,その診療における臨床検査の意義を述べる.
2)全身性エリテマトーデス
著者: 安倍達
ページ範囲:P.271 - P.274
■診断の基準
全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus;SLE)は全身性多臓器障害性炎症疾患である.患者血清中には多彩な自己抗体が出現し,なかんずく抗核抗体はSLEの血清学的特徴でもある.SLEの発症には遺伝的背景,環境の影響が深く関係している.
SLEでは臨床的には顔面の蝶型紅斑など本症に特徴的なものがあるが,そのような臨床所見は非常に少ない.そのことは検査成績でも同じことがいえる.したがって,SLEを診断するには臨床症状,検査成績を総合して行われるが,分類基準としては1982年改訂のアメリカリウマチ協会の基準が広く用いられている.その基準を表58に示した1).
3)強皮症
著者: 近藤啓文 , 穂坂茂
ページ範囲:P.274 - P.275
■強皮症とは
全身性強皮症は厚く硬い皮膚(皮膚硬化)と血管病変(Raynaud現象と小血管病変)を特徴的臨床所見とし,関節,内臓諸臓器を侵す原因不明の全身性結合組織疾患である.全身性硬化症(systemic sclerosis)あるいは進行性全身性硬化症(progressive systemic sclerosis;PSS)とも呼ばれる.
基本的病変は,①間質の線維化,②小血管病変,③実質細胞の萎縮,④単核球の浸潤から成り立っており,各臓器の病像はこれらが種々の程度に組み合わさって形成されている.
4)混合性結合組織病
著者: 隅谷護人
ページ範囲:P.276 - P.277
■疾患の概要
混合性結合組織病(mixed connective tissue disease;MCTD)は,1972年にSharpら1)によって提唱された疾患概念で,全身性エリテマトーデス(SLE),強皮症(PSS),多発性筋炎(PM)の症状を併せ持ち,同時に血清中の抗nRNP抗体が陽性を示す疾患である.患者の9割以上が女性で,30歳代の発症が多い.
特徴的な所見は,①Raynaud現象,手指・手背の腫脹(ソーセージ様と形容される),②抗nRNP抗体陽性で,そのほか,③SLE様所見として多発関節炎,紅斑,胸膜炎・心膜炎,白血球減少・血小板減少などが,強皮症様所見として手指硬化,肺線維症,食道の機能異常が,多発性筋炎様所見として筋炎の所見が見られる.MCTDの臨床所見の頻度を表62に示す.Sjögren症候群を合併することが多い.
5)結節性多発動脈炎とその他の血管炎
著者: 橋本博史
ページ範囲:P.278 - P.281
はじめに
血管炎をきたす疾患は数多くあげられ,これらを総括して血管炎症候群(vasculitis syndrome,Christian&Sergent,1976)の概念も提唱されている.その中心となる疾患は結節性多発動脈炎(polyarteritis nodosa;PAN)であるが,PANに近縁する独立した疾患,さらには他の疾患に血管炎を伴う病態も含まれる.ここでは,誌面の都合もあり,血管炎の分類,血管炎の発症機序,PANを中心とする主な血管炎症候群の疾患概念と診断に必要な検査所見について述べる.
6)Sjögren症候群
著者: 市川幸延
ページ範囲:P.281 - P.283
■概 念
Sjögren症候群(Sjögren's syndrome)は外分泌腺(主として涙腺と唾液腺)の単核球浸潤を伴う慢性炎症により,腺の破壊,分泌能低下をきたし,眼と口腔の乾燥症状を主徴とする疾患である.しかし,Sjögren症候群の患者には,乾燥症状のほかにも腺外症状や種々の自己抗体産生がしばしば認められる.さらに,本症には他の膠原病や自己免疫疾患を高率に合併することも特徴である.膠原病を合併しない症例(原発性Sjögren症候群)に対して,膠原病合併例を続発性Sjögren症候群と呼んでいる.本症の病因は不明であるが,前述の特徴から自己免疫疾患であろうと考えられている.
Sjögren症候群の90%以上は女性に発症し,乾燥症状が発現するのは40~50歳頃をピークとする.頻度は慢性関節リウマチよりやや少ない.
7)多発性筋炎/皮膚筋炎
著者: 秋月正史
ページ範囲:P.283 - P.285
はじめに
多発性筋炎(polymyositis;PM)は,横紋筋の炎症を基本病変とする原因不明の全身性炎症性疾患である.筋の炎症と変性,筋力低下,血清筋原性酵素増加および筋病変を示す組織学的および筋電図所見が特徴である.一方,皮膚筋炎(dermatomyositis:DM)は,筋炎に加えヘリオトロープ疹や関節伸側の紅斑など特有の皮膚病変を示す.両者の違いは皮膚症状の有無で,筋病変に差がなく,多発性筋炎/皮膚筋炎(PM/DM)として扱われる.
8)Behçet病
著者: 橋本喬史
ページ範囲:P.285 - P.287
■病態生理
1)病像
Behçet病は口腔粘膜のアフタ性潰瘍,外陰部潰瘍,皮膚症状(結節性紅斑,毛嚢炎様皮疹,皮下の血栓性静脈炎),および眼のぶどう膜炎を主な症状とし,ほかにも関節,血管系,中枢神経系,消化管,副睾丸,肺,腎臓などの病変による症状もみられる全身病であり,滲出傾向の強い炎症発作をくり返しつつ遷延性経過をとる.わが国では12,000~15,000人と世界で最も多い患者の存在が推定されていることに加えて,眼病変による失明率の高さや,中枢神経・血管・腸管の病変による死亡が少なからずみられることから,難病を代表する疾患として多大な社会的関心が寄せられてきた.
Behçet病の臨床病理学的特徴としては,好中球をはじめとする顆粒球と血小板の機能亢進があげられている1).好中球機能亢進については,遊走能,貧食能,活性酸素産生能,ライソゾーム酵素放出能,細胞障害性の亢進が知られており,病変部位に多数の好中球が浸潤し,活性酸素やライソゾーム酵素を大量に産生,放出することにより病変形成をもたらすと考えられている.Behçet病における好中球機能亢進の成因は長い間不明であったが,最近では単核球から放出されるサイトカインによることを示す研究報告があいついでなされ,遅延型アレルギーの関与が示唆されている2).
9)Goodpasture症候群
著者: 猪熊茂子
ページ範囲:P.288 - P.290
■原典と歴史
1919年,Ernest Goodpastureは,その前年米国におけるインフルエンザ流行時に死亡した患者の中に,肺出血と糸球体腎炎を起こした例のあることを報告した1).この症例は18歳の男性で,"typical attack ofinfluenza"の後に血痰,腎不全を生じて死亡した.頑固な咳と体重減少を生じ発症1か月で受診,胸痛,血痰,貧血,右下肺野の気管支肺炎像を認めた."肺炎"は左肺に及び,呼吸困難,多量の血痰,微量の尿アルブミンを呈し,3日後に死亡した.剖検肺は血液で充満し,腎には糸球体腎症がみられ,Bowman嚢にフィブリン析出,係蹄に細胞増殖を認め,尿細管の一部は赤血球で満たされていた.このほか脾には壊死巣がみられ,小腸壁にも出血があった.
1958年,StantonとTargeが同様の報告や自験例をまとめて「Goodpasture症候群」とした.
10)自己免疫性溶血性貧血
著者: 野村武夫
ページ範囲:P.290 - P.294
はじめに
溶血,つまり赤血球の血管内寿命が短縮したため生じた貧血を総称して溶血性貧血と呼ぶ.これには多数の疾患が含まれ,溶血が赤血球自身の欠陥に基づく内因性溶血性貧血と,環境異常のため赤血球が傷害されて発生する外因性溶血性貧血に大別される.自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia;AIHA)は後者に属する代表的疾患のひとつで,赤血球の崩壊に抗赤血球自己抗体が関与する.
わが国の調査では,AIHAの有病者数は340~1,200名(人口100万対有病率3.1~10.8),年間発症患者数は180~640名(人口100万対年間発症率1.6~5.8)と推測されている.かなり稀な疾患ということになるが,それでもわが国では内因性および外因性の諸病型のうち最も頻度が高く,溶血性貧血患者総数の約25%を占める1).
11)特発性血小板減少性紫斑病
著者: 高蓋寿朗 , 藤村欣吾 , 藏本淳
ページ範囲:P.295 - P.296
はじめに
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)は,現在では自己免疫疾患としてとらえられている.その病態は,血小板自己抗体がFab部分で自己抗原に結合し,これが網内系でマクロファージのFcレセプターを介して,貧食されて血小板減少が起こる.一方,一部のITP症例で免疫複合体の関与が示唆されている.これは,可溶性血小板抗原やウイルスなどの抗原と抗体が結合した免疫複合体が,血小板表面のFcレセプターに結合して血小板を破壊し,血小板減少を惹起するためと思われる.また,抗血小板抗体は巨核球にも結合し,血小板産生に影響を与えていると考えられている.
ITPは特徴的な検査所見に乏しく,診断は,除外診断が重要となる.表76に厚生省特定疾患特発性造血障害調査研究班による,ITPの診断基準(1990年改訂)と鑑別すべき疾患を示した.本稿では主として診断の進めかたについて臨床検査を中心に述べる.
12)橋本病
著者: 市川陽一 , 篠沢妙子 , 吉田正 , 有川一美 , 松下庸次
ページ範囲:P.297 - P.300
はじめに
橋本病は代表的な臓器特異性自己免疫疾患であり,血清中には種々の自己抗体が検出される.また,リンパ球機能の異常があり,遺伝的要因の関与を示すHLA抗原との相関が認められる.さらに,免疫異常に基づく甲状腺の破壊があり,甲状腺機能を示す諸機能の異常を伴うことはいうまでもない.
以下,橋本病に認められる検査異常と発症に関与する免疫能異常についてまとめてみたい.
13)Basedow病
著者: 紫芝良昌
ページ範囲:P.301 - P.304
はじめに
Basedow病(=Graves病,欧米ではこのほうがよく使われる)は,自己免疫疾患のうち臓器特異的自己免疫疾患と呼ばれるものの一つで,主として甲状腺,時には眼窩後組織(外眼筋を含む)や皮膚,皮下組織が自己免疫異常に巻き込まれ,その結果として甲状腺においては甲状腺の腫大と甲状腺機能亢進症,眼においては眼球突出症,皮膚では限局性粘液水腫という病変を起こしうる病態と定義することができる.これらの病変は詳細な臨床的観察によって把握することができるものであり,まず臨床所見として,理学的所見として把握することが必要なものである.そのうえで,検査を行って異常の存在を確認し診断していくわけであるが,検査は論理的に無駄のないように組み立てられなければならない.
14)糖尿病(自己免疫性)
著者: 滝俊哉 , 横野浩一 , 春日雅人
ページ範囲:P.304 - P.306
はじめに
I型糖尿病は遺伝的素因を背景とし,なんらかの環境因子が加わることにより膵β細胞を中心とした自己免疫異常が惹起され,その結果β細胞の選択的破壊を生じ,臨床的にはインスリン依存型糖尿病(insulindependent diabetes mellitus:IDDM)を呈する代謝疾患である.本稿では,I型糖尿病において認められる種々の免疫異常を,疾患の診断および発症予知という観点から概説したい.
15)インスリン自己免疫症候群
著者: 稙田太郎
ページ範囲:P.307 - P.310
はじめに
インスリン自己免疫症候群(insulin autoimmunesyndrome;IAS)は,平田ら(1970)によって最初に記載された疾患で,①自発性低血糖を主症状とし,②インスリン未使用であるにもかかわらず血中に大量のインスリン抗体が証明され,③低血糖頻発期の血清からは抗体と結合した大量のヒトインスリンを抽出できることなどをもって診断される.1990年2月までにわが国では148例の報告があり,国外の18例に比べると,本症候群はわが国で際立って多いことが注目される.
16)重症筋無力症
著者: 亀田典佳 , 塚越廣
ページ範囲:P.310 - P.313
はじめに
重症筋無力症(myasthenia gravis;MG)は筋の易疲労性を特徴とする疾患で,神経筋接合部における刺激伝達が障害されるために起こる.その機序は,神経筋接合部のシナプス後膜のアセチルコリンレセプター蛋白に対する自己免疫学的機序による.ここでは重症筋無力症の成立に関する基礎知識,ならびに診断に必要な検査とその進めかたについて,主に臨床的意義を中心に簡単に述べる.
17)多発性硬化症
著者: 荒賀茂 , 高橋和郎
ページ範囲:P.313 - P.315
はじめに
神経線維は軸索と髄鞘からなり,この髄鞘の破壊されることを脱髄(demyelination)と呼ぶ.脱髄性疾患はこの髄鞘が巣状に侵される疾患で,軸索や神経細胞は比較的保たれる.脱髄性疾患の代表は多発性硬化症(multiple sclerosis;MS)である.わが国での頻度は10万人に対して2~4人で,欧米に比べてその頻度は少ない.発症は20~40歳代に多いが,小児や高齢者での報告もある.多発性硬化症の病変は,中枢神経系のすべてに起こりうる.形成された脱髄巣は,時間の経過とともに修復され,また経過とともに再発する.したがって症状は多彩であり,寛解増悪をくり返す.
髄鞘の構成蛋白であるmyelin basic protein(MBP)を動物に感作することにより,脱髄モデル(experimental allergic encephalomyelitis;EAE)を作製することが可能となった,脱髄モデルでは,T細胞のうちヘルパーT細胞(CD4)がエフェクターであることが確認されている.
18)乾 癬
著者: 森田栄伸 , 山本昇壮
ページ範囲:P.315 - P.316
乾癬(psoriasis)は,中年以後に発症し慢性に経過する炎症性皮膚疾患である.境界明瞭な銀白色の鱗屑を伴う軽度隆起した局面としてみられ,全身どこにでも出現するが,肘,膝,殿部,腰部に好発する(図102).全身に広がり紅皮症になることもある.治療に比較的抵抗性であり,また,いったん治癒しても再発をくり返し,その経過は年余にわたるため患者に大きな心理的負担を与える.組織学的には,表皮の増殖・肥厚,角化異常,表皮および真皮内への炎症細胞浸潤,真皮乳頭の毛細血管の形態異常を特徴とする(図103).その病因は未だ明らかではないが,乾癬病変形成を説明するいくつかの生物学的あるいは生化学的異常が知られてきている.免疫・アレルギー機序の関与の程度は,さほど明らかではない.
19)天疱瘡・類天疱瘡
著者: 矢尾板英夫
ページ範囲:P.317 - P.319
天疱瘡
■概念
天疱瘡(pemphigus)とは,皮膚ないし可視粘膜に反復性,難治性,弛緩性水疱が多発する自己免疫性疾患である(図104).通常30~60歳代に好発し,病理組織学的には表皮細胞の棘融解(acantholysis)を特徴とする.免疫組織学的には患者皮膚表皮細胞間(原形質膜表面)に免疫グロブリン(特にIgG)の沈着を見,患者血清中には抗表皮細胞間抗体(天疱瘡抗体)を検出できる1).
20)自己免疫性肝炎
著者: 池田有成 , 光井洋 , 戸田剛太郎
ページ範囲:P.320 - P.322
はじめに
1956年,MackayらはSLE様症状を示し,LE細胞現象陽性の活動性慢性肝炎をルポイド肝炎と呼び,SLEでの肝病変(通常軽微である)とは区別した.その後,LE細胞現象は一過性に出現する症例もあることから,抗核抗体などの自己抗体の陽性に注目し,ルポイド肝炎を含めて自己免疫性肝炎とした.その肝障害の発症には自己免疫機序が関係していると考えられており,ステロイドが有効である.また,ウイルス性慢性肝炎とは異なり,インターフェロンは無効で,投与により悪化する可能性もあることから,本症を正しく診断することは重要である.最近では,抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎の存在やC型肝炎ウイルス(HCV)との関連が注目されている.また,syncytial giant-cellhepatitisとの鑑別も重要となってきている.
21)原発性胆汁性肝硬変
著者: 西岡幹夫
ページ範囲:P.323 - P.325
はじめに
原発性胆汁性肝硬変(PBC)は主として中等大の小葉内胆管の慢性炎症性疾患で,40~60代の女性に好発し,徐々に進行する予後の悪い疾患である.本疾患では各種自己抗体が陽性で,また,しばしば多彩な自己免疫性疾患を併発する1)など,自己免疫性疾患としての特徴をもっ.
最近の調査によれば,皮膚掻痒や黄疸など肝疾患を思わせるような自覚症状を持たないPBC,つまり無症候性PBC (a-PBC)が存在し,本症の発症頻度は症候性PBC (s-PBC)とほぼ同等,またはやや高い.PBCの臨床経過は個々の患者によって著しく異なり,さらに,一般的にPBCの予後は,従来考えられていたほど悪くない2,3).したがって,PBCの診断や治療に対する考え方も変わりつつあるのが現況といえよう.
IV.免疫組織学的検査法
1.蛍光抗体法・酵素抗体法
著者: 川井健司 , 長村義之
ページ範囲:P.328 - P.332
はじめに
細胞や組織内における抗原の局在を形態的に証明する方法として,免疫組織化学がある.免疫組織化学は,1940年代の後半にCoonsにより蛍光抗体法が発案されたのに始まり,1960年代にはNakaneらにより酵素抗体法が開発された.これらの方法は,いずれも抗原抗体反応という特異反応を基盤とし,抗原と結合した抗体の局在を蛍光の励起または酵素組織化学的に認識する方法である.本稿では,蛍光抗体法については簡単に原理について述べ,酵素抗体法の手技と基礎的な技術を中心に,本技法のノウハウの一端を述べてみたい1~9).
2.免疫電子顕微鏡法
著者: 堀貞明 , 長村義之
ページ範囲:P.333 - P.337
はじめに
免疫組織学的検索は,アレルギーや自己免疫疾患において,病態そのものを顕微鏡を通して診断者自身の眼で診断する手法のひとつとして重要である.光顕レベルの検索で十分な情報が得られるケースがほとんどであるが,糸球体腎炎でみられる免疫複合体の性状の検索など超微形態レベルでの検索も時として必要である.
本稿で述べる免疫電子顕微鏡法は,超微形態レベルにおける抗原物質の局在の証明法として有効な手段である.したがって,本特集のアレルギーや自己免疫疾患の診断のみに限らず,さまざまな疾患の超微形態的な診断(悪性リンパ腫細胞の表面マーカー,内分泌腫瘍の分泌ホルモン,ウイルス感染症のウイルスなど)に応用が可能である.
基本情報
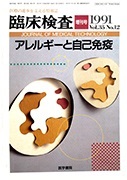
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
