染色体検査技術が進んで,染色体異常に基づく種々の病気(症候群)が確立されてくる一方で,遺伝子解析技術の最近の進歩は目覚ましく,最近次々に遺伝病(特に単一遺伝子によるもの)の病因が遺伝子レベルで,塩基の置換,欠失,挿入などにより生ずることが明らかにされてきた.成人病といわれる病気(糖尿病,高脂血症,痴呆など)ですら,その一部のものは単一遺伝子病であることが知られるようになった(インスリンレセプター異常による糖尿病,家族性高コレステロール血症による心筋梗塞,アルツハイマー病など).これまで謎とされていた発癌機構も,遺伝子(癌遺伝子,癌抑制遺伝子)との関連においてかなり明らかにされてきたことも驚きである.
重要なことは,遺伝子解析技術がきわめて速い速度で進歩していることであって,現在各国で始まったヒト染色体を構成する全塩基配列を決めようというヒトゲノムプロジェクト,さらには遺伝病を遺伝子を修正して治そうという遺伝子治療,それに伴う倫理的問題も早急な対応を迫られるまでになってきた.また妊娠早期に,胎児が重症遺伝病に罹患する異常遺伝子を持っているか否かを決める出生前診断が可能な病気も増えつつあり,遺伝カウンセリングの役割と責任もたいせつになってきた.
雑誌目次
臨床検査36巻11号
1992年10月発行
雑誌目次
特集 遺伝と臨床検査
序文
遺伝と臨床検査
著者: 三輪史朗
ページ範囲:P.5 - P.6
I 総論
1.ヒト遺伝子・染色体の構造
著者: 香川靖雄
ページ範囲:P.8 - P.18
●はじめに
本稿ではこの増刊号を読むのに必要な基本的事項を説明する.
臨床検査に必要なヒトの遺伝子は細菌の遺伝子に比べて巨大なだけでなく,染色体と呼ばれる構造の中に配列されて,核の中に納められている.ミトコンドリアには例外的に,核外の遺伝子が存在している.ヒトの遺伝子の詳細がわかり,多くの遺伝疾患の原因となる変異の部位が知られたのは最近5年のことである1~3).
2.遺伝病診断の進めかた
著者: 三輪史朗
ページ範囲:P.19 - P.25
●患者のみかた
先天代謝異常症に代表される種々の機能異常による疾患と,染色体異常症や奇形症候群など形態異常(奇形)を主とする疾患の2群に大別される.丹念な診察,詳細な病歴を調べ,遺伝性疾患が強く疑われる場合には,正確な家系図を作ることがたいせつである.家系図の書きかたに特定な取り決めはないが,図1,2に示す記号を用いるのが一般なので習慣づけておくよう心がけてほしい.
先天代謝異常症では,症状発現がいつだったかに注意する.同一酵素異常疾患でも家系によって発病年齢や症状の軽重に差異があり,乳児型,成人型などがあるためである.主に遺伝子の変異の違いによる.しかし環境条件の差で発病時期が違ってくることもある.一般的には先天代謝異常の診断は特定の酵素の活性測定や中間代謝産物測定によってなされるので,診察だけで病名の診断ができるといった特有の症状を呈しない疾患は少なからずある.
3.メンデルの法則と遺伝形式
著者: 梶井正 , 岸文雄
ページ範囲:P.26 - P.31
●メンデル遺伝(Mendelian inheri-tance)
高校で生物の授業を受けた人ならば,メンデル(Mendel)がモラビアの修道院の庭にエンドウマメを植えて交配実験をし,①優劣の法則,②分離の法則,③独立の法則を見いだしたことを知っているはずである.①は現代の用語を用いれば,一対の遺伝子座にある一対の対立遺伝子の片方が他方に対して優性に発現し,劣性の形質は現れないことを意味する.②は雑種第一代(F1)を自家受粉させて雑種第二代(F2)を作ると,F1では優性形質に隠されていた劣性形質が分離して3:1の比率で現れることをいう.これは理論的には重要だが,ヒトでは自家受粉しないから,そのままでは適用できない.
③は各形質が独立して遺伝することを示すもので,現在の連鎖(linkage)と逆の概念である.メンデルはエンドウマメの7種の形質を観察に用いたが,独立の法則を導くために用いたのは,そのうち3種である.この3種のうち,2種は1番染色体にあることが後に判明したが,その位置が遠いために両者の間に交叉を生じ,あたかも独立して遺伝しているかのような結果を来したものである.メンデルが連鎖をどの程度意識していたかは,今日では知るよしもない.メンデルが論文を書いた1865年当時は染色体の概念はなかったし,遺伝子が染色体に一定の順序で並んでいることも知られていなかった.メンデルは遺伝子をエレメントと呼び,一対のエレメントのうち片方が子供に伝えられるという概念を持っていたにすぎない.あるいは,実験を繰り返して,自分の仮説に適合する実験だけを書き残したのかもしれない。
II DNA診断 1.DNA診断のための基本的操作
1) DNAの抽出法
著者: 塚田敏彦 , 中山年正
ページ範囲:P.34 - P.38
●はじめに
DNAの抽出精製については,ゲノムDNAやベクターとして用いられるプラスミドやファージDNAなどの調製について,種々基礎および遺伝子工学実験書などに多くの方法が報告されている1,2).しかし,臨床検査の現場でのDNA診断のスクリーニング検査を目的としたDNAの抽出精製の報告は少ない3).
本稿では,臨床検査で最も用いられているゲノムDNAの材料として主に末梢血の有核細胞からの高分子DNAの分離精製法4),および現在広く使用されているPCR (polymerase chain reaction)法で用いる微量で簡易・迅速な末梢血の精製法について5),われわれの検査室で用いている方法について紹介する.さらに,これからDNA診断のスクリーニング検査に用いられると思われる蛋白変性剤にグアニジンチオシアン酸塩を用い,劇物のフェノールを使用しない安全で迅速な分離精製キット6)についての使用経験やDNA自動抽出装置7)についても簡単に記述したい.
2) RNAの抽出法
著者: 牧野鈴子
ページ範囲:P.39 - P.42
●RNAを抽出するときの注意
まず,RNAを扱う際に注意をする点について述べたいと思う.
RNAはDNAよりも分解されやすい物質である.RNAの分解は溶液をアルカリ性にした場合,またはリボヌクレアーゼ(RNAを分解する酵素)が混入した場合などに起こる.リボヌクレアーゼは細胞の中に存在するだけでなく,汗,唾液中にも分泌されるので作業中はゴム手袋を着用するとよい.また,手術材料や生体組織の場合には手術中や切除後放置している間にリボヌクレアーゼが働いて,RNAを分解してしまうことがある.切除後すぐにRNAの抽出作業ができないときには,試料をフリーズクランプなどを用いてすばやく凍結し,-70℃で保存すると,より良質のRNAを得ることができる.凍結するまでに時間がかかる場合は,試料を氷冷しておくとよい.
3)サザンブロッティング法
著者: 和田知益 , 大谷英樹
ページ範囲:P.43 - P.46
●はじめに
近年,遺伝子工学の技術的発展は目覚ましく,これら技術の導入によって多くの疾患の遺伝子の異常が解明され,現実に疾患の遺伝子レベルの解析が可能となりつつある.遺伝子の異常を解析する最も一般的で基本的な操作法が,ここで取り上げるサザンブロッティング法(Southern blotting;以下サザン法と略)である.サザン法は1975年にE.M.Southern1)により考案されたDNA解析法で,考案者の名前からサザン法と命名されている.当初はクローン化されたDNAの制限酵素地図の作成に用いられたが,改良が加えられ真核細胞のゲノムの解析に応用されるようになっている.
サザン法のあらましを図1に示した.DNA試料を制限酵素で処理し,制限酵素で切断されたDNA断片をアガロースゲル電気泳動によって大きさごとに分画する.分画されたDNA断片をゲルからフィルター上に写し取り,レプリカを作る.この写し取る操作は,ブロッティングあるいはトランスファーと呼ばれる.目的とする遺伝子を検出するための標識されたプローブを加えると,フィルター上でプローブと相補的な塩基配列を持つDNA断片とハイブリッドが形成される(ハイプリダイゼーション).標識されたプローブとハイブリッドを形成したDNA断片はオートラジオグラフィーにより検出される.
4)ノーザンブロッティング法
著者: 寺井格 , 小林邦彦
ページ範囲:P.47 - P.52
●はじめに
1975年,Southern EMが,制限酵素で切断しアガロースゲル電気泳動で分画したDNA断片を,直接ニトロセルロースフィルターに移す方法を開発した.このSouthern法は遺伝子解析手段として極めて有用であることから,その後広く用いられるようになった.1977年Starkらは,アガロースゲル電気泳動で分画したRNAをフィルターに移す方法を開発した.この方法はDNAに対する"Southern"法と対比させて"Northern"法と呼ばれている.
5)ウエスタンブロッティング法
著者: 三間孝 , 織田島弘子
ページ範囲:P.53 - P.57
●はじめに
従来の生命科学の研究法は発現している蛋白を確認し,mRNAを同定後,遺伝子構造を決定する手順でなされてきた.しかし特定の細胞機能を規定している微量蛋白を確定することは困難であった.癌遺伝子発見の実験で示されたように,細胞工学および遺伝子工学の進歩は最初に遺伝子を確認し,次いでmRNAおよび蛋白を同定する従来の手法と逆の検索方法を可能にした.
一方,蛋白検索法の進歩はH.Towbinら1)が開発したウエスタン(Western)法により微量検出を容易にし,ウエスタンブロットされた微量蛋白でアミノ酸配列が決定できるようになった.さらにアミノ酸配列から,オリゴヌクレオチドの合成,合成オリゴヌクレオチドを用いた蛋白特異的mRNAの抽出,cDNAの合成,mRNAおよび遺伝子構造の解析へと分析を進展させることが可能になった.このような生命科学研究法における蛋白の検索は遺伝子の最終情報の分析であり,遺伝子解析の出発点であるとも言える.
6) PCR法
著者: 竹脇俊一 , 永井良三
ページ範囲:P.58 - P.62
●はじめに
PCRはpolymerase chain reactionの略で,DNAの既知領域を数時間のうちに数十万倍に増幅する方法である.その反応は,二本鎖DNAの一本鎖への分離,合成プライマーの一本鎖へのアニーリング,DNAポリメラーゼによるプライマーの伸張反応,の3つの過程から成り,このサイクルを繰り返すことによりDNAを増幅する.DNAポリメラーゼは一本鎖DNAを鋳型にしてそれと相補的なDNAを合成し,二本鎖とする反応を触媒する.反応の開始にはDNAと相補的に結合するプライマーが必要で,プライマーの結合後,5'から3'の方向にDNA鎖を合成していく.DNAは通常二本鎖で存在するので,目的の領域を挟む二種類のプライマーを加えてやれば,その領域は2倍になり,それを繰り返すことにより指数関数的にDNAが増幅される(図1).したがって,既知領域の塩基配列を含むゲノムが1分子でもあれば,その領域のDNA断片が大量に得られることになる.
この方法が遺伝子研究やDNA診断に与えたインパクトは大きく,その方法論を大きく変えた.従来の分析技術は検出シグナルの増幅に焦点が置かれていたが,PCRは検出対象のDNAそのものを増幅するというまったく新しい発想に基づいている.そのため検出が,簡便な電気泳動などで十分となり,複雑な分析過程を大幅に簡略化した.
7) PCR-SSCP法
著者: 林健志
ページ範囲:P.63 - P.66
●はじめに
今日,DNA診断は臨床検査の場で,急速にその重要性を増しつつある.遺伝病診断における要因遺伝子中の突然変異の検出,癌における癌遺伝子や癌抑制遺伝子の突然変異を含む構造変化の検出,感染性疾患における病原生物の同定などである.DNA診断の有用性は従来から明白なことであったが,これには,組換えDNA技術を含むかなり高度な生物学的実験技術が必要であり,例えば臨床検査の場でこれを行うのは事実上不可能であった.1980年後半に出現したPCRは,この状況を一変させた.通常の生化学的試薬のほかに,プライマーとして使うオリゴヌクレオチドと,耐熱菌由来DNAポリメラーゼ,それに比較的簡単な装置があれば,きわめて簡単に,ごく微量のゲノムDNAから特定領域の配列を選択的に増幅し,取り出すことが可能となった.さらに,ポリアクリルアミドゲル電気泳動法を利用して,PCR産物中の突然変異の有無を,きわめて簡単に検出する実験法がPCR-SSCP(singlestand conformation polymorphism)法である.
8) DNAシークエンス法
著者: 巽圭太 , 宮井潔
ページ範囲:P.67 - P.70
●はじめに
DNAの塩基配列を決定することは,生物の設計図とも言うべきDNAの基本構造を知ることである.各種の遺伝病は,染色体異常,あるいは,塩基配列異常(置換,欠失,挿入)が病因であり,DNAシークエンス法はこのうちの塩基配列異常を明らかにする方法である.
さて,DNAシークエンス法は数年前までは,ゲノムDNAの抽出後,大腸菌を用いた組換えDNA実験法によりDNAクローニング法をしないと行えなかったこと,さらに,その後の塩基配列の決定の段階で,32Pや35Sのラジオアイソトープ(RI)を使わざるをえなかったことの2点のため,施設面ならびに煩雑さの点で,一般検査室で施行するのは非常に困難であった.しかし,最近の技術の急速な進歩により,PCR法や自動DNAシークエンサーなどが実用化されてきたことで,今や1人で10以上の検体を1日で決定することが可能となり,検査室レベルでの実用化も間近いと思われる.
9)多型性DNAマーカーと連鎖分析
著者: 三木哲郎 , 荻原俊男
ページ範囲:P.71 - P.74
●多型性DNAマーカー(polymorphic DNA marker)
集団の中で1%以上の頻度で多型が存在する遺伝子の座位は,多型性部位(polymorphic site)と定義されている.血液型のABO型,Rh型などの多型性遺伝子マーカーの遺伝子は,それぞれ9q34.1-q34.2,1p36.2-p34に座位し,個体識別や遺伝子地図作成時にその多型性が利用されている.これらの血液型などの多型は,蛋白質のアミノ酸変異による遺伝子マーカーであり,約30種にすぎなかった.このアミノ酸の変異は,遺伝子の変異に由来するものであるが,ハプロイドあたり約30億塩基対(bp)であるヒトのゲノムの塩基配列には,アミノ酸に翻訳される部分を含めて,平均数100bpに1個の多型性部位がある.したがって,多型性DNAマーカーは無数に存在することになる1).分子遺伝学の手法を用いて開発された多型性DNAマーカーは単離され続けており,医学・生物学の分野に大きな影響を与えている.
多型性DNAマーカーは,大きく分類すると図1に示すように,第一世代としてRFLP,第二世代としてVNTR,第三世代としてマイクロサテライト遺伝子に分類される.ここでは,それぞれの多型性DNAマーカーの下に示したような家系で,父親と長女が常染色体性優性の遺伝病の患者で,遺伝子マーカーは原因遺伝子座位と組換えがなく,II-3の胎児の遺伝子診断を行うと仮定して説明する.
10)遺伝子点変異のさまざまな検出法
著者: 松原洋一
ページ範囲:P.75 - P.78
●はじめに
現在,さまざまな遺伝病において,遺伝子の挿入,欠失,再構成,点変異などがその原因として報告されている.これらの変異のうち,挿入,欠失はサザン法やPCR法によって比較的容易に検出することができる.例えば,Duchenne型筋ジストロフィー(DNA診断の項参照)では,ジストロフィン遺伝子における欠失や重複が病因となっていることが多く,したがって遺伝子断片の有無を調べたり,また,その大きさを比較したりすることによって診断が可能である.しかしながら,多くの遺伝子病における変異は点変異がその大半を占めている.点変異の場合,1つの塩基が他の塩基に置換しているだけで,ごく一部の例外を除いて,通常のサザン法やPCR法を行っただけでは正常遺伝子と変異遺伝子を区別することができない.
これまでに,この1塩基のみの変化を検出するためにいくつかの方法が編み出されている.これらの方法は大きく分けて2種類に分けられる.すなわち,すでに病因であることが明らかにされている既知の点変異を検出する方法と,それに対して未知の点変異を幅広くスクリーニングする方法とである.本稿では誌面の都合で,前者の中で主なものを紹介し,筆者らの研究室における,それぞれの実際例を述べる.後者については,その代表的なものにSSCP法が挙げられるのでそちらを参照されたい.
11) DNAプローブの作製方法
著者: 江崎孝行
ページ範囲:P.79 - P.81
特定の病原体や遺伝子を検出,あるいは同定するためのDNAプローブはその長さから数千塩基の長い断片から成るものから人工的に合成した短い断片(20-40塩基)に至るまでさまざまである.実験の目的によってDNAプローブの長さは使い分けられる.また,プローブの塩基配列や標識方法も目的により選択基準が異なり,適切な使い分けが必要になる.
2.DNA診断の応用
1) Duchenne型筋ジストロフィー
著者: 有川恵理 , 荒畑喜一 , 杉田秀夫
ページ範囲:P.82 - P.87
●はじめに
従来,疾患の遺伝子解析は蛋白質レベルの異常を基に,その原因遺伝子を調べるという方法がとられていた.しかし,Duchenne型筋ジストロフィー(DMD)については最初に疾患の原因遺伝子がクローニングされ,次いで,その遺伝子産物であるジストロフィンという蛋白質が発見された.このようなアプローチの方法は"逆遺伝学"と呼ばれる.このジストロフィンの発見は,近年の遺伝子工学技術の進歩がもたらした最も輝かしい成果の1つであろう.ここではこれによって進歩した筋ジストロフィー診断技術の進歩に関してDNA診断を中心に述べる.
2)家族性高コレステロール血症
著者: 三宅康子 , 山本章
ページ範囲:P.88 - P.93
●はじめに
LDL(low density lipoprotein;低比重リポ蛋白)レセプターは,細胞表面膜上に存在しており,血中のLDLを末梢細胞に取り込ませる役割を果たしている.LDLレセプターに遺伝的変異の起きた疾患が家族性高コレステロール血症(familial hypercholesterolemia;FH)であり,LDLレセプターの対立遺伝子のうち一方が異常なヘテロ接合体の出現頻度は500人に1人という高率である.ヘテロ接合体では細胞表面上で正常に機能できるレセプター数が正常人の半数であり,血清コレステロール値は260~500mg/dlに上昇しており,30歳台から高率に虚血性心疾患を発症する.対立遺伝子の双方が異常なFHホモ接合体は100万人に1人の割合で出現し,患者では血清コレステロール値が500~1,000mg/dlとなり幼児期から冠動脈硬化が進展する.
3)フェニルケトン尿症
著者: 岡野善行
ページ範囲:P.94 - P.97
●はじめに
フェニルケトン尿症(phenylketonuria;PKU)は肝臓のフェニルアラニン水酸化酵素(phenylalaninehydroxylase;PAH)の先天的欠損によって起こるアミノ酸代謝異常症の1つで,結果として体内にフェニルアラニン(phenylalanine;Phe)が蓄積され,知能障害などの中枢神経障害,赤毛,色白などのメラニン色素欠乏を引き起こす1).常染色体劣性遺伝形式で発現し,両親は通常ヘテロ接合体である.発生頻度は,欧米で1/10,000人,中国で1/16,000人,日本で1/110,000人と地域により大きな差があるが,先天性代謝異常症の中では比較的頻度の高い疾患である.治療と診断は現在,ガスリー法での新生児マススクリーニングによる早期発見と低フェニルアラニン食による早期治療で中枢神経障害などの予防に効果を上げている.
一方,組換えDNA技術の進歩とその応用は細胞が持つ遺伝情報を直接解析することを可能とし,先天性代謝異常症の診断と治療に大きな影響を与えている.PKUの欠損酵素であるPAHは肝臓にのみ局在するため,白血球,羊水細胞,絨毛細胞などで解析される保因者診断や出生前診断は不可能と考えられていた.1983年,Wooら2)によって初めてラットPAHcDNAを利用したrestriction fragment Iength polymor-phism(RFLP)の解析によるPKUの出生前診断が報告され,以後種々の遺伝子レベルでの解析が進められている.
4)非ケトーシス型高グリシン血症
著者: 呉繁夫
ページ範囲:P.98 - P.102
●はじめに
非ケトーシス型高グリシン血症(nonketotic hyperglycinemia;以下本症)は常染色体劣性遺伝形式をとる先天代謝異常症の1つで,体液中に大量のグリシンが蓄積するのを特徴とする1,2).本症では意識障害,痙攣,呼吸障害などの重篤な中枢神経障害が生直後から急速に進行し生命予後が極めて悪い.本症のもう1つの特徴に多発地域の存在を挙げることができる.本症は比較的まれな先天代謝病の1つで,その頻度は欧米で約25万人に1人と推定されている2).ところが,フィンランド北部では約1万人の出生に1人とその発生頻度が際だって高い3).同地域において本症の出生前診断の要請は以前より強く,そのための確実で簡便な診断法の確立は臨床遺伝学上重要であった.
本稿ではまず本症の生化学的な検査法に触れた後,本症の遺伝子変異検索の実際を示す.次に,その臨床応用として本症の出生前DNA診断について述べてみたい.
5)乳酸脱水素酵素Mサブユニット欠損症
著者: 前川真人 , 菅野剛史
ページ範囲:P.103 - P.109
●はじめに
乳酸脱水素酵索(LDH)は,H (B)とM (A)の2種のサブユニットから成る4量体であり,5種類のアイソザイムを形成する.これらのサブユニットの欠損症がHは北村らにより,Mは菅野ら1)により報告された.LDHアイソザイムパターンは図1に示したごとく,非常に特徴的である.Mサブユニット欠損症発見の発端は激しい運動後のミオグロビン尿症であった.その後,4家系が本邦においてのみ報告されている.第2家系は頻度推定のマススクリーニング2),第3家系は腎障害患者3),第4家系は全身倦怠感の患者4),第5家系は皮膚の発疹の患者5)であった.日常は皮疹がある場合以外は特に症状はなく,潜在性症候性と言える.血清LDH活性も通常は正常域であることに注意したい.
6)インスリンレセプター異常
著者: 森保道 , 鏑木康志 , 門脇孝
ページ範囲:P.110 - P.113
●はじめに
インスリンはペプチドホルモンであり,その受容体であるインスリンレセプター(以下IRと略記)は細胞膜上に存在する.インスリンがIRに結合した後,受容体のチロシンキナーゼ活性が活性化され,さまざまなインスリン作用が発現されることになる.
糖尿病の大部分を占めるNIDDM (非インスリン依存型糖尿病)を含む表1に示した疾患においては,インスリン作用の発現が障害されるという,いわゆるインスリン抵抗性が認められ,従来からIRの先天的・後天的異常が示唆されてきた.
7)サラセミア
著者: 服部幸夫 , 大庭雄三
ページ範囲:P.114 - P.118
ヒトの血色素(Hb)の95%以上を占めるHbAは2分子ずつのα,βグロビン鎖から成る四量体である.α,βグロビンは赤芽球や網球でバランスよく産生されているが,サラセミアと呼ばれる病態では,その一方だけの産生障害があり,その結果,血球内のHb含量が低下し,低色素赤血球となったり,また,正常に産生された側のグロビンが相対的に余剰となり,それが赤血球膜に障害を与えて溶血性貧血を起こしたりする.βグロビンの産生低下をβサラセミア,αグロビンの産生低下をαサラセミアと称す.
III 染色体異常の診断
4.染色体分析とその実例6件―イソ21qダウン症脆弱X症候群 Miller Dieker(17p-)標準型ダウン症同胞 モザイクXO/XYFanconi貧血
著者: 中井博史
ページ範囲:P.188 - P.195
●はじめに
染色体分析にはいくつもの種類があり,目的に応じた検査を選択することが大切である.また核型写真から「こう判断する.」「こう考えていくほうが良いのでは,」という洞察を検証していく作業も必要となる.
そこで今回,染色体分析を6件の実例に基づいて解説したい.
5.白血病診断への応用
著者: 北村聖
ページ範囲:P.196 - P.200
●はじめに
特定の染色体異常が特定の腫瘍に高頻度に認められる場合には,その染色体異常によって引き起こされる遺伝子の変化が,細胞の腫瘍化の本質に深く関連する要因であると考えられる.白血病などの造血器腫瘍を中心に数多くの染色体異常が知られており,一般にこれらは複雑で疾患と染色体異常に対応を見いだすことは困難である.しかし,これらのうちの一部は染色体異常によって生じる遺伝子変化の詳細が明らかにされ,疾患との対応も明らかにされてきている.白血病の診断は当然末梢血や,骨髄血の形態的観察で可能な場合が大多数である.しかし,その病型診断,あるいは治療後の残存腫瘍細胞の検出などにおいては,いまだ少ない病型ではあるが,これらの染色体変化や遺伝子変化を捉えることで非常に鋭敏かつ正確な診断をすることができるようになってきた.本稿では白血病・悪性リンパ腫にみられる染色体異常と,それに関与していることが明かな癌遺伝子について概説し,それによる白血病の診断について述べる.
2.末梢血の各種染色体分染法
1) G分染法
著者: 家島厚
ページ範囲:P.127 - P.130
●はじめに
染色体検査法の進歩により,原因不明の奇形症候群や精神遅滞の原因解明がなされてきた.ギムザ染色のみで検査がなされた1960年代にはDown症候群や18トリソミーなど数の異常が次々と発見されたが,染色体分染法が開発された1970年代には,新しい部分トリソミー,部分モノソミーなど構造異常がだいたい出揃った.すでに1番から22番までのすべての染色体異常が報告され,原因不明の精神遅滞をみたら,染色体異常を疑う必要があるくらい染色体検査は一般化している.
染色体分染法の意義は,個々の染色体が正確に同定され,主要なバンドパターンを確認できることである.1971年パリ会議で,Qバンド,Gバンド,Rバンド,Cバンドなどの命名法が決定された.染色体分染法として,Qバンド法1)が初めて報告されたが,蛍光顕微鏡を必要とすること,Gバンドで永久標本が得られることより,本邦ではGバンド法が最も普及している.現在では,日本中のどこからでも依頼できる検査として,染色体分染法は,臨床医学の中で定着している.G分染法については,現在までに数多くの方法が報告され,各施設での変法まで入れると数え切れないほどの方法がある.染色体標本の作製法や保存方法,保存期間などにより条件が変化するため,生化学検査のように条件が一定しない.本稿では,おおまかな歴史に触れ,われわれの行っている方法を紹介したい.
2)ギムザ染色によるR分染
著者: 家島厚 , 頼田多恵子
ページ範囲:P.131 - P.136
染色体検査は臨床医学の中でルーチン検査として定着し,外注検査として日本中どこの病院からでも検査可能となった.医学教育や卒後教育の中で,臨床遺伝学の教育が必ずしも十分でないところで,染色体検査だけが,一般に普及し,結果の説明,染色体異常児のフォローが不十分のままで終わっている例が残念ながら多いようである.
本邦では,G分染法が最も普及し,R分染法は一般にはなじみがない.R分染法は,G分染法の染色と白黒逆の染色となることから命名された分染法であり,reverse bandに由来している.1971年Dutrillauxら1)の報告に始まり,現在でもフランスを中心に行われているが,本邦では一般に行われていない.Gバンドでは蛍光顕微鏡を必要とせず,鮮明なバンドが得られるのに対し,Rバンドでは,一般に蛍光顕徴鏡を必要とし,Gバンドよりバンドが不鮮明であることがこの理由と考えられる.しかし,ギムザR分染法では蛍光顕微鏡を必要とせず,Gバンド同様の鮮明な永久標本が得られる.Rバンドは単純なGバンドの裏返しではなく,Gバンドで弱点となるGバンドのwhite bandに濃淡を持ったバンドが得られ,Gバンドと相補的な関係にある.染色体異常の切断点決定などバンドの微妙な部分を決定する場合に,高精度分染法でより細かく観察することも大切であるが,Gバンドと併用してRバンドを検討することも大切である.
3)Q分染法
著者: 田沢正 , 五十嵐寛 , 岩井聡 , 丸山昭治
ページ範囲:P.137 - P.142
●はじめに
Q分染法は,Casperssonら1)により各種分染法の中で最初に発見された染色法である.蛍光色素キナクリンマスタード(QM)で処理することにより染色体を横縞の縞模様に染め出して蛍光顕微鏡で観察するもので,Q分染法2~5)(色素の頭文字の略)と呼ばれる.明るい蛍光を発しているバンドは,染色体DNAのATrich部位で,暗いバンドは逆にGC rich部位である.Q分染法は熱や薬剤処理などの前処理を必要としないので,染色体の形態が比較的よく保持され,簡便で最も安定した方法である.図1にQM染色法による分染像を示す.
近年,上記分染法のみならず2種以上の色素で染色することでよりコントラストの高い鮮明な分染像が得られる二重染色法2,6~8,11)(counter staining technique)も実用化されている.
4)C分染法
著者: 中川原寛一 , 森光子 , 皆川淳子 , 酒井京子
ページ範囲:P.143 - P.149
●はじめに
Cバンド染色部位は構成性のヘテロクロマチンであり,サテライトDNAなどの高度反復配列DNAが分布している.反復配列DNAは,数bpから数百bpのさまざまな長さのDNAがそのまま何回も繰り返したもので,真核生物特有の分画である.この高度反復配列DNA分画の中にサテライトDNAが含まれている1~3).
C分染法は,動原体の位置や逆位を確かめるのに必要な分染法である.また,特に1・9・16番染色体,Y染色体のCバンドは顕著であり,かつ異形性を示すのでマーカーとしても有用である.ここでは,熱処理した後ギムザ染色するC分染の代表的なBSG(Bariumhydroxide/Saline/Giemsa)法,蛍光色素で染色する蛍光法,およびDNAプローブを用いたin situハイブリダイゼーション法によるC分染法の技術を中心に解説する.
5)NOR染色法
著者: 大橋龍美
ページ範囲:P.150 - P.153
●はじめに
動物の細胞には核小体(仁)が存在し,rRNAの合成に関与している.これらの形成には特定の染色体の二次狭窄がかかわっており,NOR染色法あるいはN-バンド法と称される染色法で,染め出すことができる(以下N-バンド法で一括する).
N-バンド法を使うことにより,NORsがかかわる染色体の異常をより詳細に分析することができるばかりでなく,癌の診断・予後推測利用への試みもなされている.
6)SCE
著者: 中川原寛一 , 伊藤正行 , 酒井京子
ページ範囲:P.154 - P.159
●はじめに
M期における1個の染色体は,それぞれ相同な染色分体(chromatid)から成り,動原体で結合している.染色分体は1個の染色体が縦列したもので,姉妹の関係にあることから姉妹染色分体と呼ばれている.この姉妹染色分体には,DNA複製期に部分的にある位置で切断し,その部分と相応する分体が互いに入れ換わって部分的な交換を生じる現象がある.これが姉妹染色分体交換(sister chromatid exchange;SCE)である.
この稿では,自然に発生するSCE(自然SCE)に及ぼす諸因子と染色法について,筆者らの知見を交えて解説する.
7)脆弱X染色体の検出
著者: 笠井良造 , 楢原幸二
ページ範囲:P.160 - P.164
●はじめに
染色体脆弱部位(chromosomal fragile site)とは,特定の条件下で染色体を培養したときに,染色体上に認められる切断(break)あるいはギャップ(gap)を言う.脆弱部位には,共優性メンデル遺伝様式をとる遺伝性脆弱部位(heritable or rare fragile site)と,共通脆弱部位(common fragile site)とがあり,Human GeneMapping 101)ではそれぞれ26および87の脆弱部位が記載されている.X染色体上にはXp 22.31,Xq22.1,Xq 27.2の3つの共通脆弱部位と1つの遺伝性脆弱部位[fra(X)(q 27.3)]が報告されているが,fra(X)(q27.3)のみが疾患と密接に関係している.
1970年代後半にfra(X)(q 27.3)がX連鎖性家族性精神遅滞に認められることが発見されてから2,3),本疾患は脆弱X[fra(X)]症候群と呼ばれている.一般集団における本疾患の罹患率は,男性1/1,250,女性1/2,000と言われており,Down症候群に次いで精神遅滞の重要な原因である.fra(X)症候群の成人男性例では,精神遅滞,特徴的顔貌(長い顔,聳立した耳介,下顎の突出)および巨大睾丸を三大主要症状とするが,その他結合組織の異常(関節の過伸展,僧帽弁逸脱など)が高頻度に認められる.
8)DNA複製パターン
著者: 成富研二
ページ範囲:P.165 - P.168
細胞周期のS期(DNA合成期)の中~後期に相当する時期にプロモデオキシウリジン(bromodeoxyuridine;BrdU)を培養液に添加すると,S期の前半に複製した部分はRバンドとして,後半に複製した部分はR陰性バンドとして染め分けられる.X染色体のDNA複製に限って言えば,活性を持つ早期複製X染色体はX染色体全体にわたってRバンドを示すのに対し,不活性化された後期複製X染色体は,ごく一部にRバンドを示すか,あるいはまったく示さない.すなわち,X染色体の活性化状態を知ることが可能である.また,この方法で,熱処理によるR分染法(RHG法)よりはるかに解像度のよいRバンドが得られるため,常染色体のR分染法にも応用できる(RBG法,RBA法).さらに,BrdUとエチジウムブロマイド(ethidium bromide)を組み合わせることにより,同調培養をしなくても高精度R分染像を得ることができる.
9)高精度分染法
著者: 涌井敬子 , 西田俊朗 , 伊藤武 , 福嶋義光
ページ範囲:P.169 - P.174
●はじめに
高精度分染法は細胞分裂前期から前中期の細長い染色体にGバンドなどの分染を施し観察するものである.従来の方法ではハプロイド(半数染色体セット)当たり,表出されるバンドの数は320程度であったが,高精度分染法では850以上のバンドの表出が可能である.微細な染色体構造異常の同定,正確な切断点の決定,遺伝子の詳細な座位の決定など,高精度分染法は臨床の場においても,研究面においても必須のものとなっている.本稿では現在筆者らが用いている方法を中心にその具体的方法を示すとともに,本法の臨床的意義および用いる際の留意点につき述べてみたい.
10)染色体ペインティング
著者: 吉浦孝一郎 , 太田亨 , 當間隆也
ページ範囲:P.175 - P.178
●はじめに
1970年代初頭から染色体を染め分ける技術すなわち染色体分染法が開発され,ヒト24種の染色体がそれぞれ分別可能となり染色体異常症や,遺伝性疾患の知見が飛躍的に増大した.染色体分染法は他の項で述べられているように,その染色体上の縞模様(バンド)のパターン・処理法によってG-バンド,Q-バンド,R-バンド1,2)など,数多くある.その中で,本稿では染色体ペインティング(染色体彩色法)と呼ばれる技術について解説してみたい.
染色体ペインティング(chromosomal painting)は,他の分染法とは異なり,スライドグラス上に展開した染色体に,分子生物学的な手法を用いて入手したDNAライブラリーを雑種形成(hybridization)させ,その雑種形成の起こった部位のみを,蛍光が発するようにするものである.蛍光により染色体が絵の具で塗られたように観察できるので,染色体ペインティングと呼ばれている.
11)蛍光in situ分子雑種形成法
著者: 高橋永一
ページ範囲:P.179 - P.183
●はじめに
遺伝子地図(細胞遺伝学的地図および遺伝的連鎖地図)の作成は遺伝性疾患や癌などの遺伝的解析には不可欠の手段である.染色体上に遺伝子あるいはDNA配列の物理的位置づけを行う(細胞遺伝学的地図〉には最近の蛍光in situ分子雑種形成法(FISH)は極めて有効である.本稿では複製前中期R-分染核型標本の作製,FISHの標準法,さらに,二次抗体を用いたシグナルの増幅(amplification)とヒト全DNAによる抑制(in situ suppression hybridization)について述べる.
3.染色体写真
2色蛍光in situ分子雑種法
著者: 中川均 , 稲澤譲治
ページ範囲:P.184 - P.187
●はじめに
遺伝子マッピングや細胞遺伝学の分野において,蛍光in situ分子雑種(fluorescence in situ hybridization;FISH)法は重要な手法となった.従来のオートラジオグラフィーを用いた方法に比べ,簡便で迅速に結果が得られることに加え,FISH法は異なる蛍光色素と異なる核酸プローブを組み合わせることで,2種以上のプローブを同時に分子雑種させて雑種部位を色分けして観察できる.このような手法は2色,あるいは多色蛍光in situ分子雑種法と呼ばれている.本法を用いることで,近接する複数の遺伝子の配列順序の決定や染色体異常の検出,同定などが分裂期染色体上だけでなく,間期核においても可能となった.本稿ではその原理と実際的な方法,応用について述べてみたい.
IV HLAタイピング
1.HLAタイピングの意義
著者: 萩原政夫 , 辻公美
ページ範囲:P.202 - P.205
●HLAとはなにか
あらゆる高等生物は自己と他者とを識別するシステムとしての遺伝的標識を有している.主要組織適合抗原(major hitocompatibility complex;MHC)がそれであり,マウスの場合はH-2抗原,ヒトではHLA(human leukocyte antigen)抗原と呼ばれている.
日常的にこのHLA抗原の存在を身近に感じるのは,骨髄移植や臓器移植において患者であるレシピエントと臓器提供者であるドナーとの間で,HLA抗原タイプが一致していることが移植の成功の決め手になるときであろう.しかし本来HLA抗原の役割としては,われわれの環境中に存在し身体を脅かす細菌やウイルスなどの外来抗原が侵入してきたときに,自己のHLA抗原と照合することによって外来抗原を非自己であるとみなし,これを駆逐するための免疫反応を作動させるところにある(つまり移植片そのものは外来抗原そのものである).
2.抗体を用いる方法
著者: 関口進
ページ範囲:P.206 - P.210
1951年にフランスのドセー博士が初めて白血球抗原分類の方法として白血球凝集反応の手技を開発して以来,1957年以後アメリカのペイン博士,オランダのファン・ルード博士らが現在のHLA-A,-B座抗原分類の先駆けを作り,アメリカのエイモス博士,テラサキ博士が現在最も多く使われているLCT(lymphocyte cytotoxicity test;リンパ球細胞毒試験)を開発した.さらにテラサキ博士がこれを微量化し,ウサギ血清を補体として使用したので,感度も向上し,多量の検体が検査可能となり,全世界で広く用いられるようになり,WHO,NIH標準法となった.この手技は後述のごとく臓器移植のための組織適合性検査のみでなく,クロスマッチテスト,抗体スクリーニングなどにも応用され今日に至っている.その他疾患感受性,親子鑑定,人類遺伝学にと多くの分野で応用されていることは言うまでもない.
3.DNAを用いる方法
著者: 狩野恭一
ページ範囲:P.211 - P.217
過去30年間に臓器・細胞移植は劇的な発展を遂げた.特に1980年代の新しい免疫抑制剤であるシクロスポリンAは従来の腎移植のみならず,一時中止状態にあった心・肝移植や骨髄移植の例数を飛躍的に増加させた.正に臨床移植のルネサンス期に入ったと言えよう.こうした臨床の成果を支える柱として主要組織適合検査,すなわちHLAの同定とマッチングの技術も著しい進歩を遂げた.特に分子生物学的アプローチは過半数のHLAクラスI遺伝子,大半のクラスII遺伝子の一次構造を決めるに至った.恐らく今後2~3年の間にすべてのHLA遺伝子の一次構造が決められるであろう.
すでに前項「抗体を用いる方法」で詳しく述べられたように,分子生物学的アプローチは血清学的に同定が困難なHLAクラスII抗原の同定に威力を発揮してきた.現在,DNAを用いたHLAタイピングはクラスII抗原の特異性の確認と1つの特異性を,さらに細分するサブスペシフィシティの研究に用いられている.したがって本稿では,まずHLAクラスIIタイピングの古典的方法である.細胞性タイピングについて解説し,これとの対比においてDNAタイピングについて述べてみたい.
話題
APRT欠損症
著者: 鎌谷直之
ページ範囲:P.220 - P.221
1.APRT欠損症の概要
APRT(adenine phosphoribosyltransferase)欠損症は常染色体性劣性の遺伝病で,症状は2,8-dihy-droxyadenine(DHA)を主成分とした尿路結石症,腎発育不全,慢性腎不全症などである.APRTはアデニンをAMPに変換する酵素で,この酵素が欠損すると体内にアデニンが蓄積し,アデニンはキサンチンオキシダーゼの作用によりDHAとなる.DHAは極めて難溶の物質であり尿路で結晶化し,結石症や腎障害の原因となる1).
APRT欠損症はわが国からの報告が圧倒的に多い.日本以外ではヨーロッパを中心に約36人の報告があるが,1か国からの報告は10家系に満たない.われわれが診断依頼を受けたものだけでもAPRT欠損症のホモ接合体と診断されたのは73家系,90人である.世界では156人のAPRT欠損のホモ接合体が発表されており,その内120人(約77%)は日本人である.
家族性アミロイドポリニューロパチー
著者: 島田和典
ページ範囲:P.221 - P.222
家族性アミロイドポリニューロパチー(familialamyloidotic polyneuropathy;FAP)は,常染色体性優性の遺伝形式を示す先天代謝異常である.1952年にポルトガル人の症例が初めて報告されて以来,世界各国から同様の症例報告がなされており,臨床病型から下肢型,上肢型,顔面型に大別される.日本人のFAPは下肢型に分類されているが,この型は最も症例数が多く,主要症状は左右対称性に下肢末端から上行する知覚障害を主とした末梢神経障害と自律神経障害である.自律神経障害は交代性の下痢と便秘,発汗障害,立ちくらみ,インポテンツ,排尿障害など多彩である.これに全身のやせ,心臓障害などが加わり,発症後数年~十数年を経て,心不全,尿毒症,肺炎などで死亡する.病理学的には脳や脊髄実質を除く全身臓器の組織間隙,細胞外に"アミロイド"と呼ばれる"デンプン"と同じ染色性を示す不溶性線維状物質の沈着を認める.
1978年に下肢型でみられるアミロイドは,血清蛋白の一種,トランスサイレチン(transthyretin;TTR)から成ることが示され,その後,日本人のFAPでTTRのN末端から30番目のアミノ酸,バリン(Val)がメチオニン(Met)に置換した異型TTRが沈着していることが報告された.われわれはヒト肝臓cDNAライブラリーからTTR cDNAを単離して塩基配列構造を決定した1).この塩基配列構造から,下肢型FAPの異型TTRはValを規定するコドンGTGの最初のGがAに変異したためであることがわかった.この変異により,変異ttr遺伝子上には制限酵素NsiI切断部位の出現が予想された.
アカタラセミア
著者: 緒方正名
ページ範囲:P.222 - P.223
アカタラセミア(acatalasemia)は,1947年に高原によって発見された,カタラーゼを欠如する常染色体劣性形質の体質異常1)である.カタラーゼは,2H2O2→O2+2H2Oの反応を触媒する酵素である.
グルコース-6-リン酸脱水素酵素異常症
著者: 廣野見
ページ範囲:P.223 - P.224
グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PD)はペントースリン酸回路の律速酵素で,細胞を酸化から守るために必要なNADPHを供給するという重要な働きを担っている.G6PDはその異常により遺伝性溶血性貧血をきたしうることで,臨床的にも重要な酵素である.G6PD異常症はアメリカ黒人をはじめ南西アフリカ,地中海沿岸,東南アジアなどに広く分布しており,全世界で約1億人以上が本症遺伝子を持っていると考えられるきわめて頻度の高い疾患である.G6PD異常症にはまったく無症状のものから,普段は健康でも感染症に罹患したり,ある種の薬剤を服用した後に溶血発作を起こすもの,慢性的に溶血性貧血をきたすものなどさまざまなタイプがある.重症例でも障害はほとんど赤血球のみに限られている.G6PDの遺伝子はX染色体上にあるので,通常,患者は男性である.風邪をひいたり薬を服用した後でコーラのような色をした尿が出たと訴える男性の患者が来た場合には,本症を疑うべきであろう.
G6PD異常症の診断は,臨床所見,ハインツ小体陽性赤血球の出現などが参考になるが,確定診断は赤血球中のG6PD活性の低下を証明することによりなされる1).赤血球中のG6PD活性は正常者でも比較的低値であり,酵素自体も不安定で失活しやすいので,精度の高い分光光度計,純度の高い試薬,熟練した技師による測定が望まれる.G6PD異常症の診断には赤血球中の酵素活性を測定することが必要であり,血清中のG6PD活性はG6PD異常症の診断には意味がない.後者はALT,ASTなどと同様,逸脱酵素であり,正常者でも活性値がゼロのこともありうるからである.また,NADPHは還元型グルタチオン(GSH)濃度の維持に不可欠であるため,G6PD異常症患者赤血球ではGSH濃度が低下している.G6PD異常症の診断上,重要な所見である.
血友病の遺伝子解析
著者: 西村拓也 , 福井弘
ページ範囲:P.224 - P.225
血友病は第Ⅷ因子(血友病A)または第Ⅸ因子(血友病B)活性の低下する伴性劣性遺伝性の出血性疾患である.
本稿では,実際にわれわれが臨床の場で行っている血友病Aの遺伝子解析による保因者診断と出生前診断を紹介する.
ミトコンドリア脳筋症
著者: 宝来聰
ページ範囲:P.225 - P.226
ミトコンドリアには,核内にあるDNAとは異なる,独自の環状DNAが存在している.このDNAはミトコンドリアDNA(mtDNA)と呼ばれ,この中には2種類のリボソームRNA,22種類のtRNA,電子伝達系を構成するサブユニットのうちの13種類の蛋白質をそれぞれコードする遺伝子が含まれている.ヒトのmtDNAは16,569塩基対よりなり,核の染色体DNAが約30億塩基対あるのに比べて,非常に小さなゲノムである.近年ミトコンドリア脳筋症で,このmtDNAに種々の異常が明らかとなった.
ミトコンドリア脳筋症は一般に臨床病理学的に3型に分類される.すなわち,①Kearns-Sayre症候群を含む慢性進行性外眼筋麻痺(chronic progressive external ophthalmoplegia;CPEO),②ミオクローヌスてんかんを主症状とするMERRF(myoclonus epilepsyassociated with ragged-redfibers),③卒中様症状を特徴とするMELAS(mitochondrial myopathy,encephalopathy,lactic acidosis and stroke-like episodes)である.
アデノシンデアミナーゼ欠損重症複合免疫不全症
著者: 伊藤和彦
ページ範囲:P.226 - P.227
本症は,免疫不全の病因の1つが酵素欠損であることを示した最初の例である.重症複合免疫不全症(SCID)の20~30%の症例がアデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損を病因とする.最近では遺伝子治療の最適疾患として注目されている.
ホスホフルクトキナーゼ欠損症
著者: 中島弘
ページ範囲:P.227 - P.228
解糖系律速酵素ホスホフルクトキナーゼ(PFK)の筋における欠損症はグリコーゲン病Ⅷ型に分類され,最初の報告1)に由来して"Tarui病"とも呼ばれる.筋肉運動時の易疲労性を主訴とし,臨床検査では運動後の血中乳酸上昇の欠如とクレアチンキナーゼ(CK)の異常高値が認められる.また,最近は運動筋のプリン体異化亢進に基づく"筋原性高尿酸血症"2)をきたす代表的疾患としても注目される.
類縁疾患であるグリコーゲン病Ⅴ型(McArdle病,筋ホスホリラーゼ欠損症3))との大きな相違点は,軽度の溶血と間接ビリルビンの高値を認めることで,欠損酵素である筋型PFKが赤血球PFKを構成するサブユニットの1つであることに起因する.患者筋でグリコーゲン分解から解糖の各段階の代謝産物を定量すると,フルクトース-6―リン酸およびその前段階の物質が異常に蓄積し,フルクトース-1,6―ピスリン酸が著減し,PFKステップのブロックが明瞭に示される(クロスオーバー・ポイント)4).
ホスホグリセリン酸キナーゼ異常症
著者: 藤井寿一
ページ範囲:P.229 - P.230
ホスホグリセリン酸キナーゼ(phosphoglyceratekinase;PGK)異常症は慢性溶血性貧血としばしば精神・神経症状を伴うことが多く,赤血球酵素異常症の中では比較的重篤な伴性遺伝性疾患で,世界で15家系(うち,わが国の例は4家系)の報告がある1,2).PGKは正常酵素の3次構造も明らかになっており,人類遺伝学および酵素学的に非常に興味ある酵素であり,現在までに6種の変異酵素において単一アミノ酸置換が証明されている(図1)2~7).すなわち,酵素の活性基に重大な影響を及ぼす部位の単一アミノ酸置換であるPGK Uppsala, PGK TokyoとPGK Matsueは溶血性貧血と精神・神経症状は重篤である.PGK Shizuokaのアミノ酸置換の部位はN―ドメインを構成するβストランド直前で,等電点変化はほとんどないが,より側鎖の大きいアミノ酸への変化で,軽度の溶血とミオグロビン尿を呈するものの,精神・神経症状は伴わない.活性基に直接影響を及ぼさない酵素蛋白表面での異常であるPGK IIとPGK Münchenでは臨床症状は認められない.
以上,分子遺伝学的手法の進歩に伴い,変異酵素の構造異常の同定が分子レベルで可能となり,PGK異常症では変異酵素の構造異常と機能異常の関係が明らかになっている.
Zellweger症候群の遺伝子変異
著者: 折居忠夫 , 鈴木康之 , 下澤伸行 , 矢嶋茂裕
ページ範囲:P.230 - P.232
1.はじめに
典型的なZellweger症候群(ZS)の患者の多くは生後半年以内に死亡する.その意味からもペルオキシソームは生体にとって極めて重要な細胞内小器官と言うことができる.ZSの病因は不明であったが,本年初めに筆者らによりZSのF群の遺伝子変異が同定された.それによるとペルオキシソーム膜蛋白質の一部に変異を起こし,膜のassembly (統合化)に欠陥を生じ,正常なペルオキシソームが形成されず,2次的代謝障害により致死的病像を呈する.このようにZSは生体膜研究の天然の実験系として,また種々の奇形を伴うことから,ペルオキシソームの器官形成への関与,さらには神経細胞移動障害の機構などの解明に極めて貴重な疾患である.本稿では主にZSのF群の病因であった遺伝子変異の同定について述べる.
プロピオン酸血症
著者: 大浦敏博
ページ範囲:P.233 - P.233
プロピオン酸血症はプロピオニルCoAカルボキシラーゼ(PCC)の欠損により引き起こされる有機酸代謝異常症である.患児は出生後間もなくから高アンモニア血症,代謝性アシドーシスで発症し,適切な治療がなされなければ不幸な転帰をとることが多い1).
PCCはビオチンを補酵素とするミトコンドリア酵素で,2つの異なるサブユニットから成り成熟酵素はα6β6構造をとる.1986年,Krausら2)はラットPCCβ鎖の全長cDNAを初めて分離し,その全塩基配列を決定した.また,同年Lamhonwahら3)もヒトPCCα,β鎖をそれぞれコードしている部分cDNAを単離し,α鎖遺伝子は第13染色体,β鎖遺伝子は第3染色体に局在していることが明らかとなった.
HLAのDNAタイピングと人類学
著者: 徳永勝士
ページ範囲:P.234 - P.238
<はじめに>
近年のDNAタイピング法は,PCR (polymerasechain reaction)法の開発によって急速な展開を見せている.人類学領域におけるDNAレベルのデータの蓄積もPCR法の出現によって加速されている.その典型的な例がミトコンドリアDNAとHLA遺伝子群だと言える.
1991年に開催された第11回国際組織適合性ワークショップ(以下,11HW)では,人類学的研究も主要なテーマの1つに掲げられ,大規模な国際共同研究が行われた.本稿ではこの結果の一部を示して,HLA遺伝子のDNAタイピングに基づく人類学的研究の現状の紹介としたい.なお,ミトコンドリアDNAに関しては,すでにいくつかの総説があるので参照いただきたい1,2).
遺伝子治療の現状
著者: 島田隆
ページ範囲:P.239 - P.241
<はじめに>
1990年9月,米国NIHで世界最初の遺伝子治療がアデノシンデアミナーゼ(ADA)欠損による重症複合免疫不全症の4歳の少女に対し開始された.さらにその4か月後には癌の遺伝子治療も始められている.これらのニュースは世界中で大きな話題となっており,米国以外の国でも遺伝子治療開始の機運が急速に高まっている.本稿では,米国で行われている遺伝子治療を中心に,現在の遺伝子治療の考えかたについて紹介したい.
基本情報
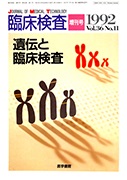
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
