止血機構は生体の持つ精緻な防禦反応の1つであり,その分子機構が詳細に解明されつつあるが,先天性出血性疾患の病態の理解がこれに大きく貢献している.止血のための血栓形成は血管損傷部位に露出した血管内皮下組織への血小板の粘着に始まり,それに続く,血小板凝集と血小板や内皮細胞表面でのフィブリン形成により完結する.この一連の反応は決して行き過ぎることはない.すなわち,血栓形成過程が継続し,血管内腔を閉塞するような大きな血栓を形成することは決してないのである.そこでは,血栓形成の方向,大きさなどを規定し,制禦する機構が働いており,プロテインC・トロンボモジュリン系,アンチトロンビンIIIなどの血液凝固制禦因子の重要性が既に指摘されているほか,血流がもたらす物理的因子,内皮細胞因子などもまた深く関与していると考えられる.
本号では"血栓症と血小板凝固線溶系検査"として,病的血栓形成をめぐる臨床検査について特集が組まれている.
雑誌目次
臨床検査40巻11号
1996年10月発行
雑誌目次
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
序
血栓症と血小板凝固線溶系検査
著者: 池田康夫
ページ範囲:P.7 - P.8
血栓症の病態
5.DIC
著者: 岡鳴研二
ページ範囲:P.55 - P.60
はじめに
播種性血管内凝固症候群(disseminated intravas-cular coagulation; DIC)は,いろいろな重篤な基礎疾患の存在下に,全身に微小血栓が形成される病態である.DICの概念が確立されたのは,今から約50年前であるが,DICと思われる最初の症例は,今から約100年前にすでに報告されている1).その後,DICの病態解析が進むにつれ,DICの病態生理は基礎病態に応じて異なることが判明してきた.本稿ではDICの病態の診断法,その多様性,およびそれぞれの病態に応じた適切な治療方法の選択について述べる.
6.TTP/HUS
著者: 高橋芳右
ページ範囲:P.61 - P.63
概念
血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic throm-bocytopenic purpura; TTP)は,1924年Moschc-owitzにより最初に報告された特異な臨床像を呈する症候群である.臨床的には細小血管障害性溶血性貧血,血小板減少症,動揺する精神神経症状,腎障害および発熱を主徴とし,脳,腎,心,膵,副腎,脾を主体とした広範な組織の細動脈および毛細血管に,主として血小板から成る微小血栓形成をきたす.TTPは種々の病態により惹起され,全身性エリテマトーデスなどの膠原病,慢性関節リウマチ,悪性腫瘍,妊娠,マイトマイシン,シスプラチン,シクロスポリンなどの薬剤投与,ウイルス感染,細菌性心内膜炎などに随伴して起こり,また,特発性,家族性の発症もある.最近では,HIV感染者での発症も注目されている.
一方,溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syn-drome; HUS)は1955年Gasserらにより初めて報告された急性腎不全,溶血性貧血,血小板減少症を主徴とする症候群である.TTPと比較し,HUSは幼児に好発し,胃腸症状(下痢,血便,腹痛)が先行する場合が多く,腎不全をきたしやすい.病変は比較的腎に限局し,病理組織学的には糸球体係蹄内皮細胞の腫脹,内皮下の浮腫・細線維綿花状物質の貯留,血小板およびフィブリンから成る微小血栓がみられる.
2.血栓形成のしくみ
1)血栓症の実験モデル
著者: 居石克夫
ページ範囲:P.16 - P.21
はじめに
血管内の血液は,生理的には流動性が保たれているが,血管壁が損傷されるとその部に限局した止血血栓が形成され,その後,しばらくして,血栓の多くは融解もしくは器質化されて血流が再開される.この一連の反応過程に関与するのが凝固,線溶(線維素―フィブリン―溶解)系である.特に,この分野での最近の研究の進歩は,凝固系活性化因子とともに制御因子の分子構造と機能,およびそれら分子間相互反応が明らかになってきたことにある.とりわけ血管内皮細胞の機能を中心とした血液凝固の制御調節機構(抗血栓性特性)に関する分子レベルでの研究の進歩は目覚ましい.血管生物学の進歩と相まって,これらの研究成果により種々の血管病変の発生,進展ならびに修復機序における血液ならびに組織凝固の役割が分子レベルで理解されるようになってきた.
本稿では,主に外因系凝固活性化の鍵となる組織因子(TF)の血栓症発生における病態学的意義について病理形態像を中心に概説する.
2)血小板系
著者: 渡辺清明
ページ範囲:P.22 - P.24
はじめに
血小板血栓の形成は,血栓症の病態,特に動脈系の血栓の発現にきわめて重要である.
血管壁がなんらかの原因で障害されると,血中の血小板は障害部位の内皮下組織に粘着し,放出,凝集を起こし,フィブリンとともに血栓を形成し,止血する.
3)凝固・凝固制御因子系
著者: 森下英理子 , 松田保
ページ範囲:P.25 - P.28
血液凝固機序
1.止血と血栓
出血の際に,破綻した血管が細小血管であるときは,血小板の粘着と凝集のみによって止血が可能であるが,比較的大きい血管が破綻したときには,血液の凝固,つまりフィブリンの形成が必要である.ところが血管が破綻していないのに,止血機序が強力に動き,血液の凝固によって血管が閉塞することがある.これが血栓症である.このように,止血の機序と血栓発現の機序は,同一の現象であると考えられる.
血液の凝固反応は,その開始機序の違いから外因系凝固と内因系凝固に大別される.生理的な止血機序は,主に外因系凝固の活性化によるものと考えられている1).
4)線溶系
著者: 岡田清孝 , 松尾理
ページ範囲:P.29 - P.32
はじめに
血液線溶系は血液凝固系の活性化によりフィブリノゲンから形成されたフィブリンを分解し,循環血液中からフィブリン(血栓)を除去する系である.このフィブリンを分解する線溶系因子は,その前駆体であるプラスミノゲンという状態で通常血液中を循環している.この前駆体はプラスミノゲンアクチベーター(PA)という酵素によってプラスミンというフィブリンを分解することのできるセリン酵素に活性化される.生体内に存在するPAには主に血管内皮細胞が生産・分泌する組織性PA (t-PA)と,主に腎細胞が生産・分泌するウロキナーゼ型PA (u-PAまたはUK)の2種類がある1).また,これらの線溶系酵素を阻害する因子としてPAに対してプラスミノゲンアクチベーターインヒビター(PAI)が,プラスミンに対してα2-プラスミンインヒビター(α2-PI)が存在し,それぞれを制御している(図1).
このように血液線溶系は活性化系と抑制系が存在し,生理的に両者のバランスで巧妙に制御されている.しかし,この活性化系の機能低下や抑制系の機能亢進が血栓傾向になり,活性化系の機能亢進や抑制系の機能低下が出血傾向をもたらすことになる.
5)血管内皮細胞
著者: 小嶋哲人
ページ範囲:P.33 - P.36
はじめに
血管内皮細胞は,従来,血漿成分の血管周囲組織への漏出を防ぐ単なるバリヤーとして働く細胞であると考えられていた.しかし,最近では血管内腔を覆う単層のこの内皮細胞はさまざまな生理活性物質を発現分泌して血液凝固・線溶の調節,血管トーヌスの調節,炎症反応(白血球接着)の調節などを行い,血管の恒常性ひいては生体ホメオスターシスに極めて重要な働きを持つことが明らかとなってきている.
血栓形成は血液凝固因子,血小板,血液レオロジー,あるいは血管内皮細胞の異常などが複雑に絡んで引き起こされるが,一方では生体の防御反応機構の一部でもあり炎症反応や組織修復反応と並行して進行し制御されている.本稿では,血管内皮細胞による血栓形成制御について,血管内皮細胞の産生するさまざまな分子を通して概説する.
4.血栓傾向
1)先天性血栓傾向
著者: 高松純樹
ページ範囲:P.42 - P.44
はじめに
先天的に比較的若年の術後患者,妊婦などにおいて反復性・家族性に深部静脈血栓症が高頻度に認められることが報告されており,注目されている.これらのうち凝固系の阻止因子・線溶系因子の先天的欠乏もしくは分子異常のため機能障害をきたし,その結果,主として深部静脈血栓症を呈する疾患群を先天性血栓傾向と称する.表1には現在までに報告されている血栓症の原因となる諸因子の先天性異常を示すが,ホモシスチン血症は厳密には凝固因子の異常ではないが最近の研究で1つの仮説として血管内皮細胞に発現されているトロンボモジュリンの機能障害を惹起することにより,プロテインCを介した抗凝固作用を阻害し,その結果,血栓症が誘発されることが明らかになった.APCレジスタンスについては別項を参照されたい.
2) APCレジスタンス
著者: 藤村博信 , 上林純一
ページ範囲:P.45 - P.47
はじめに
過去,さまざまな知見が集積するにつれて,先天性家族性血栓症の病態が明らかにされてきた.その中でも凝固制御系因子である,プロテインC,プロテインS,アンチトロンビンⅢの異常症は非常に重要な異常症であるが,その3つを合わせても患者のせいぜい10%程度の頻度しかなく,新たな血栓性素因の原因が捜索されていた.そのような状況下,1993年に新たな血栓症のリスクファクターとして,活性型プロテインCに対して先天的に抵抗性を持つ病態(APCレジスタンス)が,Dahlbäckら1)によって見いだされた.欧米の報告によるとその頻度は血栓症患者の20~60%,正常人の2~10%にみられるとされ,最も重要な血栓性素因とされる.また,APCレジスタンスの原因とされる遺伝子異常についても知見が集積されてきている.
この稿では,最も新しくそして最も重要かつ高頻度と考えられる先天性血栓性素因であるAPCレジスタンスのプロテインC凝固制御系における病態,遺伝子異常によって生じると考えられる病態,およびその臨床病態を述べることとし,異常遺伝子の解析を含む臨床検査方法については別項に述べる.
3)抗リン脂質抗体症候群
著者: 鏑木淳一
ページ範囲:P.48 - P.50
はじめに
血清中自己抗体の測定は,全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus;SLE)など膠原病各疾患において,診断・病型分類・治療方法の選択などに有用である.近年,カルジオリピン・ホスファチジルセリンなど陰性荷電を有するリン脂質に対する抗体が測定され,陽性例の臨床特徴が追究された.これにより,"抗リン脂質抗体症候群"(antiphospholipidsyndrome; APS)という疾患概念が提唱された1).APSはSLEなどを基礎疾患とする二次性(secon-dary)APSと基礎疾患が明らかでない原発性(pri-mary)APSに分類される2).
4)薬剤性血栓傾向
著者: 新倉春男
ページ範囲:P.51 - P.54
はじめに
止血機構に影響を及ぼして出血傾向あるいは血栓・塞栓症を起こす薬物は少なくないが,出血傾向に比べて,血栓傾向をもたらす機序を明確にすることは,血小板,凝固線溶系,血管内皮,血行動態などが複雑に絡むため,必ずしも容易ではない.
副作用として血栓・塞栓症が報告されている薬剤を表1に示した.これらの薬物が直接止血機構に働いて血栓傾向をもたらすとは限らず,血管内皮の障害,血行動態の変化などに関連して血栓傾向がもたらされる場合も多い.また,患者の年齢,性,嗜好品,基礎疾患の種類と重症度,併用されている薬剤などにも影響される.ここでは血栓・塞栓症の原因として比較的よく知られている薬物につき,その発生機序を解説する.
血栓症の検査 1.血小板の検査
1)血小板数
著者: 鈴木節子
ページ範囲:P.66 - P.68
はじめに
血小板数は血液疾患のみならず,止血機能に影響を及ぼす多くの疾患の進展にも広く関与する重要な指標であり,血小板減少による出血傾向の頻度は高い.血小板数算定は,主に止血機能の指標として行われる検査であり,近年では全自動血球分析装置(以下血算装置)による算定が普及している.
本稿では主として5種の装置:STKS (コールター社),SE-9000(シスメックス社),ARGOS (ロシュ社),CD3500(ダイナボット社),H・3(テクニコン社),を対象としてある.
2)血小板凝集能
著者: 松野一彦
ページ範囲:P.69 - P.72
測定の意義
血小板は刺激を受けると,種々の生化学的反応を介して,血小板膜に存在する糖蛋白GPIIbとGPIIIaが複合体を形成し,そこにフィブリノゲンが結合することによって,血小板間に架橋が形成される形で,血小板凝集が起こる.これは血小板凝集塊を形成することによって,出血の際の一次止血に重要な役割を果たす.
したがって,先天的に血小板機能異常のある血小板無力症やBernard-Soulier症候群などの診断には血小板凝集能の測定は必須である.また,血栓症,特に動脈血栓症の発症に血小板が関与していると考えられており,現在脳梗塞の再発予防などの治療に抗血小板剤が用いられている.したがって,生体内の血小板活性化の把握や抗血小板剤治療の選択およびモニターにも血小板凝集能測定が用いられている.
3)血小板停滞率
著者: 玉井佳子 , 高見秀樹
ページ範囲:P.73 - P.74
はじめに
血小板停滞率(platelet retention rate)は,ガラスビーズ(GB)カラムに血液を通過させビーズ表面に粘着・凝集する血小板を測定する検査である.以前は血小板粘着能と呼ばれていたが,血小板粘着のみならず凝集も反映しているため血小板停滞率と呼ぶべきである.より生理的なin vitro検査としてビーズ表面をコラーゲンでコートしたコラーゲンビーズカラムが開発され市販されているが,本稿では臨床検査として最も普及しているガラスビーズカラムを用いたSalzman法1)(吸引法;わが国ではその変法である安永法2)が一般的である)と,Hellem II法3)(押出法)について解説する.
4)粘着能
著者: 冨山佳昭
ページ範囲:P.75 - P.76
はじめに
血管が障害を受けると,血小板は速やかに障害部分に露出した血管内皮下組織に粘着する.さらに粘着した血小板を基盤として血小板同士が凝集塊を形成し止血血栓となる1).この過程は生理的な止血血栓に限らず病的血栓形成にもあてはめて考えることができる.心筋梗塞や脳梗塞などの原因となる動脈の病的血栓が血小板主体の白色血栓であることから,血小板の重要性が容易に理解されるが,これらの病態では動脈硬化による粥腫(プラーク)の破綻が病的血栓に至る引き金と考えられる.血管内皮下組織にはコラーゲン,フィブロネクチン,ラミニンなどが存在しているが,特にコラーゲンと血小板との直接的な粘着およびフィブロネクチンやvon Willebrand因子を介した間接的な粘着は止血血栓形成に重要と考えられている2).さらに近年,動脈硬化巣においてはコラーゲンのタイプIおよびタイプIIIが増加していること,およびこの増加が病的血栓形成と密接に関係していることが示された3).このように,血管内皮下組織と血小板との粘着を解析することは血栓形成過程の解明に必須であると考えられる.
前述の血小板停滞率は,ガラスビーズという非生理的な物質と血小板との粘着能と凝集能を全体として観察しているスクリーニングの検査法であり,異常値が観察されても,その原因を特定するのは困難である.
5)散乱光を用いた粒子計測法による血小板凝集能
著者: 佐藤金夫 , 尾崎由基男 , 矢冨裕 , 久米章司
ページ範囲:P.77 - P.80
はじめに
血小板は生理的な止血機構の中心的な役割を演じていると同時に,心筋梗塞・脳梗塞などの病的血栓の形成にも重要な役割を果たしている.血小板の機能を評価することは血栓傾向あるいは血栓準備状態の発見,および,それらの病態解明において有用な情報を提供すると考えられる.血小板機能検査には粘着能,凝集能,放出能などが挙げられるが,なかでも血小板凝集能は血小板機能検査の中心的位置を占めている.
血小板凝集能の検査法には,血小板凝集の程度を光透過性(吸光度)の変化を利用して測定する吸光度法1),血小板凝集塊が電極に付着する際に起こる電位の変化を捉えるインピーダンス法2),凝集塊の形成に関与していない単一血小板の数から凝集の程度を知る粒子数算定法3),アゴニスト添加なしにずり応力によって血小板を凝集させるshear-induced plateletaggregation (SIPA)4)があるが,臨床検査では吸光度法が最も汎用されている.しかし,吸光度法は数千個の血小板から成る巨大凝集塊が形成されて初めて吸光度の低下がみられるため,血小板凝集塊の形成と光透過性の相関が悪く,また,小凝集塊の検出ができない,などの難点がある.われわれはこれらの問題を解決すべく,新しい測定法(粒子計測法)に基づく血小板凝集能測定装置(AG-10;興和株式会社)を開発し5),その有用性について検討している.
6)ずり応力凝集能
著者: 小田淳
ページ範囲:P.81 - P.83
ずり応力惹起血小板凝集(shear-induced Platelet aggregation;SIPA)の概念と測定意義
血栓症は動脈系に生じるか,静脈系に生じるかによってかなり様相が異なる.動脈では,血栓形成の際,中心となるのが血小板であり,血小板は無色であるので,いわゆる白色血栓が生じる.例えば突然死の一部,心筋梗塞などは,粥状硬化巣の脆い部分に血流の影響などで亀裂が生じ(ulceration),そこに血栓が形成され,冠動脈の閉塞をもたらすことにより発症するものと考えられてきている.このような場合,血小板やその凝集塊は狭窄した動脈内で速い血流に曝されることとなる.この血流は,血管断面上において一定ではなく,血管中央で最大であり,血管壁の部分が速度0に近いため,速度勾配が生じる.血流速度の異なる部分の間に存在する血小板やその凝集塊には,速度勾配のため,これらを歪ませて,引きちぎろうとする力=ずり応力(shear force)が作用することとなる.最近の動物モデルを用いた詳細な研究では58±8%の5mm長の冠動脈狭窄を生じさせた際,最高のずり応力は最狭窄部の直前で認められ,それは520から3,349dyn/cm2にも達し,血栓は狭窄部の入口から1mmの地点から形成される1).この程度のずり応力ともなると5msec程度の極めて短時間でも血小板活性化されることが知られている.
7)血小板由来マイクロパーティクルの検出
著者: 野村昌作
ページ範囲:P.84 - P.86
はじめに
血小板が種々の状況下で活性化されたり,物理的な刺激を受けると,微小な膜小胞体が生成される.この膜小胞体は,活性化血小板から放出された内部顆粒や膜性微粒子,および機械的破壊によって生成された膜フラグメントなどを含み,マイクロパーティクル(mi-croparticle;MP)と呼ばれている.血小板由来のマイクロパーティクル(PMP)は,単純に血小板崩壊の指標となるものではなく,止血・凝固において重要な役割を果たしていることが判明してきた1).本稿では,フローサイトメトリーを用いたPMPの検出法とPMP測定の意義について概説する.
8)TXA生成能,血漿TXB
著者: 森田育男
ページ範囲:P.87 - P.90
はじめに
循環器疾患,呼吸器疾患においてトロンボキサン(TX) A2は,血小板凝集惹起,血管平滑筋の収縮,気管平滑筋の収縮を引き起こす原因物質である.そこで,TXA2合成阻害剤やTXA2受容体アンタゴニストの製剤化がなされ,いくつかのものが世に出されている.最近,TXA2産生の初発酵素であるシクロオキシゲナーゼ-1のノックアウトマウスが作製され,血小板機能の低下が報告された1)ことから,血小板機能とTXA2との関係は疑いのないところである.
9)β-TG
著者: 西郷勝康 , 寮隆吉
ページ範囲:P.91 - P.92
β-TGとは
βトロンボグロブリン(β-thromboglobulin,β-TG)は,次項に述べる血小板第4因子(platelet fac-tor 4; PF-4)と共に血小板特異蛋白と呼ばれ,血小板に種々の刺激が加わり活性化された際に凝集反応と同時に血小板外へ放出される.したがって血中β―TG値は血小板活性化の指標の1つとして利用されている.
β-TGは81個のアミノ酸から成るサブユニット(分子量8,850)の4量体で,血中半減期は約100分と短く,主に尿中に排泄されるため腎機能低下時には血中β-TG値は高値となる.
10)PF-4
著者: 西郷勝康 , 寮隆吉
ページ範囲:P.93 - P.94
PF-4とは
血小板第IV因子(platelet factor 4;PF-4)は前項のβ-TGと共に血小板特異蛋白の1つで,β-TGと同様α顆粒内に蓄積されている1).さらに,肥満細胞やヒト臍帯静脈内皮細胞にも存在すると報告されている.
血小板中には,PF-4,β-TG,low affinity PF-4,血小板塩基性蛋白,フィブロネクチン,トロンボスポンジンなど,数々のヘパリン中和作用を持つ物質が知られているが,PF-4が最も強い.PF-4のグリコサミアミノグリカンへの親和性はヘパリンに最も強く,次いで,ヘパラン硫酸,デルマタン硫酸,コンドロイチン硫酸と続く.
11)血漿グリコカリシン
著者: 国島伸治
ページ範囲:P.95 - P.97
はじめに
血小板膜糖蛋白(GP)Ib/IX複合体はフォン・ウィルブラント因子の受容体として一次止血に重要な役割を担っている血小板特異的蛋白質であり,GPIbα,GPIbβ,GPIXから構成されている.血小板破壊あるいは血小板膜損傷があると,内因性の蛋白分解酵素(カルパイン)などがGPIbαの膜貫通部位直上を限定分解し,この分子の細胞外部分のほとんどを占めるグリコカリシンと呼ばれる可溶性膜抗原を遊離する(図1).グリコカリシンの血漿中濃度は血小板の産生と破壊のバランスにより規定され,血小板の活性化あるいは局所的な血小板消費とは相関しないと考えられている.最近の研究によって,グリコカリシンは血小板膜損傷の特異的指標として,血小板減少症の鑑別診断に有用であることが明らかになった.本稿では,われわれが開発した測定法によって得られた知見を中心に概説する.
2.血液凝固系の検査
1)APTT,PT,フィブリノゲン
著者: 福武勝幸
ページ範囲:P.99 - P.103
血液凝固機構は第Ⅶ因子の活性化に始まる内因性凝固機構,あるいは組織因子と第Ⅶ因子により活性化される外因性凝固機構により開始され,第X因子の活性化からは共通性凝固機構に移行し同一経路でフィブリンの析出すなわち凝固に至る.近年,活性型第Ⅶ因子により第Ⅸ因子が活性化される新たな選択的経路の存在が判明し,凝固機構の概念が変化しつつある.
血液凝固機構の検査は図1に示すように,活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)とプロトロンビン時間(PT)の2つの代表的検査法により構成されている.APTTは内因性凝固機構と共通性凝固機構を反映し,PTは外因性凝固機構と共通性凝固機構を反映する検査法である.これらの検査法を組み合わせて実施し,図2に示すように結果を判定することにより,凝固機構のどの部分に異常があるかを推測することができる.ただし,凝固因子のうち第Ⅷ因子の異常はこれらの検査では検出できず,フィブリノゲンは50mg/dl程度まで低下しないと反映されないので個々に測定するのが原則である.
2) AT Ⅲ
著者: 新谷憲治
ページ範囲:P.105 - P.108
測定の意義
AT Ⅲ(アンチトロンビンⅢ)は,セリンプロテアーゼ・インヒビター(serpin)ファミリー1)の一員で,血液凝固因子のトロンビンをはじめ,活性化第X因子や第IX因子などのを不活化して,血液凝固反応を制御する重要な血液凝固阻止因子である.AT Ⅲはヘパリンに結合する性質を有し,ヘパリンに結合したAT Ⅲの抗トロンビン作用は,約1,000倍にもスピードアップされる(progressive inhibitorからimmediate inn-hibitor)となる2).血中には,AT Ⅲと同様ヘパリンに結合して,その抗トロンビン活性を増強する因子heparin cofactor Ⅱ(HC Ⅱ)が存在する3)が,その因子と血栓症との因果関係は明らかでない.一方,先天性AT Ⅲ欠損症,分子異常症では,深部静脈血栓症などの血栓症が多発する.先天性AT-Ⅲ欠乏症は,AT Ⅲ分子そのものが減少する,タイプIとAT Ⅲ分子は存在するが,その分子の構造異常により抗トロンビン活性が低下するタイプⅡに大別される.AT Ⅲのヘパリン結合部位とトロンビンとの反応部位が,分子構造上離れているので,タイプⅡは,AT-Ⅲ分子のトロンビンとの反応部位の異常を示すもの(Ⅱ RS)とヘパリンとの結合部位の異常を示すもの(Ⅱ HBS)に分けられる.
3)プロテインC,プロテインS
著者: 鈴木宏治
ページ範囲:P.109 - P.112
プロテインC (PC)凝固制御系の概要
血液凝固反応で生成されたXa因子やトロンビンなどは,主に血管内皮細胞上のヘパラン硫酸に結合したアンチトロンビンⅢによって制御される.一方,血管内壁には,Xa因子やトロンビンの生成を阻害する制御系が存在し,PC凝固制御系と呼ばれる(図1).血管内で生成したトロンビンはそれ単独では,血小板膜表面のトロンビンレセプターを活性化して凝集反応を惹起し,また血漿中のフィブリノゲン,第V因子,第Ⅷ因子,第ⅩⅢ因子などを限定分解して活性化し,凝固血栓を形成させる.しかし,内皮細胞上のトロンボモジュリン(TM)に結合したトロンビンは凝固促進活性を消失し,選択的にPCだけを活性化する.活性化PC (APC)はプロテインS (PS)をコファクターとして,内皮細胞や血小板のリン脂質膜に結合したVa因子およびⅧ a因子を分解・失活化し,凝固反応を強く阻害する.
他方,血漿中のPSは補体系制御因子のC4b結合蛋白質(C4BP)と会合・乖離の平衡状態にあり,約40%のPSは遊離型,60%のPSはC4BPとの複合体型として存在し,APCコファクター活性は遊離型PSのみに存在する.また,PSはそれ単独で凝固過程におけるトロンビン生成反応であるプロトロンビナーゼ活性を阻害する.PSはVa因子およびXa因子に結合し,プロトロンビナーゼ複合体の形成を直接阻害すると考えられている.
4) APC・PCI複合体
著者: 鈴木宏治
ページ範囲:P.113 - P.116
はじめに
プロテインCインヒビター(PCI)は生理的血液凝固制御因子である活性化プロテインC (APC)の血漿インヒビターとして発見された.PCIは当初,先天性第V・VIII両因子欠損症患者に特異的に欠損する因子ではないかと考えられたが,その後この説は否定された.最近,PCIがトロンビン・トロンボモジュリン複合体を阻害することが示され,プロテインC凝固制御系の制御におけるPCIの重要性がより明確になってきた.他方,PCIは血漿のほかに,尿,精漿,滑液などにも存在し,それらの体液や組織に存在するセリンプロテアーゼを阻害することから,プロテインC凝固制御系以外の多数の生体反応の制御にもかかわっていると考えられる.
ここでは,凝固線溶系におけるPCIの役割とその病態生理を述べた後,APC・PCI複合体測定法の原理と測定意義,基準値と異常値,測定の問題点などについて紹介する.
5) F1+2
著者: 苅尾七臣 , 宮田敏行
ページ範囲:P.117 - P.119
はじめに
近年,凝固活性化分子マーカーの血中レベルの測定により凝固亢進状態が定量的に評価できるようになった.血液凝固反応において,活性型第X因子がプロトロンビンに作用し,トロンビンが生成されるが,このとき,プロトロンビンフラグメント1+2(F1+2)が放出される.近年,エンザイムイムノアッセイを用いた血中F1+2レベルの測定が可能となった.血中F1+2は生体内のトロンビン生成を表す鋭敏な指標として臨床応用され始めている1~7).
6) TAT
著者: 東原正明 , 宮崎浩二
ページ範囲:P.121 - P.122
原理・測定意義
DICなど血管内に血栓が多発する疾患では,血管内にトロンビンが生成されている.このトロンビンは,①フィブリノゲンをフィブリンに変換する,②第V因子,第Ⅷ因子,第ⅩⅠ因子,第ⅩⅢ因子を活性化する,③血小板を活性化する,④血管内皮細胞を刺激するなどの生理活性を有していて,この血中のトロンビンを測定することは,凝固亢進状態,血栓傾向を示す大きな指標となる.しかしながら,トロンビンは,生体が備えている抗血栓性のメカニズムにより生成されても,すぐに中和されて直接測定することは困難である.この中和作用として,antithrombin Ⅲ(ATⅢ)との複合体形成,フィブリンへの吸着,トロンボモジュリンとの複合体形成,ヘパリン・コファクターⅡとの複合体形成が挙げられる.ATⅢは分子量58,000の糖蛋白で,heparin cofactor Ⅰとも呼ばれserpin (serine protease inhibitor) superfamilyに属し,血中濃度は約150mg/mlである.ATIIIとトロンビンとの複合体,thrombin-antithrombin complex(TAT)(1:1の等モル比結合)の形成は,以下のように進行することが明らかにされている.
7) SFMC
著者: 日笠聡 , 垣下榮三
ページ範囲:P.123 - P.124
原理
生体内流血中でトロンビンが生成すると,フィブリノゲン(Fbg)のN末端Aα鎖16-17位とBβ鎖14-15位のarginine-glycineの結合が切断され,フィブリノペプタイドA (FPA),フィブリノペプタイドB(FPB)が遊離し,フィブリンモノマー(Fm)が形成される.Fmは互いのN末端部とC末端部が重合してフィブリンポリマー(Fp)となり,活性化ⅩⅢ因子とCa2+の存在下で安定化フィブリンへと変換する.
この際FmはFbgやフィブリン分解産物(FDP),フィプロネクチンなどとも親和性も強いため,これらと種々の複合体を形成する.これら複合体を可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC)と総称するが,最近は可溶性フィブリン(SF)と呼ぶことが勧められている1).
8) FPA
著者: 高橋芳右
ページ範囲:P.125 - P.127
凝血学的分子マーカーと臨床的意義
凝固系が活性化されるとトロンビンが生成され,線溶系が活性化されるとプラスミン生成に至り,それぞれフィブリン血栓の形成およびその分解にあずかる.実際には生成されたトロンビンおよびプラスミンの多くは,それぞれ生理的阻止因子のアンチトロンビンおよびプラスミンインヒビターに捕捉され,トロンビン-アンチトロンビン複合体(thrombin-antithrombincomplex;TAT)およびプラスミン―プラスミンインヒビター複合体(plasmin-plasmin inhibitor com-plex;PIC)を形成し,不活性化される.
凝固線溶系因子およびその阻止因子は流血中に大量に存在し,種々の臨床病態においては,ごく一部の凝固線溶系因子が活性化されるにすぎず,各種凝固線溶系因子や阻止因子の血中濃度を測定しても,極めて高度の活性化によりその消費が認められる場合を除いて,凝固線溶亢進状態を捉えることはできない.また,トロンビンやプラスミンなどの活性型因子の血中半減期は極めて短く,直接測定することは不可能である.
9)ヘパリンコファクターH
著者: 近藤信一 , 小出武比古
ページ範囲:P.128 - P.130
原理・測定意義
ヘパリンコファクターⅡは,正常血漿中に約90mg/l存在する分子量66,000の糖蛋白質で,主として肝で合成される.ヘパリンコファクターⅡの阻害特異性は非常に高く,血液凝固因子ではトロンビンのみを阻害する.しかし,反応部位のPl位のアミノ酸残基がロイシンであることから,キモトリプシンやカテプシンGに対しても阻害活性がある.アンチトロンビンと同様にヘパリンコファクターⅡのトロンビン阻害も種々のグリコサミノグリカン(GAG)存在下に著しく(1,000倍以上)促進されるが,アンチトロンビンよりも10倍高濃度のヘパリンを必要とする.しかし,デルマタン硫酸で促進されるのはヘパリンコファクターⅡだけであり,デルマタン硫酸の産生細胞が,血管平滑筋細胞や線維芽細胞であることから,ヘパリンコファクターⅡは,血管内よりも,むしろ血管外の結合組織において機能すると考えられている.デルマタン硫酸のこのような性質はアンチトロンビン共存下でのヘパリンコファクターⅡの特異的な活性測定に利用されている.
ヘパリンコファクターⅡ欠乏症の最初の報告は,1985年にTranら1)とSieら2)によってなされた.発端者は,それぞれ中大脳動脈血栓症と深部静脈血栓症を発症しているものの,Tranらの症例1)では,発端者の家族の1人に血栓性静脈炎の病歴があるほかは,ヘパリンコファクターⅡが同様に低値の家族は,いずれも無症状である.
10)組織因子
著者: 中村伸
ページ範囲:P.131 - P.134
はじめに
組織因子(tissue factor;TF)は図1に示すように,細胞表面に発現されるレセプター様因子で,このTFに血中のⅦ因子が特異的に結合することで,図2に示す凝固反応系のカスケードが駆動される.
最近,血中にTFの"遊離型"が存在することが明らかになり,血中TFを病態マーカーにしたDICなどの凝血疾患の予知・診断が注目されていた.しかしながら,血中TFレベルは微量で,血中TFをアッセイするためにはpgレベルの測定が可能な高感度ELISAが必要であった.さらに,この高感度化によって血中TFが測定できたとしても,それがprocoag-ulant活性のない可溶性型(s-TF)か,あるいは強いprocoagulant活性を示す膜結合性型(m-TF)か,いずれのタイプであるか明らかでない.特に,種々の疾患では血中TFが顕著に増大する症例がみられるが,そのとき,s-TFならびにm-TFを簡便,迅速に測定することができれば,信頼度の高い凝血疾患の診断・予知が可能となる.
11) APCレジスタンス
著者: 藤村博信 , 上林純一
ページ範囲:P.135 - P.137
はじめに
APCレジスタンスは前項で述べたように,発表当初,頻度の高さで非常に話題となった.地域や血栓症の診断基準による差はあるものの,その頻度は深部静脈血栓症患者の17.5~64%,一般正常人の2~7%にわたって存在すると報告された1~3).しかし,その原因とされる第V因子遺伝子の点突然変異が日本人では非常に少ないか,あるいは皆無であると考えられることから,日本人血栓症患者における先天性血栓性素因としてのAPCレジスタンスの測定は,当初ほどの重要性を持たされなくなったことは事実であろう.しかしある種の病態化におけるAPCレジスタンスの測定は,患者の血栓形成状態の把握に有用であるとも考えられており,初めにAPCレジスタンスの測定法を示した後,この点についても述べることにする.また,APCレジスタンスにおける第V因子の遺伝子異常の検出については別項で述べられるであろうためここでは触れない.
12)ループス・アンチコアグラント
著者: 滝正志 , 安室洋子
ページ範囲:P.138 - P.140
測定意義
ループス・アンチコアグラント(lupus anticoagu-lant;LA)とは個々の凝固因子活性を抑制することなく,リン脂質依存性の凝固反応を阻害する免疫グロブリンである.当初LAは出血傾向の原因として考えられたが,出血傾向をきたすことはまれで,逆に血栓症との強い関連が知られるようになり,抗リン脂質抗体症侯群という新しい疾患概念が臨床の場に定着した.LAや抗カルジオリピン抗体(本誌別項参照)などの抗リン脂質抗体は,血栓症,習慣性流産・胎児死亡,血小板減少などの臨床症状と強い関連がある抗体である.特に後天性の血栓症との関連で注目されている.
13)抗カルジオリピン抗体
著者: 松浦栄次 , 小池隆夫
ページ範囲:P.141 - P.145
はじめに
抗リン脂質抗体症候群とは,血栓症,習慣流産,および血小板減少などの症状を有し,かつ,抗カルジオリピン抗体やループスアンチコアグラントなどの抗リン脂質抗体が出現する自己免疫疾患である.近年,本疾患の患者血清中で検出されるいわゆる"抗リン脂質抗体"は,カルジオリピンなどのリン脂質そのものを認識しているのではなく,血液凝固反応の制御蛋白であるβ2-グリコプロテインI (β2-GPI)やプロトロンビンなどとリン脂質との複合体を認識していることが示された.特に,抗カルジオリピン抗体は,カルジオリピンと結合することで構造変化を起こしたβ2-GPIを認識する自己抗体,すなわち,抗β2-GPI抗体であると考えられている.本稿では,抗カルジオリピン抗体の特異性および測定法について解説する.
3.線溶系の検査
1) FDP
著者: 川合陽子
ページ範囲:P.147 - P.149
原理・測定意義
フィブリノゲン・フィブリン分解産物(fibrinogen/fibrin degradation products;FDP)は線溶系分子マーカーの代表的検査である.
FDPはフィブリノゲンまたはフィブリンが,線溶活性を有するプラスミンの作用により切断されることにより生成される,起源・分解程度の異なる分解産物の混合物の総称である.
2) FDP-Dダイマー
著者: 川合陽子
ページ範囲:P.152 - P.154
原理・測定意義
FDP-Dダイマーは,二次線溶をとらえる分子マーカーの代表的検査である.凝固過程の最終産物であるフィブリノゲンにトロンビンが作用するとフィブリンモノマーとなり,フィブリンモノマーは重合してフィブリンポリマーとなる.
フィブリンポリマーはトロンビンで活性された第XIII因子とカルシウムイオンの作用で架橋化され,強固な架橋化(安定化)フィブリンポリマーとなる.架橋化フィブリンにプラスミンが作用すると,高分子の中間分解産物を経て,DD/E複合体が生成される.最終的にはDダイマーとE分画となる(図1).すなわち,Dダイマーは,架橋化フィブリンにプラスミンが作用する二次線溶亢進時のみ生成され,生体内にフィブリン血栓が存在した証明となる.
3)プラスミノゲン
著者: 広沢信作
ページ範囲:P.155 - P.157
原理・測定意義
プラスミノゲン(plasminogen)は線容系の重要な因子であり,血栓症,出血,DICの患者で測定することが必要である.プラスミノゲンはプロテアーゼの前駆体(protease zymogen)であり,分子量92,000 Daの一本鎖糖蛋白質である.主に肝臓で産生される791個のアミノ酸より成る.5個のクリングルドメインを持ち,フィブリン溶解のためにフィブリンとの結合に重要なリジン結合部位(lysine binding site: LBS)を有している(図1).最初の3つのクリングルドメインがフィブリンとの結合に強く関与している.tissueplasminogen acitivator (tPA),ウロキナーゼ,スタフィロキナーゼ,ストレプトキナーゼなどにより,Arg 561-Val 562間が限定分解され,二本鎖のプラスミンに変換される.形成されたフィブリン上にプラスミノゲンとともにtPAも結合して活性化が効率よく進行することになる.アミノ末端の違いにより,Glu-プラスミノゲンとLys-プラスミノゲンとが存在し,それぞれ活性化されると,Glu-プラスミンとLys-プラスミンに変換する.Lys-プラスミノゲンはLys 77-Lys 78間がプラスミンによって限定分解を受けるためにみられるものである.Lys上プラスミノゲンのほうが,フィブリンとの親和性が高く,プラスミノゲンアクチベーターに対する反応性も高い1).
4) PIO
著者: 広沢信作
ページ範囲:P.158 - P.160
原理・測定意義
線溶系の活性化は,プラスミノゲンアクチベーター(plasminogen activator;PA)によりプラスミノゲン(plasminogen;PLG)がプラスミン(plasmin; PM)に変換されることにより起こる.血中に大量のPAが流入してフィブリノゲンが分解されたりする場合(一次線溶)やDICのように血管内にフィブリン血栓が生じたあとにフィブリンの分解が起こる場合(二次線溶)では線溶反応が亢進する.
このようにプラスミンはフィブリノゲンやフィブリンを分解する.二次線溶では産生されたフィブリンの分解が起こり,FDPが増加するが,一次線溶の亢進ではフィブリノゲンも分解を受けることになる.線溶系の主体はプラスミンの形成であるので,形成されたプラスミンを測定するのが最もよいのであるが,α2PIによって阻害を速やかに受けるために測定しにくい.血中のα2-プラスミンインヒビター(α2-plasmininhibitor;α2PI)により,即時的に阻害されるが,阻害の結果,プラスミンとα2-プラスミンインヒビターの複合体(plasmin-α2-plasmin inhibitor complex;PIC)が形成される1).
5) t-PA,ウロキナーゼ
著者: 上嶋繁 , 松尾理
ページ範囲:P.161 - P.164
t-PA (tissue-type plasminogen activator)
1.測定意義
血液線溶系は,凝固系の活性化によって最終的に形成された血栓を溶解する生理的メカニズムである.血栓の溶解は血栓の構成成分であるフィブリンがプラスミンによって分解されることにより生じる.プラスミンは通常,その前駆体で酵素活性を持たないプラスミノゲンとして血液中に存在しており,このプラスミノゲンはプラスミノゲンアクチベーター(plasminogenactivator; PA)によってプラスミンに活性化される.ヒト由来のPAとしては,t-PAとウロキナーゼ(uroki-nase:UKまたはurokinase-type PA:u-PA)が知られている.
したがって,血液線溶系の促進因子の1つである血液中のt-PA量,特にt-PA活性量を測定することにより,線溶能を評価することができる.すなわち,血液中のt-PA量は,線溶能の亢進に基づく出血傾向や線溶能の低下に基づく向血栓性の判別の指標となる.
6) PAI-1
著者: 三室淳
ページ範囲:P.165 - P.167
原理・測定意義
血管内に血栓が生ずると,血栓を溶解するメカニズムすなわち線溶系が働き出す.この血栓溶解が早すぎれば出血を,逆に遅すぎれば血栓の増大から血管の閉塞をきたす.線溶反応の調節に主要な役割を果たしているのがplasminogen activator inhibitor 1(PAI-1)である.凝固反応の結果フィブリン血栓が生じると,フィブリンにプラスミノゲンと組織型プラスミノゲンアクチベーター(tPA)が結合する.その結果,tPAによりプラスミノゲンがプラスミンに変換され,プラスミンがフィブリンを分解する(図1).
血栓溶解はPlgの活性化段階ではtPAのインヒビターであるPAI-1により,プラスミンが生じた後はプラスミンのインヒビターであるα2プラスミンインヒビター(α2PI)により制御調節されているが(図1),α2プラスミンインヒビターはフィブリンα鎖に結合しているため血栓溶解が起こり始める初期で血栓溶解を抑制する.しかし,血栓溶解がいったん始まると血栓溶解を遅らせる作用は弱く,プラスミンの作用を血栓上にとどめてプラスミンによる他の血漿蛋白や細胞膜蛋白の分解を防ぐことに主要な作用がある.先天性欠乏症や著明な肝機能障害がない限り,プラスミノゲンやα2プラスミンインヒビターの血液濃度はほぼ一定に保たれているのに対し,種々の刺激によりtPAやPAI-1の血液濃度は大きく変動する.
7) tPA/PA1-1複合体
著者: 三室淳
ページ範囲:P.168 - P.169
原理,測定意義
線溶系におけるtPAとPAI-1の意義については,PAI-1の項目で詳しく述べているので,併せて参照してほしい.tPAは,フィブリン分子の上でプラスミノゲンを活性化する特異性の高いセリン蛋白分解酵素であり(tPAの項目を参照),PAI-1はtPAを特異的に失活させるセリン蛋白分解酵素阻害因子である.PAI-1がtPAを失活させるために結合したもの(1:1で結合している)がtPA/PAI-1複合体(tPA/PAI-1)である.この状態ではtPAとPAI-1は強固に結合し,生理的状態では解離せず,tPA/PAI-1にはtPAの酵素活性もPAI-1のインヒビター活性もない.血栓溶解開始能は主にはtPAとPAI-1の動的なバランスによって決まってくる.
血漿tPA濃度は5~6ng/ml(約80 pmol/l)であるのに対し血漿PAI-1濃度は20~30 ng/ml (約400pmol/l)とPAI-1濃度はtPA濃度の約5倍である.
8) Bβフラグメント
著者: 山角健介 , 愛甲孝
ページ範囲:P.170 - P.171
検査の概説および測定の意義
フィブリノゲン(Fbg)は肝で生合成,分泌され,血漿中に200~400mg/dl存在する分子量約34万の糖蛋白質で,構造的には3種類のポリペプチド鎖Aα,Bβ,γがジスルフィド(S-S)結合して作られる化学的二量体(AαBβ-γ)2として存在する.機能的にはFbg→フィブリン(Fbn)転換により生理的・病的血栓や創傷治癒局所でのFbnマトリックスの主たる基材として重要な役割を演じる.
図1に示すように,生体内で凝固系が活性化され,生じたトロンビンによりFbgのAα鎖16-17位のアルギニン(Arg)-グリシン(Gly)ペプチド結合が限定分解される.その結果,Aα鎖アミノ基末端より2個のフィブリノペプチドA (FPA)が切断・放出され,Fbgはdes AA Fbnに転じ,2本鎖Fbn原線維の形成が始まる.その後トロンビンはさらにBβ鎖14-15位のArg-Gly結合も限定分解し,フィブリノペプチドB(FPBβ1-14)が放出されdes AA Fbnはdes AABBFbnに転じ,2本鎖Fbn原線維からFbn線維束・Fbn網が形成されていく.また,トロンビンは同時に凝固第ⅩⅢ因子を活性化し,Fbn分子間においてイソペプチド結合による堅い橋渡しをかけることになる.この架橋結合によりFbnは物理的・化学的に安定した形のものとなる.
9)Lp(a)
著者: 川合眞一 , 淺沼ゆう , 鏑木淳一
ページ範囲:P.173 - P.175
はじめに
Lp(a)[リポ蛋白(a),lipoprotein(a);LP(a)]は1963年にBerg1)により報告されたリポ蛋白である.当初は対象によって検出される例とされない例があるとされてきたが,より感度の高い測定法の開発によりほとんどの例に検出されることが明らかとなった.
このLp(a)は動脈硬化の独立した危険因子として注目されている2).すなわち,血清Lp(a)濃度が高いと心筋梗塞などの虚血性心疾患や脳血栓症などの動脈硬化病変の発症率が高いことが疫学的に示されてきたが,この間,Lp(a)が動脈硬化の発症に直接関与するか否かに関する証拠は明らかでなかった.1987年,McLeanら3)によりLp(a)を構成するアポリポ蛋白(a)[アポ(a)]の構造がプラスミノゲンと極めて類似していることが明らかにされたことにより,Lp(a)と線溶系との関係がにわかに脚光を浴びることになった.そこで本稿では,線溶系との関連を中心として,Lp(a)について概説したい.
4.血管内皮細胞の検査
1)トロンボモジュリン
著者: 井手章子 , 丸山征郎
ページ範囲:P.177 - P.180
はじめに
血管内皮細胞は強い抗血栓作用を有しているが,この抗血栓活性は主に4つの分子が担っている.すなわち,トロンボモジュリン(thrombomodulin;TM),プロスタサイクリン(PGI2),ヘパリン様分子,プラスミノゲンアクチベーターである医このうちTMはトロンビンと1:1で結合することにより本来凝固酵素であるトロンビンを抗凝固酵素に変換するという非常にユニークな作用を持つ1,2).すなわちTMと結合したトロンビンは血小板,フィブリノゲン,第Ⅴ,Ⅷ因子などに作用しなくなり,かわりにプロテインCの活性化能を1,000~2,000倍高めることによって抗凝固能を発揮する(図1).
2) TFPI
著者: 久米田幸介 , 加藤久雄
ページ範囲:P.181 - P.185
はじめに
TFPI (tissue factor pathway inhibitor)は3つのKunitz型阻害領域(K1, K2, K3)を持つプロテアーゼインヒビターで,K2によりXa因子と結合することによりXa因子インヒビターとしての機能を持つとともに,K1によりⅦa因子と結合して,組織因子(tissue factor; TF)による血液凝固の開始反応を阻害する機能を持っている.TFPIの産生部位は血管内皮細胞が主であり,血管内皮細胞上のプロテオグリカンと結合して存在し,血管壁を抗凝固状態に保っている.また,TFPIは血流中にも存在し,その存在様式は,LDLやHDLのアポ蛋白部分と結合しているリポ蛋白質結合型と,リポ蛋白質と結合していない遊離型(free form)とに大別される1).ヘパリンの静脈投与により血管内皮細胞上のTFPIがfree formとして血液中に遊離するので,その増加量により血管内皮細胞結合型TFPIを測定することが可能となる.TFPIの測定にTFPIの活性をTF/Ⅶ aによるX因子の活性化反応の阻害作用により,Xa因子の合成基質を用いて測定する方法2,3)が一般に使用されてきた.一方,TFPI抗原測定に関しては,最近TFPI活性との相関が高い遊離型TFPI測定キットが発売され,容易に血漿中のTFPI抗原量を測定することが可能になった.
3)フォンビルブランド因子
著者: 藤村吉博
ページ範囲:P.186 - P.190
はじめに
フォンビルブランド因子(vWF)は,出血時に露出した損傷血管内皮細胞下組織に血小板が粘着,そして凝集する一時止血において両者を接着させる分子糊として働く血漿糖蛋白質である.vWFの遺伝子は第12染色体上にあり,血管内皮細胞および骨髄巨核球で産生され,流血中ではMr275,000の単一サブユニットが,種々の程度に重合したMr0.5×106~20×106の不連続に分布するマルチマー型をとる.また,凝固Ⅷ因子安定化のキャリアー蛋白質として働くことから,血中では通常Ⅷ-vWF複合体として存在する.過去10年間にvWFサブユニット上に局在する各種ドメイン構造(図1)が大まかに把握されるようになり,これに伴ってvWFの先天異常に基づく出血性素因であるvon Willebrand病(vWD)も分子レベルで解明されるようになった1).
4)血漿P-セレクチン
著者: 半田誠
ページ範囲:P.191 - P.194
はじめに
P-セレクチン(PS)は血小板と血管内皮細胞の分泌顆粒であるα顆粒ならびにWeibel-Palade小体の膜に内在する膜糖蛋白で,それらの細胞が刺激を受け,脱顆粒とともにエクソサイトーシスにより原形質膜と融合して細胞表面に表出する.そして活性化され脱顆粒したそれらの細胞と白血球の結合を仲介する.PSと結合する白血球は好中球や単球以外に好酸球,好塩基球,NK細胞そしてTリンパ球の一部(メモリーTリンパ球など)が知られている.この結合は親和性が高いものの解離速度も速く,実際血液の流れに依存して可逆性となる.
この現象はあたかも白血球がスピードを緩め血管壁上を転がり流れてゆくように見えるためローリングと呼ばれる.ローリングは炎症性刺激などで活性化された血管内皮細胞のみならず活性化した血小板の集まりである血栓上でも観察される.ローリングに引き続き白血球は活性化され,インテグリンやイムノグロブリンスーパーファミリーを介した強固な接着反応(膠着)が起こり,細胞は接着部位に停止する.そして炎症細胞が血管外に遊出する.すなわち,PSは生体内での血小板と血管内皮細胞の活性化を反映するマーカーと考えられる.PSはあくまでも膜蛋白であるが,血漿中にもその可溶型抗原が存在しており,種々の疾患や病態でそのレベルが変化することが最近明らかとなってきた.
5) PGl2生成能・尿中2,3-dinor-6-keto-PGF1α
著者: 安藤泰彦
ページ範囲:P.195 - P.197
測定意義
プロスタサイクリン(PGI2)は,細胞膜のリン脂質から放出されたアラキドン酸より,プロスタグランジン(PG) G2,H2を経て,血管内皮細胞(以下,内皮細胞)のPGI2合成酵素によって合成される.PGI2は強力な血管の拡張作用と血小板機能抑制作用を有しており,血管内皮の持つ抗血栓性の主役を演じていると考えられている.
一方,内皮細胞とは対照的に,血小板においてはPGH2から,強力な血管収縮作用と血小板凝集作用を有するトロンボキサンA2(TxA2)が合成される.そして,虚血性心疾患や脳血栓の成因の一部に,PGI2とTxA2のバランスの異常が関与しているのではないか,との仮説が提唱されて注目を浴び1),さまざまな角度からの研究がなされてきた.
5.遺伝子検査
1) AT Ⅲ
著者: 増田治史 , 辻肇
ページ範囲:P.199 - P.202
はじめに
近年発展の著しい分子生物学的手法により,種々の疾患関連遺伝子が解明されている.先天性アンチトロンビンⅢ(AT Ⅲ)欠損症,先天性プロテインC欠損症などの先天性血栓性素因においても例外ではなく発症に関する遺伝子異常の詳細が次第に明らかにされている.
本稿においては,先天性血栓性素因として重要な先天性AT Ⅲ欠損症につき概説するとともに遺伝子診断法につき,自験例を含め紹介する.
2)プロテインC,プロテインS
著者: 山崎鶴夫
ページ範囲:P.203 - P.205
先天性プロテインC欠損症の遺伝子解析
遺伝子の構造
プロテインC (PC)遺伝子は第2染色体のq13-q14に局在し,全長は約11kb,9個のエクソンと8個のイントロンから構成され,第Ⅸ因子および第Ⅶ因子遺伝子に類似した構造を持っている.
3)プラスミノゲン
著者: 大江麻子 , 一瀬白帝
ページ範囲:P.206 - P.208
はじめに
プラスミノゲンは,血栓溶解の鍵となる酵素前駆体である.その遺伝子異常が血栓症の合併を契機に発見され,特に日本人に多いため注目されている.
プラスミノゲンは,プレアクチベーションペプチド,クリングル1~5,セリンプロテアーゼ領域などを含む791残基のアミノ酸からなり,その遺伝子は,第6染色体長腕26~27に位置し,全長約53kb,18個のイントロンで分割された19個のエクソンによってコードされている1)(図1).
4)Lp(a)
著者: 一瀬白帝
ページ範囲:P.209 - P.212
はじめに
アポリポ蛋白(a)[アポ(a)]は,リポ蛋白(a)[Lp(a)]に含まれる高分子蛋白質で,血栓溶解反応の主役を演じるプラスミノゲンと相同性がある(図1)1).Lp(a)は,生理的機能が不明なことをはじめ多くの謎に満ちたリポ蛋白質であるが2),近年,動脈硬化症の独立した危険因子として注目されるようになった.高リポ蛋白(a)[Lp(a)]血症とは,遺伝的に規定された血漿中のLp(a)濃度が25~30mg/dlを超える状態である.他の原因の高脂血症(高リポ蛋白血症)と同様,単に血漿中のLp(a)濃度が高いだけでは何ら臨床症状を示さないが,次第に動脈硬化を進展させ,比較的若年であるにもかかわらず心筋梗塞や脳梗塞を発症させる点で臨床的に重要である.
5)凝固第V因子1691G/A (506Arg/Gln)
著者: 座間猛 , 村田満
ページ範囲:P.213 - P.215
原理と測定意義
プロテインCは血漿中で非活性型の状態で存在し,血管内皮細胞上のトロンボモジュリンと結合したトロンビンとの接触によって抗凝固活性を持つ活性型プロテインC (activated protein C;APC)となり,凝固第Va因子および第Ⅷa因子を酵素分解しその凝固活性を失活させる.1993年,Dahlbackら1)は先天性血栓素因を有する家系内にAPCの抗凝固活性に抵抗性を示す病態を報告し,APCレジスタンスと命名した.その後,Bertinaら2)は凝固第V因子の点変異がAPCレジスタンスの原因の1つであると報告した.すなわち彼らは第Ⅴ因子遺伝子の1691GがAに変異する結果,506Arg⇒Gln変異を生じ,かかる部位がAPCの切断部位であることからAPCレジスタンスを示すと推測した(Leiden mutation).
欧米での報告によると,APCレジスタンスの頻度は深部静脈血栓症患者の20%,正常人の3~5%,さらに原因不明の先天性血栓素因を有する家系においては40~60%にみられるとされている.
6.画像診断
1)血小板シンチグラフィ
著者: 塚田理康 , 斉藤京子 , 村田啓
ページ範囲:P.216 - P.221
はじめに
動脈血栓の形成には血小板の生理的止血機能が主役を演じている.血管内皮細胞が傷害され剥離すると,内皮細胞下組織に血小板が粘着して活性化され,放出・凝集反応を起こす.同時に血小板膜表面でプロトロンビンの活性化が起こり,フィブリン糸が作られ血栓が形成される.静脈血栓形成の主役は血液凝固反応であり,血小板は形成された血栓に取り込まれるか,フィブリン糸に結合するといった消極的関与をしているにすぎない.
生体内の血栓形成を証明する検査法として,ドプラ超音波診断(impedance prethysmography, Nuclearmagnetic resonance; NMR),血管造影(indium; In-111)標識血小板あるいはTechnetium (Tc)-99m標識抗フィブリン抗体による血栓シンチグラフィ(シンチ)が用いられている.このうち,In-111標識血小板によるシンチ検査は,血栓や血管内皮細胞下組織への血小板の集積を示すもので,新鮮な血栓の存在のみを証明し,同時に血栓へ集積する血小板量の半定量も可能にしている.新鮮な血栓は梗塞を起こす危険性を持ち,血栓の新旧の鑑別および抗血小板療法の効果判定は,臨床上重要である.
2)カラードプラ
著者: 伊藤泰司 , 松本昌泰
ページ範囲:P.222 - P.226
はじめに
非侵襲的にしかもリアルタイムに血流状態および組織性状を調べることができる超音波検査は,心臓・腹部領域に広く使われている有用な方法である.さらに超音波機器の最近の進歩により,本法は脳血管障害の診断に対しても重要な位置を占めるようになってきている.本稿では,超音波検査の中で特に多大な血流情報を与えるカラードプラ法の原理について最初に述べるとともに,本法を利用した検査として脳血管領域に使用される頸部超音波断層法と経頭蓋超音波法について概説することにする.
3)サーモグラフィ
著者: 松岡瑛 , 芝田宏美 , 山下勉
ページ範囲:P.227 - P.230
はじめに
サーモグラフィ(熱画像)とは,生体面から放射される熱エネルギーを赤外線エネルギーとして感知測定し,得られる温度分布図を画像表示するもので1,2,3),画像表示された体表温分布図の差から,生体内の組織・代謝活性および循環動態などの変動を非侵襲的に検出する機能を有し,超音波・CTなどに代表される形態画像とは異なり,生理活性機能画像としての特徴を有する.生理活性機能は,安静時体表温のみならず,各種負荷試験(冷水・温水・運動・振動・薬剤)を行うことにより,生体の反応性を経時的に追跡し,潜在的な微細な変化をも捉えることが可能である.内在する因子の微細な変化4,5)は,特に四肢末梢で体表温の変動として容易に捉えられ,臨床上の応用が幅広く試みられているが,本文では主題に沿い,糖尿病を含めた動脈硬化性疾患による血管狭窄・塞栓などの末梢血流障害6,7)について記述する.
血栓性疾患と検査
1.冠動脈疾患
著者: 野村周三 , 本宮武司
ページ範囲:P.232 - P.235
はじめに
循環器診療における狭心症や心筋梗塞症といった虚血性心疾患の占める割合は大きい.急性心筋梗塞症や不安定狭心症の発症,および冠動脈血栓溶解療法後や経皮的冠動脈形成術(PTCA)後あるいは冠動脈バイパス手術後の急性閉塞や慢性期再狭窄に血小板および血栓が関与していることが強く示唆されている.本稿では急性心筋梗塞を中心に虚血性心疾患の各種病態と検査および血栓溶解療法や抗血小板療法の効果などについて概説する.
2.心腔内血栓
著者: 三橋武司 , 島田和幸
ページ範囲:P.236 - P.239
はじめに
心腔内血栓には心臓の中で発生する心内由来の血栓と,心臓外でできた血栓が血流に乗って心内に運ばれた心外由来の血栓がある.
まず心内由来の血栓であるが,心内膜(弁膜も含む)は抗血栓性を有し,心腔内の血流が停滞することなく保たれていれば血栓が生じることは少ない.よって心腔内に血栓が生じるのは心内膜が破壊された場合か,心腔内血流の著明な低下が生じる場合と考えられ,頻度としては後者が圧倒的に多い.前者の代表は人工弁置換術後や感染性心内膜炎であり,後者の代表としては僧房弁狭窄症や人工弁置換術後の左房内血栓や心筋症,心筋梗塞後の左室内血栓がある.
3.虚血性脳血管障害
著者: 浜野均 , 篠原幸人
ページ範囲:P.240 - P.244
はじめに
虚血性脳血管障害は,症候性の脳梗塞と一過性脳虚血発作(TIA),および近年注目されている無症候性脳梗塞に分けられる.これらの中で,病態や原因が比較的容易に理解できる症例は,その診断において血小板・凝固線溶系の特別な検査を必ずしも必要としない.しかし,その病態が通常の脳卒中危険因子では説明できない,特に若年発症脳梗塞を代表とする症例においては,その診断に特殊な検査を必要とする.また,その病態に応じて抗血栓療法(抗血小板療法,抗凝固療法,血栓溶解療法など)が行われることも多く,そのモニターの1つとして血小板や凝固線溶系検査を要する場合が少なくない.本稿では,虚血性脳血管障害の病態と血小板・凝固線溶系検査に関して述べたい.
4.頸動脈内血栓
著者: 内山真一郎 , 山崎昌子 , 橋口孝子
ページ範囲:P.245 - P.250
はじめに
脳血管障害の新分類NINDS-Ⅲ1)によれば,脳梗塞はアテローム血栓性脳梗塞(atherothromboticcerebral infarction; ATCI),心原性脳塞栓症(car-dioembolic cerebral infarction; CECI),ラクナ梗塞(lacunar infarction; LACI)の3臨床概念に分類される.このうち,ATCIやその前段階と考えられる一過性脳虚血発作(TIA)は頸部や頭蓋内の主幹動脈に生じた粥腫斑(atheromatous plaque)に形成された血小板血栓に起因する血小板依存性疾患病態(plateletdependent disease state)であり,再発予防には抗血小板療法の適応がある2~5).
本稿では,虚血性脳血管障害における頸動脈病変と血小板活性化所見について筆者らの成績を中心に紹介し,血栓準備状態(prothrombotic state)の診断と抗血小板療法の効果判定における各種血小板機能検査法の有用性について述べてみたい.
5.深部静脈血栓症
著者: 折井正博
ページ範囲:P.251 - P.256
はじめに
血管外科領域の成書あるいは教科書的な入門書でも深部静脈血栓症の項を見れば,その診断に血液凝固線溶系のパラメーターのチェックが重要であると記載されている.しかし何がどの程度上昇したら,あるいは低下したら静脈血栓を疑うべきなのか具体的な数値を挙げているものはまずない.また文献的にも臨床例で静脈血栓症の臨床像と凝固線溶系の変化との関係を論じた報告はまれである.事実,臨床医の多くは静脈血栓症の診断・治療において血液検査成績にはあまり注意を払っていないというのが現状であろう.筆者も血管外科を専門とする臨床医であり,血液凝固学的知識は乏しく,次々と測定可能となる新しい分子マーカーの登場には目を回しているわけであるが,多くの静脈血栓症の患者に接し治療してきた立場から,現時点でどのような検査が実際に役だっているのか自験例のデータに基づいて明らかにしたい.なお,血液検査が診断上あるいは治療の効果判定に特に有用なのは血栓症の急性期なので,以下急性深部静脈血栓症に関し言及する.
6.閉塞性動脈硬化症
著者: 新本春夫 , 重松宏
ページ範囲:P.257 - P.261
はじめに
閉塞性動脈硬化症(以下ASO)は全身の動脈硬化の一部分症として四肢の慢性的な狭窄や閉塞をきたす疾患であり,種々の虚血症状が出現する.主たる病態としては,動脈壁における粥状硬化とともに血栓形成が挙げられ,血液の過凝固状態が深く関与している.ASOにおける血栓形成の機序は,粥状硬化に起因する血管内腔狭窄部位に生じるいわゆる2次性血栓症であり,狭窄部位において乱流が生じるために血小板にずり応力(shear stress)がかかり,血小板の活性化や凝集による血小板血栓(白色血栓)の形成に引き続き,血流のうっ滞に伴う凝固系の活性化による赤色血栓が形成される.さらに,こうした血栓が線溶系を2次的に亢進させると考えられるが,病状や病態に応じて凝固線溶機能は複雑に修飾される.
7.DIC
著者: 櫻川信男
ページ範囲:P.263 - P.266
はじめに
DIC (disseminated intravascular coagulation syn-drome)は先行する基礎疾患(別項参照)が存在し,それに起因する凝血系活性化の"引き金物質"が凝固・線溶系,血小板系および血管系のすべてにわたって活性化を惹起することに起因する血栓形成による重要臓器障害と凝血系因子の消費による減少がもたらす出血を伴う病態である.したがって表1,図1に示すごとく多くの凝血系活性化を示す要因(因子群と分子マーカー)がそれぞれ特異の意味を持って診断に使用されるが,それらの特性は上記の"引き金物質"によって決定される.例えば白血病や固型癌ではそれらの病的細胞に含有される組織因子(tissue factor; TF)による凝固活性化;急性前骨髄球性白血病では組織プラスミノゲン・アクチベーター(tissue plasminogenactivator; t-PA)による線溶系活性化;重症感染症ではエンドトキシンによる血管内皮や単球からのTF放出やインターロイキン1による血管内皮細胞障害などが複合作用を及ぼして終局的にトロンビンやプラスミンが出現し,ほかに血小板も刺激を受けて血栓形成をもたらす.この過程では凝血系酵素や補酵素および阻害要因は相互に反応して限定分解を受けて消費されて減少し,その結果として分解産物やペプタイドあるいは阻害物質の複合体が出現して,いわゆる"分子マーカー"の測定意義が生ずる.
8.TTP/HUS
著者: 藤村欣吾
ページ範囲:P.267 - P.269
TTPの病態1)
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)や溶血性尿毒症症候群(HUS)は互いに類似した稀な疾患であり,米国では10万人当たり0.1といわれている.
これらの疾患は微小血管症性溶血性貧血,血小板減少症,腎機能障害,発熱,動揺する脳神経精神症状の5徴を特徴とする.これら臨床症状は血管内皮細胞障害の結果,微小循環系に血小板を主体とした血栓が形成されることによって生ずると解釈されている.
血栓症治療薬とモニター検査
1.抗血小板剤
著者: 中井桂司 , 長屋章三郎 , 西川政勝
ページ範囲:P.272 - P.275
はじめに
現在,血栓発生の際に血小板が果たす役割の重要性が広く認識され,また種々の新しい抗血小板薬が登場し,日常の臨床においても抗血小板療法が積極的に実施されるようになっている.しかし,種々の血栓性疾患に対して血小板が血栓生成にどのような役割を果たしているか,そして抗血小板療法を実施するに当たり,多様な血小板機能の何を抑制すべきか必ずしも明らかではない.
以前から,欧米において虚血性心疾患や脳梗塞などの血栓症に対するさまざまな抗血小板剤の効果について,大規模臨床調査が行われ抗血小板療法の再発予防に対する有用性が確認されている.しかし,対象症例やその病態,投与薬剤とその投与量・投与方法,投与効果の判定方法がまちまちであり,多くの問題点を抱えていると考えられる.薬剤選択の問題もさることながら,これらの大規模臨床調査においてさえ,抗血小板剤の投与が血小板機能などのモニタリング検査を行うことなく施行されているのが現状である.それにはいくつかの現実的な問題もあるが,投与によって実際にどの血小板機能がどの程度抑制されているのか,的確に把握する必要があると思われる.高血圧症や高コレステロール血症治療薬の投与の際には必ずモニタリングがなされ,投与効果の判定さらには投与量の調節,他の薬剤への変更や併用が行われている.また,薬物動態における個体差の問題も無視できない.さらに,抗血小板剤の投与は必然的に出血という副作用を招く恐れもある.
2.ヘパリン
著者: 青崎正彦 , 上塚芳郎
ページ範囲:P.276 - P.282
はじめに
ヘパリンは血栓症の治療・予防に現在広く用いられている抗凝固薬である.ヘパリンは経口抗凝固薬のワーファリンと比べると,その効果は速効性である特徴を有するので,血栓症の急性期や即時的な抗凝固効果を要する場合に不可欠の薬剤である.最近では低分子量ヘパリンによる治療も行われるようになった.ヘパリンの効果を発輝し,出血の合併を防ぐために,活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)などによる凝固能のモニターが必要である.
3.ワルファリン
著者: 中川雅夫
ページ範囲:P.283 - P.286
はじめに
近年,血栓性疾患の増加に伴い,抗血栓療法が注目を集めている.また,血栓症のみならず種々の疾患の病態形成にも血液凝固の関与が指摘されており,血栓症治療薬に関心が払われている.こうした中で新しい血栓症治療薬の開発も進められている.ワルファリンは古くから用いられている経口抗凝固薬であるが,本剤の主たる薬理作用が血液凝固機序の阻害にあるところから,投薬によって患者の血液凝固能の低下や易出血性がもたらされる.したがって,ワルファリンの投与時には副作用としての出血傾向がもたらされる可能性がある.それゆえ,本剤の臨床応用にあたっては本剤の作用機序に関する理解を深めるとともに,患者の病態を厳重に管理する必要がある.
本稿ではワルファリンの薬理作用と出血副作用を防止する目的で行うモニター検査について概説することにする.
4.t-PA,ウロキナーゼ
著者: 後藤信哉 , 半田俊之介
ページ範囲:P.287 - P.291
はじめに
組織に酸素を供給する動脈が血栓性に閉塞して虚血あるいは壊死の危険に曝されたとき,血栓による閉塞を解除して組織への血液供給を再開する手段として血栓溶解療法が選択される.冠状動脈の血栓性閉塞による急性心筋梗塞症に対してウロキナーゼ(uro-kinase),組織plasminogen activator (t-PA)などの線溶薬による血栓溶解療法を施行すると,死亡率の減少1,2),左室機能の改善3)など延命につながる効果を期待できることが複数の大規模臨床研究により明確に示されている.
最近では,米国の一部の施設を中心として,脳梗塞症においても血栓溶解療法により神経症状の発現を抑制し得るとの報告4)もみられ,肺塞栓症5),下肢静脈血栓症などと併せて血栓溶解療法の適応は拡大する傾向にある.血栓溶解療法は,閉塞血栓の溶解,組織灌流の再開という明確な臨床的有効性を有する一方,止血血栓の溶解による出血性合併症という重篤な合併症の可能性を常に内在している.出血というnegativeな効果を最小にして,positiveな効果を最大に引き出すためには,血栓溶解療法に伴う線溶動態の変化のみならず,凝固,血小板機能を含めた生体内の血栓形成と溶解のダイナミックなバランスに及ぼす効果を慎重にモニタリング(monitoring)し,必要に応じて適切な対策を立てることが必須となる.
ミニ情報
遺伝子組換え型トロンボモジュリン
著者: 広沢信作
ページ範囲:P.28 - P.28
トロンボモジュリン(thrombomodulin;TM)は,血管内皮細胞上に存在するトロンビン受容体である.トロンビンの活性を阻害するとともに,プロテインCの活性化を促進する.活性化プロテインCは,活性化血液凝固第Ⅴ,Ⅷ因子を不活化する.TMは血漿中にも検出され,可溶性TMと呼ばれている.遺伝子組換え技術により細胞内と膜ドメインを欠いて,細胞外のドメインのみを有するTM遺伝子が作製されている.TMを含むベクターをCHO細胞に導入して,発現させ,培養上清から遺伝子組換え型のTMを精製している.トロンビンとの結合に必要な領域は,EGF様ドメインの4,5,6番目であり,この部分は含んでいる.液相のトロンビンと結合してプロテインCを活性化させる.また,結合したトロンビンをアンチトロンビン-Ⅲに渡した後,TMは再利用される.投与後の血漿中の半減期T1/2αは約4時間,T1/2βは約20時間である.遺伝子組換え型TMが播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascularcoagulation;DIC)を中心に,現在臨床治験が行われており,白血病などのDICに良い効果が確認されてきている.
ヘマトクリットと止血・血栓
著者: 半田誠
ページ範囲:P.41 - P.41
以前から脱水などの急激な血液濃縮は心筋梗塞や脳梗塞などの急性血栓症の誘発原因ではないかと信じられていた.実際,真性多血症患者においては血栓症の合併率が高いことが知られ,術後の下肢深部静脈血栓症は瀉血によりヘマトクリット値(Ht)を下げることでその発生率が低下すること,さらに赤血球造血因子であるリコンビナントエリスロポイエチン(EPO)を使用した慢性透析患者において貧血の改善とともにシャント部位の狭窄などの血栓症の発症が増加する事実は,Ht増加が血栓症発症の原因となりうる可能性を示唆するものである1).
一方,貧血患者における止血機能の低下が以前より指摘されていた.慢性透析患者では出血時間が延長し,血小板粘着能(血小板停滞率)が低下しているが,輪血やEPO投与でHtが改善されるとともにそれらの検査値も正常化の方向に向かう2).
トロンボモジュリン欠損症
著者: 丸山征郎
ページ範囲:P.60 - P.60
トロンボモジュリン(thrombomodulin; TM)は血管内皮細胞上でトロンビンを凝固酵素から抗凝固酵素へと変換する1本鎖の糖蛋白である.すなわち血中で生じたトロンビンは強い親和性でTMと結合するが,TMと結合したトロンビンはフィブリノゲン→フィブリン転化活性,血小板活性化能,第Ⅴ,Ⅷ因子活性化能が消失し,逆にプロテインC (PC)活性化能が約1,000倍以上に増強される.活性化PCは活性化第Ⅴ,Ⅷ因子を分解し凝固阻害的に働く.したがってTMは血管内で血栓が生ずるのを防いでいる膜蛋白である.
したがってこのTMが先天的または後天的に減少すると血栓傾向となるのは容易に予想されることである.後天的にはエンドトキシン,IL-1,TNFがTMの発現を抑制する.これは感染症や敗血症,悪性腫瘍時のDICや血栓傾向の原因の1つと考えられる.またホモチスチン,酸化変性LDL,糖化蛋白などもTMの発現を抑制する.
レオロジーと血管内皮細胞
著者: 川合陽子
ページ範囲:P.64 - P.64
血管内皮細胞は絶えず血流にさらされ,血流が内皮細胞の機能維持に重要な役割を演じていることが近年明らかとなった.血流が内皮細胞に及ぼす血行力学的因子はずり応力"shear stress;SS"と呼ばれ,血流速度(v)と流れからの距離(1)で規定される速度勾配(dv/dl)と血液の粘性(μ)の両者によって生ずる.通常大動脈では10~20dynes/cm2,細小動脈では20dynes/cm2,静脈では1.5~6dynes/cm2のずり応力が内皮細胞に負荷されていると考えられている.かかるずり応力は内皮細胞の形態に影響を与え,ずり応力を負荷された内皮細胞は,血流の方向に紡錘状に配向変化するとともにストレスファイバーを形成する.
ずり応力は内皮細胞の機能にも影響を与え,透過性・ピノサイトーシス・リポプロテインの取り込みの亢進の他,血管のトーヌスの調節にも重要な働きをしており,平滑筋を弛緩させ血管を拡張する血管内皮由来血管拡張物質(EDRF・NO)やPGI 2を,また血管収縮を起こすエンドセリン(ET-1)などの産生や放出を調節している.
PAI-2
著者: 新谷憲治
ページ範囲:P.72 - P.72
プラスミノゲンアクチベーターインヒビター2(PAI-2)は,Kawanoらにより胎盤中に発見されたプラスミノゲンアクチベーター(PA)に対する阻害物質(PAI)の1つで,現在では,単球,マクロファージ,ケラチノサイト,血管内皮細胞,線維芽細胞など多くの細胞に発現されていることが知られている.
PAI-2は健康成人の血中に証明されず,PAI-Iに比べて生理的意義が乏しいとされてきたが,最近PAI-Iが酸化されると,そのPAI活性を失うのに反し,PAI-2は酸化抵抗性であることが報告され,PAI-2が炎症や免疫現象の反応の場での線溶制御に中心的役割を演じていると推定される.糖鎖を有する分子量60kDaのものと糖鎖のない47kDaのPAI-2が,U-937細胞より鈍化された.PAI-2は,Metから始まり,疎水性に富んだシグナルペチドを保持したまま成熟型となる特異な蛋白でchicken ovalbuminに最も近いホモロジーを示すserine protease in-hibitors(serpins)の一員である.PAI-2による,マクロファージ,好中球の機能を抑制作用,さらに移植片の拒絶反応の抑制作用なども観察されている.
遺伝子組換え第IX因子
著者: 高松純樹
ページ範囲:P.112 - P.112
血友病B治療には現在までヒト血液由来の製剤を用いた治療がなされてきている.近年では従来のプロトロンビン複合体から,高度に純化精製された第Ⅸ因子製剤が使用されるようになってきており,大量投与による血栓症の副作用は減少しているものの,ヒト由来のウイルス感染症を完全に否定することはできない.
そこで遺伝子組換えによる第Ⅸ因子製剤の開発が進められてきている.本製剤はChinese HamsterOvary(CHO)由来細胞にヒト第IX因子遺伝子を導入して発現させた蛋白を濃縮したもので,用いたCHO由来細胞は既に20年以上種々の遺伝子組換え蛋白を発現させた実績があり,現在までに1億人以上の患者に種々の蛋白が投与されているがウイルス感染の報告はない.さらに現在報告されている製剤ではその製造過程および製品中にもヒト,または動物由来の蛋白は一切使用されておらずヒト,動物由来のウイルス感染の可能性はほぼないといえよう.生化学的には分子量55,000で血液由来の第IX因子とアミノ酸構造.post-translational modificationの差異は認められていない.
網血小板測定
著者: 武内恵
ページ範囲:P.116 - P.116
網血小板の歴史
1969年,IngramおよびCoopersmithは,末梢血をnew methylene blueで超生体染色し,顕微鏡下で血小板内に明瞭に濃染する網状物質を見いだし,reticulated platelets (網血小板)と名付けた.網血小板は,赤血球の網赤血球に相当すると考えられ,骨髄における血小板生成を反映するものとした.しかし,同定手技の煩雑さから,その測定は普及するには至らなかった.ごく最近,フローサイトメトリーを用いた網血小板の報告がなされ,比較的簡単に測定可能で有用と思われることから,注目を集めている.
出血時間創からの出血パターン解析
著者: 高見秀樹
ページ範囲:P.130 - P.130
出血時間検査は簡便で,かつ生理的条件下で総合的止血機能をみることのできる唯一のin vivoの検査である.筆者らは,出血時間検査の精度を向上させ,出血時間を秒のオーダーで測定すると同時に総出血量,出血速度および出血パターンが測定可能な定量的出血時間測定装置を開発し,その有用性を検討している.健常者の出血パターンはほぼ一定で出血時間創作製直後より徐々に出血量の増加を認め,1~3分後ピークとなった後漸減して止血に至るものである.出血時間延長例の出血パターンは症例により異なることが明らかとなり,図1の4型に分類した.
Ⅰ型は出血のピーク後の出血量の減少が正常パターンに比して緩やかであるもの,Ⅱ型は出血のピークの後も出血の減少傾向がないもの,Ⅲ型は出血のピーク後の出血の減少は正常パターンに類似しているものの少量の出血が持続するもの,Ⅳ型は出血パターンに一定の傾向がなく出血量の増減が顕著で,止血傾向があるものの再出血がみられるものである.
好中球エラスターゼと血液凝固
著者: 岡嶋研二
ページ範囲:P.134 - P.134
好中球エラスターゼ(granulocyte elastase;GE)は,分子量30,000の好中球のアズール好性顆粒に含まれる蛋白分解酵素で,好中球により貪食された異物の分解に重要な役割を担っている.本酵素の基質特異性は低く,in vitroでは,エラスチンやコラーゲンをはじめ,多くの生体構成成分が分解される.血液凝固線溶系に関連する基質としては,アンチトロンビンIII(AT Ⅲ),α2-プラスミンインヒビターおよびPAI-1などが知られている.GEは,in vitroで,凝固の活性化に伴い細胞外へ放出されることが示されており,DICなどの全身の凝固異常においても,その病態形成に関与している可能性がある.
GEは血管内皮細胞の構築性を傷害することが知られているが,筆者らの解析から,GEは重症感染症に伴うDICで上昇し,特に肺傷害症例で高値であった.これらの事実は,重症感染症に伴うDICで,GEの作用部位は,活性化好中球が集積する肺の血管内皮細胞である可能性を示す.
トロンボポエチンによる血小板活性化
著者: 小田淳
ページ範囲:P.137 - P.137
最近,巨核球増殖,分化誘導因子であるトロンボポエチン(TPO)のcDNAが複数のグループによりクローニングされ,TPOにin vivo,in vitroにおける巨核球増殖促進,分化誘導,血小板数増多作用があることが判明している.既に,化学療法後の血小板減少症の治療目的で,各国で第Ⅰ,Ⅱ相試験が進行している.
しかし,TPOが受容体に結合した後の細胞内情報伝達経路の詳細は不明である.筆者らはヒト血小板を用いてTPOがさまざまな刺激下における血小板凝集を亢進させること1).TPO刺激の下流にJak 2系およびShc-Grb 2系の2つの情報伝達系が関与することを証明した2).さらにJak 2系の下流にあるとされるStat蛋白(転写因子)が血小板に存在することと,そのうちStat 3とStat 5がTPO刺激下にチロシンリン酸化されることを証明した3).また,c-Cb1蛋白が血小板にあることを初めて証明し,血小板およびc-Mpl (TPOの受容体)発現FDCP-2細胞においてTPO刺激下にチロシンリン酸化されることを認めた.さらに,c-Mplのtruncation mutantを発現したFDCP-2細胞を用いて,c-Cbl蛋白チロシンリン酸化が細胞増殖に必須ではないことを証明した4).
Mg2+依存性血液凝固系
著者: 関屋富士男
ページ範囲:P.157 - P.157
血液凝固にCa2+(血漿濃度;遊離イオンとして約1.2mmol/1)が必須であることは周知である.同じアルカリ土類金属であるMg2+も血漿中に豊富に(遊離イオンとして約0.5mmol/l)存在するが,その凝固に対する作用は不明であった.筆者らは最近,多くのビタミンK依存性凝固因子のうちでもIX因子に特異的に,Ca2+のみならずMg2+もその本来の高次構造と生理活性の維持に重要であることを見いだした1).Ca2+のみの場合でもⅨ因子は機能しうる.しかしそこに生理的濃度のMg2+を添加すると,高次構造は明瞭に変化し1),生物活性は大幅に亢進する2).Ⅶ a因子・組織因子複合体(Ⅶ a・TF)によるⅨ因子の活性化反応(基質としてのⅨ因子),およびⅨa・Ⅷ aによるⅩ因子の活性化反応(酵素としてのⅩⅠ a因子)を検討したところ,いずれの反応もMg2+の添加によって反応速度が数倍上昇した2).さらに透析した血漿を用いて凝固時間へのMg2+再添加の影響を観察したが,Ⅸ因子を介する凝固反応の場合はすべて明らかな短縮を認めた2).
現在,いわゆる内因系経路はその臨床検査的意義はさておき生理的には意味がないこと,TFにより開始される凝固においてもⅨ因子が活性化されることが認められている.
ヒルジンとその誘導体
著者: 新谷憲治
ページ範囲:P.190 - P.190
ヒルジンは,医用ヒル(Hirudo medicinallis)の唾液から分離された65個のアミノ酸からなる蛋白で,in vitro,in vivoのいずれにおいても,強力にトロンビンの活性部位および基質認識部位の2か所に結合して,特異的にトロンビン活性を抑制する1).最近血中でより安定なポリエチレングリコール処理リコンビナントヒルジンやトロンビンの活性中心への結合能は弱いがトロンビン基質認識部位へ結合して抗トロンビン活性を発揮するヒルローグ(hirulog)が開発され,動物実験で,静脈内投与された場合,比較的低濃度で静脈血栓の形成を抑制し,血管内凝固を阻止することが示され,さらに,高濃度で血小板依存性の血栓形成をも阻害する.
米国での組織プラスミノゲンアクチベーターとアスピリンを併用して治療した急性心筋梗塞患者246名のphase Ⅱの臨床治験の成績では,ヒルローグの障害血管の再閉塞防止効果が,ヘパリンより優れていることが示されている.
抗GPIIb/IIIaアンタゴニスト
著者: 小田淳
ページ範囲:P.194 - P.194
抗GPIIb/IIIaアンタゴニストは現在導入されつつある強力な抗血小板薬の一群である.血小板凝集はGPIIb/IIIaがフィブリノゲンなどと結合することにより起こるのであるから,GPIIb/IIIaをブロックすることは血栓症の治療に有用である.副作用は出血である.体内の抗GPIIb/IIIaアンタゴニストの効果の簡便なモニタリング法はex vivoにおける血小板凝集である.GPIIb/IIIaアンタゴニストは日本でも現在臨床試験が進行中であり臨床検査学上も重要トピックである.主要なGPIIb/IIIaアンタゴニストを掲げ簡潔に説明する.
DICと炎症性サイトカイン
著者: 岡嶋研二
ページ範囲:P.202 - P.202
血液凝固線溶反応は,血管内皮傷害の修復に重要である.凝固系は,血管内皮細胞傷害により流入した組織因子と血液との接触(凝固外因系の活性化),もしくは血管内皮細胞剥離後に出現する異物表面と血液との接触(凝固内因系の活性化)によってその引き金がひかれる.これらの現象は,見方を変えれば,血管内皮細胞傷害に伴う異物の侵入に対して,凝固外因系の活性化により形成されるフィブリンが物理的障壁として機能し,また凝固内因系の活性化の結果,生成するカリクレインやF.XIIaにより活性化される好中球から放出される種々の炎症性メディエーターが化学的障壁として機能しているとも考えられる.
すなわち,凝固反応も生体防御という観点から考えれば,炎症反応の一部であるといえる.この関連は,特に"全身の炎症"とも形容できる敗血症において顕著である.この炎症と凝固を結び付ける物質が,サイトカインである.これらの中でも,腫瘍壊死因子(tumor necrosis factor-α;TNF-α)やインターロイキン-1β(IL-1β)は,エンドトキシンによって活性化された単球より産生され,好中球と血管内皮細胞を活性化し,活性化好中球による血管内皮細胞傷害を惹起するのみならず,血管内皮細胞表面の組織因子の発現を増強させ,抗凝固物質であるトロンボモジュリンやヘパリン様物質の発現を正常の約半分に減少させる.
ヒスチジンリッチグリコプロテイン
著者: 東博之
ページ範囲:P.221 - P.221
ヒスチジンリッチグリコプロテイン(histidine-richglycoprotein;HRG)は,ヒスチジンおよびプロリン残基に富む507アミノ酸残基から成る分子量81kDaの一本鎖糖蛋白質で,血液中,巨核球および血小板内に存在する.その血中濃度は9.2~12.5mg/dlであり肝で合成,分泌されている.HRGはin vitroではヘパリン結合能,フィブリノゲン(フィブリン)やトロンボスポンジンなどとの相互作用,活性化血小板との結合能,種々の二価金属イオンやヘムとの結合能,赤血球とTリンパ球間の自己ロゼット形成阻害能,Tリンパ球との結合能,ヘパリンの血管平滑筋増殖阻害作用の中和能などの多彩な作用を持つ多機能蛋白質の1つと考えられている.
HRGのin vivoにおける働きはまだ不明な点が多いが,その血中濃度の増加と血栓症との関連が報告され,プラスミノゲンと結合することにより線溶活性を低下させることが血栓症発症の機序と考えられている.しかし,HRGの欠乏症や異常症は発見されておらず,HRGのin vivoにおける意義は不明であったが,1993年,筆者らは右横静脈洞血栓症で発症した世界初の先天性HRG欠乏症1家系を見出し1),HRGのin vivoにおける生理機能について解析を行った2).その結果,発端者の血小板数,出血時間,プロトロンビン時間,活性化部分トロンボプラスチン時間などの凝血学的検査はすべて正常であった.
ビトロネクチンと線溶系
著者: 朝倉伸司
ページ範囲:P.239 - P.239
ビトロネクチン(VN)は,本来細胞接着仲展因子としての役割を担っているが,補体蛋白質のS―プロテインと同一であることが判明した.さらには凝固系のトロンビン/アンチトロンビンⅢ(T-AT)複合体を含め,広く,トロンビン/セリンプロテアーゼインヒビター(SERPIN)複合体と結合し,スカベンジャーとしての役割や,線溶系のSERPINであるプラスミノゲンアクチベーターインヒビター1(PAI-1)と結合し,組織に限局させ,線溶活性の制御に関与していると考えられている.
最近ではさらに,PAI-1のみでなく,線溶因子のほとんどすべてと結合し,そのモジュレーターとしての役割がクローズアップされてきつつある.VNの特徴的なことは,血中に存在するnative-form (nVN)とマトリックスへ吸着やurea処理して得られるactive-form (aVN)とは構造的に大変異なっており,aVNはヘパリン結合ドメイン(HBD)やソマトメジンBドメイン(SBD)が露呈され,ヘパリン結合活性やVN多量体(VN-multimers)形成を促進させる.VN-multimersは強力なヘパリン結合活性を有し,血小板凝集にも関与.しており,vWF-multimersと近似した性格を有すると推定される.
偽性血小板減少症
著者: 加藤淳
ページ範囲:P.244 - P.244
未梢血中の血小板数を正確に知るには,抗凝固剤なしで採血し,直ちに血算盤に添加後,位相差顕微鏡下で算定する方法が,最も信頼性が高いが,今日ではEDTA (エチレンジアミン四酢酸)添加末梢血を自動血球分析機に注入し測定する方法が一般的である.偽性血小板減少症(pseudothrombocytopenia;PTP)とは,抗凝固剤添加,巨大血小板,寒冷凝集素の存在下で,血小板数が実際よりも少なく測定される現象を指す.実際には抗凝固剤としてEDTAが用いられることが多いので,臨床的にはEDTAによるPTPが問題となることが多い(EDTA添加末梢血検体の0.06~0.13%).その原因の多くは血小板凝集であり,ごくまれに(約15万人に1人),白血球の細胞表面に血小板が接着する血小板衛星現象(plateletsattelitism)がみられる.
PTPは,年齢,性差,疾患特異性はなく,健常人でもみられるが,臨床的に頻度の高い特発性血小板減少性紫斑病(ITP)を迅速かつ正確に診断するうえで無視できない現象である.EDTAによる血小板凝集は採血後室温で,5分から数時間の間生じ,血小板凝集塊は必ずしも自動血球分析機によって検出されないので,同時に血液塗抹標本を観察することが重要である.またPTPが疑われる場合は,直接算定法により採血後直ちに血小板数を確認する必要がある.
活性化血小板の検出法
著者: 野村昌作
ページ範囲:P.266 - P.266
血栓傾向における最も初期の反応は,血小板の活性化である.近年,血小板機能に関する分子機構の研究が進み,血小板膜糖蛋白上の受容体と各種粘着性蛋白との結合のメカニズムについては,ほぼ全貌が解明された.
最近は,これら血小板の活性化に関連した膜糖蛋白の構造変化や血小板に由来する内因性因子を血小板系分子マーカーとして,血栓傾向の診断に利用しつつある.
糖化蛋白と血栓症
著者: 丸山征郎
ページ範囲:P.270 - P.270
糖尿病患者は末梢動脈閉塞症,虚血性心疾患,脳梗塞の最大のハイリスクグループである.この原因としては,糖尿病患者の動脈硬化や高脂血症,高血圧などが背景にあるが,最近糖化蛋白がにわかにクローズアップされてきた.
蛋白と糖を混合し,37℃に放置すると非酵素的に蛋白に糖が結合する.この反応はメイラード反応あるいはグリケーションと呼ばれるが(図1),最終的には後期段階生成物(advanced glycation endoproducts;AGE)となる.血糖コントロールのマーカーとして日常診療で使われているヘモグロビンA1c,フルクトサミンなどは可逆的糖化蛋白で,アマドリ型である.高血糖が長期に続くと生体内で寿命の長い蛋白類は糖化される.例えば上記のヘモグロビンのほかに水晶体クリスタリン,アルブミン,アンチトロンビンIII,フィブリノゲン,LDL,HDL,インスリン,コラーゲン,ケラチン,ミエリン,赤血球スペクトリンなどが糖化されると報告されている.そして実際アテローム硬化の部位にこれらの糖化蛋白が沈着しているという報告もある.
血栓症と連関する遺伝子ポリモルフィズム
著者: 村田満 , 松原由美子
ページ範囲:P.292 - P.293
高血圧,糖尿病,高脂血症などは動脈硬化の代表的危険因子であるが,一般に多因子遺伝でありpene-tranceや環境因子などが複雑に絡み合って発症すると考えられその遺伝的解析は必ずしも容易ではない.近年,genome search法の技術進歩とともにこれらの責任遺伝子の解明が着々と進められており,特に糖尿病においてその研究成果は著しい.
一般に心筋梗塞や脳血管障害などは,動脈硬化病変を基礎に血小板や凝固因子が血栓を作ることにより発症すると考えられている.血栓形成機序の分子学的知見が深まり,血栓形成を促進する因子や逆にこれを抑制する因子が次々とクローニングされた.この際,これら因子の一部には遺伝子多型(polymorphisms)が存在することが明らかとなった.遺伝子多型の中には,その因子の活性に直接影響を与えるものもあり,ある個体がある血栓症に罹患しやすいかを遺伝的に規定している可能性がある.
基本情報
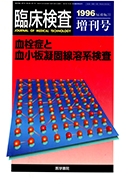
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
