感染症の診断は,その疾患が感染症であるかどうかを確認することである.
そのための臨床検査は,①感染症であるかをスクリーニングする病態検査,②感染部位の検査,③起炎病原体の決定あるいは推定のための検査である.このうち,治療に直結するものとして重要な検査は,微生物学的に起炎病原体を明らかにすることである.
それには,従来より,①塗抹鏡検法による病原体の推定あるいは確認,②分離培養法による病原体の同定,が細菌や真菌の検出に日常的に行われてきている.ウイルスの検出も,基本的にはウイルスの分離同定であるが,これは検査に関する諸条件が整った限られた施設でのみ検査を行うことができ,どこでも行うというわけにはいかないなどの理由で,抗体検査が一般的である.
雑誌目次
臨床検査47巻2号
2003年02月発行
雑誌目次
今月の主題 病原微生物の迅速検査
巻頭言
病原微生物の迅速検査
著者: 猪狩淳
ページ範囲:P.125 - P.126
総論
微生物迅速検査の活用
著者: 栁原克紀
ページ範囲:P.127 - P.135
〔SUMMARY〕 原因微生物を推定し,最も適した抗菌薬を選択することが抗菌化学療法の基本である.また,感染症に対する治療は,早期に開始するほど予後が良いことが知られており,原因微生物を迅速に推定することは重要である.原因微生物の迅速検査としては,塗抹染色,抗原検出,遺伝子診断などが行われている.呼吸器感染症において喀痰のグラム染色は極めて有用な検査である.また,喀痰,尿,血液からの各種抗原検出法や遺伝子診断は,近年大きく進歩した.抗酸菌の迅速培養検査であるMGITも臨床応用され,微生物の迅速検査は感染症の診療に大きく貢献している〔臨床検査 47:127-135,2003〕
検体直接塗抹標本鏡検の重要性
著者: 山中喜代治
ページ範囲:P.137 - P.144
〔SUMMARY〕 顕微鏡を用いた検体の直接塗抹鏡検法は最も古くから行われている感染症検査の1つであり,特別な装置や高価な試薬および広い作業スペースを必要とせず経済性,簡便性,迅速性に優れた基本的検査である.実際にはグラム染色,抗酸染色,特殊染色などを駆使して各種細胞成分の種類,量および質などから炎症像を推察するとともに,多くの感染症起炎微生物を推定(決定)し,早期診断と治療薬選択に貢献している.〔臨床検査 47:137-144,2003〕
DNAチップ/マイクロアレイ法の応用と今後の展望
著者: 山田博子 , 江崎孝行
ページ範囲:P.145 - P.150
〔SUMMARY〕 感染症の病原体を数時間で迅速に検出し臨床医に報告する体制が構築されることは,感染症の診断と治療法を大幅に変革する可能性を秘めている.なかでもDNAチップ/マイクロアレイ法は病原微生物の網羅的診断への利用が期待できる方法である.本稿では,臨床検査への応用と展望について述べる.〔臨床検査 47:145-150,2003〕
各論 消化管感染症起因菌の迅速検査
ヘリコバクター・ピロリ
著者: 長田太郎 , 三輪洋人 , 佐藤信紘
ページ範囲:P.151 - P.157
〔SUMMARY〕 ヘリコバクター・ピロリ菌の感染診断が迅速かつ簡便にできるようになっている.内視鏡で得られた生検組織を用いる迅速ウレアーゼ試験は,病変のある患者に対し短時間にその場で感染診断ができる方法として,特に除菌前診断では有用性の高い検査である.尿素呼気テストはヘリコバクター・ピロリ菌のウレアーゼ活性を利用する検査で,非侵襲的で精度も高く除菌判定に最も有用な検査と考えられており,最近では赤外分光分析装置により短時間で測定できるようになっている.血液や尿を用いた診断法では,ヘリコバクター・ピロリIgGを測定し診断する.数分から数十分で診断できる簡易キットが市販され,最近では国内由来株を用いたELISAキットが開発され,高い精度での診断が期待される.いまだ保険適用にはなっていないが,便中抗原を直接測定することにより尿素呼気テストと同様,除菌後の判定にも利用できると考えられている.〔臨床検査 47:151-157,2003〕
ロタウイルス抗原
著者: 岩田敏
ページ範囲:P.159 - P.161
〔SUMMARY〕 ロタウイルス抗原迅速診断キットには,検出方法としてラテックス凝集法(LA法),酵素抗体法(EIA法),イムノクロマトグラフィー法(IC法)があり,LA法では凝集の有無,IC法では発色したラインの有無,EIA法では吸光度の測定によりそれぞれ判定を行う.LA法は感度の点でやや劣っている.これらのキットではA群ロタウイルスのみが検出可能であるが,適切な感染予防対策および治療を行ううえで,臨床的価値がある.〔臨床検査 47:159-161,2003〕
腸管出血性大腸菌O157抗原,ベロトキシン
著者: 河野原吾 , 本田武司
ページ範囲:P.163 - P.168
〔SUMMARY〕 臨床検査の分野では,迅速に精度良く,臨床に即した検査結果を報告することが求められている.腸管出血性大腸菌O157:H7感染症の治療においても,迅速な検査結果が求められる.ここでは,基本的な分離培養法を解説するとともに,今後さらに重要となるであろう各種迅速診断法の臨床的有用性について解説する.〔臨床検査 47:163-168,2003〕
クロストリディウム・ディフィシル毒素
著者: 加藤はる
ページ範囲:P.169 - P.174
〔SUMMARY〕 Clostridium difficile関連下痢症/腸炎の細菌学的検査には,糞便検体中の毒素検出および毒素産生性C. difficileの分離培養がある.現在日本では,糞便中の毒素検出にはモノクロナール抗体を用いた酵素免疫法によるtoxin A検出キットが利用でき,施行が簡便かつ迅速であるが,感度が高くないことと,toxin A陰性toxin B陽性菌株が検出されないこと,院内感染が疑われた際には疫学的調査に菌株が必要であることから,毒素産生性C. difficileの分離培養を並行して行うことが必要である.〔臨床検査 47:169-174,2003〕
話題
白血球中細菌核酸同定検査
著者: 松久明生 , 嶋田甚五郎
ページ範囲:P.175 - P.180
1.敗血症(セプシス)の細菌学的診断の位置
敗血症(セプシス)とその関連病態〔セプティックショック,播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation;DIC),急性呼吸窮迫症候群(acute respiratory distress syndrome;ARDS),多臓器機能障害症候群(multiple organ dysfunction syndrome;MODS)を含む〕は,一般に予後が悪く,また死亡率も高いので迅速かつ的確な診断が行われ,患者の予後を高める治療につなげなければならない.
このような緊急診断を要する敗血症の細菌学的検査には,従来から患者血液を用いた血液培養法が実施されている.血液培養法の改良の方向は,いかに迅速に感度よく細菌を分離・同定するかに主力が置かれてきた.しかし現状では,培養法に基づいた診断は日数を要し(分離に2~3日以上,同定・薬剤感受性検査を含めれば3~5日以上),しかも,その陽性例は10%前後と低い1).
このように,血液培養法を基礎とした菌血症あるいは敗血症の診断方法では感染症治療に十分には対応しきれておらず,新しい感染症の概念に立脚した迅速診断法が常に要請されてきた.
1990年代初頭,アメリカではBoneらがSIRS(systemic inflammatory response syndrome;全身性炎症反応症候群)という炎症概念をsepsis(敗血症)の病態に導入することで(SIRSの概念に基づいた敗血症は日本の敗血症定義とは必ずしも同一ではなく,セプシスと区別する),敗血症(sepsis)および感染症とSIRSの相互関係を定義づけた2)(図1).この概念によって,細菌などによって起こる感染症が侵襲(この場合septic SIRSと呼ぶ)という炎症メカニズムとして把握され,敗血症の治療はこの炎症反応をいかに初期で抑えるかに重点が移っている.そこでは敗血症の診断には菌血症の確定診断(血液培養陽性)を必須としなくなっている.日本でもこのような考え方は緊急医療分野を中心に浸透し始めており,敗血症の病態を把握できるような迅速細菌診断法が考案・実施されつつある.ここでは,感染防御初期の主要なディフェンスラインである好中球などの敗血症へのかかわりに着目した,筆者らの開発した白血球中細菌核酸同定検査法を紹介する.
尿中肺炎球菌抗原検出
著者: 小林隆夫 , 松本哲哉 , 山口惠三
ページ範囲:P.181 - P.183
1. 市中肺炎で最多の起因菌である肺炎球菌
肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)はグラム陽性球菌であり,細胞壁の外側に多糖からなる莢膜をもち80以上の型に分類されている.肺炎球菌は日本を含む諸外国での市中肺炎での起因菌のうちで30~50%と最多を占めている.本号で別に取りあげられているレジオネラと同様に,肺炎球菌による肺炎は重症化するとしばしば致命的となり,特に血液培養で陽性となった場合に死亡率が上昇することが報告されている1).さらに,最近はペニシリン耐性肺炎球菌(penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae;PRSP),ペニシリン中等度耐性肺炎球菌(penicillin insusceptible Streptococcus pneumoniae;PISP)が臨床分離検体の約半数を占め,ペニシリンなどの抗菌薬への耐性化が問題となっている2).
2. 肺炎球菌の検査上の問題点
特に小児では肺炎球菌はヒト上気道にも常在することがあり,喀痰培養で肺炎球菌が検出された場合でも即肺炎の起因菌とは断定できない.気道由来の検体では品質が問題となり,肺炎患者であっても上気道由来の検体が採取された場合は培養では検出されない可能性もある.また,肺炎球菌は自己融解酵素autolysinを有し,検体の取り扱いによっては,検体中の菌が死滅してしまう.日本の検査室での肺炎球菌の喀痰からの検出率は約5~10%と欧米の30%より低いとされる2).肺炎球菌の培養同定には2~3日を要する.実際には抗菌薬の投与後に喀痰の検査がなされることも多く,これは検査の感度を低下させる.肺炎球菌の検出の感度を高めるためPCR(polymerase chain reaction)法3)などの検査法が検討されたが,コストや手間といった点から普及していない.血液培養は特異度の高い検査であるが,肺炎球菌の血液培養の検出率は10%程度4)と高くない.肺炎球菌はグラム染色で陽性の双球菌連鎖状に特徴的である.グラム染色は,迅速に起因菌を検出できる点は優れているが,手間やコストなどの点から必ずしもすべての医療施設で施行されているとは限らない.従来わが国でもよく利用されていた1993年のアメリカ胸部疾患学会(ATS)の市中肺炎のガイドライン5)では,診断に必須ではない,としている.日本や諸外国での市中肺炎での起因菌の同定率は40~70%前後であり6,7),市中肺炎の患者の30~60%では起因菌不明のまま治療を行わざるを得ないが,このような患者のなかにも肺炎球菌肺炎が多数含まれていることが想像される.起因菌が不明のままの治療は失敗の一因であり,また,広域スペクトルの抗菌薬の濫用に陥りやすい.
尿中レジオネラ抗原検出
著者: 小林隆夫 , 舘田一博 , 山口惠三
ページ範囲:P.184 - P.186
1. レジオネラとは
レジオネラ(Legionella spp.)は好気性グラム陰性桿菌の1つで,自然界中の土壌や水系(河川,湖,温泉など)に広く分布している.人工的な環境すなわち空調冷却水,給水設備にも存在し,このような環境に多いアメーバや藻類の中で共生して増殖可能な性質をもつ.Legionella pneumophilaが主要菌種で,これはさらに15以上の血清型に区別される.レジオネラにはそのほかにもL. bozemaniiなど48菌種が報告されている.レジオネラで汚染された水や蒸気を吸入することにより肺炎や軽症型のポンティアック熱を起こす1,2).なお,レジオネラは,ヒトからヒトへは感染しないといわれている.
1976年の米国での在郷軍人大会での集団発生3)以来,「在郷軍人(Legionnaires)」と「肺を好む(pneumophila)」というラテン語からレジオネラLegionellaと命名され,市中肺炎や院内肺炎の起因菌の1つとして知られるようになった.その主要菌種がLegionella pneumophilaである.欧米では市中肺炎,院内肺炎の約10%を占めるとされている.日本では1981年に斉藤らにより初めて報告4)されたが,1994年の日本の市中肺炎の調査5)ではレジオネラはごく少数であった.しかし,温泉や入浴施設での集団感染例がしばしばマスコミでも報じられ,1999年の感染症新法では第4類感染症に分類されて報告が義務づけられた.感染症新法の施行後は,わが国でも毎年100名以上の患者が報告されている6).レジオネラや肺炎球菌による肺炎はいったん重症化すると致命率も高く,迅速な診断が望まれる.しかし,レジオネラ肺炎は他の微生物による肺炎と比較して特徴的な症状に乏しく,特異的診断法が必要であるが,以下に述べる問題点があり,実際の診断は容易ではない.
血清中抗抗酸菌抗体測定
著者: 河野弘明
ページ範囲:P.187 - P.191
1.はじめに
1950年以降順調に減少してきたわが国の結核罹患率は,最近その減少率が鈍化し,再興感染症としての結核が再び注目を集めている.結核の診断は,喀痰などの臨床材料からの結核菌直接検出(塗抹染色法・培養法)が基本であったが,前者は検出感度が低く,後者は長時間を必要とすることから,臨床症状や胸部画像所見・ツベルクリン反応などの臨床的診断が行われて治療が開始される場合も多かった.最近PCR法をはじめとする遺伝子増幅法が取り入れられ,排菌陽性者の診断は著しく改善されたが,わが国では実際に菌を検出しないままに抗結核化学療法を開始する症例が,肺結核症と診断された患者の約半数に存在している1).これらの症例に抗酸菌症としての根拠を与え,適切な治療と処置を行うことは重要な問題である.
ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')の迅速検出
著者: 中臣康雄
ページ範囲:P.193 - P.196
1. はじめに
これまで日常の細菌学的検査におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の判定には,オキサシリン(MPIPC)やセフチゾキシム(CXZ)を用いた薬剤感受性試験が広く用いられているが,培養法のため翌日まで判定を待たなければならず,また,用いる薬剤,試験方法,手技などによりしばしば判定が変動し混乱を来たすこともあった.
本稿では,MRSAの多剤耐性機構の本態であるペニシリン結合蛋白2'(PBP2')の検出によるMRSA判定法と,PBP2'検出用スライドラテックス凝集試薬について述べる.
生物発光を用いた結核菌の迅速薬剤感受性測定
著者: 山崎利雄
ページ範囲:P.197 - P.199
1.はじめに
1%小川培地を基礎培地に用いているわが国の現行結核菌薬剤感受性試験法は,判定までに2~4週間を要し,判定にも技術者の熟練を要し,また個人差が出やすい.さらに,判定時期を遅らせると耐性と判定されやすいなどの問題がある.米国疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention;CDC)は,結核菌薬剤感受性試験結果は,検体が検査室に提出されてから15~30日以内に報告されなければならないと勧告している1).結核菌薬剤感受性試験の迅速化のために,バクテック法(ベクトン・ディッキンソン),ミジット法(ベクトン・ディッキンソン),ブロスミックMTB-1法(極東製薬工業)といった,液体培地を用いた迅速な試験法が報告され実用化されている.しかし,バクテック法は,放射能を用いるため,わが国では導入されていない.ミジット法は,供試菌液調整条件と判定日が厳格に規定されているし高価である.ブロスミックMTB-1法は,感性菌と耐性菌の明確な判定基準濃度が確立されていないなどの問題がある.そこでわれわれは,生物発光による結核菌の薬剤感受性試験法の実用化をめざし検討2~4)を重ね,簡便で数値化による客観判定ができ,しかも5日間で判定可能な方法を確立した.この新しい結核菌の迅速薬剤感受性試験法について紹介する.
今月の表紙 電気泳動の解析シリーズ・2
クリオグロブリン(cryoglobulin)とその解析
著者: 橋本寿美子
ページ範囲:P.122 - P.123
Cryoglobulinは4℃で白濁沈殿し37℃で溶解する可逆性の温度依存性蛋白であり,臨床上,重篤な症状を発現することの多い蛋白質である.Cryoglobulinは,①1種類の単一クローン(monoclonal;M-蛋白)性免疫グロブリンのみからなる単一成分型,②数種の蛋白成分よりなり,1種類の成分がM-蛋白である混合型,③混合型であるがM-蛋白を含まない型,の3群に大別される.
図1はcryoglobulin血症例で,②のM-蛋白を含む混合型の白濁沈殿物(右)である.図2は上記症例の1) セルロース・アセテート(セ・ア)膜電気泳動,2) 寒天ゲル電気泳動,3) 寒天ゲル免疫電気泳動像である.各泳動像は,a:原血清,b:寒冷沈殿物除去後上清血清,c:精製寒冷沈殿物である.
コーヒーブレイク
トキの舞う里
著者: 屋形稔
ページ範囲:P.191 - P.191
2002年9月の日朝首脳会談で,北朝鮮に拉致された日本人のうち8人の死亡が伝えられ,日本中に衝撃が走った.このとき5人の生存も判明したが,その一人曽我ひとみさんは佐渡真野町の出身であった.それも拉致とは知られず1978年8月に母親と2人突然行方不明となり捜索するも手がかりなく,86年9月に裁判所の失踪確定宣告でお葬式もすまされていた.
母親の生死は不明で,真野町に一人残った老いた父親の驚きは察するに余りある.真野は順徳帝の真野御陵のある静かな田園地帯で,私も数度美しい真野湾を眺めたことがあった.失踪当時この湾に数度不審船の出没するのが認められたという.曽我さんの勤務先だった佐渡病院も近くの真野療養所も馴染み深かっただけに,静けさに乗じて行われた国家主権の侵害には怒りを禁じ得ない.
シリーズ最新医学講座・Ⅰ 免疫機能検査・26
先天性無ガンマグロブリン血症の病因分類
著者: 峯岸克行
ページ範囲:P.201 - P.206
はじめに
無ガンマグロブリン血症は,ヒトにおいて最初に発見された原発性(先天性)免疫不全症で,1952年にBrutonによって報告された1).この最初の症例は8歳の男児で,生後4歳半より肺炎球菌による敗血症を10回以上繰り返した.この疾患がこのとき初めて同定されたことには,抗生物質の開発の寄与が大きく,それ以前には診断前に敗血症などにより死亡していたものと考えられる.さらには,新たに開発された血清蛋白の電気泳動により,ガンマグロブリン分画の欠損が示され,免疫学的な検討により抗原特異的抗体の産生の障害も証明された.ヒト濃縮免疫グロブリン分画の皮下投与により,易感染性の改善を証明しており,50年以上前にこれだけ優れた検査,診断,治療まで含めた臨床免疫学が存在していたことは大変感銘深い.その後,細胞免疫学の進歩により,無ガンマグロブリン血症のほとんどすべてが末梢血中のB細胞を欠損するB細胞欠損症であることが明らかにされ,後述するように,分子生物学,遺伝学の進歩により,B細胞欠損症の原因遺伝子が次々と明らかにされた.
シリーズ最新医学講座・Ⅱ シグナル伝達・2
MAPキナーゼファミリー
著者: 白壁恭子 , 澁谷浩司
ページ範囲:P.207 - P.212
はじめに
多細胞生物を構成する個々の細胞は,細胞外の様々なシグナル分子を感知してそれに応じた細胞増殖・細胞分化・細胞死などの細胞運命を決定する.細胞外シグナルから最終的な細胞運命の決定が導かれる過程で重要な役割を果たしているのが,細胞内シグナル伝達経路である(図1).細胞外シグナル分子は主に細胞膜上に存在する受容体によって感知され,受容体が特定の細胞内シグナル伝達経路を活性化することによって,遺伝子の発現誘導もしくは発現抑制,細胞内骨格の再構築,蛋白質の分解など細胞運命の決定にかかわる様々な事柄が制御される.現在までに非常にたくさんの細胞内シグナル伝達分子が明らかにされているが,本稿ではそのなかでも特に古くから研究が行われ,かつその理解が最も進んでいるシグナル伝達分子であるMAPキナーゼファミリーに注目し,その概要を解説したい.
キナーゼとは蛋白質中のOH基をもつアミノ酸(セリン,スレオニン,チロシン)のOH基にリン酸を付加する(リン酸化する)酵素である.リン酸化を受けるとそのアミノ酸の電荷が変わるので,蛋白質全体の構造や化学的性質が変化して蛋白質がもつ生理活性も変化する.また,付加されたリン酸基は脱リン酸化酵素(ホスファターゼ)によってはずすこともできる.これらのことから,リン酸化および脱リン酸化は蛋白質の機能を可逆的に制御できる翻訳後修飾の1つとして細胞内シグナル伝達経路において中心的な役割を果たしている.
古典的なMAPキナーゼ(Mitogen Activated Proteinキナーゼ)は,種々の増殖因子や発癌プロモーターによって共通に活性化するセリン/スレオニンキナーゼとして見出された.その後,古典的なMAPキナーゼと相同性をもつJNK(c-Jun N-terminal Kinase)やp38といったセリン/スレオニンキナーゼが報告され,これらのキナーゼが1つのファミリーを構成していることが明らかになった.そこで本稿では,混合をさけるために古典的なMAPキナーゼをヒト遺伝子の名称であるERK(Extracellular signal Regulated Kinase)と呼び,ERKとJNKとp38からなるキナーゼファミリーをMAPキナーゼファミリーと呼ぶことにする.
トピックス
細菌性腟症の診断
著者: 松田静治
ページ範囲:P.214 - P.217
1.はじめに
細菌性腟症(bacterial vaginosis;BV)は,以前には非特異性腟炎,ガードネレラ腟炎,ヘモフィルス腟炎,嫌気性菌腟症などとして知られていたが,現在では乳酸桿菌(Lactobacillus)が優勢の腟内細菌叢から好気性菌のGardnerella vaginalis,嫌気性菌のBacteroides属,Mobiluncus属,Peptostreptococcus属,そのほかMycoplasma hominisなどが過剰増殖した複数菌感染として起こる病態と考えられている1,2).また腟自浄作用の低下,化学的,器械的刺激,エストロゲン機能の失調などの誘因が細菌増殖に関連するのであろう.しかし本症の診断基準に合致する例の1/3から半数が帯下感がなく無症状であり,病因はいまだ完全には解明されていない.
近年BVが注目されるのは,本症を有する妊婦で絨毛膜羊膜炎(chorioamnionitis;CAM),早産,前期破水が頻度が数倍高くなることや,子宮内膜炎(産褥含む),子宮附属器炎(pelvic inflammatory disease;PID)罹患の危険率が上昇することで,時に腟トリコモナス症や子宮頚管炎とも合併する.BVを腟炎(vaginitis)とせず腟症(vaginosis)なる名称にした背景には,腟炎を分離される細菌で規定せず,腟分泌物の性状所見などに主眼をおいた事情が存在しよう.なお,BVをSTD(sexually transmitted disease)に含めることに反対の意見が多く,現在ではむしろsex associated diseaseとして捉えたほうがよい.
IT技術と微生物検査
著者: 田辺一郎
ページ範囲:P.217 - P.219
1. はじめに
情報技術(information technology;IT)の充実は,「IT基本戦略」として,2000年7月,当時の森首相が内閣府に設置した「IT戦略会議」から,国家戦略として掲げられるほどの重要な命題となっている.(http://www.kantei.go.jp/jp/it/index it.html)
ここでいうITとは単なる情報処理・通信の技術としてのものではなく,コンピュータの進歩に基づくところによる技術のことである.この報告のなかで,ITの進歩によりめざすべき社会の具体的な例の1つ,医療に関する部分として「医療・介護:在宅患者の緊急時対応を含め,ネットワークを通じて,安全に情報交換ができ,遠隔地であっても質の高い医療・介護サービスを受けることができる」とある.
医療においては「緊急」「安全」「高品質」がキーワードとなろう.
なお,本題とは関係ないが,この報告のなかには昨今社会的に話題となった国と地方自治体のオンライン化に関する提言も含まれている.批判も多いなか,この施策の実施に踏み切ったということは,本報告の実現化に政府も腰を入れて取り組んでいるという1つの表れかもしれない.
さて,「微生物検査」はITによってどのように変われるであろうか.以下に具体的な例とともに考えていきたいと思う.また,政府が唱える「緊急に対応」でき,「ネットワークを通じた安全な情報交換」,「質の高い医療」の恩恵をどう日常の業務のなかに生かすことができるであろうか.
乳癌のHER-2免疫組織化学的検査法―ハーセプテスト
著者: 黒住昌史 , 松井武寿 , 小林康人
ページ範囲:P.220 - P.223
1.はじめに
2001年からわが国においてもHER-2に対するモノクローナル抗体であるトラスツズマブ(ハーセプチン)を用いる抗体療法が,乳癌の新しい薬物療法として行われるようになった.この薬剤を使用するためには乳癌組織におけるHER-2過剰発現の有無を検査することが必須であり,その検査法としてハーセプテストが広く用いられている.本稿では乳癌におけるHER-2蛋白過剰発現の検査法であるハーセプテストの実際と問題点を中心に述べることとする.
基本情報
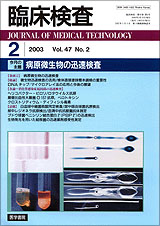
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
