先天性免疫不全症は,免疫系において重要な役割を果たしている分子の異常により,生体防御機構が低下し,易感染を呈する疾患である.近年,先天性免疫不全症の責任遺伝子が次々に同定されてきており,診断法の確立,生体防御機能低下のメカニズム解明,病態理解の進歩,よりよい治療法の選択に役立っている.こうした免疫不全症研究の進歩をもとに,International Union of Immunological Societies(IUIS)は,2年ごとに分類を改訂している.
しかし,免疫不全症の分類は難しい.例えば,遺伝子から分類するのか,臨床病態から分類するのかと言う問題がある.遺伝子名だけでは,実用性に欠ける分類となろう.例えば,高IgM症候群は責任遺伝子で分類することになった.これは,高IgM症候群は,原因遺伝子としてCD40 ligand(CD154),CD40,AID,UNGが知られているが,前2疾患は細胞性免疫不全と液性免疫不全をきたす複合型免疫不全症であるが,後2疾患は液性免疫不全であり,病態や治療法が異なるため,高IgM症候群と同一名称にした場合の混乱を避けるためである.また,高IgM症候群という名称でありながら,症例によっては血清IgMが高値をとらず正常値の場合がある.臨床医が免疫不全症患者を診療した際に,IgMが正常であることから高IgM症候群を鑑別診断から除外してしまい,診断を誤る可能性もある.これらのことから今回の分類では高IgM症候群という疾患名をなくし,遺伝子名を病名とすることとなった.しかし遺伝子名で分類することは,非専門医にとってわかりにくくなった側面もある.高IgM症候群という名称は歴史的にも長く使われており,概念的にわかりやすい.今後どのように分類するか工夫が必要である.
雑誌目次
臨床検査53巻5号
2009年05月発行
雑誌目次
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
巻頭言
臨床検査免疫不全症2009
著者: 野々山恵章
ページ範囲:P.525 - P.526
総論
原発性免疫不全症の疾患概念
著者: 矢田純一
ページ範囲:P.527 - P.532
免疫系は獲得免疫系(B細胞,T細胞,抗体)と自然免疫系(食細胞,樹状細胞,NK細胞,NKT細胞,補体)とに分けられる.そのいずれかの欠陥(ほとんどは遺伝子異常による)によって生体防御不全を呈している状態を原発性免疫不全症という.上記の免疫担当因子は互いに共同して働くので,1つの欠陥は他の2次的欠陥をもたらすし,1つの遺伝子産物の異常が複数の免疫担当因子の欠陥をもたらすこともある.現在,原発性免疫不全症はどの免疫担当因子の欠陥を中心に分類されているか,どの遺伝子の異常によるかという視点や臨床上の便宜という面からも概念を整理すべきであろう.
免疫不全症候群の遺伝子診断の中央化とデータベース
著者: 今井耕輔 , モハンスジャータ , 小原收
ページ範囲:P.533 - P.540
厚労省研究班と理化学研究所は共同で,原発性免疫不全症(PID)の登録データベースであるPIDJを稼働した.全国の一般医からも気軽に使ってもらえる電子紹介状を提供し,同時に匿名化データがデータベースに蓄積されていく.経時的なデータ蓄積も行え,PID専門医によるカンファレンスも可能である.また,欧米のPIDデータベースとの互換性をとっており,将来的に国際共有も可能である.臨床検体の解析,保存,遺伝子解析の中央化もスタートした.さらに,遺伝子変異を軸としたデータベースであるRAPIDも稼働し,臨床医への情報提供を行っている.こうした取り組みは国際的にも注目を集めており,今後PID患者の診断,治療,予後の改善に貢献することが期待される.
免疫不全症の臨床検査
免疫不全症のFACSによる簡易診断法
著者: 金兼弘和 , 堺千賀子 , 宮脇利男
ページ範囲:P.541 - P.546
免疫不全症は生体の免疫系を維持するうえで必要な免疫担当分子の先天的欠陥によって生じる.障害部位によって分類され,150種類以上からなる雑多な症候群であるが,120種類以上で責任遺伝子が同定されており,遺伝子診断による確定診断が可能である.しかし遺伝子解析には時間と労力を要する.利用可能なモノクローナル抗体があればFACSによる簡易診断が可能な疾患がいくつかあり,本稿では免疫不全症におけるFACSによる簡易診断法について紹介したい.
免疫不全症遺伝子解析法の実際
著者: 大嶋宏一 , 小原收
ページ範囲:P.547 - P.552
かずさDNA研究所では,PIDJプロジェクトの一員として,100種類を超える免疫不全症関連遺伝子解析を行っている.解析を迅速に行うために,実験のフローチャートを作成し,途中段階で実験に不具合が生じた場合にはすぐに再解析を開始するなどの工夫だけでなく,PCRダイレクトシーケンシングの効率化などを図っている.本稿では,この遺伝子解析の実際の方法を解説するとともに,得られた解析結果を概説する.
TRECs測定による重症複合免疫不全症のマススクリーニング
著者: 森西洋一 , 今井耕輔
ページ範囲:P.553 - P.559
重症複合免疫不全症(SCID)は,乳児期早期に重症日和見感染症を発症する致死的な先天性免疫不全症である.しかし,発症前に造血幹細胞移植が実施されれば高い生存率が期待できるため,早期の発見と介入が重要であり,その早期診断法として,T細胞新生能のマーカーであるTRECsの定量が有用とされる.健常人の末梢血中のTRECs値は,乳児期に最も高く加齢に伴い低下するが,胸腺内T細胞の分化・新生障害を共通病態とするSCIDでは,原因遺伝子による表現型の差異にかかわらず著減している.診断が遅れて難治化,あるいは死亡するSCIDの子供たちを救うためにも,TRECs定量による新生児マススクリーニングの整備が急務である.
各疾患の遺伝子異常,診断と治療
重症複合免疫不全症(SCID)
著者: 久間木悟
ページ範囲:P.561 - P.567
重症複合免疫不全症患者は,乳児期から重症の感染症を繰り返し,骨髄移植などの根本的治療を施さないと救命できない重篤な疾患である.これまでに明らかにされた責任遺伝子は少なくとも17種類あり,サイトカインシグナル系,T細胞受容体シグナル系,T細胞やB細胞の抗原受容体再構成機構,代謝にかかわる分子の異常で発症する.また,同じ遺伝子の変異でも様々な表現型をとりうることも知られるようになってきた.治療は前述の骨髄移植のほか,臍帯血移植,遺伝子治療などが試みられるようになってきている.
分類不能型免疫不全症候群および免疫グロブリンサブクラス欠損症
著者: 金子英雄 , 近藤直実
ページ範囲:P.569 - P.574
分類不能型免疫不全症候群(CVID)は先天性免疫不全症のなかで最も頻度の高い疾患であり,易感染と抗体産生不全を特徴とする.CVIDは様々な病態が混在している症候群であるが,その一部は病因遺伝子が明らかになってきた.CVIDの治療法は,免疫グロブリン置換療法が主体であるが,今後,個々の病態に合わせた治療開発が期待されている.免疫グロブリンサブクラス欠損症,IgA欠損症でも,一部の遺伝子異常が明らかにされてきたが,今後,さらに病態を明らかにしていく必要がある.
伴性高IgM症候群(CD40 ligand欠損症)
著者: 富澤大輔 , 今井耕輔
ページ範囲:P.575 - P.579
高IgM症候群(HIGM)は,免疫グロブリンのクラススイッチの障害による易感染性を特徴とする原発性免疫不全症候群であり,現在,5つの病型が知られている.最も頻度が高いのが,活性化ヘルパーT細胞上に発現するCD40 ligandの異常による,1型(CD40 ligand欠損症:HIGM 1)である.HIGM 1は,抗体産生障害による易感染性に加えて,ニューモシスチス肺炎やクリプトスポリジウム腸炎などの日和見感染症が問題となる,複合型免疫不全症である.適切な感染予防・管理に加えて,適切なドナーが得られる場合には,根治療法として造血幹細胞移植による免疫再構築が推奨される.
Wiskott-Aldrich症候群
著者: 川村信明
ページ範囲:P.581 - P.586
Wiskott-Aldrich症候群(WAS)は湿疹・血小板減少・易感染性を3主徴とし,自己免疫・悪性疾患を高率に合併するX連鎖遺伝形式の疾患である.1994年に原因遺伝子(
先天性好中球減少症
著者: 岡田賢 , 小林正夫
ページ範囲:P.587 - P.592
先天性好中球減少症は慢性好中球減少,前骨髄球~骨髄球の段階での成熟障害を臨床的特徴とし,生後早期から重症細菌感染症を反復する先天性免疫不全症である.近年,種々の責任遺伝子が同定され,本症の分子レベルでの病因が明らかとなりつつある.本疾患では,好中球エラスターゼの責任遺伝子
慢性肉芽腫症
著者: 水上智之
ページ範囲:P.593 - P.597
慢性肉芽腫症は,食細胞殺菌障害により,重症細菌・真菌感染症を反復する先天性免疫不全症である.加えて最近は炎症性腸疾患症状を呈するCGD腸炎例も広く知られ,全身疾患としてのCGDの広さ・複雑さが認識されてきている.治療面では,特に造血幹細胞移植技術に大きな進歩がみられ,国内の移植成績が良好であることが示された.さらに国内で遺伝子治療計画が進められている.これら治療法の確立により,CGD患者の治療選択肢はさらに広がると考えられる.
家族性血球貪食症候群
著者: 大賀正一 , 田中珠美
ページ範囲:P.599 - P.604
血球貪食症候群/血球貪食性リンパ組織球症(HPS/HLH)は,発熱,血球減少,肝脾腫,播種性血管内凝固および高フェリチン血症を呈し,血球貪食組織球が増加する高サイトカイン血症を背景とした危急症である.HLHは感染症やリンパ腫などに続発するものが多いが,家族性血球貪食症候群(FHL)はHLHをきたす常染色体劣性遺伝病である.FHLのほとんどは乳児に発症し,細胞傷害性顆粒代謝異常がその本態である.perforinを含む3つの原因遺伝子が明らかになったが,まだ約半数の症例の遺伝子異常は不明である.唯一の根治療法は同種造血細胞移植で,その時期と方法に関する検討が行われている.
自己炎症性疾患
著者: 西小森隆太
ページ範囲:P.605 - P.610
自己炎症性疾患は臨床的には周期熱を特徴とする遺伝性疾患群の総称であり,主として自然免疫系に関与する遺伝子の異常で発症する.本総説では代表的な疾患である家族性地中海熱,TRAPS,高IgD症候群,CAPS,若年性サルコイドーシス/Blau症候群について,日本における実情を織り交ぜながら,診断,検査特に遺伝子検査について記載した.
話題
高IgE症候群
著者: 峯岸克行
ページ範囲:P.611 - P.614
1.はじめに
高IgE症候群(hyper-immunoglobulin E syndrome, Hyper-IgE syndrome;HIES)は,別名Job's syndromeと呼ばれる先天性免疫不全症候群である.第1例は1966年にDavisとWedgewoodらによって報告された.Job(ヨブ)の名前は,全身性で反復性のブドウ球菌感染症による寒冷膿瘍(cold abscess;膿の蓄積を認めるのに,発赤・熱感・疼痛などの炎症症状を欠く膿瘍)が,旧約聖書のヨブが神から受けた肉体的試練の記載に類似していることに由来する1).その後,1972年にBuckleyらは,同様の寒冷膿瘍を発症した女児に,顔貌異常と著しい高IgE血症が合併していたことを報告し,このためBuckley症候群と呼ばれることもある2).1999年にGrimbacher,Puckらは皮膚,肺の膿瘍と高IgE血症などのアレルギー症状に加えて,骨・歯牙の異常が多くの症例に合併していることを報告し,高IgE症候群が免疫系だけではなく骨,軟部組織,歯牙の異常を含めた多系統の疾患(multisystem disease)であるとの本症候群の重要な概念を確立した3).その原因遺伝子は多くの研究にもかかわらず長い間不明であったが,高IgE症候群の症状に,細胞内寄生細菌とヘルペスウイルスに対する易感染性を合併する症例の原因遺伝子が,Jakファミリーチロシンキナーゼ
自然免疫異常による免疫不全症
著者: 高田英俊 , 原寿郎
ページ範囲:P.615 - P.620
1.はじめに
自然免疫における分子免疫学的メカニズムが解明されるに伴い,それを構成する分子異常による,原発性免疫不全症も明らかになってきた.2007年にIUIS(International Union of Immunological Societies)から出されている分類によると,自然免疫不全症として,無汗性外胚葉形成不全免疫不全症候群,IRAK4欠損症,WHIM症候群,Epidermodysplasia verruciformis,単純ヘルペス脳炎関連免疫不全症が挙げられている1)が,それ以降MyD88欠損症が新たに報告されている.
遺伝性血管性浮腫(hereditary angioedema;HAE)
著者: 香坂隆夫
ページ範囲:P.621 - P.628
1.はじめに
C1 inhibitor(C1INH)欠損症は,古くから遺伝性血管神経性浮腫(hereditary angioneurotic edema;HANE)の名前で知られていたが,現在は遺伝性血管浮腫(hereditary angioedema;HAE)が正式名称となっている.本症は補体欠損症の中でも症例数が多く,皮下浮腫から,窒息,消化管イレウスなど派手な症状を呈する.皮下浮腫はいわゆる硬性浮腫でクインケの浮腫の名でよく知られるとおり,古くからの由緒ある疾患である.しかし,案外,臨床家の間で見逃され,軽視されてきた.その理由は,診断後の治療に関して特効的根治的な治療方法はなく,特に急性期の治療に関してはお手上げの状態であった.しかし,血漿由来のC1INH製剤がわが国でも発売され,その補充治療が可能となった.さらに,この疾患の発症原因がブラジキニン(bradykinin)によるものと判明し,直接この系を抑制する治療薬が分子生物学的手法により開発され,著効の治験結果が得られ,本疾患を見落とすことが臨床上許されなくなった時代的背景がある.実際,米国では医師会からの注意喚起がなされ,また米政府もこの報告書を受け入れた1).分子標的薬や生物学的製剤は米製薬業界の経済的重点項目であることも関連し,政府の後押しを受け,医療界への認識が一気に広がっている2).今や本疾患は,免疫,補体の専門家だけでなく,救急を扱う医師にとっても熟知すべき疾患の一つとなった.
今月の表紙 帰ってきた真菌症・5
病原性接合菌
著者: 矢口貴志 , 西村和子
ページ範囲:P.522 - P.524
接合菌症はMucoralesに属する菌種が原因となるムーコル症とEntomophthoralesに属する菌種が原因となるエントモフトラ症に分けられる.エントモフトラ症の感染部位は鼻粘膜と皮下組織にほぼ限られ,また,わが国では熱帯,亜熱帯に発生する本症の症例はない.これに対して,ムーコル症は日和見感染として発生する重篤な感染症で,接合菌症の大半を占め,肺,鼻,皮膚などが侵される.病原性接合菌類はいずれも速やかに生育し,寒天培地上でシャーレの蓋に達する毛足の長い綿毛状の集落を形成する(図1).菌糸は幅広く,有性胞子として接合胞子(図2)を形成する.属の特徴となる構造として,仮根(菌糸の一部から生じる植物の根のような構造),胞子囊,柱軸(柄が胞子囊内に突き出た部分),アポフィシス(胞子囊下部の構造)がある.無性胞子は胞子囊胞子と呼ばれ,胞子囊内に形成され,成熟すると胞子囊壁は破れ放出される.
ヒトに対する主要なムーコル症原因菌を以下に示す.
映画に学ぶ疾患
「愛を乞うひと」―ミトコンドリア病
著者: 安東由喜雄
ページ範囲:P.598 - P.598
映画「愛を乞うひと」は,母の子に対する強烈な虐待がストーリーの重要な部分を占める.豊子(原田美枝子:娘:照恵との二役)は戦後の混乱期の生活苦の中で,夜の商売などをしながら身体を張って日銭を稼いで生きてきた.その娘照恵は,物心ついたころから,母親から折檻を受けつづけていた.照恵の父(中井貴一)は台湾人でとても優しい人であったが,病死した後母親の虐待に拍車がかかった.殴られて顔が腫れる,髪をひっぱられて束になって抜ける,階段から突き落とされる,それでも娘は耐え続けた.時は流れ,何十年かの時が過ぎ,彼女は結婚もし,今や高校生の一人娘がおり,やっと落ち着いた生活を送ることができるようになっていた.しかし,どれだけ時が流れても,彼女には忘れられないトラウマがあった.雨の中,父が母の虐待から自分を守るために母から引き離した日のこと,そして何よりわが子への愛し方を知らずに暴力によってしか愛を乞うことができなかった母のことである.この映画では,母の折檻をどう受け止めたらいいのかわからないまま耐え忍び,愛を乞い続けた娘の姿が切々と描かれて心に迫る.
さて,幸せなことに,私には狂おしいくらい好きな母がいる.弟が生まれるまでの私はいわば末っ子のように育ち,幼い頃からとりわけ母に対する思慕が強かった.幼稚園生のときは,朝が来ると急に幼稚園には行きたくなくなり,母のスカートのすそを握り締め,毎日のように泣いてばかりいた.小学生の頃の私には,父,母,私,兄の順番に床を並べて寝るのが一日の終わりの何よりも幸せな行事であった.それは小学校二年生の春,真夜中のことであった.大分県地方に比較的大きな地震が襲った.人生で初めて体験する得体の知れない不穏な出来事に,なすすべもなく呆然としていた私に,母は半狂乱になって,私と兄の身体に覆いかぶさり続けた.地震の終わりとともに暗闇の中で垣間見た,放心したように安堵した母の美しい横顔は今でも忘れない.
シリーズ最新医学講座・Ⅰ 死亡時医学検査・5
死亡時画像(Ai)と超音波
著者: 内ヶ崎西作
ページ範囲:P.629 - P.635
はじめに
死体の画像診断に対する認識は最近とみに高まっている.そのツールとしては,一般的にはCTあるいはMRIが用いられているが,他の画像診断であっても応用は可能である.筆者は2001年より法医学領域への超音波画像診断の応用を検討しており,解剖前の超音波画像と解剖所見との比較を行っている.救命救急の現場では「死」の状態に非常に近い来院時心肺停止(cardio-pulmonary arrest on arrival;CPA-OA)症例に対しても超音波画像診断が行われているので,死後少し時間が経過してから行われる死体検案での超音波画像診断の応用を中心に説明する.
シリーズ最新医学講座・Ⅱ iPS細胞・5
ヒトES細胞およびヒトiPS細胞を用いた血小板産生
著者: 高山直也 , 江藤浩之 , 中内啓光
ページ範囲:P.637 - P.642
はじめに
再生医療とは,通常の修復機構では対応できない大きな損傷を受けた臓器や組織を再生する医療である.そのソースとして“幹細胞”という存在が注目を浴びている.幹細胞は大別して,特定の臓器・組織に存在し自身に必要な細胞を生涯を通じて絶えず供給する役割を担っている体性(組織)幹細胞と,着床前初期胚から樹立され試験管内(
しかし,ES細胞由来の細胞を移植治療のソースとして用いる場合にはいくつかの問題点がある.第一に現在移植治療で問題となっているように,レシピエントとドナーのヒト白血球型抗原(human leukocyte antigen;HLA)が異なれば免疫学的拒絶を受けてしまうため,核移植などの技術を用いて,レシピエントと同じHLAを持ったES細胞を樹立しなければならないという点である.第二には,ES細胞の持つ高い増殖能と多分化能のために,三胚葉系(外胚葉:神経細胞など,中胚葉:心筋・血液細胞など,内胚葉:肝細胞・膵細胞など)の細胞成分が無秩序に混在した腫瘍であるテラトーマ(奇形腫)を形成する能力を持ち合わせている点である.この為,移植細胞にES細胞が残存していると将来的に腫瘍化する可能性が懸念される2).
一方,血小板は生体内のホメオスタシスを保つ為に必須の無核の機能細胞である.各種悪性腫瘍に対する抗がん剤治療,骨髄移植後の致命的な血小板減少,先天性血小板減少症の大量出血時に対しては,血小板輸血が現段階の唯一の対症療法であるが,これらは現在すべて献血に依存している3,4).しかも,血小板は赤血球などほかの血液細胞と比較すると寿命が最大約7日,献血後の濃厚血小板の使用期間は4日間と短く,冷蔵保存も不可能である為,相対的な血小板製剤不足が度々経験される5).血小板の大きな利点は無核の細胞であるため,遺伝情報が永久に保存されることがなく,さらに残存する有核細胞を取り除く為に輸血前に放射線照射を行うことも可能6)であり,ES細胞を移植医療へ応用する際の問題点である腫瘍化の可能性を考慮する必要がないということである.また,抗血小板抗体を保持している特殊な患者以外では,HLAの一致を考えずに輸血が可能である.以上の利点,臨床的な需要の高まりを考慮するとES細胞から分化誘導した血小板は,現段階においてES細胞由来の細胞療法として実現度が高いと思われる.マウスES細胞からは既に筆者らのグループを含め数グループから血小板の前駆細胞である巨核球および,その最終分化形態である血小板へ誘導する系が確立されてきた7~10).さらに最近われわれは京都大学で樹立された3株のヒトES細胞株(KhES-1,2,3)を用いて,機能を有する血小板の誘導に世界で初めて成功した11).
このシステムでは試験管内で未分化なES細胞から中胚葉系の細胞へ分化を経て,血球前駆細胞,巨核球,さらにその終末分化細胞である血小板へと分化する一連の発生過程を観察することが可能である.また,核を持たない血小板レベルでの遺伝子操作は不可能であるが,ヒトES細胞を用いれば試験管内で遺伝子改変血小板を分化誘導し,比較的簡便に機能解析が行えるという実験モデルとしての将来的な発展性も期待できる.
本稿では,ヒトES細胞からの血小板産生法と,最近樹立されたヒト誘導型多能性幹細胞(induced pluripotent stem Cell:iPS細胞)を用いた医療への応用の可能性について概説する.
研究
持続性部分てんかん患者の脳磁図によるjerk-locked back average
著者: 橋詰智保 , 佐藤綾子 , 渡司博幸 , 杉村有司 , 金子裕
ページ範囲:P.643 - P.647
Epilepsia partialis continua(EPC)を呈する3例のてんかん患者で脳磁図によるjerk-locked back average(JLA)を測定した.2例では上肢に,1例では下肢にEPCがみられた.筋電図より-54.6~-37.1msec先行し,再現性のある波形を記録でき,等価電流双極子はそれぞれ手足の領域に相当する運動野に求められた.1例ではJLAの双極子はスパイクマッピングと一致したが,2例では異なっていた.JLAによって従来のスパイクマッピングだけではわからない病態を診断できた.
Coffee Break
若くして逝った旧友N君が世話になったと枕元に現れる
著者: 佐々木禎一
ページ範囲:P.560 - P.560
1941(昭和16)年から小樽中学同期生であったN君は眉毛の濃い好男子であったと記憶している.中学校の授業で先生が「誰か坊さんをしている家があるか?」と質問をしたことがあった.この時N君が手を挙げたが,結局何か感違いしたことがわかり皆の失笑をかった.それ以来N君は“坊主(ボンズ)”というあだ名となったが,ここではN君と表現することとする.
さて,われわれの中学生活は「大東亜戦争」と重なり,3~4年生の頃には軍関係の学校や一部上級学校へ進学したり,また室蘭の軍需工場へ終戦まで動員されたり,その後の進路も不詳だった同級生も少なくなかった.N君も当時新設された樺太医学専門学校へ行ったとの情報を耳にした.しかし,終戦とともに樺太医専はもちろん閉校,その結果N君も帰道し,医学への道をやめ銀行員として元気にやっていることも知った.
--------------------
あとがき フリーアクセス
著者: 岩田敏
ページ範囲:P.650 - P.650
桜前線は北上を続け,関東地方は初夏の陽気に包まれています.1年の内でもっとも過ごしやすい季節がやってまいりました.私たち医療従事者にとっては,新人を迎え職場が明るく華やかな雰囲気に包まれるとともに,新人教育に学会活動にと,何かと忙しい時期です.医療安全の観点からは神経を使いますが,これからの医療を背負う人材を育てるという意味で,指導者にとってはより一層の力が入るところでもあります.
今月号の主題には「免疫不全症候群と遺伝子異常」を取り上げました.近年の免疫学の進歩には目覚ましいものがあります.とりわけ免疫系に欠陥をきたす遺伝子異常に関する研究は飛躍的に進歩し,原発性免疫不全症候群の分類方法も,どのような免疫担当因子の欠陥があるかに加えて,どのような遺伝子の異常があるのかという視点から行われており,かつて私たちが学生時代に学んだ臨床像を中心とした分類と比べて,極めて詳細なものとなっています.また,原発性免疫不全症候群の診断に関しても臨床症状に加えて,遺伝子診断を行うことにより,より確実な診断をつけられることから,より適切な治療や,将来的に期待される遺伝子治療にも結びついてくると思います.今回はこの領域のオピニオンリーダーでいらっしゃる防衛医科大学校小児科の野々山恵章教授に企画をお願いし,原発性免疫不全症候群に関する最新の検査,診断,治療についてまとめていただきました.極めて充実した内容となっており,小児科医である私も参考書として手元に置いておきたいと考えている1冊です.検査医学に携わる読者の皆様の今後の活動にきっと役立つことと存じますので,ぜひご一読いただければ幸いです.
基本情報
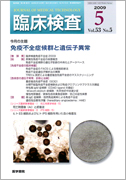
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
