超音波(エコー)検査は全身のスクリーニングに用いることができるうえ,経済的かつ簡便で,ベッドサイドでも施行が可能です.また,さまざまな症状や部位,放射線被曝を避けることが望ましい女性や小児など,多彩な場面で活用することができ,日進月歩の画像診断領域においても特に重要視されてきています.
エコー検査に対する需要増加に伴い,エコー検査に従事する者に求められるエコー所見の知識・診断能力も,より広範囲・高度化してきています.さらに,時には,限られた時間のなかで緊急性の有無を含めた的確な判断が求められることもあるでしょう.広範かつ緊急性の高い症例にも対応できる知識・能力は,エコー検査の基本かつ重要な要素となってきていると考えられます.
雑誌目次
臨床検査64巻4号
2020年04月発行
雑誌目次
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
はじめに フリーアクセス
著者: 藤崎純
ページ範囲:P.315 - P.315
1章 腹部エコー
肝損傷
著者: 丸山憲一
ページ範囲:P.320 - P.325
疾患の概要
臓器損傷
臓器損傷の多くは交通事故や高所墜落など高エネルギー外傷による全身に対するイベントであり,肝損傷も全身に生じたイベントの一部として捉える必要がある.肝臓のみだけでなく複数臓器にわたる損傷や頭部外傷,骨盤外傷との合併損傷による多発出血,それに拍車をかける凝固障害に対して,優先順位をいかに判断し,どのように治療方針を決定していくか,これこそがエコー検査も含めた外傷画像診断の果たすべき重要な役割である.
肝膿瘍
著者: 山本幸治
ページ範囲:P.326 - P.328
疾患の概要
肝臓内に膿瘍が形成される疾患で,細菌性とアメーバなどの非細菌性に分けられる.原因菌は90%が細菌性で,大腸菌をはじめとするグラム陰性桿菌である.
感染経路は,消化管や骨盤腔内臓器の化膿性炎症が門脈や肝動脈を通じて波及するもの,胆道の化膿性炎症が上行性に波及するものなどがある.
囊胞内出血
著者: 山本幸治
ページ範囲:P.330 - P.333
疾患の概要
肝囊胞は,腹部エコーなどの画像診断の普及により健康人でもしばしば発見される肝の良性疾患である.そのほとんどが単純性肝囊胞であり,立方上皮で内腔が覆われ内容に液体(漿液成分)を有するものである.多くは,エコーやCTなどの画像診断で評価され無治療であるが,時には経過観察を要する場合もある.
頻度は低いが,囊胞腺癌や嚢胞内出血などにより内部エコーをもつ囊胞(complicated liver cyst)がみられる場合は注意が必要である.また,自覚症状がある場合や感染,出血,破裂などを合併したときには外科的治療の適応となることもある.
急性肝炎
著者: 丸山憲一
ページ範囲:P.334 - P.338
疾患の概要
疫学
急性肝炎とは,主に肝炎ウイルスが原因で起こる急性のびまん性疾患であり,肝炎ウイルスにはA,B,C,D,E型の5種類が確認されている.肝炎ウイルスではないものの,EBウイルス(Epstein-Barr virus:EBV)による伝染性単核球症やサイトメガロウイルス(cytomegalovirus:CMV)感染に伴う肝障害も知られており,さらには,急性肝炎様に発症する自己免疫性肝炎(autoimmune hepatitis:AIH)や抗菌薬,解熱鎮痛抗炎症薬,精神神経領域薬などで肝障害をきたす薬物性肝障害(drug-induced liver injury:DILI)も存在する.
国立国際医療研究センター・肝炎情報センターからの報告では,1980〜2017年の期間におけるわが国の急性肝炎の起因ウイルス別発症頻度は,A型(約30%),B型(約30%),C型(約10%),非A非B非C型(約30%)である1).2010〜2017年の期間に限ると,A型(約10%),B型(約40%),C型(約10%),非A非B非C型(約40%)とA型の発症頻度は低下してきている.B型は性的接触による感染が多く,D型は,診断そのものが困難で正確な感染状況は把握されていない.一方,E型は2000年ごろから北海道や関東地域での集団発生,流行が問題となってきている.
急性胆囊炎(胆囊軸捻転症含む)
著者: 刑部恵介
ページ範囲:P.339 - P.345
疾患の概要
疫学
急性腹症の1つである急性胆囊炎は,腹痛患者のなかで3〜10%程度を占めている.なお,年齢によって罹患率が変わり,50歳以下の腹痛患者では6%と低いのに対して,50歳以上では21%と高率となる1).
急性胆管炎
著者: 岩下和広 , 岡庭信司
ページ範囲:P.346 - P.350
疾患の概要
急性胆管炎は胆管内に急性炎症が発生した病態であり,その発生には①胆管内に著明に増加した細菌の存在,②細菌またはエンドトキシンが血管内に逆流するような胆管内圧の上昇の2因子が不可欠となる1).特に重症例では,ショックや意識障害,播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation:DIC)などの予後不良な病態に進行するため早期治療が必要な疾患である.そのため生理検査パニック値(像)の運用指針ワーキンググループが定める腹部エコー(ultrasound:US)検査のパニック像では,急性胆管炎が疑われた時点でGrade Ⅱ,症状を伴わない閉塞性黄疸も急性胆管炎へ移行する可能性があることからGrade Ⅰとしている2).
胆汁は本来無菌であるが,胆管閉塞などにより胆汁のうっ滞が生じると細菌増殖(胆汁感染)をきたす.胆管閉塞の原因としては肝外胆管結石の頻度が最も高いが,近年は悪性疾患や硬化性胆管炎,非手術的胆道操作などによる急性胆管炎も増加傾向にある1).
総胆管結石
著者: 刑部恵介
ページ範囲:P.352 - P.355
疾患の概要
疫学
総胆管結石とは,肝内胆管や胆囊内ではなく肝外胆管(左右肝管合流部より下流側)に結石が存在する胆石症である.高齢者に多く,男女比では男性にやや多くなっている.
閉塞性黄疸
著者: 岩下和広 , 岡庭信司
ページ範囲:P.356 - P.360
疾患の概要
黄疸はビリルビンが血中に増加し,全身の皮膚や粘膜が黄色に染色された病態であり,閉塞性黄疸は胆管が閉塞することにより生じる黄疸である.閉塞性黄疸をきたす疾患では胆管結石が最も頻度が多いが,炎症性疾患や胆道癌や膵臓癌といった悪性疾患まで多岐にわたる(表1).
褐色尿や皮膚の黄染が発見契機となることが多いが,結石や腫瘍による痛み,胆管炎による発熱もある.自覚症状が全くなく,他疾患の検査目的で施行した血液検査の異常で指摘されることもある.閉塞性黄疸に感染が加わると,急性胆管炎や急性化膿性胆管炎から敗血症に至るため,迅速な診断,治療が必要である.
急性膵炎(グルーブ膵炎含む)
著者: 川端聡
ページ範囲:P.362 - P.365
疾患の概要
疫学
厚生労働省の2011年の調査によると,わが国では急性膵炎は年間63,080人が発症し,近年増加傾向である.男女比は1.9:1で,男性は60歳代,女性では70歳代が最も多い1).急性膵炎全体に占める重症膵炎の割合は20%前後で推移しており,重症例は50歳代の男性に多い傾向がみられた1).アルコールの多飲や胆石の保有,肥満などが危険因子となる.
自己免疫性膵炎
著者: 木下博之
ページ範囲:P.366 - P.370
疾患の概要
自己免疫性膵炎はびまん性膵腫大と膵管狭窄像を特徴とし,時に膵腫瘤を形成する特有の膵炎であり,1995年にわが国より発信された疾患概念である1).血清免疫グロブリン(immunoglobulin:Ig)G4の上昇とIgG4陽性形質細胞の著しい浸潤を認め,膵外病変を伴うことも多く,IgG4関連疾患の膵病変と考えられている2).自己免疫性膵炎国際コンセンサス診断基準では,IgG4の関与する1型と好中球病変を中心とする2型に分類されるが1),わが国では自己免疫性膵炎は主として1型であり2),ここでは1型自己免疫性膵炎について示す.
十二指腸潰瘍
著者: 竹之内陽子 , 畠二郎 , 谷口真由美
ページ範囲:P.372 - P.374
疾患の概要
病態・原因
潰瘍とは消化管粘膜の限局性組織欠損であり,少なくとも粘膜筋板を越える深さの欠損をいう.潰瘍は病理学的に組織欠損の深さによって,Ul-Ⅰ(粘膜層のみの組織欠損,びらん),Ul-Ⅱ(粘膜筋板を越え,粘膜下層に達する組織欠損),Ul-Ⅲ(組織欠損が固有筋層にまで達するもの),Ul-Ⅳ(組織欠損が固有筋層を越え,漿膜に達したもの)までの4段階に分類される.
若年期のヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori:H. pylori)菌感染や非ステロイド性消炎鎮痛剤(nonsteroidal antiinflammatory drug:NSAIDs)の服用が原因で,粘膜による防御の働きと胃酸による攻撃とのバランスが崩れ,胃酸による粘膜障害をきたし発症する.したがって胃に近い十二指腸球部が好発部位である.
消化管穿孔
著者: 廣辻和子
ページ範囲:P.375 - P.379
疾患の概要
消化管穿孔とは,さまざまな原因で消化管の壁に孔が開き,内容物(胃液や胆汁・腸液・大腸内の便など)が腹腔内に漏出し,汎発性腹膜炎を引き起こす,手術適応を考慮すべき急性腹症である.穿孔とは壁を貫いてその外の空間に内容物が漏れ出ること,穿通とは壁を貫いてその壁の外が空間ではなく何らかの組織がある状態を指す.
穿孔部位により,上部消化管と下部消化管に分けられる.上部消化管の原因としては胃・十二指腸潰瘍が多く,その他に胃癌・特発性食道破裂・腹部外傷・誤嚥・医原性(内視鏡検査・治療)などがある.十二指腸は球部前壁では穿孔が多いが,後壁では穿通が多い.
消化管AGML(急性胃粘膜病変)
著者: 浅野幸宏 , 長谷川雄一
ページ範囲:P.380 - P.382
疾患の概要
急性胃粘膜病変(acute gastric mucosal lesion:AGML)は,1965年にacute erosive gastritis,acute gastric ulcer,hemorrhagic gastritisの3つの病態に分類し報告された.わが国においては,1973年に“急性に発症し,内視鏡あるいはX線検査で所見がみられる”病態の包括的な概念,すなわち一種の症候群として急性胃病変(acute gastric lesion:AGL)が提唱された.その後,AGMLの診断基準を“突発する上腹部痛,吐き気,嘔吐,時に吐血・下血の症状を伴って発症し,この際早期に内視鏡で観察すると,多くの場合,胃粘膜面に急性の異常所見,すなわち明らかな炎症性変化,出血,潰瘍性変化(びらん,潰瘍)が観察されるもの”と定義している.内視鏡所見としては,多発性のびらんや浅い潰瘍を認めることが多く,活動性の出血や凝血を伴う.しばしば,びらんや潰瘍は地図状を呈した特徴的な内視鏡所見を呈する.AGMLの主な成因は,精神的・身体的ストレスや薬剤〔ステロイド,非ステロイド性抗炎症薬(nonsteroidal antiinflammatory drug:NSAIDs)製剤,抗癌剤など〕などであり,薬物,食物なども挙げられる.
腸閉塞(イレウス)
著者: 山下安夫
ページ範囲:P.384 - P.388
疾患の概要
腸閉塞(イレウス)とは,何らかの原因で腸管内容の通過が障害された状態と定義される.従来,腸閉塞とイレウスは同義語として用いられてきたが,「急性腹症診療ガイドライン2015」1)において,“腸閉塞”と“イレウス”を区別することが提案され,“腸管が機械的に閉塞した場合を腸閉塞とし,機能性(麻痺性)のものをイレウスと呼ぶ”と定義された.
腸閉塞は,血流障害を伴わない単純性腸閉塞と血流障害を伴う複雑性腸閉塞(広義の絞扼性腸閉塞)に分類される(図1).単純性腸閉塞の原因は,小腸では開腹術後や炎症(Crohn病など)による癒着が最も多く,大腸では腫瘍が大部分を占める.一方,複雑性腸閉塞の原因は,小腸では開腹術後の索状物(バンド)による絞扼,ヘルニア嵌頓,腸重積,腸軸捻転など,大腸では乳児の腸重積と高齢者に好発する軸捻転が主なものである.イレウスは腸管の蠕動運動の低下により腸管内容物の通過障害をきたした状態で,麻痺性イレウスと痙攣性イレウスがある.麻痺性イレウスは開腹術後が最も多く,そのほかには種々の原因による腹膜炎,腹腔内出血などが原因で発症する.痙攣性イレウスの原因は,手術や外傷,神経障害,中毒などであるが,頻度は極めて低い.
大腸憩室炎
著者: 西田睦
ページ範囲:P.389 - P.391
疾患の概要
近年,わが国では大腸憩室の保有率が増加しており1,2),大腸憩室炎の頻度も増している.大腸憩室炎は急性疾患であるが,再発しやすく,簡便で無侵襲に施行可能なエコー検査(ultrasonography:US)による診断は有用である.
急性虫垂炎
著者: 大石武彦
ページ範囲:P.392 - P.396
疾患の概要
疫学と分類
急性虫垂炎は虫垂の急性化膿性炎症性疾患であり,急性腹症のなかでも高頻度に遭遇する疾患である.幅広い年齢に発症するが,10〜20歳代に好発する.虫垂炎は炎症の程度により組織学的に3つに分類され,カタル性,蜂窩織炎性,壊疽性の順に進行する.
ヘルニア(嵌頓)
著者: 喜舎場智之
ページ範囲:P.398 - P.403
疾患の概要
ヘルニア(hernia)には先天性と後天性があり,体内の臓器が本来あるべき部位から脱出した状態と定義される.腹部領域においては外ヘルニアと内ヘルニアに大別される(表1).脱出する臓器は消化管や腸間膜,大網がほとんどで,まれに卵巣や虫垂が脱出することもある.
腸管出血性大腸菌感染症(O157腸炎)
著者: 林健太郎
ページ範囲:P.404 - P.407
疾患の概要
大腸菌は家畜や人の腸内に常在し,そのほとんどは害がない.しかし,なかには下痢などの症状を引き起こす“病原性大腸菌”があり,細菌学的には菌の表面にある抗原(O抗原とH抗原)に基づいて細かく分類される.そのうち,ベロ毒素(Vero toxin:VT)を産生する大腸菌を“腸管出血性大腸菌(enterohemorrhagic Escherichia coli:EHEC)”と呼ぶ.代表的なものは,O157(60〜70%),O26(20%),O111(10%)などであるが1),重症化するものの多くは,大半が病原性の高いVT2を産生するO157である.本稿では,O157腸炎を中心に解説する.
O157腸炎は夏季に多いが冬季にもみられ,集団発生事例の報告は減ったものの,散発事例における患者数は漸増状態で,わが国でも毎年4,000人前後の発生が続いている1,2).
腹水の診かた(FAST,腹腔内出血,癌性腹水)
著者: 佐藤通洋 , 井上征雄 , 吉見登美子 , 横山一紀
ページ範囲:P.408 - P.414
FAST1)
FAST(focused assessment with sonography for trauma)は外傷の初期診療において,腹腔内出血,胸腔内液体貯留および心囊液貯留の検出に焦点を絞った簡易超音波検査法である.短時間に一定の走査を行う手技で,ショック症例では1分以内の施行が望ましい.走査部位は心囊,胸腔,肝周囲,脾周囲,骨盤腔であるが,気胸の診断を加えたextended FAST(eFAST,EFAST,E-FAST)や,下大静脈の観察による循環血液量の評価も行われている.
2章 心エコー
急性心筋梗塞(急性冠症候群)とその合併症
著者: 加賀早苗
ページ範囲:P.416 - P.421
疾患の概要
急性心筋梗塞の成因は,冠動脈プラークの破綻とそれに続く血栓形成による冠動脈内腔の閉塞であり,共通の機序によって生じる不安定狭心症を含めて,急性冠症候群(acute coronary syndrome:ACS)という一連の病態として扱われる1).急性心筋梗塞はさらに,貫壁性の虚血が生じていることを示唆する心電図上のST上昇を伴うST上昇型心筋梗塞(ST elevation myocardial infarction:STEMI)と,それを伴わない非ST上昇型心筋梗塞(non ST elevation myocardial infarction:NSTEMI)に分類される.
急性心筋梗塞と不安定狭心症は心筋壊死の有無(心筋バイオマーカーの上昇の有無)によって区別される.ACSの自覚症状は前胸部痛や前胸部圧迫感であるが,非典型的な症状や軽微な症状が重篤なACSの症状であることもまれではない.症状が20分以上持続する場合は,急性心筋梗塞の可能性が高い1).発症後,再灌流療法までの時間が遅れるほど心筋障害が進行して死亡率が上昇するため,早期診断が極めて重要である.
急性大動脈解離
著者: 木村豊
ページ範囲:P.422 - P.425
疾患の概要
疫学と病態
大動脈解離とは,日本循環器学会の「大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン(2011年改訂版)」1)によると“大動脈壁が中膜のレベルで二層に剝離し,動脈走行に沿ってある長さを持ち二腔になった状態で,大動脈壁内に血流もしくは血腫が存在する動的な病態”と定義されている.突然の激しい胸部または背部痛を主訴として発症する場合が多く,適切な治療が行われない場合には死亡率の高い疾患である.厚生労働省の人口動態調査によると,本疾患による死亡者は,毎年1万人弱程度となっている.発症原因は明らかではないが,高率に高血圧症を合併し,動脈硬化の危険因子の関与が示唆されている.またMarfan症候群などの結合組織疾患における,大動脈壁の脆弱性が発症原因となる場合がある.
典型的な症例では胸部痛や背部痛により発症するが,解離腔の位置および偽腔血栓化の状況によりさまざまな症状や病態を呈する.解離により冠動脈血流障害が生じた場合には心筋梗塞として,また頸動脈への解離進展により脳虚血を発症した際には,脳梗塞として治療が開始されている場合がある.これらの疾患の検査を行う際には,大動脈解離合併の有無を意識して検査を行う必要がある.
急性肺塞栓症
著者: 飯田典子
ページ範囲:P.426 - P.431
疾患の概要
病態
急性肺塞栓症(pulmonary embolism:PE),急性血栓肺塞栓症(pulmonary thromboembolism:PTE)はしばしば致命的な疾患で,臨床的に診断が難しい疾患の1つであるといわれている.典型的な症状として呼吸困難,チアノーゼなどが知られているが,急激なショックから突然死に至ることもある.心エコーは心電図や造影CTとともに,速やかに診断・治療を進める手掛かりを与えてくれる重要な検査である.PEは急性と慢性に大きく分けられ,2018年に日本循環器学会より「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断,治療,予防に関するガイドライン」が示されている1).
最近ではPTEと深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)を併せて静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism:VTE)と総称する.急性PEは,主に下肢あるいは骨盤内のDVTが塞栓源となり,起立,歩行,排便などの際に下肢の筋肉が収縮し,筋肉ポンプの作用により静脈還流量が増加することで,血栓が遊離して肺動脈(pulmonary artery:PA)を閉塞することが推測される.
たこつぼ型心筋症
著者: 谷口京子
ページ範囲:P.432 - P.434
疾患の概要
たこつぼ型心筋症の誘因は心身ストレスといわれている.閉経後の中高年女性に好発し,左室造影検査で壁運動異常所見が特徴的なたこつぼの形に見えることから命名されている.たこつぼ型心筋症は,症状や病態が急性冠症候群に類似しており,なかには鑑別が困難な場合もある.主訴は胸痛が多く,呼吸困難や動悸などを認める場合がある.また,本疾患は夏に多く秋に少ない傾向があり,1日のうちでは朝の発症が多いといわれている.
日本循環器学会による診断基準1)では,心尖部のballooningを呈する原因不明の疾患で,左室は“たこつぼ”に類似する形態を呈すると定義されている.除外基準にはA.冠動脈の有意狭窄病変の存在や冠攣縮,B.脳血管疾患,C.褐色細胞腫,D.心筋炎が挙げられており,脳血管疾患や褐色細胞腫などよる心筋障害は“たこつぼ様心筋障害”として特発例と区別されている1).
急性心筋炎(劇症型含む)
著者: 石神由美子
ページ範囲:P.436 - P.441
疾患の概要
疫学
心筋炎は心筋を主座とした炎症性疾患である.心膜まで炎症が及ぶと心膜心筋炎と呼ばれる.軽症例は確定診断が困難なために,わが国における発症率や死亡率の詳細は不明である.剖検例からの推測では,症候性心筋炎は剖検10万例当たり115例で,一方無症候性心筋炎は非心臓死剖検例の0.6%との指摘がある1,2).一過性に無症状で経過する軽症心筋炎はさらに多いと思われる.
心タンポナーデ
著者: 古島早苗
ページ範囲:P.442 - P.447
疾患の概要
病態
心タンポナーデとは,心膜液貯留により心膜腔内圧が上昇し心腔内圧を凌駕した結果,心室拡張期の静脈還流が障害され,心拍出量が低下することで循環不全をきたした状態であり,急性経過ではしばしばショックに陥る.心膜液貯留の原因は多岐にわたる(表1).
心膜液貯留量と心膜腔内圧は必ずしも相関せず,外傷,大動脈解離および心破裂,診断治療手技の合併症(冠動脈穿孔や心筋の穿孔)など,心膜液が急速に貯留した場合には心膜が広がることができないため少量の心膜液でもタンポナーデを呈するが,癌性心膜炎などで緩徐に貯留した場合には代償的に心膜が伸展するため,多量に貯留するまではタンポナーデをきたさない.また,心室内圧もタンポナーデ発生に関与するため,心室肥大や心室拡張末期圧が上昇している状態では,心膜腔内圧の影響を受けにくい.
3章 腎・泌尿器エコー
腎盂腎炎
著者: 白石周一
ページ範囲:P.450 - P.453
疾患の概要
腎の炎症性疾患のなかで最も多いのが腎盂腎炎であり,腎盂,腎杯および腎実質の細菌感染により引き起こされる.ほとんどは上行性感染であるが,まれにリンパ行性や血行性感染もみられる.病理組織学的には,局所的あるいは散在性の尿細管や間質の病変を主体とする間質性腎炎所見を呈する.
尿管結石
著者: 米山昌司 , 南里和秀
ページ範囲:P.454 - P.457
疾患の概要
尿管は腎盂に続き腎門の内下方から大腰筋の前面を下行し,総腸骨動・静脈の前を横切って骨盤内に入る.その後,骨盤外側壁に沿って走行し膀胱壁に進入し尿管口に開く.全長約25〜27cmで,生成された尿を蠕動により運搬する.
精巣捻転,精巣上体炎
著者: 河本敦夫
ページ範囲:P.458 - P.463
疾患の概要
陰囊の疼痛,腫張,そして発赤などを伴う急性発症の疾患群を急性陰囊症(acute scrotum)と呼ぶ.その原因から外傷性と非外傷性の2つに大別される.非外傷性の急性陰囊症にはさまざまな疾患があるが(表1),臨床的によく遭遇するのが精巣捻転と精巣上体炎である.
臨床所見からこの両者を鑑別することは難しく,画像検査が非常に重要となる.特に精巣捻転は治療までの時間が予後を決定し,緊急的外科処置が必要となる.急性陰囊症におけるエコーは,第一に精巣捻転の有無を評価する検査といってよい.
4章 婦人科エコー
Fitz-Hugh-Curtis症候群(FHCS)
著者: 金子南紀子 , 藤崎純 , 渡邉学
ページ範囲:P.466 - P.469
疾患の概要
疫学
1930年代にCurtisが淋菌性骨盤内感染症患者の開腹手術時に肝表面と腹壁間の癒着の存在を示し,その後Fitz-Hughが右季肋部の急性淋菌性腹膜炎を報告したことから,このFitz-Hugh-Curtis症候群(Fitz-Hugh-Curtis syndrome:FHCS)が提唱されることとなった.
現在,FHCSの主な起炎菌はクラミジアとされているが,淋菌が原因となる場合があることも知られている.わが国において性器クラミジア感染症は性感染症のなかで最も多く,男女ともに多数の保菌者の存在が指摘されている.FHCSは今後さらに増加する可能性が高く,エコー検査(ultrasonography:US)時に遭遇する機会も増えると考えられる.
異所性妊娠(妊娠)
著者: 宇治橋善勝 , 棟方伸一 , 狩野有作
ページ範囲:P.470 - P.473
疾患の概要
疫学
異所性妊娠とは,受精卵が正所である子宮内膜以外の部位に着床することと定義され,全妊娠中の1〜2%にみられる.異所性妊娠の95%は卵管妊娠であり,そのうち70%が膨大部で発生している.その他の着床部位には,卵巣,子宮頸管,腹膜,大網,帝王切開瘢痕部妊娠などがあるが,いずれもまれである.
異所性妊娠のリスクは卵管病変によって上昇するが,特にリスクを上昇させる要因としては,卵管手術,異所性妊娠,骨盤内感染症,生殖補助医療,喫煙などの既往歴が挙げられる.通常,子宮内避妊器具を装着している場合は妊娠が起こる可能性は低いが,妊娠した場合の約5%で異所性妊娠が生じる.また,生殖補助医療による妊娠では,異所性妊娠の発生率が2〜4%とされており,自然妊娠に比べて高率になる.
5章 血管エコー
腹部大動脈瘤破裂(切迫破裂)
著者: 山本哲也
ページ範囲:P.476 - P.480
疾患の概要
破裂の原因
動脈瘤破裂の誘因としてストレスや精神的興奮による高血圧,運動,筋力トレーニング,荷重労作,咳,アルコール,Marfan症候群における妊娠,出産が指摘されている1).また,安静時や日常動作時に破裂をきたすこともある.
孤立性上腸間膜動脈解離
著者: 八鍬恒芳
ページ範囲:P.481 - P.484
疾患の概要
疫学
孤立性上腸間膜動脈解離(isolated superior mesenteric artery dissection:ISMAD,以下,孤立性SMA解離)は比較的まれな疾患である.罹患率は,剖検例で6,666例中4例(0.06%)との報告1)や,救急患者の腹部CTで発見された826例中5例(0.60%)で認めたとの報告2)がある.50歳代前後の男性に多い疾患とされている3).
急性下肢虚血
著者: 和田理
ページ範囲:P.485 - P.489
疾患の概要
急性下肢虚血(acute limb ischemia:ALI)は,下肢の急激な血流減少を呈する病態であり,迅速な診断と適切な治療を行わなければ下肢の切断や生死にかかわる.
原因は外傷性や医原性を除けば塞栓症と血栓症に分類され(表1),血栓症に比べ塞栓症の頻度が高い.塞栓症は塞栓原により心原性と非心原性に分類され,その大半が心原性に由来する.
動脈穿刺部出血
著者: 石田啓介
ページ範囲:P.490 - P.493
疾患の概要
カテーテル治療は,バイパス術とともに血流改善に有効な血行再建術の1つである.冠動脈や下肢のみならず全身の血管に適応が拡大しており,近年は心臓の弁膜症においても治療が行われるようになった.診断,治療において動脈穿刺は必要不可欠であるが合併症のリスクを伴う.合併症を疑う主訴としては動脈穿刺部出血や腫脹,疼痛,止血困難などで,代表的な合併症としては,医原性仮性動脈瘤,医原性動静脈瘻,穿刺部血腫,動脈閉塞,感染症などが挙げられる.動脈の穿刺部位はさまざまで,カテーテルによる医原性仮性動脈瘤の発生頻度は穿刺部位により異なる.上腕動脈で0.046%,大腿動脈で1〜8%,橈骨動脈で0.03%という報告もある1).医原性動静脈瘻の発生頻度はさらに低く,大腿部で0.003〜0.86%,上肢においては数例の報告があるのみである1).
6章 小児エコー
肥厚性幽門狭窄症
著者: 岡村隆徳
ページ範囲:P.496 - P.499
疾患の概要
肥厚性幽門狭窄症は胃の幽門輪状筋の攣縮と幽門輪状筋の過形成による肥厚が原因となって幽門部に狭窄を生じ,胃幽門部における通過障害を起こす疾患である.発症原因は不明であるが,遺伝的要因に加え,感染や人工乳といった環境的要因が組み合わさって発症すると考えられている.生下時に認められることはなく,生後2週〜2カ月の乳児に好発する.男女比は4:1で男児に多い1,2).主症状は嘔吐であり,発症早期には嘔吐回数は多くないが,数日で頻回の噴水状嘔吐を呈するようになる.狭窄部が幽門部であるため,吐物に胆汁が混ざっていない非胆汁性嘔吐であることが特徴的である.触診では心窩部のやや右側に肥厚した幽門部をオリーブ様腫瘤として触知できることが多い.重症例では脱水症および低クロール性代謝性アルカローシスへ至り,活気不良や体重減少がみられるようになる.
中腸軸捻転
著者: 岡村隆徳
ページ範囲:P.501 - P.505
疾患の概要
中腸軸捻転は腸回転異常に合併する疾患であり,中腸軸捻転の病態の把握には腸回転異常の理解が重要である.正常例における腸管の発生(図1)1)では,中腸〔上腸間膜動脈(superior mesenteric artery:SMA)により栄養されている十二指腸から横行結腸中部までの腸管〕が胎生期に反時計方向に270°回転するが,この腸管発生の際に腸管の回転や腹膜・後腹膜への固定が完成しなかった状態を総称して腸回転異常と呼ぶ.
腸重積
著者: 岡村隆徳
ページ範囲:P.506 - P.510
疾患の概要
口側腸管が肛門側腸管内に引き込まれ腸管が重なり合った状態を腸重積と呼び,腸重積によって引き起こされる腸閉塞症を腸重積症という1).消化管ポリープ,Meckel憩室,重複腸管,感染性腸炎,血管性紫斑病,悪性リンパ腫などの器質的疾患は腸重積の発症原因となることがあり,腸重積の原因となるこの器質的疾患を病的先進部という1).腸重積は病的先進部が原因になっているものと,病的先進部が存在しない特発性腸重積に分類される.また,腸重積の発症部位として小腸-小腸型,小腸-結腸型,結腸-結腸型に分けられる.腸重積の多くが3歳までにみられる特発性腸重積であり,その場合はほとんどが小腸-結腸型の腸重積である.4歳以降の腸重積では病的先進部を伴っている可能性が高く,消化管のどの領域でも発症する可能性がある.
男女比は2:1で男児に多い1,2).腸重積の3大主徴は腹痛(または啼泣・不機嫌),血便,腹部腫瘤触知であり,消化管通過障害に伴い嘔吐を認める例もある.腸重積では腸管とともに腸間膜や腸間膜動静脈も引き込まれるため循環障害に伴う絞扼性変化をきたすことがあり,進行例では腸管虚血,壊死,穿孔によりショック状態を呈することもある.
基本情報
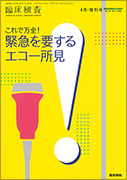
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
