今回の増刊号のテーマである“検査相談室”は,主に医師,看護師,薬剤師,医療事務といった医療者からの問い合わせ窓口として,年々そのニーズが高まっています.検査部内に具体的な機能ユニットとして検査相談室を設置している医療機関も存在しますが,実際の問い合わせにはまだ検査現場の担当者が個別対応している場合が多いと思われます.
診断・治療が医師個人の経験と裁量に委ねられていた時代から大きく変わり,現在ではエビデンスの集積に伴うガイドラインの構築と,最新の知見と技術に基づく診療方法の開発により,臨床の多様化・横断化が加速度的に進んでいます.他方,この変化は,臨床医が検査診断学の習得と実践に費やすことのできる時間と労力に物理的な制約を生じさせています.昔も今も1日は誰にとっても24時間しかありません.一部で指摘されている若手医師の“検査離れ”は,その象徴なのかもしれません.検査相談室へのニーズが高まる背景には,検査自体の多様化と相まって,これらの事情があるものと考えられます.
雑誌目次
臨床検査65巻4号
2021年04月発行
雑誌目次
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
はじめに フリーアクセス
ページ範囲:P.283 - P.283
一般検査
CKDの重症度の評価に用いるCGA分類について教えてください
著者: 丸橋遼太
ページ範囲:P.290 - P.291
慢性腎臓病(CKD)1,2)
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)は,一定以上の腎機能の低下が持続する病態群である.CKDは末期腎不全の原因であるとともに,心血管死のリスク要因ともなる.このため,腎臓専門医が介入して予後改善を計るべき患者を適切に把握するために提唱された概念がCKDである(表1).
健康診断で尿蛋白が1+であった場合は,腎臓専門医へのご高診を依頼したほうがよいのでしょうか?
著者: 平石直己
ページ範囲:P.292 - P.293
尿蛋白1+以上は末期腎不全(ESKD)や心血管疾患(CVD)のリスクが上昇する
尿蛋白1+以上の受診者は,−の受診者に比べて末期腎不全(ESKD)に至るリスクのみならず,心血管疾患や総死亡など臨床的に重要なアウトカムリスクが明らかに高いことが,一般住民を対象とした前向き研究をまとめた大規模研究やメタ解析において示されている.さらに,尿蛋白−に比べ,±,1+,2+以上と用量依存性にリスクが高くなることも示されており,推算糸球体濾過値(eGFR)で層別化した解析においても各eGFR群において同様の結果が示されている.
どのような患者が,造影剤の投与後に腎障害を起こしやすいのでしょうか?
著者: 横山貴 , 新田孝作
ページ範囲:P.294 - P.295
造影剤
主にCT検査や血管造影検査などに使用される造影剤の多くはヨード造影剤である.
急性腎障害(AKI)の早期診断に用いられている尿中バイオマーカーを教えてください
著者: 森田賢史
ページ範囲:P.296 - P.297
急性腎障害(AKI)とは
急性腎障害(acute kidney inury:AKI)は“さまざまな要因により腎機能が急激に低下する病態”と定義され,KDIGO®(Kidney Disease Improving Global Outcomes)の診断基準に基づく「AKI診療ガイドライン2016」1)に血清クレアチニンと尿量による診断基準および重症度分類が示されている(表1)1).
AKIは腎前性,腎性,腎後性に分類され,腎性AKIは腎前性AKIよりも院内死亡率が高い可能性があるため,区別して対応することが提案されている.また,早期診断および予後予測が臨床上重要であるので,血清クレアチニンに加えて,尿中バイオマーカーとしてL型脂肪酸結合蛋白(liver-type fatty acid-binding protein:L-FABP),好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(neutrophil gelatinase associated lipocalin:NGAL),N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ(N-acetyl-β-D-glucosaminidase:NAG),α1-マイクログロブリン(α1-microglobulin:α1-MG),β2-マイクログロブリン(β2-microglobuin:β2-MG)などの有用性が検討されている.
ベンスジョーンズ蛋白(BJP)の特徴を教えてください
著者: 西山大揮
ページ範囲:P.298 - P.299
ベンスジョーンズ蛋白(BJP)とは
ベンスジョーンズ蛋白(Bence Jones protein:BJP)については,1844年に英国・ロンドンの内科医であるWilliam Macintyreが,共通の症状をもつ患者尿が異常高比重であることに気付き,内科医であり病態化学者でもあったHenry Bence Jones医師に解析を依頼したことで発見された.
BJPは多発性骨髄腫などの形質細胞増殖疾患によって過剰に産生された免疫グロブリン遊離軽鎖とされている.遊離軽鎖(free light chain:FLC)とは免役グロブリン軽鎖(L鎖)で免疫グロブリン重鎖(H鎖)と対にならないものである.炎症における多クローン性高γグロブリン血症や腎機能障害ではこのFLCの血中濃度が上昇することはあるが,κ鎖とλ鎖は均等に上昇するため,κ/λ比は変化しない.しかし,多発性骨髄腫などの形質細胞増殖性疾患では単クローン性のFLCが産生されるため,κ/λ比が異常となる.FLCは単量体(もしくは二量体)で分子量が約22,000と比較的小さく,また陰性荷電も少ないことから腎糸球体で濾過される.
糸球体からの出血を評価するには,どのような検査を依頼すればよいですか?
著者: 小堀祐太朗
ページ範囲:P.300 - P.301
尿検査からわかること
尿は非侵襲的に採取できるため,腎尿路系および全身疾患のスクリーニング検査として広く用いられている.検査項目は,尿の色調観察,尿定性検査,尿沈渣検査があり,多くの病院で実施されている.そのなかでも,尿中有形成分を顕微鏡で観察する尿沈渣検査は,赤血球・白血球などの血液細胞や,腎尿路系を構成する上皮細胞,尿細管腔を鋳型として形成する円柱などを観察することができ,多くの情報を得ることができる.
特に尿沈渣中の赤血球はさまざまな形態を示すため,その特徴から出血部位が糸球体由来か非糸球体由来かを推定することができる.赤血球の膜の厚さが均一なものを非糸球体型赤血球といい,赤血球の膜の厚さが菲薄し不均一で多彩な形態を示すものを糸球体型赤血球という.
尿中リンパ球が増加した場合,どのような病態が考えられますか?
著者: 吉永治代
ページ範囲:P.302 - P.303
尿中リンパ球の形態学的特徴
リンパ球の大きさは好中球より小型で,N/C比が高く顆粒成分の少ない単核の細胞像を呈する.
染色性は,Sternheimer染色では核が青色〜青紫色を呈し,生細胞の場合は染色性がやや不良である(図1).必要に応じて,尿沈渣塗抹標本のMay-Grünwald Giemsa染色で細胞の詳細な確認を行う.尿白血球定性検査は陰性である.
尿沈渣検査でアデノウイルス感染症の評価はできますか?
著者: 井上真由
ページ範囲:P.304 - P.305
はじめに
同種造血幹細胞移植(HSCT)後にはアデノウイルス(AdV)やBKウイルス(BKV)などによる出血性膀胱炎(HC)が発生する可能性がある.特にアデノウイルス性出血性膀胱炎(AdV-HC)の合併は致死的経過となりうるため,AdVを早期に検出する必要がある.
原因となるAdVは11型が多く,AdV-HCの診断は,肉眼的血尿の観察と,PCR法などでの尿中AdVの検出によってなされるが,PCR法は結果が出るのに時間を要し,いまだ薬事承認もされていない1).そこで,近年,保険収載され,かつ簡易的に検査できる尿沈渣検査でAdV感染を疑う細胞が検出できると報告され始めている2,3).
わが国におけるHSCT後の遅発性(前処置終了後10日以降)HCのAdVによる発症頻度は約10%と報告されており,HSCT後患者の尿沈渣中に以下の細胞を認めた際には,AdV感染細胞を疑い,鏡検する必要がある.
尿沈渣検査で,HSCT後患者のAdV感染細胞を見落とさず検出することは重要である.
Fabry病患者の尿中にみられる,マルベリー細胞やマルベリー小体について教えてください
著者: 小林紘士
ページ範囲:P.306 - P.307
マルベリー細胞およびマルベリー小体の特徴
Fabry病患者の尿沈渣中にはマルベリー細胞,あるいはその細胞の一部と思われるマルベリー小体と呼ばれる,いずれも細胞内部の構造が渦巻き状を示す成分が認められる(図1,2).顕微鏡で観察するときに微動を細かく調整して観察することが鑑別のポイントとなる.渦巻き状構造こそが最大の特徴であるが,卵円形脂肪体,あるいは脂肪顆粒と比較しても渦巻き状構造以外の所見で判別することは困難と思われる.しかし,ズダンⅢ染色での染色性が不良であることが,卵円形脂肪体や脂肪顆粒との鑑別ポイントの1つとなる.
ほかの類似成分として,抗真菌薬投与中の患者尿で真菌薬の影響によって変形した真菌が挙げられるが,この成分には光沢感はなく,重屈折偏光像も示さないため判別が可能である.一方で,近年では渦巻き状構造を示さないマルベリー細胞あるいはマルベリー小体も認められることが報告されており,それらを初見で鑑別することは非常に困難であると思われる.まずは典型的な渦巻き状構造のマルベリー細胞,マルベリー小体を確実に検出することが重要と思われる.
多発性囊胞腎の患者尿で認められる特徴的な赤血球について教えてください
著者: 服部亮輔
ページ範囲:P.308 - P.309
尿沈渣検査で認められる赤血球
尿沈渣検査で認められる赤血球は腎・尿路系の出血性病変を示唆する有形成分であり,出血部位の違いによって尿中赤血球形態が異なる.糸球体腎炎などによる糸球体性血尿では“糸球体型赤血球”が認められ,非糸球体性血尿である下部尿路(腎盂,尿管,膀胱,尿道)からの出血では“非糸球体型赤血球”が認められる1).非糸球体型赤血球の形態には,円盤状赤血球,球状赤血球,円盤・球状移行型赤血球,膜部顆粒成分凝集状脱ヘモグロビン赤血球がある.多発性囊胞腎の患者尿では,囊胞液の影響を受けて膜部顆粒成分凝集状脱ヘモグロビン赤血球が認められる.
胸水・腹水検査で滲出液と漏出液の鑑別法について教えてください
著者: 金並真吾
ページ範囲:P.310 - P.311
滲出液と漏出液との鑑別する意義
胸水・腹水は胸腹膜からの分泌・再吸収などによって生理的変動の範囲内に維持されている.この生理的変動を超えると腔内に液体が貯留する.滲出液と漏出液とでは発生機序は異なる.両者を鑑別することは,原因疾患を推定し治療方針を決めるために重要である1).
関節液の診断に必要な関節液検査項目を教えてください
著者: 横川直人
ページ範囲:P.312 - P.313
3C(cell count,culture,crystal)が必須である.関節液検査は治療方針の変更にかかわるため,迅速に結果が得られることが望ましい.
血液
機械法(フローサイトメトリー)による血算と肉眼法(鏡検)による血算の違いを教えてください
著者: 常名政弘
ページ範囲:P.314 - P.315
血球数算定
機械法による血算の基本的な原理には電気抵抗方式が用いられているが,近年ではフローサイトメトリー(FCM)法も利用されている.電気抵抗方式は細胞の容積によって分類しているため,破砕赤血球や巨大血小板の出現時には他の血球数に影響を及ぼすこと(誤差要因)が知られている.また,有核赤血球(赤芽球)は,核が残存し白血球として分類される.一方,FCM法では内部構造やメーカー独自の染色によって,それらの影響を抑えて測定される1).しかし,一部の疾患や病状で上記の細胞が多数出現している場合ではFCM法でも影響を受けることがある.そのようなときは肉眼法(鏡検)による補正が必要である.
前回値と比べて血算値が大きく乖離する場合に考えられる原因は何ですか?
著者: 韮澤恵 , 増田亜希子
ページ範囲:P.316 - P.317
A 検体に起因するものと患者の状態に起因するものに大別される
乖離の原因は2つに大別される
前回値と比べて血算値が大きく乖離する原因は以下の2つに大別される.
MCHCが異常高値となる原因を教えてください
著者: 佐藤尚武
ページ範囲:P.318 - P.319
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)
平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)は赤血球個々のヘモグロビン(Hb)濃度の平均値である.成人の基準範囲は32〜35g/dLであるが,年齢変動があり,小児は36g/dLが上限である.
血液検査でRDWやMPVなどのデータが同時に出てきます.評価方法を教えてください
著者: 竹田知広 , 近藤弘
ページ範囲:P.320 - P.321
赤血球粒度分布幅(RDW)(図1)
赤血球粒度分布幅(red cell distribution width:RDW)は赤血球の粒度分布曲線から計測する赤血球容積分布の指標で,赤血球大小不同症では高値を示す.粒度分布曲線は横軸に血球容積,縦軸に血球の相対個数(%)をプロットして平滑化したもので,平均赤血球容積(MCV)が赤血球ヒストグラム全域から算出されるのに対して,RDWは粒度分布曲線の左脚の血小板凝集塊,大血小板,電気的ノイズ,および右脚の凝集赤血球などを除外して計算する.RDWは変動係数(CV)(%)または標準偏差(SD)(fL)で表す.これらには装置の測定原理,報告により差がみられる.
破砕赤血球が何%あると有意な所見といえますか?
著者: 土屋逹行
ページ範囲:P.322 - P.323
破砕赤血球とは
破砕赤血球(schizocyte, red cell fragment)とは,循環血中で機械的な機序によって破砕された赤血球断片である.血栓性微細血管性貧血(TMA)と呼ばれる微細血管における血栓形成によって破壊されるため出現するとされている.
末梢血液塗抹標本(以下,標本)で破砕赤血球が認められる代表的な病態は,赤血球破砕症候群(red cell fragmentation syndrome)と一括して呼ばれる播種性血管内凝固症候群(DIC),血栓性血小板減少性紫斑病(TTP),溶血性尿毒症症候群(HUS)などである.いずれも重篤な病態で迅速な診断と対処が必要である.検査室からの破砕赤血球を認めるというコメントは,このような病態の診断のきっかけになる重要な情報である.判定は目視によって行うので,標本を観察する臨床検査技師の技量が求められる.
白血球の偽Pelger核異常の意義を教えてください
著者: 野田幸代
ページ範囲:P.324 - P.325
家族性Pelger核異常(Pelger-Huët anomaly)
遺伝性Pelger核異常は核膜上の蛋白質であるラミンBレセプター(LBR)の遺伝子変異による,顆粒球の核形態異常(低分節)を特徴とする常染色体優性遺伝である.健常人好中球の核は通常2〜5分節で,3分節が最も多く認められる.しかし,本症では文節数が1〜2分節と少なく,好酸球や好塩基球にも同様の変化を認める.発症は約6,000人に1人の割合といわれ,ヘテロ接合体の好中球は2分節にとどまり,左右対称のメガネ様が多数認められる.一方,ホモ接合体では核の分節がなく,太い桿状,あるいは類円形の単核を呈するものが多く,好中球遊走能の低下が報告されている.診断には,家族性に出現したかどうかの検索が必要となる.
大型血小板が認められた場合の考え方を教えてください
著者: 三ツ橋雄之
ページ範囲:P.326 - P.327
大型血小板とは
大型血小板とは正常な血小板よりも大きな血小板であり,正常の血小板が直径2〜3μm程度に観察されるのに対し,4μm以上を呈するものである.塗抹標本では赤血球との比較で大きさを評価し,赤血球の直径の約半分である4μmから赤血球大(約8μm)までのものを大血小板,赤血球サイズを超えるものを巨大血小板(giant platelet)と呼ぶことが多い.
大血小板や巨大血小板はいくつかの先天性疾患や後天性の病態で出現するが,健常人でも少数の大血小板や巨大血小板がみられることがあるため,血小板減少の有無や血小板形態,出血などの臨床症状や検査値異常の有無などを合わせた評価が必要である.
血小板数が偽低値を呈する原因と,その対処を教えてください
著者: 金子誠
ページ範囲:P.328 - P.329
血小板数減少症とは
末梢血血小板数の基準値は,基準個体値(健常者)の分布から算出したメーカー推奨値を使用することが多いが,一般的には15〜45万/μL1)である.血小板減少症はこの基準値を下回るもので,軽度(15〜10万/μL),中等度(<10万/μL),重度(<5万/μL)に分類される.一般的に2桁から1桁(万/μL)へ減少している中等度以下の値であると異常が認識されやすい.特発性血小板減少性紫斑病(immune thrombocytopenia:ITP.英文では免疫性と表記される)は10万/μLを下回る場合が診断基準である.
血小板数が偽高値を呈する原因は何ですか?
著者: 石井清 , 小倉加奈子
ページ範囲:P.330 - P.331
血小板数偽高値とは
血小板数偽高値とは,生体内で血小板増加が起きていないにもかかわらず,測定値で高値を示す現象である.この現象は自動血球計数装置による測定時に限って起こり,血小板以外の物質を血小板と誤認識することで生じる.
血液疾患以外におけるフローサイトメトリーの活用について教えてください
著者: 谷田部陽子 , 涌井昌俊
ページ範囲:P.332 - P.333
フローサイトメトリーについて
フローサイトメトリー(flow cytemetry:FCM)というと血液学では造血器腫瘍検査のイメージが強い.しかし,FCMは細胞の表面または内部に存在する抗原決定基(エピトープ)と,エピトープに対する抗体とを反応させて測定することで,細胞の性質を見分けることができる.したがって,白血球以外にも赤血球や血小板など,細胞であれば測定が可能で,研究など多様な方面で利用されている手法である.
検体検査における抗凝固剤添加(EDTA,クエン酸Na,ヘパリン)の使い分けについて教えてください
著者: 下村大樹
ページ範囲:P.334 - P.335
凝固させないメカニズム
抗凝固剤の違いによって血液を凝固させないメカニズムが異なる.エチレンジアミン四酢酸(EDTA)とクエン酸ナトリウム(sodium:Na)は,凝固反応に不可欠なカルシウムイオン(Ca2+)をキレートすることによって血液凝固を阻止する.ヘパリンは抗凝固として働くアンチトロンビンと結合し,主にトロンビン,活性化Ⅹ因子を阻害することによって血液凝固を阻止する.なお,採血管に含有されている抗凝固剤の性状は,EDTAとヘパリンが粉末,クエン酸Naが溶液である.
血液透析の際に凝固検査を実施する意義を教えてください
著者: 岩村菜々美 , 木村秀樹
ページ範囲:P.336 - P.337
血液透析では抗凝固薬が不可欠
血液は異物に接触すると凝固する性質をもっており,異物と接触した際に血液を凝固させて異物が全身に拡散するのを防止する.しかし,血液透析などの体外循環では,血液を一度体外に出して再び体内に戻すという操作を連続的に行うため,血液回路やダイアライザといった異物と血液が接触した場合,凝固カスケードが亢進して体外循環回路の閉塞を起こす.そのため血液透析を行う際には抗凝固薬を用いて血液凝固を阻止することが必要不可欠となる.
コントロールが困難な術後出血に対して有用な血栓止血学的検査を教えてください
著者: 田村利尚 , 平田敬治 , 岡本好司
ページ範囲:P.338 - P.339
止血の機序
止血機構は血管,血小板,凝固因子,線溶因子,それらのインヒビターによってバランスが保たれており,これらのいずれか,あるいは複数の因子が質的,量的に異常をきたせば正常の止血は行われなくなる.コントロール困難な術後出血に遭遇した場合,止血機構の破綻,すなわち出血傾向の原因を探らなければならない.
直接経口抗凝固薬(DOAC)が測定系へ影響する凝固検査と影響しない凝固検査を教えてください
著者: 鈴木敦夫
ページ範囲:P.340 - P.341
DOACの作用機序と種類
直接経口抗凝固薬(DOAC)の作用は,同じ経口抗凝固薬であるワルファリンのそれとは異なり,凝固反応の過程で生じる“活性化した”凝固因子を阻害することで抗凝固作用を発揮する.現状,わが国では,活性化第Ⅹ因子(Ⅹa)を標的とした直接抗Ⅹa薬であるリバーロキサバン(イグザレルト®),アピキサバン(エリキュース®),エドキサバン(リクシアナ®)と,トロンビンを標的とした直接抗トロンビン薬であるダビガトラン(プラザキサ®)が上市されている.
凝固異常を示唆する出血が認められないのにAPTTが延長する場合の原因は何ですか?
著者: 松田将門
ページ範囲:P.342 - P.343
APTT延長の機序を考える
血液凝固反応はリン脂質とCa2+を要する,凝固因子の連続的な活性化反応である.活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)は内因系および共通系凝固因子がかかわる凝固反応を反映する.APTT延長の機序には凝固反応進行に必要な要素の不足,進行を阻害する物質の存在が考えられる.前者の例には血友病に代表される凝固因子欠乏があり,後者の例には凝固因子に対する抗体を発生する後天性血友病,活性化凝固因子に結合する薬剤の使用,リン脂質に対する抗体をもつ抗リン脂質抗体症候群などがある.これら各要因の性質を考慮することで効率的に原因検索ができる(図1).なかでも,被検血漿に正常血漿を添加してAPTT延長の“補正の可否”を評価するクロスミキシング試験は有用である.
ワルファリン服用患者におけるLAテストの実施方法を教えてください
著者: 内藤澄悦 , 家子正裕
ページ範囲:P.344 - P.345
ループスアンチコアグラントの定義と測定法
ループスアンチコアグラント(lupus anticoagulant:LA)は,リン脂質依存性の凝固時間検査を用いて検出される抗リン脂質抗体(aPL)である.“個々の凝固因子活性を阻害することなく,リン脂質依存性の凝固反応を阻害する免疫グロブリン”と定義される.
LAの測定は国際血栓止血学会標準化委員会(ISTH-SSC)の推奨する方法に従い,活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)と希釈ラッセル蛇毒時間(dRVVT)の延長でスクリーニングし,過剰リン脂質の添加により延長した凝固時間が短縮すること,および凝固時間の延長が凝固因子欠損や抗凝固薬の混入ではない場合にLAと判断する1).
臨床化学
ALPアイソザイム検査で,ALP3型が高値です.原因と解釈について教えてください
著者: 山田将臣
ページ範囲:P.346 - P.347
ALPアイソザイム検査
アルカリ性フォスファターゼ(ALP)はAST,LDのように細胞損傷によって遊出し,血清中に増加する酵素ではなく,臓器内での産生増加を機序とし,血清中で上昇する酵素である.さまざまな臓器から産生されるため,総活性が増加した際にはアイソザイム解析を行うことで由来臓器の鑑別につながる.電気泳動により表2に示す通り,5つに分画される.ALP3型は等電点が近いALP2型,高分子ALP5型と易動度が重なるため,ノイラミニダーゼやプロテアーゼ処理により易動度を変化させ,区別する必要がある.
血清Na値,Cl値が前回値からの臨床経過と合致しません.原因と解釈の仕方を教えてください
著者: 戸枝義博
ページ範囲:P.348 - P.349
血清NaおよびCl測定の概要
血清ナトリウム(Na)・塩素(Cl)値は,水代謝や酸塩基平衡の異常の推定に不可欠な検査である.日常検査法は,簡便・迅速なイオン選択電極(ion selective electrode:ISE)法であり,生化学自動分析装置では,全て希釈法(希釈電位差法)である.ISE法は電極反応であることから,電極膜の安定性を維持する使い方が重要である.また,Cl電極では特にブロムイオン(Br−)やヨウ素イオン(I−)に対する選択性がClイオン(Cl−)よりも高い.したがって,Cl値が単独で高値の場合はこれらの元素を含有する薬剤のチェックが必須である.
透析液の電解質は血液ガス分析装置で測定してもよいのですか?
著者: 白井秀明
ページ範囲:P.350 - P.351
透析液成分濃度を血液ガス分析装置で測定できる条件1)
日本血液浄化技術学会(JSTB)が認証した血液ガス分析装置で,かつ“校正パラメータ”が搭載された分析装置(表1)であれば測定してもかまわない.血液ガス分析装置は,血液中の各物質濃度を測定するための測定条件が決められている.通常の血液測定モードで透析液を測定すると濃度誤差を生じる.透析液を正しく測定するためには,上記の条件が備わった装置で測定することが必須である.
入院した患者さんの残余血で脂質検査を追加する場合の注意点はありますか?
著者: 山下計太
ページ範囲:P.352 - P.353
脂質検査の臨床的意義
代表的な脂質検査である中性脂肪(TG),HDLコレステロール(HDL-C),LDLコレステロール(LDL-C)は脂質異常症のスクリーニング検査として冠動脈疾患など動脈硬化性疾患の発症リスクや治療予後の因子の評価として用いられる1).
プロカルシトニン(PCT)が高値です.敗血症の所見と一致しません.解釈の仕方を教えてください
著者: 三好雅士
ページ範囲:P.354 - P.355
プロカルシトニン(PCT)の産生機序
プロカルシトニン(procalcitonin:PCT)はカルシウム代謝に関与するカルシトニンの前駆体である.生理条件下では甲状腺C細胞で合成・分泌され,ホルモン活性をもたない.一方で,細菌感染時には,エンドトキシンや炎症性サイトカインの刺激によって肺・腎臓・肝臓など甲状腺外の全身組織から産生される.これらの細胞ではPCTをカルシトニンに切断する酵素が存在せず,PCTのまま血中に分泌されるため,濃度が上昇する.
アルブミンのデータをみるときに,測定法に注意しなければならないのはなぜですか? また,どんなことに注意する必要がありますか?
著者: 村本良三
ページ範囲:P.356 - P.357
血清アルブミンの日常検査法の現状と標準化
血清アルブミンの日常検査法には,ブロムクレゾールグリーン(BCG)法,ブロムクレゾールパープル(BCP)法および改良BCP法の3法がある.しかし,3法の測定値には違いがみられ,臨床的に問題となる低アルブミン域において乖離が生じる.BCG法はアルブミンのみならずグロブリン類,特に急性期蛋白とも反応する.BCP法はグロブリン類とはほとんど反応しないものの,還元型に比べて酸化型との反応性が高く,δ-ビリルビンおよび透析患者で上昇する内因性薬物結合阻害因子による負誤差がある.改良BCP法はペニシリンGの大量投与による負誤差が指摘されているものの,従来のBCP法における酸化型と還元型の呈色度差を解消した正確度が高い測定法である.
標準化対策としては標準物質の統一が有効であるが,日常検査3法の反応性の違いから,血清アルブミン測定においては効果がない.このため,日本臨床検査医学会では日常検査法の統一化の方針を固めた.現在,改良BCP法による標準化が進められている.
尿酸値が異常低値を示す場合の原因と解釈について教えてください
著者: 竹林史織
ページ範囲:P.358 - P.359
尿酸値の臨床的意義
尿酸値(UA)の共用基準範囲は男性が3.7〜7.8mg/dL,女性が2.6〜5.5mg/dLである.異常低値(1.0mg/dL以下)を示す疾患として,①尿酸産生低下型:キサンチンオキシダーゼ欠損症,プリンヌクレオチドホスホリラーゼ欠損症,5-ホスホリボシル-1-ピロリン酸合成酵素欠損症,②尿酸排泄亢進型:腎性低尿酸血症が挙げられる1).
異常低値が継続的か一時的か確認を行い,分析前・分析中における変動要因についてもチェックする必要がある(図1).
トロポニンT/Iが陽性ですが,明らかな心筋傷害は認めません.どのようなことが考えられますか?
著者: 石橋みどり
ページ範囲:P.360 - P.361
トロポニン(Tn)測定の意義
トロポニン(Tn)は筋肉の収縮調節をつかさどるフィラメントを構成する蛋白複合体である.心筋トロポニン(cTn)は90%以上が心筋細胞の構造フィラメントに,約6%が可溶性成分として細胞質に存在する.心筋特異性が極めて高く,急性冠症候群(ACS)の診断に有用である.
cTnは2000年のESC/ACC急性心筋梗塞(AMI)診断の改定によってAMI診断基準に記載された.また,2012年からは「心筋梗塞の国際定義 第3版」1)において第1選択マーカーとして推奨されている.ACSの早期診断に有効で,高感度法では2時間未満の超急性期にも有用である(表1)2).他のマーカーと比較して発症後,長時間にわたって高値が継続するので,診断有用性が高い(図1).また,心不全患者の予後予測マーカーとしての有用性も報告されている3).
救急診療で血糖値が1,000mg/dLでした.次に必要な検査を教えてください
著者: 才津旭弘 , 小谷和彦
ページ範囲:P.362 - P.363
緊急性のある高血糖をみたら,一般的に①糖尿病ケトアシドーシス,②高血糖高浸透圧症候群,③劇症1型糖尿病を想起する.まず,血液一般,尿素窒素,クレアチニン,ナトリウム,カリウム,クロール,血糖,HbA1c,尿検査(尿糖,尿ケトン体),血漿浸透圧,血中ケトン体分画,乳酸,動脈血液ガス(pH,PaCO2,HCO3−)を検査して診断と治療を迅速に進める.
BNPとNT-proBNPが乖離する原因を教えてください
著者: 北川文彦
ページ範囲:P.364 - P.365
BNPとNT-proBNPの有用性
BNPとNT-proBNPは,心不全の診断や重症度および予後評価などに有用である.日本循環器学会ほかが提唱する「急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)」1)では,両バイオマーカーとも心不全における診断,重症度および予後評価において測定意義が高く,心不全マーカーとしての有用性は同等としている.
骨吸収マーカーと骨形成マーカー,1つずつ測定するとしたら,何がよいのでしょうか?
著者: 三浦雅一 , 佐藤友紀
ページ範囲:P.366 - P.367
骨代謝マーカーとは
骨代謝マーカーは,骨粗鬆症に代表されるような代謝性骨疾患や悪性腫瘍の骨病変の診断の診療に際して,骨代謝を非侵襲的に評価するための動的指標として知られている1,2).
骨芽細胞に由来する酵素である骨型アルカリホスファターゼ(BAP)は骨形成マーカーとして,破骨細胞由来の酵素である酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ5b(TRACP-5b)は骨吸収マーカーとして用いられる.コラーゲンの生成過程におけるプロコラーゲンの分解産物であるⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(P1NP)は骨形成マーカーに属し,コラーゲン線維の分解産物〔デオキシピリジノリン(DPD),Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX),Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド(CTX)〕は骨吸収マーカーに属する.骨形成あるいは骨吸収のいずれにも属さない物質を骨マトリックス関連物質と呼び,これらに属する骨代謝マーカーとして低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)がある.
直接ビリルビンが紹介元のデータと大きく違っていた場合,どのようなことが考えられますか?
著者: 川崎健治
ページ範囲:P.368 - P.369
直接ビリルビンが紹介元のデータと大きく違っていた場合は,紹介元と自施設の試薬が異なることが原因である.患者の身体所見や経過,検体の色調などの臨床情報と直接ビリルビンの測定値が乖離するならば,M蛋白や薬剤など検体中の成分による影響が考えられるため1,2),精査が必要である.臨床情報との乖離がない場合は,試薬中の成分とビリルビン分画の反応性の違いに起因しており(図1),しばしば閉塞性黄疸の減黄期の測定値でみられる.紹介元から直接ビリルビンの測定法に関する情報を入手し,試薬性能を理解したうえで測定値を解釈する必要がある.
試薬の添付文書にビリルビン分画の反応性が記載されていない場合があるので,表1の情報を参照する.詳細については販売元から正確な情報を手に入れるとよい.
ACTHとコルチゾールで臨床的に解離を認める原因を教えてください
著者: 山下美保
ページ範囲:P.370 - P.371
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)とコルチゾールは同時に測定することによって,視床下部-下垂体-副腎皮質系の機能評価を行うことができる.一般的に,ACTH・コルチゾールがともに高値の場合はACTH依存性Cushing症候群,ともに低値の場合は続発性副腎皮質機能低下症,ACTH高値・コルチゾール低値であれば原発性副腎皮質機能低下症,ACTH低値・コルチゾール高値であればACTH非依存性Cushing症候群と判断し,精査する.通常は血中ACTH/コルチゾール比は2前後であるが,この比がさまざまな原因で変化し,判断に迷う場合が生じてしまう.
最近,ISO 15189という用語を聞きます.精度管理の方法など,今までと何が変わったのでしょうか? 精度がよくなったのでしょうか?
著者: 桑克彦
ページ範囲:P.372 - P.373
ISO 15189とは
ISO 15189「臨床検査室—品質と能力に関する要求事項」は2003年の第1版に始まり,現在は2012年の第3版1)である.これは「品質マネジメントシステム—要求事項」(ISO 9001)と「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」(ISO/IEC 17025)の内容を臨床検査に適用できるようにしたものである.①品質マネジメントシステム(QMS)を構築でき,②自らの能力の評価に使用でき,また③認定にも使用できる.
TSHのハーモナイゼーションの進捗状況と今後の予定について教えてください
著者: 菱沼昭
ページ範囲:P.374 - P.375
TSHのハーモナイゼーションの概要
日本国内で甲状腺刺激ホルモン(thyroid-stimulating hormone:TSH)測定試薬を販売している試薬メーカーは10社ある.2021年3月末日をもって10社のTSH検査値はハーモナイゼーションされるので,このときから各社TSH値のばらつきはなくなる.なお,日本人の20〜60歳の共通基準範囲は0.61〜4.23mIU/Lとなる.
肝臓の線維化マーカーをインデックスも含めて教えてください
著者: 石嶺南生
ページ範囲:P.376 - P.377
肝臓の線維化評価には肝生検による組織診断がゴールドスタンダードであるが,侵襲的であり出血のリスクを伴うことや,採取する箇所がごくわずかなためサンプリングエラーが生じるなどの問題がある.そのような問題を克服するために,これまで非侵襲的に実施できる肝線維化評価法が種々開発され,臨床応用されている.本稿では,代表的な肝線維化マーカーを紹介する.
免疫・輸血
非特異反応による腫瘍マーカーの偽陽性が疑われる場合,どのような対応を期待できますか?
著者: 阿部正樹
ページ範囲:P.378 - P.379
非特異反応解析のためのフローチャート
図11)のフローチャートによって解析を行う.誌面の都合上,説明は簡略化するので,詳細は文献2)を参照いただきたい.
スクリーニング的にCA19-9を測定したら62U/mLでした.どう考えたらよいでしょうか?
著者: 山田俊幸
ページ範囲:P.380 - P.381
CA19-9の特徴
CA19-9は最も利用されている膵胆道系の腫瘍マーカーである.物質としてはモノクローナル抗体NS19-9によって認識される糖鎖抗原部分であり,その抗原を末端に有する細胞膜の糖蛋白が血中に遊離してきたものが測定されている.糖蛋白の構造が一様ではないことと測定条件の違いが相まって,試薬間差が生じる原因になっている1).
また,抗体に認識される抗原は癌細胞以外でも発現されているため,種々の良性疾患でも陽性となる.臨床的な陽性陰性判定のカットオフ値は,検査が世に出た当初から37U/mLと設定されており,悪性腫瘍を疑うのは100U/mL以上とされる.結論としては,62U/mLという値が,悪性腫瘍の初期の段階を意味するのか,腫瘍とは関連のない要因による値なのか,その判断は困難である.
免疫グロブリン定量(IgG,IgA,IgM)検査で注意すべきことを教えてください
著者: 井本真由美
ページ範囲:P.382 - P.383
免疫グロブリン測定の臨床的意義
免疫グロブリンが増加する高γグロブリン血症のうち,モノクローナルに異常増加を認める病態はM蛋白血症と呼ばれる.多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症などの悪性疾患や,良性の状態にあるMGUS(monoclonal gammopathy of undetermined significance)などが含まれる.ポリクローナルに免疫グロブリンが増加する高γグロブリン血症には,慢性感染症,肝硬変,膠原病やIgG4関連疾患がある(表1,21)).
キャピラリー電気泳動によるM蛋白の検査法について教えてください
著者: 簗瀬直穂美
ページ範囲:P.384 - P.385
キャピラリー電気泳動(CE)法の可能性
蛋白分画検査はセルロースアセテート膜を支持体とした電気泳動(cellulose acetate membrane electrophoresis:CAEP)法から,キャピラリー電気泳動(capillary electrophoresis:CE)法に移行しつつある.分解能,検出感度に優れるCE法は,単クローン性免疫グロブリン(M蛋白)のスクリーニングに適している.また,M蛋白量の測定やイムノタイピングによるM蛋白の同定が可能である.
ただし,「多発性骨髄腫の診療指針」1)では治療の判定基準とするM蛋白の検出および消失は免疫固定法(immuno fixation electrophoresis:IFE)で確認すると記載されている.したがって,自治医科大学附属病院臨床検査部でもM蛋白の同定はIFEで検査しているのが現状である.
皮膚筋炎のマーカーが複雑です.ぜひ整理して教えてください
著者: 三枝淳
ページ範囲:P.386 - P.387
皮膚筋炎とは
多発性筋炎/皮膚筋炎は,左右対称性の近位筋の筋力低下を主徴とする全身性自己免疫疾患(膠原病)である.特徴的な皮膚症状を伴う場合は皮膚筋炎,伴わない場合は多発性筋炎とされる.筋症状に加えて間質性肺炎,悪性腫瘍の合併がみられることも多く,これらの重症度が予後を左右する.
以前は,皮膚筋炎の診断のために測定可能な自己抗体は抗Jo-1抗体のみであった.しかし,近年はさまざまな筋炎特異的自己抗体が同定されており,抗アミノアシルtRNA合成酵素(ARS)抗体(抗Jo-1抗体を含む),抗MDA5抗体,抗TIF1-γ抗体,抗Mi-2抗体の4つが測定可能となった.これらの自己抗体は,皮膚筋炎の診断に有用であるだけでなく,臨床像と密接に相関することから,皮膚筋炎の分類,合併症および予後の予測,治療方針の決定に極めて有用である.
リウマトイド因子と抗CCP抗体の比較は,今はどうなっていますか?
著者: 本島新司 , 中下珠緒
ページ範囲:P.388 - P.389
リウマチ因子(RF)は1940年代に発見され,1958年に米国のRA(rheumatoid arthritis.関節リウマチ)分類基準に入れられた.しかし,長年,診断などに使用されているにもかかわらず,RFの産生機序やRA発症への関与機序はよくわかっていない1).一方,抗シトルリン化ペプチド抗体(ACPA.抗CCP抗体として臨床で測定する)は1990年代にその存在が明確になった.ACPAに関しては,その産生機序,ヒト白血球抗原(HLA)との関係,関節炎発症に対する関与が研究され,RA発症に非常に重要な役割を果たしていると考えられている1).
それでは,RF測定はどうでもよいか,といわれると,そうではなく,2010年RAの新分類基準(表1)2)でも同等の扱いになっている.理由は,RAにおける感度(陽性率)がほとんど同じであるからである(表2)3,4).しかし,特異度は異なり,RFは85%程度,抗CCP抗体は95%程度である1).そのため,RF陽性ではRA以外の疾患がないか注意すべきである.疾患のない若年者ではRF陽性は5%以下であるが,70歳では25%という報告もある4).変形性膝関節症の75歳高齢者にRFは1/4に陽性になる可能性があり,RAと診断されてしまう可能性があるので注意が必要である.RFも抗CCP抗体もcut-off pointを上げると特異度は上がるが,感度が低下する.
最近のイムノクロマト法の精度はどうですか?
著者: 稲野浩一
ページ範囲:P.390 - P.391
イムノクロマト法の精度を支配する要因
イムノクロマト法試薬が医療機関で一般的に使われるようになったのは2000年ごろからなので,約20年が経過したことになる.インフルエンザウイルス感染の抗原検査を中心に,より簡便に,より早く,より精度が高い,試薬が各メーカーから開発されてきている.イムノクロマト法の精度を支配する要因はいくつかあるが,主なものとして①キット自体の精度,②事前確率,③検体採取時期と量が挙げられる.全ての要素がキットの感度と特異度に影響する.
クォンティフェロンTB検査(QFT)とTスポット.TB検査(T-SPOT)の違いについて教えてください
著者: 野内英樹
ページ範囲:P.392 - P.393
両者とも結核菌特異抗原に対するインターフェロンγ遊離試験〔interferon(IFN)-gamma release assays:IGRA〕であり,従来,接触者などで結核感染診断に使用されてきたツベルクリン反応検査(tuberculin skin testing:TST)に代わって行われるようになった.BCG接種の影響を受けない特性によって推奨されている1).両者とも図1,2に示すように,陽性コントロール(Mitogen)でIFN-γ産生能を確認しながら,ESAT-6とCFP-10というBCGに存在しない結核菌特異抗原に対するIFN-γ産生を陰性コントロール(Nil)から差し引くことから測定する.しかし,方法の違いでそれぞれ以下の特徴がある.
ワクチンの効果判定の検査について方法や判定を教えてください
著者: 西山記子
ページ範囲:P.394 - P.395
ワクチンの種類と免疫
ワクチンの種類は大きく2つに分類される.1つは生ワクチンで,毒性や病原体を弱めたものを接種し,免疫系は液性免疫の抗体産生と細胞性免疫が働く.もう1つは不活化ワクチン(全粒子・全菌体ワクチン,成分ワクチン,トキソイド,遺伝子組換えサブユニットワクチン,多糖類-蛋白質結合型ワクチン)で,病原体そのものや免疫物質を作る成分のみ,または病原体の産生する外毒素をホルマリンなどで化学的に不活化したものを接種する.免疫系はB細胞とCD4 T細胞が働くが,病原体が不活化されているためCD8 T細胞はほとんど働かない.
梅毒検査の種類,方法が多くて混乱しています.整理して教えてください
著者: 池田眞由美 , 堀内裕次 , 福島篤仁 , 菱沼昭
ページ範囲:P.396 - P.397
梅毒の診断
梅毒はトレポネーマ(Treponema pallidum:Tp)の感染による性感染症であり,臨床診断が優先される.検査には顕症患者病巣からの病原体(Tp)の染色法やPCR検査(未保険収載)もあるが,通常は顕症・潜伏梅毒患者の梅毒血清反応による抗体の検出で診断される.
梅毒血清反応にはリン脂質のカルジオリピンを抗原として非特異的に抗体(破壊された組織の反応)を検出1)する梅毒血清反応検査(serological test for syphilis:STS)と,Tpを抗原として特異的にTp抗体を検出する方法があり,2種類を組み合わせて診断する.
針刺し・切創・粘膜曝露時の感染症検査と対応の要点を教えてください
著者: 秋根大
ページ範囲:P.398 - P.399
まず行うべき感染症検査
曝露源患者のB型肝炎ウイルス(HBV),C型肝炎ウイルス(HCV),ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染状況を確認する必要があるため,HBV表面抗原(HBsAg),HCV関連抗体(HCVAb),HIV抗原/抗体(HIV Ag/Ab)を測定する.曝露した人については,①HBVの免疫状態を確認するため,および②今後のベースラインとするためにHBsAg,HBV表面抗体(HBsAb),HCVAb,HIV Ag/Ab,AST,ALTを測定する(表1).
緊急輸血の対応は,どのようにしたらよいでしょうか? 大量輸血プロトコル(MTP)とは,どのような対応方法でしょうか?
著者: 大澤俊也
ページ範囲:P.400 - P.401
緊急時の輸血とは
患者の血液型が未確定で不規則抗体スクリーニング検査が未実施の場合,結果を待つ時間的余裕がない状況下で,救命のために実施される輸血療法を指す.投与可能製剤はO型Ir-RBC-LR,AB型FFP-LRである.血液型確定後,同型に切り替え,不規則抗体陰性を確認後(約50分)は“T & S”(type and screen)で対応する.緊急時においても施設の輸血実施手順を順守することは重要である.事後においては,輸血同意書の有無,輸血副作用のモニタリングや輸血療法委員会などでの症例報告なども必要である.
血液型不適合造血幹細胞移植後の血液型はどのようになり,輸血用血液製剤の血液型は何型を選択するのでしょうか?
著者: 岸野光司
ページ範囲:P.402 - P.403
造血幹細胞移植の種類
造血幹細胞移植は難治性血液疾患における治療法として行われ,正常な造血の回復が可能である.造血幹細胞移植には,自分自身の造血幹細胞を用いる自家造血幹細胞移植と,健常人ドナーから提供された造血幹細胞を用いる同種造血幹細胞移植に大別される.さらに,同種造血幹細胞移植はドナーによって血縁者と非血縁者に分けられる.また,移植に用いる造血幹細胞には骨髄,末梢血,臍帯血の3つがある.同種造血幹細胞移植では,ヒト白血球抗原(human leukocyte antigen:HLA)の一致が重要であり,患者とドナーのABO,RhD血液型が異なる組み合わせでも可能である.
不規則抗体保有の妊婦は胎児や出産後の新生児にどのような影響を与えますか? 母児間血液型不適合の胎児・新生児における影響と輸血や検査について教えてください
著者: 大槻郁子
ページ範囲:P.404 - P.405
妊産婦の不規則抗体
不規則抗体は,通常ABO血液型以外の赤血球抗原に対する同種抗体で,輸血・妊娠・出産などによって産生される.妊婦の場合,胎児に移行して影響を与えることがある(図1).妊婦の不規則抗体検査は,妊娠初期にスクリーニングを実施する.抗体産生の要因は,妊娠中に胎児血液が母体血中に流入する母児間輸血が挙げられる.そのため,不規則抗体(表1)が同定された場合は,胎児・新生児溶血性疾患(hemolytic disease of the fetus and newborn:HDFN)を発症する可能性があるため,定期的な抗体価の測定が必須となる.
ABO血液型のオモテ・ウラ検査の不一致がある症例の輸血検査はどのように進めたらよいですか? また,輸血用血液製剤の選択はどうするのでしょうか?
著者: 丸橋隆行
ページ範囲:P.406 - P.407
Landsteinerの法則
ABO血液型とRhD血液型は輸血をするうえで極めて重要な血液型である.ABO血液型においては血清中に自己がもつ抗原とは反応しない抗体が規則的に存在しており,このことを“Landsteinerの法則”という(表1)1).原則として同型の血液製剤を輸血するため,安全な輸血のためには正確な血液型判定が必須となる.
輸血を行うときの輸血セットには,どのような種類がありますか? 使用方法と各輸血セットの異なる点を教えてください
著者: 野間慎尋
ページ範囲:P.408 - P.409
輸血用血液製剤
日本赤十字血液センターから供給される輸血用血液製剤は,白血球に起因する非溶血性輸血発熱反応や感染症などの輸血関連有害事象を減少させるために,保存前に白血球が除去された製剤である1).保存前白血球除去が導入され,白血球に起因する輸血セットの目詰まりはほとんど発生していないが,保管不良,細菌汚染,薬剤との混注などによる凝集のリスクが存在している2).
感染症
血液培養を採取するときの消毒は何を使えばよいですか? 滅菌手袋は必要ですか?
著者: 立石哲則 , 織田錬太郎
ページ範囲:P.410 - P.411
血液培養とコンタミネーション
血液培養は起因菌の同定や感染臓器の推定などに役立つ,感染症診療において最も重要な検査の1つである.コンタミネーションとは,本来,血液中にない微生物が血液検体採取から培養ボトルへ分注するまでの一連の手順のなかで混入してしまうことを指す.コンタミネーションの主な原因として①採血部位の消毒不足,②消毒薬の乾燥時間の不足,③消毒後の採血者による清潔区域の汚染が指摘されている1).
コンタミネーションの結果,不必要な治療や追加検査から入院期間の延長や医療費の増大,ひいては患者への実害をもたらすことから,それを減らすための最適な検体採取法が検証されている.
血液培養陽性の場合,常に血液培養のフォローアップは必要ですか?
著者: 栃谷健太郎
ページ範囲:P.412 - P.413
血液培養のフォローアップが必要な状況
血液培養のフォローアップは常に必要なわけではない.必要な状況は主に以下の2つである(表1).
①感染性心内膜炎(IE),化膿性血栓性静脈炎,感染性動脈瘤,血管内デバイス感染といった血管内感染を疑っている,あるいは確定診断している場合
血液培養陽性が持続していれば,上記の疾患がより疑わしくなる.そのため,上記疾患を疑っている状況では血液培養のフォローアップが必要となる.また,上記疾患では治療期間を考える際に,血液培養陰性確定日を治療開始日として数えるよう勧められている.そのため,血液培養の陰性化確認が必須となる.
カテーテル関連血流感染症を疑っているのですが,カテーテル逆血での血液培養は必要ですか?
著者: 本郷偉元
ページ範囲:P.414 - P.415
回答
“必要ですか”と問われたら,答えとしては“不要です”となる.カテーテル関連血流感染症(catheter-related blood stream infection:CRBSI)とは,CRBSIが疑われる臨床状況にある患者が血流感染症(菌血症)を起こしており,かつ,その原因がカテーテルで他に原因がない場合に診断される.つまり,カテーテル先端培養が陽性であること,および菌血症を診断することが必要条件である.ところで,菌血症を診断するためには血液培養2セットが必要である.
CRBSIを疑うのだから,患者には血管内カテーテルが留置されている.血管内カテーテルが留置されているのだから,血液培養の1セットはそこから採取したくなるかもしれない.しかし,コンタミネーションの確率を減らすため,逆血からの血液培養は採取しないのが原則である.カテーテル逆血での血液培養は基本的には推奨されていない.それは,例えば無菌的な胸腔に留置されている胸腔ドレーンからの胸水培養検体などと同様に(胸腔ドレーンを血管内カテーテルと思えばよい),本来無菌的な部位からのドレーン培養検体は推奨されていないことと同じである(この場合に胸水培養を採取するには,ドレーン挿入前であってもドレーン留置中であっても,胸腔穿刺を行う).
血液培養から連鎖状のグラム陽性球菌が陽性になりました.ボトルが溶血しているといわれたのですが,どういう意味でしょうか?
著者: 三河貴裕
ページ範囲:P.416 - P.417
溶血の機序と分類
“ボトルが溶血している”というのは,血液培養ボトル中の赤血球が破壊されている,という意味である.
連鎖球菌のなかで溶血素を産生するものを“溶血性連鎖球菌(溶連菌)”と呼ぶ.微生物検査室では血液寒天培地を用いて,α溶血(不完全溶血:緑色連鎖球菌),β溶血(完全溶血:病原性が強い),γ溶血(溶血しない)の3つに分類する.ボトルが溶血している場合はβ溶連菌である可能性が高く,Streptococcus pyogenes,S.agalactiae,S.dysgalactiaeのどれかである.培地に生えたコロニーを用いてラテックス凝集反応を用いて菌名を推定することができる(Lancefieldの分類).S.pyogenesはA群(group A streptococcus:GAS),S.agalactiaeはB群(GBS),S.dysgalactiaeはC群あるいはG群であることが多い.これらの菌は病原性が高く,4本採取したボトルのうち1本しか生えていなくても,真の菌血症と考える必要がある.
尿培養検査で1×10の4乗と記載されていました.この意味はなんですか?
著者: 大塚喜人
ページ範囲:P.418 - P.419
尿培養検査の目的
尿培養検査は,細菌性の尿路感染症診断に利用される検査である.膀胱内は正常な状態では無菌的な尿が貯留されているが,排尿時には尿道,尿道口と正常常在細菌が生息する部位を通過するため,検出される細菌種,その細菌数によって臨床的判断が異なる.
検体には中間尿,カテーテル尿,膀胱穿刺尿などがあるが,尿路感染症を診断するうえで最も信頼できる検体は膀胱穿刺尿である.しかし,実際に採取されることはまれで,中間尿が一般的である.したがって,尿培養を実施する際には汚染された材料であることを念頭に置いて検査と判定をしなければならない.
喀痰培養でCandida albicansが検出されたのですが,ミカファンギンを投与したほうがいいですか?
著者: 宇野俊介
ページ範囲:P.420 - P.421
喀痰培養で検出されたCandida属の意義
Candida属は人の皮膚や粘膜に常在する真菌である.Candida感染症は,宿主防御機能が低下した場合や,広域抗菌薬の使用によって他の細菌が減りCandida属が異常に増殖した場合に生じる.つまり,殺細胞性抗癌化学療法の使用,免疫抑制薬の使用,広域抗菌薬の使用,血管内カテーテルの留置,人工物の留置,高カロリー輸液の使用などのリスクファクターを有する患者で起きる場合が多い.Candida感染症で頻度が高く重要なものは,まずは皮膚や粘膜の感染症である.さらに,血管内留置カテーテルを使用している場合,皮膚からカテーテルを介して生じる血流感染症が重要である.
喀痰を含む気道検体の培養で検出されるCandida属の多くは,採取される過程で混入してしまった常在菌である.Candida属による肺炎は非常にまれな病態であるため,気道検体で検出されたことのみで治療対象とすべきでないと,米国感染症学会のガイドラインに記載されている1).
C.difficile感染症を疑って検査をしたところ,トキシンは陰性だけれど抗原は陽性と言われました.次に何をすればよいですか?
著者: 上蓑義典
ページ範囲:P.422 - P.423
Clostridioides difficile感染症(CDI)
Clostridioides(Clostridium)difficileはグラム陽性偏性嫌気性菌であり,院内下痢症の主要な原因の1つであるC.difficile関連下痢症(CDAD)を引き起こす.CDADは,C.difficileの産生する外毒素であるtoxin Aまたはtoxin Bが腸管の上皮細胞や免疫細胞に作用し,粘膜障害などを起こすことで下痢が生じる.このため,CDIの検査は下痢症の原因としてC. difficileのtoxinの産生があるかをみることが目的であり,下痢をしていない患者に検査しても意味がない.米国のガイドライン1)では24時間以内に3回以上,形のない便を認めた患者が検査適応とされており,わが国のガイドライン2)ではその指標としてBristol Score 5以上を用いるとされている.
現在,タゾバクタム/ピペラシリン(TAZ/PIPC)を投与しているのですが,検出されたEnterococcus faecalisの感受性検査結果にTAZ/PIPCの結果が書いてありません.アンピシリンを併用したほうがよいですか?
著者: 鈴木大介
ページ範囲:P.424 - P.425
感染巣から採取された培養からアンピシリン(ABPC)感性のEnterococcus faecalisが検出され,今回の症例の原因菌であると判断した場合(以下,本症例)を想定して返答する.
Enterococcus spp.(腸球菌)がABPCに感性の場合はタゾバクタム/ピペラシリン(TAZ/PIPC)にも感性と判定してよいため,慌ててABPCを追加する必要はない.一方で,感染巣と全ての原因菌およびその感受性が判明したら,TAZ/PIPCよりスペクトラムの狭い抗菌薬への変更(de-escalation)を検討する.
β-D-グルカン検査には偽陽性があると聞きました.どのような場合に偽陽性になるのですか?
著者: 村中清春
ページ範囲:P.426 - P.427
β-D-グルカンの偽陽性
β-D-グルカンは多くの真菌において細胞壁の主要な構成成分であり,陽性となる主な深在性真菌感染症はCandida spp.,Aspergillus spp.,Pneumocystis jiroveciiである(表1).陽性とならない微生物の代表はムコール症をきたす真菌とCryptococcus spp.である(表2).前者はそもそも細胞壁にβ-D-グルカンが存在せず,後者はβ-D-グルカンをもつが,厚い莢膜多糖の影響で陽性化しないと考えられている.
β-D-グルカン検査にはいくつかの偽陽性の報告がある(表3)1).その要因としてβ-D-グルカン含有物の摂取・投与,検査手技の問題が指摘されているが,その他にメカニズムがよくわかっていないものもある.偽陽性はいわば“検査の副作用”であり,治療薬剤の副作用と同様にその因果関係を証明することは難しい.
皮膚組織の培養から迅速発育菌が検出したと報告を受けました.迅速発育菌とはなんですか?
著者: 藤原啓司 , 森本耕三
ページ範囲:P.428 - P.429
迅速発育菌とは
迅速発育菌とは,非結核性抗酸菌(NTM)のうち,固形培地で7日以内にコロニー形成(発育する)される菌と定義される.NTMは抗酸菌のなかで結核菌,らい菌を除いた菌の総称である.2020年現在,NTMは200菌種近く(迅速発育菌は90菌種近く)が確認されており,検査法の進歩に伴って報告される新種が増え続けている.迅速発育菌は自然環境から家庭環境まで広く存在しており,ヒトへの感染例が報告されている.米国ではさまざまな地域の土壌サンプルの30〜78%で迅速発育菌が分離されたと報告されている1).
治療に関しては,迅速発育菌の多くは1st lineの抗結核薬に感受性がなく,薬剤感受性試験に基づいて治療レジメンを決定する必要がある.わが国ではブロスミックRGM(極東製薬工業社)を用いた薬剤感受性試験が実施可能である.
CREが検出されたのですが,カルバペネマーゼ産生菌ではないといわれました.どういう意味ですか?
著者: 永田美香
ページ範囲:P.430 - P.431
CREはカルバペネム耐性腸内細菌科細菌(carbapenem-resistant Enterobacteriaceae)の略称であり,CRE感染症は感染症法5類(全数把握疾患)に該当する1).この場合のCREは薬剤感受性試験結果によって定義される(表1)1).カルバペネム耐性の機序として,酵素(カルバペネマーゼ)産生による抗菌薬の分解,他のβラクタマーゼ過剰産生+外膜蛋白の変化などが挙げられるが,院内感染対策においてはカルバペネマーゼ産生による耐性化が重要となる.その理由として,カルバペネマーゼを産生する腸内細菌科細菌はCPE(carbapenemase-producing Enterobacteriaceae)と呼ばれ,カルバペネム系抗菌薬およびほとんどのβラクタム薬を不活化し耐性を示すことと,カルバペネマーゼをコードする遺伝子の多くはプラスミド上に存在し,菌種を超えて伝播しうることが挙げられる.
諸外国ではカルバペネマーゼを産生するCRE(CP-CRE)の分離頻度が高いこともあり,CPEとCREは同義語として使われるが,わが国ではカルバペネマーゼ非産生のCREや,CRE定義に該当しないCPEが多く検出されるため,検査を進めるうえで注意が必要である(図1).
SARS-CoV-2のPCR検査の感度はどの程度ありますか?
著者: 山元佳
ページ範囲:P.432 - P.433
SARS-CoV-2 PCRの感度,反復検査
検出感度(検出限界)の意としては各SARS-CoV-2 RT-qPCR(以下,SARS-CoV-2 PCR)キット間の差は明らかではないが,LAMPなどの核酸検出検査や抗原検査と比べてPCRはより少ない核酸量を検出可能である.検査感度は“真の陽性”と判断された症例を“真の陽性,偽の陰性”で除したものである.ただし,COVID-19の真の陽性を規定する検査は,ほかならぬPCR検査をはじめとした核酸検出検査である.流行の当初,感度70%はSARS-CoV-2 PCR検査を反復して陽性であったものを診断のゴールドスタンダードとして,初回PCR検査の診断についての感度を算出したものであった.開発の黎明期であった点や検体が咽頭拭い液であったという問題もあり,その後のメタ解析で感度は90%前後と報告されている1).
それでも十分な感度ではないと考えて,PCR反復を行う医療機関は多かったが,その意義は乏しい.非常に疑わしい肺炎像を有し,臨床上低酸素などの問題を伴っている場合や濃厚な接触歴があるうえで発熱などの鑑別を行う場合には一定の診断的な意義は存在するが,それ以外の場面ではほぼ意義がない.本感染症の診断意義の1つに感染拡大防止があるが,感染拡大をきたす可能性のある病早期(発症前から発症7〜10日以内)2)においてPCRが偽陰性となる症例は非常に少ない可能性が高いことがウイルス検出の推移から推測できる3).
当院はSARS-CoV-2の検査をLAMP法で行っていると聞きました.LAMP法はPCR検査と同じですか?
著者: 三木田馨
ページ範囲:P.434 - P.435
PCR法,LAMP(loop-mediated isothermal amplification)法は,遺伝子増幅法を用いた検査法である点は共通であるが,その原理は大きく異なる.
ペニシリン感受性黄色ブドウ球菌(MIC≤0.03mg/L)菌血症の治療を,セファゾリンではなくペニシリンGやアンピシリンで行うことはできますか?
著者: 守山祐樹
ページ範囲:P.436 - P.437
ペニシリン感受性黄色ブドウ球菌(PSSA)とは
わが国でのメチシリン感受性黄色ブドウ球菌(methicillin-susceptible Staphylococcus aureus :MSSA)菌血症の治療薬はセファゾリン(CEZ)が第一選択となる.黄色ブドウ球菌は感受性試験でペニシリンG(PCG)がS(MIC≤0.12mg/dL)であっても,PCGやアンピシリン(ABPC)に対する誘導耐性を示すことがあるため,通常は確認試験を経てペニシリン感受性黄色ブドウ球菌(penicillin susceptible Staphylococcus aureus:PSSA)と判定する.ただし,PCGがMIC≤0.03であれば,確認試験が全て陰性であったという報告もあり1),MIC≤0.03であればPSSAと読み替えてもよいかもしれない(図1).
病理
採取した検体を固定液に浸漬するまでの時間の目安を教えてください.また,一時的に生理食塩水でも大丈夫でしょうか?
著者: 井上博文
ページ範囲:P.438 - P.439
固定とは
固定とは,経時的に進行する自己融解や細菌などによる腐食を化学反応を利用して停止・抑止し,細胞,組織形態の保持と劣化を防止する操作をいう.さまざまな方法や試薬が使用されるが,一般的に病理検査で多く利用されている固定法はホルマリン溶液を組織に浸漬する方法である.これまでは形態保持が主たる目的であったが,ゲノム医療の本格的な臨床実装によって,核酸品質にまで配慮した固定方法が求められている.
検体を固定する際に気を付ける点を教えてください
著者: 山里勝信
ページ範囲:P.440 - P.441
固定の目的
固定は病理組織検査を行ううえで検査結果にも影響する重要な最初の工程である.組織・細胞は血流が遮断された時点から自己融解が始まるため,①可能な限り生体内に存在した状態をとどめて安定させる(自己融解,成分の拡散・細胞内外物質溶出の防止),②蛋白質を一部変性させ,一定の硬度を与える,③染色性を増大する,を目的として行われる.
固定液には多くの種類があり,目的によって使い分ける必要があるが,全てを網羅できる完璧な固定液は存在しない.一般的にはホルマリンが使用されている.本稿では,近年,コンパニオン診断や次世代シーケンサー(NGS)を用いる遺伝子検査などでも推奨されている1)10%中性緩衝ホルマリンでの固定方法について述べる.
病理検体における病原体感染対策について教えてください
著者: 榎木英介
ページ範囲:P.442 - P.443
はじめに
病理検査には,さまざまな病原体をもった病理検体が提出される可能性がある.このため,臨床検査技師や病理医が病原体に曝露される可能性があり,感染対策は必須である.本稿では病理検査室の感染対策について概説する.
複数の生検検体を提出するとき,検体をろ紙に貼り付けて番号付与すれば,1つの容器に全て入れて提出してよいですか?
著者: 片倉和哉
ページ範囲:P.444 - P.445
複数の検体を1つの容器にまとめて入れてよいか
生検検体はサイズが小さいので,検体の紛失,挫滅を防ぐ目的や形態を保持するためにろ紙に貼り付けられることが多い.しかし,ろ紙に貼り付けた生検が剝がれることがある.検体の状態によってろ紙から剝がれやすいものもあり,特に食道粘膜などの扁平上皮が剝がれやすい.同一容器に複数の検体を入れた場合,容器内でろ紙から検体が剝がれることで生検番号がわからなくなり,採取部位が不明になる.その結果,同一患者における検体の取り違えが生じる危険性がある.
したがって,採取部位が異なる生検検体は別々の容器に入れるのが原則であり,それぞれの容器に必ず,患者属性(氏名,IDなど)および検体情報(採取部位,枝番号など)を記載するのが望ましい1).さらに,主治医が病理組織依頼書にも,その識別が可能であるよう記載し,検体個数を明記する.間仕切りのついた生検標本カセットを使用することで複数の採取された組織が混在しないようにする方法もある.
摘出後に臓器の撮影をするときのポイント(注意点)はありますか?
著者: 中村広基
ページ範囲:P.446 - P.447
臓器を撮影する目的
標本提出時や切り出し時に撮影された写真は標本作製や診断時に重要な情報として用いられる.そのため,臓器標本の特徴を十分再現した写真が必要になる.撮影を行うポイントは,必要な面が全て撮影されていること,臓器全体にフォーカスが合っている(パンフォーカスである)こと,明るさ(露出制御)や色合い(ホワイトバランス)が適切であること,適切な背景で撮影することなどが挙げられる.臓器写真も病理依頼書への記述と同様に,病理医への情報伝達手段であることを意識して撮影に臨んでいただきたい.
骨や石灰化を含む検体,乳腺検体の検査結果が,他の検体より遅れて返却されてくるのは,なぜですか?
著者: 山田寛
ページ範囲:P.448 - P.449
病理標本作製(図1)
病理標本の作製は工程が多く,通常でも病理診断が臨床医へ返却されるまで時間がかかるが,乳腺などの脂肪組織,骨や石灰化組織などの硬い組織はさらに時間を必要とする.これは,乳腺などの脂肪組織では脱脂操作,骨など硬組織では脱灰操作が必要だからである.
細胞診検体を提出する際に,冷蔵庫に入れるようにいわれるのですが,なぜですか? また,なぜ細胞診検体はアルコール固定なのですか?
著者: 渡部顕章
ページ範囲:P.450 - P.451
細胞の変性を最小限にするには
生体から採取された細胞は血液(酸素,栄養)の供給が絶たれ,温度,浸透圧の変化,細胞小器官による自己融解,細胞外からの刺激(細菌増殖)などによって核クロマチンの凝縮,核の断片化,細胞質の断片化,空胞化,細胞の縮小や肥大などの変性に至り,最終的には細胞が消失する.
例えば,採取後の髄液細胞は変性が早いため採取後1時間以内に検査を実施する必要がある.室温保存では2時間後には細胞が68%に減少し,細胞成分のなかでは単核球より多核球のほうが変性は早いといわれている.髄液は液体内の蛋白濃度が低いため,変性や分解が起こりやすく判定が大きく変わってしまう可能性がある.
細胞診の結果で“検体不適正”とは,どのような場合ですか?
著者: 加戸伸明
ページ範囲:P.452 - P.453
なぜ“検体不適正”なのか
細胞診結果が“不適正”判定される場合は以下の2つに大別される.
①不合格検体:検体にラベルがない,スライドの破損など.
②不適正検体:検体処理後に鏡検を行ったが,細胞の評価が困難.
実際には②の不適正検体が多くを占めている.その原因として,細胞乾燥や固定不良,末梢血混入を含む標本作製段階での操作不良,あるいは病変を推定するに足る細胞成分が採取されていない,などが挙げられる1〜5).
細胞をスライドガラスに塗抹する際の注意点はありますか?
著者: 島田直樹
ページ範囲:P.454 - P.455
臨床医が採取した細胞検体を塗抹固定する機会は多くある.婦人科の子宮腟頸部,子宮内膜の検体,呼吸器の内視鏡的気管支擦過検体,各臓器の穿刺吸引検体などが挙げられる.完成した標本は,顕微鏡下で組織構築や個々の細胞が観察しやすいことが第一である.塗抹する際の注意点は,①立体的に厚く塗抹するのではなく薄く均一に塗抹すること,②多量の血液を塗沫しないこと,③塗抹した検体を乾燥させないことが重要である.
感染症の疑いがあっても病理解剖は可能ですか?
著者: 堤寛
ページ範囲:P.456 - P.457
適切な感染防止対策を施すことで,病理解剖は可能である.いや,感染症が疑われるからこそ病理解剖は必要である.病理解剖における感染リスクの諸側面を考察する.
借りた標本に気泡が入っているときは,どうすれば気泡が取り除けるのですか?
著者: 前田和俊
ページ範囲:P.458 - P.459
ガラス標本に気泡が入る原因
病理標本の作製工程において,標本の観察と長期保存を可能とするため,スライドガラス上の組織や細胞に封入剤を満たし,その上にカバーガラスを載せることを“封入”という.その過程で標本中に空気を封じ込めてしまうと気泡となるが,原因として,以下のことが考えられる.
①封入剤の粘度が低すぎたり高すぎるため,封入剤自体に気泡が混入している.
②封入時に封入剤の量が少ない.
③封入前の標本が乾燥している.
④細胞診など標本に厚みがある.
がんゲノム検査に検体を提出したいのですが,何年前までのブロックであれば使用可能ですか?
著者: 柳田絵美衣
ページ範囲:P.460 - P.461
現在,がんゲノム検査の対象は病理組織のホルマリン固定パラフィン包埋(formalin fixed paraffin embedded:FFPE)切片である.DNAはホルマリンによって断片化されることや時間経過によって品質が低下する.固定時間や固定液の種類,FFPEブロックの保管環境によって核酸の品質は異なるが,日本病理学会は「ゲノム研究用・診療用病理組織検体取扱い規程」1)において“作製後3年以内のFFPEブロックの使用が望ましい”としている.しかし,作製後3年以内でも品質が不良な場合もある.核酸の品質は解析結果に大きな影響を与えるため,抽出した核酸は品質を確認する必要がある.
病理組織検体(パラフィンブロック)からアスベスト繊維を証明できますか?
著者: 林裕司
ページ範囲:P.462 - P.463
アスベスト繊維の特徴
アスベスト(石綿)は非常に細い繊維である.種類によって太さが若干異なるが,クリソタイル(白石綿)で0.02〜0.35μm,アモサイト(茶石綿)で0.06〜0.35μmである.この細い繊維そのものを観察するには電子顕微鏡が必要とされる.肺内に長期間滞留したアスベスト繊維の一部がフェリチンなどの鉄蛋白と結合したものはアスベスト小体(石綿小体)と呼ばれており,こちらは通常の光学顕微鏡で十分に観察可能である.
生理機能
QT延長が危険であることは知っていますが,QT短縮も危険なのはなぜですか?
著者: 河合昭人
ページ範囲:P.464 - P.465
QTが延長している心電図を認めたら危険であるという話は以前から知られているが,QTが短縮している際も失神や突然死をきたすことがいわれている1).QT短縮はQTc<350msecの場合,短縮しているとされている.QTが異常となる疾患を表1に示す.そのなかでもQT短縮症候群(short QT syndrome:SQTS)はQTc<330msecであるとその可能性が高くなる.
偽性心室頻拍とは何ですか?
著者: 野々口紀子
ページ範囲:P.466 - P.467
WPW症候群とは
WPW症候群はWolf-Parkinson-Whiteの3人の研究者が発見・報告したのが始まりで,特徴的な心電図所見〔PR間隔短縮,δ(デルタ)波,QRS幅の増幅〕を呈する(図1).通常は,心房と心室間の電気興奮は房室結節を介して伝導する.WPW症候群では,房室結節以外に先天的に心房と心室をつなぐ副伝導路(accessary pathway:AP)を有するため,心電図で先述の所見を呈する.以下にWPW症候群でみられる頻脈を示す(図2).
外挿気量とは何ですか?
著者: 星弘美
ページ範囲:P.468 - P.469
外挿気量とは
努力肺活量測定は,安静呼気位から最大吸気位まで十分に吸気させて,最大吸気位が確認できたのち,最大限の力で一気に速く努力呼気を行わせ,最大呼気位まで完全に呼出させる.測定におけるスパイログラムを努力呼気曲線(Tiffeneau曲線)と呼び,フローボリューム曲線と同時に得られる.
努力呼気曲線の最大の傾き部分の直線を延長して,最大吸気位と交わる点を呼気開始点(time zero)とし,1秒量計測の起点とする.この呼気開始点において,実際に呼出されている呼気量を外挿気量(extrapolated volume)という(図1)1).
クロージングボリューム検査では,なぜ低流速での検査が求められるのですか? 呼出時に高流速となった場合の結果の解釈はどうすればよいですか?
著者: 高谷恒範
ページ範囲:P.470 - P.471
換気血流比の不均等を検出する方法
健常人でも,重力の影響や解剖学的構造によって換気と血流は不均等に分布する.疾患になれば不均等性が一段と増大し,換気血流比不均等の結果,ガス交換障害(換気障害)が起こって低酸素血症が生じる.胸腔内圧は坐位のとき,重力の影響を受けるため,陰圧の程度は肺底部より肺尖部で高くなる.胸腔内圧は肺の部位が異なると肺容量に違いが生じる.最大吸気を行った全肺気量位では,肺尖部・肺底部にかかる胸腔内圧に違いがあっても容量にほとんど差が生じない.しかし,呼出を行って肺容量が低下していくと気道を外側に牽引する力が低下するため,低肺気量になると気道の開存性が維持できなくなって気道閉塞が起こる.坐位の場合,肺底部で肺尖部より胸腔内圧が高く,肺胞容量は低下している.そのため,肺底部から気道閉塞が起こる.これは,最大呼出時の残気量位よりも高い肺気量位で起こる.また,気腫化でみられる肺の弾性収縮圧低下や気道狭窄などの病的な状態では不完全な気道狭窄が早期で起こるため,正常な状態より早く気道閉塞が起こる.クロージングボリューム(CV)測定では,その気道閉塞が起こる初期の状態を反映しているため,末梢気道病変の早期検出に有用な臨床肺機能検査法として位置付けられている.
EFが正常なのに,心不全となっているのはどのような状態ですか?
著者: 渡邊伸吾
ページ範囲:P.472 - P.473
EFとは
左室駆出率(ejection fraction:EF)は左室拡張末期・収縮末期容積から導かれ,左室から駆出された血液量の割合である.EFの計測には侵襲度,簡便性から心エコー図検査がよく用いられ,その代表的な指標となっている.かつては心エコー図でのEFの算出にMモード法が利用されていたが,断層像から計測した左室内径を容積に換算(Teichholz法)して算出する方法や,左室内腔を直接トレースして容積を算出するdisk summation法(biplane modified Simpson法)に移行し,現在ではdisk summation法によってEFを算出することが主となっている.また,3Dエコー法でのEFの計測機会も増加している.
甲状腺の腫瘤評価において,コロイド囊胞と腺腫様結節を判断するポイントを教えてください
著者: 志村浩己
ページ範囲:P.474 - P.475
甲状腺超音波検査においては囊胞性病変と結節性病変が高頻度に発見される.良性病変であるコロイド囊胞と腺腫様結節の占める割合が極めて高く,甲状腺診療では超音波診断においてこれらを適切に診断することが非常に重要である.
コロイド囊胞では,組織学的に顕著な濾胞拡張,上皮の平坦化,および高密度の粘性物質を認める.コロイド囊胞は特に小児期に高頻度に認められ,特に小学生〜中学生の年代では50%以上の被検者に認められる1).
肝内門脈浸潤を伴う腫瘤について,鑑別疾患や評価方法を教えてください
著者: 斎藤聡
ページ範囲:P.476 - P.477
肝内門脈浸潤を伴う腫瘤
肝内門脈浸潤のみられる腫瘍の多くは肝細胞癌である.胆管癌や膵癌などでもみられるが,肝内門脈浸潤は肝細胞癌の大きな特徴である.「原発性肝癌取扱い規約」1)によれば,門脈の二次分枝より末梢がVp1,門脈の二次分枝がVp2,門脈の一次分枝がVp3,門脈本幹がVp4とされる(表1)1).原則的に原発巣部位から連続的に進展し,スキップすることはない.超音波や造影CT検査などの画像診断ではVp1やVp2までは評価も困難なことも多い.
門脈浸潤を伴う肝癌では供血路が動脈血のみの腫瘍と動脈・門脈両者の非癌部肝組織とでは造影コントラストがつきやすいが,両者ともに動脈血流のみの供給となると腫瘍の境界不明瞭化やコントラスト不良となり,さらには門脈経由の肝内転移が多発する.Vp3やVp4は非常に予後が悪く,有効な治療方法も確立されていない.門脈が完全閉塞すると門脈圧亢進症が急速に悪化し,食道静脈瘤の破裂,腹水貯留などの病態の急激な悪化をきたすことがある.
頭部MRI検査において,DWIで高信号だった場合の鑑別診断にはどのようなものがありますか
著者: 阿部考志
ページ範囲:P.478 - P.479
拡散強調像(DWI)の原理
拡散強調像(diffusion weighted image:DWI)は水分子の拡散運動(ブラウン運動)を反映した画像である.脂肪抑制T2強調像に拡散を強調する傾斜磁場(motion probing gradient:MPG)を加えた画像であり,拡散が制限された組織が高信号で描出される.
拡散強調の程度を表す単位としてb値があり,b=1,000s/mm2が広く使用されている.
DVT検査のときに考慮する疾患はありますか?
著者: 高井洋次
ページ範囲:P.480 - P.481
DVTの病態と整理
深部静脈血栓症(deep venous thrombosis:DVT)の多くは下肢深部静脈で血液が凝固する病態であり,形成された血栓が遊離し,右心房,右心室を経て肺動脈で塞栓となり肺動脈塞栓症(pulmonary embolism:PE)を引き起こす.血栓形成の原因はVirchowの3徴,すなわち,血流の鬱滞,血管内皮の損傷,血液凝固能の亢進である.
三相波はどんなときにみられますか?
著者: 代田悠一郎
ページ範囲:P.482 - P.483
三相波を呈する基礎疾患
三相波といえば肝性脳症が有名であるが,実際にはさまざまな代謝性脳症で観察される.高ナトリウム血症,甲状腺機能低下症,敗血症,リチウム中毒,高血圧脳症などの報告がある1).筆者らは,第四世代セフェム系抗生物質であるセフェピム(CFPM)を腎不全患者に使用した際に生じた意識障害に伴い,三相波様の波形が周期的にみられたことを報告した2).基礎疾患によらず意識障害に対応する脳波所見であるが,脳波異常の程度と意識障害の程度は必ずしも関連しないとされる.
薬にもよりますが,投薬に伴い速波が混入するのはなぜですか?
著者: 福地聡子 , 久保田有一
ページ範囲:P.484 - P.485
脳波とは
脳波とは,大脳皮質にある大錐体細胞の尖端樹状突起に生じるシナプス後電位の総和であり,脳の電気的活動を反映している.脳波の波形は,周波数(波の速さ)によって次のように分類される.
δ波:0.5〜3Hz
θ波:4〜7Hz
α波:8〜13Hz
β波:14〜30Hz
健常成人の脳波では安静・閉眼・覚醒時に後頭部優位にα波を主体とする基礎活動がみられる.α波よりも周波数が遅い波形(θ波・δ波)を徐波,速い波形(β波)を速波と呼ばれている.
脳死判定はどのような準備をしておけばよいですか?
著者: 栁田浩己
ページ範囲:P.486 - P.487
検査においての準備
実際の脳波測定時に,ミスや漏れがないように「法的脳死判定マニュアル」1)に準拠したチェックリストを作成しておく(図1).日常で使用している点検整備されたポータブル脳波計を準備し,法的脳死判定推奨モンタージュの設定や,脳波計によっては検査手順をわかりやすくアイコン化できる測定ナビゲーションが搭載されているので,脳死判定用に設定しておくのもよい(図2).
特に重要なのは,普段の検査で脳死と考えられる患者を法的脳死判定を想定して検査し,脳電気的無活動(ECI)の記録ができるかを確認しておくことである.判定では,2名の臨床検査技師が脳死判定予定時間の1時間ほど前に入室して電極の装着と仮記録を行い,脳死判定時の脳波記録が順調に進むように準備する.電極装着では,全ての電極の接触抵抗を2kΩ以下とすることが必須である.これができないと,たとえECIでも,脳波様微小電位(EMA)2)と呼ばれるアーチファクトが混入して高感度記録でのECI確認を困難にする.
抗がん剤による心毒性の副作用を心エコーで評価する際の注意点について教えてください
著者: 志賀太郎
ページ範囲:P.488 - P.489
がん治療薬関連性心筋傷害(CTRCD)とは
がん治療薬関連性心筋傷害(cancer therapeutics related cardiac dysfunction:CTRCD)とは,がん治療薬により生じた心筋障害,心機能低下の総称である.アントラサイクリン系薬剤による心筋障害がよく知られているが,アントラサイクリン系薬剤以外にも多く存在する.トラスツズマブ,フルオロウラシル(5-FU)などのフッ化ピリミジン系薬剤,白金系薬剤などの従来の殺細胞性がん治療薬,抗体薬やチロシンキナーゼ(TKI)阻害薬などからなるVEGF経路阻害薬,BCR-ABL阻害薬,ALK阻害薬,プロテアソーム阻害薬といった分子標的薬なども原因薬剤になりうる.昨今,治療的発展が目覚ましい免疫チェックポイント阻害薬による心筋障害もその範疇に入ってくるであろう.
薬剤ごとに心筋障害機序は異なり,心筋障害が生じる様式も異なるので,CTRCD管理法をひとくくりにすることはすべきではないと考える.まずは,アントラサイクリン系薬剤とその他の心毒性薬として管理を大別し,臨床での対応をしていくことがよいと考える.次々に新規がん治療薬が登場してくるなか,循環器的有害事象の出現については今後も注意深い観察が必要である.
ABR検査の刺激でクリック,トーンバースト,トーンピップとよく聞きますが,どのようなものでしょうか
著者: 原田竜彦
ページ範囲:P.490 - P.491
ABRの検査音に求められること
聴性脳幹反応(auditory brainstem response:ABR)は,音刺激によって頭皮上から得られる一連の聴性電位変動のうち潜時の短い反応(おおむね10ミリ秒程度まで)とされている.このため,刺激音も短時間にしないと誘発される波形も明瞭に捉えることがない.
一方,蝸牛では音の周波数別に異なる部位の神経細胞(有毛細胞)が刺激され,それぞれが別々に中枢へと伝達されていくため,周波数ごとに機能の評価をすることが重要であり,通常は聴力検査でも1つの周波数だけからなる純音が用いられる.しかし,刺激音は短くするほど周波数特異性が低く(幅広い周波数を含んだ状態に)なってしまう.
ABI検査が正常値よりも高値となった場合は,どのように評価すればよいですか?
著者: 重松邦広
ページ範囲:P.492 - P.493
ABIとは1)
ABI検査は“ankle brachial pressure index”の略である.わが国では“足関節上腕血圧比”と称され,足関節レベル(後脛骨動脈・足背動脈)の収縮期血圧を分子,両側上腕レベルの収縮期血圧のうち高いほうを分母として計算され,小数点以下2位まで記載される.従来はドプラ聴診器で各動脈(両側上下肢計4カ所)の血圧をそれぞれ測定していたが,現在ではオシロメトリック法を用いて上下肢4カ所同時に血圧測定する機器で測定される.正常人では下肢の血圧が上肢の血圧よりやや高く,ABIは1.00を超える.
閉塞性動脈硬化症(ASO)を主とする末梢動脈病変(peripheral artery disease:PAD)などでは上肢の狭窄病変は少なくほとんどの病変は下肢に認められることから,ABIの低下は下肢動脈の狭窄性病変の存在を示すことになる.
基本情報
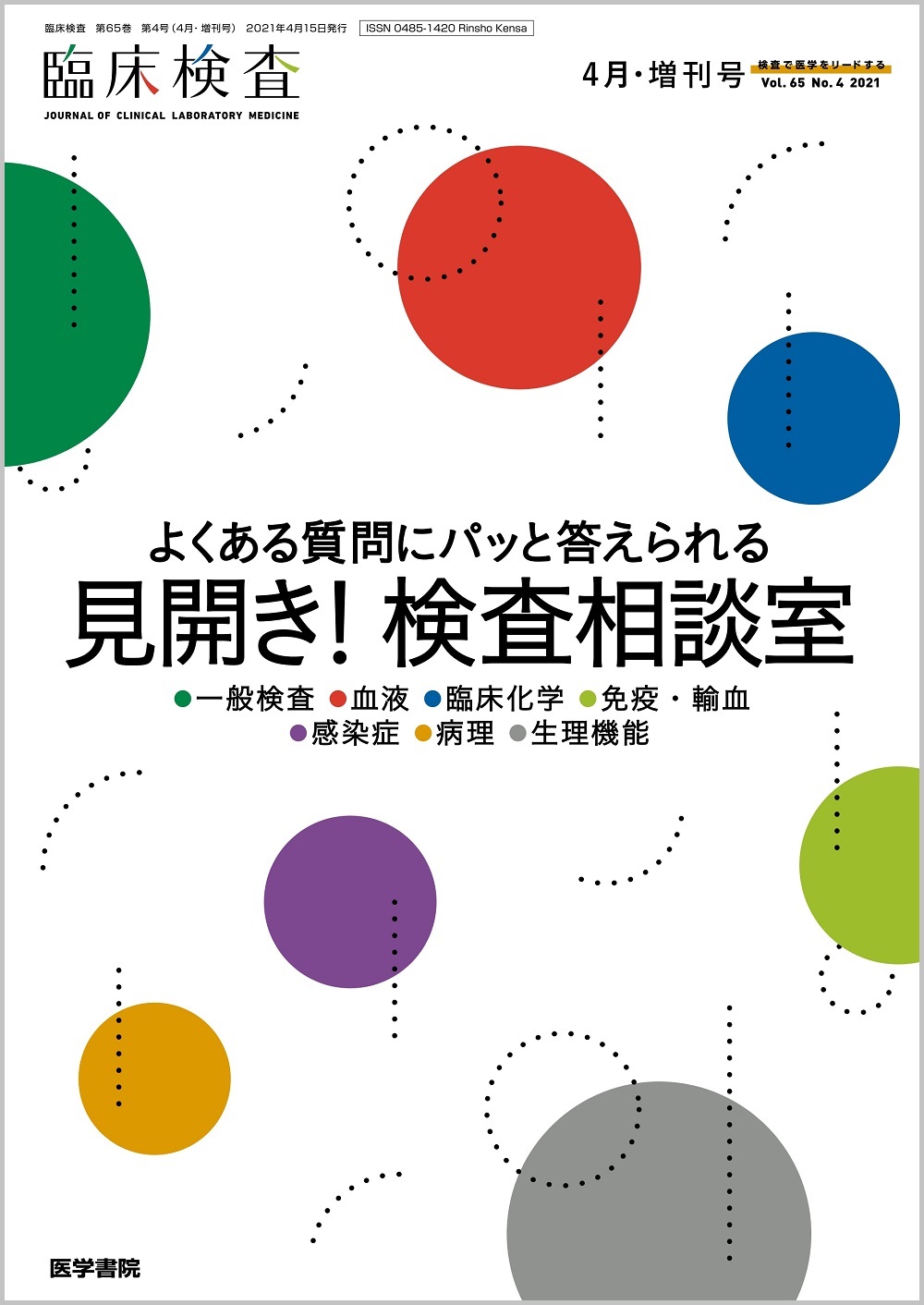
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
