血液学領域の検査結果は診断の確定や治療の選択,効果評価にしばしば直結する.そのため,検査の乖離の判断と解決は検査実地のみならず臨床実地にとって極めて重要である.しかし,血球形態検査のように単純な定量値として扱えないものや,フローサイトメトリー検査や凝固関連検査のように標準化・精度管理が難しいものが含まれるため,化学・免疫検査と比べると系統的に乖離を取りまとめて論じるのは容易ではない.
そこで,個々の検査の特性を理解し,なぜ,どのようなメカニズムで乖離が生じるのかを知ることが重要となる,血液検査は採血前からすでに始まっている.最初の一歩は,検査前プロセスが検査値に与える影響を理解することである.自動化が進んだ血算値の結果の乖離については,その原因とメカニズムを理論的に知っておくことが重要である.血球を直接観察する血球形態検査は血液検査の醍醐味であるが,標本の作製方法や細胞識別の標準化が困難という特性からさまざまな乖離が生じる.フローサイトメトリー検査は血液疾患や免疫疾患の診断のほか,移植治療でも必須の検査となっているが,検査そのものの仕組みと特性を知ることによって,検査値の乖離に遭遇した際に適切に判断し,対応することが可能になる.
雑誌目次
臨床検査66巻10号
2022年10月発行
雑誌目次
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
はじめに フリーアクセス
著者: 涌井昌俊 , 田部陽子
ページ範囲:P.1091 - P.1091
1章 血算
検査前プロセスの影響
著者: 出居真由美
ページ範囲:P.1094 - P.1097
検査のプロセス1,2)
検体検査の流れは,検査前プロセス,検査プロセス,検査後プロセスに分けられる(図1).検査の依頼から検体を採取し,検査室へ搬送され,検体検査を実施する前までの工程が検査前プロセスである.測定機器の性能がどんなに向上しても,検査前プロセスを適切に行わないと,正しい検査結果を得ることはできない.
検査を実施するうえで,検査依頼を明確に行うことが重要である.検査を依頼する医師は,検査の必要性をよく考えたうえで検査項目を選択し,検体の採取条件を確認し,患者への説明と検査者への指示を的確に行う必要がある.
有核赤血球出現時の血算の取り扱い
著者: 池田千秋
ページ範囲:P.1098 - P.1099
有核赤血球の出現
通常は,健常人では末梢血に赤芽球が出現することはないが,何かしらの異常に伴い末梢血に赤芽球が出現し,これを有核赤血球と呼ぶ(図1)1).末梢血に有核赤血球が出現する病態には,高度な溶血性貧血や大量出血,急性白血病や骨髄異形成症候群,骨髄線維症や慢性骨髄性白血病などの骨髄増殖性疾患,骨髄癌腫症などがある.
MCV,MCH,MCHCに影響する因子と貧血分類における留意点
著者: 槇亮介
ページ範囲:P.1100 - P.1103
はじめに
自動血球計数装置による全血球計算(以下,血算)は日常診療において広く用いられる.そのなかでも平均赤血球容積(MCV),平均赤血球ヘモグロビン量(MCH),平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)の赤血球恒数は貧血を分類するに当たって必要不可欠である.しかし,これら赤血球恒数は,さまざまな要因により正確な検査結果が得られない場合がある.
本稿では,赤血球恒数に影響を与える因子および,留意すべき点について解説する.
白血球著増時の自動血球計数の問題点
著者: 伊藤ゆづる , 後藤文彦
ページ範囲:P.1104 - P.1107
はじめに
自動血球計数装置は多くの検体を迅速かつ再現性よく測定でき,さらに経済性の観点からも日常業務で欠かすことのできない検査装置である.装置による各血球の測定原理には電気抵抗的方法とフローサイトメトリー法などの光学的方法があり,通常の検体測定では前者が主流である.
本稿では,NTT東日本関東病院で使用している多項目自動血球分析装置XN-9100(シスメックス社)を中心に,白血球著増時に生じる血球計数(血球数算定:以下,血算)値への影響について解説する.
破砕赤血球の定義と評価
著者: 菅原新吾
ページ範囲:P.1108 - P.1111
破砕赤血球とは
破砕赤血球は,循環血中で外因的損傷によって生成された奇形赤血球であり,血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP)/溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome:HUS)の総称とされる血栓性微小血管障害症(thrombotic microangiopathy:TMA)の診断において重要な赤血球形態である.破砕赤血球の形状についてDacieらは,正常赤血球より小型で,鋭角や鋭い棘または突起をもち,時に輪郭が丸く,通常は濃染するがヘモグロビンの損失で時に薄くなると述べている.国際血液学標準化協議会(International Council for Standardization in Haematology:ICSH)の提言では損傷のない赤血球よりも小さく,ほとんどの場合で色調は均一,鋭角と直線をもつ断片の形,小さな三日月形,ヘルメット細胞,ケラトサイト,または微小球状赤血球(前述の形状が存在する場合のみ)とされている.日本検査血液学会(Japan Society of Laboratory Hematology:JSLH)の形態標準化案1)で提示されている画像では,形状はDacieらやICSHと同様であるが,特徴について言語表現はされていない.旧厚生省試案では濃染を前提としており,有棘赤血球やウニ状赤血球と輪郭が類似する不規則変形型といがぐり型が含まれる.
破砕赤血球の評価は,血液塗抹標本で少なくとも1,000個の赤血球をカウントし,破砕赤血球の数を比率で表す.ICSHとJSLHでは出現率1%以上を(+)の報告値としている.
網血小板数の測定と評価の注意点
著者: 金子誠
ページ範囲:P.1112 - P.1115
はじめに
網血小板(reticulated platelets:RP)1〜3)は,骨髄から末梢循環に新たに放出されたばかりの血小板分画であり,血小板造血を反映している.これらの若い未熟な血小板は,成熟した血小板に比べて細胞容積が大きく,RNA量や血小板内顆粒を多く含んでいる.RPのRNAは,巨核球RNAの名残とも考えられていたが,血小板内でもこのRNAにより蛋白合成されていることが示されており,成熟した血小板と比較して反応性が高い血小板である.
RPは定常状態で全血小板数の約5%で,24〜36時間程度でRNA分解が進行し,体積が減少するとされる.骨髄中ではRP数は末梢血の平均2〜3倍で,巨核球の数と相関しており,巨核球増殖のリアルタイムマーカーでもある.このように骨髄における血小板造血を反映していることが,赤血球造血を反映する網状赤血球(reticulocytes)の境遇に類似していることから,網(状)血小板(RP)と呼ばれているが,この同等の意義のある未熟・幼若な血小板分画が自動血液分析装置によって測定できるようになっている1,3).測定機器によってその原理は異なり,そのRPに相当する血小板分画の名称も異なるが,シスメックス社の自動血液分析装置を用いて測定されたものは幼若血小板比率(immature platelet fraction:IPF)と表記される1,3,4).
偽性血小板減少症の鑑別—ITPと診断する前に除外すべき疾患
著者: 高野勝弘
ページ範囲:P.1116 - P.1119
血小板減少症の病態
血小板は骨髄の巨核球によって産生される.巨核球は多倍体を有する巨細胞であり,巨核球系細胞の分化,成熟は肝臓および骨髄のstromal cellにより産生されるトロンボポエチンという増殖因子によって制御されている.巨核球の成熟時間は約5日と推定されており,末梢血に放出されてからの血小板寿命は約7〜10日,正常な末梢血血小板数は約15〜35×104/μLである.
血小板減少は多様な疾患において認められ,その原因は①血小板破壊亢進や消費,②血小板の産生低下,③先天性血小板減少症,④血小板の分布異常,⑤血小板の喪失または希釈に分類できる.
外部精度管理調査の落とし穴
著者: 佐藤尚武
ページ範囲:P.1120 - P.1123
はじめに
外部精度管理の成績は臨床検査部門の評価に利用されることがあるため,できるだけよい成績を得たいという意識が働くことが多い.その結果,日常検査の精度管理レベルと外部精度管理調査の成績に乖離を生じる場合があり,注意が必要である.
本稿では,その実例として東京都衛生検査所精度管理調査で認められた2種類の調査における成績の乖離を紹介する.
2章 血球形態
自動血球分析装置による白血球分画と目視分画値の乖離
著者: 小笠原洋治
ページ範囲:P.1124 - P.1127
はじめに
自動血球分析装置での白血球分類機能は,界面活性剤による各種白血球の体積変化の違いから3種類(顆粒球・単球・リンパ球)に分類するものから始まり,その後,フローサイトメトリー(flow cytometry:FCM)法を組み合わせることで5種類の白血球(好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球)に分類することができるようになった1).自動血球分析装置での白血球分画値は,その分析の迅速性から診療に不可欠な情報となっているが,5種類の正常白血球以外の異常細胞が出現している場合には,目視法との結果の乖離を認めることがあり,自動血球分析装置での結果が不正確になる状況について理解しておく必要がある.
本稿では自動血球分析装置での白血球分画測定原理と,目視法の結果との乖離要因について事例を通じて解説する.
強制乾燥と自然乾燥が形態に及ぼす影響
著者: 朝比奈彩 , 大畑雅彦
ページ範囲:P.1128 - P.1131
はじめに
湿度の高いわが国では,骨髄塗抹標本は一般的に冷風で強制乾燥される.一方,海外では,自然乾燥が一般的である.国内でも一部は湿度が低く,強制乾燥が不要な地域もあり,標本作製の手技は血液検査室の環境に左右されている.形態観察における検査前プロセスとして,標本乾燥の条件が血球形態に影響を及ぼすため,正しい形態判断には,目的に応じた適切な標本作製手順と,適切な標本部位で観察をすることが肝要である.
反応性の異型リンパ球と腫瘍性の異常リンパ球
著者: 土屋逹行
ページ範囲:P.1132 - P.1135
異型リンパ球とは
血液細胞の分化・成熟の過程において顆粒球などの細胞は,成熟すると機能を果たした後,分裂・増殖することなく消滅してしまう.しかし,リンパ球に関しては,成熟した後に取得した感染症病原体の抗原情報などを生体内に残すことが感染防御のために必要なので,リンパ球の一部は分裂・増殖してそのリンパ球が取得した情報を継代する.特にウイルス感染症などで出現する異型リンパ球(atypical lymphocyte)はウイルスにより刺激を受けて感染源の情報を継代するために幼若化した細胞と考えられている.したがって,古くから異型リンパ球が多数認められていることはウイルス感染症であることの推定・診断に有用であることから末梢血中の異型リンパ球比率が求められてきた.しかし,多様な変化をきたすので異型リンパ球と判断する形態的な基準が必要であり,Downey分類をはじめとするいくつかの分類基準がある.しかし,実際は鑑別に苦慮する細胞があり,日常診療で観察者間による結果の乖離がある.
日本検査血液学会では2001年より種々の血液検査に関する標準化を目指す作業が行われており,血球形態標準化小委員会ではリンパ球,異型リンパ球の判断基準の標準化作業が行われ,判断基準の標準化案が発表された1).
抗凝固剤(EDTA)による骨髄標本の形態変化
著者: 大畑雅彦 , 高崎将一 , 朝比奈彩
ページ範囲:P.1136 - P.1139
はじめに
骨髄穿刺塗抹標本は生標本が望ましいが,検査室の対応,特に人的環境などの要因からエチレンジアミン四酢酸(ethylenediaminetetraacetic acid:EDTA)加骨髄液を用いる施設もある.最近,関連学会から一般的な造血細胞の標準化が報告され,形態学的特徴の整理がされている1).しかし,その標準化には標本作製の条件が一致していること,さらに背景として抗凝固剤入り骨髄液の影響について十分に把握していることも重要である.
筆者は以前からEDTA加骨髄塗抹標本における細胞形態への影響2,3)を検討し,論じてきた4).本稿では,これらの知見を紹介し“EDTA加骨髄液の功と罪”を整理したい.
骨髄塗抹像とLLA測定値のずれ
著者: 稲葉亨
ページ範囲:P.1140 - P.1143
はじめに
骨髄塗抹像は造血器腫瘍の診断に不可欠の形態学的検査であるが,フローサイトメトリー(flow cytometry:FCM)での表現型解析(leukemia-lymphoma analysis:LLA)と結果が乖離する場合がある.本稿では,日常診療で遭遇しうるこれらの乖離の要因について概説する.
系統由来や病型分類の判断に迷う腫瘍細胞
著者: 荒木美香 , 荒井智子 , 松下弘道
ページ範囲:P.1144 - P.1147
はじめに
骨髄塗抹標本の観察による形態学的検査は病型分類の第一歩である.一部の症例では,特徴的な形態所見から病型およびそれに伴う染色体異常をある程度,推測することができる.一方で,異常細胞が認められてもその形態学的特徴からは細胞系統の判断が付かず,その後の効率的な追加検査に迷う場合がある.
本稿では,上記のような系統由来や病型分類の判断に迷う異常細胞について,筆者らの経験した実症例を含めて紹介する.
抗がん剤による細胞形態変化
著者: 日下拓 , 田中由美子
ページ範囲:P.1148 - P.1151
はじめに
近年,造血器腫瘍や種々の固形がんに対する多くの抗悪性腫瘍治療薬が開発されている.特に,腫瘍細胞にかかわる特定の分子だけに作用し,腫瘍細胞を破壊あるいは阻害する分子標的治療薬が臨床使用され治療効果が改善している.
一部の治療薬の使用による種々の細胞形態変化に関する報告があるが,本稿では血液検査に従事する検査技師が多く経験する可能性のある抗がん剤による細胞形態変化について解説する.
骨髄検査でのhematogonesの検出
著者: 山﨑悦子
ページ範囲:P.1152 - P.1155
hematogonesの形態的特徴
hematogones(HGs)は正常Bリンパ球前駆細胞である.HGsが多数みられる骨髄生検像ではクラスター形成のないびまん性増加を示す.骨髄スメアでは多くのHGsは10〜20μmで,細胞質はほとんど認められず,核細胞質(nucleocytoplasmic:N/C)比は極めて大であり,核は円形〜類円形で,クロマチンは均一かつ緻密で濃縮した細胞としてみられる1,2).正常Bリンパ球前駆細胞であるため,その成熟段階に応じて形態も変化がみられる.最も幼若なHGsでは,円形核でN/C比が高く,時には顕著な核小体を伴う均質な核クロマチンをもつ.細胞質は好塩基性を示し,封入体,顆粒,液胞などを有することはない.これらはリンパ芽球と酷似しており,特にB細胞性急性リンパ芽球性白血病(B lymphoblastic leukemia/lymphoblastic lymphoma:B-ALL)に対する化学療法後骨髄回復期に,腫瘍性Bリンパ芽球との判別をつけるのは難しい.最も成熟したHGsは濃縮し均一なクロマチンをもち,核小体を認めることはほぼない.成熟Bリンパ球にかなり近い形態となっている.
一般的に,新生児や臍帯血以外に末梢血でHGsをみることはないものの,MCF(multicolor flow cytometry)では多くの小児,成人で少ないながらもHGsを同定することができるとされている.リンパ節においては,TdT(terminal deoxynucleotidyl transferase)を表出する幼若HGsが胎児リンパ節や小児の反応性リンパ節炎などでみられることがあるが,これらの細胞は5個以上のクラスターを呈することはない.
胸腹水の細胞形態のバリエーション
著者: 内田一豊
ページ範囲:P.1156 - P.1159
はじめに
体腔液検査は,体腔液内に貯留してきた要因を明らかにするため,算定や細胞分類を行うことで適切な診断や治療に導いている.細胞分類については,日本臨床衛生検査技師会穿刺液検査標準化ワーキンググループ1)から穿刺液の検査法が提案され,細胞のカウントは計算盤などで行う方法が説明されている.また,自動血球分析装置を用いて体腔液などを測定できることも可能となった報告もある2).
体腔液に出現する細胞は,何らかの反応性により組織球や中皮細胞が出現し,時には悪性細胞の浸潤も観察される.その細胞形態は判断が困難なことに遭遇することもある.
本稿では,胸腹水の細胞形態のバリエーションとして良悪性の細胞所見について述べる.
3章 フローサイトメトリー
検体保存方法によるMPOおよびリンパ球サブセット検査に対する影響
著者: 池亀彰茂
ページ範囲:P.1160 - P.1163
はじめに
近年,医療技術の進歩によって血液検査分野でも検査項目が増えたため,臨床現場からは信頼性の高い検査結果が望まれている.フローサイトメトリー機器を用いたリンパ球サブセットや造血器腫瘍解析は,顕微鏡下による細胞形態像と併せて評価することで,より臨床に貢献することができる検査である.ただし,フローサイトメトリー検査における検体保存,設定および解析方法を正しく実施していることが条件となる.
本稿では,フローサイトメトリー検査による結果値を正しく報告することを目的にして,検体保存,標識蛍光色素選択,コンペンセーションから腫瘍細胞のゲーティング方法について詳しく解説する.
フローサイトメトリー標準化のため米国臨床検査標準化協議会(National Committee for Clinical Laboratory Standards:NCCLS)はapproved guidelineを発行している1,2).わが国においても日本臨床検査標準協議会(Japanese Committee for Clinical Laboratory Standards:JCCLS)から末梢血リンパ球表面抗原検査に関するガイドラインが発表された3).このガイドラインでは,血液検体からのリンパ球の回収は種々の因子が関係しているため,検体は採血後すぐに処理するのが理想的であることが記載されており,それが不可能な場合は各施設において使用抗凝固剤,保存温度,試料調整法などについて新鮮検体と比較・検討しなければならないとしている.腫瘍細胞では,正常細胞と比べて細胞が壊れやすいことや検体材料によっても検体保存条件は異なることを理解しておくことが重要である.
JCCLSのガイドラインでは,18〜22℃で保存して24時間以内に測定するのが望ましいと記載されているが,藤巻ら4)の報告では,24時間室温で放置した検体で死細胞比率の増加を認めたため,採血後6時間以内に測定することが望ましいとしている.特に7-AAD(7-amino-actinomycin D)を用いた死細胞の検討において,ヘパリン採血管と比較してエチレンジアミン四酢酸二カリウム塩二水和物(ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate:EDTA-2K)含有採血管が24時間後では死細胞が顕著となると報告している.
今回,筆者らは,健常者の末梢血を用いて細胞内ミエロペルオキシダーゼ(myeloperoxidase:MPO)およびリンパ球サブセット(CD3,CD19)の経時的影響について検討した.EDTA-2K含有採血管で採血した血液を室温保存(22℃),冷蔵保存(5℃),EDTA-2K全血へ10%ウシ胎仔血清(fetal bovine serum:FBS)+RPMI 1640培地等量混和後に冷蔵保存(5℃)した全血検体を0,6,24,48hごとの各抗原発現に対する経時的影響を調べた.室温保存(22℃)とした保存については,施設環境や気候によって異なるため22℃に設定したインキュベーター内へ検体を保管して検討した.
室温保存と冷蔵保存における側方散乱(side scatter:SS)およびCD45プロット図では,冷蔵保存は各白血球の分画は保たれるが,室温保存では24時間後には好中球分画に対する影響が著しい.一方,冷蔵保存したEDTA-2K全血やRPMI 1640培地等量混和したサンプルでは各白血球分画は保たれていた.しかし,48時間後には冷蔵保存したEDTA-2K全血においても好中球分画が拡散する傾向を認めた.RPMI 1640培地等量混和して冷蔵保存したサンプルでは各白血球分画に対する影響が最も少なかった(図1).
標識蛍光色素選択やコンペンセーションの注意点
著者: 小川恵津子
ページ範囲:P.1164 - P.1167
はじめに
フローサイトメーターと蛍光標識モノクロナール抗体が市販化されてから40年近く経過している.当初はフルオレセインイソチアネート(fluorescein isothiocyanate:FITC)とフィコエリスリン(phycoerythrin:PE)による2カラー解析が主流であったが,その後,新しい蛍光色素が次々と開発され,造血器腫瘍細胞タイピングにおいてはマルチカラー化が進み,測定精度が飛躍的に向上している1).とりわけ,治療後の寛解状態を把握するために有効である微小残存病変の測定では,高感度検出が必要であるため,フローサイトメトリー法による6カラー以上のマルチカラー解析が推奨されている2,3).
本稿では主に造血器腫瘍細胞タイピングに使用されている標識蛍光色素の特徴と,パネル作製時に考慮すべき蛍光補正や蛍光染色パターンの広がり(スプレッド)について解説する.
ゲーティングによっては見落としてしまう腫瘍細胞
著者: 有賀祐
ページ範囲:P.1168 - P.1171
はじめに
フローサイトメトリー(flow cytometry:FCM)法による細胞表面・細胞内抗原(マーカー)の検索は白血病やリンパ腫の診断に欠かせない検査の1つとされ,病型分類や治療効果判定を行ううえで有用である1).対象領域の絞り込み(ゲーティング)は,FCMの結果を理解しやすくするうえで,あるいは目的の細胞(主に腫瘍細胞)にフォーカスして解析を明確にするうえで重要な操作である.
本稿では,注意すべきゲーティングのポイントについて,筆者が経験し教訓と感じた事例を用いて解説する.
細胞内抗原解析の注意点
著者: 林田雅彦
ページ範囲:P.1172 - P.1175
はじめに
フローサイトメトリー(FCM)による造血器腫瘍細胞抗原検査は病型分類および治療方針や予後推定に重要である.しかし,急性白血病細胞は未成熟な段階であることから,細胞表面における系統特異的な抗原の発現が弱いもしくは欠失,腫瘍細胞であるが故に他の系統抗原の異常な発現を認めることがあり,系統帰属の決定に苦慮する.特に混合表現型急性白血病は,細胞内抗原と細胞表面抗原の多重染色が必要となる1).FCMの正確な測定は,さまざまな細胞および細胞成分によるバックグラウンド蛍光によって妨げられることがある.バックグラウンドの原因には,自家蛍光,蛍光スペクトルの重なり,非特異な抗体の結合や吸着が存在する.これらの要素を十分に理解し,バックグラウンドの最小化および抗原陽性と陰性細胞の確実な識別は,細胞表面および細胞内抗原の解析において重要である.細胞内抗原のための固定・透過処理は,抗体との親和性や特異性の低下の要因となり,さらに陰性閾値の設定が困難であることから施設間差の原因となる.
本稿では,造血器腫瘍細胞抗原検査における細胞内抗原染色の注意点について解説する.
フローサイトメトリー検査と形態学分類による骨髄腫細胞比率の相違
著者: 永井直治
ページ範囲:P.1176 - P.1179
はじめに
近年,フローサイトメトリー(flow cytometry:FCM)検査は,測定装置や抗体試薬の開発により,複数抗原を同時に染色するマルチパラメーターフローサイトメトリー(multiparameter flow cytometry:MFC)化が進み,形質細胞腫瘍の診断に効力を発揮している.MFCは対象となる細胞の抗原異常を複合的に評価できるため,特徴的な免疫形質を用いて腫瘍細胞を段階的に絞り込むことで,高感度かつ特異的に解析が可能となる.しかし,解析で得られる形質細胞比率はFCM検査と骨髄血目視分類での乖離をしばしば認める.
本稿では,その原因および対策について解説する.
フローサイトメトリーと免疫組織染色の結果乖離
著者: 香月奈穂美 , 中峯寛和
ページ範囲:P.1180 - P.1183
はじめに
フローサイトメトリー(flow cytometry:FCM)は,未固定遊離細胞を試験管内で免疫反応にて染色(免疫細胞染色)し,流体力学的,光学的ならびに情報工学的にデジタルデータを得る検査である1).一方,免疫組織染色/免疫組織化学(immunohistochemistry:IHC)は,通常はホルマリン固定パラフィン包埋切片上で免疫反応にて染色し,担当者が光学(時には蛍光)顕微鏡下で観察することにより,アナログデータを得る検査である.
本稿ではまず,結果乖離にかかわる両検査の違いについて整理する.次に,リンパ腫を例に結果乖離の一部について具体的に解説する.
診断に有用な異常発現(aberrant expression)
著者: 藤原亨
ページ範囲:P.1184 - P.1187
はじめに
フローサイトメトリー(flow cytometry:FCM)を用いた表面抗原解析は造血器腫瘍の診断に必須の検査法である.造血器悪性腫瘍細胞は正常細胞の分化段階と同一の抗原を示す場合と,通常では発現しない抗原の異常発現を認める場合がある.特に後者については疾患特異的であることが多く,さらに治療後の微小残存病変(minimal residual disease:MRD)の評価にも有用である.
本稿では,実際の症例提示を通じてFCM検査における造血器腫瘍の診断に有用な異常発現(aberrant expression)を述べる.
系列同定が悩ましい白血病細胞・リンパ腫細胞
著者: 池本敏行
ページ範囲:P.1188 - P.1191
はじめに
成熟B細胞腫瘍の表面形質による細胞同定には,汎B細胞抗原であるCD19やCD20,CD22に加えてCD5やCD10,CD23,CD200などが利用され,リンパ腫細胞の同定には免疫組織染色による細胞内抗原も利用される1).成熟B細胞腫瘍の病型分類にはCD5とCD10の発現検索が有効であり,CD5+B細胞腫瘍には慢性リンパ性白血病(chronic lymphocytic leukemia:CLL)とマントル細胞リンパ腫(mantle cell lymphoma:MCL)があり,通常CLLはCD5+CD23+,MCLはCD5+CD23−として区別されるがCD23を発現するMCLがある(表1)1).転写因子のLEF1(lymphoid enhancer-binding factor1)もCLLに特異性が高いとされるが,びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma:DLBCL)やgrade 3の濾胞性リンパ腫(follicular lymphoma:FL)でも陽性になる症例がある(表2)2,3).表面抗原の発現量の違いもCLLと他の成熟B細胞腫瘍を鑑別する重要な情報であるが,CLLには非典型例も多く3),特に白血化あるいは骨髄浸潤したMCLとCLLの鑑別には苦慮することがある.
本稿では特にCLLと白血化/骨髄浸潤したMCLの鑑別方法について述べる.
フローサイトメトリー法によるhematogonesと腫瘍細胞の鑑別
著者: 渡邉珠緒
ページ範囲:P.1192 - P.1195
はじめに
hematogones(HGs.非腫瘍性Bリンパ球前駆体)は健康な子どもから大人までの骨髄検体でみられ,B細胞性急性リンパ性白血病(B-cell acute lymphoblastic leukemia:B-ALL)細胞と形態学的特徴や免疫表現型が類似している.また,HGsは化学療法後や同種造血幹細胞移植後の再生期に多数認める場合があり,特にB-ALL症例では,回復期によるHGsか,再発による白血病細胞かの鑑別が重要となる.
抗体製剤の使用の影響
著者: 西川真子
ページ範囲:P.1196 - P.1199
はじめに
抗体製剤は標的抗原に対する高い特異性と親和性を有し,単剤もしくは従来の化学療法薬との併用によって造血器腫瘍の治療成績を有意に向上させた.現在,抗体製剤は白血病,リンパ腫,骨髄腫などに対して広く用いられている.一方で,抗体製剤に対する耐性も経験される.
本稿では,抗体製剤の使用によるフローサイトメトリー検査(flow cytometry:FCM)への影響について概説する.
4章 凝固
採血管不良によるAPTT延長事例を踏まえた異常値への対処方法
著者: 近藤宏皓 , 久保田芽里 , 大坂直文
ページ範囲:P.1200 - P.1202
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)は,内因系凝固機能のスクリーニングや抗凝固療法のモニタリングなどの目的で日常的に測定されている項目である.測定原理は,まず試薬中の陰性に荷電した活性化剤によって凝固第Ⅻ因子を活性化させ,続いて第Ⅺ因子を活性化する.その後,カルシウムを加えることで第Ⅸ因子,第Ⅹ因子,プロトロンビンと続き,最終的に生成されるフィブリンによる性状の変化を検出する方法が一般的である.また,採血管の抗凝固剤としてクエン酸ナトリウムが用いられるが,これは血中のカルシウムをキレート除去することで抗凝固活性を発揮する.大阪医科薬科大学病院(以下,当院)では米国臨床検査標準協会(Clinical and Laboratory Standards Institute:CLSI)の提案に基づき,クエン酸ナトリウム濃度が3.2%の採血管を使用している.
APTTが延長する原因には,未分画ヘパリンや直接経口抗凝固薬などによる抗凝固療法,血友病や抗リン脂質抗体症候群などをはじめとした患者の病態に起因するものが挙げられる.しかし,実際に検査を行うに当たっては,採血手技や各種の測定条件など結果に影響を及ぼしうる要因が多数存在する.したがって,APTTの延長を認めた場合は結果が妥当であるかどうかを見極める必要がある.
本稿では,筆者らが以前に経験した採血管不良によるAPTT異常値多発事例について,原因の特定に至った過程を紹介し,またAPTT異常値に遭遇した際の対処方法について述べる.
未分画ヘパリンまたはヘパリン類似物質(低分子量ヘパリン・ダナパロイドナトリウム・フォンダパリヌクス)の混入によるAPTT延長
著者: 下村大樹
ページ範囲:P.1204 - P.1207
ヘパリンの種類と用途
ヘパリンはアンチトロンビン依存性に抗凝固作用(抗活性化Ⅹ因子:Ⅹa,抗トロンビン)を発揮する.ヘパリンの種類には,未分画ヘパリン,低分子量ヘパリン,ダナパロイドナトリウムおよびフォンダパリヌクスがあり,それぞれ抗Ⅹa/トロンビン作用の比率,半減期が異なる(表1).ヘパリンの用途は,播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation:DIC)の治療,血液透析・人工心肺などの体外循環装置使用時の血液凝固防止,血管カテーテル挿入時の血液凝固防止,静脈内留置ルートの血液凝固防止,血栓塞栓症(静脈血栓症,心筋梗塞症・肺塞栓症・脳塞栓症・四肢動脈血栓塞栓症・手術中・術後の血栓塞栓症など)の治療および予防など多岐にわたる.
—APTT試薬間での測定値の乖離—凝固因子感受性
著者: 桝谷亮太
ページ範囲:P.1208 - P.1211
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)は,接触相の活性化を起点として始まる内因系凝固反応を反映する検査であり,血友病をはじめとする先天性内因系凝固因子欠乏症やループスアンチコアグラント(lupus anticoagulant:LA),凝固因子インヒビターの存在によって凝固時間が延長する.また,APTTは上記の凝固異常症以外にも,未分画ヘパリンや直接経口抗凝固薬などの抗凝固療法のモニタリングにも用いられており,施設内でも日常的に実施される有用な検査である.その反面,病態や疾患に対する感度・特異度における試薬間差が課題でありAPTTの直接的な標準化は困難である1).主な理由として,市場に流通しているAPTT試薬の組成や濃度が多岐にわたることが挙げられる.執筆時点における代表的なAPTT試薬の一覧を表12)に示す.
APTT試薬は第1試薬として,陰性荷電物質である活性化剤やリン脂質を含む溶液と,第2試薬として塩化カルシウム溶液で構成される.この活性化剤およびリン脂質の種類や濃度がAPTTに影響を及ぼす要因として重要であり,APTT試薬間での測定値の乖離を生じさせる原因となっている.そのため,測定値の乖離を理解するためには,検査に用いるAPTT試薬の組成を把握しておくことが必須である.特にLAの検出においては用いるAPTT試薬によって感受性が大きく異なることが知られているが,これは本号の「ループスアンチコアグラント感受性」の項で詳細に解説されるためそちらを参照していただきたい.
本稿では,APTT試薬間での測定値の乖離のうち,凝固因子感受性について解説する.
—APTT試薬間での測定値の乖離—ループスアンチコアグラント感受性
著者: 徳永尚樹
ページ範囲:P.1212 - P.1215
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)は内因系および共通系の凝固因子活性を評価する検査であり,出血傾向のスクリーニング検査として用いられている.APTTが延長する疾患や病態は多岐にわたり,血友病を代表とする内因系・共通系の凝固因子欠乏や,抗リン脂質抗体(antiphospholipid antibodies:aPL)症候群,ヘパリンなど抗凝固薬の投与,肝機能低下,播種性血管内凝固症候群などさまざまである.しかしながら,APTTは,その試薬組成の違いにより,病態によっては結果値が大きく異なる場合がある.現在,上市されているAPTT試薬は10種類以上あるため,APTT値の評価には注意が必要である.他院からの紹介時に記載されているAPTT値と自施設で測定したAPTT値が異なる場合もあり,試薬の特性を理解しておかなければ真の病態を見逃してしまう可能性がある.
本稿では,APTTを延長させる要因の1つであるループスアンチコアグラント(lupus anticoagulant:LA)におけるAPTT試薬間の測定値の乖離と,そこからわかる病態鑑別の方法について述べる.
—APTT試薬間での測定値の乖離—APTT試薬のヘパリン感受性の違い
著者: 鈴木典子
ページ範囲:P.1216 - P.1219
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)は内因系血液凝固スクリーニング検査や,循環抗凝血素の検索,未分画ヘパリン投与の確認などを目的として検査が行われている.APTTの測定に使用されるAPTT試薬は,接触因子の活性化剤(シリカ,エラグ酸など)とリン脂質(合成,動植物由来)によって構成され,これらの種類,濃度などの違いにより凝固因子,ループスアンチコアグラント,未分画ヘパリンに対する感受性の違いがあることが知られている1〜4).
本稿では,筆者らが行ったAPTT試薬の未分画ヘパリンに対する感受性について紹介する.
直接経口抗凝固薬(DOAC)使用時の凝固関連検査の乖離(AT活性およびPS活性検査試薬)
著者: 森下英理子
ページ範囲:P.1220 - P.1223
はじめに
直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulant:DOAC)は2011年に初めてわが国に導入され,現在までに4種類が使用可能となっている.DOACは標的因子の違いから直接トロンビン阻害薬(direct thrombin inhibitor:DTI.ダビガトラン)と直接活性型第Ⅹ因子(factor Ⅹa:FⅩa)阻害薬(リバーロキサバン,アピキサバン,エドキサバン)に分類される.DOACの作用機序からもわかるように,本剤は一般的に使用されているグローバルな凝固時間〔プロトロンビン時間(prothrombin time:PT)および活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)〕や1),アンチトロンビン(antithrombin:AT)・プロテインC(protein C:PC)・プロテインS(protein S:PS)などの凝固阻止因子活性やループスアンチコアグラントなどの凝固検査に影響を及ぼす2,3).特に血栓症の原因精査の際,すでにDOACを内服している場合は,DOACの種類や測定法によっては凝固阻止因子活性値が偽高値となり,欠乏症の診断を見落とす可能性があるため,十分にその影響について熟知しておく必要がある.
本稿では,特にAT活性とPS活性に及ぼすDOACの影響について自験例を含めて紹介する.
エミシズマブによるAPTTへの影響
著者: 山口知子 , 長尾梓
ページ範囲:P.1224 - P.1227
エミシズマブとは
血友病Aは血液凝固第Ⅷ因子(factor Ⅷ:FⅧ)の量的・質的異常に伴う出血性疾患である.治療として血液凝固第Ⅷ因子製剤の投与を行うが,静脈内投与が必要であること,重症患者では週に2〜3回の頻回な定期投与が必要であること,抗FⅧ抗体(インヒビター)による薬効の消失があるなどの問題点があった.
エミシズマブは,活性型第Ⅸ因子(FⅨa)と第Ⅹ因子(FⅩ)とに結合する二重特異性抗体であり,活性型FⅧと同様に凝固作用を示す(図1)1).皮下注射が可能で,半減期が長いため,投与間隔を1〜4週に延長できることや,インヒビターの有無にかかわらず有効であることなどの利点がある.先述した血液凝固因子製剤の問題点を克服し,発売以降,世界的に広く使われ始めている.
小児の一過性APTT延長
著者: 岡田直樹 , 藤澤麗子 , 犀川太
ページ範囲:P.1228 - P.1231
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)に影響する病態は,APTT検査を構成する要素別に分けて考えると理解しやすい.APTT検査は,リン脂質依存性凝固時間の1つであり,被験者血漿中の凝固因子とAPTT試薬(凝固第Ⅻ因子と第Ⅺ因子の試験管内活性化を目的とした活性化剤,塩化カルシウムおよびリン脂質を含む)を用いて実施される.したがって,①内因系および共通系の凝固因子活性低下(凝固因子の量と機能の低下およびインヒビターの存在)と②抗リン脂質抗体の存在によりAPTTは延長する.具体的には,先天性凝固異常症として凝固第Ⅷ因子や第Ⅸ因子が欠乏する血友病と凝固第Ⅷ因子の運搬蛋白であるvon Willebrand因子の不足や機能異常が原因のvon Willebrand病があり,一方,後天性凝固異常症として凝固因子に対するインヒビターの出現やリン脂質に対する自己抗体が凝固反応を遅延させる抗リン脂質抗体症候群が知られている.
本稿では,感染症を契機とした小児の一過性抗リン脂質抗体陽性について解説する.本病態では“APTT延長があるにもかかわらず出血症状や血栓症状は伴わない”という“検査結果と臨床症状の乖離”に直面する.自験例の臨床的特徴とその経過を提示し,小児の後天性APTT延長を認めた場合の対応について概説する.
—フィブリノゲンの偽低値—ヘパリン・トロンビン阻害薬の影響
著者: 藤森祐多
ページ範囲:P.1232 - P.1235
フィブリノゲン測定法
フィブリノゲン測定法を表1に示す.日常の臨床検査で最も用いられているフィブリノゲン測定法はトロンビン時間法(Clauss法)であり,自動分析装置で実施することが可能である.トロンビン時間法は試薬としてトロンビンを血漿に加えフィブリノゲンからフィブリンが形成するまでの凝固時間を測定し,フィブリノゲン量に換算する比較的簡単な原理に基づく検査法である(図1).血漿に加えるトロンビン試薬は血漿中の抗トロンビン物質(アンチトロンビン,ヘパリンコファクターⅡ)の影響を抑えるために過剰量が含まれているものの,試薬ごとにトロンビン濃度が異なることが知られている.過剰量のトロンビンが血漿中のフィブリノゲンをフィブリンに変換するために,本来は生体内で生じる少量のトロンビンが凝固第Ⅷ因子や凝固第Ⅴ因子といった凝固因子を活性化することによって起こるトロンビンポジティブフィードバックは検査原理上,関与しない.
本稿で最も伝えたいことは,フィブリノゲン測定試薬中には過剰なトロンビンが含まれていることから,トロンビン活性を阻害するような薬剤の影響に対しても比較的安定的に測定を行うことができるため,日常臨床でフィブリノゲン測定をするなかでトロンビン阻害薬によってフィブリノゲンが偽低値に測定されるという可能性をそれほど心配する必要はないということである.ただし,トロンビン活性を阻害するような薬剤が試薬のトロンビン活性を上回るほど血中に存在していた場合には,フィブリノゲンがフィブリンに変換されるまでの凝固時間が延長し,結果としてフィブリノゲンの偽低値を引き起こす可能性がある.日常の臨床で使用されるトロンビン活性を阻害する薬剤として,未分画ヘパリンや直接トロンビン阻害薬が挙げられる(表2).
—フィブリノゲンの偽低値—IgA M蛋白血症
著者: 新井慎平
ページ範囲:P.1236 - P.1239
はじめに
フィブリノゲン(fibrinogen:Fbg)は血液凝固能を評価する際に測定される凝固スクリーニング項目の1つである.測定原理の異なる測定法がいくつかあるが,分析装置への適用性や測定に要する時間・試薬コストなどの観点から,日本国内のほとんどの検査室ではClauss法を原理とした方法で測定されている(Fbg活性値).
Fbgは血中成分のなかで濃度の高い蛋白であり,さまざまな病態によって血中濃度は大きく増減し,基準範囲を超えた異常値と遭遇することはそれほど珍しくはない.臨床的には低値となる病態(後天的要因)の鑑別が重要視されることが多いが,凝固検査担当者はその低値が病態を反映した真値ではない,すなわち,偽低値の可能性を念頭に置いて鑑別する必要がある.直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulants:DOAC)による偽低値(前項目「ヘパリン・トロンビン阻害薬の影響」参照)もあるが,検査室で遭遇するFbg偽低値の多くは採血不良による検体凝固やフィブリン(fibrin:Fbn)析出による吸引エラーなどの技術的要因である.一方,免疫学的測定法でたびたび問題となるような測定系に関連した異常反応はほとんど経験しない.
多くの場合,後天的要因や技術的要因が否定された場合には先天性の異常Fbg血症を疑うことになる(次項目「フィブリノゲン分子異常」参照).筆者は,Fbg活性値が異常低値を示し先天性Fbg異常症が疑われた患者で,免疫グロブリン(immunoglobulin:Ig)AのM蛋白が関与した後天性Fbg異常症の症例を経験した.
本稿では,偽低値を証明した精査方法とそのメカニズムについて解説していく.
—フィブリノゲンの偽低値—フィブリノゲン分子異常
著者: 鈴木敦夫
ページ範囲:P.1240 - P.1243
フィブリノゲン分子異常に起因する“乖離”
フィブリノゲン分子異常は,遺伝子異常に起因する先天性異常症と,産生臓器である肝臓の異常に起因する後天性異常症に区分される.両者とも比較的まれな疾患であるが,前者については約半数が無症候性であり,把握されている患者数以上に潜在的な患者数が一定数存在していると考えられている.しかし,日常検査ではみつかりにくいことも相まって,はっきりとした有病率が把握できていない.
2022年現在,日常検査としてほとんどの施設で採用されているフィブリノゲン検査法はClauss法と呼ばれる測定手法である.本稿では,フィブリノゲンの分子異常がもたらすフィブリノゲン測定における乖離現象を解説する.
—FDPやDダイマーの上昇—採血不良
著者: 高田章美
ページ範囲:P.1244 - P.1247
はじめに
フィブリノゲン/フィブリン分解産物(fibrinogen/fibrin degradation products:FDP),Dダイマーは播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation:DIC)や血栓症などのさまざまな疾患において高値を示す.しかし,まれに患者の病状や時系列結果から考えにくい検査値の上昇がみられ,偽高値を疑う症例に遭遇することがある.その原因として,採血手技の不備によるクエン酸ナトリウム(sodium:Na)血漿検体(以下,検体)の凝固による影響があり,まれであるが免疫学的測定の非特異反応による関与も考えられる.特に,凝固検査においては血液が凝固した検体での測定は不適切であることは周知の事実であり,検体が適切であると判断することが重要である.
本稿では,採血手技によるFDP,Dダイマー偽高値の原因や対処方法について紹介する.
—FDPやDダイマーの上昇—腹水・胸水由来
著者: 窓岩清治
ページ範囲:P.1248 - P.1251
はじめに
腹水や胸水貯留は,さまざまな疾患によって体腔内に生理的な量を超えて体液が貯留した病態である.腹水や胸水貯留は患者の循環器・呼吸器系に大きな負荷を及ぼすことがあるため,穿刺などによる迅速な診断と適切な治療が求められる.一方で,体液の貯留をきたす患者では,凝固線維素溶解(以下,凝固線溶)系の活性化の指標であるフィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation products:FDP)やDダイマーの増加を示すことがある.腹水や胸水貯留の貯留をきたす基礎疾患は,同時に凝固線溶系の活性化を伴うような病態であることも多く,FDPやDダイマーの上昇のみから患者の凝固線溶病態を正確に把握することは容易ではない.
本稿では,腹水および胸水貯留に伴う血液凝固線溶系の病態とともに,FDPやDダイマーの生成機序と解釈について概説する.
—FDPやDダイマーの上昇—IgA由来の非特異反応
著者: 勢井伸幸
ページ範囲:P.1252 - P.1255
はじめに
フィブリン/フィブリノゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation product:FDP)やDD構造を有するフィブリン分解産物であるDダイマーなど,抗原抗体反応を測定原理とする免疫学的測定法は,測定系に用いる抗体により反応性が異なることを十分に理解しておく必要がある.測定値が非特異反応を起こす原因は種々あるが,桜井1)の調べによると,“Dダイマー測定系”異常反応の原因である免疫グロブリン(immunoglobulin:Ig)クラスは,吸収試験により異常反応の原因抗体がわかった件に関し,1996〜2003年の統計(全133ケース)において,検体Ig由来異常反応97件,直線性不良・FDP値とのバランス不良29件,その他の異常反応7件であった.検体Ig由来異常反応の内訳はIgG,IgA,IgMおのおの5,14,78件で百分率比はIgG:IgA:IgM=5:15:80であったとしている.
Dダイマーの測定原理は,検体と抗Dダイマーモノクーロナル(マウス)感作ラテックスを混合すると,検体中の濁度が増加する.その濁度変化量を波長600〜800nmで測定する.また,同様に操作して得られた標準液の濁度変化量と比較することによって検体中のDダイマー濃度を求める2).Dダイマー測定において偽高値となる原因としては採血手技,試薬による非特異反応などが考えられる.そのなかで一番影響を与えるのは採血手技によるものであり,駆血帯の締めすぎや長時間駆血帯を巻くことによる採血管内での凝固線溶反応の亢進である.
筆者は,患者血漿中のIgAがDダイマー測定用試薬(リアスオートTM・Dダイマーネオ.シスメックス社)と非特異反応を起こし偽高値となったと考えられた症例を経験したので,その原因,対策法などを症例提示しながら解説する.
—FDPやDダイマーの上昇—血管免疫芽球性リンパ腫の非特異反応
著者: 徳竹孝好
ページ範囲:P.1256 - P.1259
はじめに
血管免疫芽球性T細胞リンパ腫(angioimmunoblastic T-cell lymphoma:AITL)は非Hodgkinリンパ腫の1.2〜2.5%に認められ,全身のリンパ節腫脹,肝脾腫,発熱,皮疹,自己免疫性溶血性貧血,高γグロブリン血症などを症状とする1).増加するγグロブリンは,B細胞性腫瘍の単クローン性と異なり多クローン性である.
一方,血液腫瘍性の高γグロブリン血症では,しばしば抗原抗体反応を原理とする検査項目において非特異反応を示すことが報告されている2,3).フィブリン/フィブリノーゲン分解産物(fibrin/fibrinogen degradation product:FDP)とDダイマー(D-dimer:D-D)測定においても抗原抗体反応が用いられているため,非特異反応の報告がみられる4〜6).これらの報告はモノクローナル蛋白(以下,M蛋白)を有するB細胞性腫瘍の症例が中心であり4,5),T細胞性腫瘍での報告は筆者らが報告したAITLの1例にとどまる6).
今回,本症例のデータの見直しを行い,当初は増加した免疫グロブリン(immunoglobulin:Ig)Mが非特異反応の主要因と考えていた推測に,IgGの影響も加味される解析結果を得た.本稿では,希釈法やその他の原因究明法も含め,非特異反応の発見の経緯,対処法を述べる.
不適切な遠心処理による血漿中残存血小板が凝固検査,特にLA検査に及ぼす影響
著者: 小宮山豊 , 松田将門
ページ範囲:P.1260 - P.1263
はじめに
活性化部分トロンボプラスチン時間(activated partial thromboplastin time:APTT)やプロトロンビン時間(prothrombin time:PT)など凝固時間検査(以下,凝固検査)は止血異常の有用なスクリーニング検査であるが,その標準化や精度保証はいまだ不十分である.特に遠心処理など検査前処理がどのように凝固検査結果に影響するかについて臨床検査技師や医師の知識や理解は不十分な部分があり,わが国ではこれらの議論に関するガイドラインも規定されていなかった.そのため,日本検査血液学会は,凝固検査の精度保証を目指した第一歩として「凝固検査検体取扱いに関するコンセンサス」(以下,コンセンサス)を邦文と英文で作成し,適正な検査前処理の普及に努めている1,2).
本稿では,①凝固検査が血小板由来のリン脂質の影響を受ける検査であること,②遠心処理後の血漿検体には血小板が残存しない前提で検査診断は進むが不十分な遠心処理では凝固検査に影響する血漿中残存血小板が存在すること,③院内で求められる迅速検査に対応しようと高速遠心処理してしまうとトロンビン活性化を招くこと,これらに対する不理解と現実を提示し,不適切な遠心処理を改善することによる血液検査結果乖離防止法を提示する.
組織液中の組織因子(TF)の混入による凝固時間を用いた検査への影響
著者: 松本智子 , 下村大樹
ページ範囲:P.1264 - P.1266
はじめに
生体内における凝固の引き金は血管壁が損傷し,血液が組織液中の組織因子(tissue factor:TF)と混ざることである.TFは血液が直接接する血管内皮や心内膜や赤血球には存在せず,血管外膜,心筋,表皮,大脳皮質,消化管粘膜などに存在する1).一方,TFが混入した血液検体では凝固検査に大きく影響する.これは診断や治療が変わってしまうため,検査結果の解釈に注意すべきである.
本稿では,TF混入の影響について凝固時間を測定する検査を中心に概説する.
ヘマトクリットが凝固検査データに与える影響
著者: 谷田部陽子
ページ範囲:P.1268 - P.1271
はじめに
凝固検査は,不安定な凝固因子を含む多数の因子が複雑に絡み合い活性化する凝固カスケードを測定する検査である.採血から測定前までにはいくつかの注意事項があり,それを怠ると測定結果に影響する恐れがある.凝固検査には,抗凝固剤としてクエン酸ナトリウムが添加されている採血管を用いる.クエン酸ナトリウムと血液の割合は1:9と決められており,規定量の血液を過不足なく採血管に採取しなければならない.しかし,規定量が守られたとしても,ヘマトクリット(hematocrit:Ht)値により抗凝固剤との割合が不適となるケースがある.
本稿では,その原因と対策について解説する.
複数の凝固因子インヒビター陽性(LAHPS/LLS)
著者: 内藤澄悦 , 家子正裕
ページ範囲:P.1272 - P.1275
はじめに
ループスアンチコアグラント(LA)は抗リン脂質抗体(aPL)の1つであり,抗リン脂質抗体症候群(APS)の診断的検査所見の1つでもある.また,LAを含むaPLはそれぞれが独立する血栓危険因子であるが,まれに出血症状に関与することがある.主に感染症や自己免疫疾患を基礎疾患とした小児および若年女性のLA陽性者に認められ,プロトロンビン活性の低下を伴う.プロトロンビンそのものに対するaPLではない自己抗体(anti-FⅡ Ab)が検出される場合が多く,LAHPS(LA-hypoprothrombinemia syndrome)と呼ばれている1).LAHPSは当初,感染症後の小児や膠原病に罹患した若年女性に多いとされたが,高齢者での報告も増えてきている2).
プロトロンビン活性は正常で,その他の凝固因子活性が低下し,時に出血症状を認めるLA症例に遭遇することがある.LAHPSに類似した症例のため,LLS(LAHPS like syndrome)と呼ばれている3).LAの臨床的意義は血栓リスクであるが,LAを基本病態とするLAHPSやLLSは時として著しい出血症状をきたす極めてまれで複雑な病態と考えられている.
本稿では,LAHPSやLLSの臨床症状や検査所見,後天性血友病A(AHA)との鑑別方法について解説する.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1092 - P.1093
バックナンバー「今月の特集」一覧 フリーアクセス
ページ範囲:P.1276 - P.1276
基本情報
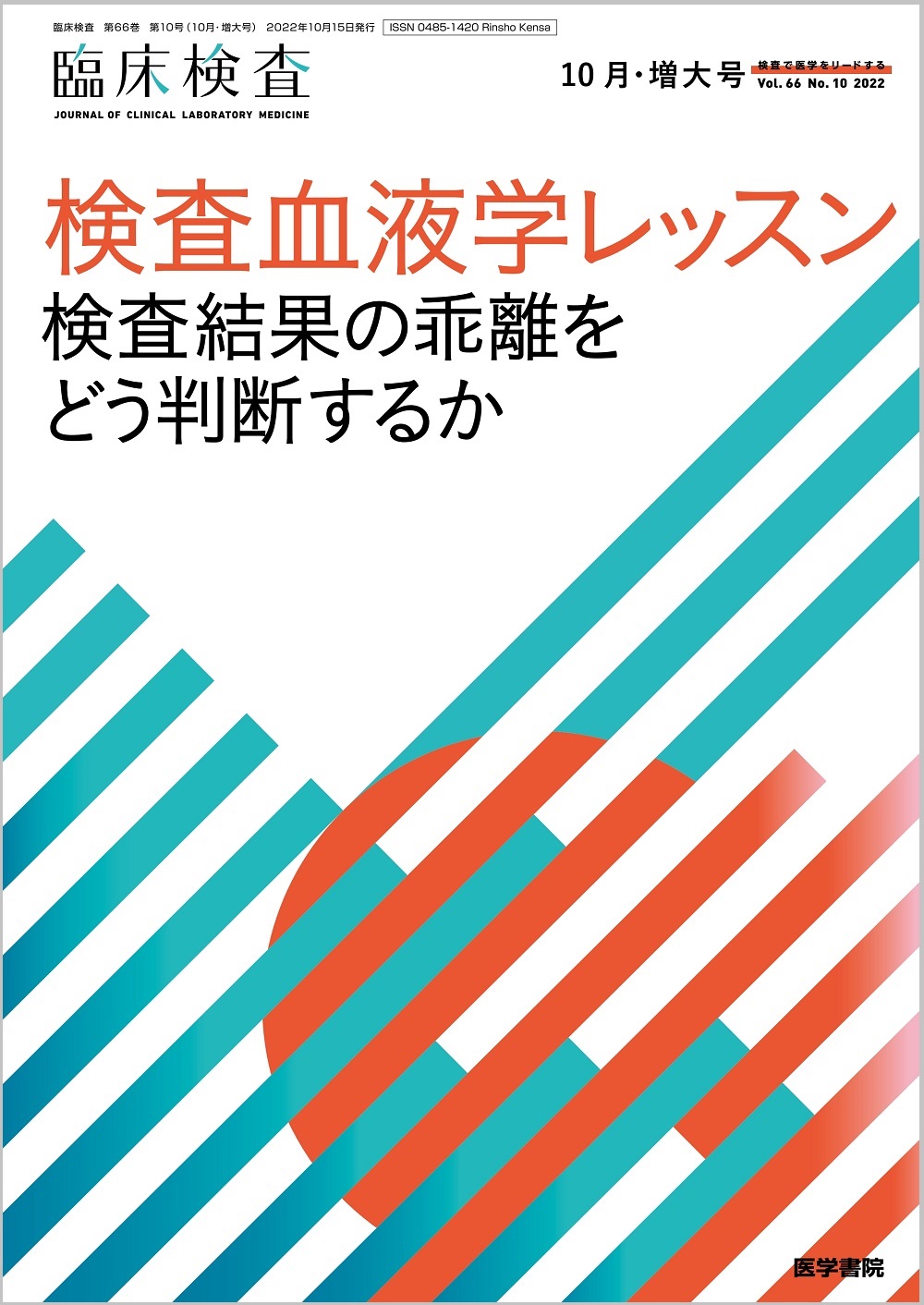
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
