肝疾患は,現代社会における深刻な健康問題になっています.肝臓は,代謝物の合成や解毒,胆汁の生成など,さまざまな生理学的プロセスを担っており,その機能が低下することで人体に深刻な影響を及ぼします.そのため,肝臓の状態を適切に評価し,早期に病態を把握することが重要です.本書「肝疾患 臨床検査でどう迫る?」は,特に肝臓の臨床検査に焦点を当て,最新の知見と実践的なアプローチを提供することを目的として企画致しました.
肝疾患の診療にかかわる医療従事者にとって,正確で包括的な臨床検査情報の理解は,意思決定の基盤となる重要な要素ですが,肝臓の機能や構造の複雑さ,病状の多様性から,病体にかかわる臨床検査の解釈は医療従事者にとって難題となっています.
雑誌目次
臨床検査67巻10号
2023年10月発行
雑誌目次
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
はじめに フリーアクセス
著者: 佐藤雅哉
ページ範囲:P.1007 - P.1007
序章 総論
肝臓とは—肝臓の構造と働き
著者: 爲田雅彦 , 中川勇人
ページ範囲:P.1012 - P.1017
はじめに
肝臓は人体にとって重要な臓器であり,幅広い役割を担っている.
本稿では,肝臓の構造と機能について解説し,その働きや肝疾患についての理解を深めることを目的としている.
—肝臓に起こる主な病気—急性肝炎
著者: 中山伸朗
ページ範囲:P.1018 - P.1023
はじめに
感染症発生動向調査によると,A型肝炎は,4年に一度の流行年に相当するはずの2022年,前年より報告数が減少したが,E型肝炎は徐々に報告数が増加し,2021年にA型,B型を抜いて第1位となるなど,近年,急性肝炎の疫学には変化が生じている.
本稿では,急性肝炎の定義,病態,疫学的動向から,重症化して急性肝不全に進展した場合の予後までを概説する.
—肝臓に起こる主な病気—慢性肝炎
著者: 平松直樹
ページ範囲:P.1024 - P.1030
慢性肝炎の疾患概念
慢性肝炎は,肝臓の炎症が6カ月以上持続する疾患として定義されている.原因には,肝炎ウイルス(B型ならびにC型)の感染,自己免疫性,アルコール性,代謝性,薬物性などがある(表1).わが国では,かつてC型肝炎ウイルス(hepatitis C virus:HCV)感染が慢性肝炎の約7割,B型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)感染が約1〜2割を占めていたが,近年,HCVは抗ウイルス療法によりほぼ100%排除され,C型肝炎の比率は減少し,非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)が増加傾向にある.
一般に,肝炎が増悪しても自覚症状がないことが多く,検査をしなければ本人は気付かないことが多い.このため,厚生労働省では,保健所などにおける肝炎ウイルス検査の促進や医療費助成を含めた患者支援などを行い,積極的に肝炎対策を進めている.
—肝臓に起こる主な病気—肝硬変
著者: 淺岡良成
ページ範囲:P.1032 - P.1037
はじめに
肝硬変は,慢性肝障害の終末像である.原因では,ウイルス性が最も多かったが,スクリーニングや治療の進歩により減少し,アルコール性や非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis:NASH)によるものが増加している.
原因に対する治療により肝病態の増悪を防ぐとともに,患者管理に関しては,肝癌や静脈瘤の定期的なサーベイランスを行い,肝硬変の症状である腹水や肝性脳症に対する治療によりQOL(quality of life)を維持することが重要である.
そのためには,各種検査により炎症,線維化,発癌リスクなどを精確に把握し,状態に応じて治療,検査計画を立てる必要がある.
—肝臓に起こる主な病気—肝臓癌
著者: 岩永光巨 , 叶川直哉 , 小笠原定久 , 加藤直也
ページ範囲:P.1038 - P.1043
はじめに
肝臓癌,すなわち原発性肝癌は肝臓を原発として発生する癌である.原発性肝癌には肝細胞癌(hepatocellular carcinoma:HCC),肝内胆管癌,細胆管細胞癌,胆管囊胞腺癌,混合型肝癌,肝芽腫,未分化癌などが含まれる.「第22回全国原発性肝癌追跡調査報告(2012〜2013)」1)によると,原発性肝癌のうちHCCが全体の91.1%を占め,次いで肝内胆管癌が多く6.4%,HCCと肝内胆管癌の性質を併せもつ混合型肝癌が1.0%であり,その他の組織型の原発性肝癌は1%未満とごく少数であった.原発性肝癌は予後不良の癌であり,部位別でみると男性では世界で2番目に,女性でも6番目に死亡者数が多い癌である2).罹患者数,死亡者数ともに増加傾向で,特にアジアで多いことが知られている.
本稿では原発性肝癌の大部分を占めるHCCに関して概説する.
1章 肝関連検査の見方
肝臓の炎症にかかわる検査—肝臓に起こる“火災”を調査する
著者: 山﨑正晴
ページ範囲:P.1046 - P.1051
はじめに—肝臓が“火災”を起こしている!
肝臓に炎症が生じた場合,その原因を迅速に特定し,その程度を評価して,それに応じた適切な治療が求められる.炎症は読んで字のごとく“炎”の病である.
本稿では,この炎症を肝臓の火災になぞらえ,臨床において日常的に行われている肝臓の炎症をみるという行為を見直して,そこにある難しさや問題点を明らかにし,それを見誤ることを回避する方策を考える.
肝臓の線維化にかかわる検査
著者: 豊田秀徳
ページ範囲:P.1052 - P.1057
はじめに
ウイルス肝炎・脂肪性肝疾患に代表されるびまん性肝疾患において,肝線維化は肝硬変および肝細胞癌をはじめとする合併症の発生リスクと密接に関連しており,肝線維化の程度を評価することはびまん性肝疾患診療における最も重要な要素の1つである.従来,肝線維化の有無・程度の評価は肝生検で採取された肝組織の病理学的評価によりなされてきており,現在でも標準的な評価法とされている.
一方で,肝生検は侵襲的な検査であり一般的に入院が必要なこと,検査に伴う出血のリスクがあること,コストなどの問題点があり,また採取する組織は肝のごく一部であることによるサンプリングエラーの問題,病理所見の観察者間でのvariabilityの問題が以前から指摘されてきた.これらの問題点を踏まえて,昨今ではさまざまな非侵襲的な肝線維化の評価法が提唱されている.非侵襲的な肝線維化の評価は,血液検査によるものと画像検査によるものに大別される.画像検査による肝線維化評価には腹部超音波診断機器を用いた超音波(ultrasound:US)エラストグラフィや磁気共鳴画像(magnetic resonance imaging:MRI)を用いたMRエラストグラフィがあるが,いずれも診断機器を要し,ある程度術者の習熟が必要となる.
一方,血液検査による肝線維化評価は,採血のみによる評価であり簡便である.現在さまざまな肝線維化の血清マーカーが提唱されているが,最適な血清線維化マーカーや肝線維化評価のカットオフ値はびまん性肝疾患の成因や目的により異なる場合が多いため,その使い分けには注意が必要となる.
本稿では,肝臓の線維化にかかわる臨床検査について概説し,その特徴,使い分けについて論じたい.
肝癌の腫瘍マーカー
著者: 熊田卓 , 腰山裕一 , 安田諭 , 豊田秀徳
ページ範囲:P.1058 - P.1063
はじめに
肝細胞癌(hepatocellular carcinoma:HCC)の代表的腫瘍マーカーには,αフェトプロテイン(α-fetoprotein:AFP)1),AFP-L3分画(レンズマメレクチン結合性AFP)1,2)およびDCP〔des-γ-carboxy prothrombin.PIVKA-Ⅱ(protein induced by vitamin K absence or antagonist-Ⅱ)とも呼ばれるが本稿ではDCPに統一した〕3,4)の3種類がある.AFPとDCP両者の同時測定が保険制度上で認められており,HCCの補助診断として広く使用されている.AFP-L3分画の測定は現行保険上では地域によって解釈が異なるが,原則HCCの可能性が強く疑われるときにのみ算定される.「肝癌診療ガイドライン2021年版」5)においてはCQ2「肝細胞癌の診断に有用な腫瘍マーカーは何か?」において,「1.肝細胞癌の補助診断に有用な腫瘍マーカーとして,AFP,DCP(PIVKA-Ⅱ),AFP-L3分画を推奨する(強い推奨,エビデンスの強さA),2.小肝細胞癌の診断においては2種以上の腫瘍マーカーを測定することを推奨する(強い推奨,エビデンスの強さA)」と述べられている.
腫瘍マーカーに求められるのは,①存在診断〔早期診断,進展度診断(Stage分類)〕,②質的診断(鑑別診断,悪性度診断),③治療効果判定・再発診断の3点である.これらを全て満たす腫瘍マーカーは現在のところ存在しない.3種類の腫瘍マーカーを効果的に組み合わせることによりその診断率は向上すると考えられ,本稿では筆者らのデータを示しながら解説する.
肝疾患にかかわる遺伝子多型
著者: 松浦健太郎 , 田中靖人
ページ範囲:P.1064 - P.1070
はじめに
ヒト遺伝子は個人差として約300個に1個,全ゲノムで約1,000万カ所の一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)が存在し,このSNPが個々の疾患の発症,薬剤反応性や副作用に大きく関与することがさまざまな疾患において明らかとなっている.近年,網羅的なSNPタイピング技術が飛躍的に進歩し,ゲノムワイド関連解析法(genome-wide association study:GWAS)を用いることにより,肝疾患領域においても治療,病態に関連する遺伝要因が明らかにされている.
本稿では,主にGWASにより明らかとなった肝疾患に関連する遺伝子多型について解説する(表1).
2章 急性の肝疾患
急激な肝酵素の上昇がみられた際の鑑別と検査オーダーの流れ
著者: 内野康志
ページ範囲:P.1072 - P.1077
はじめに
日常臨床のさまざまな状況において,スクリーニング検査として行われる血液検査には,多くの場合,アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(aspartate aminotransferase:AST),アラニンアミノトランスフェラーゼ(alanine aminotransferase:ALT)などの肝機能検査が含まれる.そのため,消化器専門医,肝臓専門医以外の医師でも,肝機能検査値の異常に遭遇することは珍しくない.
本稿では,特に急激な肝酵素の上昇がみられた際の鑑別と検査オーダーについて概説する.なお,AST,ALTなどは本来,肝臓の“機能”を反映しているものではない.しかし,これらも含めて肝機能検査と総称するのが一般的となっており,他に該当する適切な用語もないため,本稿でも肝機能検査という用語を用いることとする.
急な肝酵素上昇がみられた際の超音波検査の役割
著者: 小川眞広
ページ範囲:P.1078 - P.1084
はじめに
患者を診察する際,採血検査の結果で急な肝酵素上昇を認めた場合には,異常の程度(現在の重症度の判定)と原因を究明し治療の内容が決定される.肝臓の働きには糖,タンパク,脂質,金属,薬剤などの代謝や胆汁の産生などがあり,まずこれらになんらかの障害が起こった場合を想定する.しかし,筋肉の挫滅によるアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(aspartate aminotransferase:AST)の上昇や,血液の溶血時のビリルビンの上昇などの例もあり,採血結果の異常が全て肝臓の機能障害ではないことも理解する必要がある.そのため,複数の検査項目により総合的に評価を行うことが日常診療では求められる.
AST,アラニンアミノトランスフェラーゼ(alanine aminotransferase:ALT)に代表される逸脱酵素は肝細胞が破壊されることにより上昇し,γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-glutamyl transpeptidase:γGTP)やアルカリフォスファターゼ(alkaline phosphatase:ALP)に代表される胆道系酵素は胆汁のうっ滞により上昇する.また,プロトロンビン時間やアルブミン値などのタンパク合成能は肝予備能を反映している.これらとほぼ同時に原因検索としてのウイルス学的な検査や免疫学的検査,さらには腫瘍マーカーなどの検査項目を追加し評価する.これらの採血結果は初診時に全て出そろうわけではなく.また,一時点での評価ではなく複数の時点の経過観察によりその重症度が把握できる症例もある.
この診療体系のなかでの画像診断の役割は原因の究明と重症度判定であるが,受診からなるべく早い時期に行うことで不必要な検査を省略し,早く正しい診断に到達することが可能となり,医療経済的にも有用であると考えられる.通常施行される画像診断として,超音波検査,CT検査,MRI検査が挙げられる.肝臓は人体最大の実質臓器であり他臓器も含めた1視野での全体像の評価などには,CT検査,MRI検査が有効であるが,外来で対象者を選別することなく触診と同様の感覚で簡便に施行できるという点が超音波検査の長所である.また,超音波検査は非侵襲的な検査法のため,経過観察や治療効果判定など複数回の検査が可能な点においても優れている.しかし,一方でCT検査,MRI検査などと比較すると客観性に乏しく,有効に使用されていないことも推測されるが,近年装置の改良により超音波検査の客観性も飛躍的に上昇している.そこで,本稿では急な肝酵素上昇がみられた際に超音波検査を活用法できるように,観察の意義と描出のポイントについて解説する.
急性B型肝炎のウイルスマーカー
著者: 四柳宏
ページ範囲:P.1086 - P.1089
はじめに
急性B型肝炎の際には(図1)に示すようなウイルスマーカーの変動がみられることが知られている.
B型肝炎ウイルスに感染すると,HBs(hepatitis B surface)抗原が持続的に産生される.HBs抗原は感度の高いウイルスマーカーとして知られている.HBV DNA量の増加は,アラニンアミノトランスフェラーゼ(alanine aminotransferase:ALT)の上昇より早くみられることが多い.HBs抗体はB型肝炎の治癒後に陽性となる.
本稿では,急性B型肝炎の経過とウイルスマーカーの変化について解説する.
B型肝炎ウイルスの再活性化とモニタリング
著者: 奥村彰規 , 伊藤清顕
ページ範囲:P.1090 - P.1093
はじめに
わが国においては,人口の約1%に当たる100万人程度がB型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)のキャリアと推定されており1),HBV既往感染者〔HBs(hepatitis B surface)抗原陰性,かつHBc(hepatitis B core)抗体またはHBs抗体陽性〕は2割(2,600万人)程度存在するとされる.HBVキャリアでは“HBV DNAが10倍以上に上昇する”または“HBe(hepatitis B e)抗原が陽転化する”場合をHBV再活性化といい,既往感染者では“HBV DNAが検出感度以下より陽性化する”または“HBs抗原が陽転化する”場合をHBV再活性化という.特に,HBV既往感染者からの再活性化による肝炎はde novo B型肝炎と呼ばれる.HBV再活性化による肝炎は,B型急性肝炎に比べて急性肝不全になりやすく,また急性肝不全による死亡率が高いことも報告されている2).近年,化学療法や免疫抑制療法の進歩に伴ってこれらの治療法が多様化し使用機会も増加しているため,化学療法や免疫抑制療法が予定されている患者に対して,しっかりとガイドラインに従って対応をする必要がある.
HBV再活性化の問題に対して,世界では米国肝臓病学会(American Association for the Study of Liver Diseases:AASLD),欧州肝臓学会(European Association for the Study of the Liver:EASL),アジア太平洋肝臓学会(Asian Pacific Association for the Study of the Liver:APASL)がガイドラインを制定している.いずれも,基本的には化学療法や免疫抑制療法を行う場合,HBVキャリアには核酸アナログ製剤の投与を,既往感染者には血中のHBV DNAをモニタリングするように推奨されている.わが国における対応は,日本肝臓学会による「B型肝炎治療ガイドライン」3)に定められており,2022年6月の第4版への改訂によりHBV再活性化についても改訂が行われた.
本稿では,まずHBV再活性化を予防・判定するための関連マーカーについて触れ,その後HBV再活性化の機序と経過,化学療法・免疫抑制療法におけるスクリーニングおよびモニタリングについて解説する.
EBウイルス感染のウイルスマーカー
著者: 乾あやの , 藤澤知雄
ページ範囲:P.1094 - P.1097
はじめに
EBウイルスは肝細胞に特異的なレセプターは有さず,肝炎ウイルスとは異なるが,さまざまな肝機能障害を引き起こす.本稿では,伝染性単核球症(IM)と血球貪食性リンパ組織球症(HLH)を中心に解説する.
スコアリングによる自己免疫性肝炎の診断
著者: 大平弘正
ページ範囲:P.1098 - P.1101
はじめに
自己免疫性肝炎(autoimmune hepatitis:AIH)は,何らかの機序によって自己の肝細胞に対する免疫学的寛容が破綻し,肝障害をきたす疾患である.通常は慢性肝炎として発見されることが多いが,急性肝炎ないしは重症肝炎,急性肝不全として発症する症例が存在する.急性肝炎として発症するAIHは,抗核抗体陽性や免疫グロブリンG(immunoglobulin G:IgG)高値といった典型的な所見を示さないこともあり,診断に苦慮することがある.
本稿では,AIHの病態やスコアリングを用いたAIHの診断について概説する.
3章 慢性の肝疾患
病理検体を用いた肝線維化評価
著者: 山内直子
ページ範囲:P.1104 - P.1110
肝臓の病理検体
病理検体として日常的に提出される肝臓の検体には,主として肝針生検検体と手術検体があり,びまん性肝疾患や肝結節性病変の病理診断が行われている.肝臓の病態の評価には肝針生検検体を用いた病理診断が非常に有用であるが,びまん性肝疾患の病変は肝内で不均一であることも多く,それに対して肝針生検で得られる組織は肝全体に比べて微小な一部分である.そのため,必ずしも全体像が反映されていない可能性,すなわちサンプリングエラー問題への考慮も必要である.小さな組織から患者にとって最大限の情報を得られるように適切な特殊染色も併用しつつ病理診断が行われている(図1).通常のヘマトキシリン-エオジン(hematoxylin-eosin:HE)染色だけでなく,鍍銀染色,EVG(Elastica van Gieson)染色,Azan-Mallory染色またはMasson trichrome染色なども施行して,肝臓の構造や線維化の評価を行っている.また,過ヨウ素酸シッフ(periodic acid Schiff:PAS)染色,ジアスターゼ処理後PAS(diastase PAS:dPAS)染色,鉄染色などの特殊染色も目的に応じて施行されている.
超音波エラストグラフィを用いた肝線維化診断
著者: 黒田英克
ページ範囲:P.1111 - P.1117
はじめに
超音波エラストグラフィは,癌や動脈硬化といった組織硬化性病変を伴う疾患の画像診断として,1990年ころから研究開発が進められた.2003年に最初の臨床用装置がわが国で開発され,乳癌診断を中心にその有用性が実証された.2017年に肝硬変症例(肝硬変が疑われる患者を含む)を対象に保険適用となり,肝線維化診断や病期判定に広く利用されるようになった.
本稿では,慢性肝疾患における超音波エラストグラフィの現況,各種超音波エラストグラフィの特徴と有用性について概説する.
臨床検査を用いた肝硬変患者における肝予備能の評価
著者: 久保貴裕 , 赤羽たけみ , 吉治仁志
ページ範囲:P.1118 - P.1121
はじめに
肝硬変は,肝臓全体に再生結節が形成され,これを線維性隔壁が取り囲む病変と定義され,肝疾患の終末像である.肝機能がよく保たれ臨床症状がほとんどない代償性肝硬変と,肝性脳症,黄疸,腹水,浮腫,出血傾向など肝不全に起因する症状が出現する非代償性肝硬変に分類される.肝臓の重要な役割に,タンパク質などの合成と体内の老廃物の解毒がある.肝硬変では,肝細胞が慢性的かつ持続的に障害されることにより,肝実質細胞が減少し肝細胞機能不全となり,タンパク・アミノ酸・アンモニア代謝や糖・脂質代謝異常,ビリルビン・胆汁酸代謝の低下が起こる.その結果,アルブミン,総コレステロール,プロトロンビン時間(prothrombin time:PT),コリンエステラーゼなどが低下し,高アンモニア血症,高ビリルビン血症を呈するようになる.
肝予備能は,これらの肝予備能を表す検査値や臨床所見を組み合わせて総合的に評価する.肝予備能の評価は,肝硬変患者の重症度の評価だけでなく予後予測にも有用である.
本稿では肝予備能の評価法について解説する.
—発癌高リスク群の設定—B型慢性肝炎
著者: 保坂哲也
ページ範囲:P.1122 - P.1127
はじめに
わが国におけるウイルス性肝癌のうち10〜15%がB型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)由来のものである.一方B型慢性肝炎に対する抗ウイルス治療はインターフェロン製剤または核酸アナログ製剤を使用した治療が標準治療となっている.核酸アナログ製剤は2000年にラミブジン(lamivudine:LAM)が認可になったが,導入当初より耐性ウイルス出現頻度が高いことが問題となっていた.そこでLAM耐性出現症例に対して2004年にアデフォビル(adefovir:ADV)が認可となった.さらに2006年にはエンテカビル(entecavir:ETV)が認可となった.ETVは薬剤耐性出現頻度が非常に低く,抗ウイルス効果も良好なため,長期間にわたり核酸アナログ製剤の標準治療薬であった.2014年にはETV同様に耐性ウイルス出現頻度が極めてまれで,抗ウイルス効果の強力なテノホビル・ジソプロキシルフマル酸塩(tenofovir disoproxil:TDF)も認可され,薬剤耐性ウイルスに苦慮する場面はほとんどなくなった.2016年末にはTDFの全身曝露量を低下させながら,薬効成分を肝細胞へ効率よく移行するように改良されたTDFのプロドラッグであるテノホビル・アラフェナミドフマル酸塩(tenofovir alafenamide:TAF)が承認され,現在の標準治療薬として広く使用されている.
これらの抗ウイルス療法によりHBV増殖が抑制され,それに伴い肝機能が改善されることは周知の事実であり,それにより肝発癌のリスクは低減されるが,必ずしもなくなるわけではない1).また肝発癌リスクの低減を達成するためには,抗ウイルス療法未治療症例の発癌リスク評価が重要である.
そこで本稿ではB型慢性肝炎抗ウイルス療法未治療例の肝癌リスク評価と抗ウイルス治療後,特に核酸アナログ製剤投与例に対する肝癌リスク評価とを分けて,自験例や文献的考察を交えながら解説する.
—発癌高リスク群の設定—脂肪肝(NASH)
著者: 中塚拓馬
ページ範囲:P.1128 - P.1134
NAFLD/NASH
肝臓は生理的に1%程度の脂質を含有するが,脂肪肝は“肝組織中の脂質(中性脂肪)が5%を超えた状態”と定義される.脂肪肝の成因はアルコール性と非アルコール性に大別され,日本肝臓学会の「NASH・NAFLDの診療ガイド2021」1)によれば,エタノール換算で60g/日以上の飲酒を伴う脂肪肝はアルコール性,ほとんど飲酒をしない場合(30g/日未満:男性,20g/日未満:女性)を非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)とされる.NAFLDはさらに,病態がすぐには進行しない非アルコール性脂肪肝(nonalcoholic fatty liver:NAFL)と,肝硬変や肝癌へと進行する可能性のある非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis:NASH)に分類される(図1).
従来,アルコール性でない脂肪肝は病態が進行しないと考えられていた.しかし1980年台にMayo Clinicの肝臓病理医であるLudwigら2)は脂肪肝炎と診断される症例のなかに非飲酒者が含まれることを指摘し,さらに1986年にSchaffnerら3)は飲酒歴がないにもかかわらずアルコール性肝障害に類似した肝組織像を示す病態としてNAFLDの概念を提唱した.その後1999年にMatteoniら4)が,過剰な飲酒歴のない脂肪肝患者を肝組織の病理学的所見に基づき以下の4つに分類した〔type 1:脂肪化のみ,type 2:脂肪化と炎症細胞浸潤,type 3:脂肪化と肝細胞風船様変性(ballooning),type 4:脂肪化と肝細胞風船様変性に加えMallory-Denk体あるいは線維化〕.ballooningは肝細胞の高度障害による形態変化で,特にNASHに特徴的な所見とされる.Matteoni分類のtype 3,4の症例,すなわちballooningや線維化を伴う脂肪肝は肝硬変や肝関連死の発生が高頻度であることが明らかとなっており,これらはNAFLDのなかでも進行性の病態のNASHと総称されるようになった.
—発癌高リスク群の設定—C型肝炎治癒(SVR)後
著者: 瀬崎ひとみ
ページ範囲:P.1136 - P.1141
はじめに
C型慢性肝疾患は,インターフェロン(interferon:IFN)をベースとした治療を行っていた時代から,C型肝炎ウイルス(hepatitis C virus:HCV)が排除されるウイルス学的著効(sustained virological response:SVR)と肝発癌が抑制されるという多くの報告があり,国家公務員共済組合連合会虎の門病院(以下,当院)でも,C型慢性肝疾患の10年累積肝発癌率は,無治療群で12.0%,IFN治療無効群で15.0%であったのに対し,SVR群は1.5%と有意に肝発癌リスクが抑制されたと報告した1).2014年にわが国で初めて直接作用型抗ウイルス薬(direct acting antivirals:DAAs)を用いたIFNフリー治療が認可されてから,それまでIFNによる治療は不耐容とされていた高齢者や肝線維化高度進行症例,さらには肝癌治療後の症例に対しても広く抗ウイルス治療が行えるようになり,100%に近い症例でSVRを得られるようになった.IFNフリーDAAs治療開始より5年以上が経過し,DAAs治療によるSVR達成も肝発癌抑制効果があるという報告も集積され,コンセンサスが得られてきている.一方で,IFN時代よりSVRが得られてからも肝癌を発症する症例は一定数みられ,SVR後5年以上の長期経過後に肝発癌を認める症例を経験する.このように,ウイルス排除後も長期にわたり肝発癌リスクは完全には消失せず,post-SVRの時代として,肝発癌リスク因子を同定し,肝発癌のサーベイランスをどのように行っていくかを検討することが重要となる.
本稿では,SVR後の肝発癌リスク因子と肝発癌リスクの層別化について,自験例や文献的考察を交えて概説する.
C型肝炎ウイルス治療法の変遷—直接作用型抗ウイルス薬が変えたC型肝炎治療
著者: 芥田憲夫
ページ範囲:P.1142 - P.1146
はじめに
C型慢性肝炎,代償性肝硬変の抗ウイルス療法は2014年11月から大きく変化した.それまでの治療は注射製剤で副作用も強いインターフェロン(interferon:IFN)を軸とした時代であったが,2014年からは内服薬で副作用の少ないIFNフリー治療の時代となった.具体的には,直接作用型抗ウイルス薬(direct acting antiviral:DAA)の組み合わせだけで副作用も軽く,95%以上のC型肝炎ウイルス(hepatitis C virus:HCV)の持続陰性化(sustained virological response:SVR)が期待できる時代となった.さらに,2019年からは非代償性肝硬変まで使用可能な薬剤が製造販売承認され,HCVを100%持続陰性化できる時代も現実味を帯びてきている.
本稿では,わが国におけるC型肝炎治療プロトコルの変遷を最新情報も交えて解説する.
肝腎症候群における臨床検査の役割
著者: 古殿孝高 , 渋谷祐子
ページ範囲:P.1147 - P.1151
肝腎症候群(HRS)
肝腎症候群(hepatorenal syndrome:HRS)は肝硬変で肝不全が不可逆的に進行した時期に発症する機能的腎不全である.肝硬変患者では腎機能が重要な予後予測因子で,HRSで急性腎障害(acute kidney injury:AKI)が出現すると肝疾患の予後が悪くなることが報告されており1),肝硬変に対する長期管理において腎機能を悪化させないようコントロールすることが重要である.
HRSの病態は腎皮質血管攣縮による腎血流障害で起こる糸球体濾過量の低下である.この発症機序を図12)に示す.肝硬変でまず門脈圧亢進が生じ,一酸化窒素やその他の血管拡張物質の産生が亢進する.これにより末梢血管抵抗減弱・有効循環血液量低下が生じ,その結果,腎血流・還流圧が低下すると,レニン-アンギオテンシン-アルドステロン(renin-angiotensin-aldosterone:RAA)系,交感神経活性の亢進,ADHの上昇による腎血管収縮が起こり,腎血流障害が生じる.さらに,低アルブミン血症による循環血液量低下,生体への細菌叢の移動で引き起こされる活性酸素種やサイトカインの増加がHRSの成因と考えられている2).肝硬変である時期までは血管収縮作用と腎血流保持のバランスがとれ,糸球体濾過が保持されるが,血管収縮の影響が現れると腎血流が著明に減少し糸球体濾過圧が低下することで腎障害が生じると考えられており,感染やエンドトキシン血症が出現するとさらに腎障害が増悪する2).
肝性脳症における血中アンモニア検査の位置付け
著者: 片山和宏
ページ範囲:P.1152 - P.1155
はじめに
肝性脳症は,急性肝不全や慢性肝疾患の終末像である肝硬変などの病態で起こりうる精神神経的な症状である.原因は,中枢神経での偽神経伝達物質作用やγ-アミノ酪酸(γ-aminobutyric acid:GABA)レセプターの活性化など多岐にわたるが,なかでも窒素代謝の過程で産生されるアンモニアの関与は大きい.
肝移植周術期に行われる臨床検査
著者: 河地茂行
ページ範囲:P.1156 - P.1161
はじめに
わが国の肝移植は,生体肝移植が年間350〜400例で,2021年8月24日に総数10,000例に到達した.脳死肝移植は年々増加傾向(2020年,2021年はコロナ禍で減少したが)にあり,2023年は年間100例を超える勢いで実施されている.
肝移植の周術期にはあらゆる臨床検査が施行されており,その全てを詳述することは誌面の都合上できないが,本稿では,肝移植周術期の臨床検査の要点について解説する.
肝硬変患者における凝固・抗凝固・線溶異常
著者: 秦浩一郎
ページ範囲:P.1162 - P.1168
はじめに—閉鎖循環系・微小循環の維持と肝機能
人体は,実に数十兆個にも及ぶ種々の細胞が組織を形成し,それらが有機的に集合して臓器として機能し,生体として統合されることで生命を維持している.これら全ての細胞・組織・臓器に酸素と栄養を運搬し,老廃物をクリアランスするために張り巡らされている血管網は,成人で約10万km,地球2周半にも達する.この膨大な血管床は“閉鎖循環系”を形成し,成人では容量にして約5Lの血液がその内腔を循環することで,各細胞の生命と機能を維持している.“出血”とは,この閉鎖循環系の一部が破綻して血管内を循環すべき血液が血管外に漏出する状態であり,直ちに局所的な血管攣縮と一次的な血小板凝集・血栓形成から凝固因子による二次止血までが速やかになされることで閉鎖循環系を維持しなければならない.一方で,よどみない微小循環の維持には,血栓の形成を予防し(抗凝固),血栓ができればこれを速やかに溶解(線溶)することで微小循環が維持されなければ,臓器機能が発揮されない.
肝臓は,血管内皮細胞などで産生/発現/分泌される一部を除いて,ほとんどの凝固・抗凝固・線溶・抗線溶因子を産生する臓器である(表1)1).血小板凝集の核となるvon Willebrand因子(von Willebrand factor:vWF)重合体の特異的切断酵素ADAMTS13(a disintegrin-like and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motifs 13)も肝臓の星細胞で合成されること2),血小板の産生・放出を促すトロンボポエチン(thrombopoietin:TPO)も肝細胞で産生されること,さらに産生のみならず,活性化した凝固・抗凝固・線溶因子の分解をも担うことを考え合わせると,肝臓はまさに全身の凝固・抗凝固・線溶系,血小板系をつかさどる中心臓器である.血液の凝固(止血)と,相反する抗凝固・線溶がともに肝臓によって制御されているため,種々の病因による肝硬変から肝不全に陥ると,必然的に止血能とともに抗血栓・血栓溶解能も破綻することになり,閉鎖循環系・微小循環の維持が困難になる.
4章 肝腫瘍
肝細胞癌原因の変遷
著者: 建石良介
ページ範囲:P.1170 - P.1173
はじめに
わが国における原発性肝癌の死亡数は,1970年代半ばに急速に増加し始め,2005年ころにピークを迎え,その後は緩やかに減少している(図1)1).罹患数についても同様であるが,そのピークは,2010年ころであり,死亡数の減少が5年ほど先行している.
本稿では,わが国の肝細胞癌の原因をB型,C型,非B非C型に大別し,おのおのの動向について解説する.
肝癌の病理診断
著者: 上野彰久 , 坂元亨宇
ページ範囲:P.1174 - P.1181
はじめに
肝臓は人体最大の臓器であり,種々の腫瘍性病変が生じることが知られている.沈黙の臓器といわれるように,症状に乏しく超音波検査などの画像検査で初めて病変がみつかることも多い.
本稿では,代表的な肝腫瘍として,肝原発悪性腫瘍の代表である肝細胞癌(hepatocellular carcinoma:HCC)と肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma:iCCA)とともに,肝悪性腫瘍で最も多い転移性肝癌,および肝細胞性の良性肝腫瘍である肝細胞腺腫(hepatocellular adenoma:HCA)について概説する.
肝腫瘍診断におけるソナゾイド®造影超音波の役割
著者: 西村貴士 , 東浦晶子 , 飯島尋子
ページ範囲:P.1182 - P.1189
はじめに
造影超音波による肝腫瘍診断は,多血性か否か,washoutを認めるか,後血管相(以下,Kupffer相)の所見などを組み合わせて診断する.Bモードと同様,各腫瘍に特徴的な所見が得られれば確定診断が可能であり,CTやMRIの造影剤と比較して超音波造影剤であるソナゾイド®は卵アレルギー以外に使用を注意しなければならない対象はなく,腎機能障害でも投与量を減量することなく使用できる.
本稿では,撮像法や個々の肝腫瘍に対する造影超音波検査の有用性について述べる.
機械学習による肝癌診断
著者: 佐藤雅哉
ページ範囲:P.1190 - P.1195
はじめに
深層学習(ディープラーニング)の登場により,近年人工知能(artificial intelligence:AI)や機械学習(machine learning:ML)といった技術が注目を集めている.本技術が可能にした人間の知的活動のコンピューター上での再現により,従来は知的活動を行う人間のみに可能であると考えられていた車の運転などの活動がコンピューター上で実現され,知的活動を必要とする職業の一部が代替され始めている.MLの応用は,部分的にではあるが実臨床における医師の思考過程の模倣をも可能とし,医療分野においても近年さまざまな試みが行われている.
本稿では,肝癌の診断に関するMLの応用について概説する.
進行肝細胞癌に対する薬物治療
著者: 上嶋一臣
ページ範囲:P.1196 - P.1201
はじめに
肝細胞癌はC型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスなどによる慢性肝炎,肝硬変などの慢性肝疾患を母地として発生する癌として知られている.このため,これらのウイルス性肝疾患を有する患者を対象にきめ細やかなスクリーニングが行われ,早期発見,早期診断が可能となった.肝癌診療ガイドラインでは,C型慢性肝疾患患者,B型慢性肝疾患患者,および非ウイルス性の肝硬変患者が肝細胞癌の定期的スクリーニング対象とされ,3〜6カ月間隔での腹部超音波検査を主体とし,腫瘍マーカー測定を用いたスクリーニングを行うよう推奨されている1).しかしながら,近年の抗ウイルス療法の発達に伴って,B型肝炎ウイルス感染については,核酸アナログ製剤によるウイルス制御が可能となり,C型肝炎ウイルス感染については直接的抗ウイルス薬(direct acting antivirals:DAA)によりほぼ100%治癒可能な疾患となった.このことにより,徐々にウイルス発癌の割合は減少傾向となっている.
一方で,非アルコール性脂肪性肝疾患(non-alcoholic fatty liver disease:NAFLD)や非アルコール性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis:NASH)などを母地とする非B非C型肝細胞癌の割合が増加している.これらの患者はほとんどの場合,医療機関で発癌サーベイランスがなされておらず,症状出現あるいは検診などで指摘されて初めて診断されることが多い.実際,このような場合は診断時にはかなり巨大な癌であったり,広範囲に進展していたりすることが多く,肝細胞癌特有の治療方法であるラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation:RFA)や肝動脈化学塞栓療法(transcatheter arterial chemoembolization:TACE)などの局所療法が適応にならないこともしばしばである.巨大な肝細胞癌では可能であれば外科的切除が選択されるが,切除不能となれば全身薬物療法が選択されることになる.このような背景から肝細胞癌においては薬物療法の重要性が高まってきている.
造影超音波を用いた肝癌の治療効果予測
著者: 杉本勝俊 , 和田卓也 , 高橋宏史 , 掛川達矢 , 阿部正和 , 吉益悠 , 竹内啓人 , 糸井隆夫
ページ範囲:P.1202 - P.1206
はじめに
わが国において,肝癌の治療効果予測に最も汎用されるモダリティはその普及率とスループットを考慮するとCTであることは論をまたない.CTは肝臓とその周囲臓器も含め広い範囲をスキャンすることができ,治療効果予測だけではなく,有害事象の有無に関しても評価することが可能であり省略することは困難と思われる.しかし,(造影)超音波でしかわからない情報も多く,CTと(造影)超音波を両方行うのが理想である.また,ラジオ波焼灼療法(radiofrequency ablation:RFA)やマイクロ波焼灼療法(microwave ablation:MWA)に代表されるアブレーション治療において,超音波ガイド下で行った症例においては治療後全ての症例でCTを撮像する必要はなく,(造影)超音波による評価で十分に代用可能と思われる.
本稿では,肝癌の治療効果判定(予測)における(造影)超音波の活用について概説する.
臨床検査を用いた肝癌の予後予測
著者: 平岡淳
ページ範囲:P.1208 - P.1211
はじめに
肝細胞癌(hepatocellular carcinoma:HCC)の予後に腫瘍進行度と肝予備能が大きく関与する.肝予備能評価法としてChild-Pugh分類(以下,CP分類)や肝障害度(liver damage:LD)が用いられてきた.近年のウイルス性肝炎治療の進歩で肝予備能良好なHCCの割合が増加してきている.より詳細な肝予備能評価法としてアルブミンと総ビリルビンのみを使用したALBI(albumin-bilirubin)スコア/グレードや4段階評価のmALBI(modified ALBI)グレードの有用性が報告されている.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1008 - P.1009
バックナンバー「今月の特集」一覧 フリーアクセス
ページ範囲:P.1212 - P.1212
基本情報
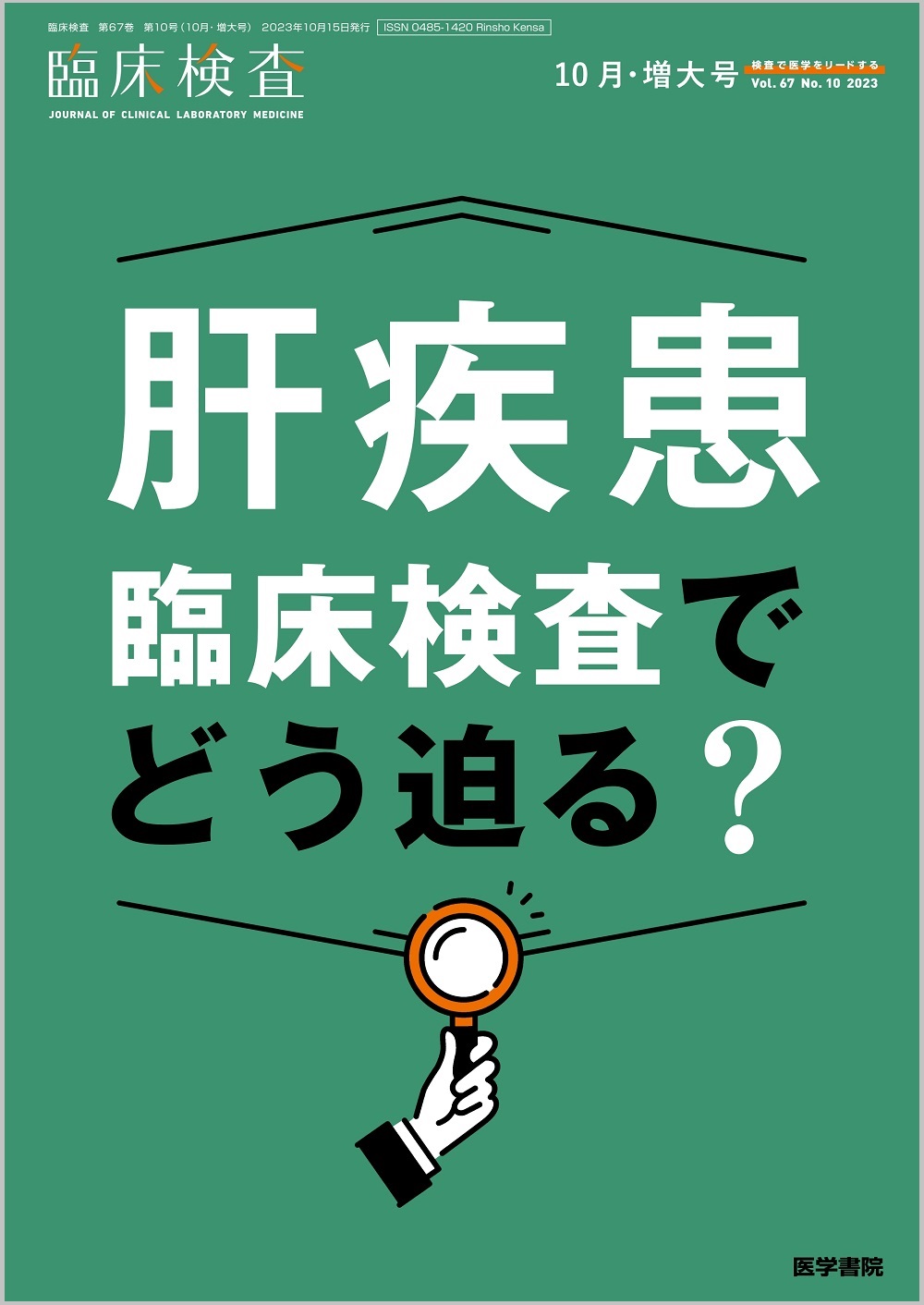
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
