心電図検査の歴史は古く,動物の心筋が心拍とともに電気を発生することを発見したのはイタリアのMatteucciです(1843年).臨床的に活用できるようになったのは1929年に市販されるようになってからで,当時は写真の現像式だったということです.心電図検査は長い歴史のなかで大きな進歩を遂げて今日に至っています.その歴史ある心電図検査は循環器学のなかで基本中の基本といわれており,その判読は医師のみならず検査技師にとっても重要となっています.本増大号は,読者の方々に心電図を基本的な判読法から学んでいただき,12誘導心電図を一定程度,判読できるようにすることを目的として企画しました.
第1章ではまず,基本的な解剖や心筋活動電位,記録方法や判読方法を解説します.続いて,第2・3章では各種波形に注目して,P波,QRS波,T波などの異常から読み解くポイントを解説します.ここでは,脈の乱れから不整脈を攻略するポイントについても,できる限り詳細に述べています.また,ペースメーカー調律についても,最新のトピックも織り交ぜながら解説しています.第4章では,患者さんの主訴をどのように心電図の判読に役立てるか,さらには,その主訴からどのようなことがわかるのかを解説します.第5章では,一般的なパニック値(クリティカルバリュー)の基準を理解し,判断ができるようにするために各施設での取り組みについて紹介します.患者さんを目に前にして行っている心電図検査では急変時の対応も求められています.その対応について救急医学の立場から解説いただきました.第6章は心電図症例を示し,今までの章で培った判読能力を試すことで,さらにステップアップを目指しています.第7章は「教えて先生!」と題して,読者からの疑問に答えるかたちで,基礎レベルではないステップアップした心電図の判読や抗不整脈薬,ペースメーカーの最新デバイス,さらには心電図検査の未来まで解説をいただきました.第8章で指導・育成と精度管理を解説することによって,日々の業務を行ううえで大切な実運用を習得していただけると考えています.
雑誌目次
臨床検査68巻10号
2024年10月発行
雑誌目次
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
はじめに フリーアクセス
著者: 河合昭人
ページ範囲:P.1123 - P.1123
1章 心電図がみるみる読めるようになる基礎知識
心臓の解剖と心筋活動電位
著者: 河合利子
ページ範囲:P.1128 - P.1135
はじめに
心臓は規則正しく拡張と収縮を繰り返し,私たちの身体のすみずみまで血液を循環させてくれる.そのことから心臓は時計内蔵の精密なポンプともいわれる.そこには規則正しい電気的興奮の発生と,心房から心室への連続的な興奮伝導が存在する.目的達成のため100〜200億ともいわれる細胞群を総合統御する機構細胞群を刺激伝導系という.命の原点ともいうべきその仕組みをマクロとミクロの視点から考えてみよう.
心電図の記録の方法
著者: 河合昭人
ページ範囲:P.1136 - P.1143
心電図の成り立ち
心電図とは,心臓から得られた電気的活動を体表面から電極を通して記録された波形である.始めに区別しておきたいのは,心電図モニターと標準12誘導心電図の違いである.心電図モニターとは体表面に3個の電極を貼り付け得られた1つの心電図波形のことであり,入院中の患者の心電図のモニタリングなどに用いられる.標準12誘導心電図とは体表面に10個の電極を装着し得られた12個の心電図波形のことであり,12個の波形より不整脈や心筋梗塞などの評価に用いられる.本稿でいう心電図とは,注意書きがなければ標準12誘導心電図のことである.
心電図の波形には双極誘導と単極誘導がある.双極誘導は関電極間の電位差を記録し,単極誘導は関電極と起電力の影響を受けない不関電極との電位差を記録する.装着部位と誘導方法を表1に示す.
基本的な判読方法
著者: 中川幹子 , 三角里美
ページ範囲:P.1144 - P.1149
心電図波形の名称と意義
心電図はP,QRS,J,TおよびU波の5種類の波形からなる.P波とQRS波との間の平たんな部分をPR部分,QRS波とT波との間の分部をST部分と呼ぶ(図1).J波とU波はない場合もある.
2章 波形に注目—読み解くポイント
P波の異常
著者: 上山剛
ページ範囲:P.1150 - P.1154
正常P波の成り立ち
心電図波形におけるP波は,心房の興奮過程を示す波形である.正常P波は,洞結節細胞の自発興奮が移行組織領域(perinodal area)を経て伝わる右房の興奮とBachmann束を介して伝わる左房の興奮によって形成される.心房の興奮は洞結節の存在する高位右房から波紋状に下方へと向かう.右房内には伝導に適した結節間伝導路と呼ばれる経路(preferential pathway)を介して房室結節へと至る.左房の興奮は,洞結節細胞によって生じた右房の興奮が,右房前方から右上肺静脈付近に伸びるBachmann束を介して左房の左房前上方向へと伝導し,分界稜を経て到達した下方からの興奮と衝突する.したがって,P波の始まりは右房の興奮を表し,前半2/3の成分は右房の興奮,後半2/3の成分は左房の興奮を反映し,両者の融合によってP波は形成される.
洞結節は上大静脈と右心房の接合部にあるため,心房興奮のベクトルは四肢誘導を反映する前額面においては左上から右下に向かう.前額面P波の電気軸は0°〜+70°にあり,多くは+45°〜60°であるためⅠ,Ⅱ誘導で陽性を示し,aVRで陰性となる.Ⅲ誘導は陽性,二相性,陰性のいずれの極性にもなりうる.二相性は7%程度にみられ,その初期成分は陽性である.aVL誘導の極性もさまざまであるが,通常陰性となることが多く,二相性となる場合の初期成分は陰性を示す.aVF誘導も通常陽性であるが,しばしば二相性あるいは平定な極性を示す.正面からみると右房は前胸部に位置しており,左房は右房の左後方に位置するため,最初に前方に向かう右房の興奮に続いて後方の左房に興奮は向かう.そのため,V1およびV2誘導では,しばしば陽性-陰性の二相性を示し,それぞれ右心房,左心房の興奮を反映する.V3〜V6誘導では,心房興奮は右から左へと向かうため,陽性となる.通常第Ⅱ誘導のP波の幅は3mm(0.12秒)未満で,P波高は2.5mm(0.25mV)未満である.またV1誘導においては,P波高は2mm(0.2mV)未満であり,陰性成分の幅と深さの積(Morris indexまたはP terminal force)は0.04未満である1).
PR時間の異常
著者: 神田茂孝
ページ範囲:P.1155 - P.1160
はじめに
PQあるいはPR時間は,洞房結節から出た電気的興奮が心房内を経て房室結節およびHis束内を通過し,心室中隔上部の脚に相当する心室筋へ至るまでの時間である.そのため房室伝導時間とも呼ばれ,そのほとんどが房室結節内通過時間で占められている.その正常範囲は120〜200msec(心電図の3〜5コマ)までであり(図1),その短縮でも延長でも異常とされる.PQあるいはPR時間の測定については,心電図上P波からQRS群がQ波で始まっていればQ波までのPQ時間であり,またQ波を認めずR波で始まっていればR波までのPR時間である.特に下壁誘導(Ⅱ・Ⅲ・aVF誘導)ではQRS群の波形にバリエーションが多く(図2),PQ時間とPR時間は双方同義であるため本稿ではPR時間と表記することとする.
—QRSの異常—R波の増高減高
著者: 髙安幸太郎 , 井上耕一
ページ範囲:P.1166 - P.1170
はじめに
QRS波形は心室の心筋の脱分極の総和によって形成される.QRS波形の始まりが下向きの振れである場合はそれをQ波,最初の上向きの振れをR波,R波に続く下向きの振れをS波と呼ぶ.これらQRS complexの異常は心筋の異常や基礎心疾患の存在を示唆しており,心電図スクリーニングにおいて特に重要である.
本稿では,そのなかでもQRS波の振幅(波高)に注目して,振幅に影響を及ぼす要素や増高と減高の機序,代表的な疾患について紹介する.
—QRSの異常—J波,ε波
著者: 篠原徹二 , 髙橋尚彦
ページ範囲:P.1171 - P.1176
J波とは
12誘導心電図において,QRS波とST部分の境界点をJ点と呼ぶ(図1a).QRS波は角度が急で,ST部分は緩やかなので,角度が急なところから緩やかなところに変わる部分がJ点となる.そして,下壁誘導(Ⅱ,Ⅲ,aVF)および側壁誘導(Ⅰ,aVL,V4〜V6)で0.1mV以上のJ点上昇した波をJ波と呼ぶ.J波はその波形からノッチ型とスラー型に分類される(図1b,c).
従来,このようなQRS-ST接合部(J点)の上昇は早期再分極として認識され,若年男性に多くみられる正常亜型として扱われてきた.しかし,近年J波が心室細動(ventricular fibrillation:VF)発症と関連することが判明し,早期再分極症候群として注目を集めている1).
異常Q波とST上昇,T波増高
著者: 齋藤佑一
ページ範囲:P.1177 - P.1183
はじめに
ST部分はQRS波の終了点からT波の開始点までの部分と定義されるもので,通常の場合,ST部分は基線に一致する.しかし,電気的興奮が心臓の各部位(心内膜側および心外膜側)でばらつく場合や,伝導遅延を伴う場合などは,ST上昇もしくは低下がみられる.ST上昇は急性心筋梗塞を代表とする,一般に緊急の対応を要する疾患を示唆する場合があり,その判読は重要である.T波は心筋が興奮から回復する時相を表すもので,通常はQRS波と同じ極性を示す.つまりT波は,aVR誘導以外では陽性(上向き)であることが一般的である(V1〜V2誘導などにおいても,病的意義なく陰性T波がみられる場合がある).T波が増高している場合にも,適切に心電図を評価できることは重要である.
本稿では,これらの心電図所見を伴う症例を提示しながら,特徴的な心電図所見について解説する.
ST低下と陰性T波
著者: 河合昭人
ページ範囲:P.1185 - P.1189
はじめに
ST-T変化におけるST低下や陰性T波は,虚血性心疾患を思い浮かべることが多いと思われるが,もちろん,それ以外のことも多い.虚血性心疾患において,ST低下の所見だけで冠動脈病変を捉えるのは困難であるので,心電図がオーダーされた背景や臨床症状なども加味しながら判断をしていくことが重要である.
T波,U波
著者: 有田卓人
ページ範囲:P.1195 - P.1199
はじめに
T波は心室の再分極を表す波であり,QRS波の幅が正常で狭い場合,T波はQRS波と同じ向きである.そのため,T波は一般的にQRSの主軸と同方向を向く場合を正常と考え,正常心電図にも陰性T波が存在し,成人では肢誘導のうちaVR誘導で陰性,胸部誘導ではV1およびV2誘導で陰性T波を認めることがある.心筋虚血による心内膜側の活動電位の持続時間が短縮する場合や心肥大(酸素消費が大きくなるため相対的酸素不足となる)の場合に陰性T波が観察される.T波の高さに関しては,正常ではQRSの1/10(あるいは1/5とする説もある)以上と考えられている.
U波はT波の後に続く小さな振れであり,その成因はいまだに不明とされるが,Purkinje細胞の再分極を表す可能性や,心室壁にあるM細胞の活動電位持続時間を表す可能性などが示唆されている.通常はV2〜V5誘導で認めることが多く,正常のU波はT波と同じ極性を示し,その高さはT波の高さの10%程度とされている(図1).臨床的にはV4〜V6で観察される陰性U波は,冠動脈左前下行枝の重症虚血を反映することが有名である.
3章 脈の乱れに注目!不整脈を攻略する
P波の脱落や消失
著者: 三輪陽介
ページ範囲:P.1200 - P.1205
P波異常
洞房結節に始まる刺激伝導系は,途中に固有心筋の興奮を伴いながら,心房,房室結節,His束,右脚・左脚,Purkinje系,心室と伝播していく.
P波は心房固有心筋の興奮を表す波形で,高位右房に存在する洞結節から始まる興奮により,まず右房が興奮し,遅れて左房の興奮が開始される.心房に障害がなければ同時に機械的な興奮を表現することになる.P波を詳細に観察すると,心房の形態的な変化を予想することができる.例えば,P波の幅が正常より広い場合には,心房の興奮伝導時間が長いということが示唆され,心房の拡大や負荷が予想されるし,P波高が正常より低い場合には,心房電位の低下が示唆され,心房収縮が弱いことが予想される.
QRSの脱落
著者: 西山信大
ページ範囲:P.1206 - P.1213
はじめに
QRSの脱落は,心電図上QRSの脱落の前にP波を認めるものと,認めないものがある.P波を認めないものについては,第3章「P波の脱落や消失」の項を参照いただきたい.本稿では,P波を認めるもの,いわゆる房室ブロックについて主に概説する.
早期に出現するP波・QRS
著者: 湯澤ひとみ
ページ範囲:P.1214 - P.1218
上室期外収縮(SVPC)
SVPCとは
まず,期外収縮とは,徐拍時の補充調律時を除き,洞結節以外からの興奮でかつ,予想されたタイミングより早くに起こるものの総称である.上室期外収縮(supraventricular premature contraction:SVPC)とは,心房期外収縮(premature atrial contraction:PAC)と房室結節期外収縮の総称で,厳密な区別は難しいことも多いが,臨床的にこの両者を鑑別する意義は乏しい.
心房期外収縮は洞調律(sinus rhythm:SR)のP波より早いタイミングで出現し,SRと同じ形状のnarrow QRS(wide QRSの場合は,第2章「QRSの異常 QRS幅の延長」を参照)が続く.房室接合部期外収縮のQRSは同様にnarrowであるが,SR時のQRSと比較してやや変形していることが多く,逆行性P波はQRS内に埋没し視認できないこともある.
—頻脈性不整脈—QRS幅が狭い
著者: 山下省吾
ページ範囲:P.1220 - P.1227
はじめに
心電図においてQRS幅の狭い頻脈(QRS幅<,100msかつ脈拍数>100回/分)に遭遇したときに考えるべき不整脈は何か.
本稿では,考えうる疾患とその特徴,そして心電図アプローチについて述べる.
—頻脈性不整脈—QRS幅が広い
著者: 徳田道史
ページ範囲:P.1228 - P.1231
wide QRS頻拍の鑑別
RR間隔が整のwide QRS頻拍(心拍数が100/分以上,QRS幅が120ms以上)が観察された場合は,第一に心室頻拍(ventricular tachycardia:VT)を疑う.臨床でみた場合は血行動態が保たれているかを確認し,電気的除細動を考慮しつつ,慎重かつ迅速に心電図の解析を行うべきである.しかし,VTと断定する前には冷静な判断が求められる.VTは確かにwide QRS頻拍の一形態であるが,wide QRS頻拍が必ずしもVTであるわけではない.変行伝導を伴う上室性頻拍(supraventricular tachycardia:SVT)でもwide QRS頻拍となるためである.
本稿ではwide QRS頻拍をみた場合,それが心室性であるのか,心房性であるのかを鑑別する方法を詳述する.
—頻脈性不整脈—QRS幅が広くRR不整
著者: 宮永哲
ページ範囲:P.1232 - P.1237
はじめに
本稿では,QRS幅が広くRR間隔が不整となる,心室細動(ventricular fibrillation:VF),torsade de pointes(TdP,トルサード・ド・ポアント),偽性心室頻拍(pseudo ventricular tachycardia)を取り上げる.いずれも,心臓から血液が十分に送り出せず,血圧が低下して,めまいや失神,突然死を起こしうる重症な不整脈である.すぐに救命処置が必要となることが多く,救急室や病棟での急変時に遭遇するような不整脈で,生理検査室ではまず目にすることはないが,Holter心電図記録や運動負荷心電図中には遭遇するかもしれない.もし,これらの不整脈を発見したときには,迷わず緊急で医師への連絡が必要である.
徐脈性不整脈
著者: 矢野健介
ページ範囲:P.1238 - P.1243
はじめに
不整脈は正常洞調律以外の調律と定義される.正常洞調律は高位右心房に存在する洞結節で起きた電気的興奮(刺激)が,心房内を伝播して房室結節へ入り,His束から右脚と左脚へと伝導し,Purkinje線維を介して左右の心室に規則正しく伝えられる.不整脈はこの一連の電気的流れ(刺激伝導システム)になんらかの異常が生じていることを意味する.不整脈は徐脈性不整脈と頻脈性不整脈に大別される1).ここで扱う徐脈性不整脈は,定義として50/分以下とすることが多いが,臨床的に問題となるのは40/分以下の場合である.徐脈性不整脈の重症度は補充収縮が出現するかどうかにかかっており,最も重篤な場合は心静止に至る.
本稿では,徐脈性不整脈の分類,メカニズム,症状,原因,診断について概説し,心電図診断のポイントについて実際の心電図を呈示しながら解説する.最後に,徐脈性不整脈の治療についても簡単に触れる.
ペースメーカの種類と機能—ICDとCRTを含むペースメーカ心電図
著者: 境田知子
ページ範囲:P.1244 - P.1249
デバイスの種類と役割
“ペースメーカ”とひとくくりにされがちであるが,植込み型心臓不整脈デバイスは下記に示すように,大きく4つに分けられる.
①植込み型心電計(insertable cardiac monitor:ICM)
②ペースメーカ(pacemaker)
③植込み型除細動器(implantable cardioverter defibrillator:ICD)
④心臓再同期療法(cardiac resynchronization therapy:CRT)
4章 主訴からみた心電図
胸痛
著者: 林秀樹
ページ範囲:P.1250 - P.1253
症例1:50歳代,男性
胸痛を主訴に緊急受診した.12誘導心電図(図1)では完全左脚ブロックを認め,Ⅰ,aVR,V1〜V4誘導でST上昇を,Ⅱ,Ⅲ,aVF,V5〜V6誘導でST低下を認めた.
動悸,息切れ
著者: 森田宏
ページ範囲:P.1254 - P.1257
症例
患者は75歳,女性.高血圧の加療中で,降圧薬内服で血圧は安定していた.半年前から労作時の息切れを自覚し,次第に短い歩行距離でも息切れを感じるようになった.昨日の朝から動悸,頻脈を自覚し,1日おいても改善せず,また息切れも増悪したため岡山大学病院を受診した.
5章 パニック値と急変時対応
東京科学大学病院(旧 東京医科歯科大学病院)におけるパニック値への対応
著者: 濱田里美
ページ範囲:P.1266 - P.1269
はじめに
東京科学大学病院(旧 東京医科歯科大学病院.以下,当院)は813床の大学病院である.特定機能病院であり,検査室はISO 15189の認定を取得している.検査部には4台の心電計があり,平日8:30〜17:15に標準12誘導心電図検査を行っている.実施するのは検査部職員の臨床検査技師とヘルスケアアシスタント(health care assistant:HCA,主に臨床検査技師免許取得後すぐに進学した修士課程の学生で週2時間程度従事する)である.2024年1月現在,検査部職員23名,HCA20名に実施権限があり,時間帯により変動するが2〜5名(検査部職員1〜4名,HCA0〜2名)で検査を行っている.検査部で心電図検査を受ける患者は平均130人/日である.
本稿では,当院検査部での標準12誘導心電図検査のパニック値と運用について述べる.なお,病院内では救急外来や病棟にも心電計があり,看護師などが心電図検査を行うため,検査部にこられない状態の患者は対象外である.
三井記念病院臨床検査部におけるパニック所見への対応
著者: 石崎一穂
ページ範囲:P.1270 - P.1272
はじめに
最初に検査結果を知る検査技師は,正しい判断と的確な対応が求められる.そして,それが的確な診療につながる必要がある.パニック所見は緊急性が高い結果であるため,直ちに医師へ報告し指示を仰がなければならない.パニック所見の存在は,国内全ての施設で同じ判断,対応,診療を行うための道しるべとなりうると考えている.
河北総合病院におけるパニック値への対応
著者: 髙野小百合
ページ範囲:P.1273 - P.1276
はじめに
当院は東京都杉並区にあり,河北総合病院(以下,本院)と隣接する河北総合病院分院(以下,分院)で合わせて369床の許可病床をもつ急性期病院である.生理機能室の心電図室は本院に2室,分院に3室あり,両検査室で2023年には年間約17,442件の心電図関連検査を実施し,それ以外の生理機能検査(超音波検査を除く)を含め,1日当たり6〜7名体制で運営している.
成功事例から学ぶ,知っておきたい急変時対応
著者: 万代康弘
ページ範囲:P.1277 - P.1280
はじめに
検査の途中などで患者とかかわっているときに,患者の状態が急変することは起きてほしくはないが,可能性はあり得る.多くの方々は「そのような場面に出くわしたらいやだな」と思われているであろう.しかし,患者と家族からみると皆さんも病院の職員であり,「何か対応をしてくれるだろう」と期待されている.そのようなときに何をすればよいのか,どのように行動すればよいか,その場に居合わせた“あなた”と仮定して行動や思考を説明していく.“あなた”がその場に居合わせたとして読んでみていただきたい.
本稿では,場面1と場面2として2パターンの流れを紹介する.
6章 難しいところに手が届く!心電図Q—ここまでの努力を試そう!
Case 2
著者: 山根禎一
ページ範囲:P.1286 - P.1289
心電図(図1)
既往歴
患者は65歳,男性.10年前に下壁心筋梗塞の既往があった.半日以上,持続する動機症状を主訴に救急外来を受診した.
Case 4
著者: 寺澤無量
ページ範囲:P.1296 - P.1300
心電図1)
患者は40歳代,男性.特記既往や家族歴はなかった.農場で働いている際に倦怠感を自覚して救急要請した.病着後に記録した心電図では心拍数(heart rate:HR)200bpmで上方軸,右脚ブロックの心室頻拍(ventricular tachycardia:VT)であった.精査の結果,冠攣縮性狭心症による心筋梗塞巣からのVTと診断に至り,植込み型除細動器(implantable cardioverter defibrillator:ICD)植込み後に退院となった.退院の9カ月後に遠隔システムでVTアラートがあり,図11)の心内電図であった.
7章 教えて先生!
ベラパミル感受性心室頻拍ってどんな頻拍ですか?
著者: 北條林太郎
ページ範囲:P.1301 - P.1304
ベラパミル感受性心室頻拍とは
ベラパミル感受性心室頻拍については1979年にZipesら1)によって,①心房ペーシングで誘発される,②右脚ブロック左軸偏位,③器質的心疾患がない,の3徴が報告され,また,1981年にBelhassenら2)によって④ベラパミルへの感受性が報告された.最も多くみられるものが左脚後枝領域に回路の出口を有するもので,右脚ブロック左軸偏位を呈する(図1a).この心電図では,心室波のなかに一定の周期でP波が記録され,房室解離を呈していることから心室頻拍と診断される.
ベラパミル感受性心室頻拍はかつて左脚後枝型(右脚ブロック,左軸偏位,頻度70〜80%)と左脚前枝型(右脚ブロック,右軸偏位,頻度10〜15%.図1b),上中隔型(頻度5%)に分類されていた.近年,左脚後枝および前枝型はそれぞれ中隔型と乳頭筋型に分類されている.さらに,左脚後枝型を逆に旋回するreverse型も報告されており,6型に分類されている3).上中隔型やreverse typeは頻度が低く,後枝型へのアブレーション後に誘発される.
R on Tはなぜ危険なのですか?
著者: 草山隆志
ページ範囲:P.1305 - P.1307
はじめに
RonTは,心電図上でT波に心室期外収縮(premature ventricular contraction:PVC)が発生する現象である.一見すると単なる期外収縮のようにもみえるが,多形心室頻拍(torsade de pointes:TdP)や心室細動(ventricular fibrillation:VF)などの致命的な不整脈を引き起こすリスクを高める危険なサインであるため,早期発見と適切な治療が重要である.
本稿では,実際の症例を通じて,RonTとTdPの発生メカニズム,危険因子,治療法について解説する.
3枝ブロックってなんですか?
著者: 白山武司
ページ範囲:P.1308 - P.1310
はじめに—3枝ブロックの概念
心室内刺激伝導系には,右脚,左脚前枝,左脚後枝の3本があると考えられており,3枝ブロックは,このいずれもが伝導障害をきたした状態である.基本概念としては,それぞれ完全ブロックでも不完全ブロックでもよい.それぞれの伝導障害が時間とともに悪化すると完全(3度)房室ブロックになる,または運動などで心拍数が上昇した際に安静時より高度な房室ブロックが顕在化する,という点で,一種の危険なサインとして認識されている.
抗不整脈薬をもっと知りたい!
著者: 志賀剛
ページ範囲:P.1311 - P.1315
はじめに
抗不整脈薬は主に頻脈性不整脈の停止,徐拍化,予防に使用される.抗不整脈薬の特徴は,不整脈を抑えるために使用しながら不整脈を発現あるいは悪化させる作用(催不整脈)をもち合わせていることである.このような“もろ刃の剣”的な薬は抗不整脈薬以外にあまりない.心電図は有効性の評価はもちろんのこと,また安全性の評価にも大きな役割を果たす.
本稿では,抗不整脈薬の特徴的な心電図変化について概説する.
ヒス束ペーシング・左脚領域ペーシングを知りたい!
著者: 藤生克仁
ページ範囲:P.1316 - P.1319
はじめに
心臓生理的ペーシング(cardiac physiologic pacing:CPP)は,心臓の自然な電気的活動を模倣することにより,特に心室の同期を改善して心不全のリスクを減少させる治療戦略である1).このCPPには,右心室リードと冠静脈内に左心室リードを挿入して,左心室を複数個所からペーシングする心臓再同期療法(cardiac resynchronization therapy:CRT)が含まれ,さらに近年広く行われるようになってきているヒス束や左脚などの刺激伝導系をペーシングする刺激伝導系ペーシング(conduction system pacing:CSP)を含む広範な概念である.
本稿で取り上げるのは,CSPのなかの2つの主要な方法である,ヒス束ペーシング(His bundle pacing:HBP)と左脚領域ペーシング(left bundle branch area pacing:LBBAP)である.近年ではその簡便さからLBBAPがより一般的に行われている.
AIと心電図の未来図を教えてください
著者: 荷見映理子
ページ範囲:P.1321 - P.1323
はじめに
人工知能(artificial intelligence:AI)による自動解析・診断技術は目覚ましい発展を遂げており,もはやAIは新たな医療機器の開発や医学研究において不可欠なテクノロジーになりつつある.特にこの数年間において,AIによる技術革新は心電図(electrocardiogram:ECG)診断の分野にまで押し寄せており,従来のヒトの目では識別できない情報をAIの認識性能を用いて判別することができるようになっている.近年では,センシング技術,高速無線通信などのテクノロジーをAI技術と組み合わせて,不整脈・心疾患の早期診断を行う研究開発が世界的に行われている.
Apple Watchの心電図って役立ちますか?
著者: 木村雄弘
ページ範囲:P.1324 - P.1326
Apple Watchの心電図って何?
スマートウォッチの1つであるApple Watchに搭載された心電図アプリケーションは心電図を記録することができる.スマートウォッチは,腕時計タイプのウェアラブル端末で,電話やSNSなどの通知,電子決済など時計以外のさまざまな用途のためにいつも身に着けている.これまでは症状のあるときに,病院を受診しなくてはならなかったが,このアプリケーションの登場により,いつでもどこでも誰でも自分の腕で心電図を記録することができるようになった.
使用方法は,Apple Watchを腕に装着した状態で,心電図アプリケーションを起動し,Digital Crown(竜頭)を反対の腕の人さし指で触ることで,心電図検査の第Ⅰ誘導に類似した波形を記録できる.アプリケーションの機能は,記録された心電図を①洞調律,②心房細動,③高い心拍数,④低い心拍数,⑤判定不能の5つに分類する1).初めてアプリケーションを起動した際には,年齢と不整脈と診断されたことがないことの確認と,心電図や結果に関する教育的コンテンツが表示される(図1).Apple WatchはiPhoneと連携して動作するため,ペアリングされたiPhoneをもっている必要がある.記録したデータは自動的にヘルスケアアプリケーションに保存される.
8章 心電図検査担当者の育成方法と精度管理
心電図検査担当者の育成方法
著者: 市川篤
ページ範囲:P.1327 - P.1330
はじめに
心電図検査は多くの臨床検査技師が携わる機会がある生理機能検査である.手技が簡便なため,超音波検査のような長期のトレーニング期間を要することなく検査が可能である.しかし,検査精度や患者安全のためには,検者の正確な手技と心電図判読力が必須となるため,その教育・訓練は重要である.また,近年,話題となっているISO 15189においても,臨床検査室における教育に関するさまざまな事項が要求されている.これらを踏まえて,本稿では東京女子医科大学病院(以下,当院)における心電図検査担当技師育成の取り組みについて紹介する.
ISO 15189における心電図検査の精度管理
著者: 小笠原直子
ページ範囲:P.1331 - P.1334
はじめに
標準12誘導心電図検査は最も汎用されている生理機能検査の1つである.反復して行われる検査の過去記録との比較が診療方針の決定のためには必須であり,検査にかかわる技師全員が正確な検査結果を提供する必要がある.そのためには各計測値の精度が担保されているという前提があり,機器精度・手技精度の管理が重要である.
心電計の精度管理については,心電計のデジタル化が進むとともに,機器精度管理はベンダーに一任することが一般的となり,外部精度管理としてのフォトサーベイが行われるのみで,実働機器の精度管理が行われていないのが現状であった.筆者が所属する帝京大学医学部附属病院中央検査部(以下,当検査部)が精度管理の試みを始めたのは2010年であったが,精度管理業務は検体検査でのみ必須で,生理検査で機器精度・手技精度とも公開情報が非常に少ない状況であった.
近年,ISO 15189が普及し,同規格の2012年版では生理検査が認定項目となったことで,検体検査に限らず生理機能検査でも精度管理の重要性が増し各施設で取り組まれるようになった.しかし,生理機能検査の精度管理については,検体検査のように確立した方法が存在せず,要求事項に従い各施設で運用を決定しているのが現状である.このような状況を踏まえ,本稿では当検査部で行っている精度管理の取り組みを紹介する.
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1124 - P.1126
バックナンバー「今月の特集」一覧 フリーアクセス
ページ範囲:P.1336 - P.1336
基本情報
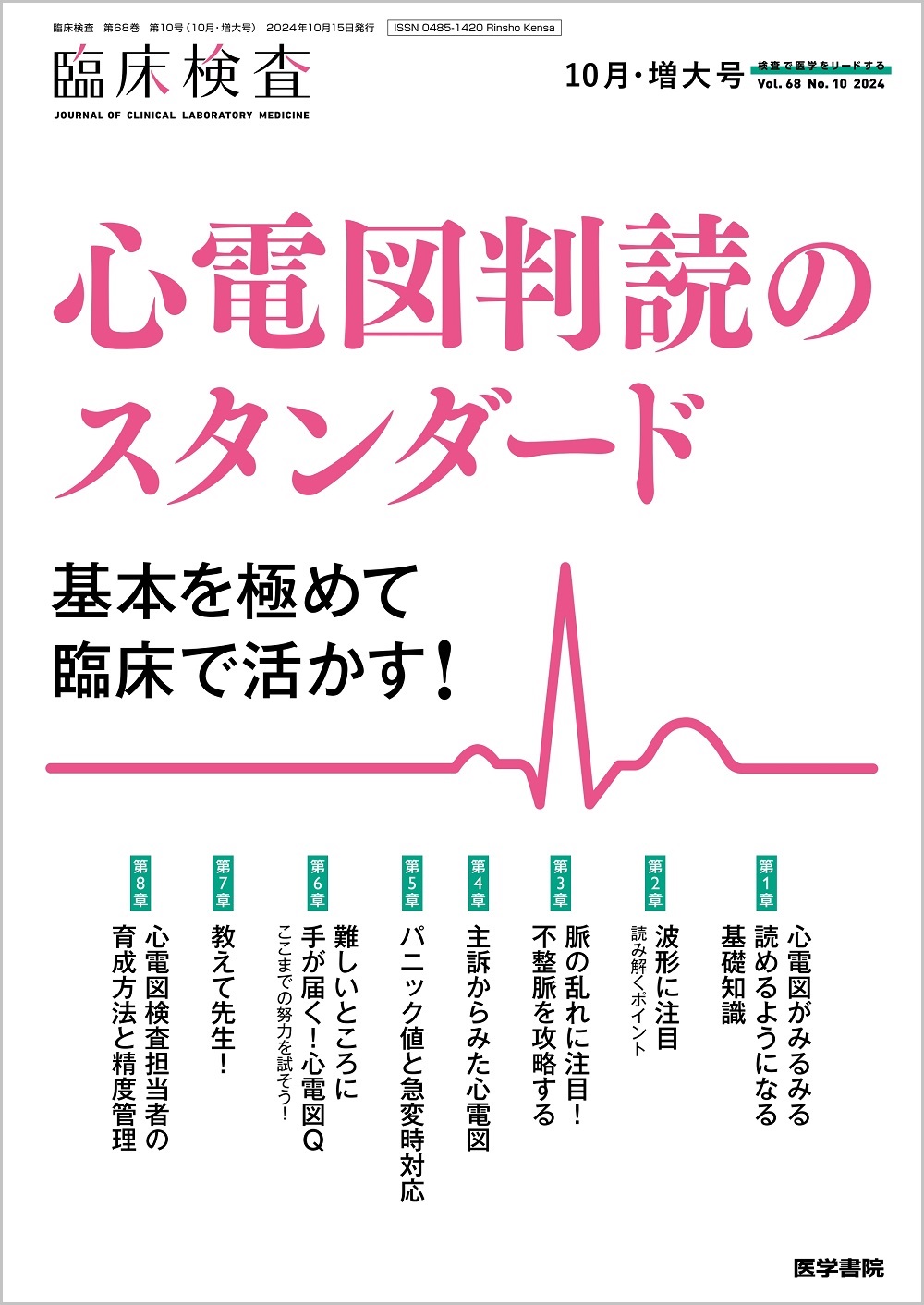
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
