腎疾患は高血圧などを介し心血管系疾患と密接な関係にあり健康寿命に大きく影響します.また,腎不全から透析に至る際の医療コストという社会的な問題もあります.しかしながら,初期のうちは症状として表れにくく,健康診断でクレアチニンを調べることがなかったり,調べたとしても1.0mg/dLだったら大丈夫などとラフに評価されたり,やや軽視されてきました.そこで,腎機能低下予防の重要性がキャンペーンされ,CKD(慢性腎臓病)という用語が医療界にも一般にもかなり浸透してきました.例えば,クレアチニンにしても,今は年齢や性別を考慮したきめ細かい評価(つまりはeGFRとしての評価)が求められています.このような背景から,CKDで特集を組み,腎疾患と関連する臨床検査を一度整理して学習したいと考えておりました.一方,予防医療,生活習慣病などの視点ではCKDとなりますが,病院の外来または入院患者には急性の腎不全も少なくなく,パニック値の概念も入ってきますし,AKI(急性腎障害)での臨床検査の活用も学びたいところです.そこで,「AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ」というタイトルにして腎臓にかかわることはこの1冊で大丈夫,を目指した特集を組みました.
第1章「腎の病態生理」では,血圧や酸塩基平衡,電解質などの体液調節に機能する腎の生理的役割について取り上げました.一見難解なところですがわかりやすく解説いただきました.第2章「腎疾患診療の進め方」では,腎疾患の医療面接,診察,検査をどのように進めていくかについて解説いただきました.臨床医の視点を理解していただけたらと思います.第3章「腎疾患と臨床検査」では,臨床検査からのベクトルで,腎疾患におけるその使い方,評価の仕方について学んでいただきます.第4章「腎疾患を知る—臨床検査ができること」では,まずAKIを取り上げ,次にCKDを社会的な視点,他職種からの視点で臨床検査とともに取り上げました.そして代表的な腎疾患群ごとに臨床検査を中心とした臨床的な解説をいただきました.最後にこの分野におけるトピックスを取り上げました.
雑誌目次
臨床検査68巻4号
2024年04月発行
雑誌目次
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
はじめに フリーアクセス
著者: 山田俊幸
ページ範囲:P.327 - P.327
1章 腎の病態生理
腎と体液量調節・血圧
著者: 久保英祐 , 春原浩太郎 , 田村功一
ページ範囲:P.332 - P.337
はじめに
血圧は,心拍出量と末梢血管抵抗によって規定され,心拍出量は体液量と心収縮力によって決定する.これらの因子は食塩摂取量や交感神経系,レニン-アンジオテンシン-アルドステロン(renin-angiotensin-aldosterone:RAA)系などにより,さまざまな修飾を受ける.腎臓は血圧異常により障害を受ける一方で,血圧の規定因子の1つでもある.このように腎臓と血圧は密接な関係をもっている.
本稿では,血圧の評価やその測定意義について,特に腎疾患との関連を中心に記載する.さらに血圧を規定する因子として重要な体液量についても概説する.
腎とカリウム代謝
著者: 武藤重明
ページ範囲:P.338 - P.343
カリウムイオン(K)の体内分布(図11))
体液は,水とそれに溶解している電解質やタンパク質などで構成され,細胞内液(intracellular fluid:ICF)として細胞内に,細胞外液(extracellular fluid:ECF)として細胞を取り囲んでいる.ECFはさらに,細胞と直接接している間質液(組織間液)と血管内を循環している血漿に細分される.ECFの血漿と間質液のイオン組成は極めて類似しているのに対し,ICFのイオン組成は全く異なっており,この違いが細胞の機能を維持するのに重要である.特記すべきは,ICFにカリウムイオン(potassium ion:K)が非常に多くナトリウムイオン(sodium ion:Na)が非常に少ないのに対し,ECFではその割合が全く逆になっていることである.これは,細胞膜に存在するNa-Kポンプ〔Na/K-ATPase(adenosine triphosphatase)〕が,アデノシン5′-三リン酸(adenosine 5′-triphosphate:ATP)の加水分解によって作られたエネルギーを利用して,細胞内からのNaのくみ出しと,細胞外からのKのくみ入れを行っているからである.こうした濃度勾配に逆らった上り坂輸送を能動輸送という.Na,K-ATPaseの細胞内基質はNa,細胞外基質はKのため,ICFのNa濃度やECFのK濃度が上昇すると,それぞれ細胞内/外の結合部位に結合し,Na-Kポンプは活性化され,細胞内へのKの取り込みが亢進する.
成人の体内総K量は50〜55mEq/kg体重で,その98%がICFに存在し,骨格筋が最も多く,肝臓や赤血球などにも分布している.一方,残りのわずか2%がECFに存在する.この細胞内外のKの濃度勾配は,前述のNa-Kポンプによって形成され,Na:Kの交換比率は3:2のため,細胞内が細胞外に比べ陰性に荷電している.その活性化に伴って膜電位が深くなり(過分極という),逆にウアバインによりその活性が抑制されると膜電位が浅くなる(脱分極という)ことから,“起電性”と呼ばれている.また,ICFのK濃度は約140mEq/Lに対し,ECFのK濃度は3.5〜5.0mEq/Lで,この細胞内外のK濃度比(35〜40/1)によって,−60〜−90mVの細胞膜電位が形成され,神経・筋細胞や心筋細胞では興奮・収縮に,上皮細胞では細胞膜や細胞間隙を介した電解質輸送に重要な役割を担っている.また,ICFのKは,細胞内浸透圧の維持,細胞容積や細胞内pHの調節などにも重要である.一方,ICFのKの一部はKチャネルを介して受動的にECFに移行する.
腎とカルシウム・リン代謝
著者: 黒尾誠
ページ範囲:P.344 - P.349
はじめに
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)とは“腎障害が3カ月以上継続した状態”と定義される.腎障害の原因は問わないが,老化現象の一環として起きるネフロン数の減少(腎老化)を,糖尿病や高血圧などの腎合併症をきたす生活習慣病が加速することで顕在化することが多い.近年,糖尿病や高血圧の治療薬は飛躍的な進歩を遂げているが,それにもかかわらず高齢社会の到来とともにCKD患者は増え続け,わが国では成人8人に1人が患う国民病となった.この事実は,糖尿病や高血圧の治療を徹底するだけでは不十分で,CKDの発症・進行を抑制する普遍的な治療法の開発が急務であることを示している.また,CKDが進行して腎不全に至れば,腎代替療法(透析か腎移植)が必要になる.血液透析患者の年間粗死亡率は約10%1),すなわち5年生存率は約60%で,悪性腫瘍全体の平均とほぼ同じである.生命予後に関しては透析導入は癌宣告に等しく,腎不全の治療法のさらなる改善も急務である.すなわち,CKDにおけるunmet medical needsは,第1にいかにして透析導入を減らすか(腎不全の予防),第2にいかにして腎不全患者の予後を改善するか(腎不全の治療)の2点に集約される.
本稿では,腎不全の予防および治療に有用と考えられる新しい臨床検査法について解説する.
腎と酸塩基平衡調節
著者: 泉裕一郎 , 向山政志
ページ範囲:P.350 - P.354
酸塩基平衡とは1)
生体が全身の臓器を正常に機能させ,生命活動を営むうえで,体液の恒常性の維持は非常に重要である.体液の恒常性には,体液量や電解質組成,浸透圧などの物理的性状が含まれるが,酸塩基平衡も重要な性状の1つである.
酸とは,水素イオン(H+)を供与するものであり,塩基とは,H+を受け取るものと定義される(Brønsted-Lowryの定義).酸と塩基が体液中に一定のバランスで保たれることを酸塩基平衡といい,その程度はpHで表される.pHはH+濃度の逆数の常用対数である.酸が多く存在しH+が増加するとpHは低下し“酸性”とされ,塩基が多く存在しH+が減少するとpHは上昇し“アルカリ性”と呼ばれる.
腎線維化のメカニズムとバイオマーカー
著者: 森西卓也 , 山本恵則 , 柳田素子
ページ範囲:P.356 - P.361
はじめに
腎機能が低下した患者では,その病因にかかわらず腎間質領域に線維化が認められる.腎線維化は全ての腎臓病におけるfinal common pathwayと考えられ,線維化の程度が腎機能の低下と強く相関するため,線維化の病態解明やその診断・治療は喫緊の課題である.腎線維化は間質領域に存在する筋線維芽細胞が細胞外基質を過剰に分泌することによって惹起されるが,そのメカニズムには不明な点も多かった.近年,遺伝子工学やさまざまな解析技術によって,腎線維化を担う筋線維芽細胞の由来やその制御機構が明らかとなってきた.
腎線維化を定量的に評価できる唯一の方法は腎生検であるが,侵襲性やリスクの観点から安易に行うことはできず,また繰り返し行うことも困難である.腎生検を行わずとも早期に腎線維化を判断することができれば,早期の治療介入・良好な腎予後へとつながる可能性があり,血液や尿から検出できるバイオマーカーを含めた体外診断法の開発が望まれる.
本稿では,近年明らかとなってきた腎線維化の分子メカニズムに加え,その診断方法,特にバイオマーカーについて概説する.
腎糸球体血行動態調節
著者: 城所研吾 , 柏原直樹
ページ範囲:P.362 - P.366
はじめに
腎糸球体は独立した循環制御機構を有しており,糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)を一定に保つことで,内部環境恒常性(milieu interieur)維持を担う.糖尿病関連腎臓病(diabetic kidney disease:DKD)を含む多くの腎疾患においては,この制御機構の破綻により糸球体高血圧・過剰濾過が生じる.糸球体高血圧・過剰濾過は腎障害進展の共通機序であると認識されており,アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(angiotensin Ⅱ receptor blocker:ARB)やSGLT2(sodium glucose cotransporter 2)阻害薬の腎保護作用の1つに,この糸球体高血圧・過剰濾過の是正効果が挙げられる.腎糸球体血行動態を理解することは,病態を把握し,適切な治療を行ううえで重要となる.
2章 腎疾患診療の進め方
医療面接,身体診察:腎疾患で確認すべきこと
著者: 永山泉 , 前嶋明人
ページ範囲:P.368 - P.372
はじめに
腎疾患は臨床症状を伴わないことが多いため,疑うことが重要である.例えば,腎炎の主な検査異常としてタンパク尿や血尿があるが,通常は自覚症状を伴わない.また,保存期腎不全では,自覚症状はほとんどなく,末期腎不全になって初めてさまざまな症状(尿毒症症状)が出現するようになる.一方,急性腎障害の場合は,症状(乏尿や無尿)を自覚した時点でかなり重症化していることが多い.
本稿では腎疾患を疑う際に重要な問診事項と診察所見について列挙し,それぞれについて考えられる腎疾患を詳しく説明する.
尿採取法を含めた尿検査の進め方
著者: 千葉(石橋)里佳 , 下澤達雄
ページ範囲:P.373 - P.377
はじめに
尿は,検査材料として最も容易に採取できる検体であり,患者への苦痛を伴わず,非侵襲性で繰り返し採取できる検体である.尿を材料にした検査は,尿定性検査,尿沈渣検査,尿化学(定量)検査,細菌検査,尿細胞診検査など多岐にわたるが,そのなかでも,尿定性検査,尿沈渣検査,尿化学(定量)検査は,腎・尿路系疾患の病態評価を行ううえで基本的かつ重要な検査となる.しかし,尿は同一患者であっても排泄量,pH,比重,浸透圧などが変動し,食事や運動,服用薬剤,精神的ストレスなどの影響を受ける.また,成分の変性や細菌の増殖により尿中成分の変化が起こる場合や食品,薬剤に含まれる成分により偽陰性・偽陽性反応を引き起こす場合がある.そのため,尿検査は採尿,判定,結果の解釈において注意が必要な検査である.
血液(全般)検査の進め方
著者: 木村秀樹
ページ範囲:P.378 - P.381
はじめに
健康診断でクレアチニン(creatinine:Cr)値の上昇,尿タンパク,尿潜血が指摘された場合,多くは一般の内科を受診し,すぐに腎臓内科専門外来を受診することは少ない.また,浮腫の原疾患も,腎疾患と鑑別すべき疾患は少なくない.ここでは,精査のファーストステップとして血液検査を軸に腎機能異常や浮腫の原疾患を大まかに鑑別してみたい.
超音波検査の進め方
著者: 髙田知朗
ページ範囲:P.382 - P.386
はじめに
超音波検査は,ベッドサイドで非侵襲かつ簡便に行えることから,腎尿路疾患の診療においてまず行うべき検査の1つである.腎疾患の原因検索のみならず,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)のフォローアップにも有用なモダリティである.
本稿では,腎疾患の鑑別を進めるうえでの超音波検査のポイントを中心として,特に内科的疾患の診療における超音波検査の活用について解説する.
画像診断(超音波以外)の進め方
著者: 井上勉 , 岡田浩一
ページ範囲:P.387 - P.390
はじめに
腎不全という旧来の病名とは異なり,早期の腎疾患群を内包する病名として,2002年に米国で慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の概念が提唱された.2009年には日本腎臓学会初となるエビデンスに基づいた本格的なCKDガイドライン(初版)が作成されている.同ガイドラインのなかでCKDの定義として,腎機能の低下や尿検査異常(主にタンパク尿)と並んで,画像検査異常が明記された.具体的にはCKD診断時に(腹部)超音波検査やX線CTを行い腎の形態評価と合併症(腫瘍や結石など)を確認すること,および核医学的糸球体濾過量の推定法が取り上げられていた.超音波検査は電離放射線や造影剤が不要で,低侵襲かつ簡便であり検査対象に禁忌がない.基本的には全てのCKD症例に行うことが勧められる最も重要な画像検査法であり,「超音波検査の進め方」(382〜386ページ)で細説される.本稿ではそれ以外の画像検査について概説する.
腎生検の適応と合併症
著者: 武田朝美
ページ範囲:P.391 - P.394
はじめに
通常,腎生検は,経皮的針生検または開放性で行われ,得られた腎組織を光学顕微鏡,蛍光抗体法,電子顕微鏡により詳細に検討する.腎疾患の正確な診断を確立して,予後を予測し,適切な治療方針を決定するために,また活動的および慢性的な腎病変の変化の程度を確認するために腎生検は行われる.腎生検の適応,禁忌,合併症対策については,日本腎臓学会編集の「腎生検ガイドブック2020」1)を参照されたい.
腎代替療法選択の進め方
著者: 八尋真名 , 倉賀野隆裕
ページ範囲:P.395 - P.398
はじめに
腎臓の働きが低下し,自分の腎臓で健康状態を維持できなくなると,腎代替療法として,血液透析(hemodialysis:HD)・腹膜透析(peritoneal dialysis:PD)・腎移植のいずれかを選択する必要がある.全ての治療法においてわが国は世界でもトップレベルの成績であるが,患者がそれぞれの長所・短所を十分に理解して,自分の生活環境やライフスタイルに最も適した治療法を選択する1)のは困難なことである.
よって,適切なタイミングで患者に療法選択に関する情報を提供し,患者自身が主体性をもって適切な治療法を選択できるよう,腎代替療法選択を進めていくことは非常に重要である.
3章 腎疾患と臨床検査
検査所見から腎疾患を想定する
著者: 梅田良祐 , 坪井直毅
ページ範囲:P.400 - P.403
はじめに
腎疾患の診断は,①病歴と臨床経過,②検査所見,③病理学的診断を合わせて行う(図1).診断における病理学的検査の重要性は非常に高いが,超音波ガイド下経皮的腎生検に際しては,その適応とともに検査に付随する合併症のリスクも評価する必要がある.例えば,片腎,囊胞性腎疾患,尿路感染症,出血リスクが高い症例などは相対的禁忌として施行が難しい場合が多い.その際は,病歴と臨床経過,検査所見をもって原疾患を推定することになる.
本稿では腎生検の実施困難例において,腎疾患の鑑別をどこまで行えるのか,検査所見にフォーカスを絞り記載する.病歴に関しては多くを述べないが,受診時の横断的検査だけでなく,以前からの連続変化を意識することが非常に重要である.
クレアチニンとシスタチンCの使い分け(推算GFR)
著者: 菅生太朗
ページ範囲:P.404 - P.407
はじめに
腎臓は尿の生成を行い,老廃物の排出のみならず水や電解質,酸塩基平衡の調整に重要な役割を果たしているほか,内分泌器官としての役割も有しており,エリスロポエチンやレニンの産生,ビタミンDの活性化や糖新生にもかかわっている.しかし,これら腎機能を総合的に判断することは困難であり,腎機能というと一般的に糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)のことを指す.
GFRの測定には,内因性または外因性であっても一定量血漿に流入し,血漿タンパクに結合せず速やかに拡散し,尿細管分泌・排泄や腎外排泄を認めず,体内でそれ以上代謝や分解されない物質が理想的である1).現在,主にわが国で使用されているGFRを推定する物質について以下に述べる.
尿定性検査の基本を押さえる
著者: 菊池春人
ページ範囲:P.408 - P.411
はじめに
本稿では尿定性検査(尿試験紙検査)項目に関して,急性腎障害(acute kidney injury:AKI),慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の診断,管理における意義,および近年CKDの治療に用いられ,AKIとの関連もあるナトリウム・グルコース共役輸送体2(sodium glucose cotransporter 2:SGLT2)阻害薬との関連について述べる.
尿沈渣
著者: 横山貴 , 塚原祐介 , 星野純一
ページ範囲:P.412 - P.417
はじめに
尿沈渣は,低コストで安全,簡便,迅速,かつ非侵襲的に繰り返し行うことができる検査である.さらに,各種尿沈渣成分の排出量を把握することによって,腎・泌尿生殖器における病態を類推できるため,各種疾患における診断と治療およびモニタリングに有用な検査として日常診療に用いられている.
本稿では,尿沈渣でどこまで病態,腎障害部位や腎症の鑑別に迫れるのかについて解説する.
尿細管マーカーの見方
著者: 池森(上條)敦子 , 木村健二郎
ページ範囲:P.418 - P.422
はじめに
腎臓では,加齢に伴い硬化した糸球体が増え,尿細管の脱落,間質の線維化が生じ,その結果,腎機能が低下する.このため,高血圧や糖尿病などの基礎疾患を有する高齢者は,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)を発症しやすく,CKDは,成人の8人に1人が罹患している国民病となっている.また,医療の革新的進歩に伴い,以前であれば対象とならなかった症例であっても積極的に先進医療が行われており,その合併症として急性腎障害(acute kidney disease:AKI)を発症する患者が増加している.従来,AKIは一過性に腎機能が低下し,その後回復する良性の病態と考えられていたが,AKIからCKDへ高率に移行することが明らかとなり,AKIの増加は,CKDの増加の一因である.これらの腎臓病は,進行すると末期腎不全となるだけでなく,心血管疾患の発症や生命予後の悪化に関連するため,適切な腎臓病の管理が重要である.
近年,腎臓病へ好影響を与える薬剤として,SGLT2(sodium glucose cotransporter 2)阻害薬や新たなアルドステロン拮抗薬による腎予後の改善が期待されている.しかし,腎機能がすでに低下した腎臓病では,これらの薬剤であっても十分な効果を実感できないのが現状であり,腎臓病が発症/進行する危険性の高い患者を早期に判別し,迅速に治療介入を行うことが求められている.腎臓病の悪化は,糸球体障害の程度よりも尿細管間質障害の程度と強く関連することや,AKIの多くが尿細管障害で発症することから,尿細管マーカーが,腎臓病診療において有用であると想定され,さまざまな尿細管マーカーが開発されてきた.
筆者らは,1997年より尿細管マーカー,尿L型脂肪酸結合タンパク(L type fatty acid binding protein:L-FABP)の開発にかかわり,尿L-FABPが腎臓病の早期診断や重症化予測に優れていることを見いだした1).その後,国内外の研究室からもさまざまな研究成果が発表され,尿L-FABPは,2011年にCKDおよびAKIに対する尿細管機能障害マーカーとして保険適用となった.尿L-FABPは,実臨床で使用できる日本発の尿細管マーカーである.腎臓病を悪化させる要因の1つが,腎内の微小循環障害により生じる尿細管低酸素であるが,尿L-FABPは,尿細管低酸素を反映する可能性がある.その後,2015年に好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(neutrophil gelatinase-associated lipocalin:NGAL)が,尿細管マーカーとしてAKIに対して保険収載された.海外では,2014年にNEPHROCHECK®{[tissue inhibitor of metalloproteinases 2(TIMP2)]×[insulin-like growth factor-binding protein 7(IGFBP7)]}が米国食品医薬品局で承認さている.ここでは,主にL-FABPについて述べるとともに,NGALとTIMP2×IGFBP7についてもふれる(表1).
尿化学定量と排泄率算出の意義
著者: 岩津好隆
ページ範囲:P.423 - P.427
はじめに
尿化学定量と排泄率(fractional excretion:FE)の算出は,従来から腎疾患や電解質酸塩基障害の診断・治療効果判定,食事摂取量の推定などに使用されている.一方で,食事摂取量の推定やFEの計算はやや煩雑であり,特に外来診療ではほとんど活用されていなかった.しかし,近年では電子カルテが普及し,検査項目として推定食事摂取量やFEを依頼すれば計算された結果が反映されるようになり,活用される頻度が増加してきている.
本稿では,腎疾患の診療で活用される尿化学定量とFEについて概説する.
腎にフォーカスした電解質の見方(Na+,K+,Cl−)
著者: 麻生芽亜 , 冨永直人
ページ範囲:P.428 - P.431
はじめに
尿電解質測定は非常に簡便かつ非侵襲的な検査であり,腎・内分泌疾患,水・電解質異常の病態評価や原因検索に有用かつ必須の検査である.生体における水・電解質の濃度,摂取量,有効循環血漿量の変化などを,さまざまな部位で感知して,最終的に腎臓で排泄量が決定される1).それ故に,尿電解質濃度は常に変動し,広範な値をとる.また,利尿薬などの薬剤の影響も受けるため,いわゆる基準値が存在せず,単純な濃度比較では病態を評価することは難しく,初学者の理解の妨げとなっている.水・電解質異常の正確な病態把握には,24時間の全尿蓄尿が適切に行われた場合,正確な排泄量を知ることができるが,検査が煩雑であることや多剤耐性緑膿菌(multiple-drug-resistant pseudomonas aeruginosa:MDRP)による院内感染の問題を踏まえ,蓄尿検査は極力行わないことが推奨されている2).
本稿では,特に臨床検査技師を対象として,より簡便な随時尿検査での評価を中心に,尿Na+,Cl−,K+濃度([Na+],[Cl−],[K+]),および尿Na+,Cl−,K+(排泄)量の解釈に関して概説するが,水電解質(濃度)異常や細胞外液量異常をみた場合,最も重要なことは,尿電解質濃度および尿電解質(排泄)量の結果から病態へアプローチすることである.
腎にフォーカスした血液ガスの見方
著者: 猪阪善隆
ページ範囲:P.432 - P.435
動脈血と静脈血
血液ガスを測定する場合,通常は動脈血ガスを用いる.特に呼吸機能を把握する場合は,動脈血ガスによる二酸化炭素分圧(carbon dioxide partial pressure:PCO2),酸素分圧(oxygen partial pressure:PO2)検査が必須である.
一方,アニオンギャップ(anion gap:AG)の計算や[HCO3−]の測定は静脈血ガスでも問題ない.表1に示すように,静脈血[HCO3−](下記*参照)のほうが動脈血に比べてやや高いが,HCO3−増加分だけCl−が赤血球内に移動するため(クロライドシフト),AGは変化しない.慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者に対して定期的に[HCO3−]検査を行う場合などは静脈血ガスで十分である.
二次性高血圧の鑑別に必要なホルモン検査と考え方
著者: 吉田雄一 , 柴田洋孝
ページ範囲:P.436 - P.439
はじめに
二次性高血圧とは,ある疾患によって二次的に引き起こされる高血圧である.この二次性高血圧は本態性高血圧と比較して,より治療抵抗性で脳心血管イベントを合併しやすい.二次性高血圧と診断とされた場合には本態性高血圧のように降圧薬による治療だけでは不十分で,その原因疾患に適切に対応しなければならない.
本稿では主にホルモン異常による二次性高血圧についてスクリーニング方法を中心に概説する.
腎性貧血の見方
著者: 三谷秀平 , 田中真司 , 南学正臣
ページ範囲:P.440 - P.443
はじめに
貧血は慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)に一般的な合併症である.発症には慢性炎症,鉄欠乏,赤血球の半減期短縮などもかかわるとされるが,主たる原因はエリスロポエチン(erythropoietin:EPO)の欠乏であり,その治療には赤血球造血刺激因子製剤(erythropoiesis stimulating agent:ESA)や新たに発売された低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(hypoxia inducible factor-prolyl hydroxylase:HIF-PH)阻害薬が用いられる.
本稿では,腎性貧血の診断と治療において臨床検査がどのように用いられているかについて,病態含め解説する.
CKD-MBDの見方(Ca,P,Mg)
著者: 濱野高行
ページ範囲:P.444 - P.448
はじめに
高リン血症や二次性副甲状腺機能亢進症などの検査値異常を呈している患者では,腎性骨症だけでなく,血管石灰化などの軟部組織の石灰化が生じ,これらが原因となって骨折や心血管イベント,さらには死亡というアウトカムにつながるという全身疾患概念(シンドローム)を慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)に伴うミネラル骨代謝異常(CKD-mineral and bone disorder:CKD-MBD)という概念で捉えるようになった.
この概念は国際的腎臓病ガイドライン機構(Kidney Disease Improving Global Outcomes:KDIGO)によって2006年に提唱され,すでに10年以上経過した.もともと透析期において提唱された概念であるが,実は保存期にその黎明がある.非常に進展したCKD-MBDに対して透析期になってから対処するよりも,保存期のうちにその程度を評価し,その対策を早めに講じることは,透析が不可避なstage4以上の患者では大切なことであろう.例えば,石灰化病変がもともと全くみられない患者の石灰化進展速度は遅いが,すでに血管石灰化が進展している患者では,その進展速度は速い.実際,血管石灰化病変に関しては,心血管イベントの既往のあるCKDあるいは糖尿病合併CKDでは簡単にみつけることができ,それらが透析導入されてからの基点病巣(nidus)になることは想像に難くない.
腎病理検査における最近の進歩
著者: 升谷耕介
ページ範囲:P.449 - P.454
はじめに
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の概念が登場して20年以上が経過し,末期腎不全および心血管病のハイリスク状態として継続的な啓発活動が行われている.尿検査異常や腎機能低下を認めた場合,かかりつけ医から腎専門医療機関へ早期に患者を紹介し,可能な限り腎生検による病理診断を行い,疾患特異的な治療を行う.個々の腎疾患においても病因・病態に関する研究が進み,新規バイオマーカーや治療薬が開発され,各疾患の治療成績が向上している.腎病理診断は単に診断のツールとしてではなく,得られるサンプルを用いた病態解明や新たな治療標的の探索においても有用な情報をもたらす.
本稿では腎生検により診断する代表的疾患と病態解明における最近の進歩,近年普及してきたバーチャル顕微鏡の応用について述べる.
4章 腎疾患を知る—臨床検査ができること AKI
定義と病態
著者: 大出佳寿 , 寺田典生
ページ範囲:P.456 - P.459
はじめに
従来,急激な腎機能低下を伴う病態は急性腎不全(acute renal failure:ARF)として認識されていたが,2000年代になり,早期診断と早期介入による予後改善を目標とすべく,急性腎障害(acute kidney injury:AKI)という新たな概念が提唱された.この背景には高齢化や慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD),糖尿病などの増加により,侵襲的で高度な治療が適応されるようになりAKIの頻度が急増してきていること,ならびにAKIを起こした場合の長期予後が著しく悪化することが広く認識されるようになったことなどがある.
本稿では,AKIの定義と病態について診断基準策定に至るまでの経緯や現況を解説するとともに,院内発症AKIと外来(初診)でみるAKIの違い,主に院内発症に多い多臓器不全を伴うAKIとAKI単独の予後の違いについて述べる.
臨床検査—さまざまなアプローチを使いこなす
著者: 中村仁美 , 土井研人
ページ範囲:P.460 - P.465
急性腎障害(AKI)の分類1〜3)
急性腎障害(acute kidney injury:AKI)は血清クレアチニン濃度の上昇や尿量減少をもとに診断するが,臨床の場においてはAKIの鑑別診断が求められる.最も広く用いられている分類は,腎前性・腎性・腎後性である(表1).それぞれの病態に応じて治療戦略が異なり,腎前性AKIでは腎灌流圧の維持が,腎後性AKIでは尿路閉塞の解除が優先される.また,腎前性と腎性の鑑別に関してはさまざまなアプローチがあり,臨床検査も多岐にわたる.
CKD
社会的問題
著者: 渡邊有三
ページ範囲:P.466 - P.469
はじめに
腎機能は加齢による腎血管構造の変化とともに低下し,わが国では65歳以上の男性の約30%,女性の約40%が慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者となる.わが国の慢性透析療法の現況(2021年末現在)によると,透析療法導入患者の平均年齢は71.09歳であり,年齢構成別で最も割合が高いのは,男性が70〜74歳,女性は80〜84歳であり,近年の高齢化は顕著である1).一方,老化の程度は1人1人異なり,暦年齢でのみ評価はできないことも当然である.高齢者は糖尿病や高血圧症,心血管疾患,脳血管疾患など種々の合併症を有することが多く,フレイルと総称される身体機能低下による日常生活動作(activities of daily living:ADL)低下,認知能力低下が重畳して,病態を複雑なものにしている.医療者依存という心理的な特徴は治療選択の意思決定の場面で支障となる.さらに高齢独居の問題も重なると,日常的な場面での介護の必要度が増え,通院支援などの社会的問題も生じる.したがって,治療選択の際には単純な医学的判断でなく,本人を取り巻く環境への社会的配慮も必要となる.
長寿化は医学的・倫理的に新たな課題を生じせしめた.末期腎不全(end-stage kidney disease:ESKD)の状態になれば,血液透析や腹膜透析,腎移植などの腎代替療法(renal replacement therapy:RRT)への導入が必然であった.しかし,認知能力が著しく低下して自己管理が不可能な場合や,重篤な腎以外の合併症により生命の危険が高まっている状態など,RRT導入による益よりも害のほうが懸念される場面にしばしば遭遇するようになった.筆者らが日本透析医学会の「維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」2)を2013年に報告した際には,RRT見合わせという議論を行うこと自体,社会に許容されるだろうかという懸念があったため,終末期患者に限定した提言とした.しかし,患者側の意思は尊重されるべきという意見が主流となり,厚生労働省からも人生会議としてのアドバンス・ケア・プランニング(advance care planning:ACP)が提唱されるようになった3).2022年には「高齢者腎不全患者のための保存的腎臓療法—concervative kidney management(CKM)の考え方と実践」4)が刊行され,RRTを開始しないという選択肢が患者の自己決定権を尊重するという面から,社会的に許容される状況となった.
本稿では従来のRRT療法の高齢者への適応ならびにCKM導入の際の留意点について概説する.
分類と病態
著者: 向井秀幸 , 長田太助
ページ範囲:P.470 - P.473
はじめに
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)は,世界中で透析療法・腎移植などの腎代替療法を要する末期腎不全患者数が増加しており,糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)低下やタンパク尿が末期腎不全だけではなく,心血管疾患(cardio vascular disease:CVD)や死亡の重大なリスク因子であることから2002年に米国腎臓財団(National Kidney Foundation)のK/DOQI(Kidney Disease Outcome Quality Initiative)診療ガイドラインで提唱された概念で,その後2012年に国際的腎臓病ガイドライン機構(Kidney Disease Improving Global Outcomes:KDIGO)から診断基準と重症度分類などがまとめられた.わが国でも日本腎臓学会が2007年に「CKD診療ガイド」を発行して以降,種々のガイドラインの改訂が重ねられ,CKD診療の普及・啓発・実践において大きな役割を果たしている.
臨床検査
著者: 相澤千晴 , 長浜正彦
ページ範囲:P.474 - P.479
慢性腎臓病(CKD)に合併する病態
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者はさまざまな合併症を有する.高血圧・ナトリウム(sodium:Na)過剰はそれ自体がCKDのリスクであるが,腎機能低下によってさらに体液貯留が進行する.そして腎機能低下が進行することによって,カリウム(potassium:K)や酸(H+),尿酸といった溶質の貯留が起こる.また腎臓の尿細管間質から産生されるエリスロポエチン(erythropoietin:EPO)や,近位尿細管で活性化されるビタミンDの作用が低下することで,貧血や骨ミネラル代謝異常(mineral and bone disorder:MBD)が起こる.CKDを診療する際にはこれらを理解したうえで,多角的に病態を捉えることが必要である.
本稿では,腎臓病診療ガイドラインの国際機関である国際的腎臓病ガイドライン機構(Kidney Disease Improving Global Outcomes:KDIGO)から2012年に発刊されたCKDガイドライン1)と2023年に日本腎臓学会で改訂された「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」2)を軸に,CKD患者で合併する病態とそれに伴う検査値異常について概説していく.
管理栄養士による栄養指導
著者: 川畑奈緒
ページ範囲:P.480 - P.485
はじめに
わが国では,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者は1,330万人といわれ,進行すると人工透析に至る.しかし,早期に対処すれば重症化を抑え,治癒を望むことも可能である.CKDの発症と進行には生活習慣の偏りが大きくかかわっていることから,腎機能を維持するために食事療法は極めて重要である.
CKD患者における栄養指導の有益性を示すエビデンスとして,わが国のランダム化比較試験であるFROM-J研究1)が挙げられる.さらに筆者らが行ったランダム化比較試験でも,管理栄養士による頻回の栄養指導が糖尿病性腎症の進行にかかわる臨床的および栄養学的指標を改善し,腎症の進行を抑制する可能性が示唆された2,3).これらの成績から,CKD患者では管理栄養士による栄養指導が非常に重要と考えられる.
そこで本稿では,CKD患者に対する食事療法基準を紹介し,栄養指導の際に参考にすべき検査所見および症例を呈示する.
看護師による生活指導
著者: 井本千秋
ページ範囲:P.486 - P.489
はじめに
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)は各病期に応じて生活指導を含めた支援が必要となる.看護師が外来受診や病棟での入院の機会に各病期だけではなく年齢,原疾患,生活背景,社会的立場なども含め,その患者に合わせた個別の生活指導を実施することで,より有効なセルフケア行動につながる.ここでは看護師が担う病期ごとのCKDの基本的な生活指導のポイントを示していく.
病診連携
著者: 角田亮也 , 山縣邦弘
ページ範囲:P.490 - P.493
はじめに
わが国の慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の患者は1,400万例を超えると推定されている1).そのなかでも加齢に伴い原因疾患としての頻度が増加している腎硬化症は,十年単位の長期経過で進行することが多く,血圧管理や生活指導などの保存的な診療が主体となる.このような状況において,全てのCKD患者を病院に属する腎臓専門医のみが診療することは不可能である.病状の比較的安定したCKD患者は,地域のかかりつけ医が主体となって診療していく必要がある.その一方で,CKDに対する適切な初期評価が行われないまま,漫然と経過観察のみが行われるのは問題である.
地域医療としてのCKD診療と,専門診療としてのCKD診療の間の線引きは明確でなく,また地域の患者分布や医療資源の状況によっても求められる診療体制は異なるため,絶対的な正解はない.しかし数多くのCKD症例のなかで,どのような症例を専門医へ紹介するか適切に判断するには,ある程度統一された一定の基準があるほうが望ましい.そこで本稿では,CKD患者における病診連携の意義と実践について考察する.
ただし,本稿の最も重要な前提として,CKD診療における病診連携のあるべき姿は地域によって大きく異なるという点を理解する必要がある.CKDについては,診療体制そのものが地域の医療資源によって大きく異なる.大学病院や総合病院が腎臓の難病や急性期の病態を重点的に診療し,診療所が病状の安定したCKDのプライマリケアに専念するという典型的な体制の地域もある一方,血液透析や腹膜透析,移植患者の通院まで含めた包括的CKD診療を実践している診療所や,常勤医の数が限られ,保存期CKDに対する保存的な外来診療に専念している病院も珍しくない.
本稿は“病診連携”がテーマであり,急性期を含め積極的な介入を要する患者を主に診療する医療機関を“病院”,安定した慢性期の診療を担う医療機関を“診療所”と便宜的に表現しているが,これらの指す対象は地域医療の実情に応じ,適宜読み替えていただきたい.
腎代替療法の現況
著者: 花房規男
ページ範囲:P.494 - P.497
腎代替療法
腎代替療法は,主に慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)が進行し,腎機能が十分ではなくなった末期腎不全患者において,腎機能を肩代わりするために行われる治療である.大きく,透析療法と腎移植とに分けられる.
透析アミロイドーシスの現況
著者: 雨宮伸幸 , 星野純一
ページ範囲:P.498 - P.501
はじめに
透析アミロイドーシス(dialysis-related amyloidosis:DRA)は,1975年に血液透析患者に手根管症候群(carpal tunnel syndrome:CTS)が多いと報告されたことから解明が始まった1).DRAはβ2ミクログロブリン(β2-microglobulin:β2m)を前駆タンパク質としたアミロイド細線維が組織に沈着することによって発症すると考えられており,透析歴が長いほどCTSの発症率が高くなることも報告されている2).
アミロイド細線維の形成は,重合核形成過程と線維伸長過程の2段階で構成される.β2mは酸性条件下でβシート構造が部分的にほぐれアミロイド伸長反応が起こりやすくなると考えられている3).また,DRAの発症進展には炎症細胞浸潤4),機械的刺激5),糖化β2mによるマクロファージ由来の骨吸収性サイトカイン〔インターロイキン(interleukin:IL)-1β,腫瘍壊死因子α(tumor necrosis factor-α:TNF-α),IL-6など〕の産生亢進6)などが報告されており炎症の関与が示唆されている.
今世紀に入り,透析技術,医工学技術,透析管理法の発展などでDRA発症率は低下していると思われるが7),依然として発症阻止には至っておらず長期透析患者の多いわが国においては重要な透析合併症となっている.
本稿ではDRAの現況,臨床症状,検査値の特徴,治療などについて概説する.
尿毒症と臨床検査
著者: 吉田栞 , 山本卓
ページ範囲:P.502 - P.505
はじめに
尿毒症とは,腎機能の悪化に伴い,尿中から体外へ排泄されるべき尿毒素物質が体内に蓄積することにより引き起こされる状態である.尿毒素はさまざまな臨床症状を引き起こすだけでなく,心血管疾患など合併症の発症リスクとの関連も報告されており,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者のQOL(quality of life)や生命予後に強くかかわる.
本稿では,尿毒症症状の原因となる尿毒素の定義や分類,尿毒素によって引き起こされる症状や合併症について解説する.また,尿毒素の定量評価や透析療法における除去効率の評価についても触れる.加えて,さまざまな合併症との関連が報告されているインドキシル硫酸の簡便化された測定方法やその臨床応用への展望についても紹介する.
腎代替療法(血液透析・腹膜透析・移植)と臨床検査
著者: 伊藤聖学 , 大河原晋
ページ範囲:P.506 - P.509
はじめに
腎機能が廃絶した末期腎不全患者に対する腎代替療法として,血液透析(hemodialysis:HD)療法,腹膜透析(peritoneal dialysis:PD)療法,腎移植の3つの治療法が挙げられる.わが国において,腎代替療法を実施している患者のそれぞれの割合は,HDが約95%,PDおよび腎移植が約3%弱ずつという現状があり,腎代替療法の臨床検査として,HD患者の臨床検査にかかわることが多い.
そのため本稿では,HD患者の臨床検査を中心に,腎代替療法に特化した検査について述べ,PD患者や腎移植患者の臨床検査についても触れる.
臨床検査で迫る腎疾患
ネフローゼ症候群と臨床検査
著者: 藤本圭司 , 古市賢吾
ページ範囲:P.510 - P.513
ネフローゼ症候群(NS)
ネフローゼ症候群(nephrotic syndrome:NS)は,糸球体毛細血管から大量のアルブミン(Alb)を主体とするタンパク尿(3.5g/日以上)が尿中へ漏出する病態である.結果的に低Alb血症(血清Alb値3.0g/dL以下)を生じる.原因が明らかでない一次性NSと他の全身疾患あるいは明らかな原因による二次性NSに大別される.
本稿ではまずNSの病態について概説した後,各検査値異常について詳述する.
IgA腎症・IgA血管炎の診断および活動性・重症度の評価
著者: 小松弘幸
ページ範囲:P.514 - P.518
はじめに
IgA腎症は1968年にBergerらによって初めて報告された,世界で最も多くみられる原発性糸球体疾患である.その病因はいまだ明らかではないが,一部に遺伝的素因がみられるほか,上気道感染時に悪化することから粘膜免疫の異常の関与が考えられている.診断から約20年の経過で約30〜40%が末期腎不全となり,人工透析などの腎代替療法を要する予後不良の疾患である1).重症度の低い早期の段階で診断され適切な薬物療法が行われれば寛解に至る症例もあるため,早期診断につながる検査方法の確立は極めて重要である.
本稿では,診療指針に基づくIgA腎症の診断基準や重症度評価を概説した後,血清免疫グロブリンA(immunoglobulin A:IgA)値およびIgA/C3比の測定意義について文献的に考察し,最近注目されている新たなバイオマーカーも紹介する.最後にIgA血管炎についても簡潔に言及する.
膜性腎症の病態評価
著者: 中里玲 , 三井亜希子
ページ範囲:P.519 - P.523
はじめに
膜性腎症(membranous nephropathy:MN)は,糸球体上皮下への免疫複合体沈着とそれに伴うポドサイト障害によりタンパク尿を呈する疾患群を指す.MNの原因は,一次性(ポドサイトに発現する標的抗原とそれに対する自己抗体の存在による)と二次性(他の全身性疾患や薬剤などに起因)の大きく2つに分けられる.2009年に一次性MNの標的抗原であるPLA2R(phospholipase A2 receptor)が同定されて以降1),MNの病態理解や診療アプローチは大きく変化している.
本稿では,MNの病態,臨床的な特徴および診断と,近年明らかとなっているMNの標的抗原に関する検査・治療への応用について概説する.
糖尿病性腎症・腎臓病と腎硬化症
著者: 田蒔昌憲 , 脇野修
ページ範囲:P.524 - P.527
糖尿病性腎症(DN)の診断と病期分類
糖尿病は慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)や末期腎不全の重要な原因であり,糖尿病の腎合併症である糖尿病性腎症(diabetic nephropathy:DN)はわが国の新規透析導入原疾患のうち最多である1).DNは,もともと糖尿病性糸球体硬化症という組織学的特徴を有する腎疾患に対する病名であった2).しかし2型糖尿病患者数は多いため,腎症を疑う全ての症例に腎生検を施行することは現実的に困難である.したがって,典型的な臨床経過と症候〔糖尿病歴,微量アルブミン尿〜顕性アルブミン尿を経て糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)低下,高度血尿なし,糖尿病網膜症・糖尿病神経障害の合併など〕を伴い,臨床的にほかの腎疾患が強く疑われない場合にDNと診断されるようになった2).
上記の通り,典型的なDNの臨床経過としては尿タンパクの悪化が先行し,次第に腎機能障害が進行し,最終的に末期腎不全へ至る.したがって,わが国におけるDN病期分類に関しては,旧厚生省糖尿病調査研究班で作成され糖尿病性腎症合同委員会で改訂された分類が広く用いられていた3).しかし,CKDの概念が提唱されCKDステージ分類が登場すると,従来のDN病期分類では主にアルブミン尿で分類され,CKDステージ分類では推算糸球体濾過量(estimated GFR:eGFR)で分類することから,両者に乖離を生じる症例が存在することが明らかとなった.そこで,2014年にDN病期分類が改訂され3),その後2023年に改訂されて今日に至る(表1)4).特に,尿アルブミン測定が重要であるが,本検査の保険適用として,糖尿病または糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(DN第1期または第2期のものに限る)に対して行った場合,3カ月に1回に限り算定できることに注意が必要である.
ANCA関連腎炎・Goodpasture症候群の活動性評価
著者: 秋山知希 , 臼井丈一
ページ範囲:P.528 - P.532
ANCA関連腎炎1〜3)
■疾患概念
血管炎とは,大小さまざまな血管に炎症を生じ臓器障害を引き起こす疾患の総称である.チャペルヒルコンセンサス会議(CHCC2012)4)で血管炎の名称や概念が整理され,顕微鏡的多発血管炎(microscopic polyangiitis:MPA),多発血管炎性肉芽腫症(granulomatosis with polyangiitis:GPA),好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis:EGPA)の3疾患が抗好中球細胞質抗体(anti-neutrophil cytoplasmic antibody:ANCA)関連血管炎(ANCA-associated vasculitis:AAV)と定義された.血管炎が腎に限局する場合は腎限局型(renal-limited AAV:RLV)と呼称する.ANCA関連腎炎とは,AAVにみられる腎炎を指す.
ANCAは好中球などの細胞質顆粒に対する自己抗体で,間接蛍光抗体法(indirect immunofluorescence:IIF)のパターンによりp(perinuclear)-ANCAとc(cytoplasmic)-ANCAに分類され,主な対応抗原はそれぞれミエロペルオキシダーゼ(myeloperoxidase:MPO),プロテイナーゼ3(proteinase 3:PR3)である.
腎アミロイドーシスとMタンパク尿関連腎障害・MGRS
著者: 黒田毅
ページ範囲:P.534 - P.537
はじめに
アミロイドーシスは,アミロイド線維を主体とするアミロイド物質が全身諸臓器に沈着し,種々の機能障害を惹起する一連の疾患群である.複数の臓器にアミロイドが沈着する全身性アミロイドーシスと,ある臓器に限局してアミロイドが沈着する限局性アミロイドーシスに分けられる.全身性アミロイドーシスのなかで高度の腎機能障害に進展し予後に重大な影響を及ぼす主要なものはALアミロイドーシスとAAアミロイドーシスである.ALアミロイドーシスは異常形質細胞から産生される単クローン性の免疫グロブリンの軽鎖(κおよびλ)がアミロイド線維を形成する.AAアミロイドーシスは各種の基礎疾患による炎症反応に伴う血清アミロイドA(serum amyloid A:SAA)タンパクが高濃度で長期間存在することによりアミロイド線維が形成される.
ループス腎炎・膠原病に伴う腎病変の活動性評価
著者: 廣村桂樹
ページ範囲:P.538 - P.541
はじめに
膠原病は全身の結合組織に障害が生じる自己免疫性疾患の総称である.結合組織は細胞同士をつなぐ成分であり,膠原線維,線維芽細胞,基質などを含む.膠原病ではこれらの結合組織が重要な構成成分となっている血管,皮膚,筋肉,関節をはじめとして,全身の諸臓器が標的になる.特に,腎臓は膠原病で障害されやすい臓器である.
膠原病のなかでも,高頻度に腎病変を伴う疾患としては,全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus:SLE)が挙げられ,腎病変はループス腎炎と呼ばれる.
本稿では,ループス腎炎に焦点を当てつつ,Sjögren症候群やIgG4関連疾患に伴う腎病変についても少々解説する.また,ANCA関連血管炎も腎病変を高頻度に引き起こし,ANCA関連腎炎と呼ばれる.ANCA関連腎炎については,528〜532ページを参照されたい.
血栓性微小血管症の病態評価
著者: 加藤規利 , 立枩良崇 , 丸山彰一
ページ範囲:P.542 - P.545
はじめに
血栓性微小血管障害とは,さまざまな原因による血管内皮障害が引き起こされた結果,微小血管において血小板血栓が形成され,血栓性の臓器障害が引き起こされることを指し,その病態を血栓性微小血管症(thrombotic microangiopathy:TMA)と呼ぶ.貧血,血小板減少をきたすが,これらは肝障害や播種性血管内凝固症候群などにも共通する検査所見であり,TMAの存在は見落とされやすい.このような血球減少をきたす患者の診療においてはTMAを“疑う”ことが重要で,診断の際に注意したいのは溶血性貧血の存在に“気付く”ことである.そのためには破砕赤血球の出現や,ハプトグロビンの低下に注目したい.
腎疾患の話題
“造影剤腎症”,まだ気になりますか?
著者: 徳竹雅之
ページ範囲:P.546 - P.549
はじめに
“腎機能が悪い場合には造影CTは禁忌である”,これは臨床の現場であたかも“常識”のように語られている.しかし,実際のところこの考え方は前時代的であり,いわゆる“造影剤腎症”にかかわる迷信に対して,正しい見識が広まる必要性を感じさせられる.
結論だけ言うと,ヨード系造影剤を使用するか否かは,臨床診断を導くために造影剤が必要か否かの軸で語るべきであり,腎機能に依存するものではない.そこで,本稿において根拠に基づいて分析し,“常識”を考え直したい.なお,本稿では主に造影剤を静脈内投与する場合について論述する.
Onconephrology
著者: 前岡侑二郎 , 正木崇生
ページ範囲:P.550 - P.553
onconephrology
悪性腫瘍は国内外で死因の上位を占め,世界の高齢化に伴い,さらに増加している.国立がん研究センターのがん統計では,悪性腫瘍と診断される確率は2人に1人であり,悪性腫瘍で死亡する確率は男性が4人に1人,女性が6人に1人と推計されている.近年,がん領域の治療が急速に進歩している一方で,より専門性の高い多様な副作用が出現するようになった.このような背景からoncology(腫瘍学)とnephrology(腎臓病学)を組み合わせたonconephrologyという造語が生まれた.onconephrologyにおいて,がん診療における腎障害は生命予後悪化に関与する最も重要な問題であり,「がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン」1)が2016年に作成され,2022年に改訂された2).
腎疾患における治療薬物モニタリング(TDM)
著者: 平田純生
ページ範囲:P.554 - P.559
腎疾患と治療薬物モニタリング(TDM)
■TDMの現状
治療薬物モニタリング(therapeutic drug monitoring:TDM)とは,個々の患者の薬物血中濃度を測定し,薬効および副作用を的確に把握したうえで,それぞれの患者に個別化した薬物投与を行うことである.わが国で薬物血中濃度の測定が保険で算定可能な薬物(特定薬剤治療管理料の算定できる薬物),すなわちTDMの対象薬には,抗菌薬,免疫抑制薬,抗癌薬,抗不整脈薬,抗てんかん薬などいわゆるハイリスク薬が多く含まれており,60数種類に上る.ただし実際に臨床現場で測定され,薬剤師が薬物動態学的評価を加えてフィードバックしている薬物の多くが腎排泄性のバンコマイシンである.バンコマイシンは投与量が多すぎると薬剤性腎障害が起こりやすく,逆に投与量が少なすぎると効果が得られず,血中濃度が低い状態(無効域)が続くとバンコマイシン耐性腸球菌などの耐性菌を出現させる恐れがあるため,多くの病院でTDMが実施されている.
そして,高額医療である臓器移植に伴って特別に他のTDM対象薬の10倍近くの高額な保険点数が設定されている免疫抑制薬の主役であるカルシニューリン阻害薬のTDMは,特に移植直後に頻繁に行われているが,臓器移植の可能な大学病院またはそれに準ずる高度医療機関のみで実施されている.
基本情報
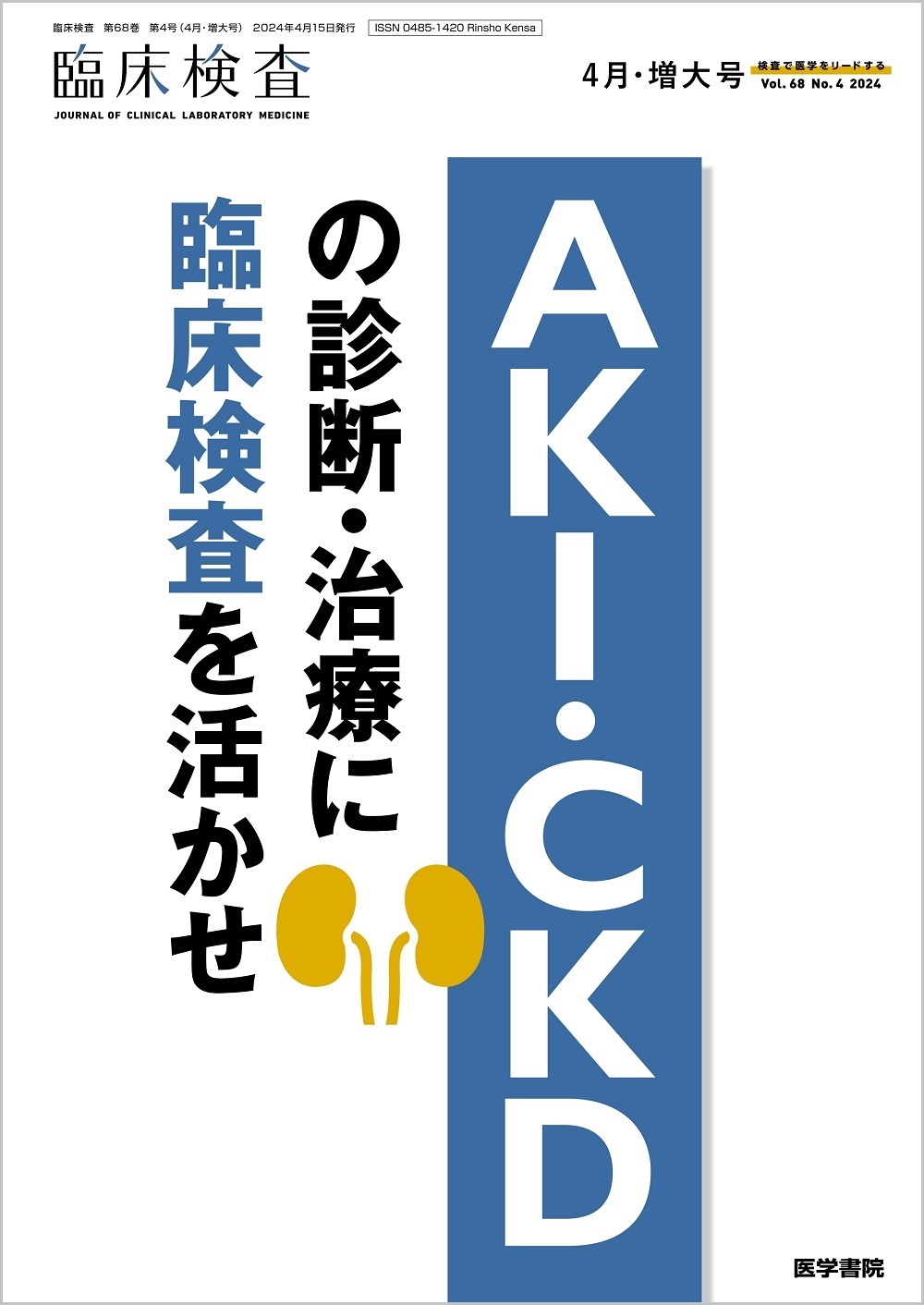
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
