薄層クロマトグラフィーが生化学の分野で大いに利用されているのはいうまでもない.それにもかかわらず,臨床検査の分野でのスクリーニング法としては,実際に用いられているものは試験紙などによるスポットテストをはじめ,試験管内反応の検査やペーパークロマトグラフィーぐらいである.その理山としては,薄層クロマトグラフィーは操作が複雑で,高級なテクニックが必要であると考えられているためと思われる.しかし,実際使用すると簡易性,迅速性,能率,鋭敏性,呈色試薬の多様性などの数々の利点があるので,上記の考えは一掃されてしまうだろう.
雑誌目次
臨床検査14巻5号
1970年05月発行
雑誌目次
カラーグラフ
グラフ
病理組織のための電顕試料作製法Ⅱ—薄切と染色
著者: 三友善夫 , 宮本博泰
ページ範囲:P.423 - P.430
一般的電子染色法に用いる染色液
染色液は染色操作(①固定後脱水前,脱水中に行なわれるブロック法と,②超薄切片に行なわれる方法)によって異なるか,超薄切片に行なう方法が安全性が高い.
抗原抗体反応・5
間接凝集反応(受身凝集反応)
著者: 松橋直
ページ範囲:P.432 - P.433
抗体がその反応部位で抗原の決定基と結合することによって,抗原抗体反応が起こり,沈降物を作ったり,凝集塊ができたりするので,沈降反応や凝集反応の間には,本質的な差異がないことは前回に述べたとおりである.しかし,溶液性の抗原と対応する抗体との間で起こる沈降反応も,抗原の大きさを大きくして赤血球ぐらいにすると,凝集反応の形で観察することができる.こうすることによって,抗原の決定基と給合はするけれども,凝集反応が起こらない特殊な抗体(これを不完全抗体とか,非定型抗体と呼んでいるが)検出できるようになったり,抗原抗体反応の感度を高めることができるので,血清学的検査法にはしばしぼ応用される.次に例をあげながら述べてみよう.
抗グロブリン試験(クームズ試験)は,凝集能力をもたない不完全抗体(非定型抗体)と反応した赤血球は,1個1個ばらばらである.このような赤血球の浮遊液に,その抗体と反応して沈降反応を起こすことができるような抗グロブリン抗体を加えると,抗グロブリン抗体は,赤血球の表面に結合している不完全抗体(非定型抗体)と結びつきあうので,凝集反応が起こる.抗グロブリン試験の場合は,生体内で赤血球に抗体が結合している患者(自己免疫性溶血性貧血)があるので,このような例では,患者赤血球をとってただちに洗い,抗グロブリン抗体と反応させて検査するので,抗グロブリン試験直接法と呼ばれている(図1).
ノモグラム・5
クレアチニンクリアランス最大尿素(Cm)クリアランス
著者: 斎藤正行
ページ範囲:P.435 - P.435
クレアチニンクリアランス 左端U/B値と右端の1分間尿量(V)を結ぶ線とC軸との交点の左側目盛りが求める値である.糸球体濾過値(GFR)などの計算もこれに準ず.
例 尿クレアチニソ21mg/dl,血清クレアチニン1.4 mg/dl,したがってU/B=15で1分間尿量3 mlとすると,C=45 ml/min.
検査室の便利表・5
放射性アイソトープ減衰計算表
著者: 松村義寛
ページ範囲:P.437 - P.437
ラジオアイソトープは,零次反応式に従って減衰していく.数式で表わすと,当初の活性度(cpm)をAo時間tが経過たときの活性度をAtとすればAt-Aoc−00.693/T1/2tT1/2tは半減期でAt=Ao/2となるために経過した時間であって核種について定まっている.
このノモグラムは半減期T1/2と経過時間とが与えられたときに,Ao=kAtとおいたときのkを求めるもので,1/k=e0.693/T1/2tを与えるものである.
総説
難聴の検査と病理
著者: 佐藤喜一
ページ範囲:P.439 - P.445
聴力検査—検査室ではあまり耳なれない科目であるが,すでに中検に属しているところもある.カナマイシンをはじめとする抗生物質の投与,現代の騒然たる生活環境などから知らぬうちに聴力機能が衰えてくる.そこで,検査室への啓蒙も含め,最新の"耳の検査"を解説する.
私のくふう
輸血用チューブを用いての感性ディスクの置きかた
著者: 津留崎利博
ページ範囲:P.445 - P.445
感性ディスク法を行なう場合,ピンセットで1ディスクずつつまみあげるには,なかなかの心労を要します.また,平板上任意の地点へ置くにもころがったり,接近しすぎたりで苦労します.そこで,私は輸血用チューブを用いて簡易に,しかも任意の地点へ置くことができ,能率的にもたいへんよい結果を生んだのでご紹介します.
ピペット安全操作器について
著者: 吉原忍
ページ範囲:P.494 - P.494
危険液のピペット操作,ことにコレステロール検査の試薬のようなものを,直接口でピペッティングすることには危険を感じ,注射器にゴム管を介してピペットを接続しても,ピペットの安定が悪く,コレステロール検査のように左手に試験管を持ち,右手でピペットを操作するというこまかい操作のむずかしさを感じ,何とか注射器とピペットを固く固定できたらと考え,次のようなものを作り便利に使っております.
技術解説
コレラ菌の新しい分離培養
著者: 坂崎利一
ページ範囲:P.446 - P.450
はじめに
1960年ごろまで,わが国においてはすでに過去の伝染病であったコレラが,東南アジアでのエルトール型コレラ菌による流行に端を発して,毎年その侵入におびやかされるようになった.それと同時に,コレラおよびコレラ菌についての研究がふたたび活発化し,19世紀の知識のままにとどまっていたこの分野に,近代医学の光があてられて各方面で新しい知見がえられている.コレラの細菌学的検査方法もまたその例外ではない.
コレラはいうまでもなくインドに古くから存在する風土病で,その細菌学的検査方法はインド人学者を中心として開拓され,いままでに報告された増菌培地や分離培地の種類は枚挙にいとまがないほどである.また,わが国でも最近TCBSヵンテンなどの新しい培地が開発され,これが東南アジア地域でかなりひろく使用されていることは衆知のことである.しかし,分離培地の価値は実際の例に直面すると,必ずしも原著の記載どおりではないことがしばしばある.
薄層クロマトグラフィー
著者: 久保博昭 , 中山妙子
ページ範囲:P.451 - P.460
薄層クロマトグラフィー(表)は,ガラス板などの支持体の上に,適当な吸着剤を一定の厚さに薄層状に固着したもの(以後,プレートと称する)を用いて,微量の混合物を分離するクロマトグラフィーである.この方法の特徴は,
1)目的に応じて吸着剤が選べる.
ひろば
衛生検査技師の立場から
著者: 軍司光夫
ページ範囲:P.450 - P.450
医師の指示について
衛生検査技師は,患者に直接間接を問わず,検査成績を知らせることは周知のとおり禁じられていることである.しかし,まれではあるが外来診療で急を要する場合に,医師が患者に直接検査成績をもって来るよう指示している場合がある.それにはいろいろと施設の状況(入手不足など)があろうが,この場合,衛生検査技師は患者の手に検査成績を直接渡すべきか否かが問題点になろう.衛生検査技師の立場からはこれは許されるべきではないが,医師の指示によるということになれば,話は別になってくると思う.しかし現実には,患者に検査成績を手渡しているのが現状だが,特にこの場合確かに医師の指示かどうか再確認を是非必要とすべきと思われる.どこまでも医師の指示どおり行なえば問題にはなるまい.
検査器械も一員
著者: 村田徳治郎
ページ範囲:P.460 - P.460
検査室を見学させてもらうことは,自分が反省するうえに大いに役だつし,そのうえ教科書にない勉強ともなり,技術的な点のみならず臨床検査技術士として,参考になる貴重な経験といえよう.ある大病院の病理室で30-40年前のザイッ(ドイツ製の顕微鏡が,今も第一線で活躍しているのを見て非常に驚いてた.しかも,染色程度の判別という,顕微鏡にとっては悪い条件ながら,よくその任を果たしていた.レンズの解像力も良好であり,全体として使いよいなという印象を受けた.
あるメーカーの技術者が"私ども制作した者でも,あの機器を使いこなすのはむずかしい,また故障が出た場合もう修善する自信がない"と7-8年前かもっと古い型の脳波計を前にして,嘆息とも感心ともつかないようであったが,とにかく現に,ある女子技術者によって非常に調子よく第一線で働いているのである.自分の技術の未熟を棚に上げて,一方的に器械の責任にしてしまう技術者も多い中で,1つの参考例としたい.
臨床検査の問題点・17
血液凝固検査—スクリーニングテストの範囲
著者: 藤巻道男 , 日比谷淑子
ページ範囲:P.462 - P.468
出血傾向,あるいは出血性素因の有無を知ることは手術を受ける患者にとっては必須であるばかりか,毛細血管の異常を発見するうえでも欠かせない.スクリーニングテストの範囲内で,適切な採血のしかたからフィブリンの析出まで実際的な問題点を検討する.
主要疾患と臨床検査・17
公害病と臨床検査
著者: 西川滇八
ページ範囲:P.469 - P.473
ロンドン市スモッグ事件
1952年12月5日,ロンドン市は濃いスモッグにおおわれてしまった,ロンドドン名物の濃霧ではあるが,この時には煙の粒子が核となってできた霧であるから,黒い霧であった。ときの要人であったチャーチル(W.Churchill)卿も自邸から市内にはいると自動車の窓を堅く閉ざして,カーテンをおろし,少しでも市内の汚れた空気が車内に侵入しないように心がけたほどである.この黒い霧は5日間も続いた.
市内のバスは動けなくなり,交通警官の先導でのろのろ運転をした.列車も速度が出せず,市内の社会的機能は極度に停滞してしまった,陸上の交通機関ばかりでなく,海上の船,空中の飛行機までロンドンには近づけなくなった.ただ,救急患者を運ぶ自動車だけがふだんよりも活発に動いていた.それは自宅に引きこもっていた気管支炎や心臓病の患者たちが,スモッグのために症状が悪化したので,彼らを病院に送り込まなければならなかったからである.
光電池の開発に偉大な功績—Dr.Bluno Langeをしのんで
著者: 吉田光孝
ページ範囲:P.474 - P.474
昨年6月3日に,あのりっぱな物理化学者であるDr.Langeが突然享年66歳で逝去されたニユースは,多くの人々の驚きと心痛であったことと思う.
1961年4月に元気で来日され,堂々たる講演で熱弁され,多くの方々に深い感銘を残された印象を新たに想い起こされる方も少なくないであろう.その時の講演内容は,"ヨーロッパを中心とした医学的検査領域における機器分析の現状"というテーマであった.あの有名な光電効果の発見から種々の光電池の開発,そして世界初めての光電光色計,炎光光度計などから,最近の進歩について語られた。その講演中,しっかりと手にされていたのは,なんと彼の開発したセレン光電池で,説明される片方の手から豆ランプの光が光電池に照射されると,光電池に連結されたかわいい風車がくるくると回りだす(光を電流に変えるという光電効果の原理を示す)模型であった……
臨床検査と‘単位’あれこれ—系統的な簡略化へ
著者: 吉野二男
ページ範囲:P.495 - P.497
混乱している表示法
長い期間をかけて普及につとめてきたメートル法がやっと軌道にのって,私どもの身辺から貫だとか,匁,坪,尺,ヤード,ポンドというものがその姿を消してきましたが,検査室ではどうかと考えてみると,よく使う単位というのはメートル法には違いないのですが,予想外に複雑であることがわかります.
その一部をあげますと表1のようになります.なかには,すぐに理解できないものもあるようですので少し説明してみますと,たとえば,長さの単位もm,cm,mm,μ,mμ,μμ,Åというしだいです.基本単位名称がmなのに途中からμというものができて,その1/1000だからmμ,さらにμのμだからμμ,またÅというように,基本単位のmとは記号も全く違ったものを用いてしまっているので,Åの単位付近のものだけを取り扱っているときにはよいかもしれませんが,全般的,共通的に老えると非常にふつこうであると思います.
1ページの知識 生化学
ガラス器具の洗浄
著者: 降矢熒
ページ範囲:P.475 - P.475
われわれが臨床化学検査に日常使用するガラス器具には,試験管,遠心管,比色計のキュベット,秤量びん,漏斗,ビーカー,試薬びん,メスシリンダー,メスフラスコ,ピペット,ビュレットやその他数多くの種類がある.これらは,容量分析に使用する場合のみならず,定性分析の場合にも使用に先だって化学的に清浄にしておく必要がある.
血液
赤血球の指数と恒数
著者: 糸賀敬
ページ範囲:P.476 - P.476
赤血球数(RBC),血色素量(Hb),ヘマトクリット値(Ht)の測定によって,貧血の有無やその程度がわかるが,それ以上に疾患の種類や原因,さらにその治療方針などを知るためには,これらの測定値から算出される種々の赤血球指数や,ウィントローブ(Wintrobe)の赤血球恒数がたいへん参考となるので,以下その算出方法を記載する.
血清
マクロファージ
著者: 水谷昭夫
ページ範囲:P.477 - P.477
抗体産生の機構に関しては,従来諸家によるさまざまの学説があり,その真相についてはいまだ明らかでない.
Burnet一派を旗がしらとするいわゆるクローン選択説(clonal selection theory)と,PaulingやHaurowitzの名前と結びついたタンパク質化学を土台とした抗原指令説(instructive theory)との間の論争が,活発に展開されているようにみうけられるが,われわれはこれらの問題に対する早急な結論を求めることにのみ目をうばわれてはならない.
細菌
検体別細菌検査(1)—おもな検出菌とその分離法
著者: 土屋俊夫
ページ範囲:P.478 - P.478
各種の検査材料につき病原体の検索を行なう場合,特定の病原体だけを目標に検索を進めることは比較的少なく,多くは検査材料から検出される可能性のある病原菌を,残らず検出できるような検査方法をこうずることが必要である.病原菌の検索は図のように進められるが,臨床細菌検査の目的を考えると,まず感染症の治療には原因菌の感受性検査が最も必要である.したがって,まず検査材料から病原菌を確実に検出し同定するとともに,できるだけ早く感受性検査を行なうことである.
病気の種類によっては,検査材料の塗抹検査で診断が可能なことがある.たとえば,咽喉頭の分泌物中のジフテリア菌,喀痰中の結核菌や肺炎球菌,尿道分泌物中の淋菌,髄液中の髄膜炎菌などがそうである.しかし,多くの病原菌は,まず検査材料を適当な方法で分離培養し,発育した菌につきさらに同定検査,薬剤感受性検査が行なわれる.
病理
脱アルコールからパラフィン包埋へ
著者: 和田昭
ページ範囲:P.479 - P.479
1.脱アルコール
パラフィン滲透に移る前に,脱水剤として用いたアルコールを除去してしまわなければならない.組織内にアルコールがあると,アルコールに溶けないパラフィンが滲透しないため,両者に溶けるクロロホルムやキシロールなどを用いてパラフィン滲透の媒介をする.これらの液を入れる容器は広口びんを用いるのがよく,3個ぐらい用意しI,II,IIIの番号をつけておき,脱水された組織片を順次に移していく.
アルコールがぬけるにつれ,組織片は飴色を呈し透明度が増してくるが,脱水の不十分な組織の場合は組織片に白濁が残るので,再びアルコールに戻して脱水を十分にやりなおさねばならない.脱アルコールに要する時間は約30分から長くても2時間ほどで,それ以上要するものはきまって脱水不十分のものか,組織片の厚すぎるものである.長時間になると組織の硬化や縮少をきたすが,特にキシロールがクロロホルムよりこの作用が強い.クロロホルムは空気中の湿気を吸いやすい性質があるので二重ぶたのびんがよく,また無水アルコールびんと同様,無水硫酸銅粉末を底に敷いておくとよい.脱水から脱アルコールへ移す組織片は,濾紙でよくアルコールをきってから移すようにすると,クロロホルムやキシロールを経済的に使用することができる.
生理
—正常波形や記録のなりたちと生理的基礎知識・3—心音図
著者: 魚住善一郎
ページ範囲:P.480 - P.480
心音図とは心活動に由来する振動のうち,主として可聴域の振動をマイクロホンで採取し,濾波器を通して適当な成分を取り出して増幅し,記録器を用いて客観的に表示したものである.通常,時間的推移をみるために参考誘導として心電図を同時に記録するが,他の部位からの心音・血管音図,可聴域下の振動図(心尖拍動,頸動・静脈波など)を同時記録することもある(同時多誘導記録法).心活動に由来する振動のうち,持続の短い振動を心音,長いものを心雑音と呼ぶ.心音は内圧,血流の急激な変動の起きる時期に生じ,雑音は主として血液の流れによって生じる.胸壁を聴診すると2つの持続の短い振動—心音が聴ける。最初の音がI音,次の音がII音である.I音は心臓収縮の開始を表わし,II音は収縮の終わりあるいは心臓の弛緩開始を示している.したがって,血行力学上I音からII音までが収縮期であり,II音から次のI音までが拡張期である.
寄生虫・原虫
寄生虫の検査(5)—免疫血清学的検査(1)
著者: 久津見晴彦
ページ範囲:P.481 - P.481
寄生虫免疫反応の特徴
寄生虫症の診断は糞便検査によって虫卵を検出する場合が多いが,寄生虫の種類によっては尿,喀痰,血液,組織について虫卵,仔虫,成虫を検査する.しかし,雄虫単独寄生や異所寄生,寄生虫が幼若・老化しているときなどはその寄生を証明することはできない.
寄生虫の免疫血清学的検査は,第1に上記のように寄生虫の存在を直接証明できない場合に有効であり,第2にある地区で寄生虫の蔓延を知ろうとする場合,検査対象となった多数の人員を,限られた時間に検査する際に簡便な方法として用いられる.後者の場合には,寄生虫抗原による皮内反応が広く用いられている.細菌性疾患やウイルス性疾患と比較すると,寄生虫症における免疫学的反応には次のようないくつかの特徴があげられる.
海外ニユース
Medical Laboratory Technicianの誕生—アメリカ
著者: 奥田稔
ページ範囲:P.483 - P.483
最近,検査技師の教育を将来いかにするべきかと題したシンポジウムがもたれ,各方面より多くの建設的意見が寄せられた.その際,米国における検査技師教育の現況について,改めて詳しい紹介および比較がなされている.
周知のように,米国の検査技師の主力は4年制の教育によるMedical Technologist(MT,ASCP)であり,わが国のそれとの相違が指摘されてきた.米国のMTははじめの3年間のカレッジ教育期間で必須課目である化学,生物学,数学(35semester hours)とオートメーション,コンピュータの普及に伴い選択課目として物理学,エレクトロニクスなどに重点のおかれた一般教養(55scmester hours)を修得する.最終学年ではaffiliateしたSchool of Medical Technologyで臨床検査を実習するのが,近年はこの期間もカリキュラムの編成などで,直接カレッジ側の指導を受けるようになり,卒業するとBachelor of Science(B. S.)の学位を取得する.
論壇
法改正をめぐる諸問題
著者: 田立耕蔵
ページ範囲:P.484 - P.485
"4本の柱"と厳しい現実
現在私たちが,その目的達成を目ざし全力を傾けている法改正運動は,1966年4月,大阪で開催された第15回日本衛生検査技師会総会で万場一致で承認され,それ以来いわゆる"4本の柱"としてとりまとめられるようになった,衛生検査技師法一部改正3か年計画に基づいているのであるが,当時その内容を説明するに当たって,提案者は"衛生検査技師法には多くの問題があり,そのためにわが国の衛生検査技師はいまだに不遇な毎日を送っている.われわれは過去7年間にも及んだ長期の法改正運動を総括し,その成果と実績を基礎として法律改正をわが掌中に収めよう"と出席者全員に呼びかけた.
全くその言のとおりであるというほかない.もともとこの法律は,日本衛生検査技術者会が,1952年7月18日に産ぶ声をあげたその日から数年にわたって続けられた,国会その他各方面への請願運動の一応の成果であったにもかかわらず,そのときすでに検査業務の範囲をめぐって,各医療関係諸団体の間でありありと浮き彫りされていた鋭い利害の対立をそのまま持ち越したかたちで,どうにか体裁だけをつくろった全くの妥協の産物にすぎなかったのである.だから,その実体がわれわれの念願とするところの真にあるべき姿からすれば,およそ遠くかけはなれたものであることは,法施行の当初から覚悟のうえであったし,さればこそ法改正運動は息つくひまもなく開始されたのであった.だが,その長期に及んだ運動の総括ともいうべき3か年計画の最終年度に当たる1969年も,ついに陽の目をみぬまま年を越してしまった.
パネルディスカッション
自治体病院検査科の機構と運営Ⅱ—第8回全国自治体病院臨床検査部会より
著者: 鳥海純 , 富田重良 , 志津功 , 岡治義彦 , 井上明弘 , 柴田進 , 諸橋芳夫 , 田中英 , 江波戸俊弥
ページ範囲:P.486 - P.494
座長(柴田)前号では,豊橋市民病院(愛知県),尼崎病院(兵庫県),芦屋病院(同)とご紹介いただきましたが,これからやっていただく加古川市民病院,加西市民病院は,われわれとして非常に悩ましい問題をかかえているクラスだと思います.
まず,加古川市民病院の岡治先生からお願います.
研究
アセチルアセトンを用いた血清トリグリセライド測定法の検討
著者: 山田満広
ページ範囲:P.498 - P.501
はじめに
血清中の脂質はトリグリセライド,コレステロール,リン脂質,遊離脂肪酸および脂溶性ビタミン,カロチンなど微量の脂溶性物質からなっている.糖尿病,動脈硬化症,心筋硬塞,ネフローゼ症候群,甲状腺機能低下症,あるいは本態性高脂血症などでは,血清中のトリグリセライド値の変動が疾患の症状をよく反映するといわれている.したがって,トリグリセライドの測定は前記疾患の診断,治療経過の判定ならびに病態の解明に,重要な臨床化学検査であるといわれている.
ところが,臨床的には測定法の容易なコレステロールは比較的よく測られているが,トリグリセライドは測定方法がかなりめんどうであり,バラツキが大きく,また測定操作に長時間を要するため,日常臨床検査に取り入れにくといわれていた.しかし,最近注目されているアセチルアセトンを用いた測定法は,きわめて短時間内にトリグリセライド値が得られることから,私はこのアセチルアセトン発色法を応用したトリグリセライドテスト(和光純薬)について,若干の検討を加えたのでここに報告する.
血清グルタミン酸脱水素酵素
著者: 遠藤了一 , 石塚昭信 , 鈴木秀治 , 森本示子 , 石岡瑞枝 , 有田聖子 , 佐藤源一郎 , 上野幸久
ページ範囲:P.502 - P.504
はじめに
このところ,血清酵素群の測定がひろく行なわれ,疾患の診断と経過の観察に役だっている.肝疾患では木下らによってグルタミン酸脱水素酵素(GLDH)の生体内分布,細胞ではミトコンドリア限局性であることをSchneider1)が明らかにした.このため正常血清中には活性が認められないことをHess2),Schmidt3)が確かめている.GLDHは肝,腎に高濃度に分布し,他の臓器ではきわめて活性が低い.ここで肝,腎障害時にGLDHの血中移行が考えられるが,ミトコンドリア膜,細胞膜を通過するためには高度の細胞壊死を伴うことが推察される.原形質に分布する酵素と異なり病態推移,細胞壊死と直接関係することが考えられる.
血色素測定試薬ヘモキットNの使用経験
著者: 黒川一郎 , 田中系子 , 鈴木五穂 , 木村寿之 , 永井竜夫
ページ範囲:P.505 - P.506
はじめに
シァンメトヘモグロビン法による血色素測定試薬は,他検査試薬の傾向を同じくし,しだいにキット化される趨勢にあるといえる.血色素測定方法は近来国際委員会の方針として,Van Kampen法1)に依拠してすすめられてきており,この点に問題はないが,Weather burnら2)の検討でも従来のDrabkin試薬を含めてかなり製品間に質的な差異があり,製品個々の吟味が必要と思われる.今回日本商事製ヘモキットNを検討する機会を得たので,現在までの成績を報告する.
感受性ディスク法に関する実験的検討
著者: 吉沢一太
ページ範囲:P.507 - P.510
まえがき
感染症の診療に際し化学療法剤の選択,臨床効果の予測を行なう場合,分離菌の感受性検査が重要となる.感受性検査法には稀釈法とディスク法があるが,簡易と迅速を目的とした感受性ディスク法は,臨床検査にとって欠かすことのできない検査の1つとなっている.
しかし,ディスク法はあくまで簡易を主体としているので,すでに多くの報告があるが1-6),なお実施面において問題となる点が数多く存在している.今回,著者は検査室の立場で,これらの問題点について検討し,一応の結果が得られたので報告する.
質疑応答
ヘマトクリット測定用プラスチック製の毛細管とガラス製毛細管との比較
著者: G生 , 寺田秀夫
ページ範囲:P.511 - P.511
問 ヘマトクリット測定用の毛細管にはガラス製,プラスチック製が現在市販されていますが,特にプラスチック製のものは遠心中に熱が加わり,多少の膨脹があるかと思うのですが.また,弾力性があるためにちょっとした刺激で管内に気泡がはいりやすいと思うのですが.いろいろの角度から見て比較したものをお教えください.
基本情報
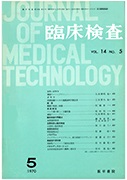
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
