リンパ性組織は免疫系組織として個体の防衛機構を担う組織で,中枢リンパ組織である胸腺と末梢リンパ組織であるリンパ節,脾臓,腸管付属のリンパ小節,扁桃から成る.後者は,胸腺由来の抗原認識能力を持つT-cellと骨髄由来で抗体産生能力を持つB-cellから成る.皮下リンパ節は外皮からの,脾臓は血管経由の,腸管リンパ小節およびそれに付属するリンパ節は腸管内皮からの,扁桃は口腔領域からの感染などの刺激に対して主として反応する.(広川)
骨髄組織診断は骨髄像を全体的に把握できる大きな特徴を有しているが,最近,臨床的に骨髄穿刺をした際,病理組織診断が要求される傾向にある.通常,3〜4μのパラフィン切片を作製し,H・E染色を普通染色とし,ギムザ,PAS,鍍銀,鉄染色などの特殊染色を行う.正常骨髄の基準は実質(造血細胞集団)/脂肪=1:1(面積比),赤芽球/顆粒球=1:3(数比),巨核球数が1mm2当たり7〜16個である.正常骨髄を見る機会は少ないので病的骨髄と対比してその一部を供覧する.(丹下)
雑誌目次
臨床検査19巻10号
1975年10月発行
雑誌目次
カラーグラフ
リンパ性組織と骨髄—正常組織像・1
著者: 広川勝昱 , 丹下剛
ページ範囲:P.1034 - P.1035
技術解説
IgE抗体の測定法
著者: 森田寛 , 宮本昭正
ページ範囲:P.1037 - P.1045
気管支喘息,アレルギー性鼻炎などアレルギー性疾患の原因となるレアギン(IgE抗体)は,これまで,皮膚反応,P-K反応,ヒスタミン遊離反応など,種々の方法で検出されてきたが,近年,WideらによりradioimmunoassayによるIgE抗体の半定量法であるradioallergosorbe-nt test(RAST)が開発され,その簡便性,一度に多くの検体を扱える点,皮膚反応,P-K反応にみられる副作用の心配がない点などから徐々に普及しつつある.その原理は図1に示してあるが,それを簡単に述べると次のようなものである.まずsolid phaseに抗原を結合させ,この抗原とIgE抗体を反応させる.IgEに対する抗体(抗IgE)を125Iでラベルしておき,この抗IgE-125Iを抗原と結合したIgE抗体と結合させ,その放射能をカウントし,その値と標準血清で得られた標準曲線からその抗体を定量する.抗原を結合させるsolid phaseとしてsepha-dex,microcrystalline,sepharose 4B,paperdisc,ポリスチレンチューブなどが用いられているが,paper discを用いた方法が最も簡単で広く行われているので,本稿ではpaper discを用いたRASTの手技について解説する.
真菌症の検査法—直接鏡検とガラス板培養法
著者: 金子修 , 高橋久
ページ範囲:P.1046 - P.1052
真菌検査では,まず臨床症状または病的状態によって真菌症ではないかと疑って初めて真菌検査へと進める.最も簡単な検査方法は水酸化カリウム標本による直接検査である.更に,菌の培養を行い,最後に菌の同定へと進む.したがって,今回は真菌検査法中最も基本的な直接検鏡所見と培養法について,現在行われている方法を紹介するとともに,検査手技上の注意すべき諸点を加えて説明する.
総説
個人の正常値—自動化健診のデータから
著者: 松岡研
ページ範囲:P.1053 - P.1060
現在,我々の日常の診療においては,生化学検査や血液検査などから得られる数値を,正常か異常かと判断するのに,いわゆる"正常値"なる物差しで行っており,それに基づいてデータ解析や,評価,指導および診断推理プランなどを立てているのが通例であり,いまや"正常値"という言葉は日常検査の中では慣用語となっている.今まで,この"正常値"の設定に関しては数多くの先人たちの努力がなされているが,今なお幾多の問題をかかえている.
すなおち,現在用いられている"正常値"は,その検査に関連ある疾患を除いたものを母集団として,それから数理統計学的手法によって算出されたものであり,集団を対象としたもので,この中には性,年齢,職業,地域,生活環境や,その他の変動因子すべてが埋蔵されたままである.
ひろば
診断名"再生不良性貧血"速急に骨髄穿刺を施行されたし!
著者: 近藤友一
ページ範囲:P.1060 - P.1060
穏やかな日に,それは起こった.血液検査をやっている女性が私の所へ来て,いくらやりなおしても白血球が2,000しかありませんと言った一言が,私を3日間頭脳と身体を奔走させることになった.まず血液を見て貧血があることがすぐに分かった.白血球を測ったら2,100であった(自動血球計数器).次にチュルク液を吸って顕微鏡で見た.3回繰り返したら2,100, 2,300, 1,900の数値が得られた.同じことを2人にやってもらった.結果は同じで,白血球減少は間違いないと確信した.次に血液像を調べて気づいたことは,リンパ球が多かった(百分率)ということだ.非白血性白血病を疑ったが,それらしき細胞は,全く見つからなかった.いやまてよ,リンパ球が増えてるのではなく好中球が減っているのではないのか.私はこの事態を徹底的に究明しようという気になった.
翌日,早速患者のカルテを引っぱり出した.いろいろなことが判明した.患者は2か月前に冠不全と低色素性貧血の疑いで入院していた.この間に血液検査を定期的に行い,輸血を繰り返してやっている.外来初診の時,貧血が著しく(W 5,100, Hb5.5g/dl,R 157万,Ht 16%)3日後に入院して直ちに輸血を行うも,4,5日後には再び貧血の状態へ戻る,これらのことを何度も繰り返し今日に至った.
臨床化学分析談話会より・26<関東支部>
一断面から連続性の解析へ—ALP,LAP,γ-GTPはすべて必要であった
著者: 菅野剛史
ページ範囲:P.1061 - P.1061
第183回分析談話会関東支部例会(1975. 6. 17)は東大薬学の記念講堂にて開催された.今回は"なぜいけないか,本当によいか"のシリーズ(2)であり,"ALP,LAP,γ-GTPの3検査は必要か"というテーマで,慶応大学中検の竹下栄子さんと慈恵医大第1内科の藤沢洌先生から話題提供がなされた.
初めに測定法に関して竹下さんの話題は,ALP,LAP,γ-GTPもすべて初速度解析による測定が可能であることを述べ,従来のone point測定の問題点を要領よくまとめていった.
症例を中心とした検査データ検討会・5
タンパク尿および糖尿を呈した症例—尿タンパクと血清タンパク分画の関係について
著者: 三浦きみ子 , 田口和枝 , 元沢陽子 , 森吉陽子 , 中野栄二 , 土屋俊夫
ページ範囲:P.1062 - P.1065
司会(中野)本日の症例は66歳,男性です.尿一般検査からお願いします.
異常値・異常反応の出た時・34
赤沈の速い時,遅い時
著者: 鈴木弘文
ページ範囲:P.1066 - P.1070
赤沈(赤血球沈降速度)検査は周知のごとく,一定時間内における赤血球層の沈降距離を赤沈管にて測定する方法であり,測定手技が容易,装置も極めて簡単であるなどの点から,血液検査室とは限らず外来診察室やナースセンターなどにおいても容易に実施することができる検査法である.しかし,測定手技や装置が簡易であるがために種種の因子,条件によって測定値が左右されやすい検査法ともいえる.したがって赤沈検査に際しては,簡単な検査であるからといって決して安易な態度で望むべきではなく,常に正しい検査が実施できるように細心の注意と慎重な態度が必要である.また,いかなる検査を行う場合でも必要なことであるが,その検査の意義あるいは異常値の意味するものなどについての十分な知識を有することがその検査を正しく実施することに結びついてくる.本論文は赤沈検査にて異常値と遭遇した場合に何を考えるかを述べるわけであるが,まず若干の基礎的問題について述べることとする.
私のくふう
多目的冷却式電気泳動槽
著者: 竹村修
ページ範囲:P.1071 - P.1071
諸物価高騰の昨今,各種廃品の再利用が見直されている.私たちの検査室の廃品,プラスチックの試薬空箱を利用して,今では日常検査に欠くことのできなくなった冷却式電気泳動槽を試作した.
ハンディーな髄液検査セット
著者: 長谷栄
ページ範囲:P.1099 - P.1099
日常の髄液検査の時,ピペット立てを利用して作ってみた,緊急時に一度に能率よく行える.持ち運び簡単でどこでも行え,場所をとらない.
尿中HCGの迅速半定量
著者: 荒木康乃
ページ範囲:P.1107 - P.1107
妊娠診断試薬であるゴナビスとゴナビスライド(持田)を用いて迅速にHCGの半定量することを試みた.ゴナビスの試薬は玉田1)の方法によりHCG半定量できる.定量値から我々2)は切迫流産予後判定の基準をもうけている.しかしゴナビスの結果は2時間を要すので,時間を短縮するため希釈尿をゴナビスライドで判定してみた.
中検へ一言・中検から一言
他部門との連繋を密に,他
著者: 伊藤久雄
ページ範囲:P.1072 - P.1073
最近,オートアナライザーなどの多種目自動化学分析装置が導入され,患者の検査成績が早急に報告されるようになったことは,我々臨床医にとって最も喜ばしい点であるが,ときに異常な高値や低値の検査成績が報告され,患者の病像と照らし合わせてその解釈に苦しむことも少なくない.我々にとって検査成績は早急であることも必要であるが,正確であることが最も重要なことである.先日,我々の病院で臨床医,臨床病理医,中検技師,看護婦の代表が集まって,中検の将来像,中検と他部門との連繋,自動化学分析装置の正確度を含めた精度管理などにつき語り合ったが,各部門にそれぞれ反省すべき点が少なくないように思われる.我々臨床医の反省すべき点をあげれば,最近の一部の臨床医は,自ら血液塗抹標本1枚すら観察したことがなく,更には重要なふん便や尿などの肉眼的な観察すら怠って,検査方法の過程や数値の意義を完全に理解せずに,検査依頼用紙の検査項目をやたらに記入すればそれでこと足りたと感違いし,検査成績を受け取ってそれをそのままうのみにして省みないという傾向もなきにしもあらずである.また中検技師の中にも,検体を分析装置にかけて得た成績をそのまま機械的に検査成績表に書き込んで臨床医に報告し,特別な異常値の再検や担当医への直接の連絡などがときとして欠けていることがある.
座談会
血清学的検査のエラーチェック
著者: 中嶋八良 , 浅川英男 , 佐藤乙一 , 松橋直
ページ範囲:P.1074 - P.1081
臨床検査におけるエラーは,技術的なものと事務的なものとに大別される.患者にとっては双方とも絶対に許せないものである.血液型,梅毒血清反応,ASOなど日常的な血清学的検査を取り上げ,その双方のエラーをどうチェックしたらよいか,日ごろの体験のなかから検討していただく.
研究
キナーゼテストの細分判定法
著者: 斎藤功 , 井上馨 , 横山桂子 , 長谷川妙子 , 橘文紀
ページ範囲:P.1082 - P.1084
緒言
溶連菌感染症の血清学的診断法としてASO価測定が広く行われているが,本反応単独では本症の診断は不確実であり,その他の本菌体外産物抗体を併用測定することが望まれる1).
なかんずく抗ストレプトキナーゼ(ASK)の測定が,近年簡単に行えるようになった.すなわち,患者血清にホルマリン,タンニン酸処理のヒツジ赤血球にストレプトキナーゼ吸着の抗原を作用し,間接的に赤血球凝集反応よりASKを測定するものである.
部分トロンボプラスチン時間の検討—第2報
著者: 塚田はつ江 , 松尾典子 , 鹿沼克江 , 小林紀夫 , 新井仁
ページ範囲:P.1085 - P.1088
緒言
血液凝固障害のスクリーニングテストとしての部分トロンボプラスチン時間(PTT)特に活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)について,方法の規準化のための基礎的検討とプロトロンビン消費試験との関係を第1報(本誌1975年9月号)において報告した.本稿ではⅧ因子,Ⅸ因子減少に対するAPTTの感度と,各種市販のAPTT試薬および一部自製したAPTT試薬を用いて測定値の相互比較性を検討したので報告する.
アスピリンエステラーゼについて
著者: 西川美年子 , 加納順子 , 高山みち子 , 林英夫
ページ範囲:P.1089 - P.1092
はじめに
今日までに開発され,測定されてきた多種類の肝機能検査法は,大別しておよそ3種に分類されうる.①肝実質細胞の傷害,変性などを表現するもの.例えば,GOT, GPT, LDHなどのいわゆる逸脱酵素の測定.②肝間質の線維化などの変化を表現するもの.例えば,硫酸亜鉛混濁試験(ZTT),チモール混濁試験,コバルト反応などの膠質反応の測定.③肝実質細胞の本来の機能の解毒,タンパク合成などを表現するもの.例えば,BSPとICG排泄試験,アセチルコリンエステラーゼ測定など.
肝の各種代謝活動を反映する検査法は,今日まで多数開発された肝機能検査法の中では比較的手法の乏しい領域であったと言えよう.1943年,Vandelliらは,モルモットの肝および腎組織がアスピリンを急速に分解する現象が酵素的過程によるものであることを立証し,1950年,Vincentらは,この酵素をアスピリンエステラーゼ(Asp-E)と名付けた.Asp-Eは,心,腎にも存在するが肝に圧倒的に多く,肝細胞のミトコンドリアに主として存在するといわれている.
酵素法による血清総コレステロール測定の自動化について
著者: 山崎忠夫 , 石田優美子 , 永井忠 , 春日宏元 , 鈴木良子 , 星野辰雄
ページ範囲:P.1093 - P.1096
はじめに
血清総コレステロール測定は従来主として強酸性条件下に反応させるのが常であったが,そのため分析装置の損傷と測定者の危険性が伴うのが欠点とされていた.
今回"デタミナーTC"を入手し,酵素法による血清総コレステロール測定の検討を進め,これをテクニコンAAⅠ型自動分析装置に適用を試みたが,試薬を大量に必要とするため,1検体当たりのコストが非常に高価なものになり日常検査に不適当と思われる.そこでAAⅠ型による希釈法を採用考案し,試薬量を用手法に比して約半量になるようにセッティングダイアグラムを作成した結果,良好な成績を得た概要について報告する.
新しいキットの紹介
免疫拡散板による血清Gcグロブリン測定法の検討
著者: 宮谷勝明 , 高畑譲二 , 福井巌 , 金田吉郎
ページ範囲:P.1097 - P.1099
緒言
α2グロブリン分画に属しているGcグロブリンは,Hirschfeld1)によって見い出された種族特異性を示すタンパクであるが,生物学的意義については,まだ,明らかにされていない.
一般に,Gcグロブリンを測定するには,免疫電気泳動法やデンプンゲル電気泳動法2)などの他に,一元平板免疫拡散法3)があげられるが,著者らは,最近,Behri-ngwerkeによって開発されたM・パルチゲンGcグロブリンを用いて行う場合の測定条件について検討を加えるとともに,併せてこの拡散板を用いて健常成人男女(男子30例,女子30例,計60例)の値をも測定したので,その成績を報告する.
新しい機器の紹介
カルシウムアナライザーによるカルシウムの検討
著者: 滝沢秀晃 , 小松正孝
ページ範囲:P.1100 - P.1103
はじめに
血清中のカルシウムの測定法として最も古い方法としてはシュウ酸沈殿過マンガン酸カリウム滴定法,Nuclear Fast Reed(NFR)のアルカリ性溶液に試料を添加して色素の一部をカルシウムと結合させ紫青色の錯化合物を作る比色法,以来いく種類かの分析法が知られているが,現在日常の検査法として広く用いられているのは,o—クソゾールフタレンコンプレクソン(OCPC)法であろう.
近年生化学検査の自動化が進むにつれ特に検体の多い施設ではその傾向が著しく,それに伴って自動分析機器の発達によりカルシウムの測定も自動化が普及されてきている.しかし自動分析機器は高価な点からも検体数の非常に多い特定の大施設でしか利用されないし,また,カルシウム分析という特殊な検査だけあって,中小病院がカルシウムの自動化に踏み切るにはまだまだ先のことと考えられる.私たちは数年前から緊急検査に,また日常の生化学検査に適した正確でしかも迅速に測定できるカルシウムの自動滴定測定機に興味を持ち,米国コーニンググラス社製カルシウムアナライザー,米国フィスケ社製カルシウムタイトレータ,国産平沼産業KK開発中のCa測定機器について使用経験を得た.ここではコーニング社製カルシウムアナライザーを中心として我々の使用経験に基づき説明することにした.
ユノペットによる血小板算定法の検討
著者: 永山正剛 , 真木正博 , 千葉敦子 , 沢尻恵美子 , 品川信良
ページ範囲:P.1104 - P.1107
はじめに
血小板算定法には間接法であるFonio法や直接法であるBrecher-Cronkite法,Rees-Ecker法などが標準的なものとして従来から行われてきている.現在では更にautocounterによる算定を行っている所も多数みられるようになった.ところで従来の間接法では塗抹部位による血小板分布の違いや,直接法では繁雑な操作と標本保存のうえでの難点などがあり,なかなか安定した値を得にくく,かなりの習熟を要するという悩みをもっている.またautocounterは大病院やセンター的な所には適していてもまだ一般病医院での検査法として普及するには至っていない.また,病的巨大血小板や凝集血小板などは算定されないといった問題点もある.
このたび,私たちは希釈用ディスポーザブルピペットであるUnopette (ユノペット)を用いてBrecher-Cronkite法により血小板計数を行い,もう一つの直接法であるRees-Ecker法と比較し,正確さ,簡便性,安定性などについて検討したところ,より優れた成績を得ることができたので報告する.
セントリフィケム・システムによる血清酵素活性の測定
著者: 成田多喜子 , 徳永賢治 , 永島昇 , 伊藤宜則 , 牧野秀夫
ページ範囲:P.1109 - P.1113
緒言
自動分析機の一つであるセントリフィケムは,米国NIHで開発されたバッチパラレル方式の測定機である.この分析機は微量の試料と試薬を用いて迅速に測定することができ,既に血清中の各成分の分析に利用されている3〜10).
ここでは血清中の酵素,すなわちGOT,GPT,ALP,LAP,LDH,γ-GTP活性の測定に関して,この分析機によった場合の精度,他の測定法との比較および正常値などの検討成績を報告する.
質疑応答
ツェンカー液の使い分け
著者: Y生 , 梶田昭
ページ範囲:P.1108 - P.1108
問 血液疾患などの骨髄標本ではしばしばツェンカー固定液を使用しますが大脳や小脳などには使用しませんが,それぞれの理由をお教えください.
日常検査の基礎技術
電気生理検査機器の漏れ電流測定
著者: 竹村靖彦 , 山口映
ページ範囲:P.1117 - P.1124
医療技術が高度になるにつれ,人体に医療用電気機器が接触する機会が増え,それだけ不測の電撃事故が発生する確率も増してきていることは否定できない.医用電気機器の安全は,漏れ電流の発生を少なくすることにつきるが,それは,機器それ自体の安全,使用環境(設備も含む)の安全,運用方法による安全確保と,3条件がバランスを保っていなくてはならない.この,どの問題を取り上げても,実は,容易に結論を出すことが難しい多くの問題を含んでおり,そのためにこそ,ME学会,IECや工業会など諸関係機関が現在各種の研究調査を行い,報告書を出すという活動をしている.ここでは,少なくとも日常検査の場で,機器の異常を発見する最少の方法としての,生理検査機器の漏れ電流測定方法を紹介するが,アース設備が完全か,電源設備が完全か,目的的に安全確保という点で最適の機器が使用されているかという問題もあることを忘れずにおかれたい.この問題については,他の機会に譲りたい.
検査と主要疾患・34
気管支炎
著者: 深谷一太
ページ範囲:P.1126 - P.1127
呼吸器系は鼻腔から始まって咽頭・喉頭・気管を経て気管支に至り,更に細気管支となり肺胞を形成して体系を作っており,血液のガス交換を営み,生命の維持に不可欠の役割を果たしている.
図1に気管支付近の模式図を示す.右気管支は正中線と約24°,左は約46°の角度をなして分岐し,右は左に比し太く短い.肺内にて肺葉に一致して3本に分岐する.左は2本に分かれる.気管から連続して軟骨壁を有し,組織学的には粘膜・粘膜下組織・外膜の3層に分かれる.粘膜下に気管支腺が存在し粘液分泌を行う.
検査機器のメカニズム・46
心除細動器
著者: 古屋一雄
ページ範囲:P.1128 - P.1129
最近のICU, CCUの普及や,手術室や心臓カテーテル検査室などの設備の近代化に伴い,心臓に高電圧を印加し,心室細動および心房細動を除去する除細動器を,頻繁に使用するようになってきた.本文では,迅速かつ適切に処理すべき除細動器使用に関し,その基本的な仕組と,電気的な取り扱いについて述べる.
検査室の用語事典
臨床化学検査
著者: 坂岸良克
ページ範囲:P.1131 - P.1131
73) Lohmann reaction;ローマン反応
Lohmannによって1934年に発見された反応で,中性付近ではATP生成に傾く可逆反応である.
クレアチン・リン酸+ADP CPK⇔クレアチン+ATP
病理学的検査
著者: 若狭治毅
ページ範囲:P.1132 - P.1132
89) Plasma cell;形質細胞
この細胞は形態的には偏心性の核を有し,胞体が好塩基性を呈し,超微構造ではGolgi装置と粗面小胞体(r.E.R.)がよく発達している.これが体液性免疫に関係することはよく知られており,メチルグリーン・ピロニン染色で胞体は赤染する.
学会印象記 第9回国際臨床化学会議
臨床化学の新たな指向—診断から治療へ
著者: 加野象次郎
ページ範囲:P.1133 - P.1133
第9回国際臨床化学会議(9th International Congresson Clinical Chemistry)は,7月13日から18日までカナダのトロントで開催された.カナダはインスリンの発見者BantingとBestを生んだ国であるが,現在もIUPAC(International Union of Pure and AppliedChemistry)で活躍しているTonksの名や,雑誌Cli-nical Biochemistryで知られるように,臨床化学の面でも国際的に大きな役割を果たしていることは,改めてふれるまでもない.
さて,会議は開催国のカナダおよび隣接の米国を中心とし世界各国から2,500名を越える参加者を得て,教育講演3,シンポジウム12(計50演題),そして481にのぼる一般演題と,まさに盛大そのものであった.日本からも,20余名の参加者があり,16演題が発表された.
Senior Course 生化学
—酵素の初速度測定—LAP
著者: 大場操児
ページ範囲:P.1134 - P.1135
LAPは常用名leucine amino peptidaseといい,系統名はL-leucyl-peptidase hydrolase,コード番号3.4.1.1に分類される酵素である.
タンパク分解酵素には,タンパク質またはペプチド鎖の中央部を切断するendopeptidaseと,タンパク質,ペプチド鎖のアミノ酸を遊離するexopeptidaseに大別されている.
血液
—検査室からみた血液疾患の特徴—骨髄腫とマクログロブリン血症
著者: 松原高賢
ページ範囲:P.1136 - P.1137
骨髄腫とは形質細胞が,マクログロブリン血症とは類リンパ球が単クローン性に悪性腫瘍化した状態であると定義できる.臨床症状および検査所見は腫瘍という形態学的病変と,腫瘍細胞の生産するタンパクに由来する化学的病変とに大きく分けることができる.後者については両疾患は類似しているので一括して述べる.
血清
—最新の免疫学的検査法—免疫不全症候群Ⅳ—分類,臨床
著者: 冨永喜久男
ページ範囲:P.1138 - P.1139
第1次および第2次分類
本項の初め(I.基礎,7月号)に原発性免疫不全症候群の分類について予備的に紹介した.Seligmanらの考えに発するこの分類は,免疫機構を体液性,細胞性に分けて眺めることを基本とし,合わせて遺伝的基盤をも深く考慮する立場をとったことで,それまでの多数の分類法に比し格段に大きい意義があった.事実,WHOの専門委員会もこの分類法を承認,採用した(1968年,仮に第1次分類と呼ぶ).著者はこの分類を紹介する際,(4)非伴性遺伝性原発性Ig欠乏症(発病と病像が種々異なる)から独立疾患が出てきていると述べたが,具体的には下の症候群である(1971年).
A.高IgM血症を伴う伴性免疫不全症
細菌
—病原性球菌の分離,同定—りん菌,髄膜炎菌の分離,同定法
著者: 横田万之助
ページ範囲:P.1140 - P.1141
表題の2菌と肺炎双球菌(Diplococcus pneumoniae)とは,形態上からは,いずれもいわゆる"双球菌"であり,発症時には,その原寄生場所から血流中に侵入して"菌血症(Septicemia)"を起こしてくることに注意を要する.
この,菌血症を起こしてくることは,これら3菌の特性で,それらの臨床病態を規制している—すなわち,りん菌は関節炎,心内膜炎,髄膜炎あるいは遠く離れた皮膚に壊疽性の炎症などを起こしてくるし,髄膜炎菌もロゼオーラ(ばら疹)様の皮疹を生じ,あるいは慢性敗血症となり(この時には,髄膜炎症状を呈しない),更には激烈なWaterhous-Friedrichsen症候群のごとき例すらも出てくるし,普通の髄膜炎型でも関節炎を起こしうる(殊に,剖検例では,ほとんどの症例にみられる).肺炎双球菌の肺炎の場合でも,病初には全例に菌血症を起こしてくるし(自験),化膿性髄膜炎は決して少なくはないし,まれには心内膜炎すらも起こしてくる.一方,髄膜炎菌による"原発性肺炎"も少なくない.
病理
—新しい病理組織標本の作り方—染色 Ⅳ
著者: 平山章
ページ範囲:P.1142 - P.1143
固定液による核染色性の低下に対する処理法
普通のルーチンの材料を固定する問題は固定時間も守られており問題はないが,非緩衝ホルマリンに長期間固定したものや,ツェンカー,ブアン液や脱灰液に長時間固定あるいは脱灰しすぎた場合,核の染色性が低下しきれいな標本を作れないことが多い.このような場合核の染色性を回復するには次のような方法を用いると良い.
生理
心機図検査
著者: 高橋文行
ページ範囲:P.1144 - P.1145
心機図という言葉は,本来,心臓の電気現象である心電図に対応して,機械的現象を表現するために用いられたものである.しかしこの言葉の使用に関しては人により多少の違いがある.広義には心音図をはじめ,心尖拍動波(以下ACG),頸動脈波,頸静脈波,心臓超音波検査,バリストカルディオグラムなど,循環器系に関するすべての記録が含まれるが,狭義には心,大血管に起因する可聴域以下の低周波振動の記録であると解釈される1).すなわち,胸壁からのエネルギーを電気的に変換し,これを曲線として記録する心尖拍動波,大動脈波,キネトカルディオグラムなどを示すことになる.また,心電図,心音図を同時記録し,これと対比することにより,なるべく多くの情報を得ようとするものであり,繰り返して行える非観血的検査法として循環器疾患の診断に不可欠なものである.
一般検査
心包液
著者: 高橋早苗
ページ範囲:P.1146 - P.1147
心包液は心外膜(Epicardium)と心包(pericardium)とで形成される腔に貯留する液体で,正常人では20〜60ml存在している.心包液に関する報告はほとんどが心包炎の液に関するもので,正常心包液の報告は少ない.心包液は血漿に由来し1.7〜3.5g/dlのタンパクを含有し,血管支配は内胸動脈の分枝である心嚢枝である.心嚢腔の圧は場所により異なり(心房の部分と心室の部分では異なる)また心臓の収縮周期によっても異なる.
心包液が貯留する疾患として,リウマチ熱,結核,尿毒症,細菌感染,ウイルス,fungal感染,外傷,関節リウマチ,SLE,強皮症などの膠原病,心筋硬塞後症候群,心膜切開後症候群,ワクチンに対するアレルギーなどによる心包炎,また心不全,低タンパク血症でも漏出液が貯留する.解離性大動脈瘤の心嚢内破裂,心筋硬塞の心室穿孔,心臓ペースメーカーの穿孔,外傷による心破裂などでは心包に血液が貯留する.しかし種々の検査を行っても原因のつかめない非特異性心包炎が大部分を占める.そのため心包炎の原因の検索は他の臨床症状,検査成績を十分検討すべきであるが,他方コレステロール心包炎,カイロペリカルデュウムなど心包液の検査が重要な診断根拠になるものもある.
基本情報
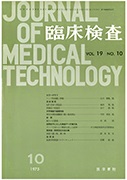
バックナンバー
68巻12号(2024年12月発行)
今月の特集2 日常診療に潜む再興感染症
68巻11号(2024年11月発行)
今月の特集2 中毒への対応
68巻10号(2024年10月発行)
増大号 心電図判読のスタンダード 基本を極めて臨床で活かす!
68巻9号(2024年9月発行)
今月の特集 知っておきたい睡眠時無呼吸症候群
68巻8号(2024年8月発行)
今月の特集 超音波検査士に必要な医用超音波の基礎
68巻7号(2024年7月発行)
今月の特集 骨髄腫と類縁疾患の検査学
68巻6号(2024年6月発行)
今月の特集 免疫・アレルギー性肺疾患と検査
68巻5号(2024年5月発行)
今月の特集 肥満と健康障害
68巻4号(2024年4月発行)
増大号 AKI・CKDの診断・治療に臨床検査を活かせ
68巻3号(2024年3月発行)
今月の特集 こどもと臨床検査
68巻2号(2024年2月発行)
今月の特集2 人工物感染症
68巻1号(2024年1月発行)
今月の特集2 補体をめぐる話題
67巻12号(2023年12月発行)
今月の特集 中枢神経系感染症アップデート
67巻11号(2023年11月発行)
今月の特集 腫瘍随伴症候群
67巻10号(2023年10月発行)
増大号 肝疾患 臨床検査でどう迫る?
67巻9号(2023年9月発行)
今月の特集 COVID-19と臨床検査—得られた知見を今後の医療に活かす
67巻8号(2023年8月発行)
今月の特集2 神経・筋疾患の超音波検査
67巻7号(2023年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 第5版
67巻6号(2023年6月発行)
今月の特集 微生物検査と臨床推論
67巻5号(2023年5月発行)
今月の特集 脳脊髄液検査—その基礎と新しい展開
67巻4号(2023年4月発行)
増大号 チェックリストで見直す 検査と医療関連感染対策
67巻3号(2023年3月発行)
今月の特集2 臨床検査で患者を救え!—知っておいてほしい疾患
67巻2号(2023年2月発行)
今月の特集 検査機器・試薬の工夫—ぎりぎり教えて,メーカーさん
67巻1号(2023年1月発行)
今月の特集2 生殖医療への貢献
66巻12号(2022年12月発行)
今月の特集 クローン性造血に関する知見と課題
66巻11号(2022年11月発行)
今月の特集 マイクロバイオーム
66巻10号(2022年10月発行)
増大号 検査血液学レッスン 検査結果の乖離をどう判断するか
66巻9号(2022年9月発行)
今月の特集2 免疫学的機序による血小板減少
66巻8号(2022年8月発行)
今月の特集2 医療従事者のためのワクチン接種アップデート
66巻7号(2022年7月発行)
今月の特集 臨床検査技師によるタスク・シフト/シェア
66巻6号(2022年6月発行)
今月の特集2 良性腫瘍の病理と遺伝子異常
66巻5号(2022年5月発行)
今月の特集2 フローサイトメトリー
66巻4号(2022年4月発行)
増大号 計測する項目と記録断面がわかる! 病態別・類似疾患別心エコー検査のルーティン
66巻3号(2022年3月発行)
今月の特集 「心不全パンデミック」を迎え撃つ!
66巻2号(2022年2月発行)
今月の特集2 血液凝固を阻害するもの
66巻1号(2022年1月発行)
今月の特集 食中毒の現状と微生物検査
65巻12号(2021年12月発行)
今月の特集 移植医療と臨床検査
65巻11号(2021年11月発行)
今月の特集2 インフルエンザを再考する
65巻10号(2021年10月発行)
増刊号 なんだか気になる心電図
65巻9号(2021年9月発行)
今月の特集 スポーツを支える臨床検査
65巻8号(2021年8月発行)
今月の特集2 図解 電気生理学的心電図—忘れていませんか? その成因
65巻7号(2021年7月発行)
今月の特集 薬物療法に活用される検査
65巻6号(2021年6月発行)
今月の特集 典型例の臨床検査を学ぶ
65巻5号(2021年5月発行)
今月の特集 薬剤耐性(AMR)対策の現状と今後
65巻4号(2021年4月発行)
増刊号 よくある質問にパッと答えられる—見開き! 検査相談室
65巻3号(2021年3月発行)
今月の特集 臨地実習生を迎えるための手引き
65巻2号(2021年2月発行)
今月の特集2 ダニ媒介感染症—適切な理解と診断の道標
65巻1号(2021年1月発行)
今月の特集 対比して学ぶエコー所見で鑑別に悩む疾患
64巻12号(2020年12月発行)
今月の特集2 臨床検査とIoT
64巻11号(2020年11月発行)
今月の特集2 パニック値報告 私はこう考える
64巻10号(2020年10月発行)
増刊号 がんゲノム医療用語事典
64巻9号(2020年9月発行)
今月の特集2 どうする?精度管理
64巻8号(2020年8月発行)
今月の特集2 IgG4関連疾患の理解と検査からのアプローチ
64巻7号(2020年7月発行)
今月の特集2 薬剤耐性カンジダを考える
64巻6号(2020年6月発行)
今月の特集 超音波検査報告書の書き方—良い例,悪い例
64巻5号(2020年5月発行)
今月の特集2 EBLM(evidence based laboratory medicine)の新展開
64巻4号(2020年4月発行)
増刊号 これで万全!緊急を要するエコー所見
64巻3号(2020年3月発行)
今月の特集2 質量分析を利用した臨床検査
64巻2号(2020年2月発行)
今月の特集2 標準採血法アップデート
64巻1号(2020年1月発行)
今月の特集2 生理検査—この所見を見逃すな!
63巻12号(2019年12月発行)
今月の特集2 高血圧の臨床—生理検査を中心に
63巻11号(2019年11月発行)
今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
63巻10号(2019年10月発行)
増刊号 維持・継続まで見据えた—ISO15189取得サポートブック
63巻9号(2019年9月発行)
今月の特集2 現代の非結核性抗酸菌症
63巻8号(2019年8月発行)
今月の特集 知っておきたい がんゲノム医療用語集
63巻7号(2019年7月発行)
今月の特集2 COPDを知る
63巻6号(2019年6月発行)
今月の特集2 薬剤耐性菌のアウトブレイク対応—アナタが変える危機管理
63巻5号(2019年5月発行)
今月の特集2 症例から学ぶフローサイトメトリー検査の読み方
63巻4号(2019年4月発行)
増刊号 検査項目と異常値からみた—緊急・重要疾患レッドページ
63巻3号(2019年3月発行)
今月の特集 血管エコー検査 まれな症例は一度みると忘れない
63巻2号(2019年2月発行)
今月の特集2 災害現場で活かす臨床検査—大規模災害時の経験から
63巻1号(2019年1月発行)
今月の特集2 薬の効果・副作用と検査値
62巻12号(2018年12月発行)
今月の特集2 最近の輸血・細胞移植をめぐって
62巻11号(2018年11月発行)
今月の特集2 ACSを見逃さない!
62巻10号(2018年10月発行)
増刊号 感染症関連国際ガイドライン—近年のまとめ
62巻9号(2018年9月発行)
今月の特集2 知っておきたい遺伝性不整脈
62巻8号(2018年8月発行)
今月の特集 女性のライフステージと臨床検査
62巻7号(2018年7月発行)
今月の特集2 現場を変える!効果的な感染症検査報告
62巻6号(2018年6月発行)
今月の特集2 筋疾患に迫る
62巻5号(2018年5月発行)
今月の特集2 不妊・不育症医療の最前線
62巻4号(2018年4月発行)
増刊号 疾患・病態を理解する—尿沈渣レファレンスブック
62巻3号(2018年3月発行)
今月の特集2 成人先天性心疾患
62巻2号(2018年2月発行)
今月の特集2 実は増えている“梅毒”
62巻1号(2018年1月発行)
今月の特集2 心腎連関を理解する
61巻12号(2017年12月発行)
今月の特集2 新鮮血を用いた血算の外部精度管理
61巻11号(2017年11月発行)
今月の特集 母子感染の検査診断
61巻10号(2017年10月発行)
増刊号 呼吸機能検査 BASIC and PRACTICE
61巻9号(2017年9月発行)
今月の特集2 臨床検査技師のためのワクチン講座
61巻8号(2017年8月発行)
今月の特集2 リンパ球の増減を正しく評価するために
61巻7号(2017年7月発行)
今月の特集 造血器・リンパ系腫瘍のWHO分類 2016 version
61巻6号(2017年6月発行)
今月の特集2 膵臓の病気を見逃さない
61巻5号(2017年5月発行)
今月の特集 ISO 15189取得簡易マニュアル
61巻4号(2017年4月発行)
増刊号 臨床検査スターターズガイド
61巻3号(2017年3月発行)
今月の特集2 在宅現場でのPOCTへの期待
61巻2号(2017年2月発行)
今月の特集2 微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
61巻1号(2017年1月発行)
今月の特集2 Antimicrobial stewardship
60巻13号(2016年12月発行)
今月の特集2 がん分子標的治療にかかわる臨床検査・遺伝子検査
60巻12号(2016年11月発行)
今月の特集2 脂質検査の盲点
60巻11号(2016年10月発行)
増刊号 心電図が臨床につながる本。
60巻10号(2016年10月発行)
今月の特集2 感染症の迅速診断—POCTの可能性を探る
60巻9号(2016年9月発行)
今月の特集2 臨床検査領域における次世代データ解析—ビッグデータ解析を視野に入れて
60巻8号(2016年8月発行)
今月の特集2 キャリアデザイン
60巻7号(2016年7月発行)
今月の特集2 百日咳,いま知っておきたいこと
60巻6号(2016年6月発行)
今月の特集2 CKDの臨床検査と腎病理診断
60巻5号(2016年5月発行)
今月の特集2 感度を磨く—検査性能の追求
60巻4号(2016年4月発行)
今月の特集2 感染症診断に使われるバイオマーカー—その臨床的意義とは?
60巻3号(2016年3月発行)
今月の特集2 smartに実践する検体採取
60巻2号(2016年2月発行)
今月の特集2 実践に役立つ呼吸機能検査の測定手技
60巻1号(2016年1月発行)
今月の特集2 グローバル化時代の耐性菌感染症
59巻13号(2015年12月発行)
今月の特集2 検査室が育てる研修医
59巻12号(2015年11月発行)
今月の特集2 腹部超音波を極める
59巻11号(2015年10月発行)
増刊号 ひとりでも困らない! 検査当直イエローページ
59巻10号(2015年10月発行)
今月の特集2 MDS/MPNを知ろう
59巻9号(2015年9月発行)
今月の特集2 臨地実習で学生に何を与えることができるか
59巻8号(2015年8月発行)
今月の特集2 感染症サーベイランスの実際
59巻7号(2015年7月発行)
今月の特集2 血液細胞形態判読の極意
59巻6号(2015年6月発行)
今月の特集2 健診・人間ドックと臨床検査
59巻5号(2015年5月発行)
今月の特集2 乳癌病理診断の進歩
59巻4号(2015年4月発行)
今月の特集2 感染制御と連携—検査部門はどのようにかかわっていくべきか
59巻3号(2015年3月発行)
今月の特集2 夜勤で必要な輸血の知識
59巻2号(2015年2月発行)
今月の特集2 血算値判読の極意
59巻1号(2015年1月発行)
今月の特集2 新型インフルエンザへの対応—医療機関の新たな備え
58巻13号(2014年12月発行)
今月の特集2 とても怖い心臓病ACSの診断と治療
58巻12号(2014年11月発行)
今月の特集2 ブラックボックス化からの脱却—臨床検査の可視化
58巻11号(2014年10月発行)
増刊号 微生物検査 イエローページ
58巻10号(2014年10月発行)
今月の特集2 尿沈渣検査の新たな付加価値
58巻9号(2014年9月発行)
今月の特集2 てんかんと臨床検査のかかわり
58巻8号(2014年8月発行)
今月の特集2 血栓症時代の検査
58巻7号(2014年7月発行)
今月の特集2 夏に知っておきたい細菌性胃腸炎
58巻6号(2014年6月発行)
今月の特集2 生理機能検査からみえる糖尿病合併症
58巻5号(2014年5月発行)
今月の特集2 改めて,精度管理を考える
58巻4号(2014年4月発行)
今月の特集2 話題の感染症2014
58巻3号(2014年3月発行)
今月の特集2 知っておくべき睡眠呼吸障害のあれこれ
58巻2号(2014年2月発行)
今月の特集2 Ⅰ型アレルギーを究める
58巻1号(2014年1月発行)
今月の特集2 深在性真菌症を学ぶ
57巻13号(2013年12月発行)
今月の特集2 目でみる悪性リンパ腫の骨髄病変
57巻12号(2013年11月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査②
57巻11号(2013年10月発行)
特集 はじめよう,検査説明
57巻10号(2013年10月発行)
今月の特集2 Clostridium difficile感染症
57巻9号(2013年9月発行)
今月の特集2 日常検査から見える病態―生化学検査①
57巻8号(2013年8月発行)
今月の特集2 輸血関連副作用
57巻7号(2013年7月発行)
今月の特集2 感染症と発癌
57巻6号(2013年6月発行)
今月の特集2 連続モニタリング検査
57巻5号(2013年5月発行)
今月の特集2 ADAMTS13と臨床検査
57巻4号(2013年4月発行)
今月の特集2 非アルコール性脂肪性肝疾患
57巻3号(2013年3月発行)
今月の特集2 血管炎症候群
57巻2号(2013年2月発行)
今月の主題2 血液形態検査の標準化
57巻1号(2013年1月発行)
今月の主題2 ウイルス性胃腸炎
56巻13号(2012年12月発行)
今月の主題 アルコール依存症
56巻12号(2012年11月発行)
今月の主題 MDS(骨髄異形成症候群)
56巻11号(2012年10月発行)
特集 教科書には載っていない臨床検査Q&A
56巻10号(2012年10月発行)
今月の主題 鉄代謝のバイオマーカー
56巻9号(2012年9月発行)
今月の主題 間質性肺炎と臨床検査
56巻8号(2012年8月発行)
今月の主題 多剤耐性菌の検査と臨床
56巻7号(2012年7月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
56巻6号(2012年6月発行)
今月の主題 めまいの生理検査
56巻5号(2012年5月発行)
今月の主題 成長と臨床検査値
56巻4号(2012年4月発行)
今月の主題 感染症検査における境界値の取り扱い方
56巻3号(2012年3月発行)
今月の主題 尿路結石
56巻2号(2012年2月発行)
今月の主題 生理活性脂質
56巻1号(2012年1月発行)
今月の主題 認知症と臨床検査
55巻13号(2011年12月発行)
今月の主題 骨疾患
55巻12号(2011年11月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査【最終回】
55巻11号(2011年10月発行)
特集 ここまでわかった自己免疫疾患
55巻10号(2011年10月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・4
55巻9号(2011年9月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・3
55巻8号(2011年8月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・2
55巻7号(2011年7月発行)
緊急連載/東日本大震災と検査・1
55巻6号(2011年6月発行)
今月の主題 脂肪細胞
55巻5号(2011年5月発行)
今月の主題 癌幹細胞と検査医学
55巻4号(2011年4月発行)
今月の主題 静脈血栓塞栓症と凝固制御因子プロテインS
55巻3号(2011年3月発行)
今月の主題 更年期医療
55巻2号(2011年2月発行)
今月の主題 腸内細菌叢
55巻1号(2011年1月発行)
-ミクログロブリン-その多様な病因,病態と検査アプローチ
54巻13号(2010年12月発行)
今月の主題 遺伝子検査の最近の展開-ヒトゲノム多様性と医療応用
54巻12号(2010年11月発行)
今月の主題 脳卒中
54巻11号(2010年10月発行)
特集 新時代のワクチン戦略について考える
54巻10号(2010年10月発行)
今月の主題 ファーマコゲノミクス
54巻9号(2010年9月発行)
今月の主題 糖尿病の病態解析
54巻8号(2010年8月発行)
今月の主題 未病を考える
54巻7号(2010年7月発行)
今月の主題 排尿障害
54巻6号(2010年6月発行)
今月の主題 注目されるサイトカイン
54巻5号(2010年5月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌制御の最前線
54巻4号(2010年4月発行)
今月の主題 広義のアポリポ蛋白
54巻3号(2010年3月発行)
今月の主題 骨髄増殖性疾患
54巻2号(2010年2月発行)
の診断と臨床応用
54巻1号(2010年1月発行)
今月の主題 POCT,医療におけるその役割
53巻13号(2009年12月発行)
今月の主題 前立腺癌
53巻12号(2009年11月発行)
今月の主題 オートファジー
53巻11号(2009年10月発行)
特集 医療・福祉施設における感染制御と臨床検査
53巻10号(2009年10月発行)
今月の主題 血栓症と臨床検査
53巻9号(2009年9月発行)
今月の主題 脳磁図で何がわかるか?
53巻8号(2009年8月発行)
今月の主題 漢方薬・生薬と臨床検査
53巻7号(2009年7月発行)
今月の主題 唾液の臨床検査
53巻6号(2009年6月発行)
今月の主題 食中毒
53巻5号(2009年5月発行)
今月の主題 免疫不全症候群と遺伝子異常
53巻4号(2009年4月発行)
今月の主題 妊娠と臨床検査
53巻3号(2009年3月発行)
今月の主題 臨床検査コンサルテーション/診療支援
53巻2号(2009年2月発行)
今月の主題 生体内微量元素
53巻1号(2009年1月発行)
今月の主題 ウイルス感染症─最新の動向
52巻13号(2008年12月発行)
今月の主題 凝固制御
52巻12号(2008年11月発行)
今月の主題 平衡機能検査
52巻11号(2008年10月発行)
特集 ホルモンの病態異常と臨床検査
52巻10号(2008年10月発行)
今月の主題 結核
52巻9号(2008年9月発行)
今月の主題 アスベストと中皮腫
52巻8号(2008年8月発行)
今月の主題 自然免疫と生体防御レクチン
52巻7号(2008年7月発行)
今月の主題 腎移植
52巻6号(2008年6月発行)
今月の主題 エピジェネティクスと臨床検査
52巻5号(2008年5月発行)
今月の主題 自己免疫疾患の診断
52巻4号(2008年4月発行)
今月の主題 歯科からみえる全身疾患
52巻3号(2008年3月発行)
今月の主題 アルツハイマー病の最近の進歩
52巻2号(2008年2月発行)
今月の主題 輸血の安全管理
52巻1号(2008年1月発行)
今月の主題 インフルエンザ診療のブレークスルー
51巻13号(2007年12月発行)
今月の主題 胎盤
51巻12号(2007年11月発行)
特集 遺伝子検査―診断とリスクファクター
51巻11号(2007年11月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム健診での注意点
51巻10号(2007年10月発行)
今月の主題 白血球
51巻9号(2007年9月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
51巻8号(2007年8月発行)
今月の主題 ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と子宮頸癌
51巻7号(2007年7月発行)
今月の主題 不整脈検査
51巻6号(2007年6月発行)
今月の主題 骨粗鬆症と臨床検査
51巻5号(2007年5月発行)
今月の主題 脂質
51巻4号(2007年4月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
51巻3号(2007年3月発行)
今月の主題 血管超音波検査
51巻2号(2007年2月発行)
今月の主題 尿路感染症の診断
51巻1号(2007年1月発行)
今月の主題 乳癌と臨床検査
50巻13号(2006年12月発行)
今月の主題 臨床検査史―国際的な流れとわが国の動向
50巻12号(2006年11月発行)
特集 ナノテクノロジーとバイオセンサ
50巻11号(2006年11月発行)
今月の主題 海外旅行と臨床検査
50巻10号(2006年10月発行)
今月の主題 認知症の動的神経病理
50巻9号(2006年9月発行)
今月の主題 高齢者の臨床検査値
50巻8号(2006年8月発行)
今月の主題 皮膚科と臨床検査
50巻7号(2006年7月発行)
今月の主題 ホルマリン固定パラフィン包埋標本からどこまで遺伝子検索は可能か?
50巻6号(2006年6月発行)
今月の主題 健康食品と臨床検査
50巻5号(2006年5月発行)
今月の主題 腎疾患と臨床検査
50巻4号(2006年4月発行)
今月の主題 検査室におけるインシデント・アクシデント
50巻3号(2006年3月発行)
今月の主題 採血
50巻2号(2006年2月発行)
今月の主題 花粉症克服への展望
50巻1号(2006年1月発行)
今月の主題 PK/PD解析を指標とした感染症治療
49巻13号(2005年12月発行)
今月の主題 メタボリックシンドローム
49巻12号(2005年11月発行)
特集 臨床検査のための情報処理技術の進歩
49巻11号(2005年11月発行)
今月の主題 肝臓癌の臨床検査
49巻10号(2005年10月発行)
今月の主題 視機能
49巻9号(2005年9月発行)
今月の主題 キャピラリー電気泳動法
49巻8号(2005年8月発行)
今月の主題 これからの臨床検査技師教育を考える
49巻7号(2005年7月発行)
今月の主題 アレルギー疾患の現況と今後の展望
49巻6号(2005年6月発行)
今月の主題 院内感染制御
49巻5号(2005年5月発行)
今月の主題 マイクロアレイ技術の進歩
49巻4号(2005年4月発行)
今月の主題 脳脊髄液
49巻3号(2005年3月発行)
今月の主題 私と臨床検査―先達の軌跡
49巻2号(2005年2月発行)
今月の主題 酸化ストレスマーカーと疾患・病態
49巻1号(2005年1月発行)
今月の主題 ミトコンドリア病
48巻13号(2004年12月発行)
今月の主題 脳機能
48巻12号(2004年11月発行)
今月の主題 自己健康管理のための検査
48巻11号(2004年10月発行)
特集 動脈硬化-その成り立ちと臨床検査
48巻10号(2004年10月発行)
今月の主題 輸血・細胞療法と臨床検査
48巻9号(2004年9月発行)
今月の主題 栄養管理のパラメーター
48巻8号(2004年8月発行)
今月の主題 更年期障害と甲状腺ホルモン
48巻7号(2004年7月発行)
今月の主題 ドーピング・スポーツ薬物検査
48巻6号(2004年6月発行)
今月の主題 小児の成長・発育と臨床検査
48巻5号(2004年5月発行)
今月の主題 アルブミン
48巻4号(2004年4月発行)
今月の主題 ワクチン―その開発と将来展望
48巻3号(2004年3月発行)
今月の主題 新しい自己抗体
48巻2号(2004年2月発行)
今月の主題 薬物代謝酵素の遺伝的多型―特に個別化薬物治療を目ざして
48巻1号(2004年1月発行)
今月の主題 感染症における危機管理
47巻13号(2003年12月発行)
今月の主題 イムノアッセイ
47巻12号(2003年11月発行)
今月の主題 生体材料の取扱いと倫理
47巻11号(2003年10月発行)
特集 プロテオミクスに向かう臨床蛋白質検査
47巻10号(2003年10月発行)
今月の主題 聴覚障害とその診断
47巻9号(2003年9月発行)
今月の主題 PSA
47巻8号(2003年8月発行)
今月の主題 プロテアーゼ,プロテアーゼインヒビター
47巻7号(2003年7月発行)
今月の主題 補完・代替医療
47巻6号(2003年6月発行)
今月の主題 アルコールと臨床検査
47巻5号(2003年5月発行)
今月の主題 食中毒,その発症をめぐって
47巻4号(2003年4月発行)
今月の主題 漢方医学と臨床検査
47巻3号(2003年3月発行)
今月の主題 樹状細胞
47巻2号(2003年2月発行)
今月の主題 病原微生物の迅速検査
47巻1号(2003年1月発行)
今月の主題 緊急検査
46巻13号(2002年12月発行)
今月の主題 臨床検査技師の教育
46巻12号(2002年11月発行)
今月の主題 プリオン病とその診断
46巻11号(2002年10月発行)
特集 造血器腫瘍
46巻10号(2002年10月発行)
今月の主題 診察前検査
46巻9号(2002年9月発行)
今月の主題 C反応性蛋白
46巻8号(2002年8月発行)
今月の主題 臨床検査測定値の標準化
46巻7号(2002年7月発行)
今月の主題 糖尿病
46巻6号(2002年6月発行)
今月の主題 細胞診自動化
46巻5号(2002年5月発行)
今月の主題 筋疾患
46巻4号(2002年4月発行)
今月の主題 再生医療と幹細胞
46巻3号(2002年3月発行)
今月の主題 HBV・HCV検査法の新しい動向―標準化に向けて
46巻2号(2002年2月発行)
今月の主題 インフルエンザ―新しい知見
46巻1号(2002年1月発行)
今月の主題 テーラーメイド医療と臨床検査
45巻13号(2001年12月発行)
今月の主題 検査領域でのリスク・マネジメント
45巻12号(2001年11月発行)
今月の主題 視機能検査と臨床検査
45巻11号(2001年10月発行)
特集 超音波検査の技術と臨床
45巻10号(2001年10月発行)
今月の主題 ビタミン
45巻9号(2001年9月発行)
今月の主題 蛋白質の活性と蛋白量
45巻8号(2001年8月発行)
今月の主題 薬剤耐性菌をめぐる最近の話題
45巻7号(2001年7月発行)
今月の主題 鉄銅代謝
45巻6号(2001年6月発行)
今月の主題 生体リズム
45巻5号(2001年5月発行)
今月の主題 在宅医療
45巻4号(2001年4月発行)
今月の主題 高齢化
45巻3号(2001年3月発行)
今月の主題 酸化ストレス
45巻2号(2001年2月発行)
今月の主題 染色体―検査と社会とのかかわり
45巻1号(2001年1月発行)
今月の主題 サイトカイン・ケモカイン
44巻13号(2000年12月発行)
今月の主題 血管新生
44巻12号(2000年11月発行)
今月の主題 毒物検査
44巻11号(2000年10月発行)
特集 細胞診―21世紀への展望
44巻10号(2000年10月発行)
今月の主題 脂質代謝関連検査項目についての再検討
44巻9号(2000年9月発行)
今月の主題 テレメディスン(遠隔医療)
44巻8号(2000年8月発行)
今月の主題 自動機器分析に要求される標準化
44巻7号(2000年7月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
44巻6号(2000年6月発行)
今月の主題 イオンチャネルの変化と心臓
44巻5号(2000年5月発行)
今月の主題 微生物培養検査のサンプリング
44巻4号(2000年4月発行)
今月の主題 抗原認識と抗体産生
44巻3号(2000年3月発行)
今月の主題 糖化蛋白と蛋白のグリケーション
44巻2号(2000年2月発行)
今月の主題 血流
44巻1号(2000年1月発行)
今月の主題 質量分析―新しい臨床検査への展開
43巻13号(1999年12月発行)
今月の主題 21世紀に向けての寄生虫症
43巻12号(1999年11月発行)
今月の主題 心電図
43巻11号(1999年10月発行)
特集 臨床検査の新しい展開―環境保全への挑戦
43巻10号(1999年10月発行)
今月の主題 血管壁細胞
43巻9号(1999年9月発行)
今月の主題 生活習慣病
43巻8号(1999年8月発行)
今月の主題 輸血検査
43巻7号(1999年7月発行)
今月の主題 マスト細胞
43巻6号(1999年6月発行)
今月の主題 高血圧と臨床検査
43巻5号(1999年5月発行)
今月の主題 結核
43巻4号(1999年4月発行)
今月の主題 原発性免疫不全症
43巻3号(1999年3月発行)
今月の主題 肝炎
43巻2号(1999年2月発行)
今月の主題 深在性真菌症
43巻1号(1999年1月発行)
今月の主題 TDMの臨床応用
42巻13号(1998年12月発行)
今月の主題 検査項目の再評価
42巻12号(1998年11月発行)
今月の主題 遺伝子多型と疾患
42巻11号(1998年10月発行)
特集 感染症診断へのアプローチ
42巻10号(1998年10月発行)
今月の主題 蛋白尿の病態解析
42巻9号(1998年9月発行)
今月の主題 in situ hybridization
42巻8号(1998年8月発行)
今月の主題 受容体
42巻7号(1998年7月発行)
今月の主題 多発性内分泌腫瘍症(MEN)
42巻6号(1998年6月発行)
今月の主題 臨床検査情報処理の将来
42巻5号(1998年5月発行)
今月の主題 注目されている感染症―Emerging Infectious Diseases
42巻4号(1998年4月発行)
今月の主題 肥満
42巻3号(1998年3月発行)
今月の主題 生物・化学発光の新しい展開
42巻2号(1998年2月発行)
今月の主題 骨代謝マーカー
42巻1号(1998年1月発行)
今月の主題 骨髄腫細胞とその産生蛋白
41巻13号(1997年12月発行)
今月の主題 臨床検査と医療経済
41巻12号(1997年11月発行)
今月の主題 標準物質
41巻11号(1997年10月発行)
特集 神経系疾患と臨床検査
41巻10号(1997年10月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー―最近の進歩
41巻9号(1997年9月発行)
今月の主題 臨床化学分析の指示反応系
41巻8号(1997年8月発行)
今月の主題 臓器移植と臨床検査
41巻7号(1997年7月発行)
今月の主題 母子医療と臨床検査
41巻6号(1997年6月発行)
今月の主題 感染症における病原因子
41巻5号(1997年5月発行)
今月の主題 自己抗体・最近の動向
41巻4号(1997年4月発行)
今月の主題 Internal Quality Control
41巻3号(1997年3月発行)
今月の主題 白血病・最近の進歩
41巻2号(1997年2月発行)
今月の主題 Helicobacter pylori
41巻1号(1997年1月発行)
今月の主題 スポーツと臨床検査
40巻13号(1996年12月発行)
今月の主題 基準値
40巻12号(1996年11月発行)
今月の主題 臨床化学とHPLC
40巻11号(1996年10月発行)
特集 血栓症と血小板凝固線溶系検査
40巻10号(1996年10月発行)
今月の主題 糖尿病―診断・治療の指標
40巻9号(1996年9月発行)
今月の主題 動脈硬化とリポ蛋白
40巻8号(1996年8月発行)
今月の主題 造血幹細胞
40巻7号(1996年7月発行)
今月の主題 ニューロパチーの臨床検査
40巻6号(1996年6月発行)
今月の主題 性感染症(STD)
40巻5号(1996年5月発行)
今月の主題 心筋梗塞の生化学的マーカー
40巻4号(1996年4月発行)
今月の主題 注目のグラム陽性菌
40巻3号(1996年3月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
40巻2号(1996年2月発行)
今月の主題 活性酸素とSOD
40巻1号(1996年1月発行)
今月の主題 検査室の安全管理
39巻13号(1995年12月発行)
今月の主題 臨床検査とQOL
39巻12号(1995年11月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー―最近の進歩
39巻11号(1995年10月発行)
特集 免疫組織・細胞化学検査
39巻10号(1995年10月発行)
今月の主題 乳腺の検査
39巻9号(1995年9月発行)
今月の主題 人畜共通感染症
39巻8号(1995年8月発行)
今月の主題 脱中央化検査技術
39巻7号(1995年7月発行)
今月の主題 赤血球―新しい展開
39巻6号(1995年6月発行)
今月の主題 抗体蛋白
39巻5号(1995年5月発行)
今月の主題 定量検査のQM―精度向上への道筋
39巻4号(1995年4月発行)
今月の主題 薬物検査
39巻3号(1995年3月発行)
今月の主題 骨髄移植
39巻2号(1995年2月発行)
今月の主題 平衛機能検査
39巻1号(1995年1月発行)
今月の主題 糖鎖の異常
38巻13号(1994年12月発行)
今月の主題 敗血症
38巻12号(1994年11月発行)
今月の主題 超音波検査―最近の進歩
38巻11号(1994年10月発行)
特集 ホルモンと生理活性物質
38巻10号(1994年10月発行)
今月の主題 胃・十二指腸疾患と検査
38巻9号(1994年9月発行)
今月の主題 臨床検査の効率性をめぐって
38巻8号(1994年8月発行)
今月の主題 可溶性膜糖蛋白
38巻7号(1994年7月発行)
今月の主題 結合組織
38巻6号(1994年6月発行)
今月の主題 前立腺と睾丸
38巻5号(1994年5月発行)
今月の主題 常在菌
38巻4号(1994年4月発行)
今月の主題 好中球をめぐる検査
38巻3号(1994年3月発行)
今月の主題 周術期の検査
38巻2号(1994年2月発行)
今月の主題 生物・化学発光計測
38巻1号(1994年1月発行)
今月の主題 MRI
37巻13号(1993年12月発行)
今月の主題 眼科画像検査―最近の進歩
37巻12号(1993年11月発行)
今月の主題 血液疾患をめぐる新しい検査
37巻11号(1993年10月発行)
特集 ロボティクスと臨床検査
37巻10号(1993年10月発行)
今月の主題 HCV
37巻9号(1993年9月発行)
今月の主題 データ処理の未来学―検査成績の報告・解析・保存
37巻8号(1993年8月発行)
今月の主題 抗菌薬感受性試験
37巻7号(1993年7月発行)
今月の主題 粘膜免疫と臨床検査
37巻6号(1993年6月発行)
今月の主題 甲状腺の検査
37巻5号(1993年5月発行)
今月の主題 酵素検査標準化の動向
37巻4号(1993年4月発行)
今月の主題 閉経と臨床検査
37巻3号(1993年3月発行)
今月の主題 プリン体代謝とその異常
37巻2号(1993年2月発行)
今月の主題 PCRを用いた病原微生物の検出
37巻1号(1993年1月発行)
今月の主題 穿刺吸引細胞診―最近の進歩
36巻13号(1992年12月発行)
今月の主題 溶血性尿毒症症候群(HUS)
36巻12号(1992年11月発行)
今月の主題 免疫不全症
36巻11号(1992年10月発行)
特集 遺伝と臨床検査
36巻10号(1992年10月発行)
今月の主題 放射線障害
36巻9号(1992年9月発行)
今月の主題 赤色尿
36巻8号(1992年8月発行)
今月の主題 輸入感染症
36巻7号(1992年7月発行)
今月の主題 皮膚
36巻6号(1992年6月発行)
今月の主題 循環生理機能検査の進歩
36巻5号(1992年5月発行)
今月の主題 大腸疾患と検査
36巻4号(1992年4月発行)
今月の主題 血管内皮細胞
36巻3号(1992年3月発行)
今月の主題 ビタミンをめぐる臨床検査
36巻2号(1992年2月発行)
今月の主題 法医学と臨床検査
36巻1号(1992年1月発行)
今月の主題 成長因子と増殖因子
35巻13号(1991年12月発行)
今月の主題 骨・関節をめぐって
35巻12号(1991年11月発行)
特集 アレルギーと自己免疫
35巻11号(1991年11月発行)
今月の主題 医療廃棄物
35巻10号(1991年10月発行)
今月の主題 膵疾患と臨床検査
35巻9号(1991年9月発行)
今月の主題 人工臓器とモニター検査
35巻8号(1991年8月発行)
今月の主題 真菌症
35巻7号(1991年7月発行)
今月の主題 呼吸器疾患と臨床検査
35巻6号(1991年6月発行)
今月の主題 臨床検査の新技術
35巻5号(1991年5月発行)
今月の主題 サイトカインと造血因子
35巻4号(1991年4月発行)
今月の主題 肥満とやせ
35巻3号(1991年3月発行)
今月の主題 心・血管系ホルモン
35巻2号(1991年2月発行)
今月の主題 脂質代謝異常
35巻1号(1991年1月発行)
今月の主題 肝炎ウイルス関連マーカー
34巻13号(1990年12月発行)
今月の主題 細胞接着因子
34巻12号(1990年11月発行)
今月の主題 リハビリテーション―臨床検査の役割
34巻11号(1990年10月発行)
特集 電解質と微量元素の臨床検査ガイド
34巻10号(1990年10月発行)
今月の主題 虚血性心疾患
34巻9号(1990年9月発行)
今月の主題 検診・健康診査
34巻8号(1990年8月発行)
今月の主題 レセプター
34巻7号(1990年7月発行)
今月の主題 集中治療室での検査
34巻6号(1990年6月発行)
今月の主題 フローサイトメトリー
34巻5号(1990年5月発行)
今月の主題 生殖
34巻4号(1990年4月発行)
今月の主題 結核菌と非定型抗酸菌をめぐって
34巻3号(1990年3月発行)
今月の主題 呼吸機能検査
34巻2号(1990年2月発行)
今月の主題 補体系
34巻1号(1990年1月発行)
今月の主題 異常環境
33巻13号(1989年12月発行)
今月の主題 精神疾患をめぐる臨床検査
33巻12号(1989年11月発行)
今月の主題 血小板・凝固・線溶系の分子マーカー
33巻11号(1989年10月発行)
特集 癌の臨床検査
33巻10号(1989年10月発行)
今月の主題 耐性菌をめぐって
33巻9号(1989年9月発行)
今月の主題 アミロイド
33巻8号(1989年8月発行)
今月の主題 糖尿病
33巻7号(1989年7月発行)
今月の主題 臨床検査における標準物質
33巻6号(1989年6月発行)
今月の主題 筋疾患と臨床検査
33巻5号(1989年5月発行)
今月の主題 注目される寄生虫・原虫疾患
33巻4号(1989年4月発行)
今月の主題 造血器腫瘍の新しい検査
33巻3号(1989年3月発行)
今月の主題 生体内の酸化と還元
33巻2号(1989年2月発行)
今月の主題 加齢と臨床検査
33巻1号(1989年1月発行)
今月の主題 臨床生理検査の自動化
32巻13号(1988年12月発行)
今月の主題 輸血に伴う感染症の検査と対策
32巻12号(1988年11月発行)
今月の主題 血中薬物濃度測定法の進歩
32巻11号(1988年10月発行)
特集 アイソザイム検査
32巻10号(1988年10月発行)
今月の主題 周産期の臨床検査
32巻9号(1988年9月発行)
今月の主題 死の判定と検査
32巻8号(1988年8月発行)
今月の主題 尿中低分子蛋白の測定と意義
32巻7号(1988年7月発行)
今月の主題 病原体抗原の免疫学的検査法
32巻6号(1988年6月発行)
今月の主題 免疫血液学検査法の進歩
32巻5号(1988年5月発行)
今月の主題 心電図の最前線
32巻4号(1988年4月発行)
今月の主題 DNA診断に必要な測定技術
32巻3号(1988年3月発行)
今月の主題 迅速検査;現状と今後の動向
32巻2号(1988年2月発行)
今月の主題 炎症マーカーとその臨床的意義
32巻1号(1988年1月発行)
今月の主題 人工知能と臨床検査
31巻13号(1987年12月発行)
今月の主題 ドライケミストリー
31巻12号(1987年11月発行)
今月の主題 透析と血漿交換
31巻11号(1987年10月発行)
特集 生検の進歩
31巻10号(1987年10月発行)
今月の主題 制癌剤と臨床検査
31巻9号(1987年9月発行)
今月の主題 医用オプチクス
31巻8号(1987年8月発行)
今月の主題 酵素結合性免疫グロブリン
31巻7号(1987年7月発行)
今月の主題 注目のウイルス・リケッチア感染症
31巻6号(1987年6月発行)
今月の主題 リウマトイド因子
31巻5号(1987年5月発行)
今月の主題 輸血;新しい技術
31巻4号(1987年4月発行)
今月の主題 臨床検査とTQC
31巻3号(1987年3月発行)
今月の主題 生体色素
31巻2号(1987年2月発行)
今月の主題 肺
31巻1号(1987年1月発行)
今月の主題 高血圧
30巻13号(1986年12月発行)
今月の主題 眼と耳
30巻12号(1986年11月発行)
今月の主題 造血器
30巻11号(1986年11月発行)
特集 先端技術と臨床検査
30巻10号(1986年10月発行)
今月の主題 病院内感染防止のための細菌検査
30巻9号(1986年9月発行)
今月の主題 唾液と汗
30巻8号(1986年8月発行)
今月の主題 生体リズム
30巻7号(1986年7月発行)
今月の主題 抗核抗体
30巻6号(1986年6月発行)
今月の主題 定量的細菌検査とその臨床的意義
30巻5号(1986年5月発行)
今月の主題 消化と吸収
30巻4号(1986年4月発行)
今月の主題 ヘモグロビン異常
30巻3号(1986年3月発行)
今月の主題 凝固線溶系の新しい検査
30巻2号(1986年2月発行)
今月の主題 免疫不全
30巻1号(1986年1月発行)
今月の主題 新生児
29巻13号(1985年12月発行)
今月の主題 動脈硬化
29巻12号(1985年11月発行)
今月の主題 細菌同定の迅速化へのアプローチ
29巻11号(1985年11月発行)
特集 リポ蛋白・脂質代謝と臨床検査
29巻10号(1985年10月発行)
今月の主題 スポーツ
29巻9号(1985年9月発行)
今月の主題 医用センサー
29巻8号(1985年8月発行)
今月の主題 移植
29巻7号(1985年7月発行)
今月の主題 悪性リンパ腫
29巻6号(1985年6月発行)
今月の主題 黄疸
29巻5号(1985年5月発行)
今月の主題 カルシウム
29巻4号(1985年4月発行)
今月の主題 まちがいやすいGram陽性菌の同定法
29巻3号(1985年3月発行)
今月の主題 アレルギー
29巻2号(1985年2月発行)
今月の主題 発光分析
29巻1号(1985年1月発行)
今月の主題 アルコール
28巻13号(1984年12月発行)
今月の主題 アポ蛋白
28巻12号(1984年11月発行)
今月の主題 臨床検査の標準化
28巻11号(1984年11月発行)
特集 産業医学と臨床検査
28巻10号(1984年10月発行)
今月の主題 男と女
28巻9号(1984年9月発行)
今月の主題 腫瘍マーカー
28巻8号(1984年8月発行)
今月の主題 エンザイムイムノアッセイ(EIA)
28巻7号(1984年7月発行)
今月の主題 染色体
28巻6号(1984年6月発行)
今月の主題 細胞膜
28巻5号(1984年5月発行)
今月の主題 副腎
28巻4号(1984年4月発行)
今月の主題 呼吸と循環(生理検査)
28巻3号(1984年3月発行)
今月の主題 画像診断
28巻2号(1984年2月発行)
今月の主題 性行為感染症(STD)
28巻1号(1984年1月発行)
今月の主題 血栓症
27巻13号(1983年12月発行)
今月の主題 モノクローナル抗体
27巻12号(1983年11月発行)
今月の主題 輸液と臨床検査
27巻11号(1983年11月発行)
特集 臨床細菌検査
27巻10号(1983年10月発行)
今月の主題 神経・筋〈生理検査〉
27巻9号(1983年9月発行)
今月の主題 レーザーと臨床検査
27巻8号(1983年8月発行)
今月の主題 血液凝固検査と合成基質
27巻7号(1983年7月発行)
今月の主題 腎不全
27巻6号(1983年6月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
27巻5号(1983年5月発行)
今月の主題 臨床診断のロジック
27巻4号(1983年4月発行)
今月の主題 循環器〈生理検査〉
27巻3号(1983年3月発行)
今月の主題 自己免疫病
27巻2号(1983年2月発行)
今月の主題 プロスタグランジン
27巻1号(1983年1月発行)
今月の主題 老化
26巻13号(1982年12月発行)
今月の主題 妊娠
26巻12号(1982年11月発行)
今月の主題 日和見感染症
26巻11号(1982年11月発行)
特集 臨床検査のシステム化
26巻10号(1982年10月発行)
今月の主題 慢性閉塞性肺疾患
26巻9号(1982年9月発行)
今月の主題 尿の臨床検査
26巻8号(1982年8月発行)
今月の主題 レセプター病
26巻7号(1982年7月発行)
今月の主題 血漿蛋白
26巻6号(1982年6月発行)
今月の主題 ショック
26巻5号(1982年5月発行)
今月の主題 糖尿病
26巻4号(1982年4月発行)
今月の主題 生体電気インピーダンス
26巻3号(1982年3月発行)
今月の主題 風変わりな感染経路の感染症
26巻2号(1982年2月発行)
今月の主題 炎症
26巻1号(1982年1月発行)
今月の主題 栄養
25巻13号(1981年12月発行)
今月の主題 血液ガス分析と酸—塩基平衡
25巻12号(1981年11月発行)
今月の主題 輸血
25巻11号(1981年11月発行)
特集 臨床神経生理学的検査の進歩
25巻10号(1981年10月発行)
今月の主題 RIを用いる検査
25巻9号(1981年9月発行)
今月の主題 新しいウイルス検査法
25巻8号(1981年8月発行)
今月の主題 血小板
25巻7号(1981年7月発行)
今月の主題 リポ蛋白
25巻6号(1981年6月発行)
今月の主題 貧血
25巻5号(1981年5月発行)
今月の主題 膵疾患
25巻4号(1981年4月発行)
今月の主題 マイコプラズマ症,クラミジア症の診断
25巻3号(1981年3月発行)
今月の主題 筋疾患
25巻2号(1981年2月発行)
今月の主題 救急検査
25巻1号(1981年1月発行)
今月の主題 リンフォカイン
24巻13号(1980年12月発行)
今月の主題 遺伝
24巻12号(1980年11月発行)
今月の主題 薬剤の検査
24巻11号(1980年11月発行)
特集 出血傾向のLaboratory Diagnosis
24巻10号(1980年10月発行)
今月の主題 生理検査
24巻9号(1980年9月発行)
今月の主題 補体
24巻8号(1980年8月発行)
今月の主題 癌の臨床検査
24巻7号(1980年7月発行)
今月の主題 微量金属
24巻6号(1980年6月発行)
今月の主題 赤血球の化学
24巻5号(1980年5月発行)
今月の主題 感染症とバイオハザード
24巻4号(1980年4月発行)
今月の主題 生理検査
24巻3号(1980年3月発行)
今月の主題 肝疾患
24巻2号(1980年2月発行)
今月の主題 集団検診の技術
24巻1号(1980年1月発行)
今月の主題 白血病
23巻13号(1979年12月発行)
今月の主題 形態検査
23巻12号(1979年11月発行)
今月の主題 甲状腺
23巻11号(1979年11月発行)
特集 免疫学的検査の進歩
23巻10号(1979年10月発行)
今月の主題 生理検査・2
23巻9号(1979年9月発行)
今月の主題 電気泳動の進歩
23巻8号(1979年8月発行)
今月の主題 細菌性食中毒
23巻7号(1979年7月発行)
今月の主題 リンパ球
23巻6号(1979年6月発行)
今月の主題 組織検査の進歩
23巻5号(1979年5月発行)
今月の主題 生理検査・1
23巻4号(1979年4月発行)
今月の主題 感染症
23巻3号(1979年3月発行)
今月の主題 DIC
23巻2号(1979年2月発行)
今月の主題 脂質
23巻1号(1979年1月発行)
今月の主題 免疫複合体
22巻13号(1978年12月発行)
22巻12号(1978年11月発行)
22巻11号(1978年11月発行)
特集 酵素による臨床化学分析
22巻10号(1978年10月発行)
22巻9号(1978年9月発行)
22巻8号(1978年8月発行)
22巻7号(1978年7月発行)
22巻6号(1978年6月発行)
22巻5号(1978年5月発行)
22巻4号(1978年4月発行)
22巻3号(1978年3月発行)
22巻2号(1978年2月発行)
22巻1号(1978年1月発行)
21巻13号(1977年12月発行)
21巻12号(1977年11月発行)
21巻11号(1977年11月発行)
特集 小児の臨床検査
21巻10号(1977年10月発行)
21巻9号(1977年9月発行)
21巻8号(1977年8月発行)
21巻7号(1977年7月発行)
21巻6号(1977年6月発行)
21巻5号(1977年5月発行)
21巻4号(1977年4月発行)
21巻3号(1977年3月発行)
21巻2号(1977年2月発行)
21巻1号(1977年1月発行)
20巻13号(1976年12月発行)
20巻12号(1976年11月発行)
20巻11号(1976年11月発行)
特集 臨床検査室マニュアル
20巻10号(1976年10月発行)
20巻9号(1976年9月発行)
20巻8号(1976年8月発行)
20巻7号(1976年7月発行)
20巻6号(1976年6月発行)
20巻5号(1976年5月発行)
20巻4号(1976年4月発行)
20巻3号(1976年3月発行)
20巻2号(1976年2月発行)
20巻1号(1976年1月発行)
19巻12号(1975年12月発行)
19巻11号(1975年11月発行)
特集 ウイルス疾患の検査法
19巻10号(1975年10月発行)
19巻9号(1975年9月発行)
19巻8号(1975年8月発行)
19巻7号(1975年7月発行)
19巻6号(1975年6月発行)
19巻5号(1975年5月発行)
19巻4号(1975年4月発行)
19巻3号(1975年3月発行)
19巻2号(1975年2月発行)
19巻1号(1975年1月発行)
18巻13号(1974年12月発行)
特集 日常臨床検査法
18巻11号(1974年11月発行)
18巻12号(1974年11月発行)
18巻10号(1974年10月発行)
18巻9号(1974年9月発行)
18巻8号(1974年8月発行)
18巻7号(1974年7月発行)
18巻6号(1974年6月発行)
18巻5号(1974年5月発行)
18巻4号(1974年4月発行)
18巻3号(1974年3月発行)
18巻2号(1974年2月発行)
18巻1号(1974年1月発行)
17巻13号(1973年12月発行)
17巻12号(1973年11月発行)
17巻11号(1973年11月発行)
特集 自動化臨床検査法
17巻10号(1973年10月発行)
17巻9号(1973年9月発行)
17巻8号(1973年8月発行)
17巻7号(1973年7月発行)
17巻6号(1973年6月発行)
17巻5号(1973年5月発行)
17巻4号(1973年4月発行)
17巻3号(1973年3月発行)
17巻2号(1973年2月発行)
17巻1号(1973年1月発行)
16巻13号(1972年12月発行)
16巻12号(1972年11月発行)
16巻11号(1972年11月発行)
特集 輸血業務と臨床検査
16巻10号(1972年10月発行)
16巻9号(1972年9月発行)
特集 負荷機能検査法
16巻8号(1972年8月発行)
16巻7号(1972年7月発行)
16巻6号(1972年6月発行)
16巻5号(1972年5月発行)
16巻4号(1972年4月発行)
16巻3号(1972年3月発行)
16巻2号(1972年2月発行)
16巻1号(1972年1月発行)
15巻13号(1971年12月発行)
15巻12号(1971年12月発行)
特集 酵素検査法
15巻11号(1971年11月発行)
15巻10号(1971年10月発行)
15巻9号(1971年9月発行)
15巻8号(1971年8月発行)
15巻7号(1971年7月発行)
15巻6号(1971年6月発行)
15巻5号(1971年5月発行)
15巻4号(1971年4月発行)
15巻3号(1971年3月発行)
15巻2号(1971年2月発行)
特集 臨床生理検査と採血
15巻1号(1971年1月発行)
14巻13号(1970年12月発行)
14巻12号(1970年12月発行)
特集 日常検査法—基礎と要点
14巻11号(1970年11月発行)
14巻10号(1970年10月発行)
14巻9号(1970年9月発行)
14巻8号(1970年8月発行)
14巻7号(1970年7月発行)
14巻6号(1970年6月発行)
14巻5号(1970年5月発行)
14巻4号(1970年4月発行)
14巻3号(1970年3月発行)
特集 巨赤芽球および巨赤芽球様細胞
14巻2号(1970年2月発行)
14巻1号(1970年1月発行)
13巻13号(1969年12月発行)
13巻12号(1969年12月発行)
特集 血清学的検査—その本質と実際
13巻11号(1969年11月発行)
13巻10号(1969年10月発行)
13巻9号(1969年9月発行)
特集 ディスポーザブル検査器具
13巻8号(1969年8月発行)
13巻7号(1969年7月発行)
13巻6号(1969年6月発行)
13巻5号(1969年5月発行)
13巻4号(1969年4月発行)
13巻3号(1969年3月発行)
13巻2号(1969年2月発行)
13巻1号(1969年1月発行)
12巻13号(1968年12月発行)
12巻12号(1968年12月発行)
特集 血液検査の問題点
12巻11号(1968年11月発行)
12巻10号(1968年10月発行)
12巻9号(1968年9月発行)
特集 成人病検査
12巻8号(1968年8月発行)
12巻7号(1968年7月発行)
12巻6号(1968年6月発行)
12巻5号(1968年5月発行)
12巻4号(1968年4月発行)
12巻3号(1968年3月発行)
12巻2号(1968年2月発行)
12巻1号(1968年1月発行)
11巻13号(1967年12月発行)
11巻12号(1967年12月発行)
特集 簡易臨床検査法
11巻11号(1967年11月発行)
11巻10号(1967年10月発行)
11巻9号(1967年9月発行)
特集 小児の検査
11巻8号(1967年8月発行)
特集 医学写真
11巻7号(1967年7月発行)
11巻6号(1967年6月発行)
11巻5号(1967年5月発行)
11巻4号(1967年4月発行)
11巻3号(1967年3月発行)
11巻2号(1967年2月発行)
11巻1号(1967年1月発行)
10巻13号(1966年12月発行)
10巻12号(1966年11月発行)
特集 グラフ特集臨床検査の基礎
10巻11号(1966年11月発行)
10巻10号(1966年10月発行)
10巻9号(1966年9月発行)
10巻8号(1966年8月発行)
特集 研究論文
10巻7号(1966年7月発行)
10巻6号(1966年6月発行)
10巻5号(1966年5月発行)
10巻4号(1966年4月発行)
10巻3号(1966年3月発行)
10巻2号(1966年2月発行)
10巻1号(1966年1月発行)
9巻13号(1965年12月発行)
9巻12号(1965年12月発行)
特集 日常検査法の基礎知識と実技
9巻11号(1965年11月発行)
9巻10号(1965年10月発行)
9巻9号(1965年9月発行)
特集 塗抹検査
9巻8号(1965年8月発行)
9巻7号(1965年7月発行)
9巻6号(1965年6月発行)
9巻5号(1965年5月発行)
特集 産婦人科領域における臨床検査
9巻4号(1965年4月発行)
9巻3号(1965年3月発行)
9巻2号(1965年2月発行)
9巻1号(1965年1月発行)
8巻12号(1964年12月発行)
8巻11号(1964年11月発行)
8巻10号(1964年10月発行)
8巻9号(1964年9月発行)
8巻8号(1964年8月発行)
8巻7号(1964年7月発行)
8巻6号(1964年6月発行)
8巻5号(1964年5月発行)
8巻4号(1964年4月発行)
8巻3号(1964年3月発行)
8巻2号(1964年2月発行)
8巻1号(1964年1月発行)
7巻12号(1963年12月発行)
7巻11号(1963年11月発行)
7巻10号(1963年10月発行)
7巻9号(1963年9月発行)
特集 一般臨床検査の要点—受験者の手引きを兼ねて
7巻8号(1963年8月発行)
7巻7号(1963年7月発行)
7巻6号(1963年6月発行)
7巻5号(1963年5月発行)
7巻4号(1963年4月発行)
7巻3号(1963年3月発行)
特集 衛生検査技師学校新卒業生のみなさんへ
7巻2号(1963年2月発行)
7巻1号(1963年1月発行)
6巻12号(1962年12月発行)
6巻11号(1962年11月発行)
小特集 ここを注意して下さい
6巻10号(1962年10月発行)
6巻9号(1962年9月発行)
6巻8号(1962年8月発行)
6巻7号(1962年7月発行)
6巻6号(1962年6月発行)
6巻5号(1962年5月発行)
6巻4号(1962年4月発行)
6巻3号(1962年3月発行)
6巻2号(1962年2月発行)
6巻1号(1962年1月発行)
5巻12号(1961年12月発行)
5巻11号(1961年11月発行)
5巻10号(1961年10月発行)
5巻9号(1961年9月発行)
5巻8号(1961年8月発行)
5巻7号(1961年7月発行)
5巻6号(1961年6月発行)
5巻5号(1961年5月発行)
5巻4号(1961年4月発行)
5巻3号(1961年3月発行)
5巻2号(1961年2月発行)
5巻1号(1961年1月発行)
4巻12号(1960年12月発行)
4巻11号(1960年11月発行)
4巻10号(1960年10月発行)
4巻9号(1960年9月発行)
4巻8号(1960年8月発行)
4巻7号(1960年7月発行)
4巻6号(1960年6月発行)
4巻5号(1960年5月発行)
4巻4号(1960年4月発行)
4巻3号(1960年3月発行)
4巻2号(1960年2月発行)
4巻1号(1960年1月発行)
3巻12号(1959年12月発行)
特集
3巻11号(1959年11月発行)
3巻10号(1959年10月発行)
3巻9号(1959年9月発行)
特集
3巻8号(1959年8月発行)
3巻7号(1959年7月発行)
3巻6号(1959年6月発行)
3巻5号(1959年5月発行)
3巻4号(1959年4月発行)
3巻3号(1959年3月発行)
3巻2号(1959年2月発行)
3巻1号(1959年1月発行)
